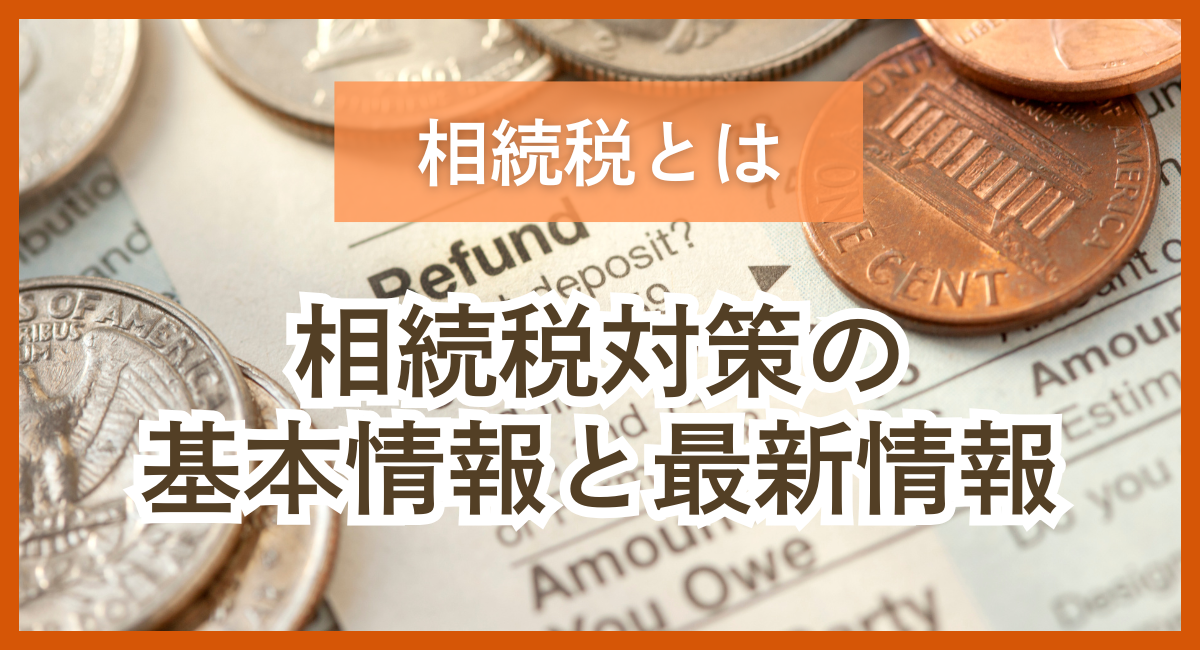相続税とは

相続などによりお金や不動産等の財産(相続財産)を取得したときにかかる税金です。
相続財産は、現金や預貯金、株などの有価証券、宝石等の装飾品、不動産、各種保険などの金銭として評価できるもの全てを指します。
ただし、相続税は必ずかかるわけではなく、相続財産の総額が基礎控除額(相続税がかからない金額)を超えると、その超えた金額に相続税がかかることになります。
相続財産の金額が大きいほど相続税が大きくなる仕組みになっています。
【基礎控除額の計算方法】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者、子2人の場合は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
が基礎控除となり、相続財産のうち4,800万円を超えた金額に相続税がかかることになります。
相続財産を減らす、もしくは各財産の評価額を削減することで相続財産の総額を小さくしていくことが、相続税を抑えるポイントとなります。
相続税を抑えるための対策(相続税対策)をしておくことで、残された人たちの税金負担を軽くすることが可能な場合がございます。
今回はこの相続税を抑えるための対策方法についてご案内いたします。

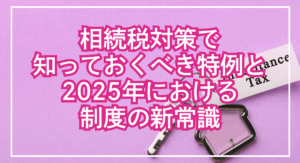
〜相続税対策の方法〜
●相続する財産の評価額を下げる

相続財産のうち、現金や預貯金は相続発生時の時価で評価されますが、不動産の価格は固定資産税評価額や路線価などをもとに評価されています。
例えば、現金1億円の場合は評価額も1億円のため、そのまま相続税の課税対象となります。一方、ある不動産を相続前に1億円で購入し、相続時に評価額が8,000万円の場合、相続税の課税対象は8,000万円となります。財産を現金から不動産に変えることで、相続税の課税対象金額を2,000万円抑えることができます。
●生命保険や死亡保険に加入しておく
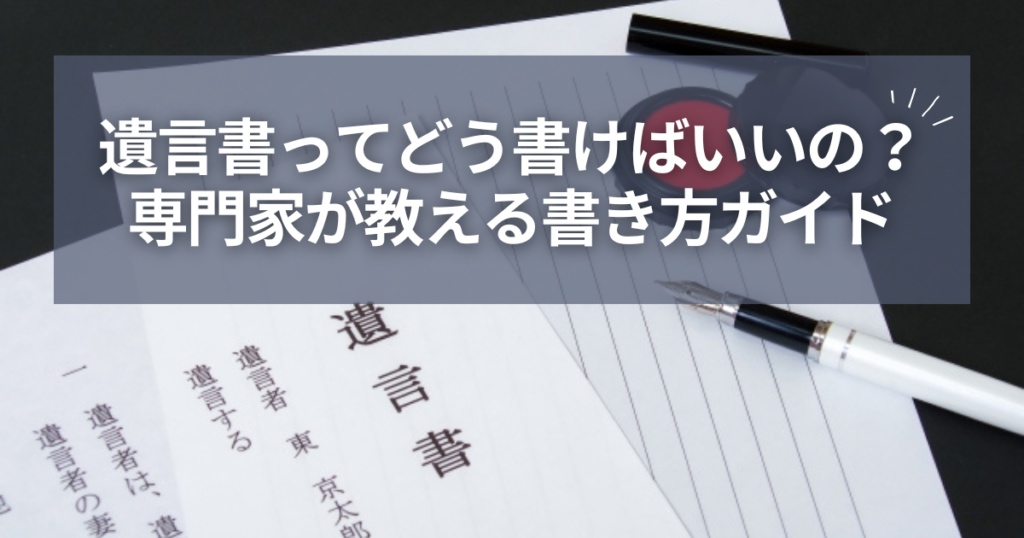
遺言書ってどう書けばいいの?専門家が教える書き方ガイド
保険料により相続財産を減らし、各種保険の非課税枠を利用する対策方法です。
例えば死亡保険に加入する場合、保険料の支払いにより相続財産を減少させることができます。その後支給される死亡保険金は相続税の課税対象ですが、一定の非課税になる限度額が設けられています。
非課税になる限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【死亡保険の有無における相続税の計算例】
現金2,000万円の場合
→2,000万円全額が相続税の課税対象になります。
- 死亡保険金2,000万円
法定相続人が配偶者、子2人の場合
→非課税枠は500万円×3=1,500万円
相続税の課税対象は、2,000万円−1,500万円=500万円になります。
上記の死亡保険金の場合、現金のまま保有していた場合よりも課税対象を1,500万円分抑えることが可能になっています。
【注意点】
- 死亡保険金の取得者が相続人以外の場合、非課税枠が適用されなくなります。
- 法定相続人の数には、その相続において相続放棄をした方も含まれます。
- 法定相続人の中に実子と養子がいる場合は、非課税の限度額を計算するための法定相続人として含むことの できる養子の人数に違いがあります。
法定相続人に実子がいる場合、養子が複数人いても1人しか含むことができません。
実子がいない場合は、養子を2人まで含むことができます。
●生前贈与を行う

相続が発生する前に、あらかじめ財産を贈与しておくことで、相続財産を減らすことができます。
注意点として、贈与の場合には贈与税が発生することがありますので、相続税と併せて検討しましょう。
生前贈与には「暦年贈与」と「一括贈与」の2つがあります。
【暦年贈与】
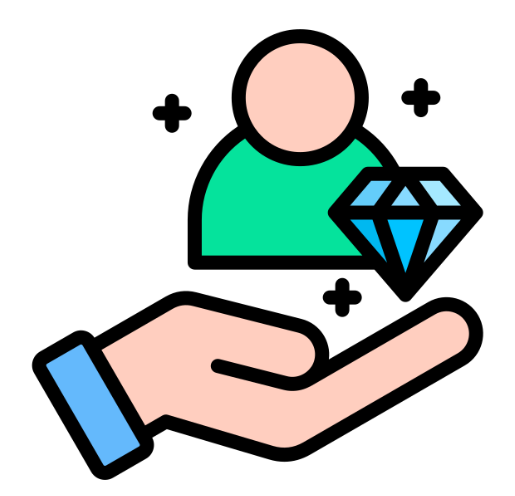
毎年1月1日から12月31日までの間(暦年)に、110万円を超えない範囲で贈与を行う手法です。
1年のうちに行った贈与が110万円以下の場合、贈与税がかからなくなります。
この手法により、毎年110万円以下の贈与を積み重ねることで、贈与税を発生させずに相続財産を減らすことが出来るようになっています。
【暦年贈与の注意点】
毎年一定額の贈与を重ねた場合、定期贈与として扱われ、贈与税が発生する場合があります。
定期贈与として扱われないための工夫として、以下の点をご参考ください。
- 違う金額で贈与を行う(100万円の贈与の翌年は、101万円で贈与を行うなど)
- 違う時期で贈与を行う(4月に贈与を行った翌年は5月に贈与を行うなど)
- 毎年行う贈与でも、各贈与において贈与契約書を作成する(贈与を行った証拠となります)
【一括贈与】
次の目的として贈与を行う場合は、それぞれの限度額までは贈与税がかからなくなります。
ただし、決められた要件や所定の手続きが必要になるので注意しましょう。
- 教育資金
2026年3月31日までは、1,500万円以下であれば非課税となります。 - 結婚・子育て資金
2025年3月31日までは、1,000万円以下であれば非課税となります。 - 住宅取得等資金
【生前贈与の注意点】
・現金の贈与などの場合、贈与を受けた人(受贈者)が口座を管理する必要があります。
現金を贈与しても、元の持ち主である贈与した人が口座の通帳や銀行印を管理している場合、その口座は受贈者が名義を借りただけとみなされ、贈与として扱われなくなります。
例えば、「子どもへ贈与したが、無駄遣いしないように贈与者が引き続き管理する」ケースでは、贈与として扱われなくなる恐れがあります。
・相続開始前の7年以内の贈与に注意しましょう。
令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降は、「相続開始前7年以内の贈与には相続税が発生する」扱いとなりました。
そのため、生前贈与を行う場合は、日付けや内容などの証拠を残すためにも、なるべく早めの長期的な生前贈与が節税対策として有効です。
●小規模宅地等の特例の利用

特例の対象となる土地(小規模宅地等)を、相続または遺贈により取得した親族が一定の要件を満たしている場合、その宅地等の評価額を最大80%下げることができます。その結果、相続財産の総額の削減となり、節税へつなげることが可能になります。
【小規模宅地等の特例の対象となる土地】
小規模宅地等は、大きく4つに分類されます。それぞれに適用できる面積と減額割合の限度が定められています。
特例を利用することができる宅地等
| 宅地等の利用区分 | 限度面積・減額割合 | |
| ①特定居住用宅地等 | 被相続人(亡くなった人)が自宅として使っていた宅地等 | 330㎡・80% |
| ②特定事業用宅地等 | 被相続人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等 | 400㎡・80% |
| ③特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人の会社(同族会社)として使っていた宅地等 | |
| ④貸付事業用宅地等 | 被相続人が貸地または貸家など貸付用としていた宅地等 | 200㎡・50% |
例えば、①特定居住用宅地等では、その宅地等の330㎡までの部分について評価額を80%削減することができます。
取得者となる親族の一定の要件
| 関係性 | 要件 |
| ①配偶者(被相続人の配偶者) | 被相続人の配偶者は、無条件で小規模宅地等の特例の適用が可能です |
| ②同居親族 (相続発生時に被相続人と同居していた親族) | ・「同居」については、住民票上の住所が同じであるだけでなく、生活の拠点が同じであることを意味します。同居期間の制限はなく、相続発生の1週間前からの同居でも特例の適用が認められます ・相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)まで継続してその宅地等を所有し、かつ、居住し続けること |
| ③同居親族以外 | ・被相続人に、①配偶者や②同居親族がいないこと ・対象の宅地等を相続した親族が、相続開始前3年以内に、その親族等が所有する家屋(被相続人が居住していた家屋を除く)に居住したことがないこと ・相続開始時に、対象の宅地等を相続した親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと ・相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)まで継続して対象の宅地等を所有していること |
【小規模宅地等の特例の計算例】
- 9,000万円、600㎡の宅地にて特例を適用した場合
9,000万円÷600㎡=15万円(1㎡あたりの単価)
330㎡までは評価額が80%下がるので、
330㎡×15万円×0.2=990万円
残りの270㎡はそのまま15万円をかけて4,050万円
合計 990万円+4,050万円=5,040万円(特例を適用した場合の評価額)
上記の例では、特例を適用した場合、差額3,960万円分の評価額を減らすことが出来ます。
【小規模宅地等の特例の注意点】

・この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要になります。
相続税の申告書は、相続財産の金額が基礎控除額を超過する場合に提出する必要があります。
ただし、このときの相続財産の金額は、小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。
・取得者が②同居親族、③それ以外の場合、相続税申告の期限内は対象の宅地等を所有している必要があります。つまり、相続税の申告期限内に売却などにより手放した場合、小規模宅地等の特例を適用することが出来なくなります。
まとめ
相続税の対策方法を講じるか否かにより、かかる相続税の金額が大きく異なります。
上記にて紹介した、各種保険への加入や様々な贈与により、相続人の生活の安定を計りながら、相続税の節税につなげることが可能です。円満な相続のためにも、生前より相続税対策を行なっておきましょう。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼