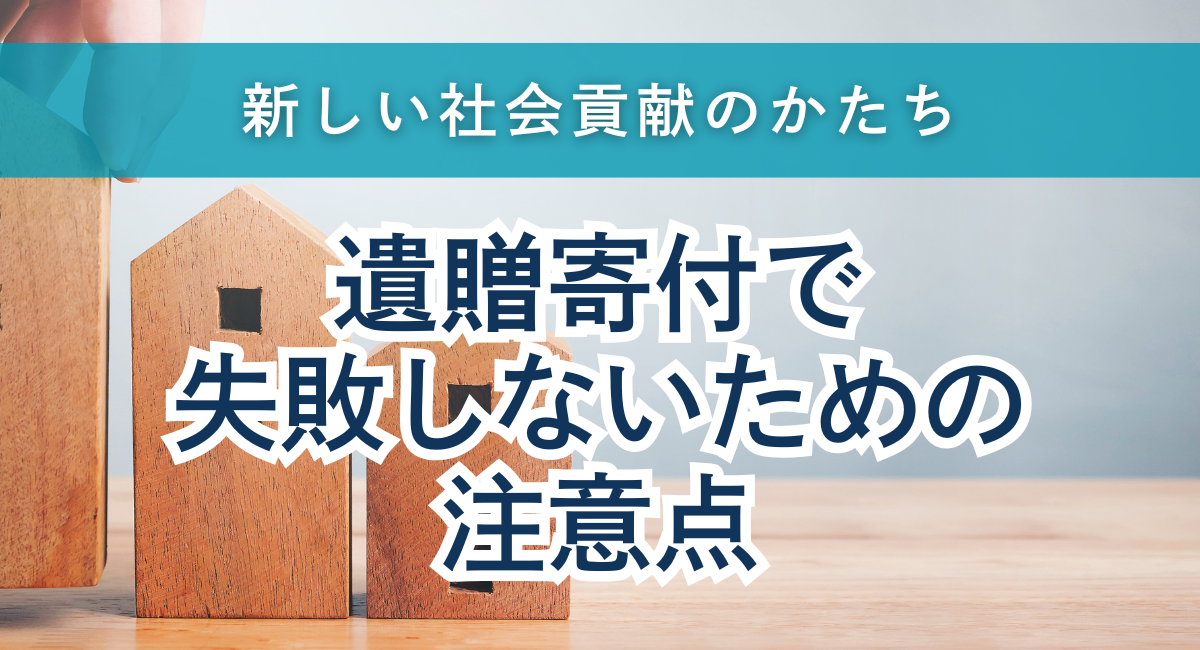あなたが終活をする中で「寄付で社会貢献をしたい」「家族以外の誰かの役に立ちたい」と感じたことはありますか。
これまでの人生を振り返り、人生の締めくくりに未来への贈り物を
そんな想いから生まれるのが「遺贈寄付」です。
自分の人生で大切にしてきた価値観や願いを、次の世代へ託す方法として今注目されています。
この記事では、そんな遺贈寄付をこれから検討していく人に向けて、失敗しないための注意点をお伝えします。
遺贈寄付とは
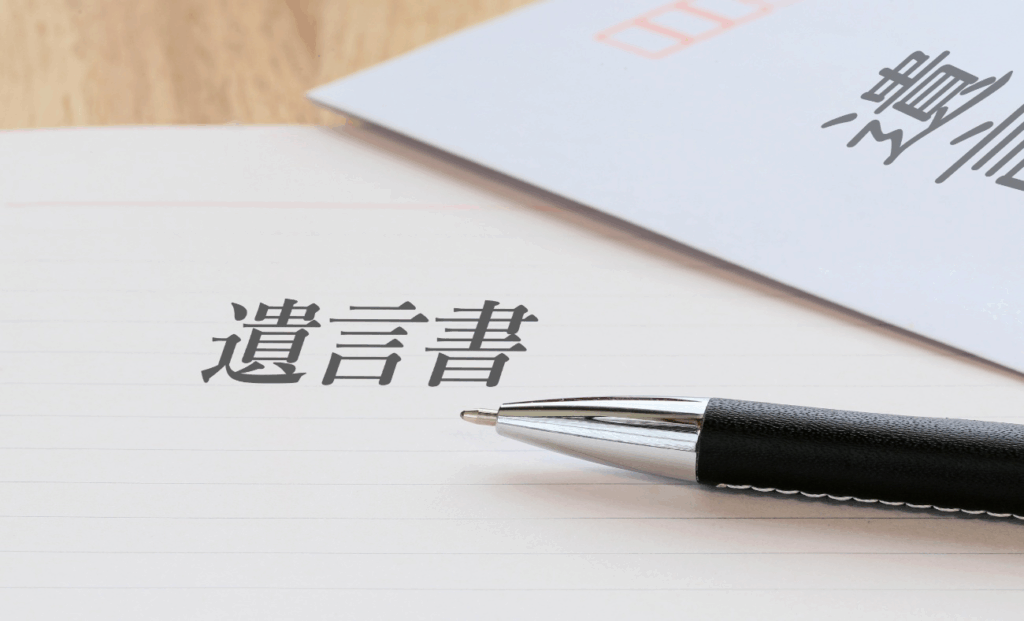
まずは遺贈寄付とは何かについて確認をしておきましょう。
そもそも遺言書などによって相続人以外の人や団体に遺産の一部を贈与する行為を遺贈と呼びます。
遺贈寄付とは、その中でも慈善団体やNPO法人など社会貢献活動を行っている先に寄付として贈与する場合を指します。
遺贈寄付にはさまざまな方法があり、信託や受取人を団体に指定する生命保険寄付、死因贈与契約によるものなどもあります。
今回はその中でも最も代表的な遺言書を使った寄付についてご案内していきます。
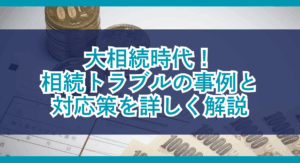
遺贈寄付への関心の高まり

近年では終活についての書籍に遺贈寄付の章があったり、雑誌で遺贈寄付の特集が組まれたり、弁護士などの士業やNPOなどが積極的に情報発信するなど、遺贈寄付について目にする機会が増えています。
それだけ遺贈は今、社会の注目を集めていると言えるでしょう。
実際に、日本財団が2,000人に対して行った2025年5月時点の調査*によると、約64%の人が遺贈寄付について認知しており、関心があると回答した人は全体の23.1%。
実に4人に1人が遺贈寄付に興味を持っており、近年の関心の高まりを示す結果となりました。

一方で、同調査では遺言を作成している人の割合は全体のわずか3.4%にとどまっており、興味はあるのに実際に行動を起こしている人が少ないことがうかがえます。
ではこのギャップはどこから生まれてくるのでしょうか?
この調査の中ではさらに「遺贈を行う場合、問題となりそうなこと」という質問をしています。
その回答として最も多かったのは27.8%の「必要な手続きが分からない」、
次いで「どこに相談したらいいか分からない」が23.0%となっており、
手続きや相談先についての情報が少ないために動きたくても動き出せない現状が見えてきました。
確かに遺贈寄付は相続人ではない人や団体に財産を遺す方法であるため、通常の遺言などとは違うメリットや注意点がいくつかあります。
では、具体的にどんな点を知っておくとよいのでしょう。
ここからは遺贈寄付について詳しく見ていきましょう。
*出典:公益財団法人 日本財団(2025年)「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」
遺贈寄付のメリット
まずは遺贈寄付のメリットについて確認をしていきましょう。
自分の意思で財産の行く先を決められる

一般的に、人が亡くなるとその財産は相続人(法定相続人)に引き継がれます。
誰が相続人となるかは民法によって決められており、遺言や生命保険による受取人の指定がなければ、強制的に財産の行く先は決まってしまいます。
また、死亡時に相続人がいない場合には、財産は国庫に帰属、つまり国の資産になってしまいます。
しかし、遺言などで行く先を示しておくことで法定相続人以外へ、仮に相続人がいない場合であっても希望に沿った財産の承継が可能になります。
遺贈の最大のメリットはここにあると言えます。
自分の想いを自由に未来の社会へ託せるため、遺贈寄付は最後の社会貢献とも呼ばれているのです。
遺贈寄付は原則、相続税の課税対象外

続いては多くの人が気になっているであろう税金についてのメリットです。
遺言書によって法人へ寄付した場合、その財産は相続税の課税対象外となります。
相続税は、相続または遺贈により財産を得た個人に対して課される税金なので、法人が財産を取得した場合には原則的に課税はされないというわけです。
つまり、遺贈によってNPO等に寄付をした財産は相続税を計算するための財産から差し引かれ、税金が算出されることになるのです。
NPO等に寄付をしたいけれど、相続税の支払いのために財産を残しておかなくちゃ…と考えている人も多いですが、遺贈寄付を使えば相続税の支払いを心配することなく自分の希望に沿った寄付ができます。
少額からでも寄付可能

「遺贈寄付はお金持ちがやるもの」「自分には遺贈寄付にまわせる財産がないと思っている」と思っている人がとても多いですが、実際にはそんなことはありません。
遺贈寄付に最低金額はなく、たとえ1万円だとしてもそれは立派な遺贈寄付です。
金額の多寡はあるかもしれませんが、あなたが生きているうちに築いた大切な財産から想いを託されたものであれば、寄付先の団体はしっかりと受け取ってくれるはずです。
複数の団体に分散もできる

また遺贈寄付をする先の団体はひとつに絞らなくてはならないという考えも誤解です。
遺言の中には寄付したい団体をいくつでも記載できますし、どのような割合にするかもあなたの自由に決めることが可能です。
寄付先を選ぶ中で「ここだ!」と思う団体が見つかってひとつ絞れれば、それはそれでよいですが、それぞれの団体の良さを分かったうえで複数を選ぶという方法もよい寄付の方法と言えます。
複数団体を遺贈寄付先に選ぶ人の傾向として、国際協力系・医療系・子供支援系・環境保護系など大きな分野ごとにそれぞれ関心のある団体をひとつ選ぶパターンや、単一の分野に絞ってその中からいくつかの団体を選ぶパターンなどが見受けられます。
遺贈寄付を検討するときの注意点
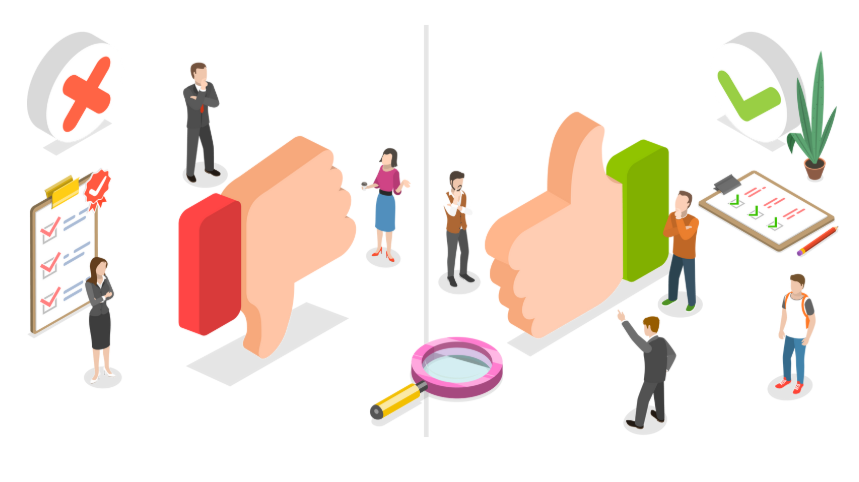
遺贈寄付のメリットが分かったところで、今度はデメリット・注意する点について見ていきたいと思います。
ここでご紹介する注意点は、しっかりとその遺言の通りに財産が分けられるために作成段階から気をつけたいことになります。
相続人とのトラブルになる可能性がある

最初の注意点として、遺贈寄付は寄付先団体と相続人との間でトラブルになりやすいことがあります。
遺贈寄付は亡くなった方の想いを自由に各団体へ託せる一方で、相続人から見ると本来受け取るはずだった財産が少なくなってしまったと感じる場合もあります。
特に相続人には遺留分という法律で認められた割合で財産を受け取る権利があります。
それが侵害されているような遺言内容であった時には、相続人が最低限の資産すら得られなかったと感じ、トラブルへ発展する可能性が高まるという点は覚えておきたいところです。
寄付する団体選びは慎重に

次に寄付先を選ぶときの注意点です。
寄付先団体はあなたの大切な財産を受け取り、実際の活動に繋げてくれる重要な役割を果たします。
当然ですが、想いを託した財産を有効に活用してくれる団体でなければなりませんが、それを判断するのは簡単ではありません。
そのためには、問い合わせをして担当者から直接話を聞いてみたり、インターネットで活動の情報を収集したり、複数団体のパンフレットを一括で取り寄せて比較検討してみるなどの方法が有効です。
また、団体によっては定期的なイベント開催やボランティア受け入れをしているところもあり、関心がある活動には積極的に参加をしてみて、団体の魅力を実感してみるのもよいでしょう。
具体的に寄付したい団体が固まってきたところで、もしあなたが不動産などの現金以外の財産を遺贈寄付しようと思っているのなら、さらにもうひとつ注意が必要です。
団体によっては不動産や有価証券などの現金以外の寄付を受け付けていない団体もあります。

遺言書を書く前には、必ず寄付先団体に希望する寄付の内容で受け取ってもらえるかを丁寧に確認しましょう。
あまり詳しく話をしたくないからとこの手間を省いてしまうと、せっかく遺言を遺したのに、団体側の状況によって寄付ができなかったという取り返しがつかない結果になりかねません。
遺贈寄付で失敗しないために

ここまで見てきたように、遺贈寄付には素晴らしい魅力がある一方で、その想いがしっかりと遂げられるための準備が不可欠です。
人生で一回しか遺言を書く機会はありません。
書いたものを書き直すことはできますが、最終的にはひとつの遺言しかこの世に残すことはできません。
そして、その遺言の内容がしっかりと達成されたか、あなたには知るすべがないのです。
そのため、しっかりとした知識と経験を持った専門家への相談がとても重要です。
遺言を遺すというと、自分一人で決着をつけるものと思われる方が多いようですが、そうではありません。
信頼できるパートナーを見つけ、そのパートナーと一緒に納得のいく失敗しないものを作り上げていくことこそが遺言を遺すという行為なのだと思います。
今、不安や分からないと感じていることがある人は、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼