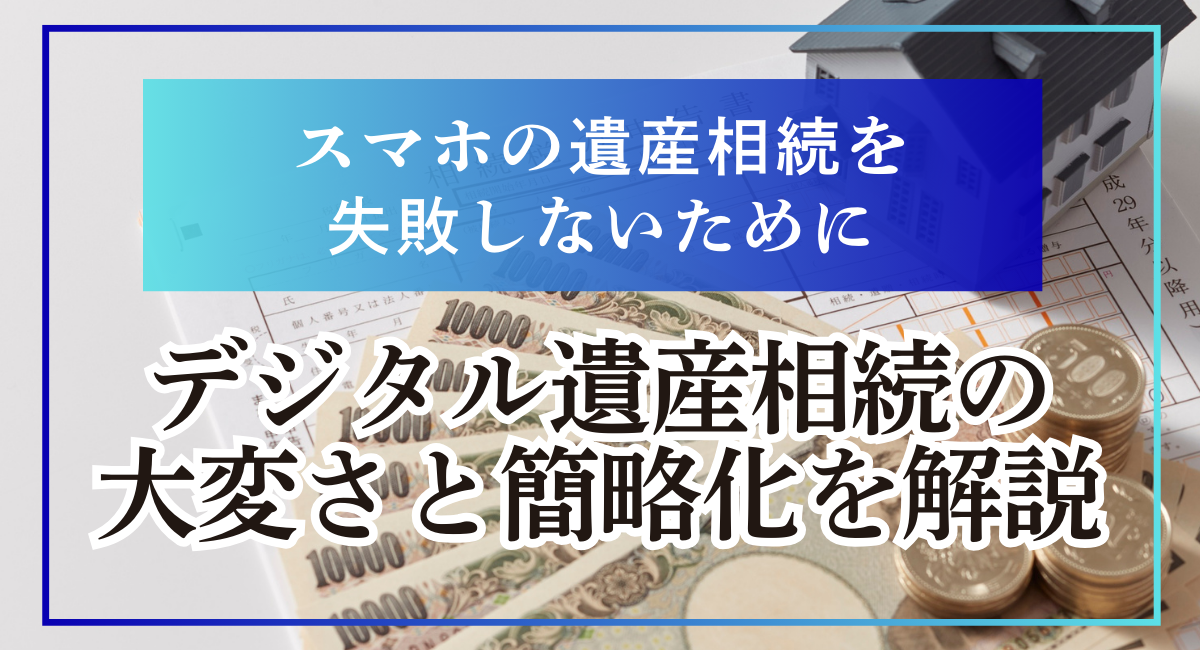スマートフォンの遺産相続は、端末本体を引き継ぐだけでなく、その中に保存されているデータやアカウント、契約内容なども含めて考えなければなりません。端末の中には写真や動画、連絡先、メモ、お金関連、SNSやメールなど多くの個人情報が保存されています。
このような被相続人(故人)の情報を「デジタル遺産」と呼び、相続の対象となる場合があります。モノの相続と同様に、デジタル遺産の管理や契約の解約には多くの手続きが必要です。本記事では、相続人(遺産を引き継ぐ方)の負担が軽減できるように、デジタル遺産の主要なスマートフォンに焦点を当てて、徹底解説します。
なぜスマホの相続でトラブルが発生するのか?

デジタル遺産は現物で残らないため、相続人がその存在自体に気付かないケースが多いのです。ネット銀行の口座やキャッシュレス決済、定額制サービスが代表例になります。このようなデジタル遺産は、後から発覚してトラブルを引き起こします。特に定額制の契約は、自動で継続されることが多いのです。解約しないまま、料金が発生し続けることも珍しくありません。
また、スマホなどのデジタル遺産の扱いをめぐって、相続人同士の意見が食い違うこともトラブルの要因になります。他の相続人に知らせずに、勝手に端末を初期化したり、データを消去したりしてしまうと、争いの火種になり得るのです。
ITに詳しい人が、情報や財産を独占するリスクもあるかもしれません。このように、スマホの相続トラブルは、複合的な要素が絡み合って発生します。
| トラブルの原因 | 内容・具体例 |
| ロック解除ができない | パスワードや指紋認証が分からず、端末やデータにアクセスできない |
| デジタル資産の存在を把握できない | ネット銀行や電子マネー、ポイント、仮想通貨などの資産が見つけられない |
| サブスク・有料サービスの解約漏れ | 定期課金サービスの解約ができず、死後も料金が引き落とされ続ける |
| 重要情報や資産の見落とし | スマホを初期化・解約してしまい、後から資産の存在が判明する |
| 相続手続きの遅延・やり直し | デジタル資産の発見が遅れ、遺産分割協議や相続税申告のやり直しが必要になる |
| データ流出・プライバシーの問題 | ロック解除できないまま端末を処分し、個人情報が流出するリスク |
| 相続人間の意見対立 | スマホやデータの管理・処分方法を巡って相続人同士でトラブルになる |
| ITリテラシー不足による手続き困難 | オンライン手続きや名義変更に相応のIT知識が必要で、相続人が対応できない |
本人しか分からない情報があるため
スマホやその中のデジタル資産は、パスワードや顔認証、指紋認証など、本人しか知らない情報で厳重に管理されています。そのため、相続人がロック解除や各種サービスへのログインを行うことは困難です。二段階認証が設定されている場合、被相続人の電話番号が解約されていると認証コードの受信ができません。つまり、アクセスが不可能になる可能性があるのです。
相続が複雑で分かりにくいため
デジタル遺産の種類や、利用しているサービスが非常に多岐にわたることも煩雑さの要因です。相続人は各サービスについて、相続財産に該当するかを確認しなければなりません。そして、評価額を計算する必要があります。それぞれのサービス窓口がオンライン化されているため、インターネットやITに不慣れな相続人にとっては大きな負担でしょう。
プライバシー保護の観点から法的手続きが進みにくいため
スマホには個人情報が集約されています。プライバシー保護の観点からも、相続人が自由にアクセスできないように、厳重に管理されています。被相続人が持っていたスマホのパスワード解除を企業元に依頼しても、通信の秘密や本人確認の厳格化により、対応してもらえないケースも多いです。
このような問題から、スマホやデジタル遺産相続では、生前からアカウント情報やパスワード、契約内容を共有しておくことが重要になります。家族や専門家に伝えておくことが、トラブル防止につながるのです。
スマホの中身を相続する具体的な手順
| スマホを遺産相続する時の手順 | ||
| 手順 | 内容 | 注意点・備考 |
| 1. 端末の確保 | 故人が使用していたスマートフォンを確保する | 重要な連絡先やデータが残っていることが多いため、すぐに処分しない |
| 2. ロック解除 | パスコード・パスワード・指紋認証などでロック解除を試みる | 分からない場合は家族や知人に確認。解除できない場合はサポート窓口へ相談 |
| 3. サポート窓口への相談 | Appleサポート(iPhone)やGoogleサポート(Android)に問い合わせる | 死亡証明書など必要書類が求められる。解除できない場合もある |
| 4. データ・アカウント確認 | 写真・連絡先・金融情報・SNS等のデータやアカウントを確認、必要な情報を保存 | クラウドサービスのID・パスワードが分かれば、端末外からもアクセス可能 |
| 5. サービスの解約・整理 | 有料サービスやサブスクリプション、契約中のアプリ等を解約・名義変更 | 解約しないと利用料が発生し続けるため注意 |
| 6. データの消去・端末処分 | データ初期化や物理的な破壊など、端末の適切な処分を行う | 個人情報流出防止のため、必ずデータ消去を実施 |
| 7. 生前準備(推奨) | パスワードやアカウント情報をリスト化し、エンディングノート等に記録しておく | 相続時の手続きが大幅に簡素化 |
被相続人が使っていたスマートフォン本体の他に、パソコンやタブレット、クラウドサービス、SNSなどのアカウントをリストアップします。スマホにロックがかかっている場合は、家族や関係者にパスコードや指紋認証の情報が分かるかを確認しましょう。
もし分からない場合は、AppleやGoogleなどのサポート窓口に死亡証明書や相続関係を証明する書類を提出してください。ロック解除の手続きを依頼することができます。ロックが解除できたら、スマホに保存されている写真や連絡先、メモ、金融情報など、必要なデータを確認し、バックアップを取りましょう。iCloudやGoogleドライブなど、クラウドストレージにデータが保存されている場合は、アカウント情報を使ってアクセスしてください。
金融アプリや証券口座、仮想通貨、SNSなどのアカウントも確認しなければなりません。必要に応じて、相続や解約の手続きを進めてください。
スマホのデータ確認や必要な手続きが全て終わったら、通信キャリア(ドコモ、au、ソフトバンクなど)でスマホの解約や名義変更(承継)の手続きを行います。
この際、死亡を証明する書類(除籍謄本や死亡診断書)、相続人の本人確認書類、SIMカードなどが必要です。一方で、スマホの解約を急ぎすぎると、SMS認証が受け取れなくなり、デジタル遺産の整理が難しくなる場合があります。さらに、SNSや金融関連のアカウントを放置すると、乗っ取りや悪用のリスクがあるのです。
スマホの中身を相続する際は、スマホ本体と関連アカウントのリストアップ、ロック解除をまずは試してください。その後、データの確認とバックアップ、デジタル遺産やサブスクリプションの整理、キャリアでの解約や承継手続き、本体の初期化・処分という順番で進めましょう。
このような手順を踏むことで、相続人の負担を軽減しながら、デジタル遺産相続の手続きが進められるのです。
デジタル遺産相続を簡素化するには?

デジタル遺産の相続をスムーズに進めるためには、事前の準備と家族への情報共有が不可欠です。ネットバンクや証券口座、SNSなど、所有するデジタル資産を一覧にまとめましょう。金銭的な価値があるものと、思い出や記録として残したいものを分けて整理しておくことで、相続人の負担が大きく軽減できます。
各サービスのIDやパスワード、二段階認証の情報なども忘れずに記録してください。定期的に見直すことが大切です。信頼できるパスワード管理アプリや紙のノートなど、安全な方法で保管しておくのもおすすめです。家族や信頼できる人が必要なときに、アクセスできるようにしておきましょう。
エンディングノートや遺言書にデジタル遺産の内容や取り扱い方法を明記し、家族と共有しておくことも有効です。デジタル庁や相続専門サービスの活用も、相続人の負担軽減につながります。
死亡・相続ワンストップサービスを活用
デジタル庁は、家族が亡くなった際に必要となる行政手続きを、オンラインで行えるようにしています。以前は、死亡届の提出や年金・保険の手続き、相続に関する申請などは、別々の窓口や機関で行う必要がありました。それが遺族にとって大きな負担となっていたのです。
新設された「死亡・相続オンラインサービス」では、死亡届や死亡診断書(死体検案書)など、重要な書類をオンラインで提出できる仕組みを用意しました。さらに、2026年度末までには、オンラインでの一括手続きを目指しているのです。
被相続人の情報をデジタル化し、信頼できる第三者による認証を経て、相続人が必要な手続きに活用できるような仕組みも準備しています。相続手続きに必要な情報を一元的に管理し、手続きの漏れや書類の不備による再申請といった手間を減らせるでしょう。
マイナポータルなどのデジタル行政サービスと連携し、法定相続情報証明制度の電子化や、証明書のオンライン申請・受け取りも可能になります。すでに多くの市区町村では「おくやみコーナー」と呼ばれる総合窓口が設置されています。このような取り組みによって、遺族の精神的・経済的な負担が大幅に軽減されるのです。
デジタル遺産相続専門サービスで手間を削減
デジタル遺産相続専門サービスは、専門家のサポートによって、スムーズかつ確実に進められています。例えば、故人の情報を知らない相続人は、ネット銀行や仮想通貨などの様々なデジタル遺産に関して、パスワードやID管理が難しいのが現状です。そして、遺族だけで手続きを進めるのは大きな負担になります。
しかし、デジタル遺産相続などに特化した専門サービスを活用することで、資産の洗い出しやパスワードの管理、アカウントの解約や名義変更などを一括して任せることができます。これにより、手続きの簡素化と迅速化が実現するのです。
デジタル遺産を正確に把握できることで、遺産分割協議のやり直しや相続税の申告漏れが防げます。さらに、有料サービスやサブスクリプションの自動更新を早期に停止できるため、遺族の経済的負担も軽減されます。
プライバシーやセキュリティを守ることができるのも利点でしょう。連絡先や写真データなどが整理されるため、葬儀の連絡や遺影の選定など、実務的な面でも役立ちます。
弁護士や行政書士なども連携するケースがあるため、法的なトラブルや技術的な障害にも安心です。遺族の精神的・時間的な負担を大幅に軽減し、安心して大切な財産や情報を引き継ぐことが可能になります。
さいごに

スマホをはじめとしたデジタル遺産相続問題は、今後さらに増えるかもしれません。被相続人のスマホのパスワードが分からない場合は、まずは家族や知人に尋ねてみてください。無理に解除を試みると、データが消去されるリスクもあります。
例えば、iPhoneの場合は、事前に「デジタル遺産アクセス(Legacy Contact)」を利用することで、生前に指定された相続人がデータにアクセスできます。Androidの場合も、Googleアカウントの情報が分かれば、クラウド上のデータにアクセスが可能です。
※二段階認証が有効な場合はアクセス制限があるため、事前に“アカウント無効化マネージャー”の設定が推奨されます 。
被相続人の立場としては、生前にパスワードやアカウント情報をリスト化するのがおすすめです。エンディングノートなどの活用で、相続手続きをよりスムーズに進めることもできるでしょう。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼