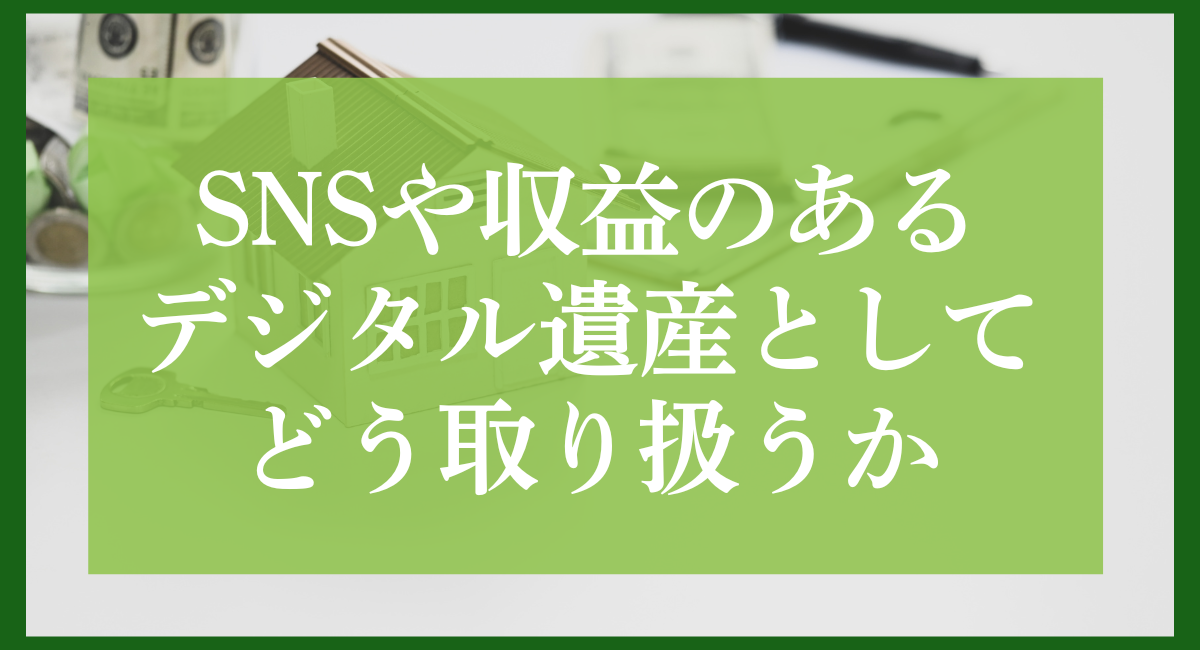事例と活用方法から課題まで
デジタル遺産相続は、故人のデジタル資産(オンラインアカウント、デジタルコンテンツ、デジタルデータなど)を相続人に引き継ぐ相続です。近年、デジタル化の進展に伴い、故人が保有するデジタル資産は多様化、複雑化しており、その相続問題は新たな社会問題として注目を集めています。従来の不動産や現金などの相続とは異なり、デジタル遺産相続には特有の課題と対策が存在します。以下にわかりやすく説明します。
デジタル遺産の範囲
デジタル遺産は、その種類と範囲が非常に広範です。具体的には以下のようなものが含まれます。
オンラインアカウント
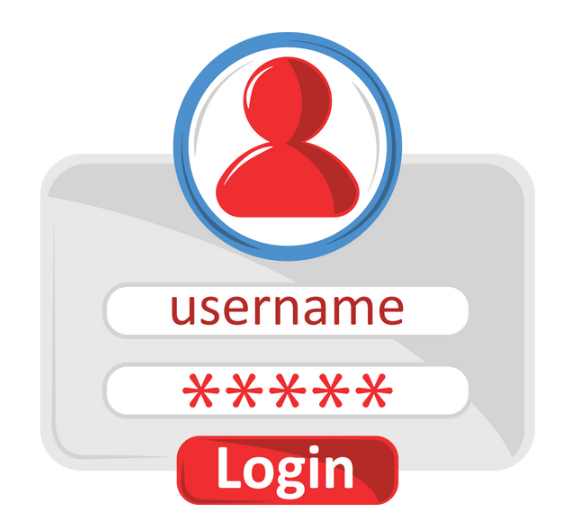
SNSアカウント(Facebook、Twitter、Instagramなど)、メールアカウント、オンラインゲームアカウント、クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox、iCloudなど)、オンラインバンキングアカウント、電子書籍サービスアカウント、ストリーミングサービスアカウントなど。 これらのアカウントには、故人の思い出の写真や動画、連絡先情報、重要な文書などが保存されている可能性があります。 SNSアカウントの中には、管理しているページが収入を得ているケースなどもあり、アカウントを遺産相続することで、所持している残高または資産も引き継いで相続することが出来ます。
デジタルコンテンツ
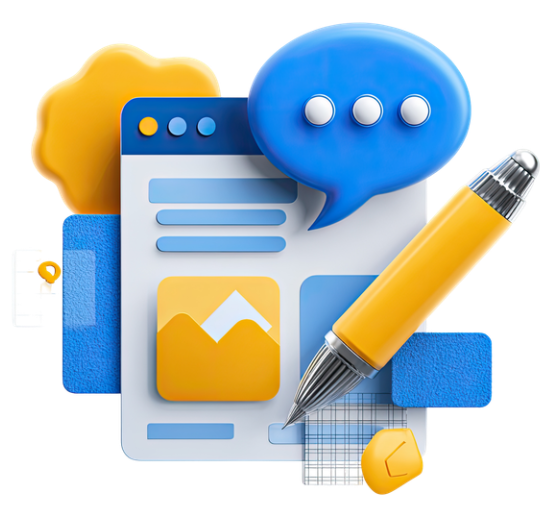
パソコンやスマートフォン、タブレットなどに保存された写真、動画、文書、音楽ファイル、電子書籍など。 これらは、故人の人生の軌跡や大切な思い出を記録した貴重なデータです。 故人が保有していた知的財産権なども含めて相続を検討する必要があります。
デジタルデータ

パソコンや外部ストレージに保存された、個人情報、金融情報、事業に関するデータなど。これらのデータは、相続人にとって経済的または法的にも重要な意味を持つ場合があります。暗号資産や著作権のあるアートなどのデータも含まれるので、故人がアーティストの場合には相続するまでの取扱などにも注意する必要があります。例として故人が有名な歌手の場合には故人の音源データなどは相続するまではリリースや公開などはできないので、デジタルデータの取扱は十分な注意が求められます。
デジタル通貨

暗号資産(仮想通貨)などのデジタル通貨。 価値変動が激しく、管理方法も独特なため、相続手続きが複雑になります。
SNSはデジタル遺産としてどう取り扱うのか
SNSアカウントは、故人のデジタル遺産の一部であり、相続の対象となる可能性があります。ただし、その扱いは、SNSの利用規約、故人の事前指示、あるいは死後事務委任契約によって左右されます。具体的には、アカウントの削除、相続人への引き継ぎ、あるいは追悼アカウントとしての継続などが考えられます。
故人のSNSアカウントが、YouTubeチャンネルやブログ、TikTokのように広告収入や商品販売による経済的価値を持つ場合は、相続の対象となる可能性があります。
SNSアカウントの相続対策
デジタル遺産を相続人にスムーズに譲渡する際に、有効なのが、遺言書です。この際に家族がデジタル遺産の存在を把握し、必要な情報を全て整えておく必要があります。
パスワードマネージャーを使って確認できる
パスワード管理は、パスワードマネージャーを使うと効率的です。これにより、複数のパスワードを一元管理でき、信頼できる家族への安全な引き継ぎも容易になります。
相続人がログインできるかどうか

デジタル遺産は、現預金や不動産とは異なり、実体がないため発見が困難です。パソコン、スマートフォン、インターネット上に分散して保管されているため、故人が利用していたサービスを特定すること自体が難しいケースが多く、本人以外がログインすることは困難です。
仮にデジタル遺産の存在が判明しても、パスワード不明のためアクセスできないケースがほとんどです。さらに、故人の端末を処分済みだった、または、二段階認証などのセキュリティ対策のためにアクセスできないケースも少なくありません。特に、ネット銀行やネット証券といった金融資産は、ログインに高いハードルがあるため、パスワードやサービス情報の有無がアクセス可否を大きく左右します。
もしログインできない場合には専門業者に依頼することが可能なので、困難な場合には最終的に検討してみましょう。
デジタル遺産相続の課題
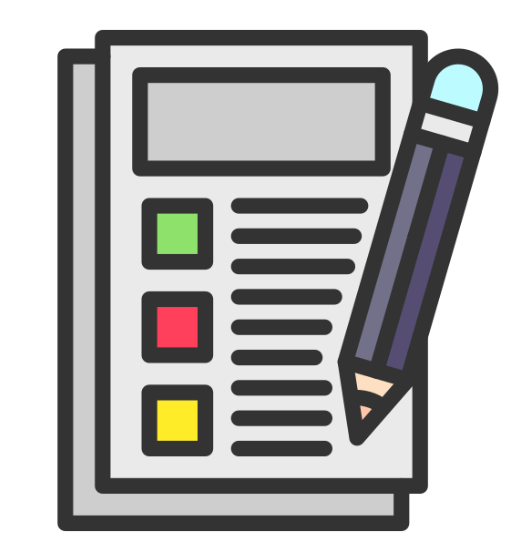
サービス事業者によっては、故人のプライバシー保護を理由に、相続人への情報開示を拒否することがあります。相続人が故人のデジタル資産を相続するためには、事業者との交渉や法的措置が必要となる可能性があります。
データの保存・管理
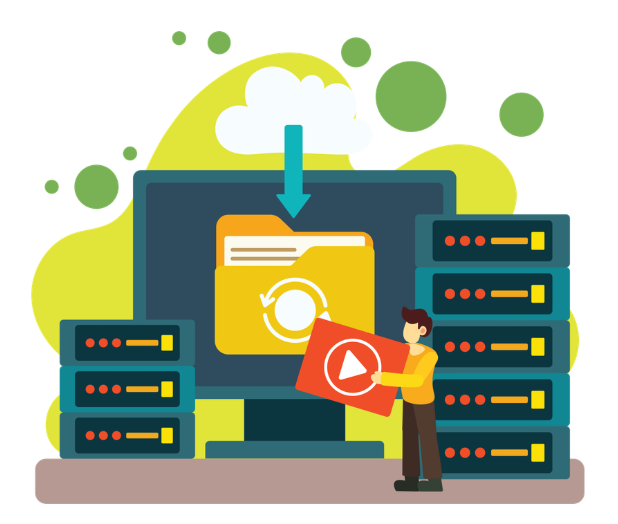
デジタルデータは、ハードウェアの故障やデータ消失のリスクがあります。相続人は、デジタル遺産を適切に保存・管理する必要がありますが、専門知識が必要となる場合もあります。クラウドサービスを利用している場合でも、料金の継続支払いや契約更新の手続きが必要となる可能性があります。
法的根拠の確認
デジタル遺産相続に関する法律や制度は、まだ整備途上です。明確な法的根拠がないため、相続手続きに混乱が生じる可能性があります。
デジタル資産の価値評価
デジタル資産の価値を正確に評価することは困難です。特に、デジタルコンテンツやオンラインゲームアカウントなどは、市場価値を算出することが難しい場合があります。相続や資産について詳しい弁護士に相談すると有意義です。
デジタル遺産相続対策
デジタル遺産相続の問題を回避するため、生前に以下の対策を行うことが重要です。
デジタル資産のリスト作成
所有するデジタル資産をリスト化し、アカウント名、ログイン情報、パスワードなどを記録しておき、安全な場所に保管し、信頼できる相続人にその保管場所を知らせておく必要があります。パスワード管理ツールを活用するのも有効です。
パスワードの共有
信頼できる相続人に、重要なアカウントのパスワードを共有します。できるだけセキュリティを考慮し、安全な方法で共有する必要があります。
遺言書の作成
遺言書にデジタル資産の相続に関する内容を明記します。誰にどのデジタル資産を相続させるか、また、どのように管理・処分するかを明確に記述することで、相続トラブルを防止できます。
サービス事業者への確認
各サービス事業者の利用規約や相続手続きに関する情報を事前に確認しておきます。各事業者の対応は異なるため、事前に確認することで相続手続きをスムーズに進めることができます。 国外のSNSやFX業者への確認は期間に余裕をもって対応しましょう。
デジタル資産の整理・削除
不要なデジタル資産は定期的に整理・削除し、データ容量を管理することで、相続手続きの負担を軽減できます。また、デジタル遺産の管理を専門業者に委託するサービスも存在します。これらのサービスを利用することで、相続手続きにおける負担を軽減することができます。
まとめ デジタル遺産の将来展望について
デジタル遺産相続に関する法律や制度の整備、デジタル資産管理サービスの進化により将来的には価値のあるデジタル遺産は相続しやすくなるでしょう。
ひとつ言えることは十分な管理をし、デジタル遺産相続対策を行うことが、相続トラブルの防止に繋がることは間違いありません。デジタル社会における新たな相続問題に、早めに対処することが重要で遺言書を準備しておくとスムーズな相続が可能です。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼