遺品整理には法的な期限はありません。葬儀・法要後など、ご家族に適したタイミングで行えます。ただし、相続放棄や限定承認時は自己判断で処分をする前に専門家への相談が大切です。
大切な家族が亡くなると、衣類などの生活用品や預貯金などの財産を「遺品整理」していくことになります。なかには、ご家族で「形見分け」を行う人も多いでしょう。
しかし、ご親族等がさまざまなエリアで暮らしている場合や、財産・負債の詳細を調べるにあたっては、いつ遺品整理を始めるべきか悩まれるケースも少なくありません。そこで、本記事では遺品整理のタイミングについて、進め方や注意点も交えながら詳しく解説します。
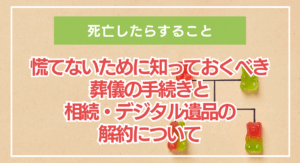
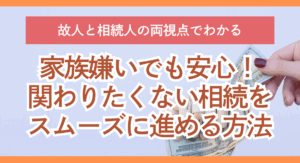
遺品整理のタイミング|7つの時期とは
遺品整理を行うタイミングには、法的な期限が設けられていません。しかし、法的な期限がある相続放棄や退去を求められた賃貸物件の解約時など、どうしても遺品についてどのように扱うか検討すべき時期もあります。
そこで、この章では遺品整理のタイミングについて、よくある「7つの時期」に分けて詳しく解説します。
1. 葬儀の直後

葬儀は多数の親族が集まるため、遺品整理を行いやすいでしょう。しかし、葬儀はご逝去後すぐに行われることが一般的であり、遺品整理は早急だと感じる人もいます。
遺品整理を行う場合でも形見分け程度を行ったり、遺品を分類したりなど、簡単な遺品整理のみ始めることが多いでしょう。親族内で今後遺品整理はどのように行うか、このタイミングで行っておくこともおすすめです。
2. 社会保険・年金関連などの手続き後(ご逝去後14日以降)
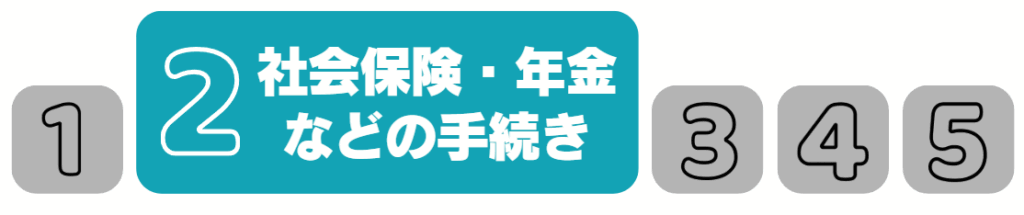
被相続人(故人のこと)の社会保険や年金関係などは、ご逝去後14日以内(厚生年金は10日以内)を目安に資格の喪失届や、支給停止の手続きを進める必要があります。
ご逝去後の慌ただしい中で期限内に行う必要がある手続きのため、手続き完了後に遺品整理に着手することも考えられます。
3. 四十九日の法要後

ご逝去後から49日目にあたる日に、仏教式の場合は「四十九日法要」
を行います。この法要は、被相続人の魂が次の世界へと旅立つ大切な節目とされており、遺族にとっても気持ちが整理できる1つの区切りとなります。また、法要時にも親族が集まるため、法要を終えた後に遺品整理を始めることも多いでしょう。
4. 相続放棄・限定承認を行う時期(ご逝去後3か月以内)

被相続人の相続財産(遺産)について相続人が承継する際には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。
もしも被相続人に多額の借金があった場合、相続したくない場合は相続放棄の手続きを検討する必要があります。また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、限定承認という方法もあります。これらの手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。※例外もあるため専門家に相談を。
相続手続きの方向性を決める重要なタイミングであり、相続放棄や限定承認を検討している場合は、被相続人の財産を引き出したり、売却したりすることはできません。(詳しくは後述します)
この時期に財産に関する書類(預貯金や不動産の有無、負債に関する通知など)を探し出すために、ある程度の遺品整理が進みます。相続放棄・限定承認を行わない場合は遺品整理を行い、不要な遺品類の処分も検討できます。
5. 遺産分割協議完了後

遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員の合意で内容を変更する場合、相続人全員で被相続人の相続財産をどのように分割するか話し合う「遺産分割協議」が必要です。遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税申告・納付や相続登記が必要な場合は期限を意識する必要があります。
- 相続税申告・納付の期限
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 - 相続登記の期限
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
(遺贈で不動産を取得した場合も同様)
遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が作成された後は遺品整理を進めやすいでしょう。特に不動産や貴重品など、価値のある相続財産については、誰が相続するか決まってからでないと処分や譲渡ができません。
なお、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく申請しなかった場合には過料(最大10万円)の対象となる可能性があります。
相続税申告や遺産分配の完了後
相続税が発生する場合、相続税の申告と納税を終えるタイミングも1つの区切りとなります。また、遺産分割協議が完了し、それぞれの相続人に財産が正式に分配された後で、形見分けなどの遺品整理を終えるケースもあります。
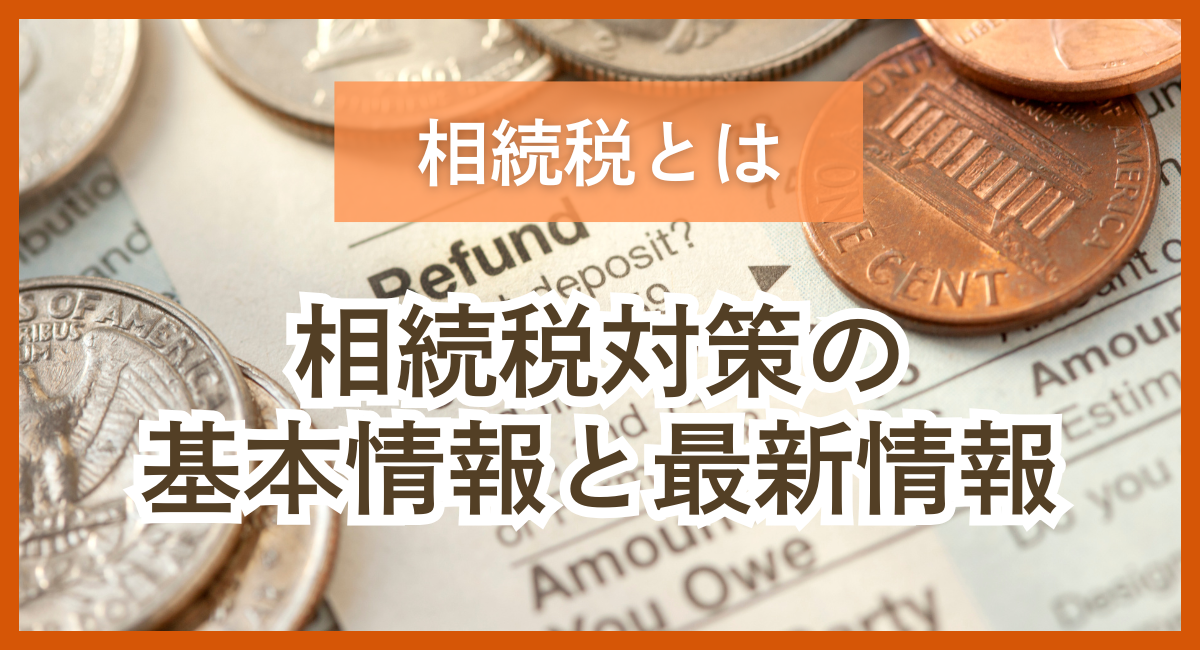
その他
上記の節目以外にも、以下のタイミングも検討できるでしょう。
- アパートやマンションの解約時期
被相続人が賃貸物件に住んでいた場合、契約が継続していると家賃が発生するため解約手続きと退去にともなう遺品整理を行う必要があります。 - 自宅の売却などの時期
被相続人が所有していた自宅を売却する場合、売却前に家財をすべて運び出す必要があります。リフォームや解体を伴う場合も同様に、遺品整理が必要です。 - 気持ちが落ち着いたタイミング
無理に急いで整理を進める必要はありません。故人との思い出の品々に触れることは、時に辛い作業となることもあります。悲しみが癒え、心の準備ができたと感じた時に、自分のペースで少しずつ整理を進めることも大切です。
遺品整理の進め方と押さえておきたい注意点
遺品整理は、大切な人との思い出を整理する時間であると同時に、多岐にわたる作業をともないます。ご自身で行うか、専門家に依頼するかによって進め方が異なるため、この章で解説します。また、遺品整理を自己判断で進められないケースにも触れますのでご一読ください。
遺品整理を自分で行う場合
ご自身で遺品整理を行う場合、労力がかかるものの費用を抑えられることや、思い出をじっくりと振り返る時間を確保できます。進め方は以下の2つです。
- 遺品を仕分けする
遺品整理の最初のステップは、遺品の仕分けです。
- 必要
- 不要
- 換える価または分配するもの
以上の3つに分けて整理をすると進めやすいでしょう。この作業は非常に時間がかかりますが、後々の負担を軽減するためにも丁寧に行いましょう。換価や分配はいわゆる「相続財産」(遺産)であり、貴金属などの価値を鑑定する必要があるものも含みます。
- 処分する
次に、不要と判断した遺品を適切に処分します。各自治体の分別ルールに従って出します。家電リサイクル法対象品(テレビ・冷蔵庫など)は、指定引取場所に持ち込むなど、一般ごみとは別の方法で処分する必要があります。
※また、家電量販店や市区町村の回収サービスを通じてリサイクル料金を支払って処分する方法もあります。
遺品整理を専門家へ依頼する場合
遠方に暮らしており、被相続人の遺品整理が難しい場合や、退去などの理由で時間がない場合、遺品整理の専門業者に依頼することも検討できます。
複数の見積もりを取得し、安心できる専門家へ依頼しましょう。遺品整理業者は数多く存在するため、料金体系やサービス内容、実績などを確認することが大切です。
被相続人が暮らしていた住まいについて退去・売却をともなう場合、部屋の状況によっては専門のハウスクリーニング業者への依頼が必要になります。遺品整理業者の中には、清掃サービスを合わせて提供しているところもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
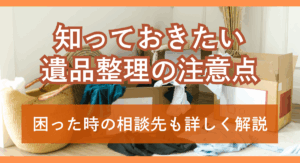
デジタル遺品は専門家の依頼がおすすめ
被相続人のパソコンやスマートフォンには、重要な個人資産が眠っている可能性があります。
いわゆる「デジタル遺品」には、写真や動画といった思い出のデータだけでなく、金銭に関わる重要な情報(ID、パスワード、クレジットカード情報など)が含まれていることがあるため、安易に破棄しないよう注意が必要です。
しかし、パスワードが分からなければアクセスできず、データの消去やアカウントの解約も困難です。プライバシーの問題も絡むため、専門知識を持つデジタル遺品整理業者に依頼することがおすすめです。
遺品整理が自己判断でできないケースに注意
被相続人の遺品を自己判断で処分できない場合もあるためご注意ください。
- 相続放棄や限定承認前の処分は法律の専門家に確認を
被相続人が多額の負債を抱えていた場合など、相続を希望しない場合は「相続放棄」が可能です。相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間内に財産を一部でも処分したり、消費したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、遺品整理を始める前に弁護士や司法書士へ相談し、何が処分可能で何が処分してはいけないのか、具体的な指示を仰ぐようにしてください。負債の一部を清算して残ったプラスの財産だけを相続したい場合には、「限定承認」も同様の対応を心がけましょう。
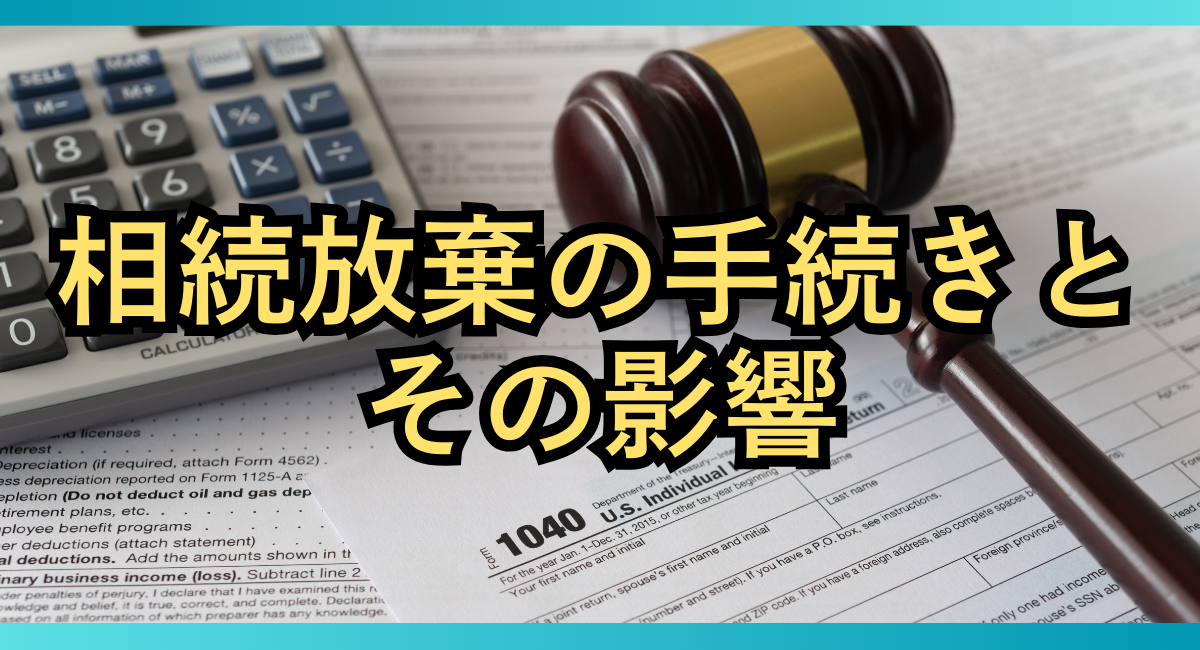
まとめ
遺品整理は、遺族にとって心の整理をする大切なプロセスです。ご自身で進める場合は、時間と労力を要しますが、大切な人を偲びながら丁寧に整理することができます。
一方、時間がない場合や精神的な負担が大きい場合は、遺品整理の専門業者に依頼することも有効な選択肢です。今回ご紹介したタイミングで、ご家族にあった方法をご選択ください。
相続放棄や限定承認を検討する場合には、遺品整理の進め方に注意が必要です。また、デジタル遺品の取り扱いにも十分ご注意ください。
Goodreiは遺品整理やデジタル遺品についてのご相談を行っております。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼

