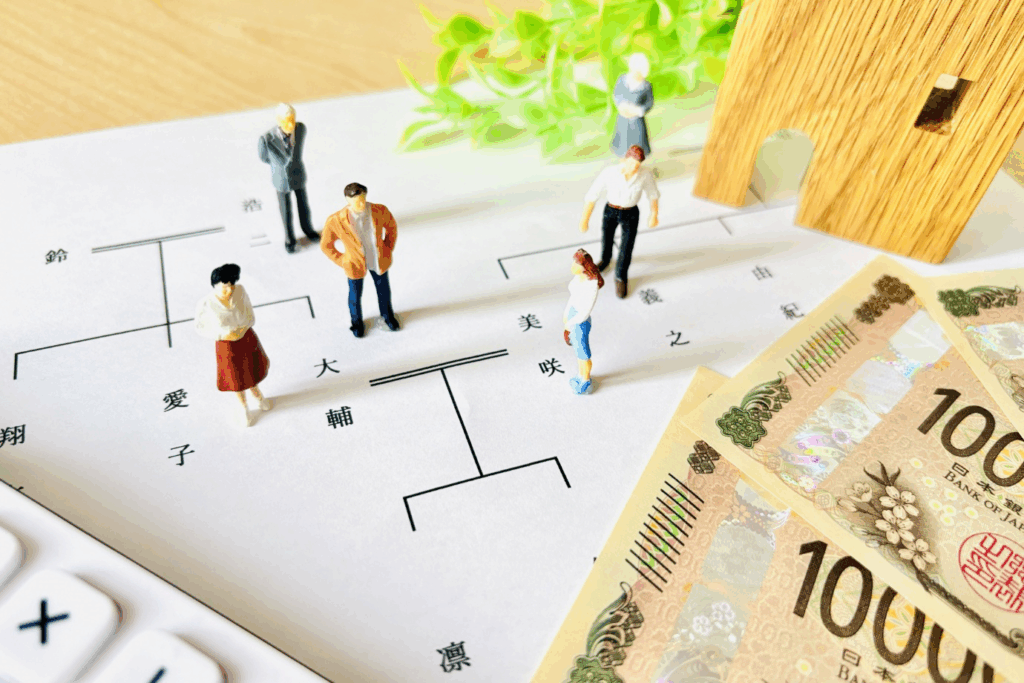
自分の相続について考えていくと「あの人にはこの財産を遺してあげたい」「この人にはお世話になったから財産を多く遺そう」といろいろな想いが頭に浮かんでくるでしょう。
そして、ほとんどの方がそれと一緒に「相続トラブルにはなってほしくない」という気持ちも持たれているはずです。
そこで気をつけたいキーワードの一つが「遺留分」です。
今回は相続トラブルを回避するうえで必ず理解しておきたい遺留分について、賢くトラブルを避ける方法とともに解説していきます。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人について法的に認められた最低限相続できる遺産の割合です。
たとえ、遺言などで自分へ一切遺産が引き継がれない内容になっていたとしても、遺留分を主張することで決められた割合の遺産を取得することが可能になるのです。
なぜ遺留分があるのか
遺留分があることによって、場合によっては遺言書の内容通りに遺産分割されないこともありえます。
本来、遺言を書くことは法律行為であり、死後その内容には法律的な拘束力が発生します。
そんな遺言書の効果にも影響を与えられるのが遺留分ですが、なぜそれほど大きな力を持っているのでしょうか。
その理由は、残された相続人の生活を保障するためです。
息子を持つ父親が亡くなった例で考えてみましょう。
この父親が財産すべてを慈善団体に寄付するという遺言書を残していたとするとどうなるでしょう。
遺言書に則れば、残された息子は一切財産を引き継ぐことができなくなってしまいます。
もし息子がまだ若く、生活の一部を父親に頼っていたとすると、財産が一切受け取れないことで息子自身の生活が非常に不安定になるかもしれません。
こうした時に遺留分があることで、息子はある程度の財産を取得できて生活の安定につながります。
このように遺留分は残された相続人の生活を保障するための役割を果たします。
遺留分を有する相続人とは
遺留分が相続人の生活のためであるとお伝えしましたが、相続人であれば必ず遺留分があるわけではありません。
遺留分が認められている相続人は
・配偶者
・子ども、孫などの直系卑属
・親、祖父母などの直系尊属
となっています。
注意すべき点は、対象の中に兄弟姉妹が含まれていないことです。
つまり、兄弟姉妹は亡くなった人からの遺産がゼロであったとしても遺留分を請求する行為は認められていないのです。
これは、兄弟姉妹では先に述べたような生活保障の必要性が乏しいからというのが主な理由とされています。
兄弟姉妹はそれぞれ独立した家庭を持っていることが多く、遺産による生活の保障を必要としていない場合が多いと考えられるためです。
それぞれの遺留分割合
では遺留分の中身について見ていきましょう。
遺留分割合はすべての相続人で一定ではなく、誰が相続人であるかによって遺留分の割合が変わります。
いくつかのパターンをご紹介しましょう。
まずは相続人が、配偶者と子ども一人だった場合です。
この場合、まず法定相続分(民法で定められた財産全体の相続割合)は配偶者が1/2、子どもが1/2です。
そして遺留分は、配偶者・子どもともに1/4ずつとなります。
両者ともに相続財産全体の1/4は最低受け取れる金額として主張することが可能というわけです。
次の例として、相続人が母親のみであった場合を見てみましょう。
法定相続分としては当然、単独相続人である母親が100%です。
そして、親に認められている遺留分割合は1/3となっています。
※直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は相続財産の1/3
つまり、仮に財産すべてが遺言で慈善団体などに寄付される場合、母親が自分の受取を主張できるのは、そのうちの1/3に対してのみとなります。
先に見た例よりも受取割合が少なくなっている点が注目すべきところです。
では最後に2つの例を組み合わせた場合で見てみましょう。
相続人は、配偶者と母親の2人です。
まずは法定相続分ですが、この場合は配偶者が2/3、母親が1/3と配偶者に多くなるように決められています。
そして遺留分ですが、配偶者が1/3、母親が1/6と差がつきます。
この差は、これまで触れたように本人が亡くなったことで生活に影響が出やすい相続人ほど遺留分割合が高くなっているという点から見れば、納得しやすいのではないでしょうか。
遺留分の割合はやや分かりにくく、法定相続分と併せて一覧にまとめておきますので、参考にしてください。
<法定相続分の割合>
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 子の取り分 | 親の取り分 | 兄弟姉妹の取り分 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
| 配偶者と直系尊属(親) | 2/3 | – | 1/3 | – |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
| 子のみ | – | 全部 | – | – |
| 親のみ | – | – | 全部 | – |
| 兄弟姉妹のみ | – | – | – | 全部 |
<遺留分の割合>
| 相続人の構成 | 遺留分割合(相続財産全体に対する) | 個別の遺留分割合(相続人ごとの取り分) |
| 子のみ | 1/2 | 子全員で法定相続分 × 1/2 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者の法定相続分 × 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者・子それぞれ法定相続分 × 1/2 |
| 配偶者と直系尊属(親など) | 1/2 | 配偶者・親それぞれ法定相続分 × 1/2 |
| 直系尊属(親)のみ | 1/3 | 親全員で法定相続分 × 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 0(遺留分なし) | – |
遺留分侵害額請求
受け取った遺産が自分の遺留分に満たない(遺留分を侵害されている)場合、多く受け取った人に対してお金による返還を求めることができます。
これを遺留分侵害額請求と呼びます。
遺留分は、本来受け取れるはずだった相続財産を受け取れず生活が立ち行かなくなるなど、不公平な相続になっている相続人を保護するためのものです。
こうした観点から遺留分侵害額請求は不公平を受けている相続人からの申し出が必要で、民法の「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方から時効制度が定められています。
・相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときを知ったときから1年
・遺留分侵害を知らなかったときは、相続開始から10年
※民法1048条
上記の期間内に遺留分侵害額請求権を行使しなかった場合、その権利は消滅するとされています(民法1048条)
遺留分請求の対象となる財産は
続いては遺留分侵害の対象となる財産についてのお話です。
これまで遺言によって遺留分侵害が起きるケースをご紹介してきましたが、実は生前の財産でも発生することがあります。
この点は、遺留分財産額の計算方法について理解すると分かりやすくなります。
遺留分の対象財産額は、死亡時に亡くなった人が所有していた財産だけでなく、これに相続人への生前贈与などの特別受益(死亡前10年以内に限る)と相続人以外への贈与(死亡前1年以内に限る)を加え、債務を差し引いて計算されます。
特別受益とは、たとえば複数の相続人がいる中で、一人の相続人のみが生前贈与を含めて、多額の財産を譲り受けている場合に、これを特別な利益とみなすものです。
このように遺留分請求の対象には一定の条件での生前贈与も含まれます。
また、遺産についても遺言で指定された財産だけでなく、本人が死亡した際に効力を発する贈与契約(死因贈与)も対象となります。
円満な相続にするために
ここまで見てきたように、円滑な相続のためには遺留分に配慮した財産承継が必要になります。
それではどんな相続対策をしていけばよいのでしょうか。
遺留分に配慮した生前贈与、遺言書の作成をする
まずは今回の内容を踏まえて、ご自身の相続対策を再度確認してみましょう。
特に生前贈与は長い期間をかけて計画的に贈与されるため注意が必要です。
遺留分の正確な知識を身につけたうえで行わないと、死後に他の相続人からの遺留分侵害額請求によって本来渡したい相続人の遺産額が減少し、意図した生前贈与とならない可能性もあります。
遺言書についても同様です。
もちろん亡くなるタイミングでの財産額は予測できませんが、相続人間で大きな差が出る配分であれば遺留分侵害がないか確認が必要です。
生前から遺産分割を家族で話し合っておく
遺留分侵害額請求は相続人に与えられた権利なので、行使するかはその相続人の判断によります。
自分はもっともらっていいはず…
なんで自分だけこんな惨めな思いをしなくちゃいけないんだ…
そんなネガティブな感情から遺留分請求を行うことも少なくありません。
この点で、亡くなる人が生前からしっかりと相続の想いを伝えておくことはトラブルの大きな抑止力になります。
事前に家族と遺産分割について話し合っておくことが、一番のトラブル回避の手段と言えます。
伝えきれなかった想いがないように、少しずつ準備を進めていきましょう。
専門家に相談する
最後に、相続対策には専門家からのアドバイスは欠かせません。
特に遺留分侵害のケースとは、特定の相続人に他の相続人よりも多くの財産を承継させたいという想いがある場合がほとんどでしょう。
しかし、相続には税務・法務でのルールが多くあり、ちゃんと理解していなかった結果、意図せず遺留分侵害が起きることもあります。
円満な相続にしていくためには、弁護士や税理士などの専門家の力も借りながら、あなたが思い描く未来に向けて少しでも早めに対策をスタートさせるのがおすすめです。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼

