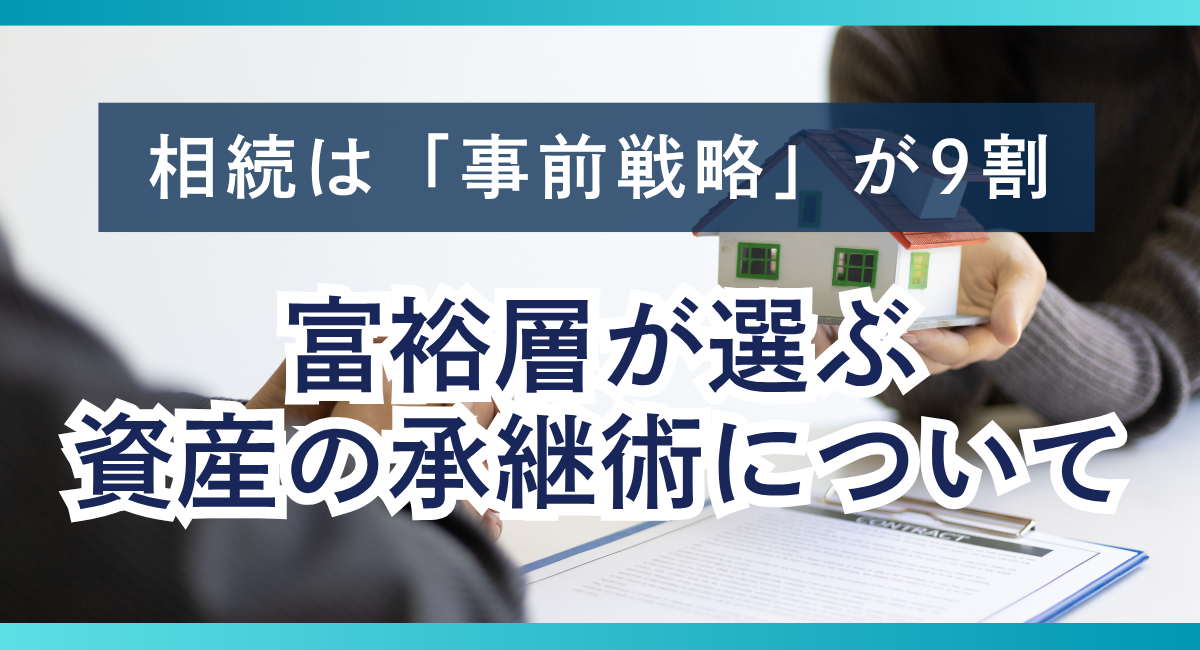相続で重要なのは、「いつか」ではなく「いま」備えることです。特に富裕層は、資産の種類や規模が多岐にわたる分、税務上のリスクや家族間の摩擦も起こりやすいです。何も準備せずに迎えた相続は、トラブルが多くなります。
しかし、事前の戦略で多くの問題を未然に防げます。不動産の組み替えや信託の活用、事業承継計画の策定など、多様な手段を駆使しましょう。これによって、次世代へ円滑に資産を引き渡せるのです。
今回の記事では「相続は準備が9割」と言われる理由を紹介します。富裕層が選ぶべき資産承継の手法に関しても、具体的な事例やポイントを交えながら、解説していきます。
富裕層が抱える相続の現実とリスク

多くの資産を築き上げた富裕層にとって、「相続」は単なる財産の引き継ぎではありません。そこに潜むリスクや、人間関係の複雑さが課題になるでしょう。莫大な資産が残っている場合、相続税の負担は大きくなります。
事前の対策を怠れば、納税資金の確保に追われます。必要な資産を手放さないといけません。資産の分け方や事業継承の内容によっては、親族間でトラブルと深い溝が生まれるでしょう。このようなリスクは、資産が多いからこそ、表面化しやすいです。表向きは順調な家庭や企業であっても、深刻な問題が進行しているケースがあります。
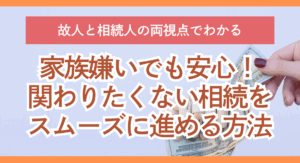
高額な相続税率と納税資金の問題

日本の相続税の最高税率は、課税価格6億円超に対して55%が適用され、世界的に見ても非常に高い水準です。相続税は累進課税が適用されます。資産の規模が大きいほど、税率が上昇するのです。実際に納める税金も多くなります。富裕層の場合は、不動産や自社株など、すぐに現金化できない資産が多いのも特徴です。
そのため、納税資金の調達が大きな課題になります。現金や預金の用意がない場合、相続人は資産の一部を売却する必要があります。借入の検討も視野に入れなければなりません。このような背景から、富裕層は生前から相続人のために、納税資金の準備や相続税対策を行う必要があるのです。
例えば、資産の現金化、生命保険の活用、生前贈与などの検討になります。何も対策せずに相続を迎えると、巨額の相続税が発生します。つまり、次世代への資産承継が困難になるのです。
資産の流動性・分割の難しさ

富裕層の相続では、資産の流動性が低さや、分割の難しさが大きな障害です。多くの富裕層は、不動産やすぐに現金化できない資産を多く所有します。このような資産は、評価額が高く相続税の対象になります。しかし、納税資金を用意するために、短期間で売却するのは難しいです。実際に、買い手がなかなか見つからないケースがあります。想定よりも低い価格でなければ、売却できない事例も多いのです。
不動産や事業資産を分割する場合、相続人同士の意見はまとまりません。遺産分割協議が長引くことも珍しくないでしょう。1つの不動産を複数人で共有すると、運用や管理を巡ってトラブルが多くなります。納税期限までに現金を用意できない場合、相続人が資産を手放す必要があります。
このようなリスクを避けるためには、不動産の信託や小口化など、事前に換金体制を整えることが重要です。生前から資産の見直しや分割方法を検討することで、相続時のトラブルや納税資金の確保に備えられます。
富裕層が実践するべき相続対策

近年、相続を取り巻く環境は大きく変化しています。相続税の税制改正も行われました。都市部を中心とした地価の上昇、金融市場の不安定化など、相続の準備には、より高度な対応が求められています。
複雑化する背景の中で、相続は家族内の問題に収まりません。財産管理や税務、法務などの多面的な視点が必要になります。特に富裕層の間では、このような環境の変化を受けて、税理士や弁護士、FPなどの専門家と、資産全体の構成を再点検する動きが加速しています。

節税テクニックに依存するのではなく、長期的な視点で、資産の流動性やリスク分散を検討しましょう。「どのように資産を守り、次世代に引き継ぐのか」この本質的な課題に取り組む姿勢が強まっています。そのような状況で重要になるのが、「家族の未来像」や「事業の継続性」などの相続設計になります。
今の時代において、相続対策は節税の準備ではなく、家族の価値観や人生観を反映させることです。次世代の未来をかたちづくるため、様々な形で相続対策を行う必要があるのです。本章では、富裕層が実践するべき相続税の対策を紹介します。生前贈与や家族信託など、制度の概要とそのメリットも解説します。
不動産の活用と購入

不動産の活用や組み替えは、相続対策として非常に有効な方法です。現金や預金などに比べて、相続税評価額を抑えられます。結果として、相続税の負担を軽減できるのです。土地や建物は、現金よりも相続税評価額が低く設定されています。特に賃貸用不動産の場合は、借家権割合や借地権割合が適用されるので、評価額がさらに下がります。
また、「小規模宅地等の特例」を活用することで、一定の条件下で、土地の評価額を最大80%に減額できるのです。この特例は相続税対策として、大きな効果を発揮するでしょう。不動産購入時に借入金を利用した場合は、その借入金は相続財産から控除できます。そのため、節税効果も高まります。

不動産の活用方法としては、アパートなどの賃貸経営が挙げられるでしょう。戸建て住宅やビル、駐車場として、貸し出す方法などもあります。土地を一定期間貸し出す定期借地や、不動産の売却・等価交換による、資産の組み替えも有効です。このような方法を活用することで、安定した収入を得ながら資産価値を守れます。
一方で、相続対策として不動産を活用する際には、様々な注意点も把握しなければなりません。例えば、節税目的のみで不動産を購入した場合です。税務署から否認されるリスクがあります。投資としての妥当性を検討する必要があるのです。
相続人の納税や生活資金のために、流動性の高い物件を選ぶことも重要です。固定資産税や修繕費などの維持管理コストも、考慮しなければなりません。
このように、不動産の活用や購入は、相続税対策や資産の有効活用におすすめです。しかし、リスクや注意点もあるため、信頼できる専門家や不動産会社に相談しましょう。計画的に進めることで、家族の将来の安心にもつながります。
| 活用方法 | 相続税評価額の引下げ効果 | 現金納付対策 | 分割相続対策 | 主な特徴・ポイント |
| アパート・マンション経営 | ◎(借家権・貸家建付地評価減) | ◎ | △ | 節税効果大、家賃収入も得られるが、空室リスクや管理の負担あり |
| 戸建て賃貸経営 | ◎ | ○ | ○ | 節税効果大、長期の安定収入、流動性が高くて、分割が比較的容易 |
| 賃貸併用住宅 | ◎ | ◎ | △ | 自宅と賃貸の併用で節税、現金納付にも有効 |
| サービス付き高齢者住宅・保育園 | ○ | ◎ | × | 特定用途で評価減、運営や管理面のハードルあり |
| オフィスビル・商業ビル | ○ | ◎ | △ | 事業用で評価減、立地やテナントリスクに注意 |
| トランクルーム | △ | ○ | × | 節税効果は限定的、収益性や需要に注意 |
| 駐車場 | × | △ | ○ | 節税効果は小さいが、流動性は高い、維持管理が容易 |
| 土地を貸す(定期借地など) | ○(借地権割合で評価減) | ○ | ○ | 貸地で評価減、安定収入ではあるが、契約期間や用途制限に注意 |
| 等価交換・リースバック | △ | ◎ | ◎ | 現金化や分割対策に有効、資産組換えや納税資金確保に活用 |
| 不動産を法人化 | 法人は相続税課税対象外 | ◎ | ◎ | 法人所有により個人の相続財産から分離して管理しやすくなる、管理や税務の専門的な対応が必要 |
生前贈与の戦略的な活用

生前贈与の活用は、相続税対策において、重要な役割を果たします。生前に財産を贈与することで、結果的に相続税の負担が軽減できるのです。
代表的な方法として「暦年贈与」があります。これは、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。この非課税枠を活用して、毎年少しずつ財産を移転することで、長期的に大きな節税効果が期待できます。受贈者が複数いる場合は、それぞれに110万円ずつ贈与が行えます。より多くの財産を非課税で移せるのです。
「相続時精算課税制度」や「教育資金・結婚資金の一括贈与特例」など、様々な特例制度も活用できます。例えば、相続時精算課税制度の利用で、2,500万円までの贈与が非課税になります。他の制度と組み合わせて、計画的に活用することがおすすめです。

贈与のタイミングや、贈与先の選択も戦略的に考えなければなりません。相続人以外の孫への贈与は、相続発生前7年以内の贈与であっても、相続財産に加算されないのです。直前の贈与でも有効な場合があります。早い段階から計画的に贈与を始めることで、節税の効果を最大化できるでしょう。
2024年の税制改正から、生前贈与加算の持ち戻し期間が、3年から7年に延長されました。相続発生前の7年以内の贈与は、相続財産に加算されます。しかし、早期の贈与や相続人以外への贈与は、現在においても有効な対策です。贈与の事実を証明するために、贈与契約書や金銭授受の記録など、客観的な証拠を残しましょう。
※加算対象は相続人への贈与に限られ、相続人以外(例:孫)への贈与は対象外です。
生前贈与を戦略的に活用するためには「早期かつ計画的な実行」が不可欠です。各種制度の組み合わせや、専門家の活用なども大切になります。このような対策を意識することで、相続税の負担を軽減できます。家族間のトラブル防止にもつながるでしょう。生前贈与は、家族の将来を見据えた、資産管理の一環として最適な対策です。
| 比較項目 | 生前贈与を活用しない場合 | 生前贈与を戦略的に活用した場合 | ポイント・備考 |
| 相続税課税価格 | 例:1億円 | 例:8,000万円(贈与で2,000万円移転) | 生前贈与によって相続財産を減少できる |
| 相続税額 | 例:770万円 | 例:470万円 | 生前贈与により相続税が約300万円軽減 |
| 贈与税額 | 0円 | 0円(基礎控除内)または少額 | 年間110万円以内なら贈与税はかからない |
| 合計税負担 | 770万円 | 470万円 | 生前贈与で総税負担が減る |
| 非課税枠 | なし | 年間110万円×贈与人数×年数 | 長期計画で非課税枠を最大限活用 |
| 相続時精算課税制度 | 利用なし | 2,500万円まで非課税(相続時に合算) | 制度の選択と組み合わせが重要 |
| 生前贈与加算(持ち戻し) | 該当なし | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算 | 令和5年改正で3年→7年に延長。早期からの贈与が有効 |
| 節税効果 | なしまたは限定的 | 大きい | 長期・計画的贈与で効果増大 |
| 注意点 | – | 定期贈与とみなされるリスク、証拠の整備が必要 | 毎年の契約書作成や記録保存が重要 |
| その他の特例 | なし | 教育資金・結婚資金一括贈与、住宅取得資金贈与 | 特例の併用でさらに節税が可能 |
生命保険の非課税枠活用
生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の人数」分の非課税枠が設けられています。この範囲内であれば、相続税は掛かりません。例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、最大1,500万円(500万円×3人)までの保険金が非課税です。これを超える金額については、他の遺産と合算して、相続税の計算対象になります。
※この人数には、相続放棄者も含まれます(ただし、みなし相続人は含まれません)
この非課税枠を活用することで、相続税の課税対象になる財産が減らせるのです。結果的に、相続税の負担が軽くなります。生命保険金は受取人を指定できるので、遺産分割をスムーズに進めたい場合におすすめです。
また、保険金は相続発生後に、すぐに受け取れます。納税資金や葬儀費用の準備にも役立ちます。一方で、非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人の場合です。生命保険の非課税枠を活用することで、相続税対策や資産の承継が実現しやすいでしょう。
| ケース | 法定相続人の人数 | 死亡保険金額 | 非課税枠(500万円×人数) | 非課税となる金額 | 相続税課税対象額 |
| 配偶者+子2人、保険金1,500万円 | 3 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 0円 |
| 配偶者+子2人、保険金3,500万円 | 3 | 3,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 配偶者+子3人、保険金2,500万円 | 4 | 2,500万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 500万円 |
| 配偶者+子1人、保険金800万円 | 2 | 800万円 | 1,000万円 | 800万円 | 0円 |
| 配偶者+子1人、保険金3,000万円 | 2 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
資産管理会社の設立

資産管理会社の設立は、相続対策の一環としても有効になります。個人で不動産や金融資産を所有する場合、収益に関して、高い所得税が課されます。一方で、資産管理会社という法人を設立して、資産を会社名義で保有・運用することで、法人税率の適用を受けられるのです。それによって、税負担を軽減できる場合が多いです。
さらに、家族を会社の役員に任命して、役員報酬を分配することで、家族内で所得を分散できる可能性があります。これによって、個人の税負担が抑えられて、家族の納税額が減らせるのです。会社から役員報酬を支払うことで、オーナー個人の資産の増加を防ぎます。つまり、相続財産を圧縮する効果が期待できるのです。
※資産管理会社の活用による節税は、実態の伴わない形態では否認リスクがあるため、実務に即した運用が必要です。

役員報酬を家族に支払うことは、贈与税に比べて税負担が少ないため、実質的な生前贈与の手段としても活用できます。このような仕組みを活用することで、資産の円滑な承継や節税、家族への資産移転がスムーズに進むでしょう。
資産管理会社を設立する際は、会社の基本事項(名称、所在地、事業内容など)を決定してください。その後に、定款を作成します。株式会社の場合は、公証人の定款認証が必要になります。資本金の払い込みや、設立登記の手続きも行いましょう。設立後は、税務署や自治体への各種届出も進めなければなりません。
一方で、注意すべき点もあります。例えば、家族を役員にする場合、実際に会社の業務に関与する必要があるのです。形式的な役員では、役員報酬が経費として認められない可能性があります。不動産を会社に移す際には、登録免許税や不動産取得税などの費用が発生することも、考慮しなければなりません。
資産管理会社の設立には、多くのメリットがあります。しかし、専門的な知識や事前の準備が不可欠です。具体的なプランや運用方法については、税理士や司法書士などの専門家に相談しながら、進めることが重要です。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 相続税対策、資産管理、節税 |
| メリット | 法人税率で節税、家族への所得分散、相続財産の圧縮 |
| 設立手順 | 定款作成・認証 → 資本金の払い込み → 登記申請 → 届出 |
| 注意点 | 役員実務の必要性、不動産移転時の税負担 |
| 専門家相談推奨 | 税理士・司法書士に相談が重要 |
家族信託の活用

家族信託は、近年の相続対策の1つとして注目されています。自分の財産を信頼できる家族に託して、管理や承継を行う仕組みです。本人が認知症などで、判断能力が低下した場合でも、家族が財産を管理できます。これによって、財産の凍結や無用なトラブルが避けられます。
さらに、家族信託の場合、自分の死後に配偶者へ、その後は子や孫へ、複数世代にわたる財産の承継先を指定できるのです。複雑な家族構成や、特定の相続人に財産を残したい場合にも、柔軟に対応できます。一方で、家族信託は相続税の節税効果は直接的には限定されますが、資産管理の柔軟性により結果的にトラブルや課税リスクの回避につながるケースもあります。近年生まれた制度でもあるため、利用する場合は、専門家のアドバイスを受けましょう。
| 項目 | 内容・特徴 |
| 主な目的 | 柔軟な財産管理・承継、認知症対策、相続トラブル防止 |
| 財産管理の柔軟性 | 本人が判断能力を失っても、家族が財産管理・運用できる |
| 承継先の指定範囲 | 一次相続だけでなく、二次・三次相続まで指定可能 |
| 手続きの簡易化 | 遺産分割協議が不要になり、相続発生時の手続きがスムーズ |
| 家族構成への対応 | 再婚家庭や子供のいない家庭など、複雑な家族構成にも柔軟に対応 |
| 節税効果 | 相続税・贈与税の節税効果は原則として直接的な節税効果は限定的 |
| 法的・税務上の注意点 | 制度が新しく、法的・税務上の解釈が確定していない部分もあるため、専門家のサポートが必要 |
| リスク対策 | 詐欺被害や不適切な財産処分のリスク軽減、倒産隔離機能あり |
| 代表的な活用例 | 認知症対策、二次相続対策、特定の相続人への承継指定など |
相続対策を成功させるためのポイント
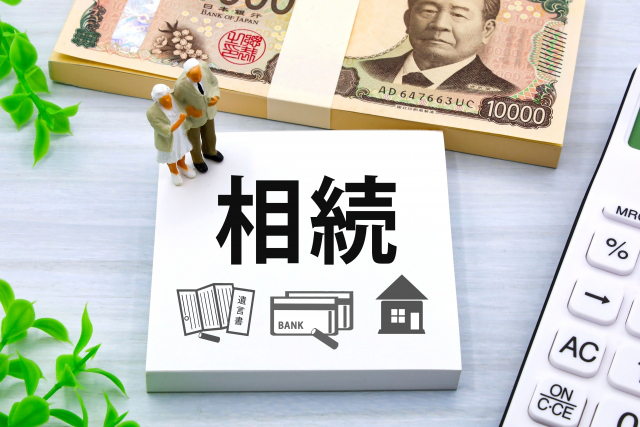
富裕層が相続対策を円滑に進めるためには、計画的かつ早期に取り組むことが必要です。時間をかけて準備を行うことによって、資産承継や節税の選択肢が広がります。生前贈与や家族信託、不動産の活用、遺言書の作成など、複数の手段を組み合わせて、総合的に対策を進めましょう。
先述の通り、非課税枠を活用した贈与や、相続時精算課税制度、教育資金や結婚・子育て資金の特例などを検討してください。資産を計画的に移転することで、相続税の負担が抑えられます。
家族信託の活用によって、本人が認知症などで判断能力を失った場合でも、資産管理や承継が続けられます。相続税の納税資金を、事前に準備することも大切です。不動産が多い場合は、現金化や生命保険の活用などで、納税資金が確保できます。
一方で、相続や税務に関する知識は専門性が高いため、信頼できる税理士や金融の専門家と連携しましょう。最新の法制度や、有効な対策を取り入れることが重要です。富裕層の相続対策は、多角的なアプローチと専門家のサポートが欠かせません。このような対策を行うことで、円満な資産承継と家族の安心へとつながります。
早期の準備と専門家の活用
相続において、認知症などで本人が意思表示できない可能性があります。その場合、口座の凍結や手続きの遅延などのリスクが高まるでしょう。事前に自分の意思を明確にして、遺言書の作成や財産の分割方法、生前贈与などの対策を進めてください。
また、相続は法律や税務、財務など、多岐にわたる知識が必要です。弁護士や税理士、FPなどの専門家を、早い段階から活用するのがおすすめです。
| 専門家 | 主な役割・活用ポイント |
| 弁護士 | ・遺言書の作成支援 ・相続争いの調停・訴訟対応 ・遺産分割協議のサポート ・成年後見制度の利用支援 ・家族構成や財産状況の詳細な説明が重要 ・早期からの相談が効果的 |
| 税理士 | ・相続税対策や申告手続き ・生前贈与や不動産評価、特例適用のアドバイス ・最新の税制や法改正への対応 ・複雑な税務処理のサポート |
相続対策を考えるうえで、FPの存在は有効です。相続制度は非常に複雑になります。何から手を付けるべきなのか、分からない方も多いかもしれません。FPは家族全体のライフプランや、資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供します。
弁護士や税理士とは異なり、相談者や家族の将来設計を見据えた助言が行えるのです。一方で、法律的な判断や税務申告の代行などの専門業務は対象外になります。実際の手続きや法的な問題が発生した場合には、税理士や弁護士と連携して対応します。
FPを含めた専門家は、遺言書の作成や相続税対策、家族間の意見調整など、実務面で大きな役割を果たします。まずは、相続に強い専門家を選び、初回の相談で相性や料金体系を確認しましょう。自分や家族の状況に応じて、最適なアドバイスを受けることが重要です。
| FPの概要 | 内容・特徴 |
| 主な役割 | ・相続全体の流れや制度、税制の整理と説明 ・家族構成や資産状況に合わせた、相続対策の提案 ・生前贈与や不動産・金融資産の整理、老後資金とのバランス設計 ・遺産分割や資産運用のアドバイス |
| 相談できる内容 | ・相続の対象 ・相続税の概算や節税方法 ・生前贈与の活用法 ・不動産や金融資産の整理 ・相続発生後の手続きや資産活用 |
| 強み | ・家族全体の将来設計を踏まえた総合的な助言 ・相続前後のトータルサポート ・必要に応じて、弁護士や税理士などの他士業への橋渡し |
| 注意点 | ・法律判断や税務申告の代行は不可 ・具体的な手続きや法的トラブル発生時は、士業(弁護士・税理士など)との連携が必要 |
| 選ぶポイント | ・相続関連の資格や経験 ・最新の税制や法改正への対応力 ・家族関係や資産状況に配慮した提案力 |
| 活用方法 | ・定期的な資産状況や家計の見直し ・ライフイベントや将来の変化に応じた、アドバイスの継続 |
税制改正への対応とリスク管理

相続対策を進めるうえで、税制改正への対応とリスク管理は欠かせません。相続税や贈与税の制度は、定期的に見直されています。最新の制度内容や改正点を把握して、自分や家族の資産状況に、どのような影響があるのかを確認しましょう。
例えば、過去の改正例としては、相続税の基礎控除額の引き下げになります。死亡保険金の非課税枠や、生前贈与に関する特例措置なども変更されました。リスク管理の面では、定期的に資産や家族構成の変化を見直しましょう。法改正やライフイベントに応じて、相続計画を更新する必要があります。将来的な制度の変更を見越したシミュレーションや、複数の対策案の検討も有効です。
家族間のコミュニケーションの重要性

相続において、家族間の円滑なコミュニケーションは必須です。遺産分割や相続税の問題は、家族の思いや立場が深く絡み合います。事前の話し合いが進まない場合、相続のトラブルが発生しやすくなります。親が元気な間に家族が集まり、財産の状況や分け方、介護や役割分担について、率直に話し合いましょう。
後の争いを防ぐためには、このような家族会議が重要です。家族会議の場では、親の希望や思いが細かく伝えられます。遺言書では、伝わりにくい気持ちも共有できます。疑問や不安を解消することで、誤解や不満の芽を早期に摘み取れるのです。必要に応じて、税理士や司法書士などを活用してください。法律や税務の面で、安心して相続の準備が進められます。早期から情報共有と意見交換を行うことが、円満な相続につながります。
相続は「財産を遺す」だけではない

相続は単純に「財産を残すこと」ではありません、富裕層にとっては、それ以上の意味を持ちます。家族の絆を守り、事業の継続を支えて、本人の想いを次世代へ伝える準備です。そのためには、遺言書の作成や信託の活用、事業承継に向けた対策、さらには認知症などのリスクにも備えなければなりません。トラブルを避けて、資産を円滑に承継するためには、法的な仕組みや税制を理解しましょう。相続は、早めに備えることが重要です。
近年では、相続を通じて、社会貢献する動きが広まっています。資産の一部を寄付に充てたり、公益活動に参加したりすることで、社会とのつながりを深める富裕層が増えているのです。このように、富裕層の相続は、単純な財産の受け渡しではありません。家族や事業、社会の未来を見据えた包括的な取り組みです。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼