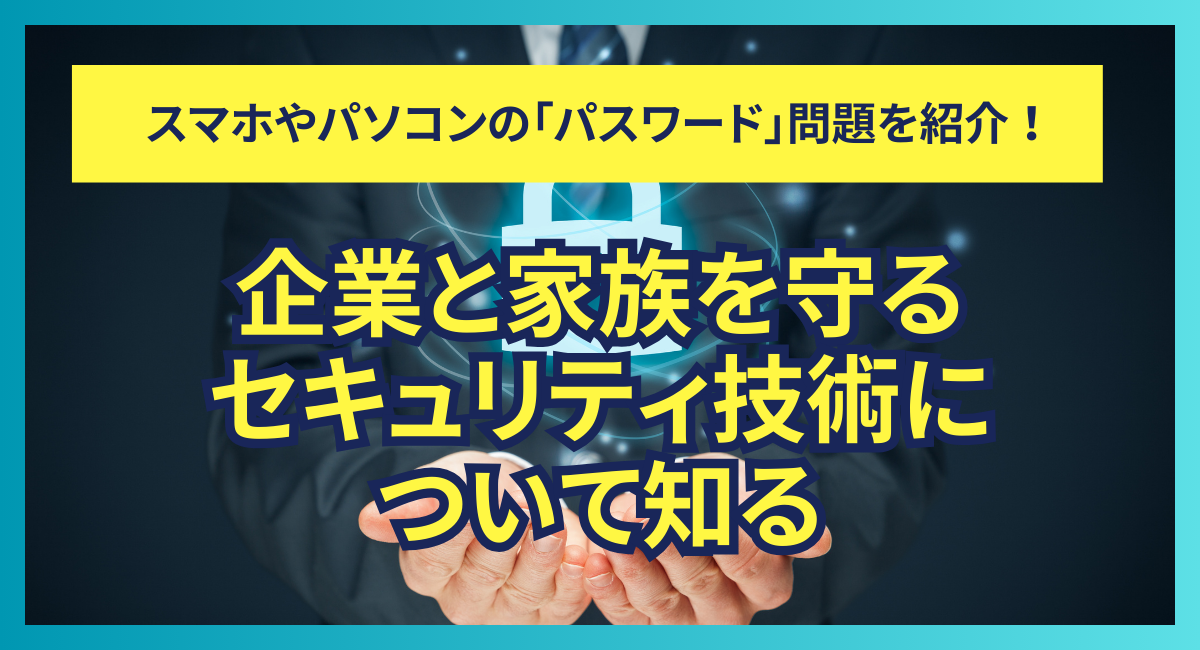スマホの普及により、私たちの生活はかつてない速度でデジタル化しています。銀行口座の管理やオンラインショッピング、仕事のやり取りはもちろん、家族や友人との思い出まで、さまざまな情報が「デジタルの世界」に保存されるようになりました。
そして、これらのデータへの入り口を守るのが、身近でありながら重要な存在であるパスワードです。しかし「パスワード」というテーマには、大きなリスクも潜んでいます。複雑なセキュリティ対策に追いつけず「覚えられない」「忘れてしまった」と悩む人も少なくありません。さらに、所有者が亡くなった場合、パスワードが分からなければ、資産や大切なデータにアクセスできず、失われてしまう可能性があります。
パスワードの管理は、単なる技術的な問題にとどまらず、セキュリティと利便性の両面で社会的にも重要なテーマです。今回の記事では、パスワードの安全対策から、将来の資産・データの相続に至るまで、パスワードの重要性と向き合うポイントを解説します。
セキュリティの第一線に立つパスワード

パスワードは、デジタルサービスを活用するときに必ず通る「入口のカギ」のような役割を果たしています。もし、このカギが他人の手に渡ってしまえば、重要な情報が危険にさらされる可能性が高いです。個人にとっては、プライバシーの侵害や金銭的な被害が発生して、企業であれば、顧客情報や知的財産といった、機密データがv流出してしまう可能性があります。
現代社会では、情報の価値がますます高まっています。一度の漏洩が、人生や組織に取り返しのつかない影響をもたらすことも、珍しくありません。一方で、強固なセキュリティを意識して、複雑すぎるパスワードを設定すると、ユーザー自身がその管理に苦労するという、ジレンマも存在します。
大文字・小文字・記号や数字を組み合わせた長いパスワードは、安全性を高めます。しかし、自身が覚えられずに「ノートや紙に書いて保存する」「複数のサービスで同じパスワードを使い回す」といった、危険な行動をとるケースが多いです。
パスワードは、セキュリティを守るための重要な壁です。一方で、デジタル化が進むにつれて、日常的に利用するアカウントの数は年々増加しています。ショッピングサイトや動画配信サービス、公共機関の手続き用ポータルなど、生活のあらゆる場面で、新しいIDとパスワードが求められます。
| テーマ | 内容 |
| パスワードの役割 | デジタルサービス利用時の「入口のカギ」。他人に渡ると、重要情報が危険にさらされる。 |
| 個人への影響 | プライバシー侵害、金銭的被害につながる可能性がある。 |
| 企業への影響 | 顧客情報や知的財産など、機密データ流出のリスクがある。 |
| 現代社会での重要性 | 情報の価値が高まり、一度の漏洩が人生や組織に深刻な影響を及ぼす。 |
| セキュリティと使いやすさのジレンマ | 強固なパスワード(大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた長いもの)は安全だが、覚えるのが困難。 |
| よくある危険な行動 | ・ノートや紙に書いて保存 ・複数のサービスで同じパスワードを使い回す |
| 現代の状況 | デジタル化でアカウント数が増加(ショッピング、動画配信、公共機関手続きなど)。日常で新しいIDとパスワードが必要になる。 |
利便性とリスクマネジメントの視点から見るパスワード
セキュリティの強化を試みると、複雑で長いパスワードや、多要素認証の導入が求められます。たとえば「大文字・小文字・数字・記号を含む12文字以上」といったルールは、外部からの不正アクセスを防ぎます。
複雑さを避けるために、短く単純なパスワードを設定してしまったり、異なるサービス間で、同じパスワードを使い回したりするケースも多いです。このような習慣は、利便性を優先した行動かもしれません。実際には、不正アクセスやアカウント乗っ取りといった、重大なリスクを一気に引き寄せる可能性が高いです。
もし利便性を優先した場合、業務で利用するアカウントやシステムが、狙われやすくなります。情報流出や不正利用といった、被害に直結する可能性が高まります。逆にセキュリティを優先しすぎると、利用者は、煩雑な手続きが必要です。業務の効率が下がったり、ユーザー体験が大きく損なわれたりする恐れがあります。
このように、利便性とセキュリティは、完全にどちらか一方に偏ることは、現実的ではありません。そのため、現代のパスワード管理においては「安全性」と「使いやすさ」をどのように両立させるのかが、本質的な課題となっています。
| 観点 | セキュリティを重視した場合 | 利便性を重視した場合 |
| パスワードの特徴 | ・大文字、小文字、数字、記号を含む12文字以上の複雑なパスワード ・多要素認証の導入 | ・短く単純なパスワード ・複数サービスで使い回し |
| メリット | ・不正アクセスを防ぎやすい ・アカウントの安全性が大幅に向上 | ・覚えやすい ・日常での入力や管理がしやすい |
| デメリット | ・覚えにくく管理が大変 ・ログイン時の手間が増える | ・不正アクセスやアカウント乗っ取りのリスクが高まる |
| 個人ユーザーへの影響 | ・情報を守れる ・安心して利用できる | ・利便性はあるが、被害発生の可能性が高い |
| 企業・組織への影響 | ・業務アカウントやシステムの安全性が強化 | ・攻撃の標的になりやすく、情報流出や不正利用のリスクが増す |
パスワードを設定した本人がいない場合を考える

自身が日常的に利用している、スマホやパソコンのパスワードをうっかり忘れてしまうことは、誰にでも起こり得る問題です。このような場合、大切に保管していた思い出の写真や、業務に欠かせない重要なデータにアクセスできなくなり、非常に困惑することがあります。
特に、仕事のデータや顧客情報などがロックされてしまうと、業務の継続に支障をきたす恐れもあります。こうした状況では、ロック解除がどうしても必要となり、迅速かつ安全な方法で、アクセスの回復を行わなければなりません。
さらに、パスワード解除が必要となるケースは、個人の問題ではないのです。たとえば、家族や職場の同僚が突然亡くなった際には、故人のスマホやパソコンの中にあるデータに、適切にアクセスする必要があります。資産整理や相続手続きを円滑に進めるためにも、パスワードの解除が不可欠です。
企業の場合では、退職した社員のアカウント管理やアクセス権限の解除も、重要な課題です。これを怠ると、情報漏洩や業務上のリスクが高まります。こうした背景から、正しい法的手続きに則ったうえで、専門的な技術と知識を持った対応が求められます。
個人の利便性を保つだけでなく、家族の安心や企業の安全を守るためにも、パスワード解除は現代の欠かせないテーマです。
「パスワード」の解除ができない影響について

情報セキュリティの重要性が、年々高まっている現代で、パスワードは大切な認証手段です。個人のアカウントから、企業の重要システムに至るまで、パスワードは不正アクセスを防ぐための最前線になります。しかし、実際の現場では、理想的な運用ができるとは限りません。
たとえば「急を要する業務で、アクセス権限をすぐ取得する必要がある」「相続の現場でスマホを、早急にロック解除しなければならない」といった状況は、日常的に発生する問題です。セキュリティ上の厳格なルールと、利便性の間で、どのように折り合いをつけるかが大きな課題です。
| 場面 | 問題点 | 主な影響 | 背景と原因 | 必要な対策や工夫 |
| 日常生活 | スマホ・PCのロック解除の失敗、パスワードの忘れ | 電話・メッセージ・電子決済が一時的に制限、クラウドやSNSにアクセス不可。 写真・文書・人とのつながりを失う可能性がある | デジタル機器の依存度の高さ | パスワード管理の工夫、リカバリー手段の準備 |
| ビジネス現場 | 特定の社員しか知らないパスワードに依存、社員の退職・不在でアクセス不能 | 業務の停滞、生産性低下、プロジェクト納期遅延、組織全体のリスクが増える | パスワード・権限の属人化、管理制度の不備 | アカウント共有・アクセス権限管理の明確化、組織的なパスワード管理体制 |
| 相続・資産整理 | 故人のスマホ・PC・クラウドへのログインが不可 | 思い出の写真・連絡先にアクセスできない、デジタル資産が喪失、相続手続きの遅延、相続人間のトラブルが発生する | セキュリティ強化(複雑なパスワードや二段階認証)と、パスワードの引き継ぎ不足 | デジタル資産管理の事前準備、パスワード・アカウント情報の適切な共有・引き継ぎ |
日常生活の場合

スマホやPCのロック解除に失敗して、パスワードを思い出せないことは、誰にでも起こり得る身近なトラブルです。一時的にデバイスが使えなくなるだけでも、電話やメッセージの確認、電子決済といった基本的な機能が制限されます。
日々の行動に大きな支障を与えるかもしれません。クラウドサービスやSNSなどのオンラインアカウントにアクセスできなくなると、写真や文書といった大切なデータや、人とのつながりに直結するコミュニケーション手段を失います。
ビジネス現場の場合

ビジネスの現場においては、パスワードが思わぬリスクを生み出すことがあります。たとえば、社員が急に退職したり、事故や病気によって長期間不在になった場合、その人物しか知らないアカウントやシステムに誰もアクセスできないかもしれません。
特に、重要なシステムや業務用ツールのパスワードが、個人に依存していた場合、業務が滞ってしまうでしょう。このような状況が長引けば、組織全体の生産性が低下するだけでなく、プロジェクト納期の遅延につながる可能性もあります。
また、適切な管理体制が整備されていない場合、こうした事態は、経営そのものに深刻な影響を及ぼす危険性があります。中小企業においては、限られた人員で業務を進めているケースが多いです。一人の社員に、権限や情報が集中してしまう傾向があるかもしれません。その人が不在になるだけで、業務が停止するリスクは大きいでしょう。
相続・デジタル資産の整理の場合

相続や資産整理の場面で、特に課題なのが、デジタル資産へのアクセス問題です。故人が生前に使用していたスマホやパソコン、各種クラウドサービスにログインできなくなると、その中に保存されていた思い出の写真や連絡先が、確認できないかもしれません。また、重要な金融資産が事実上「失われてしまう」リスクが生じます。
こうした問題の背景には、「パスワードの引き継ぎ」が十分に行われていない現状があります。多くの人がセキュリティ意識の高まりから、複雑なパスワードや二段階認証を導入するケースが多いです。その仕組みが、逆に家族にとって「相続の見えない壁」となっているのです。
資産整理の過程で、これらの情報にアクセスできない場合、相続手続きが止まってしまいます。相続全体の進行に、大きな遅れが生じることも少なくありません。特に、経済的価値をもつデジタル資産については、相続財産として、正式に評価・分配できない事態につながります。法的な手続きや相続人同士の、トラブルの火種となる恐れもあるのです。
そのため、近年では「デジタル資産」という概念が広く注目されるようになっています。事前にパスワードやアカウント情報を適切に管理して、安全かつ確実に引き継ぐ工夫が求められています。相続や資産整理の円滑化には、このような備えを、生前から整えておくことが大切です。
万が一に備えたスマホ・パソコンのパスワード解除の対策!基本構造と主な手法

複雑な文字列や多段階の認証は、外部からの不正アクセスを防ぐうえで、大きな役割を果たしています。個人のプライバシーや、デジタル資産を守るためには欠かせません。しかし、利用者本人以外がアクセスしようとすると、設定された「ロック」を解くことが大きなハードルです。
家族であっても、故人が生前に設定していたパスワードを、把握していないケースが多いです。たとえば、写真や動画といった大切な思い出、日記代わりのSNSの記録、金融情報や仮想通貨といった、重要な資産にたどり着くことができません。
故人の残した資産や情報が、アクセスできない状態が続く可能性があります。家族にとっては、精神的にも経済的にも大きな負担となってしまいます。このような状況は、相続手続きや資産管理といった社会的・法的な問題にも、直結する可能性が高いです。そこで重要となるのが、パスワード解除に関する基本的な仕組みになります。
パスワードは「守るためのカギ」であるだけでなく、本人不在の際に「適切に引き継げるのか」という観点も大切です。相続の分野でも、デジタル資産やアカウント管理を、どのように円滑に行うのか、ますます重要になります。そうした背景を踏まえながら、パスワード解除に関する基本的な考え方を、ここでは整理していきます。
正規ルートでのパスワード解除方法

多くのオンラインサービスでは、ユーザーが「パスワードを忘れた」場合に備えて、再設定の仕組みが、あらかじめ用意されています。たとえば、登録しているメールアドレスやSMSを利用した本人確認のケースです。送信された確認コードを入力することで、新しいパスワードを設定し直せる仕組みです。
より厳格なセキュリティ体制を敷いているサービスでは、身分証明書を提出する方法も導入されています。これにより、不正な第三者がなりすまして侵入することを、防ぐ役割も果たしています。たとえば、Apple IDやGoogleアカウントといった大手サービスでは、本人確認のためのステップが、複層的に設計されているのが特徴です。
利用者の利便性を確保しながらも、セキュリティを損なわない工夫がなされています。複数の認証方法を組み合わせる「二段階認証」や「多要素認証」の仕組みは、仮にひとつの手段が使えなくなっても、別の確認方法で復旧できるように設計されているのです。
さらに近年では、本人が利用できない場合への対応体制も、重視されるようになりました。AppleやGoogleなどは、一定の国や地域で、法的手続きを経ることで家族や代理人がアカウントにアクセスできる仕組みを整えつつあります。
パスワード解除のための技術的手法

正規の手続きによるアカウント復旧やロック解除が、どうしても難しい場合には、デジタルフォレンジック専門業者が解析を行うケースがあります。デジタルフォレンジック専門業者は、専用の解析ツールや技術を駆使して、パスワードや暗号化ファイルについて、多角的に調査を進めるのです。
たとえば、パスワードリカバリープログラムを用いた手法、暗号化されたディスクやファイルの構造を分析して、突破口を探ります。これらの手法は、決して簡単なものではありません。パスワードや暗号技術そのものが、非常に強固に設計されているのです。
解析には、高度な専門知識と経験が不可欠です。場合によっては、専用のハードウェアや膨大な計算が必要になります。作業そのものに長い時間を要する場合も多いです。そのため、依頼する側にとっては、相応のコストが発生する点も無視できないでしょう。しかし、サイバー事件の原因解明や、正当な相続財産の保護といった、社会的に大きな意義を持つ重要な作業になります。
注意するべきパスワード解除の問題

パスワードの解除やアカウントへのアクセスを検討する際に、重視すべきなのは「その行為に正当な権限があるか」という点です。本人の同意を得ていない、相続手続きや代理権の確認がなされていない状況で、無理なパスワード解除はおすすめできません。不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。つまり「善意だから許される」わけではないのです。
法律上は、あくまで不正アクセスとして、扱われてしまうリスクがあります。実際に、相続の場面で、故人のスマホやパソコンにアクセスしようとするケースは増えています。一方で、相続人の間で「誰がアクセスできる権限を持つのか」という点が争点になるのです。
故人の資産整理は、事前の対策を行っていないと、複雑化するかもしれません。また、企業の端末であれば、適切な承認なしにアクセスした社員が、責任を問われるケースも考えられます。そのため、より一層の慎重さが必要です。本人の同意が得られない場合や、本人がすでに亡くなっている場合には、必ず正式な相続手続きや、代理権確認の「正規のプロセス」が重要になります。
| テーマ | 内容 |
| 重視すべき点 | アカウントへのアクセスやパスワード解除には「正当な権限」が必要。 |
| 違法リスク | 本人の同意がない状態や、相続手続き・代理権の確認がない状態での解除は、不正アクセス禁止法に抵触する可能性がある。善意でも、違法になり得る。 |
| 相続における課題 | 故人のスマホ・PCへのアクセス事例が増加。誰がアクセス権限を持つかが、相続人間の争点になる。 |
| 複雑化のリスク | 事前にデジタル資産整理をしていないと、相続手続きが複雑化する可能性がある。 |
| 企業の場合 | 社員が承認を得ずに端末へアクセスすると、責任を問われる可能性があるため、慎重さが必要になる。 |
| 必要な正規のプロセス | 本人の同意が得られない場合や故人の場合は、必ず正式な相続手続き・代理権を確認しなければならない。 |
パスワード解除をめぐるセキュリティの課題

強固なセキュリティを維持するには、簡単に解除されない仕組みが大切です。たとえば、多要素認証や厳格な本人確認、一定回数以上の誤入力でアカウントを一時停止するといった仕組みは、不正利用を防ぐうえで効果的です。
一方で、本人が亡くなった場合や端末が突然利用不能になった場合には、正当な家族や関係者であってもアクセスが難しくなります。大切なデータや資産にたどり着けないという矛盾が生じてしまいます。
こうした矛盾は、現代ならではの「デジタル資産の承継」や「アカウント管理」で大きな課題です。故人が所有していた、仮想通貨やオンラインバンキングのアカウントは、パスワードが分からなければ、実質的な継承が不可能になるかもしれません。SNSやクラウドに保存された思い出のデータも、アクセスできなければ、結果的に失われてしまいます。
パスワード依存の危うさと新たな認証の必要性

パスワードという仕組みは、昔から最も広く使われている認証方法です。一方で「流出すれば、すべてのセキュリティが破られてしまう」という弱点を抱えています。利用者のパスワードが、第三者に知られてしまえば、正規のユーザーとして装われるかもしれません。それによって、内部の情報や資産に簡単にアクセスされる恐れがあります。
また、人間の記憶には限界があり、先述の通り、サービスごとに、長く複雑な文字列パスワードを設定し続けることが難しいです。どうしても「短くて覚えやすい単純なパスワード」を使うケースが多いです。一度設定したものを、複数のサービスでそのまま使い回したりする傾向があります。こうした習慣は、本人にとっては、利便性の確保という意味があるかもしれません。
パスワードは、利用者にとっては、手軽で便利な仕組みでありながら、その性質上、大きなリスクも発生します。そのため、近年では、多要素認証の導入や、パスワードレス認証の仕組み、生体認証やデバイス連携を組み合わせた対策が注目されているのです。
多要素認証(MFA)とパスワードの普及に伴う新しい障壁

スマホによる認証コードの確認や、物理的なセキュリティキーを用いるなど、複数の認証要素を組み合わせる「多要素認証(MFA)」が広く普及するようになりました。これによって、利用者がパスワードを流出させてしまった場合でも、実際にログインするためには、追加の認証要素が必要です。
不正アクセスを試みる側にとっては、大きなハードルです。銀行やクラウドサービス、大手IT企業のアカウントなどでも、標準的に導入されています。一方で、多要素認証には、別の課題も存在するのです。それは「利用するスマホや、認証手段を紛失した場合にどうなるのか」という問題です。
たとえば、多要素認証に設定したスマホをなくしたり、セキュリティキーを物理的に破損・紛失してしまったりする場合です。セキュリティの強化で、自身の利便性や柔軟性が制限されてしまうという矛盾を抱えています。このようなトラブルが、業務の停滞や個人の不便さにつながることも多いです。
| 多要素認証(MFA)について | 内容 |
| 概要 | パスワードに加えて、スマホの認証コードや物理セキュリティキーなど、複数の認証要素を組み合わせる仕組み。 |
| 効果 | パスワードが流出しても、追加の認証が必要となり、不正アクセスが大幅に困難になる。 |
| 普及状況 | 銀行、クラウドサービス、大手IT企業のアカウントなどで、標準的に導入している。 |
| 課題 | 認証手段(スマホ・セキュリティキー)を紛失・破損した場合、ユーザー自身がアクセスできなくなる可能性がある。 |
| 影響 | 業務の停滞や、個人の利便性低下につながる恐れがある。 |
| 解決策(リカバリー手段) | ・バックアップコードの保管 ・代替デバイスの登録 ・サポート窓口での本人確認による復旧 |
法行機関とパスワードの関わりにおけるプライバシー問題

個人のスマホは、セキュリティを意図的に弱めたり、外部からのアクセスを容易にする仕組みを認めたりすると、プライバシーや安全性が大きく損なわれるリスクがあります。この対立を象徴する事例が、2016年にアメリカで起きた「AppleとFBIの対立事件」です。
FBIはテロ事件の捜査を理由に、iPhoneの解除を求めました。しかし、Appleは「一度でも解除のための裏口を作れば、すべての利用者のセキュリティを根本から破壊される」として、強く拒否したのです。こうした議論が難しいのは、どちらの主張にも、正当な理由が存在するためです。
しかし、技術的な「例外の扉」をつくることは、サイバー犯罪者や不正アクセスの突破口となり得ます。セキュリティと利便性、プライバシーと公共の安全、これら相反する価値の調和を、どのように実現するのか、世界中で現在も続いているテーマです。
パスワードのセキュリティ面と利便性の可能性

パスワードは、私たちの大切な情報を守る「カギ」である一方で、セキュリティと利便性という相反する課題を抱えています。強固なパスワードを設定すれば、安全性は高まるでしょう。しかし、パスワードを覚えるのが難しくなり、日常の利用に不便さを感じることもあります。
逆に、覚えやすさを重視すると、不正アクセスや情報漏れのリスクが増大します。つまり、今求められているのは、セキュリティを確保しながらも、生活の利便性を損なわないパスワード管理の工夫なのです。
ユーザー側で行えるパスワード管理の対策法

安全なアカウント管理を実現するためには、まず「強力で特定しにくいパスワード」を各サービスごとに設定することが基本です。しかし、人間の記憶には限界があるため、複雑なパスワードを覚えるのは、現実的ではありません。そこで有効な対策なのが、パスワードマネージャーの導入です。
パスワードマネージャーを利用すれば、一つの「マスターパスワード」を覚えておくだけで対策できます。さまざまなサービスに、異なる複雑なパスワードを、自動的に生成・保存・入力できるため、利便性を損なうことはありません。
セキュリティを高めるためには、こうしたパスワード管理の仕組みに加えて「多層防御」を意識することが重要です。たとえば、2段階認証を有効化すれば、パスワードが仮に第三者に漏洩したとしても、端末による認証が求められます。それによって、不正アクセスを防げる確率は格段に高まるのです。
相続の場面では、デジタル資産を調べるうえで、多層防御は大きなハードルにつながるかもしれません。しかし、そのような場合でも、遺言書やエンディングノートなどを活用して、マスターパスワードの存在を間接的に記載することで、相続のトラブルが防げます。
企業視点で行えるセキュリティの対策

企業におけるアカウント管理は、単なるセキュリティ対策にとどまりません。組織の健全な運営と、業務継続に直結する重要なテーマです。企業として統一した、アカウント管理ルールを明文化する必要があります。
社員が事故や病気などで、突然不在になった場合は、注意しなければなりません。その社員しか知らないパスワードやアクセス情報に依存していた場合、ビジネスへの影響が深刻化する恐れがあります。最悪の場合、事業活動が一時的に止まってしまうリスクもあるのです。
こうしたトラブルを回避するためには、関係者が適切にアカウントを引き継ぎ、速やかに継続利用できる体制を、構築しなければなりません。このような対策は、リスク回避にとどまらず、取引先や顧客からの信頼につながります。つまり、アカウント管理は、従業員一人ひとりの責任に任せきりにするのではなく、組織として仕組みを整えるのが大切です。
| 観点 | 要点 |
| 重要性 | アカウント管理はセキュリティだけでなく業務継続に直結 |
| リスク | 社員不在時にパスワード依存で業務が停止する恐れ |
| 対策 | 組織として統一ルールを整備して、引継ぎ体制を構築 |
| 効果 | リスク回避と顧客・取引先からの信頼向上 |
パスワード問題で困った場合は専門業者へ依頼しよう

パスワードの問題は、企業や日常生活、相続に深く結びついているデジタル社会ならではの課題です。自力で解決を試みる方法もありますが、誤った操作によって、データが消去されたり、法的に問題のある方法に、手を出してしまったりする危険性もあります。そのため、どうしても対応が難しいと感じた場合には、無理をせず早めに専門業者へ相談することが大切です。
専門業者は法的・技術的な知識を備えており、安全性と確実性を重視した手法でサポートしてくれます。重要な情報や思い出を守るため、専門業者の力を借りるという選択肢を持っておくことは、大きな安心につながるでしょう。
まとめ

企業や日常生活、相続に関するパスワード問題は、一見すると単なる技術的なテーマに見えます。しかし、実際には「セキュリティ」「プライバシー」「利便性」の価値観が交差する、複雑で社会的なテーマです。
相続の場面であったり企業の引き継ぎであったり、重要なデータや写真、メモなどの内容は、確認する必要が出てきます。そのためには、本人不在のなかで「パスワード解除において、誰が正当な権限を持っているのか」を、まずは明確にしてください。正規の手続きを試みるのはもちろん、専門業者に依頼するケースを含めて、安全にアクセスすることが大切になります。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル資産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。