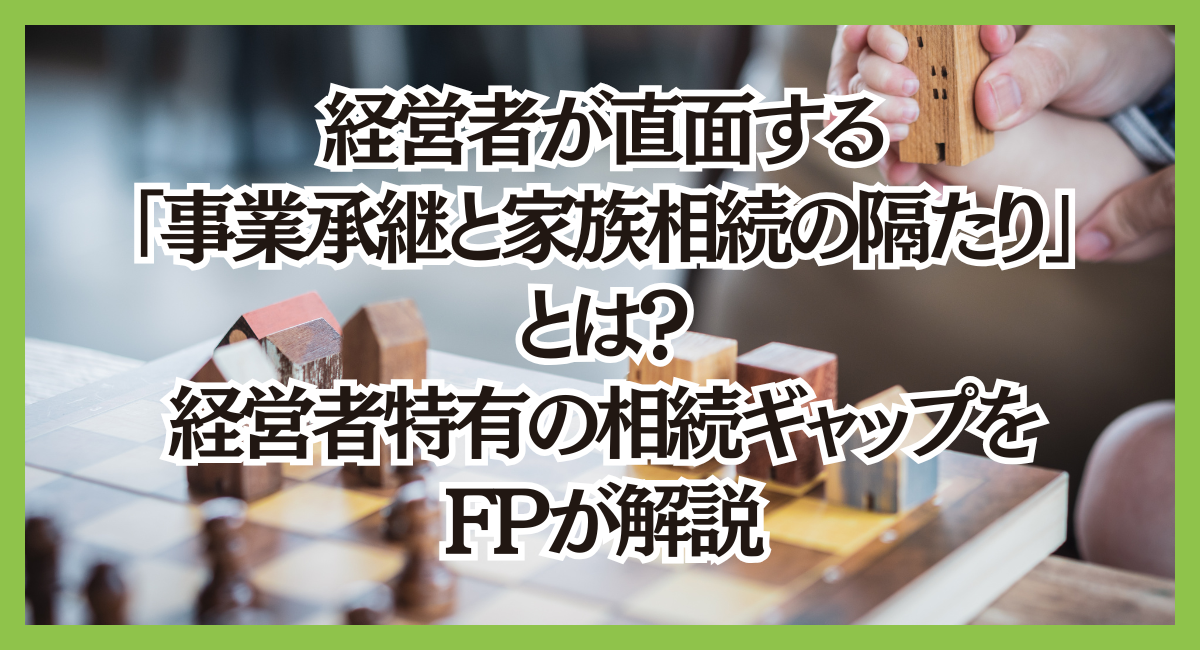経営者にとって「相続」とは、単に資産を分けるという一面的な問題にとどまらず、複雑な二重構造を持つのが実情です。ひとつは会社を将来にわたって存続させるための、事業承継の課題になります。もうひとつは、家族の生活を守るための資産相続の課題です。
この二つは表裏一体でありながら、それぞれの優先順位や視点が一致しないことも多いです。「経営者が描く会社の将来像」と「家族が望む生活の安定」との間に深い溝、つまり「相続ギャップ」が生じやすくなります。
特に、中小企業の経営者にとっては、会社そのものが最も大切な財産であり、自らの努力と歴史を注ぎ込んだ成果です。同時に、それは家族の生活基盤であり、子どもや配偶者にとっては、単に資産の一部、あるいは現金化を望む対象かもしれません。
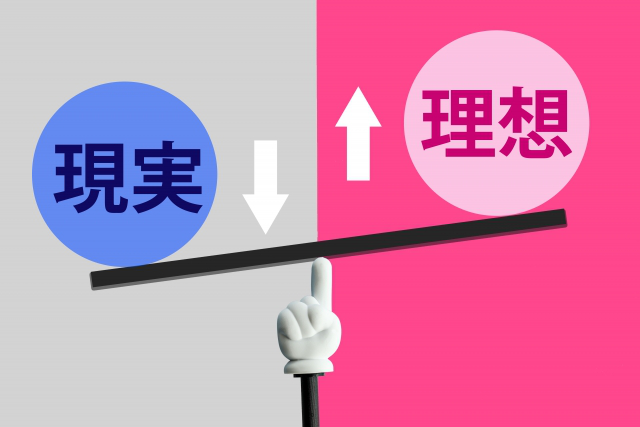
この価値観のずれは、事業承継を阻む大きな障害となり、場合によっては、家族間の対立を招きます。会社の経営基盤を揺るがす可能性があります。また、経営者自身が後継者選びに悩んだり、株式の分配方法を誤ったりすると、会社の意思決定が停滞するでしょう。
こうした問題を回避するためには、経営者の思いを的確に言語化しなければなりません。家族や後継者と共有することが大切です。相続税の対策や事業承継税制の活用など、専門的な知識を踏まえた戦略づくりも不可欠です。
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、経営者の立場と家族の立場をともに理解して、中立的な視点から双方の希望を調整する役割を果たします。今回の記事では、こうした背景を踏まえながら、中小企業の経営者が陥りやすい事業承継と家族相続の相続ギャップを整理していきます。
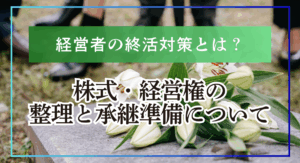
経営者特有の「相続ギャップ」とは

経営者が直面する相続問題は、一般家庭の相続とは、大きく異なるのです。経営者の遺産には、自社株や事業用不動産、会社への貸付金といった、現金以外の資産が多く含まれています。単純に相続財産を分割することが、非常に難しいのです。家族にとっては、現金での生活保障が欠かせません。
FPの視点から見ると、こうした「事業と家族のギャップ」を放置すると、将来的に家族間で、遺産分割を巡るトラブルが発生する恐れがあります。経営権の分散や相続税の納税費用によって、会社の経営危機を招くリスクが高まるのです。たとえば、経営者の株式を複数の相続人で共有することになった場合、会社の重要な意思決定が困難になるでしょう。後継者が相続税の納税資金を確保できないと、株式を売却せざるを得ず、事業承継がうまくいかない事態も生じます。

そのため、経営者は早い段階から「事業を守りつつ、家族の安心も確保できているか」という視点で相続対策を進めなければなりません。具体的には、生前に遺言書や事業承継計画を作成して、自社株の集中や、資産分割の方針を明確にしておくことです。また、必要に応じて、生命保険や信託を活用して、相続税納税資金を準備することが有効です。経営者であるからこそ、専門的な知識と計画的な対策が重要になります。
事業承継と家族相続の「ギャップ」の正体

経営者の資産は、大きく「事業資産」と「個人資産」に分けられます。事業資産には、自社株式や事業用不動産が含まれており、個人資産には、現金や預貯金、投資信託などがあります。ここで注意すべきなのは、事業資産は現金化が難しい点です。相続人の間で、均等に分けることができない可能性が高いです。そのため、相続にあたっては、単純な分割ではなく、相続税の負担や事業の引き継ぎまで考えた工夫が大切になります。
ファイナンシャルプランナー(FP)が提案するのは、資産の正確な評価と相続税のシミュレーションです。非上場株式は『類似業種比準方式』や『純資産価額方式』で評価され、会社規模によっては併用方式が用いられることもあります。会社の規模や利益状況によって、金額が大きく変わります。事業用不動産についても、路線価や固定資産税評価額を基に算出されます。

こうして資産全体の価値を「見える化」することで、相続人に現金をどのくらい分配できるのかが明確になるのです。この見通しがあるからこそ、家族の納得感が得られます。信頼関係を保ちながら、事業承継を進めることができるのです。
早い段階で資産と税負担のシミュレーションを行えば、生命保険を活用して、納税資金を準備したり、贈与や信託といった節税策を検討したりすることも可能です。遺言書や事業承継計画などの法的手続きも、スムーズに進められます。
| 項目 | 内容 |
| 資産区分 | ・事業資産:自社株式、事業用不動産 ・個人資産:現金、預貯金、投資信託など |
| 注意点 | ・事業資産は現金化が難しく、相続人で均等に分けるのが困難 ・単純な分割では不公平が生じて、事業承継にも影響する可能性 |
| 評価方法 | ・非上場株式:類似業種比準方式、純資産価額方式(会社規模・利益状況で大きく変動) ・事業用不動産:路線価、固定資産税評価額を基に算出 |
| 見える化の効果 | ・相続人に、どの程度の現金を分配できるのか、明確にできる ・家族関係を保ちながら、事業承継に進められる |
| 早期対策のメリット | ・生命保険による納税資金の準備が行える ・贈与や信託など、節税策の検討が可能になる ・遺言書や事業承継計画などの手続きで、スムーズに実行できる |
経営者と家族のギャップが生むリスク

「事業と家族のギャップ」を放置すると、さまざまなリスクが生じるでしょう。家族の間では、遺留分請求や相続争いが発生しやすく、感情的な対立によって、円滑な事業承継が妨げられることがあります。たとえば、自社株や事業資産を一部の相続人に集中させた場合、他の相続人が遺留分を主張して、紛争になるケースは少なくありません。
このような問題は、家族関係だけでなく、社員の士気低下や取引先との信頼悪化といった、経営面への悪影響にもつながります。事業面では、経営権が相続人の間で分散すると、重要な意思決定が滞る恐れがあります。

方針の不一致から、事業運営に一定の支障を起こすでしょう。相続税の負担が重くなると、後継者の資金繰りが悪化して、事業資産や株式を売却しなければなりません。最悪の場合、事業の売却や経営危機に直結して、会社と家族双方に深刻な損害をもたらします。
このようなリスクを早期に把握するためには、家族で資産状況を共有することです。資産の明確化により、相続税の見通しや、経営権の配分について、家族が納得できる設計が行えます。遺言書や生前贈与、株式の移転方法など、法的手段を活用すれば、家族間の合意形成と、事業の安定を両立させる対策につながります。
FPが提案するギャップ解消の方法
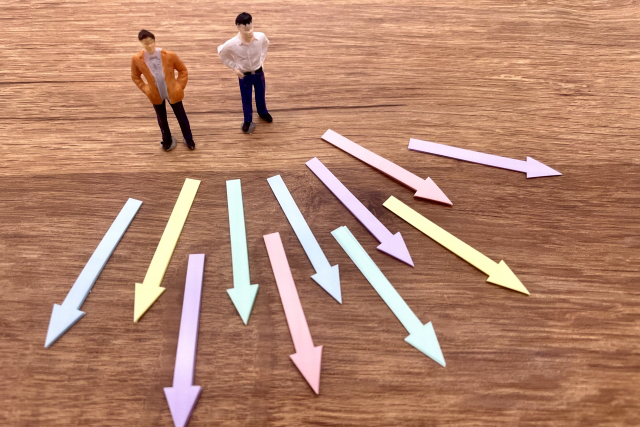
ファイナンシャルプランナー(FP)が提案するギャップ解消の方法には、事業承継プラン、家族資産の保護、総合シミュレーションの三つの柱があります。まず、事業承継プランでは、後継者の選定と育成を早期に進めることを重視します。これにより、経営能力を確実に引き継ぐことができるのです。
株式や持分を段階的に譲渡することで、一度に発生する税負担を最小化できます。そして、経営陣による買収や、事業承継信託の活用によって、経営権を計画的かつ安定的に、移譲する仕組みを整えます。
家族資産の保護については、遺言書や家族信託を活用しましょう。これによって、資産の管理や分配に関するトラブルを未然に防げます。ライフプランに基づいて、資産配分を行うことで、教育費や医療費など、将来の支出もカバーできます。事業承継と家庭の総合シミュレーションを行うことで、事業を守りつつ、家族も安心して暮らせる具体的な数値計画がつくれます。
経営者が相続ギャップを乗り越えた事例

ある中小企業経営者の成功例では、事業承継信託を活用して、自社株を後継者に譲渡しました。現金資産に関しては、配偶者や子どもに適切に分配する方法をとりました。総合シミュレーションを参考に、相続税負担を最小限に抑えることができたのです。また、家族の生活保障も確実に確保されたため、円滑な事業承継と家族の安心が実現しました。
一方で、失敗例としては、事業承継の計画を立てずに、相続が発生したケースです。株式の分配を巡って、兄弟間で争いが生じました。結果として、事業運営が停滞してしまったのです。これは、早期に事業承継の計画を立てず、資産の可視化や整理が不足したことが問題でした。
| 項目 | 成功例 | 失敗例 |
| 準備・計画 | 事業承継信託を活用して、事前に計画的なシミュレーションを実施 | 事業承継計画を立てないまま、相続が発生 |
| 株式・資産の分配 | 自社株を後継者へ譲渡。現金資産を配偶者や子どもに適切に配分。 | 株式分配を巡り、兄弟間で争いが発生 |
| 相続税対策 | FPによるシミュレーションで、相続税を最小限に抑制 | 資産の可視化・整理不足で、税務・分配に混乱 |
| 家族への影響 | 家族の生活保障を確保して、安心な生活を実現 | 相続争いにより、家族関係が悪化 |
| 事業への影響 | 円滑な事業承継が可能となり、経営が安定 | 紛争による事業運営の停滞・混乱 |
経営者のデジタル資産が現代の課題

近年、急速に進むデジタル化は、経営者にとっても、業務運営や資産管理の手法を大きく、変化させています。企業の経理や顧客管理、さらには契約管理など、多くのビジネスプロセスが、クラウドや各種オンラインサービス上で行われるようになりました。個人の資産管理も、ネットバンキングや電子証券、暗号資産など、さまざまなデジタルツールを介して行うのが一般的です。
しかし、この利便性の裏には、新たなリスクも潜んでいます。特に、経営者が突然亡くなった場合、デジタル上の重要な資産やアカウント情報が共有されていなければ、相続人や後継者が、適切に事業を引き継ぐことが困難になります。事業運営に不可欠なクラウドシステムへログインできず、業務や取引が滞るかもしれません。
経営者個人のデジタル資産についても、適切に管理・把握されていなければ、相続手続きが複雑化する恐れがあります。結果として、資産の一部が、相続漏れになるリスクもあるでしょう。経営者としては、デジタル資産の全体像を把握しなければなりません。事業の継続性を確保して、家族や従業員の安心につなげる必要があります。
デジタル資産の具体例

経営者が残すデジタル資産は多岐にわたり、その重要性は年々高まっています。仕事や生活のあらゆる場面がデジタル化されました。パソコンやスマートフォンに残されたデータや、インターネット上の各種アカウントが、相続や事業継承の場面で大きな意味を持つようになったのです。

事業関連のデジタル資産
- クラウドサービスやグループウェアのアカウント
- 法人口座のオンラインバンキング情報
- 自社のWebサイトやSNSアカウントの管理権限
- 顧客リストや取引先との契約データ
これらはすべて、会社の運営や信頼関係の維持に直結するものです。適切に引き継がれなければ、事業停止や取引先とのトラブルに発展するリスクがあります。特に、金融関連のオンライン口座や、公式サイトやSNSの管理権限を誰も操作できない状態になれば、大きな混乱を招きかねません。
個人のデジタル資産
- GmailなどのメールアカウントやSNS
- 暗号資産やネット証券口座
- クラウドに保管された写真や文書
これらは、一見私的なものであっても、事業関連の連絡がメールやチャットに残されていたり、投資資産が相続財産として計上される必要があったりします。家族や共同経営者にとっては、大きな意味を持ちます。また、サブスクのように金額が小さな契約であっても、解約ができずに課金が続く恐れがあるでしょう。
| 事業と個人の区分 | 具体例 | 意義・リスク |
| 事業関連のデジタル資産 | – クラウドサービスやグループウェアのアカウント – 法人口座のオンラインバンキング情報 – 自社のWebサイトやSNSアカウントの管理権限 – 顧客リストや取引先との契約データ | ・会社運営や信頼関係の維持に直結 ・引き継ぎが行われないと事業停止や取引トラブルの可能性 ・金融口座や公式サイト管理が不在化すると大混乱のリスク |
| 個人のデジタル資産 | – GmailなどのメールアカウントやSNS – 暗号資産やネット証券口座 – SNSや動画コンテンツなどのサブスク契約 – クラウドに保管された写真や文書 | ・私的に見えても事業関連の連絡や重要データが含まれることがある ・暗号資産やネット証券は相続財産になる可能性 ・サブスク契約は解約できず課金が続く恐れ |
経営者特有のデジタル資産

経営者の場合、事業の存続や従業員の生活に直結するデジタル資産も少なくありません。自社株式や取引先との契約データ、会計情報、顧客リストなどが、オンライン上にのみ保存されているケースは多いです。これらに後継者や家族がアクセスできなければ、資金繰りの確認ができなくなります。アカウントやパスワードを代表者本人しか把握していない場合もあります。
また、経営者の資産は、事業資産と個人資産が複雑に絡み合っているため、家族や後継者にとって「これは会社のものか、それとも個人の財産なのか」を判断できません。このような不透明さは、事業承継や相続をめぐるトラブルを招く大きな要因となり得るのです。
法律・相続の観点からのリスク
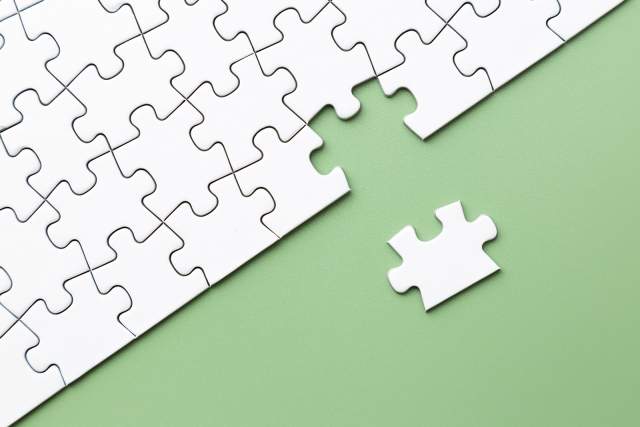
暗号資産やネット証券口座などは法律上『相続財産』に含まれますが、SNSアカウントなど利用規約上は相続できない場合もあります。経営者が亡くなった後に、家族や相続人が把握・管理できなければ、相続手続き全体が大きく滞るリスクがあります。具体的には、経営者本人が、契約していたサブスクリプションサービスやクラウドサービスは、死亡後も自動的に更新され続けます。不必要な費用が家族に対して、発生し続けるケースが少なくありません。このような無駄な支出は、事業承継後の資金繰りにも悪影響を及ぼすでしょう。

遺産分割協議において、デジタル資産が見えづらいまま進むと、家族間の話し合いが難航して、トラブルの火種となることもあります。経営者の場合、自社株や事業に関連するクラウドサービスのアカウント情報、さらには、個人のネット資産が絡み合うことで、資産の範囲や評価が曖昧になりやすいです。これによって、相続トラブルが長引くことが懸念されます。
さらに、使用されずに放置されたアカウントが、パスワード管理不備や権限不明のまま、情報漏洩や不正アクセスのリスクを抱える点も重大です。企業機密や顧客情報の流出、詐欺被害など、二次被害が発生する恐れもあります。放置されたアカウントが原因で、会社の信用問題に発展するかもしれません。
このように、事業資産と個人資産が混在するケースが多い経営者のデジタル資産相続は、法律上の整理や相続手続きが、非常に複雑になります。相続の対策を怠ると、家族や後継者の負担が増大するだけでなく、会社の存続や事業の信頼性にも重大な影響を及ぼす可能性があるでしょう。
| 項目 | 内容 | 経営者の場合の特徴・注意点 |
| デジタル資産の法的位置づけ | デジタル資産も相続財産に含まれる | 事業資産と個人資産が複雑に絡み合う |
| 相続手続きの遅延リスク | 家族・相続人が把握・管理できないと相続手続きが滞る | 相続範囲の特定や評価が難航しやすい |
| サブスク・クラウド契約の自動更新 | 死亡後も契約が自動更新され、不要な費用が発生 | 遺産の資金繰りに悪影響を及ぼす可能性 |
| 遺産分割協議の難航 | デジタル資産の見えづらさが家族間トラブルの火種に | 自社株や関連アカウントの影響で紛争長期化の恐れ |
| 放置アカウントのリスク | パスワード管理不備で情報漏洩・不正アクセスの危険 | 企業機密・顧客情報流出、詐欺被害の二次リスク |
| 法律上の整理の複雑さ | 事業資産と個人資産が混在し、整理と手続きが複雑に | 専門家の早期関与・計画的対応が必須 |
| 放置による影響 | 家族・後継者の負担増大、会社の存続・信用問題 | 事業の信頼性・継続性に重大なダメージを与える可能性 |
デジタル資産整理に関する解決策と対応

経営者がデジタル資産問題に対処するためには、専門的かつ法的に安全な方法で、デジタル資産を整理する必要があります。デジタル資産整理の専門業者を活用することが、有効な解決策の一つです。また、事前に経営者自身が「デジタル資産リスト」を作成して、定期的に更新しておくことも大切です。
リストには、クラウドサービスやサブスクリプション契約、取引口座、暗号資産ウォレットなどの情報を記載しましょう。パスワード管理ツールを活用して、ログイン情報を整理・管理してください。そして、このリストやパスワード管理ツールのデータは、信頼できる家族や法律・税務の専門家に託すことで、万一の場合にも、デジタル資産の管理・相続が行われるように備えられます。
弁護士や行政書士などの専門家と連携して、相続税対策や事業承継計画のなかに、デジタル資産の取り扱いを組み込むことが必要です。経営者がこのような多角的な対策を講じることで、デジタル時代の事業承継リスクを、最小限に抑えられます。家族や事業の安定を確保できるのです。
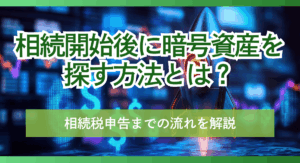
経営者の問題をサポートするデジタル資産業者とは?

デジタル資産業者とは、故人が残したパソコン・スマートフォン・クラウド・SNS・オンライン口座などの「デジタル資産」を、調査・整理・削除・引き継ぎする専門業者です。一般的には、個人のメールや写真データの整理を依頼するケースが多いですが、経営者にとってはさらに重要な存在となります。
経営者の場合、デジタル資産には次のような要素が含まれます。
- 会社のネットバンキングや証券口座の情報
- クラウド上に保管された会計データや顧客情報
- 取引先との契約データや業務メール
- 自社WebサイトやSNSのアカウント管理権限
これらが放置されると、事業継続が難しくなり、従業員や取引先にも大きな影響が及びかねません。デジタル資産業者に依頼することで、本人しか知らなかったアカウントやデータを調査できる場合があります。ただし法的制約や対応範囲に留意が必要です。
不要な契約は解約、必要な情報は、後継者に引き継ぐことができます。法務や相続に精通した専門家(弁護士・FPなど)と連携している業者も多く「個人資産と事業資産を切り分けながら整理できる」点は、経営者にとって大きな魅力です。デジタル資産業者は単なるデータ整理業者ではなく、経営者にとっては「事業承継を支えるインフラ的な存在」と言えます。
デジタル資産業者を利用するメリット
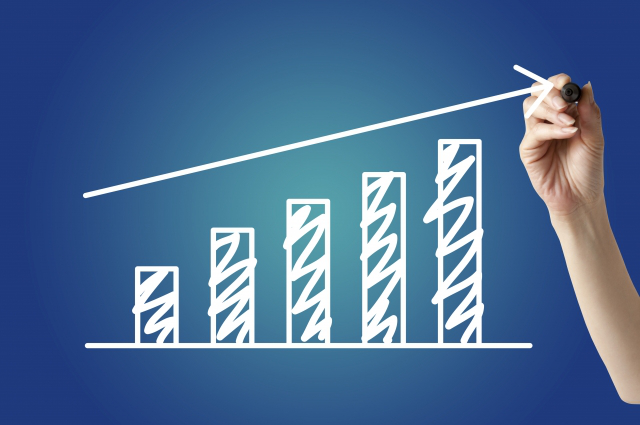
経営者が抱えるデジタル資産は、個人の写真やメールといった、思い出のデータだけではありません。会社の運営や存続に直結する、重要な情報を数多く含みます。たとえば、オンラインバンキングの取引情報や、証券口座の資産、クラウド上に保管された契約書や顧客データ、自社のホームページやSNSアカウントの管理権限などです。
これらに後継者や家族がアクセスできなくなれば、資金の出し入れができず、資金繰りが滞ったり、契約更新ができず取引先との信頼関係に影響したりと、会社にとって大きなリスクです。この「経営リスク」を未然に防ぐために有効なのが、デジタル資産業者の存在です。デジタル資産の専門業者は、パソコンやスマートフォンの解析からクラウドアカウントの調査、必要な情報の抽出・一覧化、不要な契約の解約までを、一貫してサポートしてくれます。
経営者自身が存命のうちから、整理を依頼しておけば、後継者への引き継ぎは大きく難航しません。万が一のときにも、事業を止めずに済む体制が整えられます。デジタル資産業者を活用することは、単に資産の整理を効率化するだけではありません。経営に直結するデジタル資産を守り、会社を不測の事態から守る「リスクマネジメント」の一環として、大きな意味を持つのです。
資産の見える化

経営者の資産は、現金や不動産のように目に見えるものだけではなく、オンライン証券口座や暗号資産、クラウド上に保存された契約書や取引データなど、デジタル領域にも広がっています。
これらは、本人以外には存在すら気づかれないことも多いです。相続の場面で「どこに、どのくらいの資産があるのか」が把握できないまま時間が経ってしまうケースが少なくありません。あらかじめ整理して一覧化しておくことで、資産の全体像が明確になり、事業承継や相続における大きな安心材料となります。
相続手続きの効率化

銀行や証券会社のオンライン口座などの資産は、ログイン情報がなければ、手続きが進められません。相続人が一から調査するのは非常に時間がかかり、場合によっては、資産を見落とすリスクもあります。
事前にログイン情報や利用状況を整理しておくことで、銀行・証券口座の解約や名義変更、クラウド資産の移管といった手続きをスムーズに進めることが可能です。これによって、家族の負担を大幅に軽減できます。
家族間トラブルの防止

経営者は家族に、資産の所在や性質を話しておくことが大切です。デジタル資産は、目に見えない分、管理がおろそかになりがちです。「誰がどのように受け継いでいくのか」が明確になっていれば、無用な心配を抱えずに、相続に向き合えるでしょう。
資産の整理と情報共有は、家族の不安を和らげるだけでなく、将来の安心を形にする準備でもあります。円満な承継を実現するために、少しずつでも取り組んでいくことが、大きな安心感につながるのです。
| 項目 | 内容 | 経営者の場合の特徴・注意点 |
| 資産の見える化 | 現金・不動産だけでなく、オンライン証券口座、暗号資産、クラウド上の契約書・取引データなどデジタル資産も多い。これらは本人以外に気づかれにくい。 | 事業用資産と個人資産が混在しやすく、全体像の把握が困難な場合が多い。 |
| 見える化の効果 | 整理・一覧化により資産の全体像が明確になり、事業承継や相続の安心材料となる。 | 事前整理は後継者や家族の負担軽減につながる。 |
| 相続手続きの効率化 | オンライン口座やクラウド資産はログイン情報が必須。相続人の調査には時間とリスクが伴う。 | 事前にログイン情報や利用状況を整理し共有すると、手続きがスムーズに進む。 |
| 手続きの結果 | 銀行・証券口座の解約・名義変更、クラウド資産の移管が効率化される。 | 家族の負担が大幅に軽減できる。 |
| 家族間トラブルの防止 | 事業用と個人用資産の区別や分割の誤解・疑念が紛争の原因となる。 | デジタル資産を正確に整理・共有することで情報ギャップを減らし、円滑な承継が可能。 |
| トラブル回避のポイント | 情報の透明化・共有 | 家族間の納得感や合意形成が促進される。 |
専門家に相談することで得られる安心

経営者として日々の事業運営に尽力するなか、資産や事業の将来をどのように守っていくかは、誰もが直面する大きな課題です。特に、自らが築き上げてきた会社やその資産が、家族や後継者にきちんと引き継がれるかについて、不安を感じる方も多いでしょう。事業と個人の資産が、複雑に入り組む経営者だからこそ、判断をするのは簡単なことではありません。感情のもつれや誤解から、家族との関係がぎくしゃくしてしまうリスクもあります。そのような時に頼りになるのが、FPや弁護士、デジタル資産整理の専門家といった、あなたの立場に寄り添いサポートできる専門家です。
専門家の存在は、単に手続きを助けるだけではありません。中立的な第三者として、冷静に資産を整理します。家族間の感情的なトラブルを防ぐ大きな力になります。法律や税務、情報管理の専門知識を持つ専門家が連携することで、複雑な手続きをスムーズに進められます。デジタル資産のアクセス不能や、情報漏洩のリスクを、最小限に抑えられるでしょう。
また、デジタル資産整理の専門業者は、パスワード解析やアカウントの調査整理、不要な契約の解約といった、実務面の負担を大きく軽減します。FPや弁護士などの専門家は、遺言書作成や事業承継計画の立案を通じて、経営者の想いを支援していきます。
後継者や家族とのコミュニケーションを円滑にするための橋渡し役でもあり、困難な話し合いも、専門家のサポートで進めやすくなるのです。「会社と家族を守りたい」という大きな願いが、未来につながります。一人で悩まず、信頼できる専門家と共に備えていくことをおすすめします。
まとめ

改めて、経営者にとって「事業承継」と「家族の生活保障」を両立させることは、重要な課題です。専門家の助言を得ながら、資産の正確な把握と、将来の計画を総合的に進めることで、相続に関わるトラブルを大幅に軽減できます。
早期に準備を始めることで、万が一の際にも、慌てずに事業の引き継ぎが行えます。会社と一緒に、家族の安心した生活を守れるのです。経営者は、この二つの側面から、バランスの取れた対策を着実に進めて、未来に向けた基盤づくりを心がけましょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼