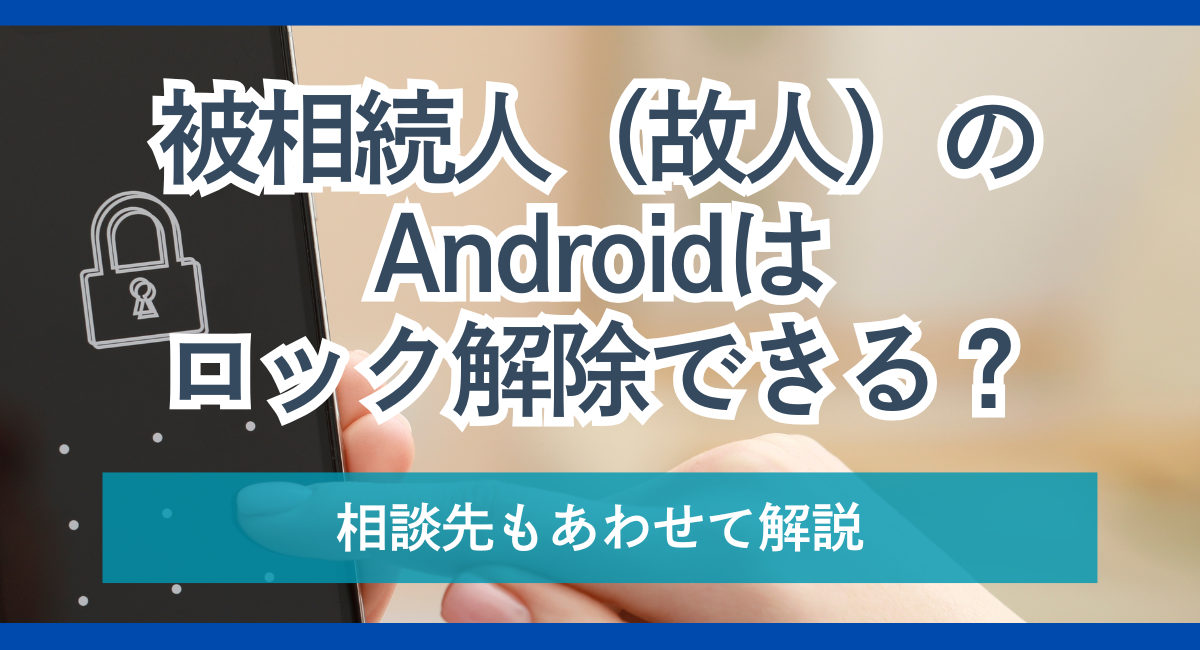被相続人(故人)がAndroidを所有していた場合、パスワードやPINコード等の解除ができない場合は専門家への相談で解除が可能です。Googleの機能にはデータが引き継げるサービスもあります。
当ホームページでは被相続人(故人)が生前に所有していたiPhoneについて、ロック解除に関する記事を後悔しています。では、根強い人気のAndroidを使用されていた場合はどのように対処すればよいでしょうか。
AndroidとはGoogleが開発したモバイル用のOS(オペレーションシステム)です。Googleが開発している「Google Pixel
だけではなく、Samsung(サムスン)やSony(ソニー)などスマホの機種を開発・販売しているメーカーも多く導入しています。
そこで、本記事ではAndroidのロック解除について、不正アクセス禁止法の概要にも触れながら安全な方法と注意点を詳しく解説します。
関連記事:被相続人(故人)のiPhoneはロック解除できる?安全な方法や注意点とは

被相続人(故人)のAndroidロック解除の基本的な方法
被相続人が生前にAndroidをご利用されていた場合、写真や連絡先などや金融資産に関する情報などが入っている可能性があり、適切にロックを解除する必要が生じます。
Androidの場合は冒頭に触れたように、さまざまなメーカーが販売しているため機種も多く、各スマホ本体によって独自の機能があります。また、普段相続人側がiPhoneを使っている場合、操作性に難しさを感じることも多い点に注意が必要です。
この章ではロック解除の基本的な流れを解説します。
PINやパスワードを解除する
被相続人(故人)が生前に使用していたAndroidには、PINコードやパスワードによるロックが設定されています。AndroidのPINは最低4桁から設定でき、最大16桁のため思い当たる番号(電話番号、誕生日や住所など)で解除できる可能性もあるでしょう。
もしも生前に被相続人が PINコードやパスワードを家族に伝えていたり、メモに残していたりする場合は、端末をスムーズに解除できます。
ご不明な場合はエンディングノートや、デバイス管理に関するメモが残されていないか確認してみることがおすすめです。
パターン認証による解除のケース
Android特有のロック解除方法として「パターン認証」があります。画面上に表示された点をなぞることで解除するものです。
この場合、もし被相続人が 比較的単純なパターンを使っていた場合、家族が軌跡を思い出して入力できるケースもあります。しかし、繰り返し誤ったパターンを入力すると、一定回数の失敗で端末がロックされてしまいます。また、複雑なパターンの解除は思い付きで突破することは難しいため、専門家への相談が望ましいでしょう。
指紋認証による解除はできない
Android端末も指紋認証を設定することが可能です。使用する本人の指紋が登録するため解除時は利便性が高いですが、使用者本人のご逝去後の解除は事実上不可能です。
指紋認証の場合、生体そのものを読み取るため、故人がすでにいない状況では使用できません。仮に指紋のコピーを作成して利用する、火葬前に解除できる可能性があると考える方もいますが、倫理的にも法的にも問題があり、正規の手続きを通じることが重要です。
倫理的に問題のある解除方法は遺産分割協議時などに家族間の火種になるおそれもあるため、「無理に解除する方法」を探すのではなく、正規のサポート窓口に依頼する、あるいは法的な手続きに基づいてアクセスすることが大切です。
ロック解除ができなかったらどうする?
「どうしてもPINやパスワードがわからない」「Androidの扱い方がわからず、相続手続きが進まない」という場合、初期化の検討も可能です。しかし、初期化をすると端末内のデータはすべて消去されます。さらにGoogleアカウント認証(FRP)が求められる場合があり、正規の手続きを経なければ利用できません。
写真や連絡先、メッセージ履歴など、大切な思い出や遺族にとって必要な情報も一緒に失われてしまうのです。したがって、初期化は「最後の手段」と位置づけるべきでしょう。
Androidのロック解除で困った時の対処法
デジタル資産が「相続財産」として重要視される現代において、Androidのロック解除やデータ取得は、遺産分割協議や相続税申告などの手続きを進める上で、避けては通れない課題です。
そこで、本章ではAndroidデバイスのロック解除に困った時の具体的な対処法と、故人のGoogleアカウントにおけるデータ引き継ぎの方法について、わかりやすく解説します。
各機種のメーカーに問い合わせる
Android機種を製造している各メーカーや店舗に問い合わせを行い、どのように対応すべきかアドバイスをもらうことが可能です。ただし、被相続人と相続人の関係性を証明するために、戸籍謄本類などの書類を提出するケースが多いでしょう。必要書類がなければ手続きできないため注意が必要です。
弁護士や司法書士など専門家へ相談する
遺産分割協議の一環としてロック解除が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談も検討できるでしょう。法的な権限に基づきよりスムーズな手続きをサポートしてくれます。
弁護士や司法書士など法律の専門家は、デジタル遺産を含めた相続財産の調査や遺産分割協議書の作成などのサポートも可能です。
弁護士は相続人の代理人として、法的な手続き全般をサポートします。司法書士は、相続登記や遺産整理業務を通じて紛争性がない相続手続きのサポートが可能です。
相続時に知っておきたい|Googleアカウントのデータ取得の方法とは
AndroidはGoogleアカウントと密接に連携しています。そこで、本章ではGoogleアカウント上にあるデータを相続人が取得する方法について解説します。
「故人のアカウントに関するリクエスト送信」の概要
Googleは被相続人のアカウントデータに関して、相続人からのリクエストに応じてくれる場合があります。この手続きは「故人のアカウントに関するリクエスト」と呼ばれ、Googleの公式サポートページから申請できます。
このリクエストは、Google側が相続時など適切な理由があると判断した場合に、Google DriveやGmail、Google フォトなどのデータが開示されるもので、被相続人のプライバシーを保護しつつ、合法的にデータにアクセスできるように設計されています。
Gmailの履歴から解約すべきサブスクや金融資産の取引先が発覚することもあるため、お早めに開示を求めることがおすすめです。
リクエストの手順
①Googleの「故人のアカウントに関するリクエスト」ページにアクセスします
②「故人のアカウントを閉鎖する」「故人のアカウントから資金を取得するためのリクエストを送信する」「故人のアカウントからデータを取得する」の3つの選択肢から目的に合ったものを選択します
③必要事項を入力し、求められる書類(死亡診断書など)を添付して送信します
Googleの審査を通過すれば、指定した方法でデータが提供されます。
参考URL Google 故人のアカウントに関するリクエストを送信する
生前からのGoogleアカウント終活とは
Androidを提供するGoogleでは、Googleアカウントのデジタル終活についてもサービスを用意しています。例として「アカウント無効化ツール
は一定期間アカウントへログインがなかった場合に、Googleアカウントを無効化したり、事前にご自身で設定した信頼できる連絡先へデータ開示したりできるサービスです。
ただし、開示されるデータではわからない金融資産等の情報も多いため、エンディングノートや遺言書と合わせて終活準備を進めておくことが望ましいでしょう。
(※2023年以降、Googleアカウントは2年間使われないと削除されることがあります)
参考URL Google アカウント無効化管理ツールについて
まとめ
Androidデバイスのロック解除やGoogleアカウントのデータ引き継ぎは、複雑で時間のかかる作業です。しかし、適切な手順を踏めば、大切な思い出や資産を守ることができます。
デバイス内に含まれた財産は機種やOS問わず相続財産に含まれ、遺産分割協議や相続税申告の対象となります。円滑に解除できずお困りの場合は、デジタル遺品整理に強い専門家へご相談いただくことがおすすめです。
Goodreiはデジタルフォレンジック調査にも精通しており、大切な思い出や資産の復元など、相続開始後に直面するさまざまなトラブルをご相談いただけます。Androidのお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼