現代社会では、私たちの生活やビジネスのあらゆる場面がデジタル化されています。スマートフォン、パソコン、クラウドサービス、IoT機器など、日々膨大なデータが生成・保存されて、やり取りされています。その一方で、サイバー攻撃や情報漏れ、不正アクセスといったリスクも増加の一途をたどっており、企業だけでなく個人にとっても、情報管理の重要性が高まっているのです。
このような背景のなか、デジタルフォレンジック(Digital Forensics)は、サイバーセキュリティや法務の分野で、欠かせない存在となっています。デジタルフォレンジックとは、電子機器やネットワーク上に残されたデジタル情報を収集・分析して、事件や不正の証拠を明らかにする技術、手法のことです。企業の内部調査や刑事事件の捜査、個人のトラブル解決など、その活用範囲は広がっています。
特に2025年以降は、データ量の爆発的な増加や、AI・クラウド環境の普及により、従来のフォレンジック手法だけでは、対応しきれない状況が予想されているのです。たとえば、クラウド上に保存されたデータの所在確認や、IoT機器からのログ取得、暗号化通信の解析など、新たな課題が次々と浮上しています。
そのため、企業や個人が、正確かつ迅速に対応できる体制を整えることが、以前にも増して重要になります。今回の記事では、2025年におけるデジタルフォレンジックの現状と最新技術、企業および個人での活用方法、法的課題や今後の展望まで、幅広く解説していきます。
デジタルフォレンジックの基本
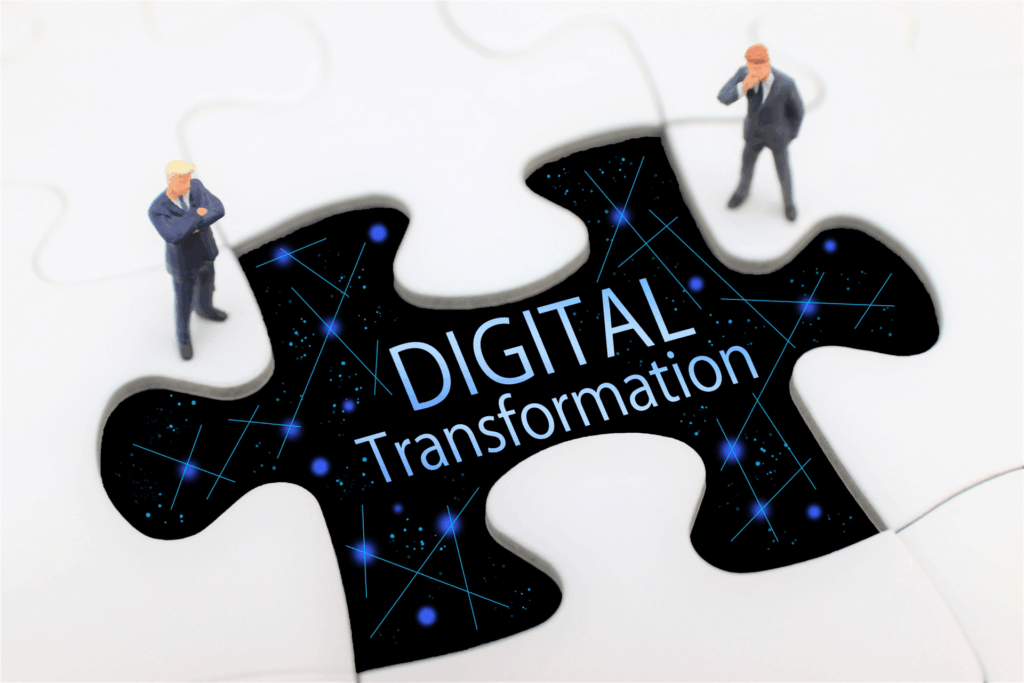
デジタルフォレンジックは、単なるIT技術の一部ではなく、法律・技術・倫理の3つの観点から成り立つ高度な専門分野です。コンピュータやスマートフォン、クラウドサービスなどに保存されたデータを解析して、削除された情報や操作履歴などを、科学的に復元・検証することで、事件や不正の証拠として活用します。
特に重要なのは、取得したデータが「裁判などの法的手続きで、証拠として認められること」です。そのためには、証拠の改ざんや漏えいを防ぐための厳格な手順を踏み、データの取得から分析、報告までの一連の流れを、記録・管理する必要があります。
また、フォレンジック調査には、専門的な知識と高い倫理意識が求められます。誤った方法でデータを扱えば、証拠能力を失うだけでなく、個人情報保護法などの法令違反となるおそれもあります。ここでは、そうしたデジタルフォレンジックの基本的な考え方や、実際にどのような手順で調査・分析が行われるのかを整理して、その全体像を明確にしていきましょう。
デジタルフォレンジックの目的
デジタルフォレンジックとは、パソコンやスマートフォン、ネットワーク、クラウド、IoT機器などに残されたデジタル情報を、科学的な方法で集めて調べて、事実関係を明らかにする作業のことです。目的は主に次の3つです。
| 活用の目的 | 内容 |
| 犯罪や不正の証拠確保 | 不正アクセス、情報漏れ、詐欺、内部不正などを調査して、裁判や捜査で利用できる証拠を収集する。 |
| インシデント対応の支援 | 企業のシステム障害やサイバー攻撃の原因を特定して、再発防止策やセキュリティ改善に役立てる。 |
| 法的手続きへの対応 | 裁判・行政手続で使用できるように、データを適切に保全・解析する。証拠として提出できる形に整える。 |
対象となるデータも年々広がっています。以前はパソコンやサーバーのデータが中心でした。しかし現在では、スマートフォン、タブレット、クラウドサービス、IoT機器までが対象です。
たとえば、メールやファイル、ブラウザ履歴、SNSのやり取り、通話記録、監視カメラの記録などの解析が可能です。デジタルフォレンジックの作業は、大きく「収集」「保全」「解析」「報告」の、4つの段階で行われます。
- 収集(Acquisition)では、ハードディスクのコピー作成やクラウドデータのバックアップなど、元のデータを壊さずに安全に取得します。
- 保全(Preservation)では、取得したデータが改ざんや消失しないように保管します。このとき、証拠の経路を記録して「チェーン・オブ・カストディ(証拠管理の連続性)」を守ることが法的に重要です。
- 解析(Analysis)では、削除済みファイルの復元やアクセス履歴の確認などを行い、事件やトラブルの経緯を明らかにします。
- 報告(Reporting)では、解析結果をわかりやすく整理して、裁判や行政で使用できる形で報告書を作ります。専門用語を避けて、客観的事実に基づく記述が求められているのです。
2025年のデジタルフォレンジック技術の動向
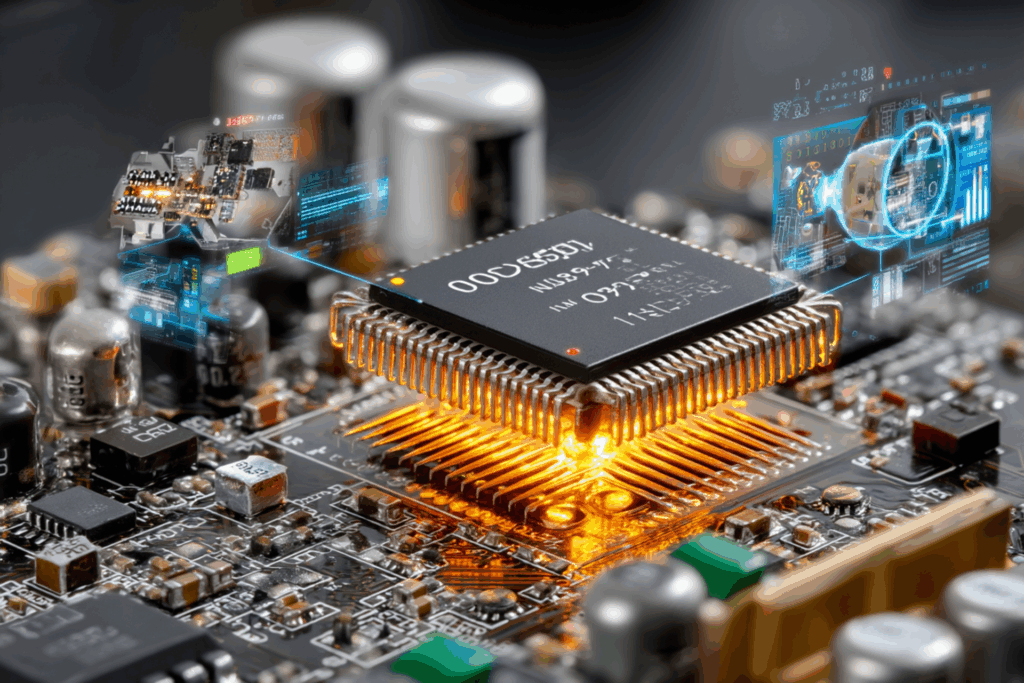
デジタルフォレンジックは、技術の進化とともに、手法や対象も常に変化しています。2025年現在では、特にAI(人工知能)、クラウドサービス、IoT(モノのインターネット)、暗号化技術といった複数の分野が、フォレンジック調査に大きな影響を与えています。AIを活用したデータ解析は、膨大なログや通信記録から、重要な情報の素早い抽出が可能です。
クラウドやIoTの普及により、従来のパソコンやサーバーだけではなく、スマートフォンやウェアラブル端末、クラウド上のデータも、解析対象に加わっています。また、暗号化技術の高度化により、情報の保護は強化される一方で、解析には、より専門的な知識と高度な手法が求められています。
サイバー犯罪の変化と対応
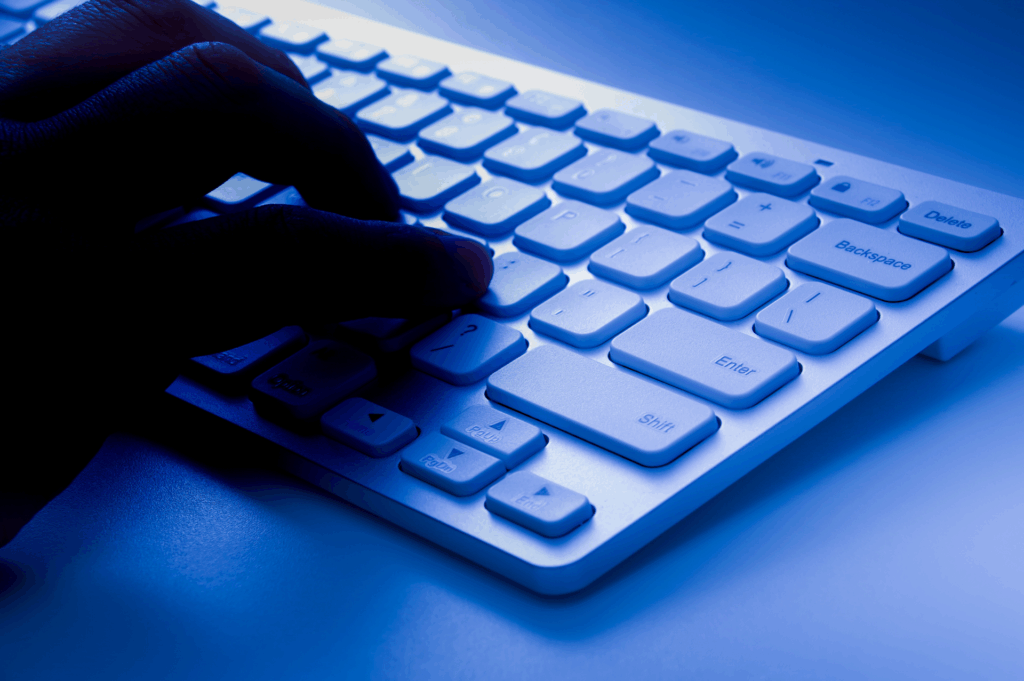
サイバー犯罪は年々、巧妙化・多様化しており、その手口や対象も急速に変化しています。単純なウイルスや不正アクセスだけでなく、フィッシング、ランサムウェア、クラウドサービスやIoT機器を狙った攻撃など、多岐にわたる手法が登場しているのです。
そのため、デジタルフォレンジックの重要性は、以前にも増して高まっています。企業や個人が被害を最小限に抑えるためには、まず、サイバー犯罪の最新動向や手口を正しく理解することが不可欠です。
そのうえで、事前の予防策や、インシデント発生時の迅速な対応策を整えて、証拠保全や被害状況の特定に役立てることが求められます。こうした取り組みは、被害の拡大を防ぐだけでなく、法的手続きや損害賠償、リスク管理の面でも、重要な役割を果たすでしょう。
サイバー犯罪の現状
2025年現在、サイバー犯罪には、次のような特徴があります。
- ランサムウェア攻撃の増加
企業や自治体を狙ったデータ暗号化型攻撃が急増しています。感染後、復号の対価として、巨額の身代金が要求されるサイバー攻撃です。
- 標的型攻撃(APT攻撃)
特定の企業や組織を狙った巧妙な攻撃が増えて、長期間にわたって、システム内に潜伏するケースが見られます。
- 内部不正・情報漏えい
従業員や関係者による機密情報の持ち出しや、不正アクセスも依然として大きなリスクです。
- 個人を狙った攻撃
フィッシングメールやSNSアカウント乗っ取りなど、個人情報を標的にした被害も増加しています。
| サイバー犯罪の種類 | 特徴・内容 |
| ランサムウェア攻撃 | 企業や自治体を狙ったデータ暗号化型攻撃が急増している。感染後、データ復号と引き換えに、巨額の身代金を要求される。 |
| 標的型攻撃(APT攻撃) | 特定の企業・組織を狙い、巧妙な手口で侵入する。長期間システム内に潜伏して、機密情報を盗み出すケースが増加している。 |
| 内部不正・情報漏えい | 従業員や取引先による不正アクセスや、情報の持ち出し。組織内部からのリスクが、依然として高い傾向がある。 |
| 個人を狙った攻撃 | フィッシングメール、SNSアカウント乗っ取りなどを通じて、個人情報を詐取する手口が増加している。 |
| 現在の傾向 | 従来型のITセキュリティ対策だけでは防ぎきれず、被害後の「事後対応(フォレンジック・再発防止)」の重要性が高まっている。 |
企業におけるデジタルフォレンジックの中心的な役割

企業でのデジタルフォレンジックは、サイバー犯罪に対する調査や、証拠確保の中心的な役割を担います。事後調査の迅速化においては、攻撃の痕跡を詳細に解析することで、侵入経路や被害の範囲を明確に特定します。
内部不正では、社内で発生した情報漏れの原因や、その行動履歴を明らかにして、問題の根本を把握することが可能です。また、法的証拠の確保という観点では、証拠保全の手順を適切に遵守することで、刑事訴訟や損害賠償請求などの法的手続きにおいて、有効な証拠として活用できます。
さらに、再発防止策の策定においては、攻撃手口や脆弱性を分析して、セキュリティ改善策を立案することで、将来的な被害の発生を未然に防ぐ役割も果たします。こうした一連のプロセスを通じて、デジタルフォレンジックは、サイバーセキュリティの維持と強化に欠かせない重要な手段となっているのです。
企業が直面するリスク
企業におけるサイバー犯罪の影響は非常に大きく、単なる金銭的損失にとどまらず、ブランドイメージの低下や、取引先との信頼関係の損失にも直結します。具体的には、経済的な面では、身代金の支払い、業務停止による損失、システム復旧にかかる費用などです。法的なリスクとしては、個人情報保護法の違反や、契約違反による賠償責任が発生する可能性があります。
信用面では、顧客や取引先からの信頼が低下することで、将来的な取引や事業継続に影響を及ぼすおそれがあります。こうしたリスクを軽減するためには、日常的なセキュリティ対策の徹底に加えて、万が一の事態に、迅速かつ適切に対応できるフォレンジック調査体制を整備しておくことが不可欠です。
| 観点 | 内容・影響 | 対応策 |
| 経済的影響 | ・ランサムウェアをはじめとした身代金の支払い ・システム停止や業務中断による営業損失 ・システム復旧やセキュリティ改善にかかる追加費用 | 被害を最小限に抑えるための迅速な調査、復旧体制の構築 |
| 法的リスク | ・個人情報保護法違反による行政処分や罰金 ・契約違反、損害賠償請求などの法的責任 | 法務、コンプライアンス部門と連携した法的対応準備 |
| 信用・ブランドへの影響 | ・顧客、取引先からの信頼失墜 ・企業ブランドや市場価値の低下 ・将来的な取引機会の喪失 | 信頼回復に向けた透明な情報開示と、迅速な対応 |
| 求められる対策 | ・日常的なセキュリティ強化、社員教育 ・フォレンジック調査体制の整備による、迅速かつ法的に有効な対応 | 事故発生時に即応できる外部専門家との連携体制を構築 |
個人でもできる初期対応
企業だけでなく、個人もサイバー犯罪に巻き込まれるリスクがあります。被害を最小限に抑えるためには、初期対応が非常に重要です。まず、端末の電源を切り、操作を控えることで、被害の拡大やデータの改ざんを防ぎます。
次に、パスワードを変更したり、ログイン履歴を確認したりして、不正アクセスの状況を把握します。また、信頼できる専門業者に相談することで、適切な対応や解析を受けることが可能です。
スクリーンショットやログなどを保管しておくことは、後に証拠として利用できるため重要です。個人レベルでも、こうした正しい初期対応が、その後の解析や法的手続きの有効性に、大きく影響するでしょう。
社内フォレンジックチームの構築

企業が自前でデジタルフォレンジック体制を整備する場合、複数の重要な要素が求められます。まず、専門人材の配置が不可欠です。ITセキュリティやネットワーク解析に精通したスタッフを中心に、法務やコンプライアンス部門と連携して、体制を構築します。
次に、標準化された手順書の整備が必要です。インシデント発生時の証拠収集手順や、ログ解析手順、報告書作成のフローを明文化することで、誰が対応しても、一定の品質で処理できるようにします。社員に対する教育や訓練も重要です。
定期的なセキュリティ研修や、模擬インシデント対応訓練を通じて、実践的なスキルを身につけることができます。社内にこうしたフォレンジックチームを持つことで、インシデント発生直後の初動対応が迅速化して、被害の拡大を防げるでしょう。
外部専門業者の活用
自社での対応が難しい場合や、高度な解析が求められるケースでは、デジタルフォレンジック専門業者の活用が有効です。デジタルフォレンジック専門業者は、AI解析や暗号化データの復号、クラウド環境のフォレンジックなど、専門的なツールと技術を駆使して高度な解析を行うことができます。
また、証拠保全の手順や報告書作成に精通しており、裁判における証拠提出も、スムーズに行える点がメリットです。さらに、外部業者を利用することで、社内人材の負担を軽減して、通常業務への影響を最小限に抑えられるでしょう。
緊急時の対応マニュアルとシミュレーション
企業は、フォレンジック調査だけでなく、サイバーインシデント全体を見据えた対応体制の構築が求められます。そのためには、まず発生時の初動手順や連絡体制、証拠保全の方法、関係者への報告フローを文書化した、対応マニュアルの作成が必要です。
さらに、模擬サイバー攻撃や情報漏れのシナリオを用いた定期的なシミュレーションを実施する必要があります。シミュレーションで明らかになった課題は、マニュアルに反映して、常に改善を重ねることで、実際の事件発生時にも混乱せず、スムーズかつ的確な対応が可能です。
情報セキュリティポリシーとの連携
デジタルフォレンジック体制は、企業の情報セキュリティポリシーと密接に連動しています。まず、データへのアクセス権限を厳格に管理することで、内部不正のリスクを軽減します。次に、システムやネットワークの操作ログを適切に保管することで、必要に応じて、フォレンジック調査に活用できる体制を整えます。
また、セキュリティポリシーが、確実に遵守されているのかを定期的に監査して、必要に応じて、改善策を導入することも重要です。こうした取り組みにより、フォレンジックは単独の技術にとどまらず、組織全体のリスクマネジメントと連携することで、より高い効果を発揮できるのです。
個人向けデジタルフォレンジックについて

デジタルフォレンジックは企業だけのものではなく、個人レベルでも重要性が高まっています。スマートフォンやパソコン、クラウドサービスの普及により、個人情報の流出や端末の紛失、家族間でのトラブルなどのリスクが増えています。個人が被害に遭った際、迅速かつ正確に対応できる知識と方法を知っておくことが重要です。
個人で直面するリスク
個人がデジタルフォレンジックの対象となるケースは多岐にわたります。
- スマホやPCの紛失・盗難
端末内に保存された個人情報、写真、パスワード情報などが不正利用される可能性があります。
- クラウドサービスの不正アクセス
主に、メールアカウントやSNS、オンラインバンキングなど、不正ログインによる個人情報漏れなどが挙げられます。
- フィッシングや詐欺被害
メールやメッセージを通じた情報取得・金銭詐取のリスクです。
- デジタル遺品の管理
家族が亡くなった際に、故人のデジタル遺品(クラウドアカウントや暗号資産)へのアクセス方法や整理方法が課題になります。
こうしたリスクに備えるため、個人でも初期対応や証拠保全の基本を知っておくことが重要です。
| ケース | 内容 |
| スマホやPCの紛失・盗難 | 端末内の個人情報・写真・パスワードなどが、不正に利用されるおそれがある。 |
| クラウドサービスの不正アクセス | メール、SNS、オンラインバンキングなどへの不正ログインにより、個人情報が漏えいする危険がある。 |
| フィッシングや詐欺被害 | 偽メールやメッセージを通じて、情報を抜き取られたり、金銭を詐取されたりするリスクがある。 |
| デジタル遺品の管理 | 故人のクラウドアカウントや、暗号資産などのアクセス・整理方法が課題になるケース。 |
| 対策の重要性 | 個人でも初期対応や、証拠保全の基礎知識を身につけておくことが重要。 |
個人でできる初期対応
トラブルが発生した場合、迅速な対応が被害の拡大を防ぐカギとなります。まず、端末の操作は控えて、紛失や不正アクセスが疑われる場合は、電源を切るかネットワーク接続を遮断して、データの改ざんを防ぎます。次に、メールやSNS、金融サービスなどのパスワードを速やかに変更することで、不正利用のリスクを低減できます。
また、アクセス履歴やスクリーンショット、メッセージ履歴などのログや証拠を保存しておくことで、後の解析や法的手続きに役立てることが可能です。さらに、自力での対応が難しい場合には、デジタルフォレンジックの専門業者に相談することで、安全かつ確実な調査と対応が行えます。
デジタル遺品整理との関係
個人向けフォレンジックでは、デジタル遺品整理が重要になります。故人が残したスマートフォンやパソコン、クラウドアカウントには、多くの個人情報や資産情報が含まれており、これらを法的かつ倫理的に整理することが求められます。
まず、クラウドサービスやSNS、電子マネー、暗号資産などのデジタル遺品に、アクセスするための手順を確認して、適切な権限を把握することが必要です。そのうえで、必要なデータは安全に保全して、不要な個人情報は適切に削除することで、情報漏れのリスクを防ぎます。
証拠保全とプライバシー保護のバランス
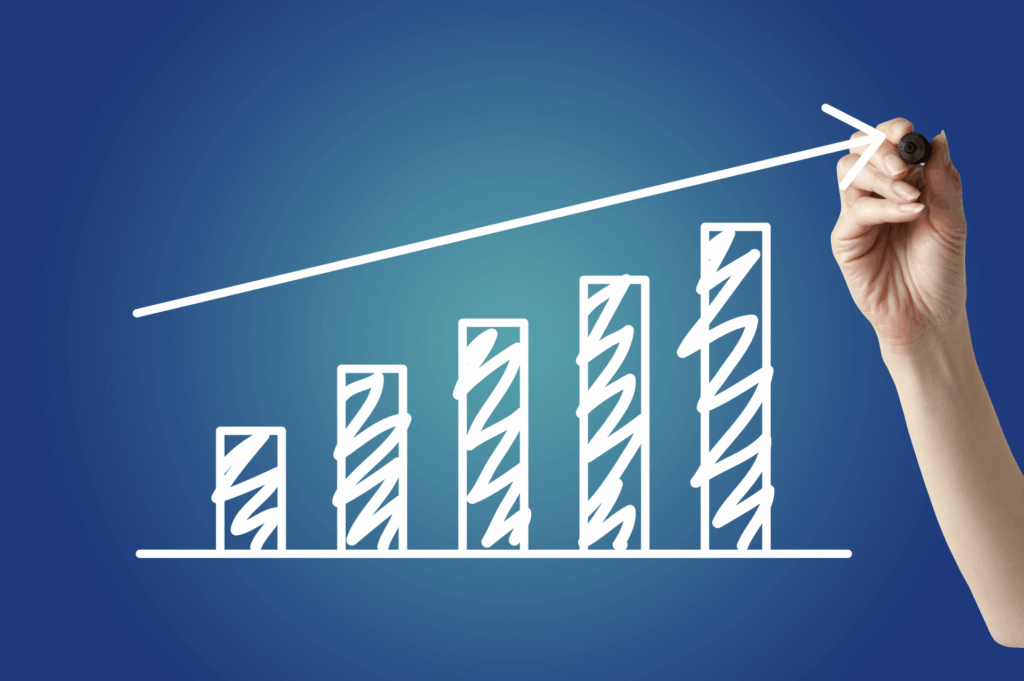
デジタルフォレンジックの調査では、個人情報や機密情報を扱う場面が多く、法的および倫理的配慮が欠かせません。証拠としての要件を満たすためには、収集したデータが改ざんされていないことを、法的に立証できる必要があります。裁判で証拠として採用されるためには、データの収集手順や保全方法を厳密に管理して、その過程を明確に示すことが求められます。
また、日本国内では、個人情報保護法の規定に従い、データの収集・保管・利用の範囲を明確に定めなければなりません。対象外の情報を不必要に取得したり、第三者へ無断で提供したりすると、法的リスクを伴うおそれがあります。そのため、調査過程では、常に個人の権利保護と、法令遵守の観点を意識する必要があるのです。
さらに、企業が自社内でフォレンジック調査を実施する場合には、社内規程や従業員の同意書との整合性を保つことも大切です。内部調査であっても、プライバシー侵害や手続き上の不備があれば、トラブルに発展する可能性があります。あらかじめルールを整備して、適切な運用を行うことが求められます。
国内法の規制
デジタルフォレンジックに関わる日本国内の法的枠組みは、複数の法律によって構成されています。まず、刑事訴訟法では、証拠の保全や押収に関する手続きが定められており、捜査機関がデジタル証拠を取得する際には、この規定に従う必要があるのです。
次に、民事訴訟法は、民事事件における証拠の提出や開示に関する規定を設けています。企業間の取引トラブルや契約紛争などの民事訴訟でも、メール記録やサーバーログなどのデジタル証拠が、重要な役割を果たすのです。
さらに、個人情報保護法は、個人データの取得・利用・保管・第三者提供に関するルールを詳細に定めています。この法律に違反した場合には、罰則が科せられることもあり、デジタルフォレンジック調査の実施にあたっては、特に慎重な対応が求められるでしょう。電子帳簿保存法や不正アクセス禁止法に関しても、デジタルフォレンジックに密接に関係しています。
電子帳簿保存法は、業務データの電子的な管理や保存方法を規定して、法令に適合した形でデータを扱うことを求めています。また、不正アクセス禁止法は、正当な権限を持たずに、システムへアクセスする行為を禁止しており、デジタルフォレンジック調査時にも、この規制を遵守しなければなりません。
| 法律名 | 内容 | デジタルフォレンジックとの関係 |
| 刑事訴訟法 | 警察や検察などが、捜査で証拠を押収・保全する際のルールを定めた法律。 | 犯罪や不正の調査で、パソコンやスマホなどのデジタル証拠を「正しい手順で」入手・保存するための基準となる。 |
| 民事訴訟法 | 企業や個人の間で争いが起こった場合、証拠を提出・開示する手続きを定めている。 | 取引トラブルや契約紛争の時に、メールやログなどの電子データを、裁判の証拠として活用できる。 |
| 個人情報保護法 | 住所、メールアドレスなどの個人情報を安全に扱うためのルールを定めている。 | 調査中に個人データを扱う際に、この法律を守ることが必須。不正に扱うと、罰則を受けることもある。 |
| 電子帳簿保存法 | 会社の帳簿や取引記録を電子データで、保存するための基準を定めている。 | 調査対象のデータが業務記録の場合、法に沿った正しい保存や検証が求められる。 |
| 不正アクセス禁止法 | 許可なしに他人のシステムへ侵入する行為を禁止する法律。 | フォレンジック調査を行う際も、無断アクセスをしてはいけない。必ず正当な権限が必要。 |
デジタルフォレンジック専門業者の活用で安心・確実な対応を

デジタルフォレンジックは高度な技術と法的知識が求められる分野であり、企業や個人が自力で完全に対応するのは、困難な場合があります。そのような場合は、信頼できるデジタルフォレンジック専門業者を活用することが有効です。
企業における専門業者のメリット
- 高度な解析能力:AI解析、暗号化データ復号、クラウド環境のフォレンジックなど、社内だけでは困難な調査を、迅速かつ正確に実施する。
- 法的対応支援:証拠保全や報告書作成に精通しており、裁判や行政手続きでもスムーズに利用できる。
- リソース効率化:社内人材の負担を軽減して、通常業務への影響を最小化できる。
個人における専門業者の活用
- 初期対応の支援:スマートフォンやパソコンの紛失、不正アクセスなど、迅速な対応が必要なケースでも、適切な手順でデータを保全する。
- デジタル遺品整理:故人のクラウドアカウントやSNS、暗号資産などの整理を安全かつ法的に実施して、家族の負担を軽減する。
- 法的リスクの回避:無断アクセスや誤った操作による法律違反を防ぎ、安心してデータ管理が可能になる。
専門業者を活用することで、技術的にも法的にも、安全・確実な対応が可能となり、企業・個人ともに、被害の最小化や再発防止につなげられます。特に2025年以降、データ量の増加やクラウド・IoTの普及により、フォレンジックの難易度が上がるなかで、専門業者の存在は、欠かせない選択肢です。
| 区分 | 主な活用場面 | 専門業者のメリット・効果 |
| 企業での活用 | サイバー攻撃、不正アクセス、情報漏えい、内部不正などの調査 | 高度な解析能力:AI解析や暗号化データの復号、クラウド環境のフォレンジック対応が可能。 法的対応支援:証拠保全・報告書作成に精通して、裁判・行政手続きにも適用が可能。 リソース効率化:社内人材の負担軽減と通常業務への影響を最小化。 |
| 個人での活用 | スマホ・PCの紛失、不正アクセス、詐欺被害、デジタル遺品整理など | 初期対応の支援:迅速かつ適切なデータ保全対応が可能。 デジタル遺品整理:故人のクラウドアカウントや暗号資産などを安全・法的に整理。 法的リスク回避:無断アクセスや誤操作による、違法行為を防止。 |
| 総合的効果 | 企業・個人共通 | 技術的・法的に安全で、確実な対応が可能。被害の最小化や再発防止につながる。データ量やクラウド環境が増える2025年以降、デジタルフォレンジック専門業者の重要性は、さらに高まっている。 |
まとめ

デジタルフォレンジックは、企業・個人を問わず、現代のデジタル社会において不可欠な技術であり、リスク管理や資産保護の重要な手段です。2025年以降は、AIやクラウド、IoT、暗号化技術の発展により、解析の効率や精度は向上する一方で、膨大なデータ量や多様なデータ形式、法的・倫理的課題への対応が求められます。
企業は、社内フォレンジックチームの整備や外部専門業者との連携、インシデント対応マニュアルの作成・定期的なシミュレーションを通じて、迅速かつ確実な初動対応体制を構築することが重要です。個人においても、端末紛失や不正アクセスへの初期対応、証拠保全、デジタル遺品整理など、日常生活のなかで、フォレンジックに関する知識を活用することで、被害の最小化や法的リスクの回避につなげられます。
今後も、技術・法規制・倫理の三つの視点をバランスよく理解して、知識や体制を継続的にアップデートすることが、安心・安全なデジタル社会を維持するために不可欠です。デジタルフォレンジックを単なる事件対応の手段としてではなく、リスクマネジメントと資産保護の一環として捉えることで、企業・個人は将来的な被害を最小化して、信頼性の高い社会の構築に貢献できるでしょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【仮想通貨復元スペシャリストのご案内】
・スクリーンショットやテキストデータで残しておいたシークレットリカバリーフレーズや秘密鍵が見つからない
・リップル(XRP)やエイダ(ADA)が取り出せなくなった
暗号資産の復元のお困りごとにつきまして、「仮想通貨復元スペシャリスト」サービスをご検討ください。
私たちの専門チームは、以下のような特徴を持つ信頼できるサービスを提供しています。
- 豊富な復元実績(BTC/ETH/XRP/ADA)
- 秘密保持契約を締結し、お客様の秘密情報及び個人情報の保護を徹底
- 一部成功報酬型で対応
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得
まずは無料相談から承ります。経験豊富な専門家が、あなたの大切な資産の復元をサポートいたします。


