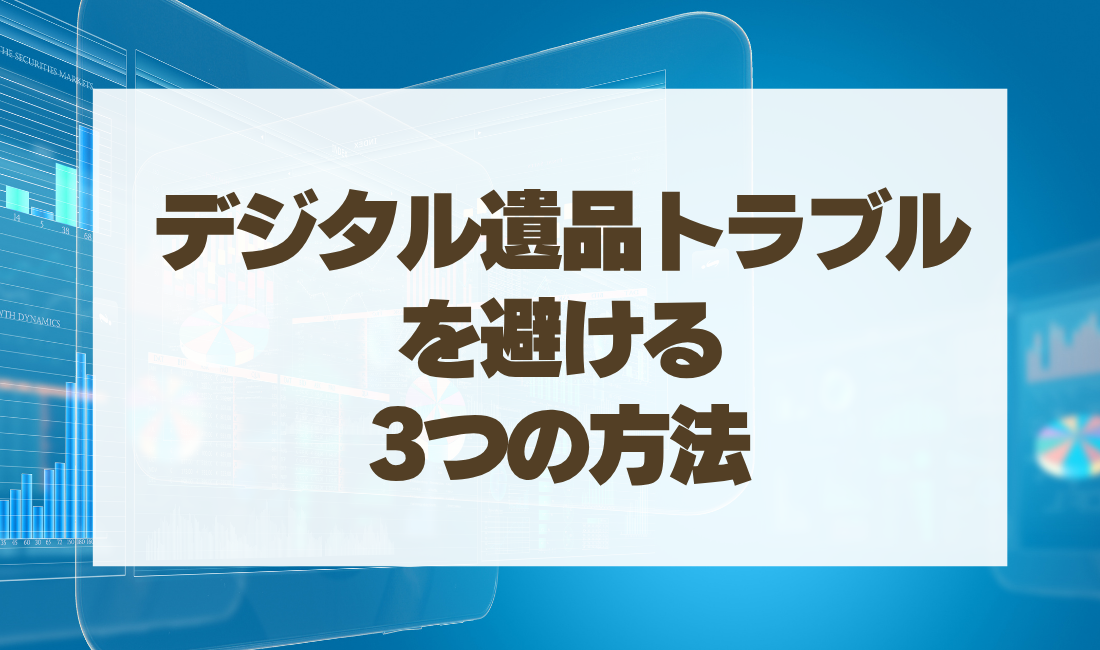デジタル遺品とは?
デジタルがより身近となった令和では、スマートフォンを始めとした端末の利用者が増えています。総務省の令和5年度の調査によると、スマートフォンの所持率は77.3%と年々増加しています。伴って、インターネットの利用状況も上昇傾向にあり、若い世代はもちろんのこと、60歳以上の利用率は86.8%、70歳以上は65.5%と非常に多くの方がネット環境に身を置いていることが分かっています。
さまざまなサービスをインターネットを通じて受けることができるようになった現代では、写真を撮ってスマートフォンに保存したり、webサイトや動画を閲覧するだけにとどまりません。銀行口座に接続したり、商品をインターネットを通じて購入することも可能になっていますし、むしろそういった生活が自然になりつつあります。
そこで考える必要が出てくるのが、「デジタル遺品」の整理についてです。デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウントなど、故人が残したデジタルデータを指します。形の残る商品ばかりではなく、目に見えないものも多数存在するため、近年注目されはじめ実際にトラブル事例も増えてきています。
デジタルデータに関して注意を払うポイントは次の2点です。
①故人が所有していたスマートフォンなどデジタル端末の内部に残されたデータ
②故人が生前にインターネットを通じて申し込んだ各種サービスにて外部に生じ得るデータ
これらがどのようなトラブルを引き起こす可能性があるのが、1つずつ見ていきましょう。
あなたが亡くなったらスマートフォンの中身はどうなる?

携帯電話やスマートフォンには画面ロックをかけることが出来ますから、中身をみられることは基本的にありません。また、ご本人でパスワードを設定していることがほとんどですから、ご本人以外の人間が開けることも実際は不可能です。そのため、データの閲覧がされたりどこかに漏れてしまうようなことは基本的にありません。
しかし、注意が必要となるのは、例えば重要な連絡先やデータが保存されているような場合です。スマートフォンのロックは、かなり厳重なものとなっています。仮に親族であったとしても、回線事業者や販売代理店は教えてくれません。さらに、何度かパスワードを間違えてしまうと機器の方で初期化となってしまうようなこともあり、うかつに試すこともできません。
もし重要なデータや、家族に残すべきことがスマートフォンに残されている場合には、ロックを解除できるパスワードを、自身が所有する回線番号とともに書面に残しておくとよいでしょう。また、その所在を親族の方にきちんと伝えておくことも大切です。とはいえ、生前にうかつに知られては意味がありませんので、そうならないような工夫が必要です。保管場所や保管方法に留意しましょう。
インターネットサービスはどうなる?
インターネットを通じて申し込むことが可能である定額料金での有料サービス、いわゆるサブスクを申し込んでいる場合もあるかもしれません。通常、定期購入契約というものは契約者が死亡したら解約となり、遺族が引き継ぐことはありません。ただし、スマートフォンの回線契約を解約しても、他で申し込んでいたサブスクの契約も同時に解除されるわけではありません。利用規約がサービスごとにことなるために詳細は確認する必要がありますが、解約し忘れたことで利用料の滞納分を残された遺族が支払わなければならなくなる可能性も考えられます。
そうならないためにも、生前で利用していたサブスクリプションサービスは書き出しておき、親族と共有しておくとよいでしょう。また、自身が何を申し込んでしまっているのかわからなくなってしまったというケースもあるかもしれません。iPhoneであれば、設定アプリから確認できます。設定⇒Apple ID⇒サブスクリプションを順番にタップします。そうすると現在契約しているサブスクリプションが一覧で表示されます。Androidであれば、Google Playストアアプリから確認できます。画面右上のアカウントアイコン⇒メニュー⇒お支払いと定期購入を順番にタップしましょう。 加入中のサブスクの確認がしたい場合は定期購入から、今まで購入したアプリやアプリ内課金の内訳を知りたい場合は予算と履歴から確認が可能です。
実際にどんなトラブルが起こっているの?

①連絡先が分からない
故人がスマートフォンに保存していた連絡先しか残されておらず、ロックが開けないために訃報を伝えることが出来なかったというトラブルがあるようです。
②サブスクリプションのサービスを取り消してしまう
意外と多いのは、クラウドサービスでデータ管理を行っているケースです。遺族がよくわからずにすべてのサブスクリプションサービスを解約してしまったがために、故人がこれまでに保存していた写真や著作物などもクラウド上から消えてしまいます。
③スマホを通じて金融資産取引をしている
故人が使っていたネットバンキングアカウントのパスワードを忘れてしまい、口座が凍結されてしまったというケースがあります。利用していた口座を見つけられずに、取引も確認できないと遺族としては不安が尽きないかと思います。
④遺族間のトラブル
スマートフォンについても相続財産の一部となる可能性があり、その場合は相続人全員で対応する必要があります。ロックを解除する場合や、何か解約手続きをする場合などは共同相続人に相談した上で進めるのがよいでしょう。
まとめ
デジタル遺品に関するトラブルはまだまだ件数は多くありませんが、これからさらに普及率が増えより身近な形でサービスを受けられるようになると、問題が深刻化する可能性もあります。
そのため、生前からデジタルに関する遺品整理を行っておくとよいでしょう。その際は以下3点を念頭に置いておくとよいでしょう。大半の方の利用端末はスマートフォンに移行してきています。ある意味トラブルとなる起点もスマートフォンにあるといえますので、そこをクリアにしておけばトラブルに巻き込まれる可能性も減らせるでしょう。
①スマートフォン・携帯電話のロック解除パスワードを紙に残しておく
②申し込んでいるサブスクリプションサービスについては共有しておく
③遺言を残してデジタルデータをどう処分してほしいか記しておく
3点目の遺言書については、生前から親族間で話し合いをしており様々なことを共有できていれば必要ないかもしれません。ただ、これを機に自身が保有している財産について今一度見直してみるのも良いかもしれません。遺言を書くのをためらう方も、残された遺族に負担をかけないためのものと思うと少しは気が楽になるのではないでしょうか。
さらに不安があるようであれば、専門家に相談しましょう。人によっては社外秘のデータを保存している場合や、家族に内緒の口座をネット上で保有しているというケースもあるかもしれません。その場合、事前に何をしておけるのか準備しておくことが必要です。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼