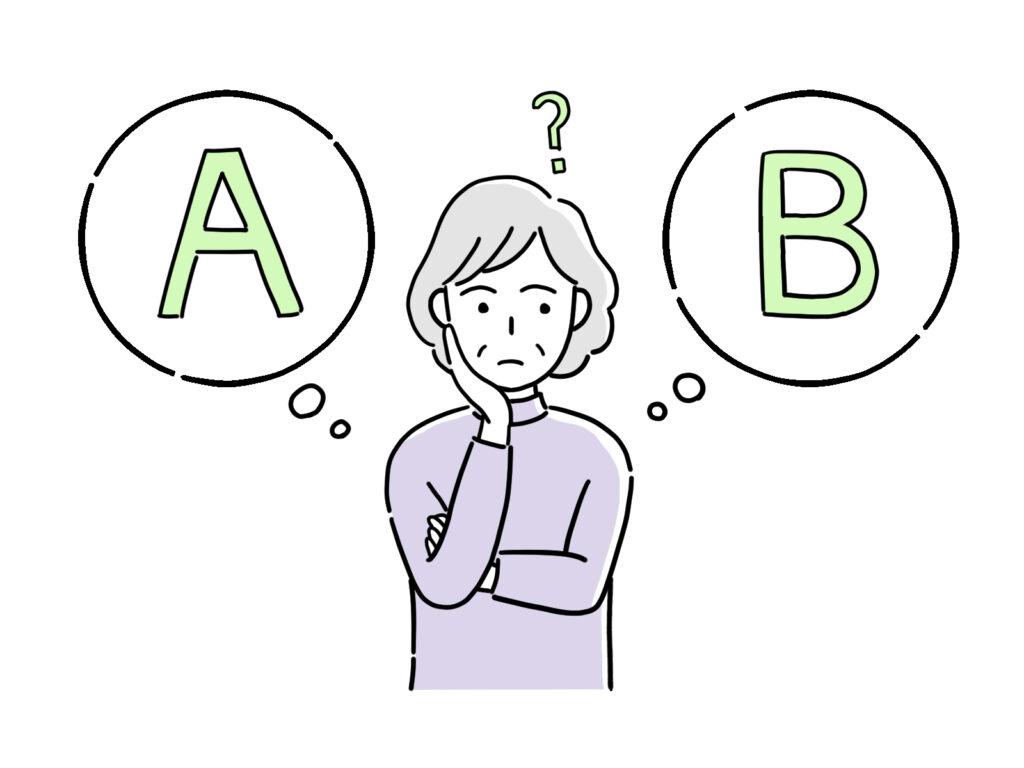
はじめに
これまでに説明してきた任意後見制度と家族信託はそれぞれを単独で利用することも、併用することもできます。ここまでのところで、それぞれの制度について簡単に比較してきましたが、超高齢社会に存在する様々なニーズに叶えるためには、いずれか択一ではなくいろいろと組み合わせた形での契約が必要になってくると考えられています。
たとえば、任意後見と家族信託の併用が必要なケースとして、受託者を直系血族の息子や娘ではなく血縁の遠い甥や姪あるいは知人としなければならない場合や、信託にまわしたい財産以外にも管理が必要となる財産を複数保有している場合が考えられます。一方で併用不要と考えられるケースとして、親族がいて今後のことを託すことができたり、信託契約または法定相続のみで財産を承継させられたりするような場合が考えられます。
併用の意義
前述の通り必要性が高く併用を求められるケースのほかにも併用を必要とするケースが考えらえれます。日本の家族信託の多くは自益信託といって、委託者と受益者が同じ人(父が息子に財産管理を委託して、父が利益を受ける)であるケースが多く、委託者が何らかの事情で信託事務を適切に行わない場合に、受益者が満足な履行を受けられなくなるということも考えられます。自身の判断能力がしっかりしている間に、自らも権利を行使できるよう任意後見制度も組み合わせて備えておくことも検討するとよいかもしれません。
さらには、家族信託では遺言に代わる機能を持たせることも可能ですから、設定契約によっては親族間で争いが起こってしまうことも考えられます。信託事務を適正に行えるよう、とりわけ受益権の行使において、他の相続人からの妨害を受けてしまうということがないように、法律専門職を始めとした第三者に間に入ってもらうことも考えておくと良いでしょう。客観的に状況を整理しながら適切に執行してもらえます。その場合は、第三者と任意後見契約を結ぶことで、様々な事態に備えることができます。

使い分けのポイント
一般論では、賃貸用の不動産や一定の金融資産をお持ちで積極的に投資を行うことに興味があるような場合や、障害のある子がいてその子のために長期的に財産を残したいとお考えである場合には、信託契約を結ぶことで効果をあげることができます。つまり、受益者を連続させる信託契約を活用することで遺言や後見制度では実現できない効果をうけることができます。
これに対して、運用するような財産は持っておらず承継についても遺言や法定相続で対応すれば十分であるが、身上監護はしっかり行いたいとお考えである場合には、任意後見契約が適していると言えるでしょう。また、後見制度は一度発効すると原則として本人が死亡するまで効果は続きますので、単発的な財産管理を希望する場合には適さないと言えるでしょう。
そのほかにも、財産の種類によっては信託譲渡できない場合もありますので、その場合は民事信託ではなく任意後見契約で対応した方がよいケースがあります。
どのように使い分けをしたらよいか、を判断する主なポイントは次の5つです。
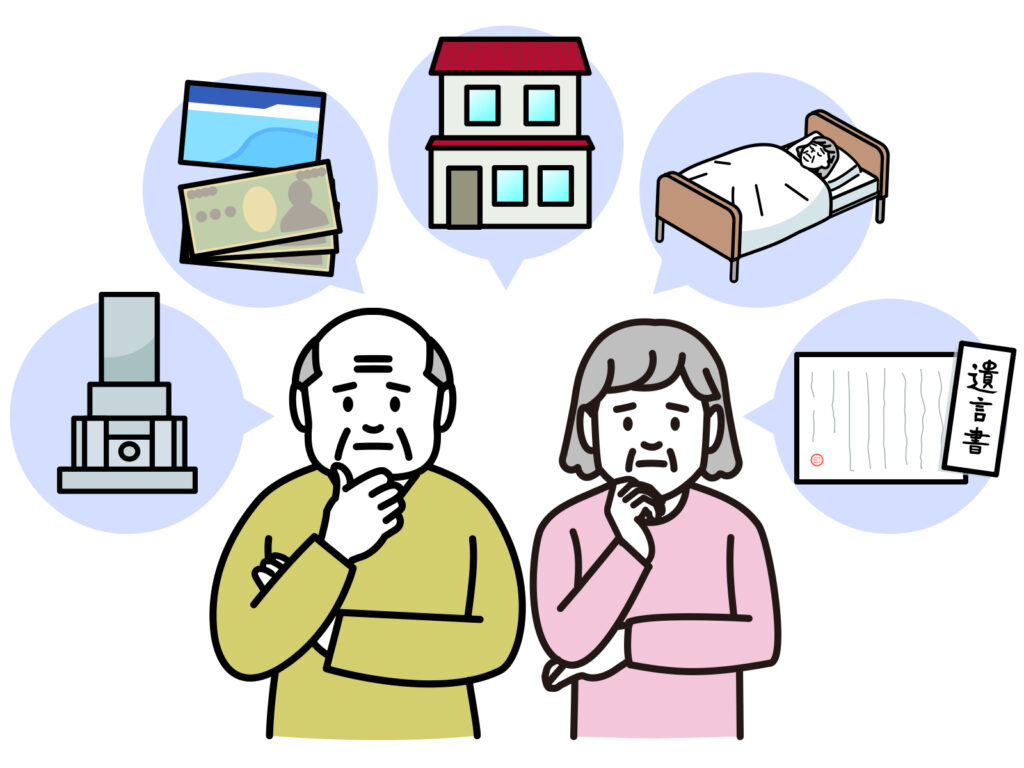
- 身上監護を必要とするかどうか
- 遠方に住んでいて、もし何かあったときにはすぐにかけつけることが難しい場合の対応方法
- 老人ホームの契約などは信託契約では対応できない
- 財産管理と財産承継のどちらに重きをおくか
- 後継ぎ遺贈をさせる必要があるか
- 息子に会社をつがせたあとは、孫に継がせるよう先に決めておきたい
- 遺言書や現状の相続法の範囲では後継ぎ遺贈は有効とならないために信託を活用する
- 財産の種類
- 財産運用の予定、一時的な利用を希望するか否か
- 現行の後見制度は一度始まると本人が亡くなるまで継続する点を考慮する
これらを総合的に判断して、どのパターンがいいか検討するのがよいでしょう。たとえば、昨今のニュースをみていて、高齢者の母が振込詐欺に遭わないか心配で任意後見制度を利用しようと考えたとします。ただ、母の判断能力はまだ十分な状況であったとすると、結局キャッシュカードでお金をおろすことはできますし、直接的に詐欺を防ぐことはできません。そういった場合には、主たる財産を信託契約にすることで詐欺によって財産を失われるというリスクは抑えられるでしょう。
反対に、母の財産を守るために信託を利用しようと考えたとします。しかし、保有財産が預貯金と自宅のみで、法定相続分に従って分配すれば問題ないようなケースでは、むしろ将来的に介護施設に入ることなどを想定すると信託を設定することでかえって不都合が生じることにもなりかねません。
併用する際の留意点
2つの制度を併用するわけですから、留意する点がいくつか存在します。まだ世間的にも利活用が進んでいない分野であり、実例が少ないのも実情ですがここでは2つだけ紹介いたします。
- 契約上の地位を兼ねることができるか
- 信託における受託者が任意後見人を兼ねられるかどうか、つまり息子に財産管理を委託したが、同時に任意後見契約も息子と交わすような場合です。このとき、双方を兼ねてはならないという法律の定めはありません。
- 受益者(父)は受託者(息子)が適切に業務を遂行するか監督することが出来ます。しかし、父の判断能力が低下してしまった場合には、その監督権も失われてしまいます。任意後見契約が発効することになりますので、父の後見人として息子が就任します。先ほどの監督権は息子に受け継がれることになりますから、受託者(息子)の業務を委託者(父)に代わり、後見人(息子)が管理監督するという状態になります。つまり、自分で自分を監督することとなり、仮に業務を怠っていたような場合ではその後も満足な業務遂行が期待できなくなってしまいます。可能であれば、任意後見人は別に設定した方がよいでしょう。
- 任意後見契約では代理権目録の作成が必要となります。信託と併用する場合には、どこまでの行為を目録に記載するかを十分に検討しておきましょう。将来的には、任意後見人に信託契約の監督を行えるようにしておくか否かなど範囲を明確にしておくことが大切です。
- 費用や報酬が重複する
- 任意後見人制度を発効するには、任意後見監督人の選任が必要となります。任意後見監督人には報酬の支払いが必要で、管理財産によってその額は決定します。相場としては、管理財産額が5000万円以下の場合には月2万円程度、それ以上の場合は月に3万円程度が目安です。一方で任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で自由に決めることができます。繰り返しになりますが、一度発効すると本人が亡くなるまで後見が続きますので、思わぬ負担となることもあり得ます。
- 家族信託契約では、受託者への報酬のほかに公正証書の作成が経費として考えられます。公正証書作成手数料は財産の額によって異なりますが、最大で10万円程度です。受託者への報酬も契約の中できめることができます。
まとめ
ここまで後見制度と家族信託に関してお伝えしてまいりましたが、どちらが一方的に優れているという制度設計ではありません。ご自身の状況に応じて適切な選択をすることが肝要です。まずは親族間で十分に話し合い、財産を残す側はどのように考えているのか、10年後や20年後の状況など様々な観点で考えておくことが必要でしょう。また、状況が複雑になっている場合には遠慮せず専門家に相談しましょう。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼

