デジタル時代とも言える現代では、オンライン資産の種類も増え、電子マネー等を含めると多くの方が何かしらのオンライン資産を保有するようになりました。しかし、一般的な銀行に預けられている預貯金のように、目に見えづらい特性上、相続時に気づかれないケースも少なくありません。今回は、オンライン資産の相続や管理のしかたについて解説します。
オンライン資産とは?
オンライン資産とは、オンライン上に所有している資産のことを指し、デジタル資産とも呼ばれます。具体的には、以下のようなものがオンライン資産にあたります。
- ネット銀行(オンラインバンキング)の口座にある預貯金
- オンライン取引中の株式や投資信託、FX
- ビットコイン等の仮想通貨
- 電子マネーやキャッシュレス決済のチャージ残高
さらに、オンライン上に保管している個人情報もオンライン資産にあたります。例えば、写真や動画、SNSアカウント、サービスやツール等の利用で入力している個人情報やパスワードなどです。
このように、オンライン資産は実際の手元に形として存在しないため全容が分かりにくいものではありますが、親が亡くなった時には相続資産に含まれるため注意が必要です。

オンライン資産も相続税が発生する

オンライン資産は目に見えにくいものではありますが、ネット銀行の口座の預貯金や保有している株式等は価値のある金融資産であり、一般的な銀行の預貯金やタンス預金、不動産などと同様に相続する場合には相続税が発生します。
しかし、オンライン資産の全容は当の本人が亡くなってしまってからでは把握することが難しいのが現状で、そもそも何も知らされていない場合にはどのようなオンライン資産をどのくらい保有しているのか見つけることは困難です。さらに、オンライン資産を確認するには本人が管理していたIDとパスワードを入手する必要もあり、きちんとした形で情報を残していなければ非常に手間のかかる手続きを要するでしょう。
オンライン資産を知らずに相続の手続きをした場合
もし、故人が保有していたオンライン資産の存在を知らずに相続の手続きをした場合、申告漏れによる相続税の追加納付が発生する恐れがあります。相続にあたり、遺産分割協議をした場合は、また協議をやり直す必要も出てきます。相続税を支払ったとしても相続する人にとってプラスになればあまり問題になることはないでしょうが、FX取引等で資産がマイナスになっていた場合は返済義務を相続人が負うこととなる可能性もあるため、注意が必要です。
オンライン資産の相続手続きのしかた
主なオンライン資産の相続手続きの流れについて確認しておきましょう。
ネット銀行の相続手続き

楽天銀行やPayPay銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行などのネット銀行は、対面店舗を持たずインターネット上で取引が完結するようになっているため、相続の手続きについても非対面で行っていくのが主流です。
- 該当の銀行の相続専用の部署(相続センター)などに電話する
- 相続手続きのための書類を送ってもらう
- 必要書類を整えて送付する
- 遺産分割の決定後、相続手続きが完了
基本的に、故人が設定していたWeb上のログインパスワードや暗証番号は、分からなくても問題なく手続きが進められるようになっています。必要書類は、相続預金払戻手続依頼書をはじめ、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など多岐にわたります。
遺産分割の場合は遺産分割協議書、遺言書による相続の場合は遺言書(公正証書遺言・検認済み遺言書・遺言書情報証明書)が必要になるでしょう。また、状況によっては他の書類も求められることがあります。
ネット証券の相続手続き

ネット証券も、実店舗がないため電話やインターネットの窓口から手続きを進めることとなります。まずは相続に関する相談窓口を探しましょう。
- 該当のネット証券の相続専用の部署などに連絡をする
- 相続手続きの書類を送ってもらう
- 残高証明書の申請、取得
- 遺産分割の決定後、相続人が証券口座を開設
- 株式の移管手続きをする
ネット銀行と同様に、遺産分割協議書や遺言書を求められるのが通例です。店舗のある証券会社での流れと手続き自体は同じですが、ネット銀行での手続きと同様に対面での相談ができない難しさは感じるかもしれません。
仮想通貨の相続手続き

仮想通貨の相続手続きは、相続人が取引所に連絡をして行うことが可能です。
- 該当の仮想通貨取引所に連絡をする
- 必要書類を準備して提出する
- 故人が保有していた仮想通貨の残高証明書を取り寄せる
- 遺産分割の決定後、解約申請手続きを行う
- 口座の解約後、仮想通貨の価値相当の金額が相続人に振り込まれる
仮想通貨の場合、需給によって価格が大きく変わり、常に変動しています。相続時のタイミングで仮想通貨の価値を評価する必要があります。しかし、市場が活発な仮想通貨以外の場合、その評価も難しい可能性があるため、マイナーな仮想通貨の相続時は税理士等の専門家に相談した方がスムーズかもしれません。
電子マネーの相続手続き
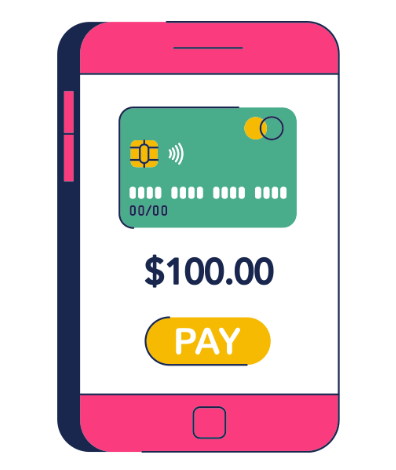
Suicaの残高など、電子マネーに残っているお金はさほど多額でないケースが多く、相続手続きの必要性を感じづらい方もいるでしょう。しかし、こうした電子マネーの残高も相続税の対象になる可能性があるため注意が必要です。なお、ここで言う電子マネーとは、チャージ型のキャッシュレス決済サービスのことを指し、即時決済型(デビット型)や後払い型(ポストペイ型)については除外しています。
また、電子マネーの種類によっては、利用規約で相続が禁止されているものもあります。該当のサービスが一身専属制をとっている場合、相続人がいてもその権利の譲渡や移転を認めていないというケースです。かつてはPayPayもこの一身専属制により相続ができませんでしたが、現在は規約の改定により相続が可能となっているため、まずはサポートセンター等に確認してみましょう。
オンライン資産の管理方法

オンライン資産は、故人が情報を残していない限り全容が分かりにくく、相続が決定した後にその存在に気づくことも珍しくありません。また、オンライン上でのやりとりが主となることから、スマホやパソコンへのログインが難しければ手続きも難航する恐れがあります。
自分が相続人になる場合のオンライン資産の管理

親など、自分が相続人になる可能性が高い相手が元気なうちに、できるだけオンライン資産の内容をリストアップして把握できるようにしておきましょう。もし、自分だけがオンライン資産の存在について知っていることが周囲とのトラブルにつながりかねない場合は、親に話をして財産目録をつけた遺言書を作成してもらったり、オンライン資産状況が把握できるリストを作ってもらったりするよう頼んでみてはいかがでしょうか。
自分が被相続人になる場合のオンライン資産の管理

自分がオンライン資産を保有しており、遺された人に財産を分ける場合も、基本的に先ほどご紹介した対策と同じ方法で管理するのがおすすめです。特に、財産目録をつけた遺言書があると、その後の手続きがスムーズになるでしょう。オンライン資産のリストアップをしておく場合は、口座情報やアカウントのID・パスワードについても記載しておくと便利です。また、PCやスマホのロック解除、各サービスのパスワード等も一覧にしておくと良いでしょう。ただし、これらの情報は非常に重要なものであり、保管には十分な注意と対策が必要です。
もう1つの方法として、終活の一貫として亡くなる前にオンライン資産を整理しておくことも、被相続人ができる解決策ではないでしょうか。あらかじめオンライン資産を売却し現金化しておくと、相続手続きがスムーズに漏れなく行いやすくなります。
オンライン資産は万が一に備えて管理を
オンライン資産を保有する人の数は年々増えています。まだ詳しく理解できていなかったり、万が一に備えていなかったりする人は多く、いざ大切な人が亡くなった時に気づかないというケースも珍しくありません。しかし、オンライン資産も相続税の対象となり得るため、相続人になる場合・被相続人になる場合のどちらも想定して備えをしておくことが大切です。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼

