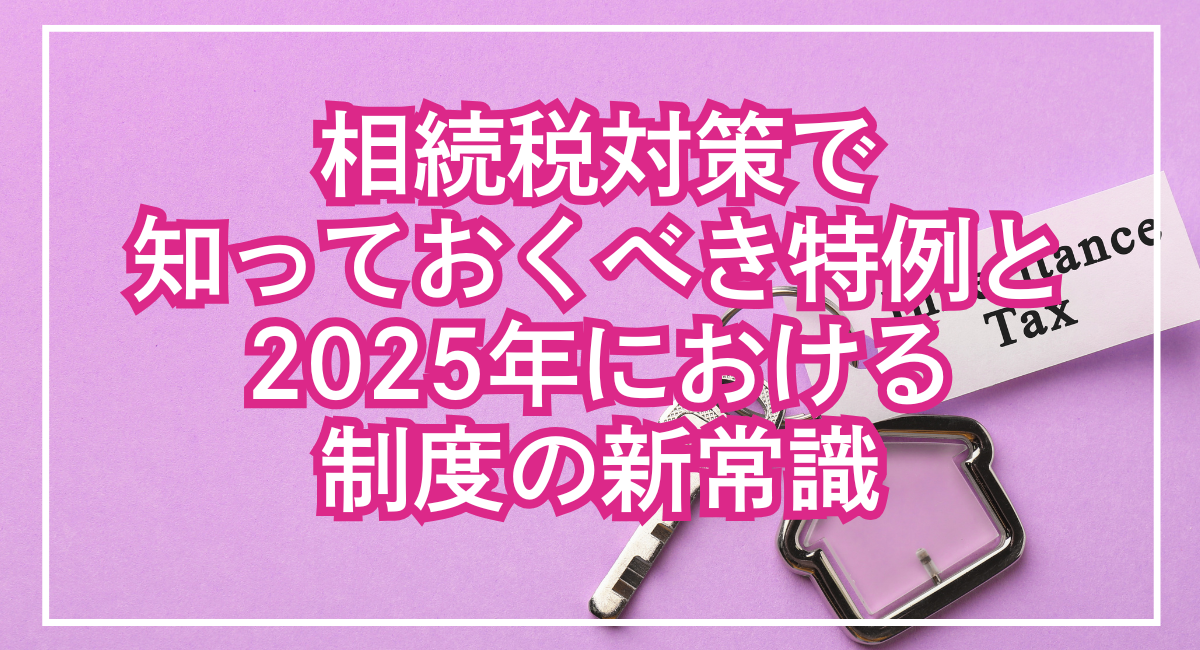相続税をめぐる環境は、2025年を迎え、大きな転換点を迎えています。団塊世代が後期高齢者となる「2025年問題」に直面しているためです。相続税の課税対象者が増加する中で、従来の常識だけでは、十分な対策が難しくなっています。
実際、基礎控除額の引き下げや小規模宅地等の特例など、知っておくべき特例や減税策は複雑化しつつあります。生命保険金の非課税枠拡大に関する議論も進んでおり、2024年改正を受け、2025年度の動向にも注目が集まっています。
※適用対象外となるケースもあるため、事前に確認が必要です。
今回の記事では、相続税の概要とこれからの節税ポイントを解説します。2025年に押さえておくべき新しい制度や、最新の法改正の動向とともにチェックしてください。
1.相続税とは?仕組みと目的について

相続税とは、家族や親族が亡くなった際に、その人の財産を受け継ぐときにかかる税金です。相続税の制度には、単なる税収確保だけではありません。社会全体で財産の偏りを是正し、経済的な公平を保つという目的があります。
また、生前に十分に課税されなかった財産についても、相続時に適正な税負担を求める役割を果たします。相続税の仕組みと背景を知ることは、将来の相続や資産管理を考える上で非常に重要です。
2.相続税対策に活用できる代表的な特例と各種控除

相続税の負担軽減のために、法律の「特例」や「各種控除」を上手に活用しましょう。例えば、土地や事業の承継など、特定の条件を満たすことで、相続税の課税額を大きく減らせます。代表的な特例とその活用ポイントを知ることで、無駄な税負担を避け、円滑な資産承継につながります。
2-1.生前贈与の活用
生前贈与は、相続税の節税対策として非常に有効です。生前贈与とは、被相続人が生きている間に、財産を子や孫などへ移転することを指します。これにより、将来の相続時に課税対象となる財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。
例えば、日本では「毎年110万円までなら贈与税がかからない」というルールがあります。つまり、毎年110万円ずつ家族にお金を渡せば、贈与税が掛からないのです。その分だけ自分の財産が減るので、相続時の税金も少なくなります。これを何年も続けることで、相続税の節税効果が大きくなります。
2-2.生命保険の非課税枠の活用

生命保険の非課税枠を活用することで、相続税の負担を大きく減らせます。亡くなった方が「契約者・被保険者」で、受取人が「法定相続人」の場合、「法定相続人の数×500万円」までの死亡保険金は、相続税がかかりません。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人のケースで解説します。この場合、1,500万円(500万円×3人)までの死亡保険金は非課税となります。非課税枠を超えた部分だけが相続税の対象です。
この非課税枠は、受取人が複数いる場合でも、受け取った保険金の割合に応じて、分けて計算されます。例えば、保険金の合計が2,000万円で相続人が2人の場合、先述の通り非課税枠は1,000万円です。2人が1,500万円と500万円で分けて受け取る時には、非課税枠も1,500万円と500万円の割合で分配されます。
※保険金の非課税枠は、相続人ごとに500万円まで適用され、それぞれの受取額に応じて控除されます
生命保険の非課税枠を活用するメリットは、相続税の節税対策だけではありません。現金でまとまった資金を遺族に残せることや、遺産分割のトラブル防止に役立つのです。
| 法定相続人の数 | 非課税枠(500万円×人数) | 死亡保険金が非課税となる上限 |
| 1人 | 500万円 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 | 2,000万円 |
2-3.配偶者控除の活用
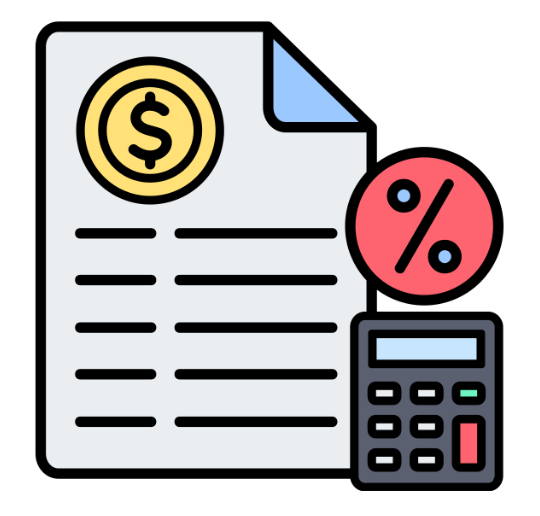
相続税には「配偶者控除」という特別なルールがあります。これは、亡くなった方の配偶者が遺産を受け取る時に適用されます。1億6,000万円まで、または、配偶者の法定相続分までなら、相続税が掛からないという制度です。どちらか多い方が配偶者控除として活用できます。
例えば、遺産が1億円なら、配偶者がすべて受け取っても相続税は0円です。遺産が3億円で、配偶者の取り分が1.5億円なら、その1.5億円までは相続税が掛かりません。
| 配偶者控除の内容 | 控除される上限額 | 適用条件 |
| 配偶者が相続する遺産は「1億6,000万円」または「法定相続分」まで非課税(どちらか多い方) | 1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで | ・法律上の配偶者であること ・遺産分割が確定していること ・相続税申告書の提出 |
2-4.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた宅地(自宅や事業用地など)を、相続や遺贈で取得した場合に適用できます。一定の要件を満たせば、その宅地の相続税評価額を最大80%減額できるのです。この特例を活用することで、土地に掛かる相続税の負担を大幅に軽減できます。
2-5.不動産の活用

不動産を活用することで、相続税を軽減できます。例えば、現金や預金の場合、そのままの金額が相続税の対象です。しかし、不動産の場合は「相続税評価額」というルールが活用できます。例えば、1億円の土地でも相続税の計算を行う際に、8,000万円前後になる場合があるのです。
その土地にアパートなどを建てて、人に貸し出した場合「貸家建付地」として、評価額が下がります。建物も「貸家」として安く評価されます。つまり、同じ1億円の現金でも、賃貸アパートを建てて貸すことで、相続税の計算上、6,000万円前後まで下がることがあるのです。
一方で、アパート経営には空室が出る可能性があります。不動産の活用は相続税対策で効果的ですが、リスクや手間も発生します。そのため、専門家に相談しながら、計画的に進めることが大切です。
2-6.養子縁組による法定相続人の増加

養子縁組をすると、相続税を計算するうえで「法定相続人」の人数が増えます。相続税には「基礎控除」という、税金が掛からない金額の枠があります。この基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で決まるのです。つまり、法定相続人が多いほど、税金が発生しない金額が増えるので、相続税が少なくなるのです。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は4,200万円ですが、養子縁組で3人になれば4,800万円に増えます。また、生命保険金や死亡退職金にも「500万円×法定相続人の人数」まで非課税となる枠があるのです。
しかし、養子縁組をする場合、相続税の計算でカウントできる養子の数には制限があります。実の子がいる場合は養子は1人まで、実の子がいない場合は2人までが上限です。
また、養子縁組には注意しなければならない点があります。それは、養子縁組をすると、他の家族の相続分が減ってしまう点です。親族間でもめる原因につながるため、事前の話し合いが欠かせません。
養子縁組で法定相続人を増やすと、相続税が安くなる場合があります。一方で、人数の上限や家族の関係に注意が必要です。実際に養子縁組を考える時には、専門家に相談しながら進めると安心でしょう。
| 項目 | 内容 |
| 基礎控除の計算式 | 3,000万円+600万円×法定相続人の人数 |
| 法定相続人に含める 養子数 | 実子がいる場合:養子1人まで 実子がいない場合:養子2人まで |
| 生命保険・退職金の 非課税枠 | 500万円×法定相続人の人数 |
| 養子縁組の効果 | 法定相続人が増えることで、基礎控除・非課税枠が増える 相続税負担が軽減される |
| 特別養子・連れ子養子 | 「実子」とみなされ、人数制限なし |
| 注意点 | 養子が増えると他の相続人の取り分が減るため、 トラブルの原因になりやすい |
| 2割加算 | 孫を養子にした場合など、 相続税が2割増しとなるケースあり |
2-7.相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、親や祖父母が、子や孫に生前贈与をする際に活用できる特例です。贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上という条件のもと、累計2,500万円までの贈与について贈与税が掛からないのです。
この制度の特徴は、贈与者が亡くなった時点で、贈与した財産を相続財産に加えて、相続税を計算する点でしょう。
例えば、不動産や株式などを早めに子や孫に移しておくことで、値上がり益に対する相続税が抑えられます。また、賃貸不動産など、収益を生む財産を早期に移転することで、以降の収益は受贈者のものになります。これにより、贈与者の財産増加を抑える効果があるのです。
一方で、相続時精算課税制度には注意点もあります。一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税(毎年110万円の贈与が非課税)に戻すことができません。
また、不動産を贈与した場合は、不動産取得税や登録免許税の負担が大きくなる場合があります。「小規模宅地等の評価減の特例」が使えないなどの、デメリットも存在します。
相続時精算課税制度は、少額贈与や将来値上がりが見込まれる財産の早期移転に有効な選択肢です。しかし、制度選択後の変更ができないことや、特例対象外となる財産もあります。利用を検討する際は、家族の状況や財産内容を事前に把握しておかなければなりません。
| 項目 | 内容 |
| 適用対象 | 贈与者:60歳以上の父母・祖父母 受贈者:18歳以上の子・孫 |
| 非課税枠 | 累計2,500万円まで贈与税がかからない |
| 贈与税率 | 2,500万円超過分は一律20% |
| 年間基礎控除 | 2024年以降、年110万円の基礎控除が新設(この分は相続財産に加算されない) |
| 相続時の取扱い | 贈与した財産は贈与時の価額で相続財産に加算し、相続税を計算 |
| 主なメリット | ・多額の生前贈与が可能 ・値上がり資産の早期移転で節税効果 ・収益物件の所得移転ができる |
| 主なデメリット | ・一度選択すると暦年課税(年110万円非課税)に戻れない ・小規模宅地等の特例が使えない ・不動産取得税や登録免許税の負担増 |
| その他の注意点 | 孫が法定相続人でない場合、相続税が2割加算されます 贈与財産の種類や家族状況によっては節税効果が限定的 |
3.いま知っておきたい相続税対策の新常識

少子高齢化が進む日本では、「相続」はもはや一部の資産家だけの話ではありません。誰にとっても身近な課題となりつつあります。「うちは資産がないから大丈夫」と考える方も多いです。しかし、現実に相続が発生すると、想像以上の税負担や家族間のトラブルも少なくありません。
万が一に備えて、最新の知識と現実に即した対策が求められるのです。相続税対策の新常識と2025年の最新動向をぜひ参考にしてください。
生前贈与の「持ち戻し」期間が7年に延長
2024年の税制改正により、生前贈与の「持ち戻し」期間が従来の3年から7年に延長されました。これまでは、被相続人が亡くなる前の3年以内に相続人へ贈与した財産については、相続財産に加算されたのです。つまり、相続税の課税対象でした。しかし、今後はこの期間が段階的に延長されて、最終的には、7年以内に行われた贈与が持ち戻しの対象になります。
具体的には、2024年1月1日以降の贈与から新しいルールが適用されています。2031年1月1日以降に発生する相続については、亡くなる前の7年以内の贈与が全て相続財産に加算されます。
この改正の背景には、富裕層の相続税回避を防ぐことにあります。また、高齢者から若い世代への資産移転を促進する目的もあるのです。将来的に、相続直前の「駆け込み贈与」による節税効果は小さくなります。今後は長期的な視点で、贈与や相続税対策を考えなければなりません。
相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設
2024年1月1日から、相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。これまでは、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与を受けた金額にかかわらず、毎年贈与税の申告が必要でした。改正後は、1年間に受け取る贈与額が「110万円以下」であれば、贈与税がかからず、申告も不要です。
この基礎控除は、従来からある特別控除2,500万円とは別枠で設けられています。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税も相続税も掛かりません。将来贈与者が亡くなった際にも、相続財産に加算されないのです。
この改正によって、より柔軟に生前贈与を活用できるようになりました。例えば、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告も不要です。相続税対策としても有効になります。
110万円を超える贈与分については、従来通り2,500万円の特別控除の範囲内であれば、贈与税は発生しません。特別控除を超えた部分には、20%の贈与税が課税されます。複数の贈与者から同じ年に贈与を受けた場合は、110万円の基礎控除を贈与額に応じて、按分して適用します。
このように、2024年からの改正によって、相続時精算課税制度はより使いやすくなりました。少額贈与による資産移転や、相続税対策が行いやすくなったのです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2024年1月~) |
| 年間基礎控除 | なし | 110万円まで非課税・申告不要 |
| 特別控除 | 2,500万円(累計) | 2,500万円(累計) |
| 控除の扱い | すべて相続財産に加算 | 年110万円分は相続財産に加算不要 |
| 贈与税の申告 | 金額にかかわらず毎年必要 | 110万円以下なら申告不要 |
| 非課税枠の合計 | 2,500万円(特別控除のみ) | 最大2,610万円(特別控除2,500万円+基礎控除110万円×年数) |
| 複数贈与者からの贈与 | 合算して計算 | 複数の贈与者から贈与を受ける場合、合計額から基礎控除を適用し、按分します |
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置が延長
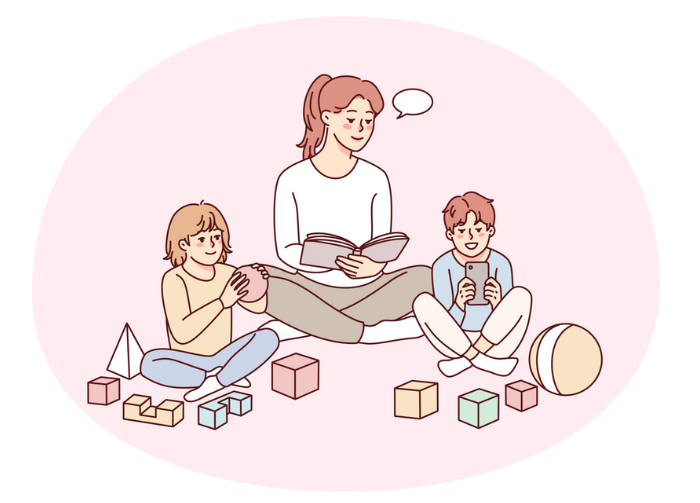
結婚・子育て資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置は、2025年4月1日以降も、引き続き適用されています。適用期限が2年間延長されて、2027年3月31日まで利用できるようになりました。
この制度は、父母や祖父母などが、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や出産、育児に必要な資金を一括で贈与した場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となるものです。制度を活用するには、金融機関での専用口座開設や、書類の提出が必要になります。
非課税枠を利用した贈与に関しては、贈与者が亡くなった際に残額がある場合、その残額が相続税の課税対象です。また、受贈者が50歳に達した場合にも、贈与税課税になります。制度を活用する際には、このような細かい注意点を把握しておかなければなりません。
この非課税措置は、暦年贈与や相続時精算課税制度の基礎控除・特別控除、住宅取得資金贈与の非課税制度との併用が可能です。相続税対策や若い世代への資産移転を計画的に進める際には、非常に活用しやすい制度でしょう。
| 項目 | 内容 |
| 適用期間 | 2027年3月31日まで延長(2025年4月1日以降の贈与も対象) |
| 非課税限度額 | 受贈者1人あたり最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで) |
| 贈与者 | 父母・祖父母など直系尊属 |
| 受贈者 | 18歳以上50歳未満、前年所得1,000万円以下 |
| 必要手続き | 金融機関で専用口座開設・申告書提出 |
| 非課税対象費用 | 結婚(挙式・引越し等)、子育て(不妊治療・保育料等) |
| 注意点 | ・贈与者死亡時や受贈者が、50歳到達時の残額は相続税 ・贈与税課税対象 |
| 併用可能制度 | 暦年贈与・相続時精算課税・住宅取得資金贈与・教育資金贈与と併用可 |
4.相続税対策で後悔しないために

相続税をめぐる制度や社会環境は、ここ数年で大きく変化しています。従来の常識や対策だけでは十分とはいえません。最新のルールや新たな考え方を押さえておくことが、これからの円滑な資産承継や、税負担の軽減に大切でしょう。相続税対策の「新常識」を理解し、賢く備えてください。それが将来の安心と、家族のための最善の選択につながります。