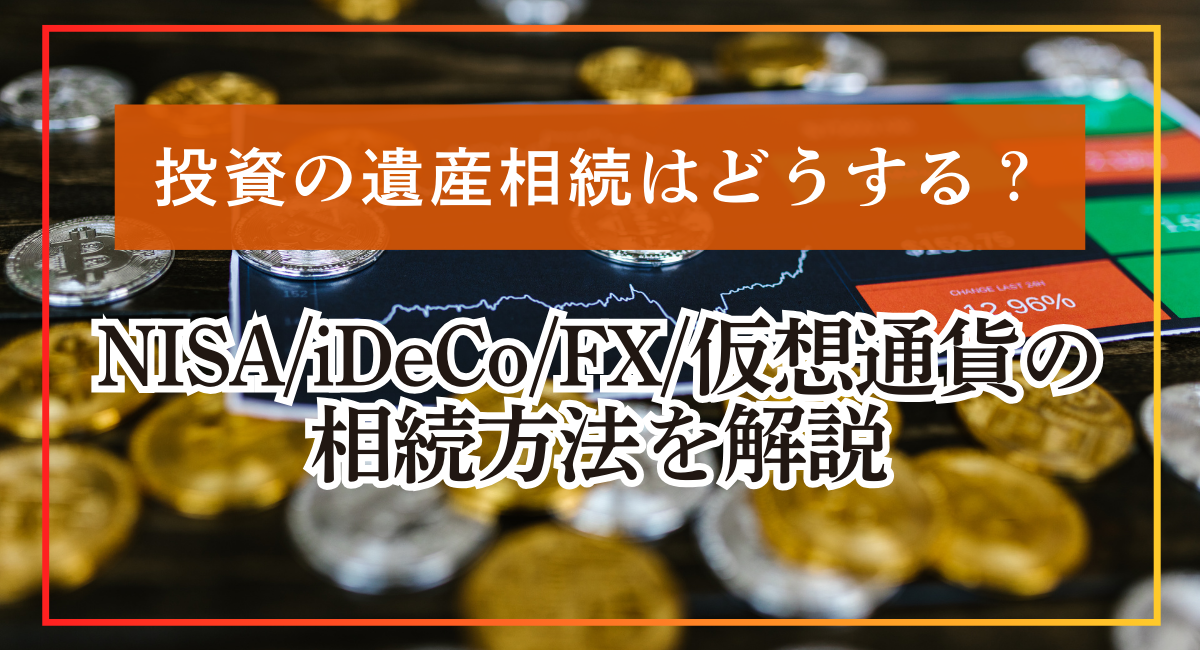近年は資産形成の手段にNISAやiDeCo、FXといった投資を選ぶ方も増えています。その一方で「投資している商品は相続できるのか?」「投資に損失が出ている状態の場合、相続はどうなるのか?」といった悩みや不安を抱えている方も多いでしょう。
また、近年は手続きのすべてがデジタルで行われる商品も多いので、相続の際にトラブルに発展する可能性もあります。
本記事では、比較的新しい投資であるNISA・iDeCo・FX・仮想通貨に焦点をあてて、スムーズに相続するために被相続人がやっておくべきポイントを解説します。
投資は相続可能?商品ごとに解説

近年は個人が投資できる商品も増えています。代表的な投資方法である株は、株券の名義を変更することで投資が可能です。ここでは、NISA・iDeCo・FX・仮想通貨の4種類について、相続が可能かどうか解説します。
NISA
NISAは、投資で得た利益が非課税になる「少額投資非課税制度」の略です。株式や投資信託等、幅広い金融商品に投資できるのが特徴です。NISAを行うには、「NISA口座」と呼ばれる専用の口座を開いてそこから投資を行います。
NISA口座自体は相続できませんが、保有していた株式や投資信託は課税口座に移されて相続されます。NISA口座を開設した本人が亡くなった場合、口座は使えなくなり、相続した株式は相続人の特定口座か一般口座に移されます。相続が発生した時点で含み益があればその分は非課税です。しかし、相続後に特定口座や一般口座に移された金融商品の配当金や分配金には所得税や地方税がかかります。
iDeCo
iDeCoは「個人型確定拠出年金」の略で、自分で拠出した資金を自分で運用して老後の資金を作る私的年金制度です。
iDeCoを運用していた方が亡くなった場合、その資金は「死亡一時金」扱いになり、一括して受け取りになります。公的年金のように「年金」として毎月定額の受け取りはできません。口座を引き継いで法定相続人がiDeCoの運用を続けることもできないので注意しましょう。
死亡一時金は『みなし相続財産』として扱われ、生命保険金などと同様、相続税の課税対象になります。ただし、500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。したがって、相続放棄をした場合でも受取人に指定されていれば、死亡一時金を受け取れます。それに加えて「みなし相続財産」は、受取人の人数×500万円まで非課税です。なお、死亡一時金は受取人が自分で手続きして受け取る必要があり、5年間手続きされないと、法務局に供託になります。
このほか、死亡一時金は「確定拠出年金法」によって受取人が決められます。確定拠出年金法では、配偶者を除いて「加入者の収入で生活をしていた者」が優先されます。例えば、自分で生計を立てている子どもと加入者の収入で生計を立てる子どもがいた場合、加入者の生計で生活を立てている子どものほうが受取人の優先順位は上です。なお、加入者が受取人を生前に指定しておくこともできます。
FX
FXは、少額で大きな取引ができるのが特徴の投資です。開始するには口座を開く必要がありますが、FX口座は名義変更できません。口座に未決済の取引(ポジション)が残っていた場合、すべて決裁して売却して、得られた現金を相続します。現金を相続するには、相続人が新しくFX口座を開く必要があります。手続きに時間がかかるケースもあるため、早めの手続きが必要です。
また、FXは保有している通貨によってはポジションの時点で含み損がでている可能性があります。含み損が多くなるとFX会社のルールに従ってロスカットが行われる場合もあるでしょう。
決裁した時点で損失が大きくなると口座への入金が必要です。場合によっては負の財産のほうが大きくなるでしょう。ポジションを持ったまま口座の名義人が亡くなった場合、決済のタイミングを計る必要があります。さらに、相続が発生した時点で多額な損失があると分かった場合、「相続」「限定承認」「相続放棄」の3種類から相続発生から3ヶ月以内に決断しなければなりません。
仮想通貨
仮想通貨は、現金・株式・不動産同様相続の対象になります。仮想通貨を取引している口座は名義変更が可能です。したがって、口座を開設した方が亡くなった場合は法定相続人が名義変更をして、口座ごと仮想通貨を引き継いで運用を続けていくことも可能です。
仮想通貨を相続する際は、相続日の取引価格を基準として相続税が発生します。そのため、相続日に保有している仮想通貨が値上がりすると相続税が高額になる可能性もあるでしょう。また、引き継いだ仮想通貨を売却した場合は別途「所得税」が課せられる場合もあります。
仮想通貨はまだ新しい資産のため、法律の整備が追い付いていないところもあります。したがって、保有している仮想通貨の種類や量、価値によっては相続税率の最大は55%であり、110%という表現は誤りです。仮想通貨の評価額に対して相続税と所得税を合算すると非常に高額になる、という意味であれば、具体例を用いた表現への変更を検討してください。
価値の高い仮想通貨を多量に保有している場合は、相続の方法を専門家に相談するのがおすすめです。
終活で投資を整理しておく重要性と方法

投資は、資産を増やす有効な方法です。しかし、投資を行っている最中に名義人が亡くなってしまうと相続で大きなトラブルが発生する恐れがあります。
ここでは、終活で投資を整理しておく重要性や方法を紹介するので参考にしてください。
投資によっては遺産がマイナスになる恐れがある
FXなど短期間で大きな金額が動く投資の場合、投資を放りっぱなしにしたまま亡くなると大きな損失が出る恐れがあります。損失の額によっては、遺産がマイナスになる可能性もあるでしょう。
「限定承認」を行えば自宅など特定財産の相続は可能ですが、遺族に大きな迷惑をかけることには変わりありません。また、仮想通貨は相続税だけでなく所得税がかかるので、遺族の金銭負担が大きくなる可能性もあります。
終活の一環として取引を少しずつ縮小させたり、保有している仮想通貨を現金に換えておいたりするなど対処が必要です。
遺産相続のやり直しが発生する可能性がある
近年は投資開始の手続きや運用がすべてオンライン上で可能なので、家族でも投資をしていることを知らないケースも珍しくありません。
投資をしている方がお亡くなりになり、スマホやパソコンのロックが開けられなくなった場合、相続がすべて終わってから投資をしていた、と発覚するケースもあるでしょう。このような場合、投資のやり直しが発生する可能性もあります。
また、iDeCoの一時金は5年間請求がないと法務局に供託になり、受け取るには「供託物の払渡しの請求」の手続きが必要です。
投資をしていることをエンディングノートに記す
投資をしている場合、投資の内容や額、相続の方法などを家族に伝えておくかエンディングノートに記しておきましょう。投資の種類、口座のID・パスワード・投資額・決算方法などを記しておけば、いざという時も安心です。
また、iDeCoの死亡一時金の受取人を指定している場合は、その旨も記しておきましょう。
専門家に相談して節税対策をする
仮想通貨やFXの場合、終活の一環として節税対策を行うのも有効です。特に、仮想通貨は相続が発生した際に相続税がかかり、売却した際に所得税がかかります。相続人に財産を残したいならば、保有している方が元気なうちに現金化して非課税の範囲内で生前贈与しておいたほうが節税になるケースもあるでしょう。
専門家に相談し、どのような節税方法があるか知っておくだけでも役立ちます。
まとめ
投資の相続は、相続のタイミングや方法によっては大きな損失が出る恐れがあります。また、被相続人が投資をしていることを知らなかった場合、相続のやり直しが発生する可能性もあるでしょう。終活の際は、投資も縮小していく、投資の現状を家族に伝える、節税の方法を専門家に相談するなど対処が必要です。
そうすれば、相続が発生した場合も投資で築いた資産をスムーズに遺族へ渡せるでしょう。
【仮想通貨復元スペシャリストのご案内】
・スクリーンショットやテキストデータで残しておいたシークレットリカバリーフレーズや秘密鍵が見つからない
・リップル(XRP)やエイダ(ADA)が取り出せなくなった
暗号資産の復元のお困りごとにつきまして、「仮想通貨復元スペシャリスト」サービスをご検討ください。
私たちの専門チームは、以下のような特徴を持つ信頼できるサービスを提供しています。
- 豊富な復元実績(BTC/ETH/XRP/ADA)
- 秘密保持契約を締結し、お客様の秘密情報及び個人情報の保護を徹底
- 一部成功報酬型で対応
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得
まずは無料相談から承ります。経験豊富な専門家が、あなたの大切な資産の復元をサポートいたします。