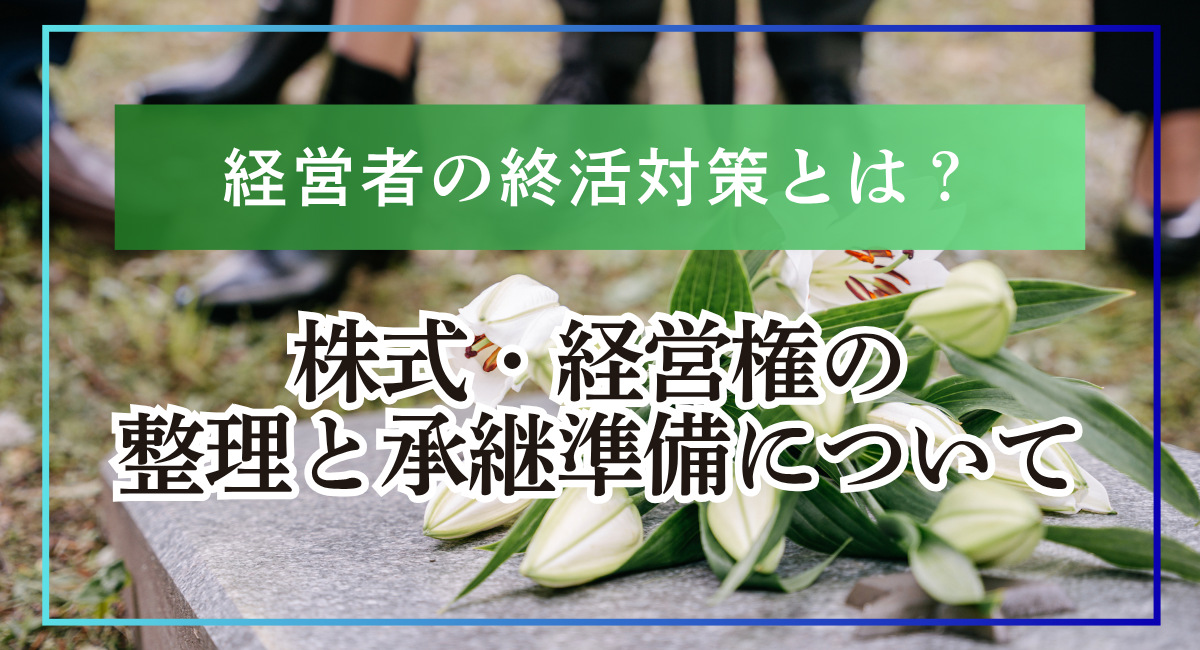企業の経営者として、忙しく過ごしていると、自分自身の「終活」について考える時間が少ないかもしれません。しかし、会社の未来や従業員の生活、家族の将来を見据えた時に、経営者自身が終末期と向き合う必要があります。
経営者の終活は、会社と家族を守るために重要な準備です。後継者の育成や経営権の移譲など、具体的な対策を講じることで、企業の存続と家族の安心につながります。
今回の記事では、なぜ経営者に終活が必要なのか、その理由や対策を紹介していきます。
1.経営者の終活が必要な背景とは

経営者にとって終活が必要な理由は、会社や関係者の将来を守るためです。経営者が突然亡くなった場合、会社の運営が滞るかもしれません。停滞が続くと、事業の継続が難しくなります。特に中小企業では、経営者が株式や経営権を一手に握っていることが多いです。後継者や事業承継の準備が不十分だと、企業の存続自体が危ぶまれます。
経営者の不在は、従業員や取引先にも大きな混乱をもたらすでしょう。そのため、事前に終活を進めて、事業承継や会社の方針を明確にすることが重要です。経営者が亡くなった際には、家族が会社の承継や相続の問題に直面します。終活を通じて、遺言や株式の承継準備を整えておけば、家族の負担も大きく軽減できるのです。
企業の信用や価値を守るためにも、経営者自身が早めに終活に取り組みましょう。万が一の事態に、会社や関係者が困らないためにも、早めに備えることが大切です。このような準備を進めることで、経営者の想いやビジョンが次の世代へ、しっかりと引き継がれます。
2.経営者が終活する上で注意すべきポイント
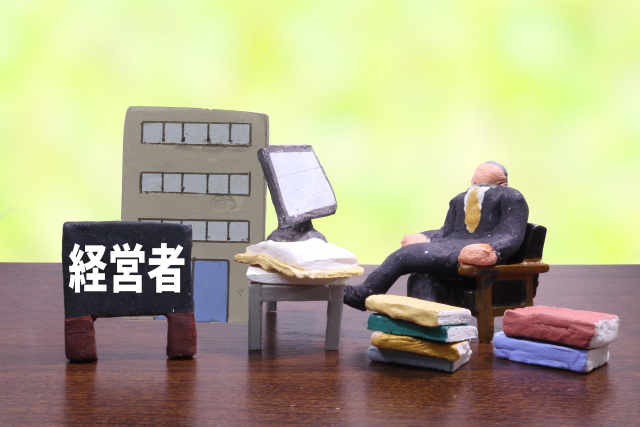
経営者の終活は、周囲の人々への影響を視野に入れた、慎重な対応が求められます。一つの判断ミスが、会社の経営や家族関係に影響を引き起こすかもしれません。経営者だからこそ、直面する複雑な課題を的確に乗り越える必要があります。終活の注意すべきポイントを事前に把握して、計画的に取り組むことが不可欠です。
| 項目 | ポイント |
| 後継者の選定 | 企業文化や価値観の共有が重要。早めの準備が必要。 |
| 後継者の育成 | 5〜10年かかる。計画的な育成が不可欠。 |
| 経営権を整理 | 株式の譲渡方法を慎重に検討。遺言も準備する。 |
| 事業継続計画 | 万が一に備えて、BCPや多角的な対応を行う。 |
2-1.後継者の選定と育成が必要になる
経営者が終活を進める上で、後継者の育成が課題になります。適切な後継者を選ぶことで、企業のビジョンや価値観を維持できます。一方で、後継者選びには時間がかかるため、早めの準備が大切です。
後継者の選定は、経営能力やスキルだけでは決められません。企業文化や価値観の共有が、重要になります。後継者が優秀な場合でも、十分な育成期間を設けなければ、組織運営やリーダーシップの発揮は難しいのです。一般的に、後継者の育成には、5〜10年かかることが多いといわれます。
2-2.経営権を整理しなければならない
まず、会社を存続させるのか、それとも廃業するのかという大きな決断が求められます。事業承継の準備は、経営者の終活において、最も重要なステップです。経営権の多くは、自社株式の所有に結びついています。
そのため、株式の譲渡方法について、慎重に検討しなければなりません。経営者が亡くなった場合に備えて、遺言を作成する必要もあります。事業継続計画(BCP)の策定も忘れてはいけません。このように、経営理念の承継を含めて、多角的に対応することで、万が一に備えたトラブル防止につながります。
3.株式の継承や相続人への気配り

3-1.株式譲渡・贈与・相続の選択
経営者の終活を考える際に、会社の株式をどのように後継者へ引き継ぐかは、大きなテーマです。株式の承継には、「有償での譲渡」「生前贈与」「相続」の3つの道筋があります。
まず「有償での譲渡」は、経営者が存命中に、後継者へ株式を売却する方法です。この場合、経営者が現金を受け取れるため、その後の生活資金として活用できます。また、後継者が株式を購入するため、他の相続人とのトラブルが起こりにくいです。しかし、後継者に十分な資金がなければ、有償譲渡は難しいかもしれません。
次に「生前贈与」は、経営者が存命中に、後継者へ株式を無償で譲り渡す方法になります。生前に株式を移転することで、経営の引き継ぎや、後継者の育成を計画的に進められます。贈与税の非課税枠や事業承継税制の活用によって、税負担も抑えられるのです。一方で、贈与税の発生や、他の相続人とのバランスで配慮が必要でしょう。
3つ目は、経営者が亡くなった後に株式が引き継がれる「相続」です。この場合、後継者が資金を用意する必要はありません。相続税の基礎控除も大きく受けられます。しかし、相続税の納税資金の確保や、遺言書がない場合に、遺産分割協議が難航する恐れもあります。
| 承継方法 | メリット | デメリット |
| 有償譲渡 | 現金化できる | 後継者に資金が必要 |
| 生前贈与 | 計画的に承継できる | 贈与税がかかる場合がある |
| 相続 | 資金が不要 | 納税や分割協議が課題 |
3-2.後継者以外の相続人への配慮
会社の株式や事業用資産が、遺産の大部分を占める可能性があります。後継者に集中して承継させる際に、相続トラブルが発生するかもしれません。このような事態を防ぐためには、遺言書を作成するのが有効です。遺留分に配慮した分割方法を明確にしましょう。
そして、何より重要なのは、家族や関係者との十分な話し合いです。事業承継や相続の方針を共有することで、全員が納得できる形が目指せます。専門家の助言を受けながら、計画的に争いのない事業承継を進めてください。
4.経営の引き継ぎと法務対策の準備

4-1.代表権・経営権の移譲
経営者にとっての「終活」は、個人の人生整理にとどまりません。特に、代表権や経営権の移譲は、事業の継続性や取引先との信頼関係など、多方面に大きな影響を及ぼします。
先述の通り、経営者は自らの健康や年齢を考慮して、早い段階から後継者の選定と育成に取り組む必要があります。代表権の交代 は、代表権の引き継ぎは、後継者を代表取締役に選び、登記を変更することで完了します。また、経営権の中核である自社株式の過半数(できれば3分の2以上)を後継者に移転しなければなりません。
他の相続人の遺留分に配慮しなければ、後継者への株式集中が法的に阻害される場合があります。そのため、遺言や生前贈与の活用などは、専門家への相談がおすすめです。
親族内での承継が難しい場合は、従業員への承継や、M&Aによる第三者への引継ぎも現実的な選択肢でしょう。どのような方法でも、経営者自身がご存命のうちに、会社の財務状況を整理しなければなりません。
4-2.「事業承継税制」の活用
経営者が終活を考える際に、株式の承継が進まないと、経営の安定や後継者育成に支障が出ることがあります。そのため、早い段階から株式の移転方法や納税資金の確保など、計画的な準備が不可欠でしょう。
このような承継を円滑に進めるために、活用できるのが「事業承継税制」です。非上場株式にかかる相続税や贈与税が一時的に猶予される制度であり、発生しないわけではないのです。
一定の条件を満たせば、後継者の負担を大幅に軽減できます。一方で、この特例措置を利用するには、都道府県に「特例承継計画」を提出しなければなりません。「特例承継計画」の提出後に、認定を受ける必要がある点にも注意してください。
経営者の終活は、会社の将来を左右する大きなテーマです。事業承継税制を活用して、計画的に準備を進めることで、後継者への円滑なバトンタッチが行えます。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
| 対象株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2まで | 全株式 |
| 適用期間 | 制限なし | 2027年12月31日まで |
| 特例承継計画の提出 | 不要 | 必要 |
| 納税猶予の割合 | 贈与100%、相続80% | 贈与・相続ともに100% |
| 後継者の人数 | 筆頭株主である後継経営者1人のみ | 持ち株10%以上の後継経営者3人まで |
| 雇用確保の要件 | 5年平均で相続・贈与時の80%以上を維持 | 実質撤廃 |
| 役員就任の要件 | 贈与前3年以上役員 | 贈与直前までに役員(2025年改正で緩和) |
| 事業継続困難時の免除要件 | 民事再生や会社更生時に再計算して、超過分を免除 | 経営環境変化などの要件で、譲渡・合併時も減免可能 |
5.円滑な事業承継のために
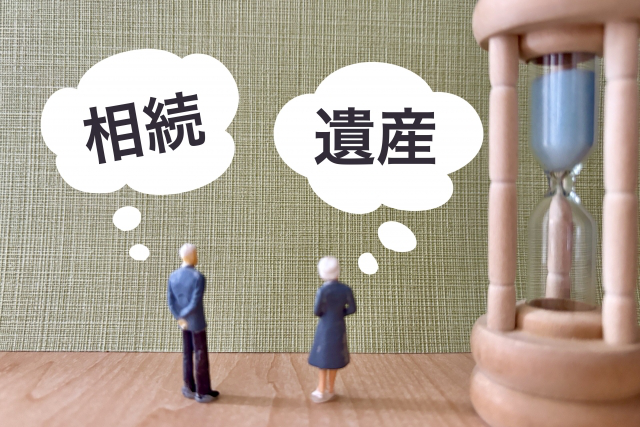
経営者が「終活」を考える際には、早めに事業承継の準備を進めなければなりません。会社を今後存続させるのか、それとも廃業するのか、根本的な方針を明確にしましょう。経営権や株式の承継に関しても、遺言や生前贈与などの法的手段を活用してください。スムーズな引き継ぎを実現できるように、準備することが重要です。
また、家族や従業員、取引先など、関係者としっかりコミュニケーションを取りましょう。承継の方針や計画の共有によって、引き継ぎ時の混乱が防げるのです。公的な支援機関や専門家の力を借りることで、より安心して準備が進められます。
事業承継は経営者にとって、最後の大きな経営判断になります。早めに準備を始めて、計画的に対策を進めるのが有効です。円滑な事業承継は、ご自身と会社の「これまで」と「これから」をつなぐ、大切な架け橋になるでしょう。