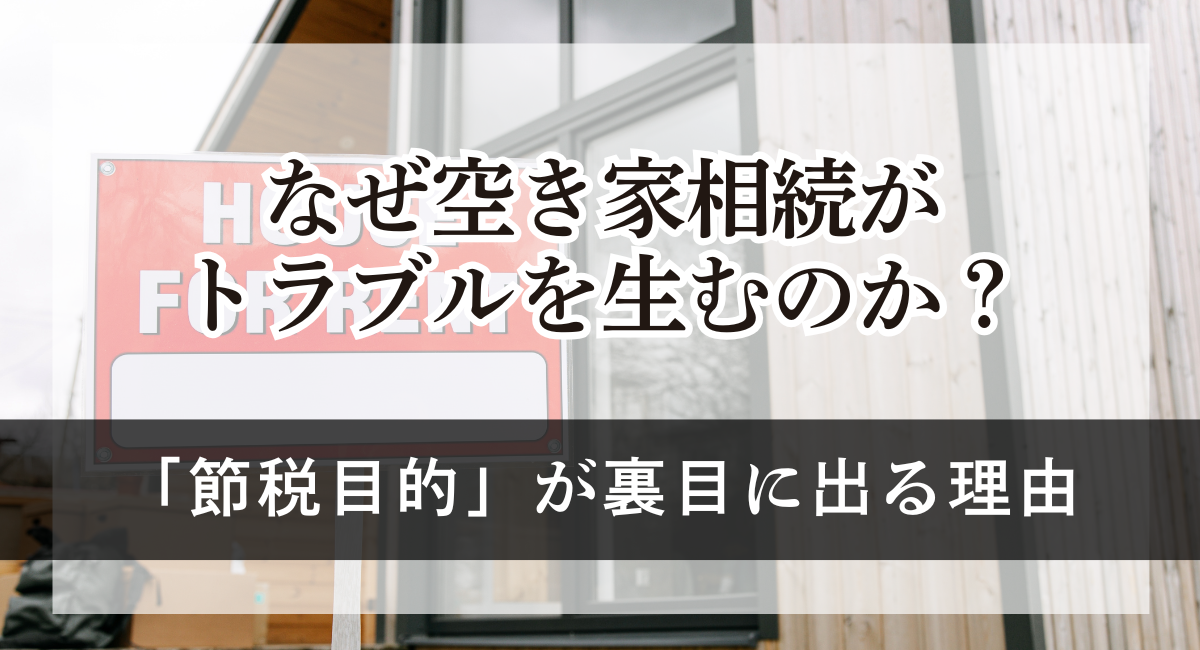相続対策として「空き家を活用すれば節税になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。
確かに、評価額を抑える方法として一見有効ですが、実際には「使い道のない空き家=負動産」に転じ、管理・税金・家族間トラブルの温床になるケースが少なくありません。

本記事では、なぜ節税目的の空き家相続が裏目に出るのかを解説し、実際に起こっているトラブル・管理費用・税制度の落とし穴から、“今”取るべき具体的な対策まで網羅します。
空き家を相続する可能性がある方・既に相続したけど処理に悩んでいる方は、ぜひ最後までご一読ください。
なぜ相続した空き家が「負動産」になるのか?

かつては「家や土地を持つこと=財産を築くこと」と考えられてきました。しかし、近年では、相続した空き家が「負動産」と呼ばれる場合があります。負動産とは、所有していても利益を生まず、維持管理の手間や費用、税金負担が大きく掛かる不動産です。
参考:令和5年(2023年)時点で、全国の空き家数は約 900万戸。
そのうち、総住宅数に占める空き家率(空き家数÷総住宅数)は 13.8%。
特に、地方や人口減少が進む地域では、空き家の売却や活用が難しいです。思いがけず、大きな負担を背負うことになることも珍しくありません。
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。資産価値がほとんどない不動産でも、手続きや費用が発生するようになったのです。買い手と借り手が見つからない地域では、解決が非常に困難なテーマかもしれません。不動産会社が、積極的に取り扱わないことも多いのです。
相続した空き家が資産ではなく「負動産」となるのは、人口減少や都市集中などが要因の1つです。空き家の増加、税制や管理コストの負担増、地方経済の縮小なども大きな問題になります。先述の通り「家や土地=資産」とは限らず、相続した不動産が負担となる時代になっているのです。
なぜ地方に空き家があふれるのか?深刻化する地域の実情

地方で空き家が増え続ける背景には、社会的な事情が複雑に絡み合っています。多くの若い世代が、進学や就職を機に都市部へ移り住んでいるのが要因の1つです。親世代が亡くなった後に、引き継ぐ人がいない、子ども世代が遠方にいるなどの理由で、空き家として放置されてしまうのです。
また、空き家の管理や解体には、費用や手間が掛かります。相続の手続きが複雑で、所有者がはっきりしないまま、放置される住宅も多いです。税制上、家を取り壊して更地にすると、固定資産税が高くなります。そのため、老朽化した家屋でも長年残されてしまうのです。
空き家の増加によって、老朽化による倒壊や火災、不審者の侵入などのリスクが高まります。また、空き家が多い地域では、地価が下がり、商業活動が大きく停滞するかもしれません。経済の停滞は、自治体の税収減少にもつながります。経済面で大きな打撃になるでしょう。住民同士のつながりが薄れて、地域コミュニティの活力が失われる、この負のサイクルが深刻化します。
地方の空き家問題は、単なる住宅の老朽化や管理の問題に収まりません。地域の安全や経済、コミュニティの存続にまで影響を及ぼす、深刻な社会課題になっているのです。
| 分類 | 内容 |
| 背景 | 高齢化・人口減少、相続・管理困難、税制の問題 |
| 空き家による影響 | 景観・治安悪化、地価下落、コミュニティ衰退 |
節税のはずが裏目に?相続税対策が招く地方物件のリスク

地方の不動産を利用した相続税対策は、節税に有効な手段に思われるかもしれません。一方で、想定外のリスクや負担を招く可能性もあります。地方の土地や建物は、首都圏と比べて、土地面積が広いケースが多いです。そのため、相続税評価額が高くなる傾向があります。
しかし、実際の市場価値(時価)が低いため、「相続税評価額>時価」となってしまいます。売却しても、相続税の支払いに十分な資金を得られないことがあるのです。つまり、売れにくい地方物件を相続した場合、相続税だけが重くのしかかります。現金化が難しい「負動産」となるリスクが高いのです。
また、地方の空き家や土地は、管理コストや固定資産税が毎年発生します。所有しているだけで、経済的な負担が続くのです。放置すれば、老朽化による倒壊リスクや、近隣住民とのトラブルに発展するかもしれません。最悪の場合には、「特定空き家」に指定されます。固定資産税の優遇措置が外れるなど、大きな負担増につながる可能性があります。
相続した不動産に資産価値がなければ、売却や賃貸は難しいでしょう。次世代への相続時に、さらに引き継ぐ人がいない「負動産の連鎖」を招く恐れもあります。
市場価値と評価額の逆転現象
空き家や土地などの不動産を受け継ぐ場合、「市場価値」と「相続税評価額」が逆転するケースが増えています。地方や一部の都市部では、人口減少や空き家の増加によって、不動産の需要が大きく減少しています。
実際に売ろうとしても、買い手がつかず、想定よりも安い価格でないと売却できない事例が多いです。一方で、相続税の計算に使われる評価額は、過去の地価や路線価をもとに算出されます。そのため、現実の市場価格と大きな差が生じてしまいます。
このような逆転現象が起きると、相続人は実際の売却価格よりも、高い評価額に基づいて相続税を納めなければなりません。特に空き家の場合、管理や維持の負担が重くなり、放置される要因にもなるのです。
| 比較項目 | 市場価値(実勢価格) | 相続税評価額(路線価等) |
| 価格の決定要因 | 実際の売買・需要 | 過去の地価・路線価 |
| 変動の速さ | 変動が早い | 変動が遅い |
| 逆転現象 | 実際の価格が低い | 評価額が高い |
| 相続人の負担 | 売却しづらい・安い | 税負担が重い |
空き家を巡る相続トラブルの実態

空き家をめぐる相続トラブルや「負動産」は、地方だけでなく、全国的に増えています。その背景には、家族間の複雑な関係や手続きの難しさ、経済的な負担などが挙げられます。相続が発生した時に、遺産分割協議がまとまらず、法定相続分で不動産を共有名義にするケースがあります。この場合、空き家の売却や処分には、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対する人がいると話が進まず、結果として、空き家が長期間放置されます。
さらに、相続手続きを長期間放置すると、相続人の数が世代を経て増え続けます。所有者が膨大な人数に膨らむこともあります。空き家の管理費用や修繕費をめぐって、兄弟姉妹間で争いが起きるかもしれません。
空き家の放置は、治安の低下や倒壊や火災など、法的・社会的なトラブルに発展します。空き家をめぐる相続トラブルは、家族間の合意形成の難しさや、手続きの複雑さ、経済的負担が絡み合うのです。
相続人の増加で権利関係が複雑化する
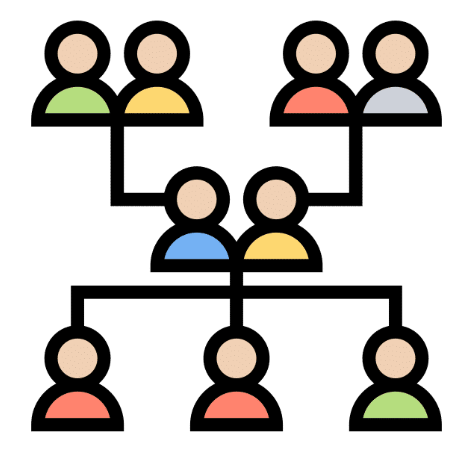
相続が発生した後、不動産の名義変更(相続登記)をせずに、放置する事例があります。放置することで、時間の経過とともに、相続人が増える可能性があるのです。例えば、最初は兄弟姉妹だけが相続人の場合でも、そのうちの1人が期間を経て、亡くなってしまうかもしれません。そのような場合に、配偶者や子どもが新たな相続人として加わります。このような世代交代が繰り返されることで、相続人の数が膨れ上がることも珍しくないのです。
相続人が増えると、不動産の売却や処分、名義変更などの手続きを進める際に、全員の同意が必要になります。連絡が取れない人や、顔も知らない遠い親戚が相続人になる場合もあります。このような状況では、全員の意見をまとめるのは非常に難しいでしょう。その結果、話し合いがまとまらず、不動産が長期間放置されてしまいます。
期間が長引くことで、空き家の管理や修繕が、行き届かなくなるのです。建物が老朽化して、地域の問題へと発展するリスクも高まります。この相続人の増加と権利関係の複雑化は、相続登記を先延ばしにすることで生じる、典型的なトラブルです。
| トラブル内容 | 主なリスク・影響 |
| 相続人の増加・複雑化 | 手続きが困難、意見の集約が難しい |
| 売却・処分が困難 | 全員の同意が必要で進まない |
| 管理不全・老朽化 | 空き家問題、地域トラブル |
| 書類取得が困難 | 手続きがさらに複雑・長期化 |
| 税金・負担増加 | 延滞金・罰則リスク |
| 義務化・罰則 | 未登記で罰金の可能性 |
空き家の維持・管理費用と責任の負担が悩みに
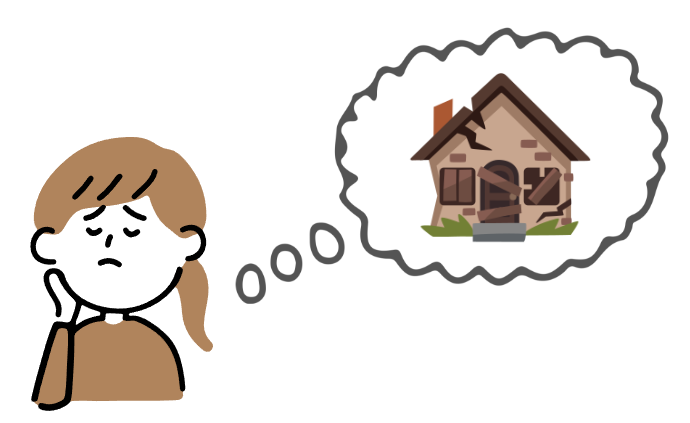
空き家を相続した場合に、その維持や管理にかかる費用や責任は、全ての相続人が法定相続分に応じて、分担します。
- 固定資産税
- 建物の修繕費
- 庭の手入れ費用など
相続財産の中に現金がある場合には、まずはそこから支払うことができます。しかし、現金が足りない時や遺産分割協議が済んでいないこともあります。そのような場合は、各相続人が持分割合に応じて、費用を支払わなければなりません。
空き家の管理が不十分な場合には、さらに注意が必要になります。例えば、建物の一部が壊れて、近隣に被害を与えてしまうと、相続人全員が連帯して責任を負わなければなりません。
- 建物や土地の安全確保
- 定期的な点検や修繕
- 不法侵入の防止など
このようなトラブルを防ぐためにも、空き家を相続した際には、できるだけ早く相続人同士で話し合いましょう。管理や費用分担の方法について、決めておくことが大切です。
相続における政府の空き家対策とマッチング制度

日本では、相続をきっかけに発生する空き家の増加が社会問題です。このような状況を受けて、政府は空き家の発生や放置を防ぐため、様々な対策を講じています。
まず、2024年4月からは、相続による不動産の名義変更、いわゆる「相続登記」が義務化されました。これによって、相続人の負担が増えるかもしれません。一方で、所有者が不明な空き家や土地の放置が防げます。相続登記を怠った場合には、空き家の管理や売却が難しくなります。行政から指導やペナルティを受けるリスクも高まるのです。
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」も強化されました。この法律では、危険な状態にある空き家を「特定空き家」に指定します。そして、所有者に対して、指導や命令、行政による撤去を行って、その費用を請求できるのです。
空き家の活用を促すために「空き家バンク」というマッチング制度も広がっています。購入や賃貸を希望する人や団体と情報を共有して、自治体や国が、空き家の仲介を行う仕組みです。
※自治体によって補助金や制度の内容が異なります
このように、政府は相続による空き家の放置を防ぐため、法制度の整備や税制優遇など、多角的な対策を進めています。今回は代表事例として、譲渡所得税の特例と空き家バンクについて、解説していきます。
相続する空き家の3,000万円特別控除(譲渡所得税の特例)

相続した空き家を売却する場合に、譲渡所得税の優遇措置が受けられます。この制度は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれています。空き家の売却による利益(譲渡所得)から、最大3,000万円までを差し引けるのです。
つまり、税金の負担を大きく減らせる制度になります。対象となるのは、相続や遺贈によって取得した、家屋とその敷地です。
注意点としては、相続開始時に、被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいた場合になります。1981年5月31日以前に建てられた、戸建て住宅でなければなりません。また、売却価格が1億円以下であることや、売却前に耐震改修を行えるかが、制度を活用する要件の1つです。
この特例が使用できる期間は、相続が始まった日から、3年を経過する年の12月31日までになります。そして、2027年12月31日までの売却が対象です。なお、2024年税制改正により、相続人が複数いる場合の控除額は最大2,000万円に制限される見通しです。
※2024年4月時点。制度の詳細は最新の税制改正動向を確認してください。
実際にこの控除を受けるには、空き家がある自治体で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得してください。確定申告の際に、必要書類を税務署に提出する必要があります。この特例を活用することで、空き家の売却時にかかる税金を大きく抑えられます。空き家の売却に悩んでいる場合は、この制度の活用を検討してみましょう。
| 項目 | 内容 |
| 控除額 | 最大3,000万円(相続人3人以上は1人2,000万円) |
| 適用期間 | 2027年12月31日まで、相続開始から3年以内 |
| 対象物件 | 1981年5月31日以前の戸建て空き家 |
| 居住状況 | 被相続人が一人で住んでいた |
| 売却価額 | 1億円以下 |
| 売却方法 | 耐震改修後、または解体後に売却 |
| 手続き | 自治体で確認書取得→確定申告 |
「空き家バンク」の活用
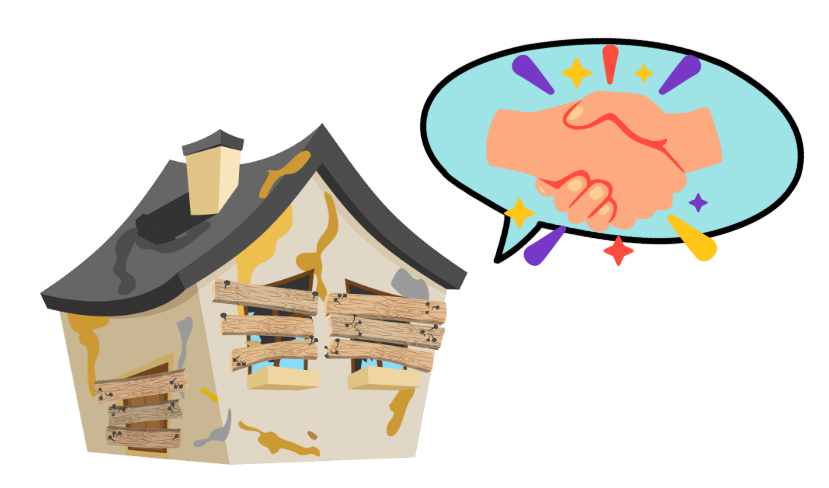
空き家バンクは、国や自治体が主導するマッチング制度です。空き家の情報を集約して、物件を探している人と、所有者を結びつける場として機能しています。所有者は、空き家を空き家バンクに登録しておきます。
これによって、従来の不動産の流通ルートでは出会えなかった、新しい利用希望者と接点が持てるのです。利用希望者は、自治体のウェブサイトなどで、多様な空き家情報を閲覧します。気になる物件があれば、問い合わせや内覧、契約手続きへと進む流れです。
この仕組みを活用することで、地方の空き家や古民家などの、個性的な物件に出会えるチャンスが広がります。価格も、一般的な市場より抑えられているケースが多いのです。自治体が運営に関わることで、取引の透明性や安心感が高まります。地方移住や新規事業の拠点探しなど、様々なライフスタイルやビジネスニーズにも応えるでしょう。
都市部では登録物件が限られていたり、契約の際に宅建業者を介するなど、様々な注意点もあります。しかし、空き家バンクは、所有者・利用希望者の双方に、新たな可能性をもたらしているのです。この制度は、地域の活性化や空き家問題の解決にもつながる、有効な手段になります。
| 項目 | 内容 |
| 仕組み | 国や自治体が運営。空き家所有者が物件を登録して、利用希望者が情報を閲覧・問い合わせできる。 |
| 主な流れ | 1. 所有者が登録 2. 自治体が情報公開 3. 利用希望者が閲覧・問い合わせ 4. 内覧・契約 |
| 主な対象物件 | 地方の空き家、古民家、個性的な物件など |
| メリット | ・市場に出づらい物件に出会える ・価格が安い場合が多い ・自治体が関与し安心感がある ・補助金や支援制度がある自治体も ・地域活性化や空き家問題の解決に貢献 |
| デメリット・注意点 | ・都市部の物件は少ない ・物件の状態にばらつきがある ・成約保証はない ・契約時に仲介手数料が発生 ・積極的な売却活動はない ・契約や交渉の手間がかかる |
| 利用例 | 地方移住、新規事業拠点探し、古民家再生、セカンドハウス取得など |
| 地域への効果 | 移住者増加、空き家減少、地域経済の活性化、景観改善など |
「空き家相続」は早めの判断と行動が鍵

空き家の相続は、感情や手続きコストなど、様々な課題が絡む複雑なテーマです。放置すればするほど、リスクが高まります。家族間のトラブルや、資産価値の目減りにもつながるでしょう。相続が発生する前から備えて、判断と行動を早めに起こすことが重要です。「まだ先の話」と思ってはいけません。専門家への相談を含めて、今できる一歩を踏み出しましょう。