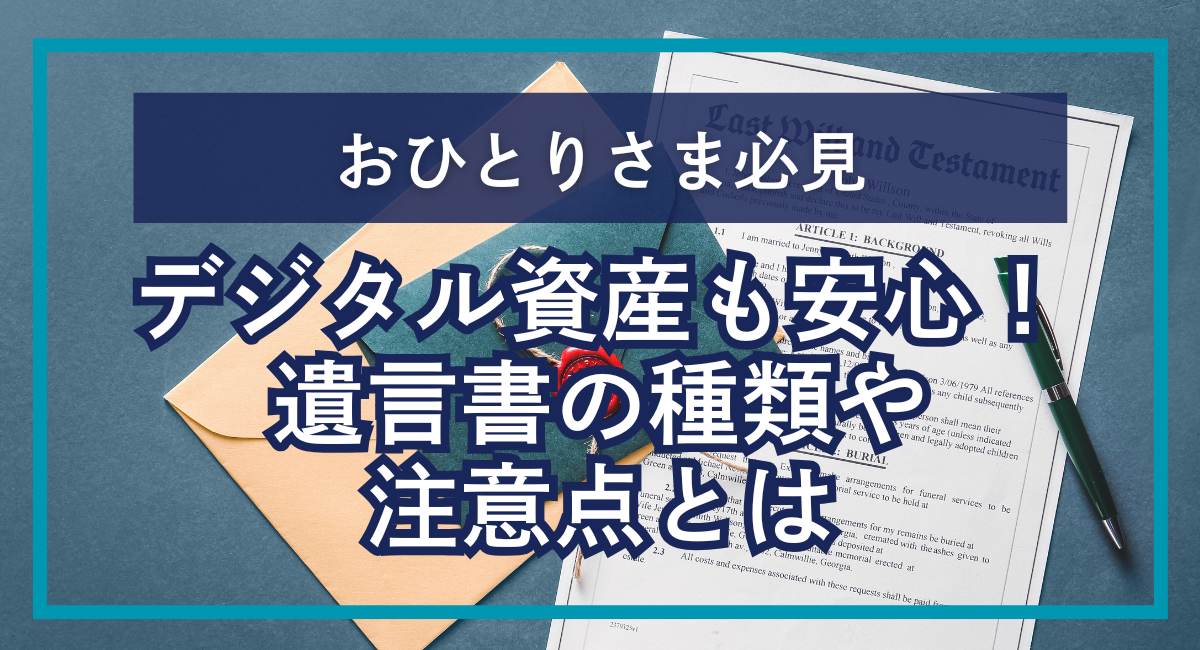現在日本国内は人口減少と高齢化の促進が加速しています。その背景には未婚率の上昇も挙げられ、単身世帯は2035年に2,450万世帯でピークに達すると予測されています。単身世帯の増加は相続手続きにも大きな影響を及ぼすと考えられており、配偶者や子がいない相続の増加によって、相続人以外への遺贈や遺言書の作成に注目が集まっています。
特にパソコンやスマホの普及で、デバイス上で管理していた資産やセンシティブな情報をご自身の死後にどう扱ってほしいか、遺言書を使って検討する人も増加傾向にあります。そこで、本記事では、おひとりさま向けに遺言書の種類や注意点をご紹介します。
参考URL 国立社会保障・人口問題研究所 日本の世帯数の将来推計(全国推計) 令和6(2024)年推計
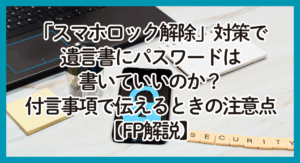
遺言書の種類とは?

遺言書には主に以下の3つの種類があります。種類によって必要となる手続きや費用、注意点が異なるため、ご確認の上で作成を検討されることがおすすめです。
自筆証書遺言
遺言者(遺言書を書く人)自身が全文を自筆で書く遺言書です。紙とペンがあれば作れるものであり、最も手軽でお手頃な遺言書ですが、法的な要件を満たしていないと無効になるリスクがあるため注意が必要です。自筆証書遺言のメリット・デメリットは以下をご確認ください。
| メリット | デメリット | |
| 作成費用 | かからない(無料) | – |
| 作成方法 | 手軽に作成できる | 形式不備で無効になるリスクが高い |
| 保管 | 自筆証書遺言書保管制度(法務局保管)の利用で安全性を高められる | 紛失・偽造・変造・隠匿のリスクがある |
| 手続き | – | 原則として家庭裁判所での「検認」手続きが必要(保管制度利用時は不要) |
| 専門性 | – | 法律知識がないと不備が生じやすい |
| トラブル | – | 相続人間での紛争の原因となることがある |
公正証書遺言
公証役場にて公証人が遺言者の話を聞き取り、証人2人以上の立ち会いのもと作成する遺言書です。最も安全で確実な方法とされており、公証人が病院などへ出張してくれる方法もあります。公正証書遺言のメリット・デメリットは以下をご確認ください。
| メリット | デメリット | |
| 作成費用 | – | 費用がかかる |
| 作成方法 | 公証人が作成するため無効になるおそれが極めて低い | – |
| 保管 | 原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がない | – |
| 手続き | 家庭裁判所での「検認」手続きが不要 | 証人2人以上が必要(自分で用意するか、公証役場で手配してもらう) |
| 見直し | – | 費用がかかるため、再作成をする人は少ない |
| トラブル | 書式不備によるトラブルは起きにくい | – |
秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し封筒に入れて封印し、その封筒を公証人と証人2人以上に提出して、自分の遺言書であることを証明してもらう遺言書です。内容は秘密にできますが、形式不備のリスク残りやすく一般的にあまり利用されていません。
| メリット | デメリット | |
| 作成費用 | – | 費用がかかる |
| 作成方法 | – | 形式不備で無効になるリスクがある |
| 保管 | 公証人が関与するため紛失しにくい | – |
| 手続き | – | 家庭裁判所での「検認」手続きが必要 |
| 見直し | – | 秘密証書を作成し直す際には再度費用が必要 |
| トラブル | – | 公証人は内容にはタッチしないため不備は起きやすい |
おひとりさまに遺言書がおすすめされる3つの理由

遺言書は一般的に「財産が多い方」が作成するイメージが強いですが、おひとりさまの方の場合は、財産の多さにとらわれることなく遺言書を作ることがおすすめです。そこで、この章ではおひとりさまに遺言書がおすすめされる理由について、3つにわけて解説します。
ご自身の希望に沿った遺産の分配ができる
遺言書がない場合、財産は民法の定める「法定相続人」の順位に沿って分配されます。
- 配偶者は常に相続人となる
- 第1順位 直系卑属(子や孫)
- 第2順位 直系卑属
- 第3順位 兄弟姉妹
おひとりさまの場合、法定相続人がいないか、いても疎遠な親族であるケースも少なくありません。遺言書があれば、ご自身の本当に希望する相手に財産を残すことができます。
例として、内縁のパートナーは異性・同性問わず、法律上の婚姻関係がないため遺言書がないと財産を相続することができません。長年お世話になった友人や特定の団体、慈善団体やNPO法人に寄付をしたい場合も、遺言書に記載しておかなければ財産を「遺贈」することができません。
遺言執行者を選べる

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。遺言書で指名しておくことで、相続手続きや財産の分配などをスムーズに進めてくれます。
おひとりさまの場合、ご自身に万が一のことがあった際、財産を巡る手続きは残された方(法定相続人や関係者)にとって大きな負担となる可能性があります。遺言執行者を指定することで、その負担を軽減しご自身の希望が確実に履行されるように手配できます。
遺言執行者には、弁護士や司法書士など法律の専門家をご自身で指名することも可能です。
デジタル資産の承継・破棄を希望できる

現代のおひとりさまにとって、デジタル資産は無視できない存在です。ネットバンキング、証券口座やSNSアカウント、各種サブスクリプションサービス、クラウドストレージなど、その種類は多岐にわたります。
デジタル資産をどのように処分してほしいかを遺言書の付言事項に明記することで、残された方が手続きを漏らすことなく相続手続きを進めることが可能です。さらに、遺言執行者がいればスムーズに処分が進みます。
デジタル資産については以下の関連記事もご一読ください。
関連記事:SNSや収益のあるデジタル遺産としてどう取り扱うか
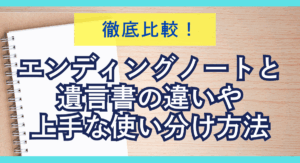
遺言書を作る場合の注意点とは
遺言書は、ご自身の意思を明確に伝えるための重要な書面です。法的な要件も定められているため、もしも要件をクリアしていなかった場合には、遺言書が無効となるおそれがあります。そこで、作成時にはあらかじめ注意点をクリアしておきましょう。
加除訂正には注意が必要
費用をかけずに気軽に作れる「自筆証書遺言」は加除訂正(加筆修正のこと)を行いやすく、気軽に書き換える人も少なくありません。
しかし、自筆証書遺言の作成後における追加や訂正には、民法で定められた厳格なルールがあります。ルールに従わない加除訂正は、その部分が無効になったり、遺言書全体が無効になったりする可能性があります。
注意ポイント:訂正方法を守ること訂正箇所に二重線を引いて押印し、欄外に訂正した旨と何字訂正したかを記載して、再度署名と押印が必要です。
加除訂正を繰り返していると記載内容がわかりにくいだけではなく、不備も起きやすくなります。内容を訂正する際は、最初から全て書き直すことがおすすめです。
財産目録は定期的な見直しがおすすめ

遺言書に添付する「財産目録」とは、預貯金や不動産、有価証券など、ご自身の財産を一覧にしたものです。財産は時間の経過とともに変化するため、定期的な見直しがおすすめです。特に以下のタイミングでは、遺言書全体を見直すようにしましょう。
- 大きな財産の取得や処分があった時(不動産の売買、高額な預金の移動など)。
- 新たな口座を開設したり、閉鎖したりした時。
財産が多い場合は税理士や弁護士への相談も検討を
不動産や株式など多額の財産がある場合、相続人や受贈者(遺贈を受けた人)がいる場合は相続税が発生する可能性があります。また、複雑な希望を盛り込みたい場合や、資産の評価方法が難しい暗号資産などをお持ちの場合は、遺言書の作成時に専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
- 税理士
相続税の試算や、生前贈与など税に関するアドバイスを受けることが可能です。資産の評価全般を相談できます。
- 弁護士
遺言書の記載内容や、将来起こりうるトラブルへの対策について相談できます。
- 司法書士
不動産の登記に関するアドバイスを中心に相談できます。
専門家を活用することで、ご自身の希望に沿った遺言書を作成し将来のトラブルを未然に防ぐことも可能です。
まとめ
おひとりさまにとって、遺言書はご自身の人生の終着点と、大切にしてきたものや想いを次へとつなぐための「大切な手紙」です。
法的な効力を持つ書類であると同時に、ご自身の希望を明確に示せるため、おひとりさまこそご検討されてみてはいかがでしょうか。特に、増加するデジタル資産への対応はプライバシーの観点からも遺言書を活用されることもおすすめです。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼