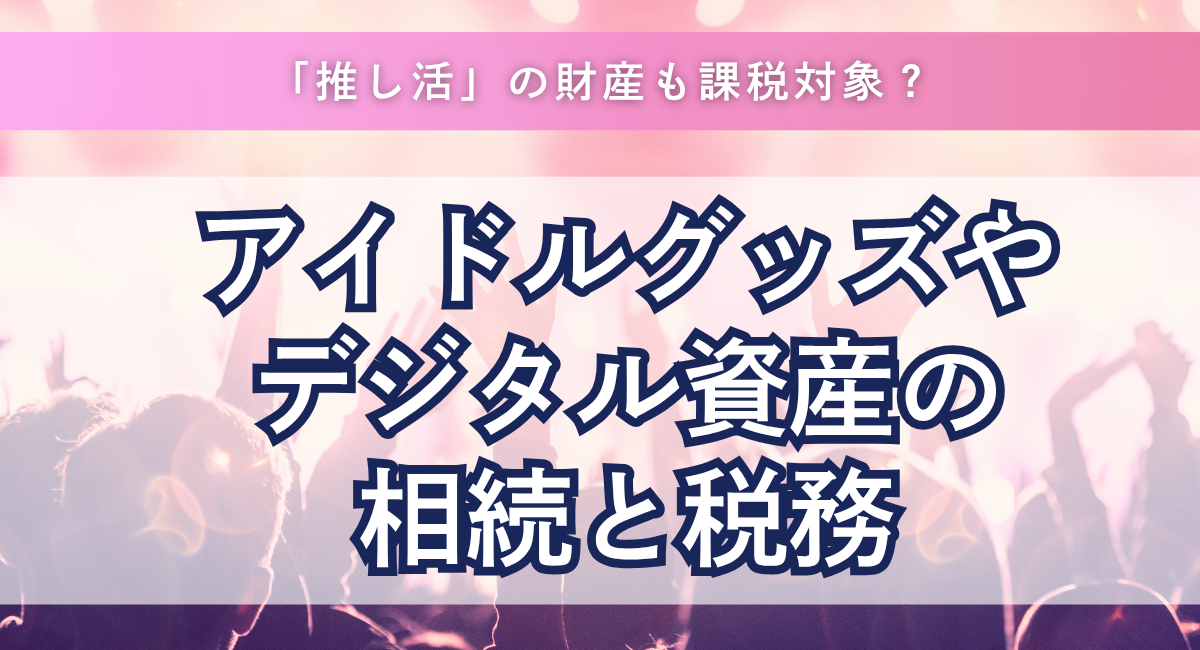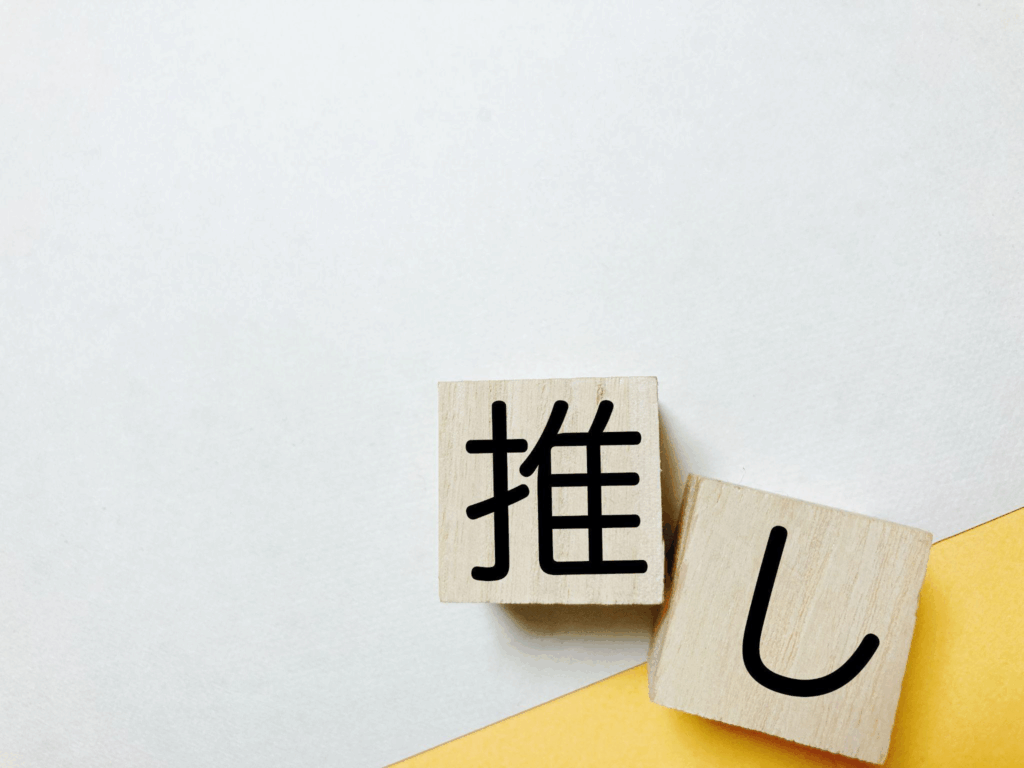
個人の趣味や「推し活」に関連した財産が、相続の現場で注目を集めています。このような資産は、金銭的な価値が明確でない場合が多いです。しかし、市場では高額で取引されることもあります。税務上の扱いが課題となるケースが増えているのです。
相続税の対象となるのは「金銭的価値のあるもの」です。「推し活」で蓄積されたコレクションやデジタル資産は、一定の条件下で課税対象となり得ます。今回の記事では、新しい形の資産に対する、相続・税務上の注意点について解説します。
「推し活」が資産になる時代?

近年、「推し活」が趣味や消費活動を超えて、新たな資産形成の手段としても、認知され始めています。推し活とは、アイドルやアニメ、芸能人など、ご自身が応援している存在を支えることです。これまでは、グッズの購入やイベントへの参加などの「消費型」応援が主流でした。最近では、推し活の範囲は広がり、投資や資産運用が結びつくケースも増えています。
好きな芸能人などが所属する企業の株式を購入することで、応援と資産運用を同時に実現するのです。推し活を通じて、貯金や計画的な支出管理、自己投資の意識が高まります。推し活そのものが人生を豊かにする「自己資産」になるのです。このように、推し活市場は年々拡大して、経済的にも大きな影響を与えています。
ご自身の「宝」が他人の「謎」になる現実
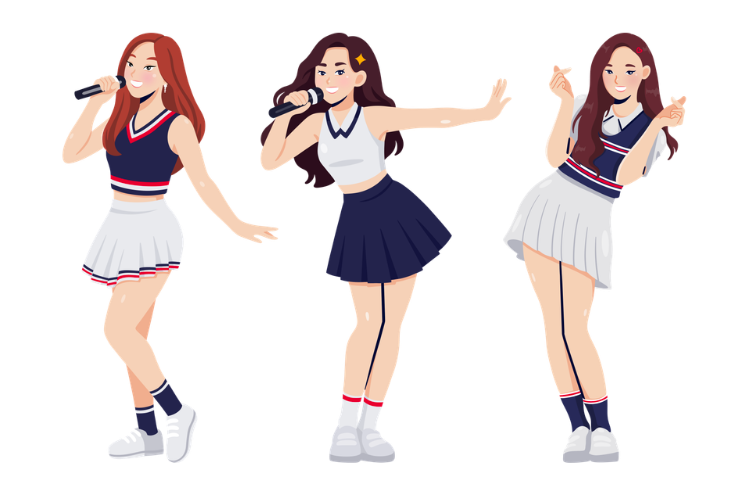
推し活で手に入れたグッズや思い出は、ご自身にとってかけがえのない「宝物」です。推しの存在は日々の励みになります。人生を豊かにする大切な存在です。しかし、その「宝物」も、他人から見ると、なぜそれに価値があるのか分からない「謎」に映るかもしれません。
大切にしているフィギュアや限定グッズ、ライブのチケットの半券などは、思い出が詰まった唯一無二の存在です。しかし、興味のない人にとっては、単なるモノや紙切れにしか見えません。家族や友人に推し活の話をしても、温度差を感じるでしょう。理解されずに、寂しさやもどかしさを覚えることも多いのです。
CD、限定グッズ、サイン入りアイテムも資産価値あり?
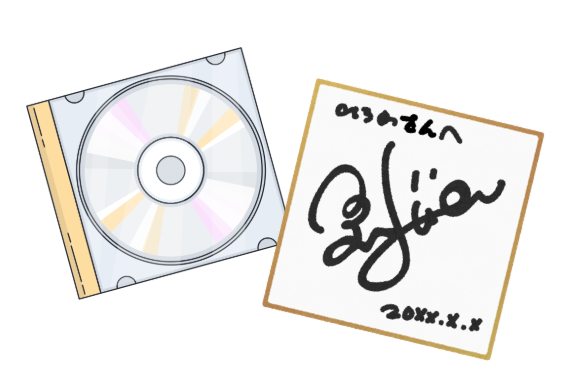
CDや限定グッズ、サイン入りアイテムは、趣味のコレクションを超えて、資産価値を持つ存在です。例えば、限定グッズや、著名人の直筆サイン入りアイテムになります。その希少性や人気の高さから、コレクターの間で高額で取引されることが珍しくありません。
発売当時は数千円だったCDやグッズが、年月を経てプレミア価格になる可能性があります。オークションで数万円、場合によっては、数十万円以上で売買されるケースも存在します。自分にとって大切な「推し活」のアイテムが、思わぬ資産になるのです。
フリマアプリやオークションで価格がつくグッズは要注意

「推し活」グッズは、家族や相続人にとっては、価値が分かりにくいものです。フリマアプリなどで取引される価格が、相続時の評価額の参考になることがあります。高額売買の実績がある場合、遺産分割や相続税の申告に影響を与えるかもしれません。
一方で、オークションなどで高値で取引されている場合でも、その価値を知らずに家族が処分してしまうケースがあります。思い入れやコレクションの背景が伝わらない状態で、「謎のグッズ」として扱われてしまうのです。家族や周囲の人に、そのアイテムの内容や背景を明確に示しておくことが大切です。推し活グッズも「資産」として意識して、家族と情報を共有することが、円滑な相続につながるでしょう。

これも課税対象?意外と知らない「相続財産」の範囲

相続財産と聞くと、多くの人が現金や不動産などを思い浮かべるかもしれません。実際には、相続税の対象となる財産は数多く存在するのです。例えば、株式や投資信託などの有価証券、自動車や貴金属になります。さらに、骨董品、ゴルフ会員権や著作権、特許権などの権利も相続財産として扱われるのです。
相続税法上は「みなし相続財産」と呼ばれるものも課税の対象です。具体的には、生命保険金や死亡退職金などになります。
亡くなる直前の3年以内に、被相続人(亡くなった方)から相続人へ贈与された財産なども、相続財産として課税されます。家族名義の預金の場合も、被相続人が管理・運用していた場合は、本人の財産とみなされることがあります。
このように、相続財産の範囲は想像以上に広いのです。推し活グッズ以外に、「まさかこれも?」と思うものまで、課税対象となる場合があります。相続の際には、どの財産が課税対象になるのかを把握しましょう。必要に応じて、専門家に相談することも重要です。
| 区分 | 主な例 | 備考(非課税枠など) |
| 本来の財産 | 現金・預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、骨董品、権利(著作権等) | |
| みなし財産 | 生命保険金、死亡退職金 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 生前贈与 | 死亡前3年以内の贈与財産 | 令和9年(2027年)以降は、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象となる予定 |
| 非課税財産 | 墓地、仏壇、香典、公益団体への寄付 |
現物資産とデジタル資産、どこまでが評価対象?

相続税の課税対象となる財産には、現物資産とデジタル資産の両方が含まれます。現物資産は、不動産や自動車、貴金属、骨董品など、目に見える形のある財産です。一方で、デジタル資産は、ネット銀行の口座残高、電子マネー、仮想通貨などが該当します。
さらに、収益を生むウェブサイトや動画チャンネルなど、経済的価値が認められるものは、相続税の対象になるのです。金銭的価値があるものは、広く相続税の評価対象になります。相続財産の全体像を、正しく把握することによって、適切な資産の承継や終活にもつながります。
| 分類 | 主な例 | 相続税評価・備考 |
| 現物資産 | 不動産、貴金属、骨董品など | 目に見える形のある財産。時価などで評価する。 |
| デジタル資産 | ネット銀行の預金、電子マネー、仮想通貨など | 相続発生時の残高や時価で評価。金銭的価値があれば、課税対象になる。 |
| 収益資産 | WEBサイト、動画チャンネル | 将来収益見込額を基に評価。著作権等は「年平均収入×0.5×評価倍率」等で算出する。 |
| その他権利 | 著作権、ゴルフ会員権など | 経済的価値があれば、課税対象になる。 |
SNSアカウント・配信購入履歴・NFTの扱い

SNSアカウントや配信サービスの購入履歴、NFTなどのデジタル資産は、相続時に扱いが異なります。主要SNS(例:X、Instagramなど)の利用規約上、アカウントの相続・譲渡は原則不可とされていますが、削除や凍結の申請は可能です。遺族が申請することで、アカウントの削除や切り替えが可能になります。
配信サービスの購入履歴や、サブスクリプション契約も同様です。個人利用が前提のため、相続人が権利を引き継ぐことは、基本的にできません。動画や音楽、電子書籍などのサービスは、契約者が亡くなった後も、自動的に解約されない仕組みです。そのため、遺族が速やかに解約手続きを進める必要があるでしょう。
また、NFTなどのデジタル資産は、相続財産として扱われるケースが増えつつあります。相続人が必要な手続きを行えば承継が可能です。しかし、パスワードや管理情報が分からないとアクセスできないため、事前の情報整理が重要になります。デジタル遺産の管理や、承継を円滑に進めるためには、生前から資産内容やアクセス情報を共有することが大切です。
そのままでは家族が困る?推し活アイテムの“遺し方”

推し活アイテムは、持ち主の大切な宝物でも、家族にとっては価値や扱い方が分かりません。将来的に相続に立ち会ったとしても、多くの人は戸惑うでしょう。希少性や市場価値がある場合でも、適切な評価や管理ができない状態で、処分されるケースもあります。
このような混乱を避けるためには、まず自分のコレクションをリストとして、作成してください。アイテムごとの特徴や思い入れ、入手経路、現在の相場などを記録することが大切です。写真やデジタルデータの活用によって、家族が後から見ても分かりやすくなります。
特に大切にしているアイテムや譲る相手がいる場合には、その旨をエンディングノートや遺言書に記載しましょう。具体的な希望を書いておくことで、家族が迷わず対応できます。
コレクションの中に希少な品がある場合は、専門家に鑑定を依頼するのもおすすめです。推し活アイテムは、そのまま残すのではなく、事前に整理や情報共有をしてください。これによって、家族が困ることなく、ご自身の大切なコレクションや思いを受け継いでもらえるのです。
ご自身でグッズの保管・処分方針を決めておく

推し活グッズの管理や整理については、保管方法や処分の方針を決めておきましょう。ご自身の思いだけでなく、家族の負担を減らす上で欠かせません。
コレクションを良い状態で保つには、直射日光や湿気を避けてください。定期的にホコリを取り除いて、汚れがあれば、綺麗にして保管しましょう。手放す基準をご自身で設けることで、整理がしやすくなります。今はもう興味が薄れたものなど、基準を明確にすれば、迷わず処分できるかもしれません。
グッズを処分する際は、自治体の回収や不用品回収業者の利用、フリマアプリやオークションでの販売を検討しましょう。知人への譲渡や、専門店への買取依頼など、様々な方法があります。価値のあるものは、専門業者などの有識者に相談してください。適正な価格で手放せる可能性があります。
このように、推しグッズの保管や整理・処分の方針を事前に決めることで、大切なコレクションを良い状態で維持できます。また、販売や譲渡を検討することによって、思い入れのあるグッズを処分とは異なる形で継承できるのです。
| 項目 | おすすめ方法・ポイント | 備考・注意点 |
| 保管方法 | ・クリアケースや収納ボックスで分類 ・防湿剤やシリカゲルを利用 ・UVカットカバーで色あせ防止 | 直射日光・湿気を避ける |
| メンテナンス | ・定期的にホコリ取りや汚れ落とし ・点検リストや写真で記録 | 定期的な見直しが大切 |
| 手放す基準 | ・「1年以上使っていない」など、自分ルールを設定 | 明確な基準を設けると、整理しやすい |
| 処分・譲渡方法 | ・自治体の回収・不用品回収業者 ・フリマアプリやオークションで販売 ・知人やファン仲間へ譲渡 ・専門店で買取 | 価値があるものは、専門業者に相談 |
| 家族への配慮 | ・整理や保管状況を記録 ・定期的に見直し・整理 | 家族の負担を減らすためにも、記録が有効 |
| その他のポイント | ・コレクションの写真を残す ・寄付やチャリティも選択肢 | 思い出を形として残すこともできる |
エンディングノートや遺言書の活用法
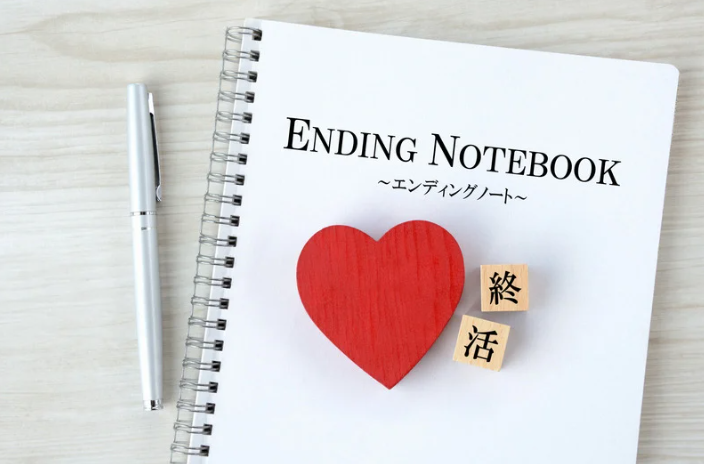
推し活で集めたコレクションを、家族や大切な人に引き継ぎたい場合、エンディングノートや遺言書を活用しましょう。エンディングノートは、形式にとらわれず、ご自身の思いや希望を書き残せるノートです。例えば、「このグッズはあの人に譲りたい」「特に思い入れのあるアイテムはこれ」など、具体的な指示が残せます。

また、グッズのリスト、保管場所、コレクションへの想いなどを、自由に記載できます。写真を添えることで、家族がアイテムを特定しやすくなるかもしれません。ネット上のアカウントや、デジタルコンテンツについても、エンディングノートが活躍するでしょう。利用しているサービス名や管理方法を書き残すことによって、家族の負担が大きく減少します。
一方で、遺言書は法的な効力を持ちます。推し活グッズの中で、大切な品や資産価値の高いコレクションを「誰に譲るか」など、希望を確実に実現したい場合に有効です。遺言書に明記することで、家族間のトラブル防止や、スムーズな相続手続きにつながります。
このように、自分の気持ちや希望を伝える場合には、エンディングノートが使いやすいです。法的な意思表示をしたい場合には、遺言書が有効になります。事前に意思を残しておくことで、推し活の成果や大切なコレクションを次世代に託せるのです。生前から家族とコミュニケーションを重ねて、グッズの価値や思い入れを共有することも、円滑な承継のためには大切です。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
| 目的・特徴 | ・形式が自由で、思いや希望を気軽に記載できる ・家族へのメッセージや希望の伝達に最適 | ・法的効力があり、財産やコレクションの分配を確実に実現できる |
| 記載の内容 | ・譲りたいグッズや思い入れのある品の指定 ・コレクションリストや保管場所、想い ・写真添付も可 | ・推し活グッズや価値あるコレクションの譲渡先を明記 ・相続トラブル防止に有効 |
| デジタル資産の対応 | ・ネットアカウントやデジタルコンテンツの管理方法も、記載が可能 | ・デジタル資産も対象にできるが、明記が必要になる |
| 法的効力 | なし(希望や思いの伝達が主目的) | あり(法的に効力を持つ) |
| 作成・修正のしやすさ | ・自由に何度でも書き直しが可能 ・市販ノートや自作、アプリも利用できる | ・自筆証書遺言、公正証書遺言など形式に要件がある ・内容変更には、手続きが必要 |
| 保管方法 | ・家族が分かる安全な場所に保管して、場所を共有することが重要 | ・自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要 ・公正証書遺言は、公証役場で安全に保管される |
| 家族へのメリット | ・希望や想いが伝わりやすく、家族の負担が軽減される | ・相続手続きがスムーズで、トラブル防止につながる |
| 注意点 | ・法的効力はないため、財産分配の希望は、遺言書との併用が望ましい | ・形式不備だと無効になる場合があるため、専門家の確認が安心 |
「ご自身らしい最期」を演出する一歩として

ご自身らしい最期を実現するためには、単なる資産整理や相続対策にとどまりません。個人の価値観や、ライフスタイルを「どのように反映させるか」という視点が重要です。近年では、「推し活」などのパーソナルな趣味・関心領域も財産とみなされるケースがあります。
円滑な相続を実現するには、早めの計画と情報共有が不可欠でしょう。「思い」や「意志」を含めた、総合的なエンディング・プランニングこそが、今後の終活の形なのかもしれません。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼