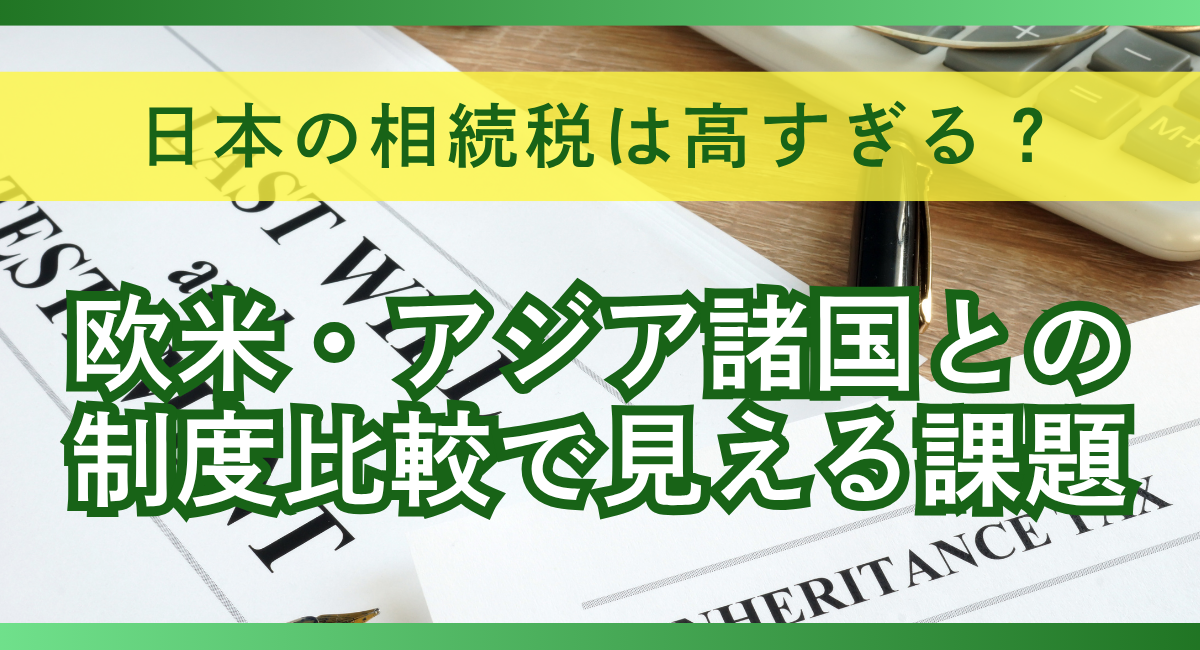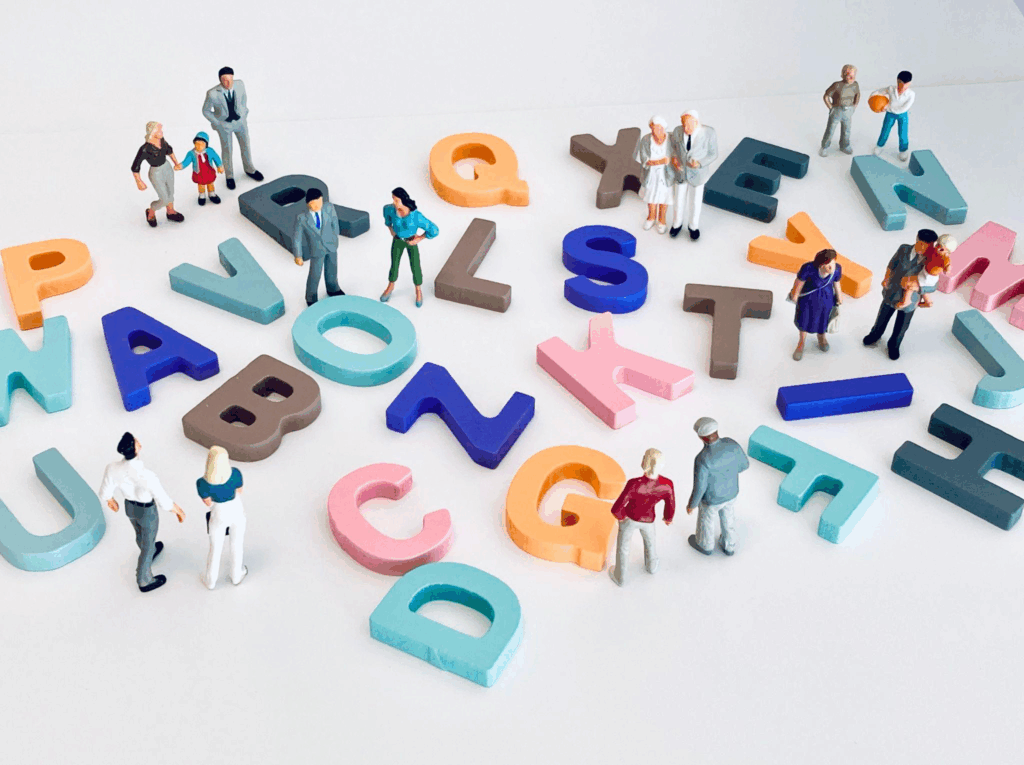
都市部の不動産価格の上昇や高齢化によって、一般家庭でも、相続の課税対象になる事例が増えています。その結果「日本の相続税制度は過剰ではないか」などの議論が活発になっています。欧米諸国やアジアの近隣国と比較すると、相続税の最高税率や基礎控除の水準などに、大きな違いがあるのです。
相続税自体を廃止した国もあれば、非常に高い課税基準を設けて、富裕層のみに課税する国もあります。今回の記事では、日本の相続税を国際的な制度と比較しながら、その特徴と課題を解説します。
なぜ「相続税の国際比較」が注目されるのか

近年、「相続税」制度の議論が国内外で活発化しています。特に日本では、高齢社会の進行とともに、相続の件数が増加しているのです。団塊の世代が後期高齢者となったことで、今後10年ほどの間に「大相続時代」が到来すると言われています。相続が発生する件数も、大幅に増加する見込みです。
このような背景から、相続税の仕組みや節税対策に関する情報へのニーズが高まっています。SNSやメディアでも、相続税に関する議論が活発に行われるようになりました。かつては「相続税は富裕層だけの問題」でした。しかし、現在では一般家庭でも、相続税の申告や納税が必要となるケースが増えているのです。
そのような状況で注目されるのが「相続税の国際比較」になります。世界各国で相続税の仕組みや税率は、大きく異なります。日本の制度が「重い」のか「妥当」なのかを、見極めるための重要な視点になるかもしれません。国ごとの考え方や背景を読み解くことで、日本の相続税の位置づけや今後の課題がより明確になるでしょう。
「日本の相続税は高すぎる」という声の背景
日本の相続税に対して「高すぎる」という声が多く聞かれるのは、様々な理由が重なっているためです。日本の相続税の最高税率は55%で、世界でも非常に高い水準です。アメリカやイギリス、ドイツなどの先進国と比べても突出しています。
また、2015年に行われた税制改正で、基礎控除額が大きく引き下げられました。これによって、相続税とは無縁だった一般家庭にも、課税されるケースが増えたのです。特に都市部では地価の上昇もあり、高額な相続税が発生することも珍しくありません。
さらに、日本の相続税は、累進課税方式が採用されています。相続する財産が多いほど、税率が上昇するのです。そのため、遺産が多い家庭ほど、納税額が大きくなり、負担感が強まります。
「所得税や住民税を納めた後の財産にも、相続税がかかるのは納得できない」など、不満の声が広がっています。そのため、相続税の高さや制度の見直しを求める意見が目立つようになりました。相続税が「高すぎる」と感じる背景には、累進課税の厳しさや制度への不信感などが、複雑に絡み合っているのです。
グローバルでの視点が必要な理由
社会や経済のグローバル化が進む中で、相続についても国際的な視点が欠かせません。従来は、財産や相続人が日本国内に限られていました。しかし、現在では海外に資産を持つ人や、他国に家族がいるケースが増加しています。その結果、国ごとに異なる法律や税制、文化的な慣習が相続に影響し始めました。
例えば、遺言による財産分配の自由度などは、国によって異なります。相続税率や課税対象となる財産の範囲も、各国で大きな差があるのです。同じ財産に対して、複数の国で課税される「二重課税」などの問題も生じています。
資産の管理や移転が国境を越えることで、より複雑な相続対応が求められます。このような状況から、国内だけでなく、海外の税制や慣習も踏まえる必要があります。グローバルな視点で対策を考えることが、円滑な資産承継やトラブルの防止につながるのです。
日本の相続税制度の全体像

日本の高齢化が進む中、相続をめぐるトラブルや課税への関心が年々高まっています。2015年の税制改正以降、相続税の課税対象となる家庭が増えました。「自分にも関係があるのでは?」と不安を感じる方も多いです。相続税制の基本的な仕組みを知ることで、将来の相続に備えることができます。ここでは、日本の相続税制度の全体像について、分かりやすく解説します。
課税対象になる財産の範囲
相続税の課税対象は、被相続人が亡くなった時点で所有していた資産です。例えば、現金や預金、株式などの金融資産、不動産、自動車、著作権などが挙げられます。家庭内の家具や美術品、事業に関する資産も対象です。
また、死亡保険金や死亡退職金も、相続税の計算上「みなし相続財産」として扱われます。これらは、被相続人が保険料を支払っていた生命保険や、勤務先から支給される退職金などが該当します。相続が始まる前の3年以内に、被相続人から贈与された財産は、相続税の課税対象に含まれる点に注意してください。相続時精算課税制度を利用して、贈与された財産も同様です。
一方で、仏壇などの祭祀財産や、死亡保険金・退職金の非課税枠、遺族年金などは、相続税の対象外になります。
このように、相続税がかかる財産の範囲は非常に幅広いのです。基本的には、経済的価値のあるものは、ほぼすべて対象になります。相続の際には、どの財産が課税対象になるのかを、事前に確認することが大切です。
| 区分 | 内容・例 | 課税対象 | 備考 |
| 現金・預貯金 | 現金、銀行預金、郵便貯金 | 〇 | |
| 有価証券 | 株式、債券、投資信託など | 〇 | |
| 不動産 | 土地、建物、マンション、貸地、農地など | 〇 | |
| 動産 | 自動車、貴金属、宝石、骨董品、美術品、家具など | 〇 | 骨董的価値が高い仏具等は、課税対象 |
| 事業用資産 | 機械設備、商品在庫、売掛金、貸付金など | 〇 | |
| 会員権 | ゴルフ会員権など | 〇 | |
| 権利 | 著作権、特許権、商標権など | 〇 | |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金 | 〇 | 非課税枠(500万円×法定相続人)あり |
| 生前贈与財産 | 相続開始前3年以内の贈与、相続時精算課税の贈与 | 〇 | |
| 祭祀財産 | 墓地、墓石、仏壇、仏具など | × | 骨董的価値が高い場合は、課税対象 |
| 死亡保険金・退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人まで | × | 超過分は課税対象 |
| 遺族年金 | 遺族基礎年金、遺族厚生年金など | × | |
| 公益目的の財産 | 公益事業用の財産、条例による給付金受給権など | × |
基礎控除と税率(超過累進課税)
相続税には、「基礎控除」と呼ばれる一定額の非課税枠が設けられています。この基礎控除は「3,000万円に法定相続人の人数×600万円を加えた金額」です。相続人の数が多いほど、控除額も大きくなります。例えば、相続人が2人の場合は「3,000万円+1,200万円=4,200万円」が基礎控除額です。この金額までは相続税が発生しません。
遺産の総額が基礎控除を超える場合、その超過分に対しては、相続税が課せられます。相続税の税率は「超過累進課税方式」で、課税される金額が高くなるほど、税率も高くなるのです。例えば、課税対象額が1,000万円以下の場合、税率は10%です。金額が増えるごとに15%、20%、30%と段階的に税率が上がり、最高で55%まで適用されます。
このように、相続税は基礎控除によって一定額まで非課税になります。それを超えた部分については、金額に応じて高い税率が適用される仕組みです。そのため、遺産の規模や相続人の人数によって、負担する相続税額が大きく変わります。
| ケース | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 配偶者と子ども2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者と親1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者と兄弟姉妹3人 | 4人 | 5,400万円 |
申告・納税の流れと義務
相続税の申告と納税には、明確な手続きと期限が定められています。被相続人が亡くなった後、相続人は遺産の内容や相続人の範囲を調査する必要があります。そして、課税対象になる財産が、基礎控除額を超えるかを調べます。基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税の準備を進めなければなりません。
申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。この期間内に、相続人は遺産分割協議や必要書類の準備を行います。相続税申告書を作成して、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書の提出は、郵送やe-Tax(電子申告)を利用することも可能です。
相続税の納付は、原則として、現金一括払いである点に注意してください。申告書の提出と同時に行う必要があります。納付は、税務署や金融機関、場合によってはコンビニやクレジットカードでも可能です。
| 項目 | 内容 |
| 期限 | 死亡を知った翌日から10ヵ月以内 |
| 提出先 | 被相続人の住所地の税務署 |
| 提出方法 | 窓口・郵送・e-Tax |
| 納税方法 | 原則現金一括(税務署・金融機関・コンビニ・クレカなど) |
| 注意点 | 期限遅れは加算税・延滞税の可能性あり |
主要国の相続税の制度について
相続税制度は、世界各国で大きく異なります。日本では、相続人が受け取る財産の金額に応じて、10%から55%までの累進課税が適用されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
アメリカの場合は「遺産税(Estate Tax)」が導入されています。税率は18%から40%です。しかし、基礎控除額が約1,361万ドル(約20億円)と非常に高いため、課税対象になるのは主に富裕層です。配偶者への相続は非課税になります。州によっては、独自の相続税が設けられている場合もあります。
※2025年末に期限を迎え、2026年以降は約600万ドル台に戻る見通し
イギリスでは、相続税率は一律40%です。基礎控除額は32万5,000ポンド(約6,240万円)になります。住宅を直系の子孫が相続する場合は、さらに控除額が加算される特例があるのです。配偶者への相続は非課税になります。
フランスは「遺産取得課税方式」を採用しています。税率は5%から45%までの累進課税です。基礎控除額は子ども1人あたり10万ユーロ(約1,500万円)で、配偶者が相続する場合は非課税になります。また、生前贈与が相続税の課税対象に含まれる期間が、15年と長いのが特徴です。
※「贈与税の非課税枠は15年ごとにリセットされる仕組みであり、相続税の加算期間とは異なる
ドイツもフランスと同じく「遺産取得課税方式」になります。税率は7%から30%(場合によっては最高50%)です。配偶者には50万ユーロ(約8,100万円)、子どもには40万ユーロ(約6,500万円)の基礎控除が認められています。さらに、配偶者には、特別な非課税枠も設けられています。
カナダやオーストラリア、スウェーデン、シンガポールなどでは、相続税自体が存在しないのです。つまり、相続に対する税負担がありません。このように、各国の相続税制度によって、税率や控除額、課税の仕組みなどに大きな違いがあります。
※カナダには相続税はありませんが、みなし譲渡としてキャピタルゲイン課税されるケースがあります。また、一部の国では相続税の復活を検討している動きもあります。
なぜ日本の相続税は高く感じるのか?
日本の相続税が高く感じる理由として、制度の特徴が影響しています。まず、相続税の最高税率が55%と非常に高く、世界的に見てもトップクラスです。遺産の額が大きくなるほど、税率が上がります。
基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と、低く設定されている点も大きな要因です。欧米諸国では、基礎控除額が数億円から十数億円と高額に設定されています。そのため、相続税が課されるのは、ごく一部の富裕層に限られます。日本の場合は、一般家庭でも課税対象になるケースが多いのです。
また、日本の相続税は、各相続人が受け取る財産額に応じて、超過累進課税が適用されます。これにより、個々の税負担が重くなりやすく、全体として「相続税が高い」という印象につながっています。これらの制度設計に加えて、高齢世帯への資産集中などが重なり、多くの人が日本の相続税を「高い」と感じているのです。
中間層にも課税されやすい仕組み
日本の相続税制度は、中間層にも課税が及びやすい構造です。これは、2015年の法改正によって、基礎控除額が引き下げられたことが要因になります。以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が基礎控除でした。しかし、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に減額されたことで、相続税の対象となる家庭が大幅に増えたのです。
特に都市部では、土地や住宅の評価額が高いです。現金や金融資産がそれほど多くなくても、相続税の課税対象になるケースがあります。そのため、相続税は一部の富裕層だけでなく、幅広い層にとっても無視できない税金になります。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 影響 |
| 基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×人数 | 3,000万円+600万円×人数 | 控除額が大幅減少 |
| 課税割合 | 約4% | 約10% | 課税対象が倍増 |
| 対象層 | 主に富裕層 | 中間層にも拡大 | 一般家庭も課税対象に |
海外に比べて「非課税枠が少ない」「節税策が限られている」
日本の相続税は、海外と比べて「非課税枠」が非常に小さいのが特徴です。先述の通り、日本では相続財産が「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えると、相続税が発生します。アメリカでは、約20億円まで税金が掛かりません。海外では、本当に資産が多い人のみが相続税の対象になります。
また、日本では生前贈与などを活用した節税策も限られています。非課税で贈与できるのは、年間110万円までの範囲です。海外では、さらに大きな金額を非課税で贈与できます。様々な控除や特例が、用意されている国もあるのです。
これからの制度改正と国際的な動向
日本の相続税制度は、今後の社会状況や国際的な動向を踏まえて、さらに変化するかもしれません。近年は、資産の世代間移転や、格差是正の必要性が強調されています。相続税と贈与税の制度を、より連携させる方向で議論が進んでいるのです。
例えば、2024年から相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が導入されました。生前贈与と相続の枠組みがより柔軟になったのです。また、結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税措置の延長など、若い世代への資産移転を後押しする特例も継続されています。
一方で、相続税の基礎控除や税率は、以前の大幅な見直し以降、現状維持が続いています。そのため、都市部を中心に中間層にも相続税の負担が広がっているのです。アメリカやイギリスなどの多くの国では、非課税枠が大きいです。OECDなどの国際機関を中心に、課税ルールの国際的な調和などが進んでいます。
相続税の国際的なトレンド
近年、世界の相続税制度は、大きな変化を迎えています。多くの国では、相続税の「廃止」や「縮小」が進んでいるのです。スウェーデンやノルウェー、オーストリア、香港、シンガポールなどは、すでに相続税を撤廃しています。カナダやオーストラリアなども、相続税が存在しません。
一方で、イギリスやフランス、ドイツ、アメリカなどでは、相続税や遺産税が引き続き、維持されています。格差是正や財政健全化を目的に、課税強化の議論も行われています。しかし、このような国々では、非課税枠が大きく設定されています。相続税の負担は、富裕層に限られているのです。
今後も、各国の経済状況や社会のニーズに応じて、相続税の制度は見直されるでしょう。世界の相続税は「廃止や縮小を進める国」と「維持・強化する国」に分かれる傾向があります。そのような状況の中で、日本は依然として、高い税率と広い課税範囲を持っています。
日本でも議論される「生前課税強化」や「資産課税」の可能性
日本において「生前課税強化」や「資産課税」の導入が重要なテーマです。2024年の法改正で、生前贈与が相続税の課税対象になる期間が変更されました。「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」へと延長されたのです。これによって、相続税を回避するための生前贈与が難しくなり、実質的な課税強化につながりました。
また、金融資産や不動産などの、保有資産に課税する「資産課税」などが検討されています。国際的にもOECDやG20を中心に、富裕層への資産課税やグローバルな最低税率の導入が議論されています。資産格差の是正や税収確保のために、課税強化の流れが強まっています。日本でも財政健全化を目的とした新たな税制導入が、大きな課題になるかもしれません。
グローバルな資産防衛と節税の方向性
近年は、各国で税制が強化されて、国際的な情報共有が進んでいます。そのような状況において、グローバルな資産防衛も重要になります。単純に税率の低い国へ資産を移すだけでは、十分な対策になりません。資産を守るためには、複数の資産クラスや、地域に分散投資することが基本です。株式や債券、不動産、金などに分散することで、為替変動やインフレリスクに備えられます。
AIを活用した資産管理方法や、金融商品への投資など、資産運用の様々な手法が広がっているのです。資産防衛と節税対策には、分散投資、国際税制への対応が欠かせません。各国の税制改正や国際的な規制強化の動向を注視しながら、資産戦略を見直すことが節税対策につながります。
| 項目 | 内容 |
| 国際的な税制強化 | 各国の税制強化・情報共有の進展により、単純な資産移転だけでは、資産防衛・節税が困難に |
| 主要な国際的動向 | OECD主導のBEPSプロジェクト、グローバル・ミニマム課税(最低15%課税)など |
| 分散投資の重要性 | 株式・債券・不動産・金など複数資産や、国内外・先進国・新興国への地域分散で、リスクを低減 |
| インフレ・為替対策 | 不動産や金など、インフレ耐性資産の組み入れ、為替リスクの分散 |
| AI活用による資産運用 | AIやロボアドバイザーによるデータ分析、投資戦略提案、自動リバランス等が一般化 |
| 日本の税制改正の動向 | グローバル・ミニマム課税の導入、外国子会社合算税制の見直しなど、2025年度以降も規制強化が進行 |
| 資産戦略の見直し | 各国の税制・規制強化の動向を注視して、柔軟に資産戦略を見直すことが節税・資産防衛のカギ |
| 総合的な資産防衛戦略 | 分散投資、AI活用、国際税制対応などを組み合わせて、変化に柔軟に対応することが不可欠 |
まとめ:相続税の「重さ」は数字だけでは測れない
相続税の「重さ」は、単に税率や基礎控除額などの数字だけでは判断できません。日本の相続税は最高税率が高く、非課税枠も小さいため、数字上は「重い」と感じられます。しかし、実際の負担感はそれだけで決まりません。様々な要素が複雑に絡み合っています。
都市部では、不動産の評価額が高く、現金化しにくい資産にも相続税が掛かります。そのため、納税資金の確保が大きな負担になるのです。また、中間層にも課税されやすい制度設計や、相続税の計算の複雑さも、心理的な面で不安感を強めます。
国際的な視点において、一部の富裕層のみに相続税が課される国が多いです。しかし、日本では一般家庭や中間層まで、広く課税対象になっていることが「重さ」を感じる原因です。制度への納得感や公平感の違いに関しても、負担感に影響を与えているかもしれません。
相続税の「重さ」は、数字だけでは測れないのです。制度の仕組みや社会的背景、個々の状況や価値観によっても、大きく左右されます。そのため、相続税を考える際には、実際の生活や社会に与える影響、人々の実感にも目を向けることが大切です。
単純な税率比較では見えない制度の複雑さ
相続税制度は、表面上の税率や基礎控除額だけを見ても、本当の複雑さや負担感は分かりません。日本の相続税は、遺産総額から債務や非課税財産を差し引きます。そして「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除を引いて、課税遺産総額を算出します。
その後、課税遺産総額を法定相続分で分けるのです。それぞれに累進税率をかけて、税額を計算します。最終的には、実際の分割割合に応じて、各相続人の納税額を決める流れになります。このように、複数のステップを踏む必要があるのです。この過程で、相続人の人数や分割方法で税負担が大きく変わるため、単純な「相続額×税率」では収まりません。
さらに、配偶者控除や小規模宅地の特例、未成年者控除など、多くの特例があります。それぞれに細かい条件や計算方法が設定されています。生前贈与が相続開始前7年以内であれば、課税対象に加算されるなど、贈与税との関係も絡み合うのです。
このように、日本の相続税は、計算方法や特例の適用が複雑です。数字だけでは見えない「分かりにくさ」や「手続きの煩雑さ」が大きな負担になります。そのため、表面的な税率比較だけでは、実際の制度の重さや納税者の感じる負担感を正確に把握できないのです。
| 手順 | 制度の詳細 |
| 1. 遺産総額の算出 | 財産から債務・非課税財産を差し引く |
| 2. 基礎控除の適用 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数を控除 |
| 3. 課税遺産総額の計算 | 上記控除後の金額を算出 |
| 4. 法定相続分で按分 | 課税遺産総額を法定相続分で分ける |
| 5. 累進税率を適用 | 各人の按分額に10~55%の税率をかける |
| 6. 実際の分割割合で再分配 | 実際の取得割合に応じて納税額を決定 |
| 7. 特例・控除の適用 | 配偶者控除、小規模宅地特例などを適用 |
| 8. 生前贈与の加算 | 7年以内の贈与財産を加算 |
「公平」と「格差是正」の視点で制度を見直す必要
相続税制度は「公平さ」と「格差の是正」の観点から、今後も見直しが求められています。相続税や贈与税は、本来、資産が一部の家系に集中し続けることを防ぐためです。社会全体の格差拡大を抑える役割を担っています。
仮に相続税がなければ、資産を持つ家庭が何世代にもわたって、富を引き継ぐかもしれません。つまり、経済的な格差が固定化する恐れがあるのです。政府も、このような背景を認識しており、格差是正のための制度改革が議論されています。
現行の制度には、多くの特例や控除があります。しかし、全ての相続人にとって、平等とは言い切れません。事業承継や配偶者の特別な優遇措置などが、制度の複雑さや不公平感につながることもあります。相続税の制度は、時代の変化や社会のニーズに合わせて、柔軟に制度を見直すことも不可欠なのです。
相続税対策は日本と外国の制度理解がカギ
相続税対策を行う上で、日本国内だけでなく、海外の相続税や法律についても理解しておきましょう。グローバル化が進み、海外に資産を持つ人なども増えています。どの国でどのように課税が行われるかを、把握しなければなりません。思いがけない税負担や、トラブルに直面する可能性があります。
日本では、相続人が国内に住所を持つ場合、海外の財産も含めて全てが課税対象です。しかし、相続人や被相続人が海外に住む場合は異なるのです。課税の範囲や適用される法律が変わります。
同じ財産に対して、日本と現地で「二重課税」が発生することもあります。各国の税制や、二重課税防止条約の内容を確認しておきましょう。相続税対策には、日本と海外の制度や税制の違いを理解してください。制度の改正や国際的な視点で、総合的に相続計画を立てることが重要です。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼