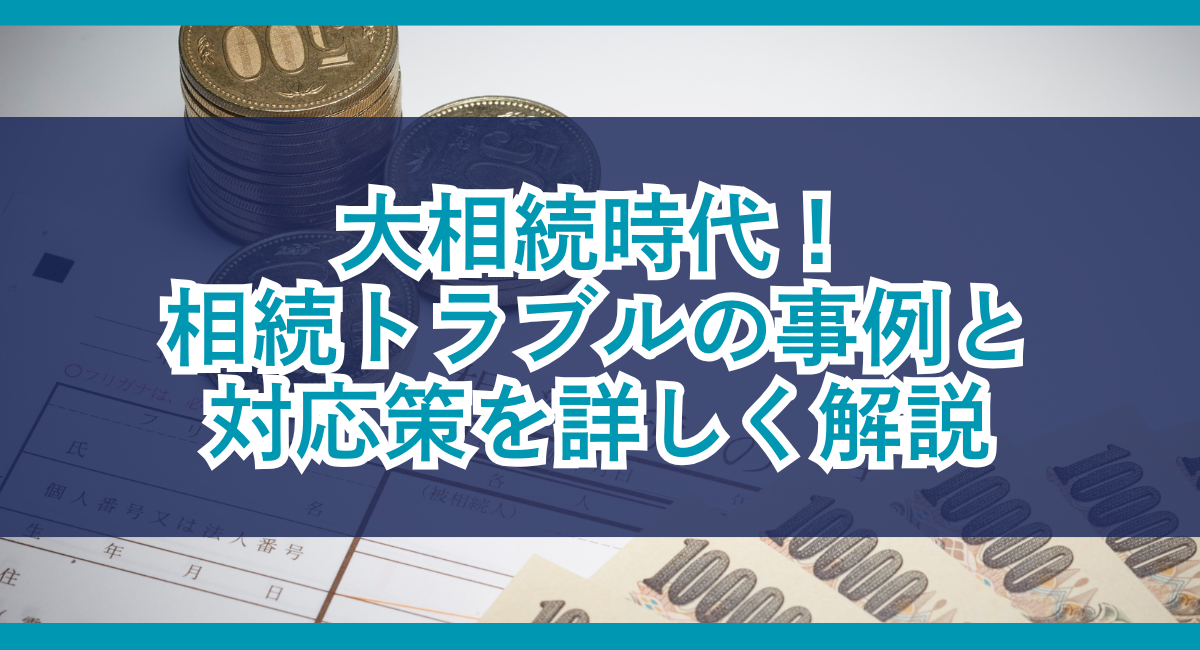2025年以降の大相続時代においては、少子高齢化をきっかけとした相続トラブルが増加すると考えられます。遺言書や遺贈などの対応策で生前からの対策を進めることが大切です。
「大相続時代」とは現在の日本が直面している、相続に関するさまざまな課題やトラブルが多発する時代を指します。これは主に、少子高齢化の進行によって引き起こされており、2025年以降は団塊世代の高齢化によりさらに相続トラブルは増加するおそれがあります。
そこで、本記事では大相続時代を迎える今、知っておきたい相続トラブルの事例と対応策をわかりやすく解説します。
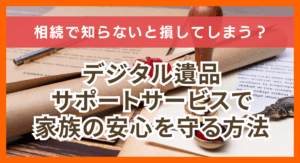
大相続時代とは?少子高齢化が招く相続トラブル7例
子どもが多かった団塊世代が75歳以上(後期高齢者)となる2025年以降は、多くの相続が発生していくことによりトラブルも増加すると考えられています。
また、先進国でも急速に少子化が進行している日本ならではの問題も山積みです。そこで、本記事では少子高齢化が招く相続トラブルについて7例をご紹介します。
1.事業承継ができない

少子高齢化により、相続時に中小企業の後継者がいないというトラブルが発生しています。事業の後継者がいないことにより、事業を畳む・会社や故人の借入を整理する必要があるなど、相続時に大変な労力が必要となるケースも少なくありません。
生前からM&A(合併・買収)なども視野に入れつつ、事業の存続方法を模索する必要があります。しかし、事業の実態や財務状況を把握ができないまま社長が亡くなるケースもあります。
2.祭祀財産を承継する人がいない
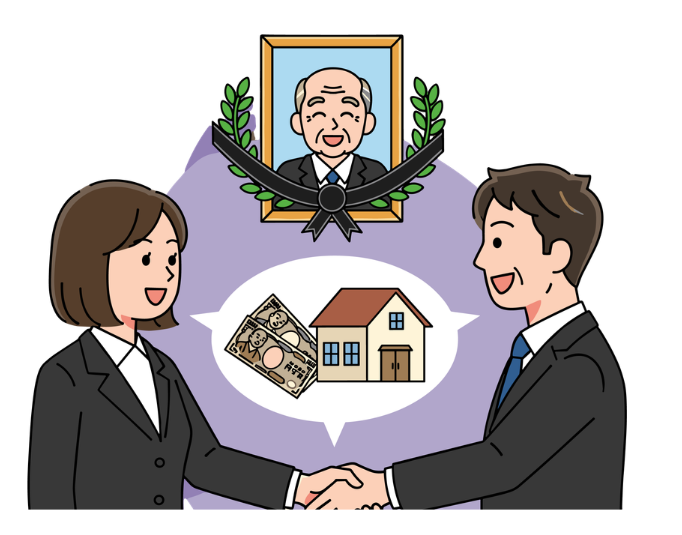
お墓や仏壇などは「祭祀財産」と呼び、預貯金や不動産などの相続財産には含みません。祭祀財産の管理は労力だけではなく、管理のための費用を要することも多く、相続でこれまで管理していた方が亡くなったことをきっかけに、管理・承継する人がいなくなり、放置されるトラブルも発生しています。
※祭祀財産は民法上、一般の相続財産とは別に取り扱われ、特定の者に承継される性質があります。
都市部への人口集中や核家族化が進む中で、地方に残された先祖代々の墓を守る労力は増しており、遠方に住む親族が管理を引き受けることになっても、結果的に墓じまい(墓の撤去)を選択する人も少なくありません。
しかし、墓じまいには寺院側や親族の同意が必要となることが多く、意見の対立が生じることもあります。
3.相続人も高齢化している

現在の日本では被相続人の財産を相続する相続人も高齢になっているため、相続手続きを進めるのが困難になったり、判断能力の低下からトラブルに発展したりするケースも見受けられます。
例として相続人が70代・80代といった場合、書類の取り寄せや準備手続きに時間がかかったり、金融機関とのやり取りに戸惑ったりすることがあります。
4.相続が相次ぐ
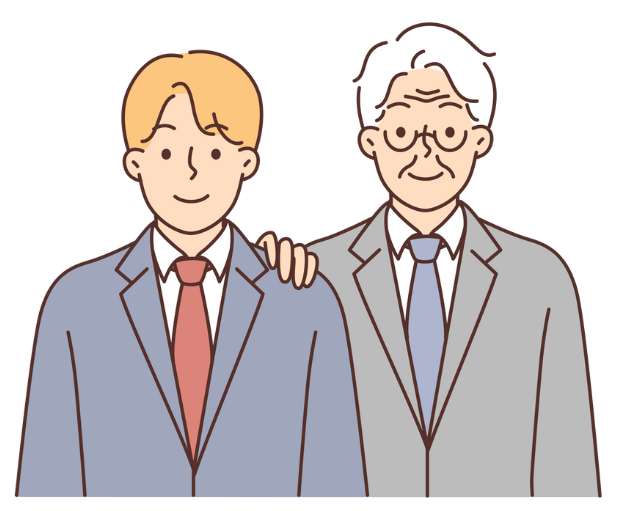
親や祖父母の相続の後、間もなくその相続人も亡くなり、立て続けに相続が発生することがあります。これを「数次相続」や「相次相続」と呼びます。
- 数次相続…遺産分割協議中に相続人が亡くなってしまい、次の相続が起きること
- 相次相続…相続完了後から10年以内に、次の相続が発生すること ※相続税負担を軽減する控除が適用されることもあります。
例えば、父親が亡くなり、その数年後に母親が亡くなるような場合です。このようなケースでは相続税の納付が続きやすく、相続人に重い負担がのしかかります。
5.認知症の相続人がいる可能性が増える

高齢化が進んでいると、相続人の中に認知症を患っている方がいる可能性が高まります。
認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議がスムーズに進まないなどの問題が生じます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、認知症により認知能力が不十分な場合、その合意が無効となる可能性があります。この場合、成年後見制度の利用を検討する必要があり、家庭裁判所への申立てが必要になるため、相続手続きが長期化するトラブルも発生しています。相続手続きが長期化する可能性もあるため、早めの対策が重要です。
6.相続人がいないケースが増える

少子化や未婚化の進行により、法定相続人が一人もいないケースの相続もあります。法定相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。
もしもご自身の財産を大切な知人や友人・団体などへ遺贈したい場合は、あらかじめ遺言書を用意するなどの注意が必要です。
7.財産の相続手続きに戸惑う

実家や空き家など住む予定のない不動産や、活用方法のない動産類など、相続したものの管理や処分に困る「負動産」が増え、その整理に手間取ることがあります。
特に地方の不動産は、需要が少なく買い手が見つかりにくい上、固定資産税などの維持費だけがかかる「負の遺産」となりがちです。
また、デバイスの処分に困るケースも多く、情報のリセットやデジタル資産の承継に戸惑うケースも少なくありません。特にデバイス周辺の資産は進化が著しく、価値があるもの・処分していいものの境目がわかりにくいというデメリットもあります。
関連記事:投資の遺産相続はどうする?NISA・iDeCo・FX・仮想通貨の相続方法を解説
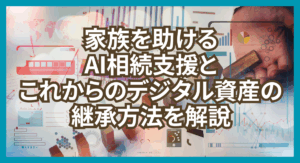
相続手続きをトラブルなく乗り越えるには?
大相続時代において、トラブルなく相続を乗り越えるためには、事前の準備と対策が非常に大切です。トラブルに発展すると弁護士等の専門家の力が必要となり、裁判所での手続きに時間を要する事態に発展しかねません。そこで、この章では相続手続きの乗り越え方を解説します。
遺言書を作成する

自身の財産に関する意思を明確に伝えるため、そして相続人間の不要な争いを避けるために、遺言書を作成することがおすすめです。
遺言書があれば、誰にどの財産をどれだけ残したいかを具体的に指定できます。また、遺産分割協議の必要がなくなるため、相続トラブルが起こりにくくなります。
特に、特定の相続人に多く財産を渡したい場合や、相続人以外の人に財産を遺したい場合には欠かせない手法であり、内縁の配偶者や同性パートナーへの財産も遺言書なら可能です。
家族で相続対策を開始する

相続が発生する前に、家族で相続や財産について話し合い、共通の認識を持つことが大切です。特に特定の相続人に財産が集中し、高額の納税が予定される場合は税理士に相談しながら相続対策を進めましょう。納税資金の準備も行っておくことが望ましいでしょう。
また、複雑な事業承継や相続人間の財産トラブルが予想される場合は弁護士を交え、遺言書対策などを進めておくことがおすすめです。
生前贈与や家族信託といった節税対策を検討できます。また、家族間で財産状況を共有することで、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。
不要な財産は早めの整理・処分を開始する

相続人にとって負担となる可能性のある不要な不動産や動産は、生前のうちに整理・処分を進めることを検討しましょう。これにより、相続発生後の手続きを簡略化できます。具体的には、住む予定のない実家や空き家の売却・解体、価値のない動産の処分などが挙げられます。
また、デバイス内に多くのデジタル資産がある場合、不要なものは処分しておくことがおすすめです。また、スマホには個人情報が集約されています。生体認証・PIN等により、相続人であっても開くことが難しいため、万が一高額の資産が眠っている場合は、遺言書やエンディングノートの活用で、確実に承継できるように準備しておくことが望ましいでしょう。

遺贈寄付を検討する

相続人がいない場合や、特定の財産を社会貢献に役立てたいと考えている場合は、遺贈寄付を検討するのも一つの方法です。遺贈寄付とは、遺言によって自身の財産を特定の団体や法人に寄付することです。
自身の最後の遺志を社会貢献という形で実現できるだけでなく、故郷への恩返しや、長年応援してきた団体への支援なども可能です。遺贈に関しては以下の関連記事もご一読ください。
関連記事:新しい社会貢献のかたち・遺贈寄付で失敗しないための注意点
まとめ
大相続時代は少子高齢化によって引き起こされる、さまざまな相続問題が顕在化してくる時代です。
事業承継の困難さや祭祀財産の承継問題、相続人自身の高齢化などのトラブルが予想されますが、これらのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続を実現する対策法もありますので、ぜひご活用ください。
デジタル資産をはじめ、相続に関して不安な点や具体的な相談があれば、相続前からでも専門家へ早めに相談しましょう。
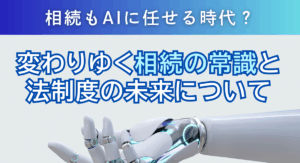
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼