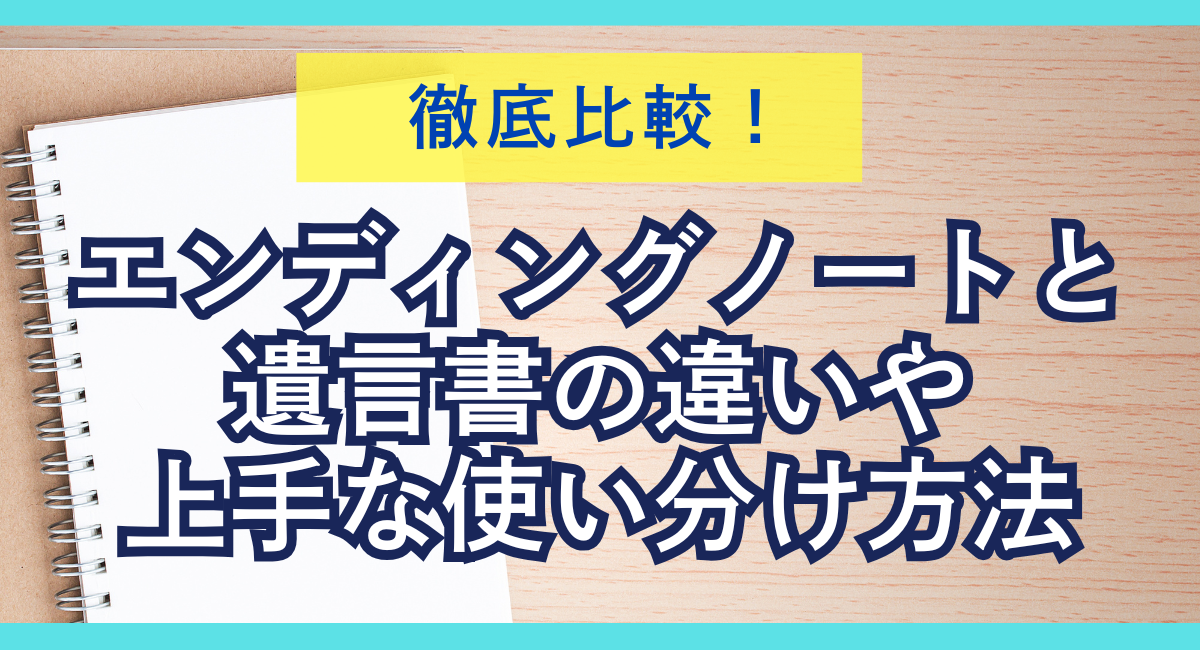終活が人気となり、近年はさまざまな終活グッズや解説本が出回るようになりました。
以前に比べると手軽に相続や遺言について知ることができるようになったことで、早い段階から自分の生前整理を始める人が増えています。
そうした中で、これからエンディングノートや遺言書に取り組んでみようと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、この2つを始めるときにはお互いについてしっかりと理解していなければ、書いた内容が無駄になってしまう可能性もあります。
今回はエンディングノートと遺言書の違いについて、上手な使い分けも併せて解説していきます。
目的の違いを理解しよう
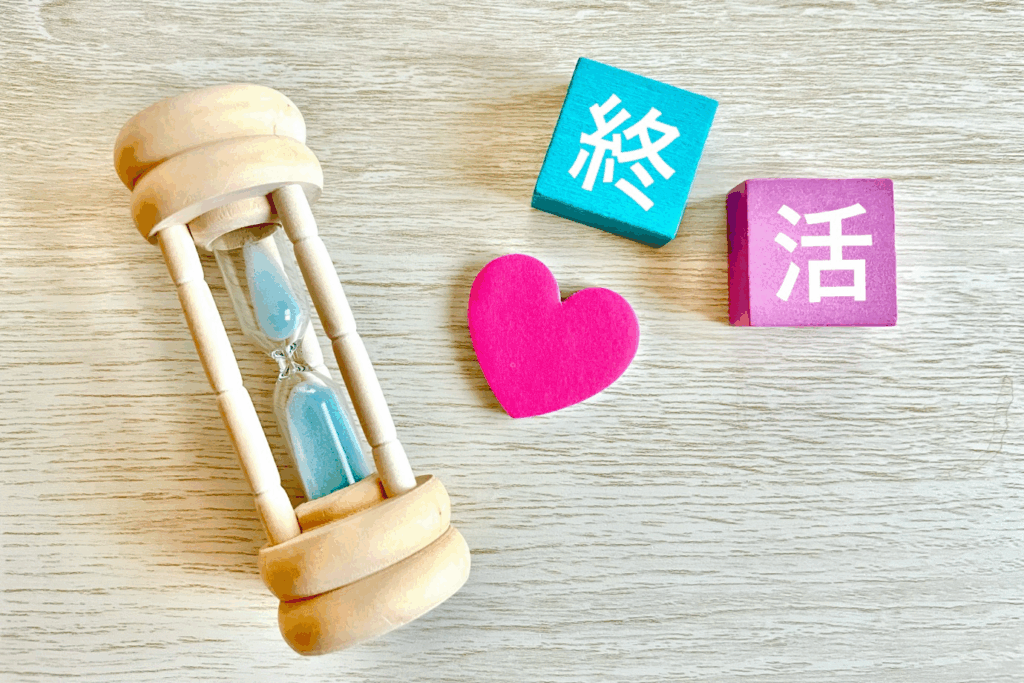
エンディングノートと遺言書、それぞれは何のために書くものなのでしょうか。
両者を役立てていくためには、それぞれを書く目的をしっかり把握しておかなければなりません。
エンディングノートに何を書くか、それは基本的にその人の自由です。
自分の半生を振り返っての思い出を整理するのもよし、残された家族への感謝の気持ちを書き記すもよし、自由に書いて問題ありません。
実際、生前に伝えきれなかった家族への想いをエンディングノートに記す人も多く、それはとても大切なことです。
また、エンディングノートを作る大きな目的のひとつとして「大切な情報を伝える手段としての活用」が挙げられます。
たとえば、
- これまでの病気の状況を伝えたいとき
- 自分に万が一のことが起こって意識がない場面で家族に治療方針を任せるとき
- 亡くなった後に家族に葬儀の方法を決めてもらうとき
- 残った思い出の品の取り扱いを考えるとき
こうしたこれからやってくる重要な決断のときに本人の意思が示されたものがあれば…
そんな思いを叶えてくれるのがエンディングノートなのです。
直接伝えられなかったとしても、エンディングノートが家族にとっての大きな道しるべとなるでしょう。
一方で、遺言書の目的についてはどうでしょうか。
もしかするとここまで話を聞いて「それって遺言書でもできるのでは?」と感じた人もいるのではないでしょうか。
実は、今お話したようなエンディングノートの内容が遺言書に書かれることはほとんどありません。
それはなぜなのでしょうか。
理由は大きく2つあります。
一つ目の理由として、
遺言書は本人の死後について書かれたものだからです。
当然ですが、遺言書の内容を家族が知るのは死後がほとんどです。
そのため、これまでの病気のことや治療方針が書かれていたとしてもそれはもう過ぎてしまったことであり、遺言書で伝えるのはふさわしくありません。
二つ目の理由として、
遺言書が本来の役割を果たせるのは、
1.財産の処理に関する事項
2.相続人の身分(相続人の廃除や子供の認知、未成年後見人の指定)に関する事項
この2つの事柄についてのみです。
詳しくはこの後の効果のところで説明しますが、遺言書は強力な力を持っているがゆえに対象となる事項は限定的であるということを覚えておいてください。
効果にも違いがある
目的と併せて理解しておきたいのがそれぞれの効果です。
遺言は書くことで法的な拘束力が発生するものです。
法律行為であるがゆえに、遺言書があるにもかかわらず、相続人の意に沿わない内容だったからと内容を偽造したり、破り捨てたり、故意に隠してしまうと、刑事罰を受けるほか、最悪相続権を失ってしまう場合もあります。
先にも触れたように遺言の対象が財産と相続人の身分に限られている一方で、不正を行うと罰則や相続人としての立場を失うなど、強い法的効力を有しているわけです。
補足として、遺言書には上記で挙げた財産と相続人の身分以外についても記載することはできます。
これは付言事項と呼ばれます。
付言事項があるケースとしては遺産分割の理由を伝えたい場合です。
付言事項で遺言に込めた想いや考えを書き残しておくことで、仮に相続人の意に沿わない内容だったとしても、その意向を汲んでトラブルを避けられる可能性があります。
それではエンディングノートが持つ効果はどうでしょうか。
結論としては、エンディングノートはその内容に法的な拘束力は一切ありません。
家族や周りの人に伝えたい大切なことを書いておく場所という性格が強いので「いざというときに家族が困らないため」という位置付けです。
費用の違い
ここまでエンディングノートと遺言書の内容的な違いを説明してきましたが、最後に両者の費用にも触れておきましょう。
エンディングノートはとても安価に作成できるのが魅力的で、必要費用という点では数千円程度が一般的な相場です。
ノート自体は市販のものや最近ではアプリを利用して手軽に作成できるようになっています。
また購入せずともネット上で無料ダウンロードも可能です。
ただし、手に入れやすい一方で、どんな項目が盛り込まれているかはそれぞれのノートに特徴があって、書いておきたいことの項目がないという場合もあるでしょう。
値段に差はそれほどありませんので自分の書きたいと思っている項目がしっかりと書けるものであるかが選定の重要なポイントといえます。
また作成の支援サービスを受ける、セミナーに参加して勉強するなど、ノートの購入とは別に費用をかける人もいます。
一方、遺言書の作成費用には数千円から数十万円とかなりの幅があります。
これほどの幅が生まれるのは、作成方法にさまざまな選択肢があるからです。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、自筆証書遺言はその名の通り自ら手書きする遺言書で、用紙にも制約はなく便せんや原稿用紙、メモ帳など好きな方法が取れます。
もう一つの公正証書遺言は、公証役場で公証人と呼ばれる法律の専門家に作成をお願いする方法で、作成した遺言書も公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、有効性も保証されています。
さらに遺言書の作成にあたっては内容について弁護士や税理士、行政書士などの専門家のアドバイスが必要となることも多く、そのための費用も作成者の負担となります。
このように用紙の購入費用だけで作成する人もいれば、弁護士などの士業のサポートを受けつつ、公正証書にて作成する人もいるため、費用の差が生まれるのです。
上手な併用の方法
ここまでエンディングノートと遺言書の違いについていくつかの角度からみてきました。
これまで見てきたように、両者はカバーできる範囲と効果に違いがあり、上手に併用するとお互いを補完しあうことが可能です。
それではどんな風に併用していくのがよいのでしょうか。
たとえば「預金のすべてを長男に相続させる」という遺言書があったとします。
こうした遺言書は多く見られますが、法律的な有効であり、長男は亡くなった方の預金すべてを引き継ぐ権利を取得します(遺留分侵害など、他の点は問題ないものと仮定します)
しかし、もし財産の明細が何も記載されていなかったとしたら、亡くなった方の預金口座がどこの銀行にあるのか分からないケースもあるでしょう。
そうすると、本来は受け取れる権利を持っている預金を見つけられず放置されてしまうという可能性があります。
ここで、もしエンディングノートに亡くなった人がどこの金融機関に口座を持っていたかがしっかりと記載されていたとしたらどうでしょう。
漏れなく口座を把握することができ、スムーズに相続手続きが進んでいくでしょう。
最近では通帳を発行しない金融機関も増えており、所持品の中から預金口座を特定するのが以前よりも難しくなっているという現状もあり、今後はこのようなエンディングノートの活用方法が増えると予想されています。
まさに理想的な両者の併用方法と言えるのではないでしょうか。
まとめ
今回はエンディングノートと遺言書の違いについて、両者を賢く併用できる方法についてもお話をしてきました。
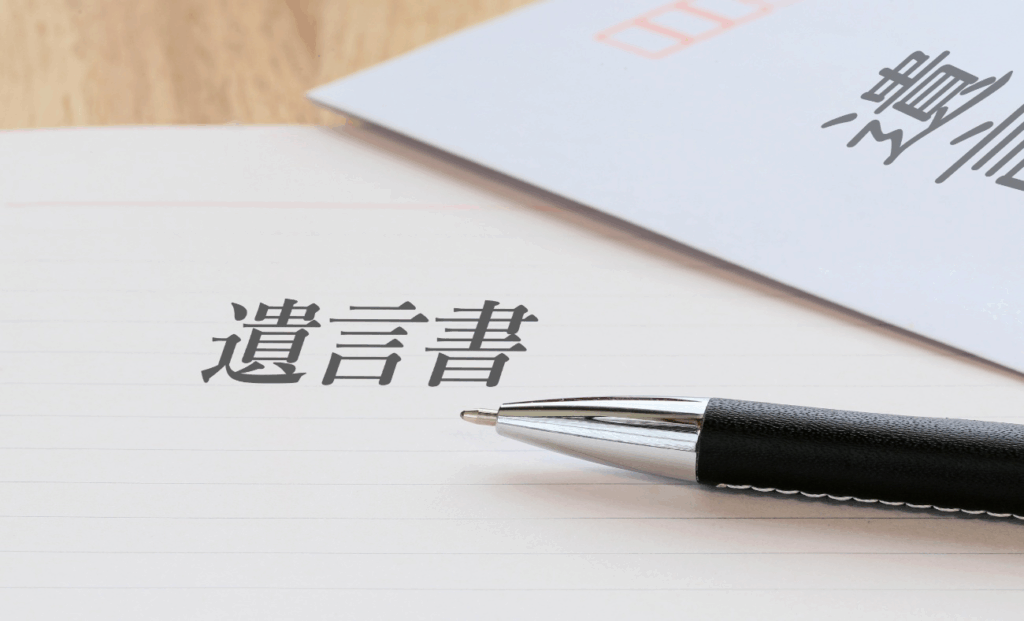
今回お話したように両者はそれぞれまったく異なる役割を持っており、うまく使い分けることで万が一のことがあったときでも家族が安心してさまざまな手続きを行えます。
そして、これから終活を始めようとする人には、まずはエンディングノートの作成からスタートすることをおすすめします。
何度か触れたようにエンディングノートはその自由度の高さゆえに気軽に始められるという利点があります。
一冊自分の書きたい事項が載っているものを購入してみて、まずはそこから書き始めてみる、その後で興味が湧いた部分から少しずつ埋めていく、そうした流れであまり切迫感を持たずに取り組んでみるのがよいでしょう。
そして、ある程度エンディングノートを書き進め、自身の財産についての考え方もまとまってきたところで、遺言書の作成も検討し始めてみる。
そんなやり方であれば無理なく漏れも少なく終活を進めていけるのではないでしょうか。
ぜひ気軽な気持ちで実践してみてください。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼