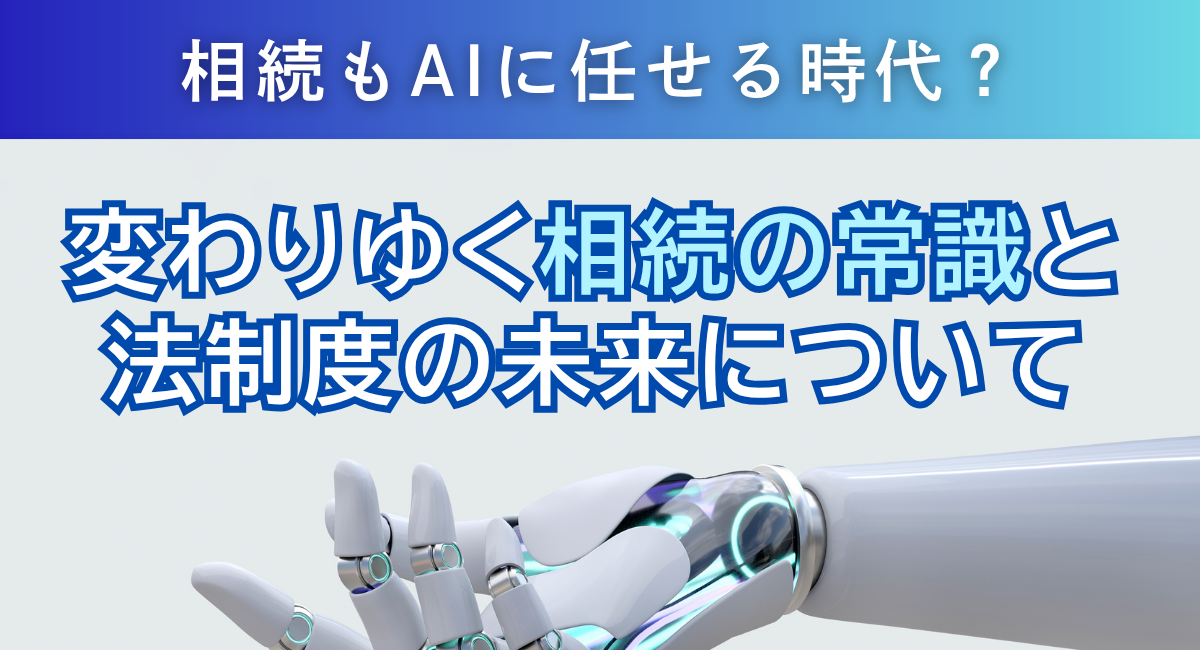現在の相続は、家族間での話し合いや専門家の助言によって、慎重に進めます。しかし、その常識が大きく変わりつつあります。それは、急速に進化するAI(人工知能)技術の活用です。相続の分野にも「自動化」と「最適化」の波が押し寄せています。
AIによる遺言書作成の支援や、資産評価の自動分析、ブロックチェーンを活用した相続財産の管理などが挙げられます。人間の判断に委ねられてきた領域に、テクノロジーが入り込んでいるのです。今回の記事では、AIがもたらす相続の進化と、未来に向けた法制度の課題について、多角的な視点で紹介します。
相続の「常識」が変わる背景

近年、相続に関する「常識」が揺らいでいます。その背景には、家族構成や社会環境の変化に加えて、テクノロジーの急速な発展があるのです。特に注目されるのが、AI(人工知能)の活用です。2025年7月から国税庁が、相続税の調査にAIを本格導入予定です。
これまでは、人の経験や勘による調査方法でした。現在は、膨大なデータをもとにしたAI分析へとシフトしています。これによって、相続で「今まで通り」が通用しないケースが増えました。AIの新たな視点で大きな転換点を迎えているのです。
高齢化社会と相続件数の増加
日本は急速な高齢化で、団塊の世代が後期高齢者になる時期を迎えています。それに比例して、相続の件数が大幅に増える「相続の増加時代」が到来しているのです。
この背景には、相続人も被相続人も高齢である「老老相続」の増加があります。遺言の作成や、遺産分割の手続きが複雑化しているのも現状です。また、2015年の相続税法改正によって、基礎控除が引き下げられました。相続税の対象になる家庭が増えて、納税資金の準備に悩むケースが発生しています。
少子化や核家族化の影響で、相続人の構成が多様化しています。親族間での遺産分割トラブルも起きているのです。このように、高齢化社会の進展は、相続件数の増加を引き起こしています。今後は、相続の適切な準備や対策が、より一層重要になるでしょう。
不動産や仮想通貨などの相続財産の多様化
近年の相続財産は、土地や建物、現金などでは収まりません。株式や投資信託なども対象になります。海外に保有する資産や、暗号資産(仮想通貨)など、新しい形態の財産も相続の対象です。
資産の多様化で、相続手続きは非常に複雑化しています。特に、海外資産の場合は、各国の法律や税制が関わります。評価や手続きが難しくなるのです。暗号資産は、保有状況の把握や相続人への引き継ぎ、評価方法などが明確化されていません。
そのため、相続が発生する場合、専門的な知識が求められます。財産の種類が増えることで、遺産分割や相続税の申告手続きも煩雑になります。そのため、資産を円滑に相続するために、早めの準備や対策が大切です。
| 財産の種類 | 具体例 | 複雑化するポイント |
| 不動産 | 土地、建物、海外不動産 | 海外法規や評価の違い |
| 金融資産 | 現金、預金、株式、投資信託 | 海外口座や外国株の把握・評価が困難 |
| 暗号資産 | ビットコイン等 | 保有状況の把握・評価基準が未整備 |
| 債務 | ローン、借入金、保証債務 | 債務確認や相続放棄の検討が必要 |
| 非課税財産 | 祭祀財産、公益寄付 | 節税目的の支払いに注意 |
| みなし相続財産 | 生命保険金、死亡退職金 | 非課税枠の範囲の確認が必要 |
| 海外資産 | 海外不動産・金融資産 | 各国の法律・税制が絡み、手続きが複雑 |
調査官の人員構成の変化
国税庁の調査官をはじめとする、税務職員の人員は減少傾向にあります。限られた人員で、増加する相続税申告に対応しなければなりません。そのため、従来の経験や勘のみで、調査対象を選定するのは難しいです。相続財産の多様化で調査の難易度も高まっています。
このような背景から、国税庁においてAI(人工知能)が導入されました。2025年7月からは、AIを活用して相続税申告書のデータを分析します。申告ミスや申告漏れが発生しやすいケースを、自動的に抽出するのです。
AIは膨大なデータを短時間で処理します。そのため、調査の必要性が高い案件を、効率的かつ客観的に選定できます。今後は人とAIが連携することで、より適正で効率的な相続税調査が行われるでしょう。
相続における遺言書の作成と執行方法

遺言書の作成には、主に3つの手段があります。1つ目は「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は、遺言者自身が全文、日付、氏名を手書きして押印します。費用が発生せず、簡単に作成できるのが特徴です。しかし、書き方に不備があると、無効になる恐れがあるため、注意が必要でしょう。
2つ目は「公正証書遺言」になります。公証人役場で公証人に内容を伝えて、証人2人の立ち会いのもとで作成します。原本は公証役場で保管される仕組みです。そのため、紛失や改ざんの心配がありません。法的にも非常に強い効力を持ちます。しかし、作成には手間と費用が発生します。
3つ目は「秘密証書遺言」です。内容を秘密にした状態で、公証人と証人の前で遺言書の存在のみを証明する方法になります。遺言書の内容を明かしたくない場合に最適です。一方で、形式の不備や紛失のリスクが伴う点にも注意してください。
2025年現在、デジタル遺言、デジタル遺言(電子的な遺言書)は法的に認められていません。今後は、公正証書遺言のデジタル化が進むでしょう。現在の日本では「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」が主流です。遺言の執行は、遺言執行者が中心で進められます。デジタル化の進展によって、より便利で安全な遺言制度が整備されます。
| 種類 | 作成方法の概要 | 特徴・注意点 |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・氏名を自筆して、署名押印を行う。 | 費用がかからない。形式不備で無効になるリスクがある。 |
| 公正証書遺言 | 公証人に口頭で内容を伝えて、公証人が作成する。証人2名の立会いが必要になる。公証役場で原本の保管を行う。 | 法的効力が強く、紛失や偽造のリスクが低い。費用と手間がかかる。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にした状態で、公証人と証人2名の前で、遺言書の存在のみを証明する。 | 内容の秘密性は高い。形式不備や紛失リスクがある。 |
AI導入で相続の何が変わるのか
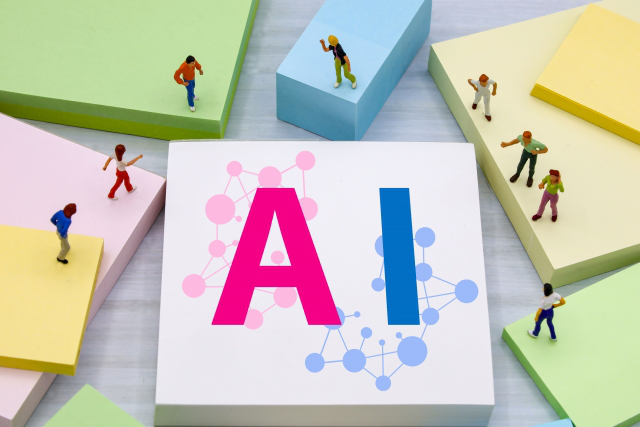
先述の通り、2025年7月から、相続の分野にAIが導入されました。相続税申告の在り方が大きく変わります。AIは過去の申告データや海外送金履歴など、複合的な情報をもとに、申告漏れなどのリスクを数値化します。リスクが高いと判断された申告は、優先的に税務調査の対象になるのです。海外資産やデジタル資産などの把握が難しい財産も、より正確に検出できます。つまり、申告漏れや不正が見つかるリスクが高まります。「見落としがちな資産」もAIで把握されやすくなるのです。
また、相続手続きに関しても、AIの自動化が進むかもしれません。例えば、戸籍謄本のデータ化や、相続関係説明図の自動作成などが挙げられます。これによって、相続人や金融機関の負担が軽減されます。現在よりも、スムーズな資産移転が可能になるのです。AIによる厳格なチェックが前提になる可能性があります。透明性と正確性の高い相続税申告が、求められる時代へ移行するかもしれません。
遺言書の作成が誰でも簡単にできる
AIの導入によって、相続手続きや遺言書の作成方法が変わりつつあります。今までは、遺言書を作るために、法律の専門知識が必要でした。遺言書の相談を、専門家に依頼するケースも多いです。しかし、AIを活用したツールが普及し始めています。誰でも簡単に遺言書の土台が作成できるのです。
AIは、利用者が質問に答える形式で必要な情報を集めます。法律に則った遺言書の土台を、自動的に作成します。そのため、法律に詳しくない人でも、手軽に自身の希望を反映した遺言書が準備できるのです。AIは、相続に関わる法律上の注意点や、トラブルになりやすい部分も指摘してくれます。
このようなAIサービスは、スマホやパソコンから、いつでも利用できるのが特徴です。作成に必要な時間も大幅に短縮されます。費用面においても、従来より低コストで利用できるケースが増えています。つまり、多くの人が手軽に遺言書作成に取り組める環境が整っているのです。
一方で、現在の法律では、AIで作成した遺言書はあくまで「草案」になります。正式に法的効力を持たせるには、全文を自筆で書かなければなりません。しかし、AIの活用で遺言書作成のハードルは、大きく下がりました。相続の準備が、身近で手軽なものになっています。今後は、多くの人がAIを活用して、自身の意思を確実に残せる社会が進むでしょう。
親族間の相続トラブルが減少する
AIの導入で、相続トラブルの予防と公平性の向上が進んでいます。近年では、AI技術を活用したチャットボットやシミュレーションツールが実用化されました。相続の課題に対して、迅速かつ正確な対応が可能です。例えば、AIチャットボットは、24時間365日対応します。相続手続きの流れや必要な書類、税金の概算などを自動で提供するのです。
これによって、平日に時間が取れない人や、専門家の相談にハードルを感じる人の大きなサポートになります。また、AIは膨大な法律データや過去の判例をもとに、個別のケースに応じた助言やシナリオ分析も行えます。相続対策の質を高めるだけでなく、親族間の感情的な対立を防ぐための「事前準備」として有効です。
複雑な財産構成や複数の相続人がいる場合でも、AIが公平な分配方法をシミュレーションします。それによって、「なぜその分け方になるのか」根拠が明確になるのです。相続人間の誤解や、不満を減らす役割を果たします。このようなAIの活用は、単なる利便性の向上にとどまりません。相続というデリケートなテーマで、心理的・経済的な負担を大きく軽減できるのです。
デジタル遺産が管理しやすくなる
デジタル遺産の管理や相続手続きの対応は、これまで以上に円滑に進んでいます。例えば、AI-OCR技術の活用です。戸籍謄本や各種証明書を自動で読み取ることで、相続関係説明図や、遺産分割協議書の作成が迅速になりました。煩雑な戸籍の収集や相続人の特定作業も、AIが自動で処理することで、大幅に手間が省けます。
金融機関などでも、AIを活用しています。書類の作成や必要事項のチェックが自動化されて、複雑な手続きが簡略化されました。このように、AIを活用することで、デジタル遺産を含む相続全体の手続きが効率化されます。誰でも不安なく、相続準備を進められる時代が到来しています。
相続の将来的なリスクと納税者の備えについて

国税庁は全国の相続税申告書に対して、AI(人工知能)の自動スクリーニングを導入しました。2023年以降に提出された、相続税申告書がAIの分析対象になります。AIが「申告ミスや申告漏れが起こりやすいパターン」を学習して、リスクスコアを付与する仕組みです。
このAIの体制は、申告内容の規模や複雑さに関係ありません。全国の相続税申告書が、AIのスクリーニング対象になります。そのため、「自身は対象外」と考えるのは危険です。AIは、財産債務調書や金融機関の入出金記録、海外送金など、膨大な関連データを自動的に照合します。不自然な資金移動や説明できない取引がある場合、リスクスコアが上昇して、調査対象の可能性が高まります。
AIが「申告漏れやミスの可能性が高い」とスコアリングした申告は、実地調査や電話照会の優先対象になるのです。形式的な不備や説明不足などは、AIに「要注意」と判定されやすくなります。そのため、財産や債務の全体像を正確に把握しなければなりません。根拠となる資料の準備が必要です。
税理士などの専門家のサポートを受けて、AIが注目するポイントを事前に整理しましょう。それによって、相続税の申告リスクが低減されます。今まで以上に「正確性」と「説明責任」が求められます。根拠資料の準備と、専門家との連携を徹底してください。AI時代の新たなリスクに備えることが、相続税の申告には不可欠です。
相続税の申告漏れやこれまでの常識が通用しない
AIは、全ての相続税申告書を自動的に評価します。目視や経験則では、発見が難しい海外資産や仮想通貨なども対象です。例えば、各国との情報交換や取引所からの報告、ブロックチェーンのデータなどを、横断的に解析します。これによって、申告漏れが特定できるのです。AIの導入で、調査の基準が全国一律になります。
つまり、地域や担当者によるばらつきがなくなるのです。今後は「見つからないだろう」は通用しなくなります。納税者が公平にチェックされる時代です。このような変化に対応するためには、相続人や納税者は、被相続人の資産を正確に把握しなければなりません。口座や取引記録を整理することが重要です。複雑なケースや不明な点がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
専門家の活用の新たな役割
税理士などの専門家にも、新しい役割が求められています。AIは、定型的な作業やデータ分析を中心に行います。一方で、専門家は複雑な財産評価や、最新の法改正への対応など、個別の事情に応じた柔軟なサポートが期待できるのです。
判断が難しいグレーゾーンの解釈や、家族間の合意形成など、人間ならではの対応力が重要です。今後は、AI分析の活用は欠かせません。しかし、依頼者ごとに事情は異なります。最適な相続対策を提案するには、税理士やFPなどの専門家が必要です。AIと専門家のそれぞれの強みを活かして、相続対策を進めるのがおすすめです。
テクノロジーの革新と法制度のギャップ

近年、AI技術の急速な発展によって、遺産分割の提案や相続の相談にもイノベーションが起きています。専門家の手を必要としていた複雑な手続きが、AIやチャットボットの活用で、迅速かつ効率的に進められます。このようなテクノロジーの進化は、様々な利便性をもたらします。一方で、現行の法制度が十分に追いついていません。AIが生み出す新たな相続のかたちと、現在の法的課題について解説します。
デジタル遺言の法的整備と外国の現状
2025年現在、日本ではデジタル遺言の法整備は進んでいません。パソコンやスマートフォンによる電子的に作成した遺言書は、正式な遺言として認められないのです。遺言書として効力を持つのは、紙に手書きする自筆証書遺言や、公証人のもとで作成する公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。動画や音声、メール、SNSなどを使用した遺言に関しても、法律上は無効になります。
一方で、2019年に相続分野に関して、民法改正が行われたのです。自筆証書遺言の「財産目録の部分のみ」は、パソコンで作成したデータの添付が可能になりました。しかし、印刷した後に、署名・押印を行う必要があるため、完全なデジタル遺言制度の法整備までは進んでいません。
法務省などでは、高齢化やデジタル社会の進展を見据えて、デジタル遺言の制度化について検討が進められています。2025年には、公正証書遺言の一部手続きがデジタル化される予定です。しかし、電子データのみで有効な遺言書を作成するには、まだ時間がかかるでしょう。本人確認の方法や改ざんのリスク、データの管理などが課題として残っているのです。
アメリカでは、州によっては電子遺言が認められています。コロナ禍以降、オンラインでの公証や、電子署名を利用した遺言作成が広がりました。韓国においても、録音や動画の遺言が法的に有効になります。証人の立ち会いなど、一定の要件を満たした上で、家庭裁判所の判断により有効とされるケースがあります 。
ドイツなどヨーロッパの多くの国では、現時点でデジタル遺言は認められていません。このように、日本だけでなく、世界各地でデジタル遺言の導入議論が続いています。国や地域で対応が分かれており、国際的な動向も注視する必要があります。
※フランスでは一部の公証文書でデジタル化が進みつつありますが、遺言の完全電子化には至っていません。
| 国・地域 | デジタル遺言の法的効力 | 主な特徴・現状 |
| アメリカ | 州ごとに異なる(合法な州あり) | ネバダ、インディアナ、アリゾナ、フロリダ州などで、電子遺言が認められている。コロナ禍以降、オンライン公証手続を認める州が増加している。 |
| 韓国 | 録音・動画による遺言が有効 | 遺言者が「趣旨・氏名・生年月日」を口述する。証人の確認が必要である。音声を残すことで、動画も有効とされる。 |
| ドイツ・フランス | 認められていない | デジタル遺言は無効になる。現行法との整合性や、真正性担保が課題である。 |
| イギリス・カナダ・中国 | 国や州によって異なる | 一部でデジタル化の議論や、限定的な導入が行われる。 |
相続登記の義務化とテクノロジーの活用
相続登記の義務化は、所有者不明の土地問題が深刻化する現状を踏まえて、導入されました。全国的に登記簿上で、所有者が特定できない土地が増加しています。相続登記が行われずに、放置されているケースも多いのです。この問題は、都市開発や公共事業の妨げになるだけではありません。空き家の増加や防災対策の遅れ、相続トラブルなど、社会全体に影響を及ぼします。
このような背景から、2024年から相続人は、不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請する必要があります。相続の登記が法律で義務付けられました。申請を怠ると、10万円以下の過料が科されます。今後は、テクノロジーの活用によって、相続登記の手続きの円滑化が期待されます。被相続人の所有不動産を氏名や住所から網羅的に検索できる「所有不動産記録証明制度」の導入が予定されているのです。
これによって、相続人が自身の相続対象になる不動産を簡単に把握できます。登記漏れの防止や手続きの簡素化が進むでしょう。マイナンバーや戸籍情報との連携で、本人確認や相続関係の証明の自動化、オンライン申請も開始されました。テクノロジーの活用で、今後も相続登記の負担が軽減されるでしょう。所有者不明の土地解消にもつながります。
| 項目 | 内容 |
| 義務化開始日 | 2024年4月1日 |
| 申請期限 | 相続を知ってから3年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 |
| 背景 | 所有者不明土地問題の解消 |
| 手続きの簡素化 | 所有不動産記録証明制度、オンライン申請 |
| 期待できる効果 | 登記漏れの防止、手続きの円滑化、土地問題を解消 |
AI時代の相続設計と今後の社会的な課題
AI技術が、司法や税務に浸透しつつある現代で、相続分野も様変わりしています。相続といえば「家族内の話し合い」や「専門家への相談」が主な手段でした。しかし、今ではAIの活用で、誰でも相続設計に取り組めます。AIによるシミュレーションツールは、複雑な税制や資産状況を瞬時に分析します。
遺言書の作成に関しても、AIが法的要件をチェックして、必要な文言を自動で生成するのです。これによって、専門知識がなくても、一定水準の書類が作成できます。しかし、社会的・法的な課題も浮かび上がっています。それは、AIが相続設計を主導することで、家族間の対話や合意形成のプロセスが省略される点です。
納得感や感情的な調整が、置き去りにされるリスクがあります。特に、本人の意思や価値観を、どこまでAIが反映できるのか不透明な部分があるのです。AIは入力された情報や、過去のデータに基づいて提案を行います。そのため、高齢者や認知症の方など、意思確認が難しい場合、法的有効性や妥当性が問われるでしょう。
AIが作成する遺言書にも課題があります。それは、内容に誤りがある場合です。責任の所在が曖昧であるため、相続時にトラブルを招く可能性があります。資産情報や家族構成など、センシティブな個人情報をAIに入力するリスクもあるでしょう。今後は、AIはあくまで「補助ツール」として活用するケースが増えるかもしれません。最終的な意思決定を家族や専門家が行うことで、相続やセキュリティ面でリスク低減が行えます。
将来に向けて、AIによる相続支援の法整備が進んでいます。利用者のプライバシー保護や、AIの透明性確保などを目的にした倫理ガイドラインの策定も、世界各国で進行中です。このように、AIの進展で相続の在り方は変わりつつあります。本人の意思をはじめとした本質的な価値の守り方が、今後の社会的・法的な大きな課題です。
AIによる相続支援の限界と倫理的配
相続分野のAI活用は、業務の効率化や判断の精度向上など、大きなメリットをもたらします。一方で、重要な課題も浮き彫りになっています。まず、AIの判断精度です。相続税の申告や資産評価などの分野では、高いパフォーマンスを発揮します。しかし、その判断過程において、ブラックボックス化しやすい問題があるのです。
特に、深層学習(ディープラーニング)を用いたAIになります。「なぜその判断を行ったのか」を人間が説明できないケースがあるのです。税務や法的判断が必要な現場では、説明責任の観点から、AIに全面依存することは困難です。
また、納税者がAIの根拠を理解できないかもしれません。そのようなケースで回答が難しい場合、納税者の権利保護や、公平性を損なう可能性があります。倫理面の課題も挙げられます。相続の分野では、個人情報や財産情報などの、機密性の高いデータをAIが大量に扱わなければなりません。プライバシー保護やデータの適正利用が不可欠です。
AIによる判断が、差別を助長する可能性もあります。そのため、倫理的なガイドラインや、監督体制の整備が求められるでしょう。今後は、説明の根拠を高める技術(Explainable AI)の導入が期待されています。技術が進むことで、信頼性や透明性が向上します。このように、相続分野のAI活用は大きな可能性を秘めています。しかし、判断の精度や倫理面など、解決すべき課題が多いのも現状です。
変化を前向きに捉えた備えと「相続リテラシー」の向上
テクノロジーが発達した現代では、専門的な知識がなくても、相続税の計算や対策を簡単に調べられます。これは「備え」の重要性を考える良い機会になります。例えば、自身の通帳や証券、不動産の書類を整理することが、スムーズな相続につながります。
生前贈与や家族信託などの対策も同様です。記録や書類を整えることで、AIによる調査にも安心して対応できます。また、税理士などの専門家に早めに相談することで、AI時代に合わせたアドバイスが受けられるでしょう。
今後は、AIやデジタルツールを使いこなす必要があります。つまり「相続リテラシー」を高めることが大切です。AI導入による変化を、新しい時代の前向きな一歩と捉えましょう。今できることに目を向けて、相続リテラシーを高めることで、次世代の相続対策に備えられます。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼