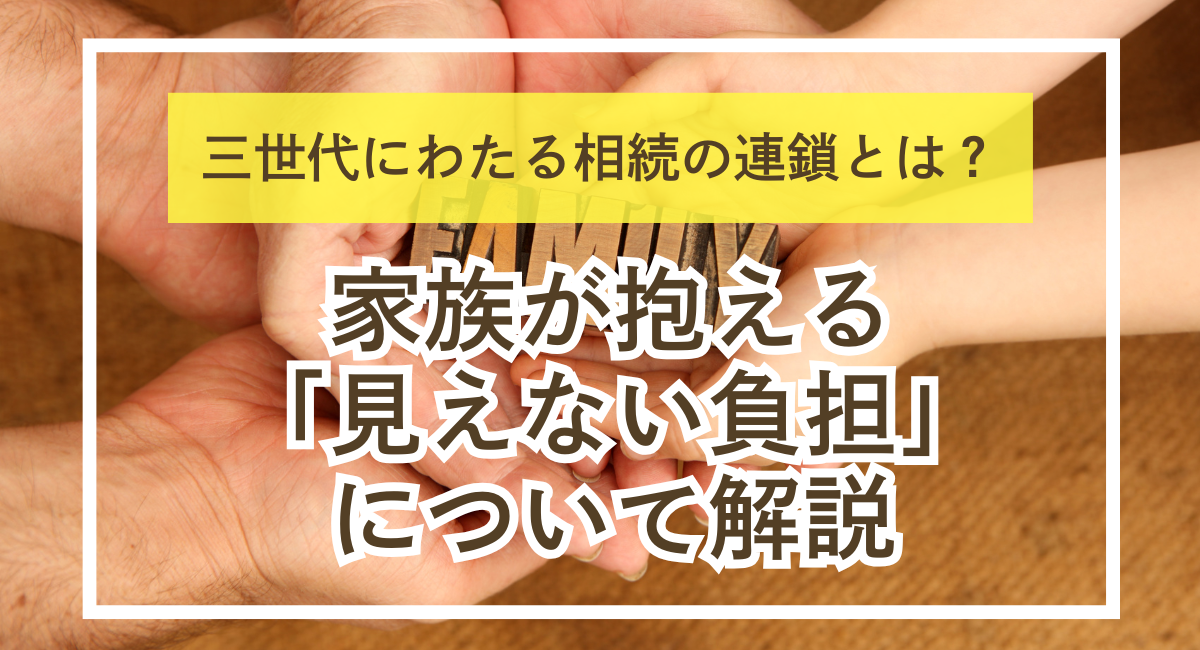現代の日本では、高齢世代の長寿化と資産の多様化が進んでいます。高齢化の進行で、相続の問題は、親・子・孫と三世代にわたるケースが増えています。三世代相続が発生した場合、家族内の人間関係や資産の承継構造が複雑化するのです。想定外のトラブルや心理的な負担を招くケースも多いです。
このような連鎖の中で、新たな課題や事前の対策も浮かび上がります。今回の記事では、三世代にわたる相続の仕組みと、家族が直面する「見えない負担」について、細かく紐解いていきます。今後の相続設計に向けた解決策もご紹介します。
高齢化と長寿化が生み出す「三世代相続」

かつての日本では、相続は一生に一度経験するかしないかの問題でした。しかし、平均寿命の向上と高齢化社会の進行で、相続は一度きりの問題ではなくなりつつあります。複雑化する家族構成や税制度の変化も影響を与えています。
祖父母の相続を終えても、次は親の相続があります。将来的には、自身の相続の準備を行わなければなりません。財産は世代を超えて、受け継がれます。相続の手続きやトラブル、税金などの見えない負担も引き継ぐ必要があるのです。
三世代にわたる相続の連鎖は、家族にとって、精神的にも物理的にも大きな重圧になります。例えば、祖父名義の不動産がまだ整理されていないうちに、父が亡くなるケースです。不動産の名義が、三世代にまたがって複雑化します。兄弟姉妹で財産の分け方をめぐって争いが起きる可能性があります。そのトラブルが次の世代まで、尾を引くケースも多いです。
さらに深刻なのは、「相続税の負担」になります。日本では、世代をまたいで相続が繰り返されると、相続税の控除が段階的に減少するため、結果的に負担が増えるケースもあります。三代にわたって財産を承継するうちに、その多くが税金として失われるかもしれません。
「三世代相続」とは何か?
三世代相続とは、財産の相続が「親、子、孫(またはひ孫)」と、三世代以上にわたって、受け継がれるケースです。例えば、祖父が亡くなった際に、その子(父)がすでに他界していた場合、孫が祖父の財産を相続します。さらに、その孫も亡くなっている場合には、ひ孫が相続人になる可能性があります。
このように、相続権が一代ずつ世代を超えて受け継がれていく仕組みが「三世代相続」です。日本では、相続のたびに相続税が課されます。三代にわたって相続が続くと、財産が大幅に目減りするのです。「三世代相続」は、資産の目減りリスクを象徴する言葉として、使用されることもあります。
相続の連鎖が生まれる仕組み
三世代相続や相続の連鎖が起こるのは、法律に「代襲相続」が規定されているためです。通常、亡くなった方の財産は、その子どもが受け継ぎます。しかし、その子どもがすでに亡くなっている場合には、相続人が変わります。子どもの子、つまり孫が相続人になるのです。これを代襲相続と呼びます。
もし、孫も亡くなっている場合には、ひ孫が相続人になります。直系の子孫であれば、何世代にもわたって、相続権が引き継がれるのです。この仕組みによって、相続人が複数の世代にまたがります。相続の連鎖が発生すると、遺産分割や名義変更などの手続きが煩雑になりやすいです。そのため、専門家のサポートを受けることが大切です。
| 順位 | 本来の相続人 | 本来の相続人が死亡等の場合の代襲相続人 | 代襲相続の範囲・備考 |
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 孫 → ひ孫(再代襲も可) | 何世代でも直系卑属に代襲相続が可能 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 祖父母 → 曾祖父母 | 上の世代で存命の者が相続人 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) | 甥・姪 | 代襲は1代限り。甥姪の子には不可 |
| 常に相続人 | 配偶者 | ― | 配偶者は常に相続人 |
家族が抱える「見えない負担」

三世代にわたる相続において、表面上では気付きにくい、様々な負担が生じます。特に、資産の内容や管理状況について、十分な情報共有が行われていない場合です。相続が発生したときに、何から手をつければよいのか分からず、手続きが複雑化します。必要な書類を集めたり、役所での手続きを行ったりするだけでも、多くの時間と労力が発生します。精神的なプレッシャーも大きくなるでしょう。
親が所有する不動産や賃貸物件を相続した場合、その管理責任が子や孫にのしかかります。物件の修繕や入居者対応など、経験のない業務を行わなければなりません。本業がある方にとっては、負担が大きくなりがちです。日本の相続税は、取得する遺産の金額が多いほど、税率も高いです。
一次相続だけでなく、二次・三次相続まで見据えた準備をする必要があります。配偶者の税額軽減が使えなくなる二次相続以降は、税負担が急増する恐れがあるのです。代襲相続では、資産や負債の詳細が伝わっていないことが多いです。借金を引き継ぐリスクもあります。
相続放棄の手続きが間に合わず、予期せぬトラブルに巻き込まれることも少なくありません。現代は、家族や親族のつながりが希薄になりがちです。相続人同士でスムーズな連絡が取れない可能性があります。このような、トラブルや手続きの遅れが生じることも「見えない負担」につながります。
相続手続きの膨大な戸籍収集と書類作成の現実
三世代にわたる相続手続きでは、戸籍の収集と書類作成が複雑です。膨大な作業になるケースが多いです。相続を進めるためには、被相続人の出生から死亡までの、全ての戸籍謄本を揃える必要があります。しかし、戸籍は結婚や転籍、戸籍法の改正などで何度も新しくなります。本籍地が変わるたびに、各自治体へ請求しなければなりません。
祖父母から親、そして子へと続く家系を証明するために、多数の戸籍を収集する必要があるのです。場合によっては、10通以上の戸籍を取り寄せることも珍しくありません。被相続人に子どもがいない場合は、相続権が兄弟姉妹や甥・姪にまで及びます。つまり、収集すべき戸籍の数はさらに増加します。
集めた戸籍から、相続人を正確に確定する作業は難しいです。古い戸籍は、記載内容が難解です。初めて手続きを行う人にとっては、この解読が大きな負担になります。また、過去の相続が未処理で連鎖的に発生する「数次相続」にも注意してください。数次相続とは、遺産分割協議が終了する前に、相続人が亡くなるケースです。
例えば、祖父の相続が終わる前に、父親が他界してしまい、配偶者や子どもが新たな相続人になる場合です。遺産分割協議書の作成や、合意形成もより一層複雑になります。戸籍は、複数の役所から取り寄せる必要があります。郵送で請求する場合、時間や費用もかかるでしょう。相続人が遠方や海外にいる場合は、手続きの負担がさらに増加します。
戸籍収集や書類作成が膨大な場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼しましょう。円滑な相続手続きを進めるための、現実的な方法です。三世代相続における戸籍の収集と書類作成は、時間と労力を要します。専門知識が必要なため、多くの方が相続手続きの難しさや悩みに直面するのです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 必要な戸籍の種類 | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍) ・相続人の現在戸籍 | 戸籍は結婚、転籍、戸籍法改正で何度も新しくなるため、連続した戸籍をすべて取得する必要がある。 |
| 戸籍の取得方法 | ・本籍地の役所窓口で直接請求 ・郵送請求 ・一部地域でコンビニ交付も可能 | 郵送は10日程度かかることが多く、コンビニ交付は条件あり。除籍謄本や改製原戸籍はコンビニ不可。 |
| 戸籍の数が多くなるケース | ・代襲相続(孫や甥姪が相続人になる場合) ・被相続人に子どもがいない場合の、兄弟姉妹相続 | 代襲相続は、法定相続人全員が亡くなっている証明が必要。戸籍数が膨大になる。 |
| 戸籍の内容の難しさ | 古い戸籍は手書きや旧字体で記載されており、解読が困難 | 初めての方には大きな負担になる。 |
| 数次相続の注意点 | 遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなるケース(例:祖父の相続前に父が死亡) | 手続きや合意形成がさらに複雑化する。 |
| 手続きの負担増加要因 | ・複数自治体から戸籍を取り寄せる必要がある ・郵送請求による時間・費用 ・相続人が遠方や海外にいる場合 | 手続きの負担が増大して、時間や費用がかかる。 |
| 専門家への依頼の推奨 | 司法書士や行政書士に、戸籍収集や書類作成を依頼することで、手続きが円滑に進む | 複雑な三世代相続では、専門知識が必要になる。 |
| 法定相続情報証明制度の活用 | 戸籍謄本などの束を法務局に提出する、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」の認証を受けられる | 手続きの簡略化や、戸籍の束の提出回数削減に役立つ。 |
疎遠な親族との交渉や対立がもたらす心の負担
これまで交流のなかった親族同士が、相続人として関わりを持ちます。その結果、疎遠だった親族と、遺産分割の話し合いを進めなければなりません。交渉や対立が精神的な負担になります。叔父や叔母、甥や姪など、普段は接点の少ない親族が相続人の場合もあるでしょう。
コミュニケーションが上手く取れず、話し合いが進まないことが多いです。相続手続きは、身近な人の死という喪失感の中で、行わなければなりません。もともと心に重圧がかかるものです。そのような中で、財産分配をめぐる利害の対立や価値観の違いが発生します。感情的な対立や不信感が生じやすくなります。
場合によっては、法的な争いに発展する恐れもあるのです。世代ごとに、財産や家族の役割に対する考え方が異なります。それによって、合意形成が難しくなります。そして、心の負担が大きくなります。このように、三世代相続における、疎遠な親族との交渉や対立は、精神的なストレスにつながります。
相続に関する費用負担と不動産維持の経済的リスク
三世代の相続では、相続手続きの費用負担や、不動産を維持するための経済的リスクが大きな課題です。相続登記を行う場合、登録免許税や専門家への依頼料が必要になります。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて算出されます。戸籍謄本の取得費用や郵送費、交通費などの細かな出費も積み重なるでしょう。
費用をどのように分担するのか、相続人同士で事前に決めておかねばなりません。相続税や葬儀費用、遺品整理費用なども発生します。一部は税務上の控除対象になります。しかし、全てを経費に計上するのは難しいです。不動産を相続した場合、その維持管理には継続的な負担が伴います。固定資産税や管理費、修繕費などのランニングコストが発生します。
空き家の場合には、資産価値の下落や管理責任、売却の難しさなど、様々なリスクを考慮しなければなりません。不動産を複数の相続人で共有する場合は、管理や売却の意思決定が、円滑に進まないことが多いです。結果として、経済的な負担が長期化します。このように、三世代相続は、手続きにかかる費用だけでは収まりません。不動産を維持するための経済的リスクも大きいです。相続人にとって、大きな負担になる恐れがあります。
| 項目 | 内容 |
| 手続き費用 | 登録免許税、専門家報酬、書類取得費用など |
| 費用分担 | 相続人同士で事前に話し合いが必要 |
| 不動産維持費 | 固定資産税、管理費、修繕費など、継続的な負担 |
| 空き家リスク | 価値下落、管理責任、売却困難 |
| 共有不動産の課題 | 意思決定が難しく、負担が長期化 |
| その他費用 | 相続税、葬儀費用、遺品整理費用 |
借金や不動産などの「負の遺産」
三世代にわたる相続では「負の遺産」を引き継いでしまうリスクが問題です。相続財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金や住宅ローン、未払い金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続人は「負の遺産」を背負わなければなりません。
使い道のない土地や老朽化した建物、管理が困難な山林など、不要な不動産を相続した場合は大きな課題になります。これらの資産は、売却が難しいだけではありません。固定資産税や維持管理費などのコストが、継続的に発生するのです。
このようなリスクを回避するために、相続放棄の選択肢があります。相続放棄を行うことで、プラスの財産もマイナスの財産も、引き継がずに済みます。一方で、三世代相続の場合です。親が相続放棄をしても、祖父母の相続で孫が代襲相続人になるケースがあります。このような場合、改めて相続放棄の手続きを行わなければなりません。
三世代相続では、負債や不要な資産は「負の遺産」です。相続人にとって、経済的リスクや負担になります。相続が発生した際には、被相続人の負債や資産の状況を、早急に調査しましょう。必要に応じて、相続放棄を検討することが重要です。
| 項目 | 内容 | 注意点・ポイント |
| 負の遺産の例 | ・借金(ローン、未払い金) ・使い道のない土地 ・老朽化した建物 ・管理困難な山林 | プラスの財産と同様に相続対象となる |
| 負の遺産を相続した場合のリスク | ・借金返済義務の発生 ・固定資産税や管理費の継続的負担 ・売却困難な場合の経済的損失 | 放置すると、損害賠償や行政指導の恐れがある |
| 相続放棄の方法 | 家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを行う | 相続開始を知った日から、3か月以内に手続きが必要になる |
| 相続放棄の効果 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない | 相続人としての権利・義務が全て消滅する |
| 三世代相続特有の注意点 | ・親が相続放棄しても、孫が代襲相続人になる場合がある ・その場合、孫も相続放棄の手続きが必要 | 連鎖的な放棄の手続きが必要になる |
「三世代相続」の負担を減らすためにできること

三世代にわたる連鎖相続を防いで、相続の負担を軽減するためには、早めの対策が不可欠です。家族間のコミュニケーションも非常に大切です。生前贈与や生命保険の活用、小規模宅地等の特例などを利用することで、相続財産や相続税の負担が減らせます。
公正証書遺言を作成して、具体的な分割方法や次世代以降の承継方針を明確にしてください。それによって、相続人同士の争いを未然に防げます。家族信託の活用もおすすめです。認知症で判断能力が低下した場合でも、資産管理や承継をスムーズに進められます。
そして、家族会議を開いて、財産や相続について事前に話し合いましょう。家族全員が、納得した形での承継が実現しやすくなります。場合によっては、孫への一代飛ばし相続や、相続放棄などの方法も有効です。一方で、税制上の注意点や手続きの期限があるため、慎重な判断も求められます。
生前贈与や遺言書で相続人を整理する
三世代相続においては、生前贈与や遺言書の活用が大きく役立ちます。例えば、生前贈与を利用するケースです。被相続人は自分の意思を反映できます。子や孫などの次世代・三世代にわたって、財産を計画的に分け与えられます。これによって、相続財産そのものを減らせるのです。「誰に、どの財産を、いつ渡すか」を決められるため、後々のトラブルを未然に防げます。
特に、孫への贈与は、相続人でなければ原則として相続財産への加算対象外ですが、孫が相続人の場合には加算されます。そのため、三世代相続の対策として有効です。また、遺言書の作成もおすすめです。被相続人の意思を明確に示せます。相続人ごとに「誰が、どの財産を、どれだけ受け取るのか」を具体的に指定できるのです。遺言書があることで、遺産分割協議の混乱や争いが防げるでしょう。
しかし、遺言書の内容が曖昧であったり、財産の記載漏れがあったりすると、トラブルの原因になります。専門家のアドバイスを受けながら、正確に作成することが重要です。生前贈与と遺言書を組み合わせて活用することで、三世代にわたる相続人の関係が整理できます。相続時の混乱や、争いの火種が抑えられるのです。
| 項目 | 生前贈与 | 遺言書 |
| 主なメリット | ・被相続人の意思で「誰に、どの財産を、いつ渡すか」を決められる ・相続財産を減らせる ・三世代(子・孫)へ計画的に分与できる ・孫への贈与は、相続財産への加算対象外となる場合あり | ・被相続人の意思を明確に示せる ・「誰が、どの財産を、どれだけ受け取るか」を指定できる ・遺産分割協議の混乱や争いを防げる |
| 注意点 | ・贈与税がかかる場合がある ・贈与の時期や方法に注意しなければならない ・孫への贈与は相続人でない場合、加算対象外になる | ・内容が曖昧、財産の記載漏れはトラブルの原因になる ・遺留分を侵害できない(法定相続人の最低取得分は守る必要あり) |
| 有効な活用場面 | ・三世代にまたがる財産承継 ・相続税対策 ・特定の孫や子に早めに財産を渡したい場合 | ・遺産分割の明確化 ・相続人間のトラブル防止 ・特定の相続人に配慮したい場合 |
| 専門家の関与 | 税理士や司法書士などのアドバイス | 弁護士や行政書士などのサポートで、正確な作成が重要 |
不動産の早期処分と共有解消を検討する
不動産の早期処分や共有状態の解消は、将来の相続トラブルや、管理負担を軽減するためには重要です。相続した不動産が遠方にあったり、利用する予定がなかったりする場合には、早い段階で売却や譲渡を検討しましょう。寄付で手放すことも有効策です。不動産を複数人で共有名義にする場合、売却や活用する時に全員の合意が必要になります。
相続人が増えるほど、意思決定の難易度が高まります。そのため、遺産分割の段階で一人の相続人に集約する、他の財産で調整して不動産の共有を避けるなどの対策が大切です。売却が難しい場合には、隣地所有者への譲渡や、自治体・法人への寄付なども検討してください。
手数料や一定の条件はありますが、「相続土地国庫帰属制度」の利用も選択肢になります。この制度を活用することで、不要な土地を国に引き渡せるのです。このように、不動産の早期処分や共有解消を進めることで、三世代にわたる相続の複雑化や、負担の連鎖が未然に防げます。
| 対策・制度 | 内容 | 費用・条件 | 注意点 |
| 早期売却 | 不動産を早めに売却 | 仲介手数料・税金あり | 相続人全員の合意が必要 |
| 共有状態の解消 | 持分譲渡や放棄で共有解消 | 譲渡所得税が発生 | 合意形成が難しい |
| 寄付・隣地所有者への譲渡 | 自治体や隣地所有者に譲渡・寄付 | 受け入れ先の条件による | 受け入れ先が見つからない場合がある |
| 相続土地国庫帰属制度 | 不要な土地を国に引き渡す制度 | 審査手数料1万4千円+負担金約20万円 | 要件が厳格、全員の同意が必要 |
家族間で情報共有とコミュニケーションを図る
三世代相続を円滑に進めるためには、家族間の情報共有とコミュニケーションが非常に重要です。相続財産や不動産、預貯金、保険などの資産内容について、家族全員が正確に把握してください。どこに、どのような財産があるのか、遺言書の有無などを事前に確認しましょう。
家族会議を開いて、相続の希望や不安、親の意向などを話し合うことも大切です。話し合いの場を設けることで、家族全員が相続の考え方や、価値観を共有できます。誤解や感情的な対立が防げるのです。また、家族全員が相続のプロセスに関わることで、責任感が生まれます。将来的な家族間の不和も減らせます。
家族間で情報共有することは、三世代にわたる資産承継と家族の絆の強化、相続トラブルの対策に欠かせません。必要に応じて、専門家のアドバイスを活用して、家族全体で相続問題に向き合いましょう。
専門家への依頼を検討する
三世代相続を円滑に進めるためには、専門家の力を積極的に活用してください。相続には、法律や税金、不動産の手続きなど、多岐にわたる知識が必要になります。家族だけで対応すると、思わぬトラブルや負担が発生するかもしれません。
税理士は、相続税の計算や申告、財産評価、節税対策の提案などのサポートを行います。特に、不動産や非上場株式など、評価が難しい資産がある場合には、税理士の専門的な知識が必要です。弁護士は、遺産分割協議や相続人同士のトラブルを解決します。相続協議がまとまらない場合や、対立が生じた際には、弁護士の介入で冷静かつ公平な解決が期待できるでしょう。
司法書士は、不動産の相続登記や相続放棄の手続き、戸籍の収集、相続関係説明図の作成など、法的な手続きを行います。不動産の相続登記を怠ると、今後の活用や売却に支障が出る可能性があります。そのため、司法書士のサポートも欠かせないでしょう。
行政書士は、戸籍収集や財産の名義変更手続きなど、書類作成や事務手続きを代行します。このように、三世代相続では複数の専門家が連携して、それぞれの分野で家族をサポートします。家族会議や相続設計の場に、専門家が同席することで、感情的な対立が避けられます。早い段階から専門家に相談して、家族の状況や希望に合った対策を検討しましょう。
| 専門家 | 主な役割・サポート内容 | 相談が有効な場面・特徴 |
| 税理士 | ・相続税の計算・申告 ・財産評価 ・節税対策 ・生前贈与や遺言書作成のサポート | 相続税が発生する場合や、節税・財産評価が必要な場合 |
| 弁護士 | ・遺産分割協議のサポート ・相続人間のトラブル解決 ・法的紛争への対応 | 相続争い・トラブルが発生した場合や、法的な判断が必要な場合 |
| 司法書士 | ・不動産の相続登記 ・相続放棄の手続き ・戸籍収集 ・相続関係説明図の作成 | 不動産の名義変更や、法的手続きを正確に進めたい場合 |
| 行政書士 | ・戸籍収集 ・財産の名義変更手続き ・各種書類作成の代行 | 書類作成や事務手続きの負担を減らしたい場合 |
相続は「受け継ぐ」だけではなく「整える」こと

相続は単に財産を「受け継ぐ」だけではありません。次の世代、その先の世代へと、円滑に承継できるように「整える」ことが重要です。特に、三世代相続を見据える場合、被相続人の財産を把握する必要があります。分割しにくい不動産や、自社株の対策を講じることで、相続人の負担や将来のトラブルを大きく減らせます。
不動産が複数ある場合は、売却や活用方法を事前に決めておきましょう。また、預貯金を複数の金融機関に分散している場合は、できるだけ集約してください。通帳やカードの保管場所なども、家族で共有することがおすすめです。財産目録やエンディングノートの作成で、相続財産の全体像が把握しやすくなります。遺産分割や、相続放棄の判断もスムーズに進むでしょう。
このような準備を行うことで、相続手続きの混乱や申告漏れなどのリスクが避けられます。精神的・事務的な負担も大きく軽減できます。相続は「受け継ぐ」だけでは終わらないのです。次世代が安心して、資産を引き継げるように「整える」ことが、三世代にわたる円満な資産承継につながります。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼