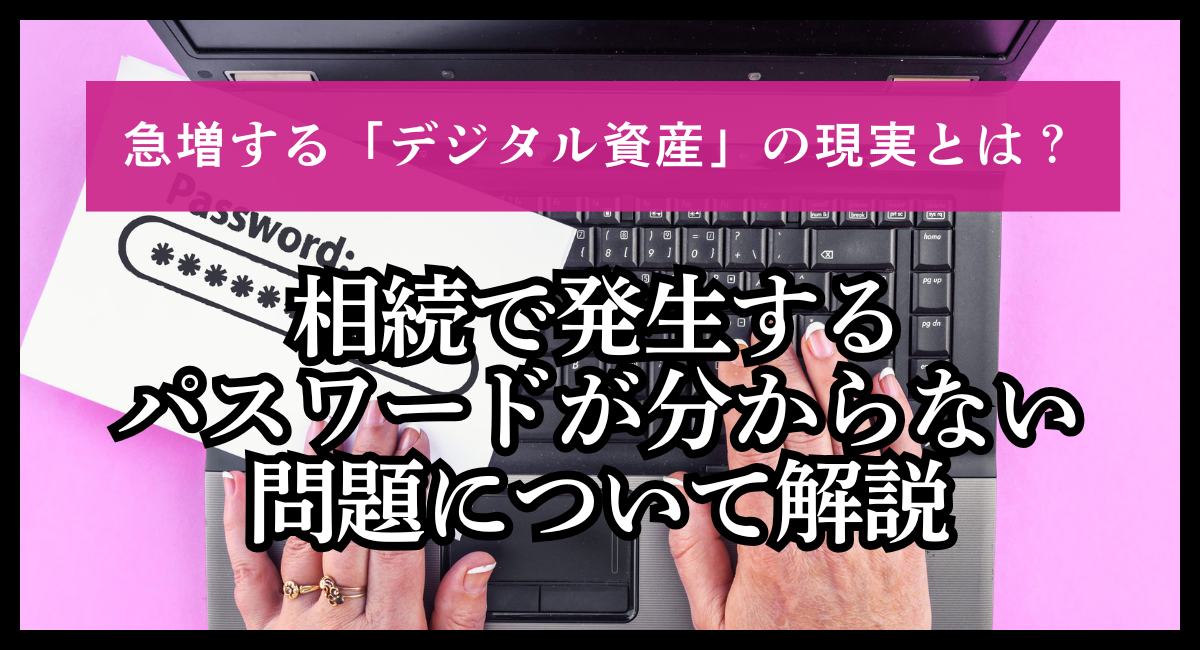スマホやパソコン、オンライン口座、SNSなど、現代人が生前に残す「デジタル資産」は年々増加しています。これらは、物理的に目に見える遺品とは異なります。アクセスするには、IDやパスワードが必要不可欠です。
しかし、相続の現場では「パスワードが分からない」「ログインできない」などの問題が多発しています。財産の確認や手続きが進まないケースも少なくありません。今回の記事では、急増するデジタル資産の現実と、それに伴って浮上するパスワードの問題、相続時に必要な対策について、分かりやすく解説します。
デジタル資産相続で最初に意識するべきポイント

故人のスマホやパソコンに関して、多くの遺族が扱いに困るケースが増えているのです。スマホやパソコンには、写真やメッセージ、各種アカウント情報などの、デジタルデータが保存されています。これらを「デジタル資産」と呼びます。物理的なスマホやパソコンは、目に見える有形の遺品です。
一方で、内部に保存されているデジタルデータや知的財産権も、相続の対象になる可能性があります。その取り扱いには、専門的な知識と慎重さが求められます。故人のスマホやパソコンは、遺品以上の価値を持つものであり、適切な対応が必要です。デジタル資産についての理解は相続トラブル防止に役立ちます。
そもそもデジタル資産とは?身近に潜む相続の見えない遺品

故人が生前使用していた、スマホやパソコン内のデータはデジタル資産です。たとえば、写真や動画、メールの履歴、SNSアカウントなどが挙げられます。クラウドサービス、ネット銀行や証券口座、仮想通貨のウォレットなど、デジタル上の資産も含まれます。
端末そのものではなく、端末やインターネット上に保管されたデータや、アカウント情報が主な対象です。身の回りにある見えにくい遺品は、多岐にわたります。具体的には、FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSアカウントです。このようなデジタル資産は、パスワードや認証が必要な場合が多く、家族が存在に気づかないまま、放置されることがあります。
その結果、貴重な思い出や資産の消失、利用料金の請求に関するトラブルが発生するかもしれません。現代では、デジタル上の財産も法律上の相続対象として扱われるようになっています。そのため、事前にパスワードやアカウント情報を整理して、遺言書やエンディングノートに記載しておきましょう。
デジタル資産とは、故人が残したデジタル世界の「見えない資産」です。スマホやSNS、クラウド、仮想通貨など、多様なデジタル情報や資産が含まれています。このような情報は、相続の状況において重要な財産です。
相続で注意するべき「デジタル資産」の代表例とは?
先述の通り、スマホやパソコン内の写真、メール、SNSアカウントなどのデジタル資産は、相続の場面において、注意しなければなりません。クラウドサービスの保存データやネット銀行、オンライン証券の口座、仮想通貨の情報も対象になります。オンラインの有料サービスの契約も、相続の対象です。
多くの場合、パスワードやログイン情報は故人のみが把握しています。デジタル資産の所在やアクセス方法がわからない場合は、相続の手続きが煩雑化します。遺産分割の再協議や、相続税の申告訂正を求められるかもしれません。相続後に新たなデジタル資産が見つかると、家族の間でトラブルに発展しやすいです。
故人のネット上のアカウントへ無断でアクセスした場合、不正アクセス禁止法に抵触する可能性もあります。そのため、デジタル資産の管理情報やアクセス権を、遺言書に明記することが法的に安全でしょう。
遺言書以外に、エンディングノートによる管理も行えます。これらを踏まえて、デジタル資産の情報や引き継ぎ方法を「見える化」してください。管理体制を整えることが重要です。故人のプライバシー保護や、相続人の負担軽減にもつながります。
| デジタル資産の代表例とポイント | ||
| デジタル遺品の種類 | 内容 | 注意点・ポイント |
| ネット銀行や、ネット証券の口座 | インターネット上で管理される預金口座や証券口座。通帳がないため、相続人は気づきにくい。 | 存在を把握して、ログイン情報を確認する必要がある。 |
| PCやスマホ内の写真、文章 | 家族の思い出の写真や、趣味の文章などのデジタルデータ。プライバシーに配慮が必要になる。 | 安易に公開せず、相続人間で取り扱いを明確にしなければならない。 |
| SNSやブログ、オンラインゲームなどのアカウント | FacebookやX(旧Twitter)、ブログ、ゲームなどのオンラインサービスのアカウント。放置すると、乗っ取りリスクが高まる。 | アカウントの管理・削除方法を確認して、トラブル回避を図る必要がある。 |
| 仮想通貨や電子マネー、ポイント、NFTなど | ブロックチェーン技術を利用した仮想通貨、電子マネーやマイレージポイント、デジタルアート(NFT)など。経済的な価値がある。 | IDやパスワードなどが無いと、資産にアクセスできない。 |
| オンラインサービスのIDやパスワード、メール、チャットの履歴 | 各種オンラインサービスのログイン情報や、故人のメール履歴。相続手続きの進行で、必要になる場合が多い。 | 生前に整理して、記録することが望ましい。相続手続きが円滑になる。 |
「パスワードが分からない」だけで仮想通貨が消える?
近年、相続トラブルにおいて、仮想通貨ウォレットに関する問題も深刻化しています。たとえば、アクセス不能による資産の喪失です。故人が所有していた仮想通貨の秘密鍵や、復元フレーズは相続人に伝わらないケースが多いです。数千万円規模の資産が、事実上、利用できなくなるケースも発生しています。
仮想通貨には、銀行預金のような復旧システムが存在しません。秘密鍵やリカバリーフレーズなしで資産の取り出しは、現状不可能になります。ウォレットの管理情報を紛失した場合、資産は「消失」状態です。相続人は、仮想通貨の存在を知っていても、利用できなくなります。
故人が仮想通貨を所有した事実を相続人に知らせていない場合、相続手続きが行われません。資産が放置されるケースがあります。このような場合は、相続税申告や遺産分割協議を複雑化させます。相続で後々のトラブルになるのです。
この問題を回避するためには、生前に秘密鍵や復元フレーズを、安全な場所に保管する必要があります。そして、信頼できる家族と、仮想通貨に関する情報を共有しなければなりません。たとえば、遺言書やエンディングノートに仮想通貨の所在や管理方法を明示することで、法的なトラブルも未然に防げます。
家族でも開けない?パスワードが壁になる相続の現実

パスワードが分からない場合、家族や相続人であっても、故人のスマホやパソコンなどの、デジタル機器のロックは解除できません。法律上は、故人のデジタル資産は相続人に引き継がれます。しかし、パスワードが不明の場合は、解除が非常に困難です。このパスワードは「遺された障壁」になります。
解除できないと、ネット銀行の口座や証券の資産確認が取れません。相続の手続きに、支障が出てしまいます。不要なサブスクリプションが、自動更新されて料金が発生し続けます。大切な写真や仕事のデータが、取り出せない問題も生じるでしょう。個人情報が悪用されるリスクもあります。
このような問題を回避するには、生前に家族とのパスワード共有が必要です。いわゆる「デジタル終活」として、ログイン情報を管理することが大切です。一方で、SNSアカウントの場合、契約内容によっては、相続財産とみなされません。
パスワードが判明しても、アカウントの削除や追悼設定など、遺族は限られた対応になります。現在の日本の法制度では、デジタル資産に関する取り扱いが十分に整備されていません。パスワードは相続人にとっても、簡単には突破できない「遺された障壁」です。
| デジタル資産のパスワード管理と解除の障壁 | |
| 項目 | 内容 |
| セキュリティ体制 | 多くのデジタル機器や、クラウドサービスに厳格な本人確認のセキュリティ体制が導入されている。 |
| 書類の提出 | 相続人は戸籍謄本、遺言書、死亡証明書などの、書類を提出する必要がある。 |
| アクセス権 | サービス提供者や、機器メーカーのプライバシー保護や内部規定により、アクセス権がすぐに認められない。 |
| 手続き | 一部サービスでは手続きを受け付けない、または非常に限られた条件でのみ、解除を認めない場合がある。 |
| デジタル終活の重要性 | 上記の状況を踏まえて、デジタル資産の相続を円滑に進める「デジタル終活」が重要になる。 |
| 相続手続きの特徴 | 故人の戸籍謄本や遺言書、死亡証明書、相続人の本人確認書類などが必要になる。各サービスで手続きや審査基準が異なる。 |
| 仮想通貨などの場合 | 取引所に連絡して、残高証明書取得や遺産分割協議、解約申請など、複数段階の手続きを行わなければならない。 |
| 電子署名付き文書や書類提出の必要性 | 手続きに電子署名付の電子文書が求められる場合がある。戸籍謄本などは、現段階で紙書類の提出が必須になる。 |
| 生前準備・デジタル終活 | 遺言書の記載やパスワード管理の共有、不要サービスの解約など、生前に準備することで相続を円滑にできる。 |
| 専門家の利用について | 相続人が複雑な手続きを理解して準備するために、専門家の助けを借りることが望ましい。 |
デジタル資産へのアクセスは厳格な審査が求められる
多くのデジタル機器やクラウドサービスには、厳格な本人確認のセキュリティ体制が導入されています。相続人が戸籍謄本や遺言書、死亡証明書などの書類を提出しても、厳格な審査が必要です。
サービス提供者や機器メーカーのプライバシー保護、内部規定によって、アクセス権がすぐには認められません。手続きを受け付けないサービスや、非常に限られた条件のみで、解除される場合もあります。このような状況を踏まえて、デジタル資産の相続を円滑に進めるために「デジタル終活」もおすすめです。
デジタル資産の相続におけるパスワードの難題
デジタル資産の相続でパスワードは「遺された障壁」です。ネット銀行や仮想通貨、SNSアカウントなど、多くのデジタル資産は、パスワードで保護されています。本人が遺したパスワードが分からない場合、相続人は、デジタル資産にアクセスできません。大切なデータが残されたままになります。このような状況は、相続手続きにおいて大きな障害です。
先述の通り、生前に遺言書やエンディングノートを活用して、パスワードの所在や管理方法を明確にしましょう。パスワード管理アプリで、信頼できる家族や専門家と、安全に共有する方法も有効です。しかし、セキュリティやプライバシーの観点から、すべての情報を公開する必要はありません。漏えいリスクを抑えながら、適切に情報を伝える配慮が求められます。
知らずに行うと危ない!相続で起きる解除失敗のリスク

相続の場面では、手当たり次第にロック解除を試みるのは、リスクが高い行為です。スマホやパソコンには、パスワードを一定回数間違えると、データが消える仕組みがあります。不注意な操作で、大切な情報が失われるかもしれません。
不正アクセス禁止法によって、正当な権限のない他人のID・パスワードで、システムへアクセスすることは、禁止されています。違反した場合、罰則が科せられます。ITに不慣れな家族が対応すると、操作ミスによるアカウント停止や、法令違反につながるでしょう。問題が複雑化する恐れがあります。
間違った解除方法でデータが消去されるリスク
近年のスマホやクラウドサービスは、セキュリティが非常に強化されています。パスコードを複数回間違えて、不正アクセスだと判断した場合、自動的にデータが初期化される可能性があるのです。
「思い出の写真が消えた」「金融情報や契約書類のデータが閲覧できない」などのトラブルが発生しています。国民生活センターも注意を呼びかけています。また、金銭や契約に関わるデジタルサービスの場合、解約の手続きを適切に行わなければなりません。経済的な損失が発生するリスクもあります。
不正アクセス禁止法違反などの法的リスクについて
デジタル資産において、パスワードの解除やデータ復元を行う専門業者が増えています。パスワードを調べる過程で、遺族は「不正アクセス禁止法」に注意しなければなりません。デジタル資産には、第三者の個人情報や、著作権に関わるデータも含まれています。
これを無断で扱うことによって、法的な問題をさらに引き起こします。このようなリスクを回避するためには、専門家への相談がおすすめです。専門家のサポートを活用しながら、デジタル資産の相続・整理を進めましょう。
専門業者による「デジタル資産対応サービス」とは

専門業者が提供する「デジタル資産対応サービス」とは、故人のデジタル機器に保存された情報を、専門的に整理・管理・処分するサポートです。たとえば、パソコンやスマホ、クラウド上のデータなどが挙げられます。写真や動画、SNSアカウント、ネットバンキングの情報など、さまざまなデジタル資産が増えています。このようなデータを放置することで、遺族の負担や個人情報の漏えいリスクを招くでしょう。
専門業者は、データの抽出や削除、機器の初期化、パスワード解除などを代行します。大切な情報を守りながら、デジタル資産の整理をサポートするのです。これによって、遺族の負担が軽減されます。トラブルの予防や、生前整理の一環としても、注目されています。
デジタル資産の整理・復元を専門に扱う業者の存在
デジタル資産の整理は、個人や家族だけでは、対応が難しいケースが多いです。専門知識と技術を持つプロに依頼することで、安全にデジタル資産の整理が進められます。専門業者は、パソコンやスマホのロック解除、データ復旧・削除などを取り扱っています。
金融資産やデジタル契約サービスの確認、解約サポートなども幅広く対応するのです。高いデータ復旧成功率を誇る企業もあります。このような専門業者に依頼することで、トラブルやデータ消失のリスクを回避できる可能性が高いです。
技術的に適切な手順で、デジタル資産の整理が行えます。デジタル資産業者の利用を検討する場合は、対応実績や費用、サポート内容を事前に確認しましょう。
高齢世帯・遠方の家族の強い味方にもなる専門業者
デジタル資産業者は、特に高齢者世帯や遠方に住む家族にとって、心強い存在です。故人のスマホやパソコンのロック解除、データ抽出など、デジタルに関する各種手続きを、安全に代行してくれます。
遠方に住む家族が現地に行かなくても、書類やオンラインのやり取りで依頼できるサービスも増えています。そのため、時間や距離のハードルも大幅に軽減できるのです。デジタル資産だけではなく、物理的な遺品整理をまとめて依頼できる業者もあります。
これによって、家族の負担軽減や安心感の向上につながっています。「何から手を付けて良いのかわからない」「個人情報やプライバシーの扱いに不安がある」などの悩みを持つ遺族には、専門家の存在は大きいでしょう。
| 高齢世帯のサポートを行う専門業者・サービス一覧 | |||
| 分野 | サービス内容 | 対応例・業者 | ポイント |
| デジタル資産管理 | スマホ・パソコンのロック解除、データ抽出、デジタル遺品整理 | 専門デジタル資産業者 | 遠隔で書類やオンラインで、依頼可能。家族の負担軽減や安心感の向上。 |
| 見守りサービス | 高齢者の金融行動の監視、詐欺の検知、健康や生活リスクの情報共有 | ネットワーク関連企業 | 月額制で、異常検知通知。遠方の家族も見守り参加が可能 |
| 資産管理・運用 | 銀行口座管理、投資管理、生前資産運用 | 銀行や証券会社など | 声紋認証や生体認証導入、高齢者の認知機能低下に配慮した安全管理 |
| 遺品整理 | 物理的遺品整理の代行 | 遺品整理専門業者 | 遠方でも依頼が可能。家族の負担が減少。 |
| 生前支援・相続 | 遺言書作成支援、相続税対策、エンディングノート作成 | 相続サービス関連業者 | オンライン遺言作成、専門家との連携でトラブル防止。 |
| 司法書士・弁護士との連携 | 財産管理、死後事務委任契約、長期入院・施設入居時の代理対応 | 司法書士・弁護士の連携サービス | 契約によって、法的な安全性を確保。 |
| 健康・生活支援 | 高齢者の健康見守り、リスク情報の家族共有 | ネットワーク関連企業 | 生活リスクを可視化。家族の不安を解消。 |
デジタル資産を安心して任せられる業者と費用感

専門業者を選ぶ際には、さまざまなポイントを確認しましょう。「総務省の登録」がある業者は、大きな安心感があります。専門業者は、ロック解除やデータ復元の技術力も必要です。公的機関からの依頼実績がある業者は、専門力が高いと判断できます。プライバシー保護や、セキュリティ対策が万全であることも大切です。
たとえば、スマホ1台のロック解除やパスワードの解析は、一般的に1万円から5万円程度が相場です。データの復元費用に関しては、機器の状態や数によって異なりますが、1万円から数万円程度の見積もりが多いです。
一方で、悪質な業者の存在にも注意しなければなりません。見積もり内容が不明瞭で、説明が十分ではないケースがあります。先述の通り、遺品整理やデジタルデータの取り扱いは、専門知識が必要です。依頼前に契約内容を確認して、安心できる業者を選びましょう。
総務省登録とデジタル機器対応実績で見る業者の信頼性
電気通信事業法に基づいて、電気通信事業を営む業者は、総務大臣の登録を受けなければなりません。この登録は、事業計画の合理性や経営基盤、体制の整備などを審査します。登録を受けている業者は、法令遵守の体制が整っている信頼の証です。
「デジタル機器対応実績」の有無も重要な判断基準になります。デジタル機器のパスワード解除やデータ復元が豊富であることは、その業者の技術力と安全管理能力を示します。デジタル資産を扱う場合には、機器の安全性や秘密情報の保護が求められます。
対応実績のある業者を選ぶことで、大切なデータを守りたい遺族も安心できるのです。法律・規制を遵守しながら、高い技術力で、デジタル資産の管理や復元を行える業者に依頼しましょう。
スマホロック解除とデータ復元の費用相場
一般的に、スマホのパスワード解除費用は、数万円ほどから始まります。機種やロックの種類によっては、10万円以上かかる可能性があります。複雑なロック解除や高度な解析が必要な場合は、費用がさらに高くなる点には留意してください。
データ復元の費用は、復元する内容や端末の破損状態によって、大きな幅があります。数万円から数十万円になる場合が多いです。特に、暗号資産が関係するケースでは、専門業者による対応が必要になります。
暗号資産取引所の取引手数料や、出金手数料は数百円から数千円前後です。一方で、パスワード解除やデータ復元は、通常の取引所サービスには含まれません。専門業者への依頼が一般的です。このように、パスワード解除やデータ復元などは、本体の状態や作業の難易度によって、費用が変化します。正確な費用は専門業者に直接相談して、見積もりを取ることが必要です。
| 専門業者におけるデジタル資産の作業項目と費用相場(目安) | ||
| 作業内容 | 費用(目安) | 備考 |
| パスワード解除 | 2万円〜5万円程度 | 機種やロック種類、作業難易度によって変動する。解除成功時に、料金発生が多い。 |
| データ復元(軽度障害) | 数千円〜数万円程度 | 軽度の障害などが該当する。端末の状態によって、費用が変動する。 |
| データ復元(重度障害・物理破損) | 数十万円程度(20万円〜100万円前後) | 物理破損や重度の障害が該当する。復旧期間やデータ容量によって、費用が大きく異なる。 |
| データ復元(容量別目安) | 500GB未満:5,000円〜 1TB以上:2万〜3万円〜 | 容量や障害箇所によって、価格が変動する。 |
| 暗号資産関連の復元 | 数十万円〜 | 秘密鍵やウォレット復元など、高度な技術が必要になる。専門業者への依頼が推奨される。 |
デジタル資産の相続トラブルが起きる前に活用する「エンディングノート」

デジタル資産の相続トラブルを防ぐには、エンディングノートの活用が役立ちます。ネット銀行や証券口座、仮想通貨などの資産情報だけでなく、アカウントIDやパスワードなどを、一緒に記載してください。登録したメールアドレスやスマホ・パソコンのロック解除方法も欠かせません。
SNSやサブスクリプションの契約内容、アカウント削除の手順などの内容も、エンディングノートへまとめておきましょう。これによって、家族が資産を円滑に引き継ぐことができます。相続手続きの混乱を、大幅に減らせます。エンディングノートに情報をまとめることで、デジタル資産の全体像が家族に伝わりやすいです。
資産の発見や名義変更、解約などもスムーズに進みます。相続漏れや誤解、税務申告の遅れなど、トラブル発生リスクも軽減されます。エンディングノートは、金庫やセキュリティが整っている場所に置いておきましょう。そして、家族へ所在を知らせておくのがポイントです。パスワードの管理や、機器自体は別々にしてください。
盗難や不正ログインを防ぐ工夫も、必要になります。内容の見直しや、更新を定期的に行って、最新の状態を維持することも大切です。たとえば、情報を一本化したことで、遺族がすぐに資産内容を把握できる事例があります。
エンディングノートの存在が伝わっておらず、相続の手続きが、複雑化した失敗談も存在するのです。エンディングノートは、法律上の効力はありません。しかし、デジタル資産の調査や相続のサポートにつながります。このように、早めにエンディングノートを準備して、家族と情報共有することで、デジタル資産をめぐる相続問題の多くを防げるのです。
| 相続トラブルが起きる前に活用できるエンディングノート | ||
| 項目 | 内容例 | ポイント・注意点 |
| 記載する情報 | ・ネット銀行、証券口座のアカウントID、パスワード ・仮想通貨のウォレット情報 ・登録メールアドレス ・スマホ、パソコンのロック解除方法 ・SNSアカウント情報 ・サブスクリプション契約内容 ・アカウント削除、解約手順 | 体系的にまとめて、遺族が手続きしやすいようにする。 |
| 保管場所 | 金庫をはじめとした安全な場所に保管する。 | 所在を信頼できる家族へ伝える。 |
| 管理の工夫 | パスワードや機器本体は、別々に管理する。 | 盗難や不正ログインのリスクを軽減する。 |
| 定期的な見直し、更新 | ノートの内容を最新にする。 | 変化した情報に合わせて、更新する必要がある。 |
| メリット | 不要な口座を解約して、情報を統一できる。遺族が資産を把握しやすくなる。 | 相続の情報が一本化される。 |
| デメリット | エンディングノートの存在が伝わらない場合、手続きが複雑化してしまう。 | 遺族への周知が重要になる。 |
| 法的効力 | なし(参考資料として役立つ)。 | 遺産の分配意思を明確にする場合、遺言書の作成も検討する。 |
最後に:解決できないときはプロに任せるという選択肢

故人のスマホやパソコンには、思い出や大切な資産が多く保存されています。しかし、このようなデジタル資産の整理は、遺族のみで行うと、時間と労力がかかります。専門知識も必要です。そのため、生前のデジタル資産に関する終活が大切になります。生前の対策としては、エンディングノートが有効です。
パスワードやアカウント情報をあらかじめ残すことで、遺族の負担が軽減できます。しかし、家族の間でパスワードの共有がない場合、スマホやパソコン内部の確認は難しいです。大切なデータや資産も調べられません。そのような状況においては、デジタル資産の整理を専門のプロに任せることがおすすめです。
デジタル資産整理の専門業者は、パスワード解析やデータの抽出、不必要なデータの消去まで、幅広く対応します。大切な思い出や資産も、安全に守れます。専門の技術によって、データ復旧や削除、個人情報の保護、故人のオンライン資産の把握が可能です。
前提として遺族は、突然の相続で心の整理が必要になります。気持ちの整理が付かない状況で、煩雑な手続きを進めなければなりません。そのため、専門家にデジタル資産の整理を任せることは、思い出と資産を守る有効な方法でしょう。相続トラブルを防ぐためにも、デジタル資産に関する終活と、日頃の家族間での情報共有が大切です。