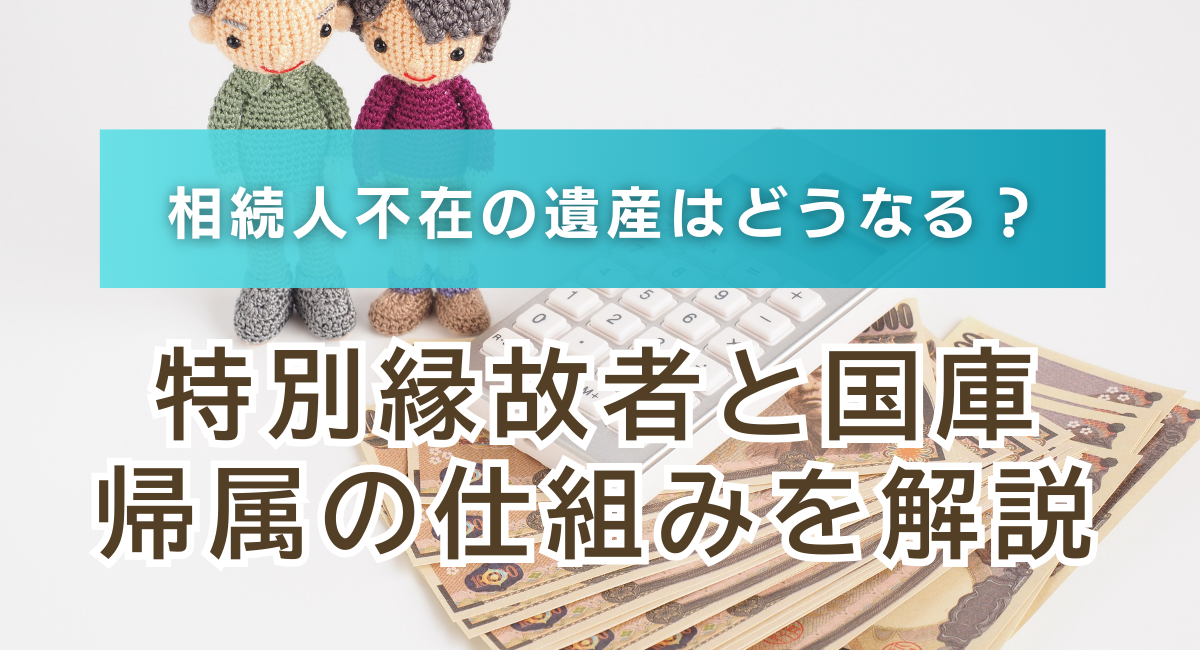高齢化や単身世帯の増加で、相続人がいない状態で亡くなるケースが問題視されています。親族との関係が希薄であったり、生涯独身を貫いたりする人も、現代では珍しくありません。「遺産はあるけれど、相続人がいない」という状況は、特別な事例ではないのです。相続人が不在の場合、遺産は国庫に帰属されます。つまり、国のものになります。
一方で、長年介護をしていた内縁のパートナーや、献身的に支えた友人などが活用できる、特別縁故者制度も存在するのです。今回の記事では、相続人が不在の場合の、遺産相続の流れを紹介します。「特別縁故者」とは、どのような制度であるのか、遺産がどのように国庫に帰属されるのかに関して、具体的に解説していきます。
「相続人不在」の社会的背景について
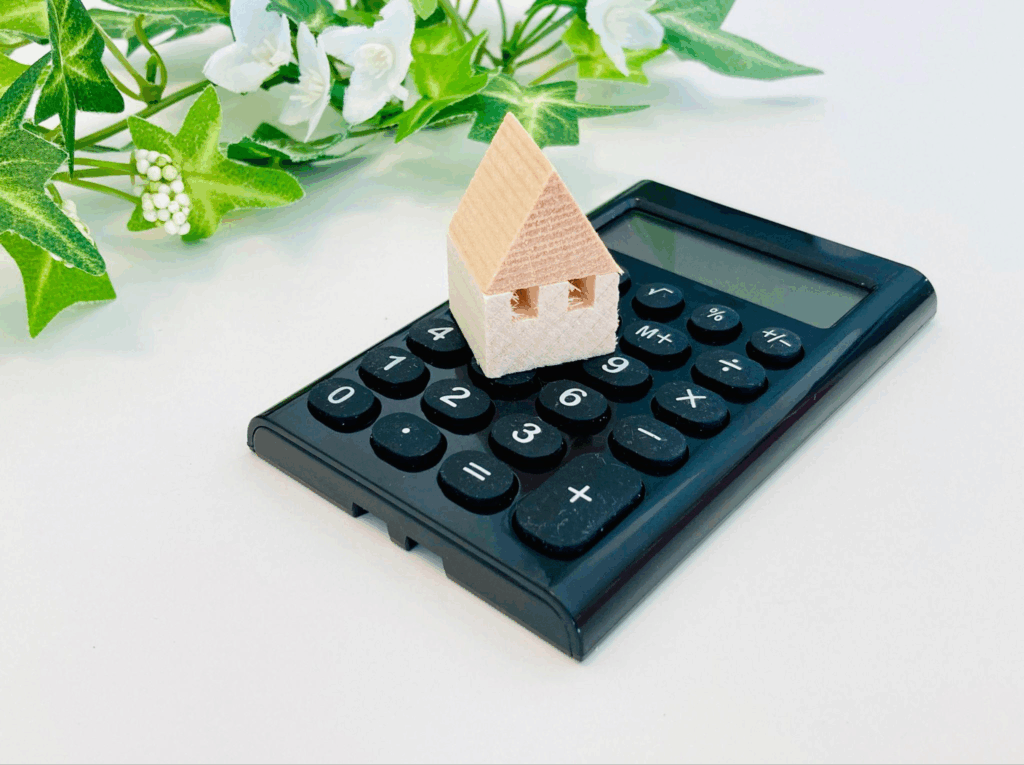
日本では「相続人不在」の現象が増加傾向です。その背景には、様々な社会的要因が絡み合っています。まず、少子高齢化の進行によって、高齢者の割合が増えています。子どもを持たない高齢者が多いのも現状です。
未婚率の上昇や、単身世帯の増加も大きな要因になります。結婚しない人や、結婚しても子どもを持たない世帯が増えました。結果として、配偶者や子どもなどの法定相続人が、不在になる事例が目立っています。
さらに、都市部への人口集中と、地方の過疎化も影響しています。地方に残された高齢者が亡くなった場合、相続人が遠方にいる、もしくは全くいない状況が生まれているのです。遺産に負債が多い場合や、固定資産税の負担を避けるために、相続を放棄するケースも増えています。核家族化や地域コミュニティの弱体化で、親族間の交流の減少も進んでいます。
このような社会的な背景のもと、相続人不在の遺産や、関連した不動産が注視され始めました。所有者が不明な土地の増加や、行政負担の増大なども深刻化しています。この傾向は、今後も続く可能性があるため、社会全体での対応が必要になるでしょう。
「相続人不在」における遺産の流れと手続き

相続人がいない場合の遺産の扱いは、法律に基づいた特別な手順が定められています。まず、被相続人の戸籍を辿ります。法定相続人が本当に存在しないかを、慎重に確認するのです。相続人が見つからない場合、利害関係者や検察官が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。管理人には、通常、弁護士などの専門家が選出されます。
管理人が決まると、官報などを通じて、相続人を探すための公告が行われるのです。この公告は、最低でも6か月間続きます。その間に被相続人に対して、もしくは債権を持つ人や、遺言で財産を受け取る予定の人にも、請求の機会が与えられます。申し出がある場合、その分の支払いが優先される仕組みです。
公告期間の終了後、相続人が現れない場合があります。被相続人と特別な関係にあった人は、家庭裁判所に対して、遺産分与の申し立てが行えます。遺産の分与に関しては、家庭裁判所が、関係性や貢献度などを考慮して判断するのです。
特別縁故者への分与がなかったり、分与後に財産が残ったりした場合には、最終的にその遺産は国のものとなります。全ての手続きが終わった後は、相続財産管理人が家庭裁判所に報告を行います。それによって、管理業務が完了する流れです。このように、相続人がいない場合でも、遺産は段階的な法的手続きを経て、最終的な帰属先が決まる仕組みになります。
| 手続きの段階 | 内容 | 主な申立人・関係者 | ポイント・注意点 |
| 相続財産清算人の選任申立て | 家庭裁判所に相続財産清算人(管理人)の選任を申し立てる | 利害関係人、検察官など | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立て |
| 法定相続人の捜索・公告 | 官報等で公告し、法定相続人がいないか調査 | 相続財産清算人 | 公告期間は通常6ヶ月 |
| 債権者・受遺者への対応・財産整理 | 債権者や受遺者への弁済、遺産の整理 | 相続財産清算人 | 借金や遺贈があればこの段階で清算 |
| 相続人不存在の確定 | 公告期間満了後も相続人が現れなければ「相続人不存在」が確定 | 家庭裁判所 | ここで初めて特別縁故者申立てが可能 |
| 特別縁故者への分与申立て | 特別縁故者として財産分与の申立てを家庭裁判所に行う | 特別縁故者(申立人) | 申立ては公告期間満了から3ヶ月以内 |
| 特別縁故者の認定・分与決定 | 家庭裁判所が特別縁故者として認定し、財産分与の内容を決定 | 家庭裁判所、特別縁故者 | 分与額や範囲は裁判所が総合的に判断 |
| 財産分与の実施 | 認定された特別縁故者に実際に財産が分与される | 相続財産清算人、特別縁故者 | 分与財産は相続税課税対象 |
相続人がいない場合の対応策?特別縁故者制度とは

特別縁故者制度は、被相続人(亡くなった方)に、法定相続人がいない場合に適用される制度です。相続人がいない場合、被相続人の遺産は、最終的に国のものになります。しかし、被相続人と生前に特別な関係があった人や、療養看護などで、大きな貢献をした人もいるでしょう。その人が遺産の全部、または一部を受け取れるのが「特別縁故者制度」です。
特別縁故者として認められるためには、一定の条件があります。例えば、被相続人と生計を同じくしていた人や、長期間にわたって療養看護に努めた人などが該当します。具体的には、内縁の配偶者や事実上の親子関係にあった人です。長年にわたって、介護や生活の支援を行った知人も挙げられます。
この制度を利用するには、まず、相続人がいないことを家庭裁判所で確認する必要があります。それによって、相続財産管理人が選任されます。その後、特別縁故者となりうる人が、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。裁判所が、判断して、遺産の分与を決定します。分与の申請が認められた場合、その人は遺産を受け取れるのです。
特別縁故者制度は、法定相続人が一人でもいる場合には利用できません。家庭裁判所の判断に大きく左右されるため、申立ての際には、具体的な証拠や事情の説明が重要です。分与された財産に、相続税が課される点にも注意しなければなりません。
特別縁故者制度は、被相続人と深い絆や貢献があった場合に、遺産が受け取れる大切な制度です。手続きや証明には、専門的な知識が必要になります。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
特別縁故者制度の創設の背景と役割
特別縁故者制度が創設された背景には、戦後の民法改正による、相続人の範囲縮小があります。日本の旧民法では、戸主制度や家督相続制度が存在しました。相続人の範囲が、広く設定されていたのです。相続人が全く存在しないケースはほとんどありませんでした。
現行の民法では、相続人の範囲が限定されます。法定相続人がいない状態で、被相続人が亡くなってしまうのです。それによって、遺産を国庫に帰属する事例が増加しました。また、日本では遺言を残す人が少ない傾向にあります。急な死亡などで、遺言が用意できない場合も多いです。
そのため、被相続人と生前に特別な関係があった人が、法律上は遺産を受け取れない問題が発生していました。特に、内縁の配偶者や、長年介護に行った親族などが挙げられます。このような事情を踏まえて、特別縁故者制度は、1962年の民法改正で導入されました。
相続人がいない場合でも、特別な縁故があった人が、家庭裁判所の判断で遺産が受け取れるようになったのです。特別縁故者制度は、遺言や遺贈制度を補完する役割を持ちます。被相続人と深い関係や貢献があった人を、救済するための大切な制度です。
特別縁故者になり得る人とは?
特別縁故者に該当する具体的な例としては、内縁の配偶者が挙げられます。法律上の婚姻関係がなくても、実質的に夫婦として暮らした場合、特別縁故者と認められる可能性があります。また、戸籍上、親子関係にない事例もあるのです。
実際には、親子同然の関係で生活していた人、いわゆる事実上の養子や養親です。相続権のない親族でも、被相続人と生活を共にしていた場合は、特別縁故者とみなされるケースがあります。また、被相続人の療養や介護に長期間携わった親族や友人、知人なども対象です。
入院中の世話や生活の援助、葬儀の手配など、被相続人のために献身的に尽くした人が、このような事例に当たります。被相続人の生活を経済的・精神的に支えた友人や知人に関しても、特別縁故者として認められる場合があります。
身元引受人や、任意後見人として日常的にサポートした人も該当します。このように、特別縁故者は血縁や法律上の関係に限りません。被相続人との深い結びつきや、具体的な貢献が認められる場合に、家庭裁判所の判断で幅広く認定されるのです。
| 該当区分 | 具体例 | 備考 |
| 被相続人と生計を同じくしていた者 | 内縁の配偶者、事実上の養子、叔父・叔母、継子、子の配偶者、同居していた親族・知人 | 同居していなくても生活費等の援助があれば該当する場合あり |
| 被相続人の療養看護に努めた者 | 長期間介護・看護を行った親族や知人、日常的な世話をした人 | 報酬を受けている職業従事者は、特別な事情がない限り該当しない |
| その他特別の縁故があった者 | 被相続人の世話をしていた人、扶養していた人、菩提寺、老人ホーム、勤務先、地方自治体等 | 法人も該当する場合あり。個別事情ごとに家庭裁判所が判断 |
| 過去の裁判例で認められた具体例 | 甥の妻、従兄弟の子、義理の妹、実子でないが子のように育てた甥姪、精神的支援をした友人等 | 被相続人との密接な関係や貢献の内容が重視される |
特別縁故者の申立てから認定・分与の流れ
被相続人に法定相続人がいない場合、家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を申し立てます。相続財産管理人が選任されると、その人が、被相続人の財産の調査や管理、債務の清算などを行うのです。相続財産管理人は、債権者や受遺者に対して、官報などで公告を行います。
その後、家庭裁判所の指示に従って、法定相続人が本当に不在なのかを調査します。公告期間(通常6ヶ月以上)が経過しても、相続人が現れない場合、「相続人不存在」が確定する流れです。相続人不存在が確定した後、特別縁故者になり得る人は、家庭裁判所へ財産分与の申し立てができます。
この申立ては、相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内に行わなければなりません。家庭裁判所は、提出された資料や関係性などを審査します。特別縁故者として、認めるかを判断します。認定された場合には、相続財産の全部、または一部が分与されます。
分与される財産の範囲や割合は、様々な事情を考慮します。例えば、被相続人との関係の深さや貢献度、財産の規模、他の特別縁故者の有無などです。実際に、分与された財産は「相続による取得」とみなされます。つまり、相続税の課税対象になるのです。
全体の手続きに関しては、1年以上かかることが多いです。申立ての期限を過ぎた場合は、権利を失うため、特別縁故者になり得る人は注意しなければなりません。手続きや必要書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で確認しましょう。
| 手続き段階 | 主な内容・流れ | 必要書類・費用例 | 期間・ポイント |
| 申立て準備 | 利害関係人などが、家庭裁判所に申立てを行う | ・申立書 ・被相続人の出生~死亡までの全戸籍謄本 ・住民票除票 ・財産資料など | 収入印紙、郵便切手、官報公告料 |
| 予納金の納付 | 財産が少ない場合、申立人が予納金を納付する | 予納金額は裁判所が指示(報酬等に充当) | 申立から1ヶ月程度 |
| 相続財産管理人の選任 | 家庭裁判所が審判して、管理人を選任・公告する | 資格要件なし(弁護士・司法書士が多い) | 申立から2ヶ月程度 |
| 相続人の捜索・公告 | 官報で相続人捜索の公告を行う(6ヶ月以上) | 官報公告料 | 公告期間6ヶ月以上 |
| 債権者・受遺者への公告 | 債権者・受遺者に請求申出を促す公告をする | – | 公告と並行、または同時に実施 |
| 相続人不存在の確定 | 公告期間満了後も、相続人が現れなければ「不存在」確定する | – | |
| 特別縁故者の申立て | 特別縁故者が3ヶ月以内に、財産分与の申立てを行わなければならない | ・申立書 ・関係性を証明する資料 | 期限の厳守(期限が過ぎると、権利が喪失) |
| 家庭裁判所の審査・分与 | 関係性や貢献度などを考慮して、全部または一部を分与する | – | |
| 残余財産の国庫帰属 | 分与後も残れば国庫に帰属 | – | |
| 報酬・費用の精算 | 管理人の報酬は原則相続財産から支払い、足りない場合は予納金で補填 | – |
家庭裁判所での判断基準について
特別縁故者制度において、家庭裁判所は法律上の要件のみで判断しないのです。被相続人との実際の関係性や、貢献の具体的な内容を重視します。被相続人と申立人が生計を同じくしていた場合には、単なる同居だけでは認定されないケースがあります。
生活費をどのように分担していたのか、家計を一緒に管理していたのかなど、生活の実態が重要な要素になります。住民票の記載や銀行口座の動き、家計簿など、実際に生活を共にしたことを裏付ける、客観的な証拠が重視されるのです。また、被相続人の療養や看護に努めていた場合には、その期間や具体的な支援内容が評価されます。
診療記録や介護記録、関係者の証言なども有力な証拠になります。「その他特別の縁故があった者」として認められるには、単なる友人や知人の関係では要件を満たしません。社会通念上、特別な結びつきがあったのかを判断します。
長年にわたる精神的・経済的な支援や、被相続人にとって、不可欠な存在であったことなどです。これらの事情を裏付ける、客観的な資料や証拠も必要になるケースがあります。最終的には、財産分与を受ける社会的・道義的な必要性や、分与額の相当性も考慮されます。
相続トラブルを回避するために!国庫帰属の仕組み
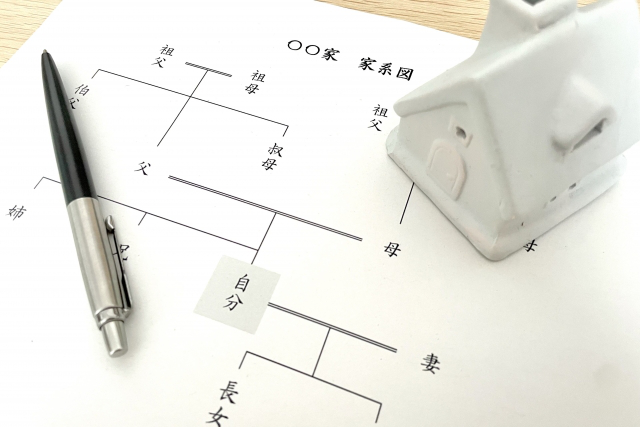
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月から施行された新しい仕組みです。この制度は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たすことで、国に引き渡せるのです。近年では、相続した土地を管理できずに、放置するケースが増えています。
利用する予定のない土地や、遠方の土地を持ち続けることは、所有者にとって大きな負担です。このような土地が放置されると、地域の環境悪化やトラブルの原因になります。制度を利用するには、土地の所有者が法務局に申請して、国による審査を受ける必要があります。
審査において、管理や処分に著しく手間や費用がかかる場合や、土壌汚染、境界争いなどの問題がある土地は、対象外になります。申請が認められた場合、所有者は一定額の負担金を納めなければなりません。しかし、その後に土地の所有権と管理責任を国へ移せます。この制度によって、不要な土地を手放したい人は、相続放棄をせずに、土地だけを国に引き渡せるのです。
国庫帰属までの具体的な手続きを解説
土地を国庫に帰属させたい場合は、土地が所在する都道府県の、法務局の不動産登記部門で、事前相談を行いましょう。事前相談では、必要な書類や制度の説明が受けられます。その後、申請者は必要な書類を準備して、法務局に申請書と一緒に提出します。
提出する書類には、土地を取得した証明書や、土地の位置・範囲を示す図面などが含まれます。法務局に申請書類が受理されると、法務局による審査が開始されます。審査では、土地に建物が存在していないのか、土壌汚染や境界紛争がないのか、要件のチェックが行われるのです。
審査には、半年から1年程度かかる場合があります。承認通知が届いた場合、申請者は、通知到達日から30日以内に負担金(原則20万円)を納付しなければなりません。負担金の納付が遅れると、承認が失効して、手続きのやり直しにつながります。
負担金の納付によって、土地の所有権は国に移転します。申請者が、別途登記申請を行う必要はありません。国が所有権移転登記を行います。このように、事前相談、申請書類の提出、法務局による審査、負担金の納付、所有権の国庫帰属という流れで手続きが進むのです。
| 手続き段階 | 内容 | 主な提出書類・ポイント |
| 事前相談 | 管轄法務局(本局)で事前相談を行い、対象可否や必要書類の説明を受ける | 相談予約が必要 |
| 申請書類の提出 | 必要書類を準備し、法務局本局に申請書とともに提出 | 申請書、土地の位置・範囲図面、境界点写真、現地写真、印鑑証明書など |
| 書面調査・実地調査 | 法務局による書類審査および現地調査 | 審査手数料の納付が必要。建物の有無、担保権や境界紛争などの確認 |
| 承認・不承認決定 | 法務局が要件を満たしているか判断し、承認または不承認を決定 | 承認通知書が届く |
| 負担金の納付 | 承認通知到達日から30日以内に負担金(原則20万円)を納付 | 納付が遅れると承認失効 |
| 国庫帰属 | 負担金納付が確認されると、土地の所有権が自動的に国に移転 | 登記申請不要、国が所有権移転登記を行う |
遺産分与における実務上のポイントと注意点

特別縁故者が遺産分与を受けるためには、実務上のポイントや注意点があります。
先述の通り、特別縁故者として主張が認められやすいのは、内縁の配偶者や事実上の家族です。家庭裁判所でも認められる可能性が高くなります。一方で、一時的な関係性や、支援・看護の実態が乏しい場合は、認められにくい傾向があります。
申立ての際には、申立書や戸籍謄本、特別な縁故を証明する資料が必要です。例えば、同居や看護の記録、写真、手紙、領収書などの書類です。これらの証拠資料は、できるだけ多く、客観的なものを用意するのがおすすめです。申立てを認めてもらうためのポイントになります。
分与される財産の種類によっても、手続きが異なります。不動産の場合は、家庭裁判所の審判に基いて、名義変更の登記手続きが必要です。預貯金の場合は、金融機関で審判書を提示してください。払い戻しや名義変更などが行えます。このように、特別縁故者として遺産分与を受けるには、期限内の申立てや十分な証拠、財産の適切な手続きが大切です。
遺言書の作成と信託制度の重要性

特別縁故者制度は、あくまでも例外的な救済措置です。家庭裁判所の審査を経て、初めて認められます。必ずしも、遺産を受け取れるとは限りません。そのため、特別縁故者や法定相続人以外の方に、財産を確実に遺したい場合は、遺言書の作成が不可欠です。
遺言書を作成することで、誰にどの位の財産を譲るかを指定できます。希望通りの相続が実現できるのです。遺言書がない場合、特別縁故者が遺産を受け取るには、裁判所での手続きが必要になります。認められないケースも多く、最終的には、国のものになる可能性があります。
遺言書の内容はいつでも変更や撤回が可能です。一方で、法的な形式も守らなければなりません。大切な人に確実に財産を遺したい場合や、相続トラブルを防ぎたい場合は、早めに専門家へ相談しましょう。遺言書の作成や生前贈与の対策を、把握することも重要です。
遺言書の作成方法とそのメリットを紹介
特別縁故者に財産を遺したい場合、遺言書の作成が確実な方法です。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの作成方法があります。自筆証書遺言は、遺言者自身が全文、日付、氏名を自筆して、押印することで成立します。紙とペンのみで、自宅で作成できるのが特徴です。作成する時の費用もかかりません。しかし、形式に不備があると無効になる恐れがあるため、注意が必要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。遺言者が、内容を口頭で伝えます。公証人が文章化して、遺言者と証人2名が署名押印する流れです。公正証書遺言は、紛失や無効のリスクが少なく、安全性が高いのが特徴になります。
どちらの方法でも、特別縁故者や法定相続人以外に財産を受け渡せます。遺言書には、誰にどの位の財産を残すのかを、明確に記載してください。特別縁故者の氏名や生年月日、住所などを記載することで、意思をより確実に伝えられます。
遺言書の作成では、遺留分などの法定相続人の権利にも配慮しましょう。内容や形式に不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。遺言書は、何度でも書き直しや撤回が可能になります。特別縁故者に財産を遺したい場合は、遺言書を作成して、意思を明確にすることも有効です。
| 区分 | 内容・特徴 | 注意点・必要書類等 |
| 遺言書による遺贈 | ・自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの対応も可能になる ・誰にどの程度の財産を遺すのかを、明記できる | ・遺留分に配慮が必要 ・特別縁故者の氏名・生年月日・住所等を明記 ・形式不備に注意 |
| 特別縁故者制度による申立 | ・法定相続人がいない場合に限る ・家庭裁判所への申立てが必要になる ・認められた場合、財産取得が可能になる | ・申立期限がある(公告から3か月以内) ・証拠書類が多数必要になる ・申立費用・予納金がかかる |
| 特別縁故者の主な要件 | ・生計同一者(内縁、事実婚、同居親族等) ・療養看護に努めた者 ・その他、特別な縁故がある者 | ・生計同一:住民票や家計簿、銀行明細など ・看護:介護記録や領収書、医療機関証明など ・その他:手紙、写真など |
| 申立てに必要な主な書類 | ・申立書 ・被相続人の戸籍謄本 ・申立人の住民票等 ・財産目録 ・縁故を示す資料 | ・家庭裁判所によって、異なる場合がある ・事前確認が推奨される |
| 申立てにかかる費用 | ・収入印紙代 ・郵便切手代 ・書類取得費用 ・官報公告料 ・予納金 | ・予納金は、数十万~100万円程度の場合がある |
生前贈与と信託制度の活用方法
遺言書以外に、特別縁故者に財産を遺したい場合は、生前贈与や信託などを活用しましょう。生前贈与は、被相続人が生きている間に、特別縁故者へ財産を直接譲り渡す方法です。例えば、内縁の配偶者や家族同然の関係にある人に対して、贈与契約書を作成します。双方の署名・押印を残すことで、後々のトラブルが防げます。
贈与税には、年間110万円までの非課税枠があるのです。この範囲内であれば、税負担を抑えられます。計画的に財産の移転が行えるのです。また、信託制度を利用することで、財産の管理や分配方法を、事前に細かく指定できます。
つまり、特別縁故者を受益者にできるのです。家族信託や遺言信託の活用で、相続発生後も自身の意思通りに財産を譲り渡せます。これによって、家庭裁判所での複雑な手続きが避けられます。これらの方法を組み合わせて活用することで、特別縁故者への財産承継を、より確実かつ円滑に進められるのです。
まとめ
相続人不在の場合でも、国は法律に則って、粛々と手続きを進めます。そのような状況のなかで、特別縁故者は家庭裁判所の審判を経て、遺産の一部、または全部が受け取れるのです。この仕組みは、相続の不透明さを取り除きます。そして、公正な資産の移転を実現するために、設けられました。
そのため、相続人や被相続人に限らず、自身の財産が将来どのように扱われるか、今のうちに考えることが重要です。遺言書の作成や、信託制度の活用の準備を進めることで、思いがけない相続のトラブルが避けられます。相続は「誰に渡るのか」だけではありません。「どのように引き継ぐのか」を考えましょう。これによって、より安心で納得のいく相続の形がつくれます。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼