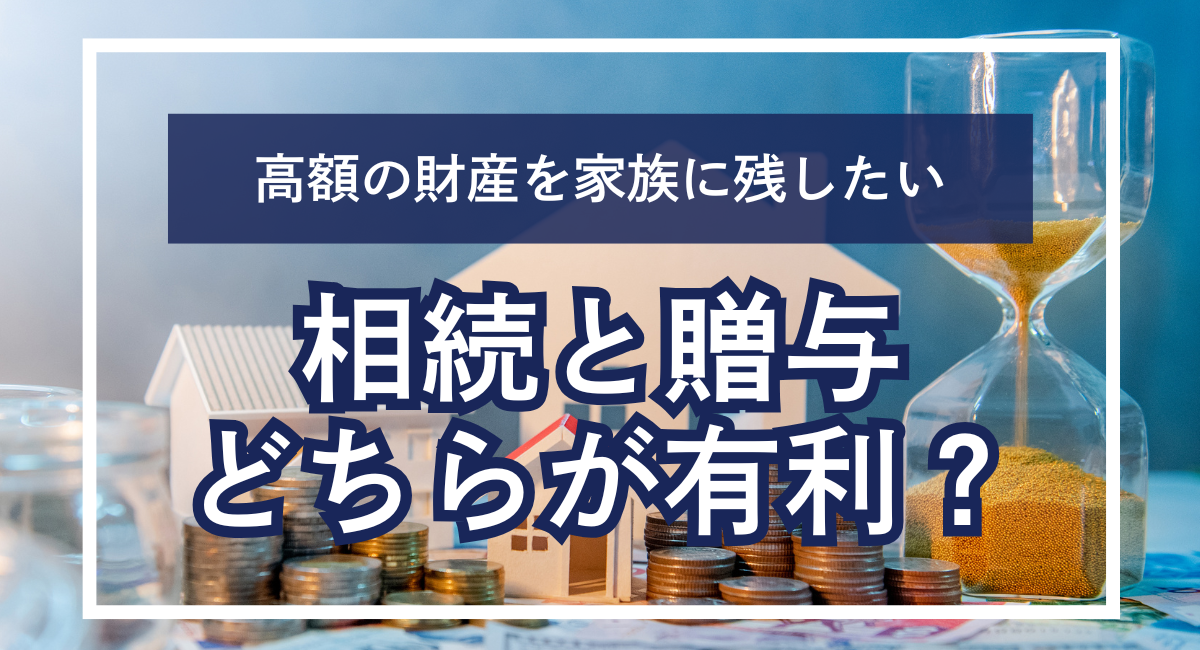高額の財産を家族に残す方法には相続と贈与の2つの方法が考えられます。税率は相続時が有利ですが、財産の種類や家族間の関係にも考慮し、じっくり検討しましょう。
ご自身で築き上げた大切な財産を、ご家族へ円滑に、そしてできるだけ税負担を抑えて引き継ぎたいと願っている人は多いでしょう。
相続と贈与は、財産を次世代へ承継するための方法ですが、それぞれに異なる税制とメリット・デメリットが存在します。近年は相続登記の義務化や持ち戻しにおける対象期間の変更など、大きな改正が続いており、今後も相続や贈与はしくみや税率の変更が続くと予想されています。
また、資産形成は従来の預貯金や不動産以外の金融資産も増加しており、暗号資産などの「デジタル資産」が急速に拡大しています。こうした財産は資産形成に欠かせないものですが、相続時における税務上の取り扱いが新たな課題として浮上しています。
そこで、高額の財産を家族に残す場合における相続と贈与について、どちらが有利なのか詳しく解説します。相続税と贈与税の基本的なしくみを踏まえて解説しますので、ぜひご一読ください。
相続税と贈与税の基本的なしくみと税制の違いとは
ご自身の財産が家族などへ移る際には、ご逝去後の場合は「相続税」が、生前の贈与の際には「贈与税」が課税されます。これらの税金は課税のしくみや適用される税率、用意されている非課税枠などに大きな違いがあります。まずは、それぞれの税制の基本的な特徴と違いについて詳しく解説します。
1.相続税の特徴
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人(財産を受け継ぐ方)が相続や遺贈によって取得した場合に課される税金です。おもな特徴には以下の点が挙げられます。
- 基礎控除枠がある
相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」という基礎控除枠が用意されています。この基礎控除額を超えた部分にのみ相続税が課税されます。
- 累進税率構造(10%〜55%)
相続税の税率は、課税される遺産の額に応じて10%から最高55%までの累進課税となっています。遺産総額が大きくなるほど、適用される税率も段階的に高くなります。
- 特例や控除が多数用意されている
相続税には小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、特定の条件を満たす場合に税負担を大幅に軽減できる特例や控除が多数用意されています。基礎控除を超えていたとしても特例や控除の適用で相続税が0円になることも少なくありません。
2. 贈与税の特徴
贈与税は、個人(贈与者)から財産を無償で受け取った場合、その財産を受け取った人(受贈者)に課される国税です。贈与税にはおもに以下の特徴があります。
- 年間110万円の基礎控除
贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという「年間110万円の基礎控除」があります。この贈与は暦年贈与と呼ばれ、少額の贈与を毎年継続的に行うことで、将来の相続財産を少しずつ減らせることになります。
- 贈与方法によって税率は異なる
贈与税の税率は、贈与方法によって異なります。暦年贈与には特別税率(直系尊属から贈与)と一般税率が設けられており、特別贈与の方が税率が低く設定されています。
相続時精算課税制度を利用する場合は2,500万円までの贈与は非課税となり、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。(110万円の基礎控除も新設されました)
相続と贈与はどちらが有利?
相続と贈与には、税制や手続きの点で大きな違いがありますが、お得に財産を承継していくにはどちらが有利でしょうか。税率の面では相続税には大きな基礎控除や控除などが用意されており、お得に見えるかもしれません。しかし、死後に行われる手続きであり、遺産分割協議が必要となるケースも多く、税率以外の観点も含めて総合的に考える必要があります。
収益性の高い財産は早めの贈与もおすすめ
アパートやマンションなどの不動産は家賃収入などが入るため、生前贈与を検討することもおすすめです。相続時に引き継ぐことも可能ですが、贈与後の収益は受贈者のものとなるため相続財産を減らせる効果があります。
贈与税は確かに相続税より高くなる傾向がありますが、収益性などを見越して資産の移転を検討することが大切です。また、株式やデジタル資産などの財産は将来性が高く、相続時には高額の資産となっている可能性があります。早めに贈与を行えば、相続時の高額な相続税請求は避けられるというメリットもあります。
相続トラブルにも備えた対策が必要
相続税は贈与税と比較すると安くなる傾向があるものの、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要です。ただし、遺言書がある場合は遺産分割協議が不要となることもあります。
特定の相続や取得したい金額をめぐって相続人が対立することも多く、相続には生前から対策を行うことも大切です。相続時にだけ起こる可能性があるトラブルも多いため、家族関係や相続財産の金額なども配慮しながら相続・贈与のいずれが適切か慎重に検討しましょう。
相続・贈与のどちらがお得か税理士へ確認がおすすめ
相続・贈与の判断は税金の問題が深く関わります。自己判断だけで進めてしまうと思わぬ税負担が発生したり、将来的なトラブルの原因になったりする可能性があります。
後悔しないためにも、必ず専門家である税理士に相談し、最適な相続・贈与対策を検討してください。
株式(上場・非上場)やデジタル資産の相続時の注意点
現代の財産構成は、従来の不動産や現金預金だけでなく、株式やデジタル資産といった多様な形態へと広がっています。これらの資産は、その性質上、相続や贈与において特別な注意が必要です。
上場株式の相続時の注意点
上場株式は、証券取引所で日々取引されているため、その評価は比較的明確です。しかし、相続時には上場株式の評価額に注意が必要です。評価額は被相続人が亡くなった日(相続開始日)の終値、またはその月の終値の平均、前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価額を選択できます。適切な評価時点を選ぶことで、相続税を抑えられる可能性があります。
非上場株式の相続時の注意点
非上場株式の相続は、上場株式に比べて複雑で専門知識を要します。非上場株式には市場価格がないため、会社の財務状況から株式を評価します。評価方法の選び方も複雑であり、税理士へ相談の上で判断する必要があります。
会社の支配権に関わるため、複数の相続人間で非上場株式をどのように分割するかは、しばしば争いの原因となります。
デジタル資産の相続時の注意点
近年増加傾向にあるデジタル資産は、その特性から相続において新たな課題が多発しています。暗号資産(ビットコイン、イーサリアムなど)は時価評価が難しく、思わぬ金額の相続税に発展するおそれがあります。税務調査を回避するためにも、税理士との連携が不可欠です。
また、暗号資産以外にも推し活や趣味嗜好による収集品で購入したものや著作権、ブログ収入など副業的な収入を得ている方も増加しており、相続財産から漏れる傾向も見られます。こうした資産は家族が所在を把握していないことが多いためです。もしもデジタル資産をお持ちの場合は、遺言書やエンディングノートなどの方法でしっかりと生前から対策を講じておくことがおすすめです。
関連記事:「推し活」の財産も課税対象?アイドルグッズやデジタル資産の相続と税務
相続と贈与はどちらも生前から比較し、慎重に判断しよう
相続と贈与は、どちらか一方が常に有利という画一的な答えはありません。被相続人となる方の財産・家族構成、財産承継の目的など個別の事情に応じたきめ細やかな検討が不可欠です。
現代においては、不動産や預貯金といった資産だけでなく、上場・非上場株式、そして暗号資産やNFT、デジタルコンテンツなどのデジタル資産を含む、多様な財産構成への対応が必要となります。これらの新しい資産は、評価方法や管理方法において従来の資産とは異なる注意点が多く、専門知識が求められますので、家族揃って早めの税理士相談がおすすめです。また、デジタル資産に相続時に直面した際には、遺産分割協議や相続税申告から漏れないように、早急に存在を確認し、適切に処理を進める必要があります。
デジタル資産の困りごとは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼