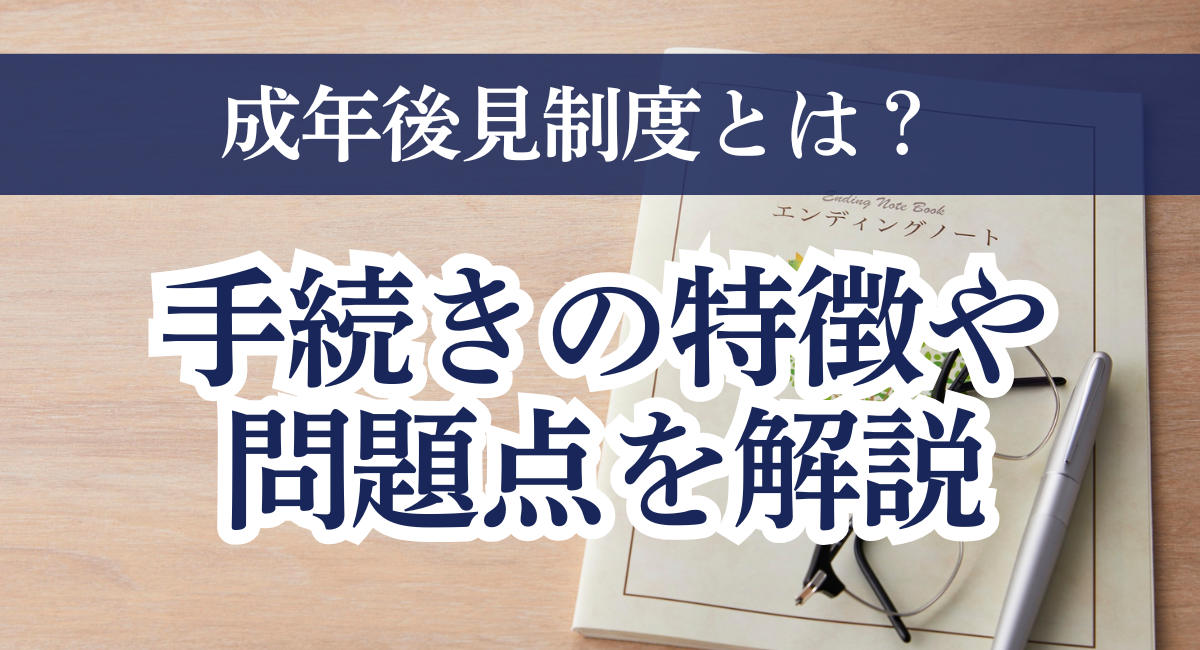高齢化が進む現代社会において、認知症などで判断能力が不十分になった際の財産管理や契約行為をどうするかは、ご家族にとって大きな課題となっています。また、判断能力が不十分なご状態で法定相続人になった場合、遺産分割協議が進められない可能性もあります。
そこで今注目が集まっているのが「成年後見制度」です。この制度は、判断能力が不十分になった方を保護・支援するためのものですが、利用上の注意点、多くの問題や課題も抱えています
そこで、本記事では成年後見制度について手続きの特徴や問題点、利用時の注意点を詳しく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分な方々が、不利益を被らないように、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、その方の生活や財産管理などをサポートする制度です。この章では高齢者が増加する日本で注目度が高まっている成年後見制度について、しくみの概要を解説します。
成年後見制度のしくみ
成年後見制度は大きく分けて、以下の2つの類型があります。
- 法定後見制度
法定後見制度はすでに判断能力が不十分になった方を対象とする制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の家庭裁判所が3つの中から適しているものを選び、後見人等を選任します。 - 任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が元気なうちに、自ら選んだ任意後見人に、どのような支援をしてもらうかを公正証書で契約しておく制度です。法定後見制度とは異なり「本人の意思が尊重される点
が大きな特徴です。判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じ、任意後見人が支援を開始します。

成年後見制度を利用する手続きの特徴
成年後見制度を利用するための主な手続きは以下の通りです。ここでは法定後見制度について解説します。
- 申立て書類の用意
本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てを行います。申立てには家庭裁判所の書式である申立書、戸籍謄本や住民票などの書類が必要です。 - 申立て書類の用意
本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てを行います。申立てには家庭裁判所の書式である申立書、戸籍謄本や住民票などの書類が必要です。 - 調査・審判
家庭裁判所は申立ての受理後に、申立て内容の調査として本人への面談、医師による鑑定(必要な場合)、親族からの意見聴取などを行います。その上で、本人の判断能力の程度、後見人等候補者の適格性などを総合的に判断し、適切な後見人等を選任する審判を下します。 - 後見人等の選任
家庭裁判所は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家や、本人の親族などを後見人等に選任します。申立て時に特定の親族を候補者として挙げることもできますが、家庭裁判所が判断するため要望が通るとは限りません。特に財産額が大きい場合は、弁護士などの専門家が選任される傾向にあります。 - 後見開始
後見人の選任後、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します。その後、本人の生活や財産を保護するための職務を開始し、定期的に家庭裁判所に報告書を提出して監督を受けます。
必要書類などについては、下記裁判所のリンクをご確認ください。
参考URL 裁判所 後見ポータルサイト
成年後見制度の課題と問題点
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護するための重要な制度ですが、運用上の問題点や課題も指摘されています。特に近年は法定後見制度における問題点が報道される機会も増えており、不安を感じる方も少なくありません。
では、成年後見制度における課題や問題点とは一体どのようなものでしょうか。
継続的に報酬が発生する
成年後見制度は申立て時に印紙代や医師の診断書の費用、必要に応じて10万程度以内が目安の鑑定費用もかかるため、申立て人側にとっては少なからず負担が発生します。
さらに、成年後見人には報酬が発生することがあります。(報酬額は家庭裁判所が決定)
親族が成年後見人になる場合は無報酬にすることも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、報酬が発生することが一般的です。
この報酬は本人(被後見人)の財産から支払われます。月額で数万円程度となることが多く、後見期間が長期にわたると、本人の財産が大きく減少する原因となることがあります。
自由な財産の運用はできない
成年後見制度が開始されると、成年後見人等には、被後見人の財産を保護・保全する義務が課せられます。判断能力が低下している被後見人の生活費や医療・介護費用を確保し、本人の財産が不当に失われることを防ぐためです。
しかし、この「財産保全」という目的のために、成年後見人等による財産の自由な運用は原則として認められていません。豊富な財産があったとしても、株式投資や不動産投資などはできなくなるため、柔軟な相続税対策も事実上できなくなってしまうのです。
報酬も発生することから、被後見人の財産はどんどん減ってしまうという問題点があるのです。
トラブルが多発している
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護する重要な制度である一方で、トラブルも多発しており、報道でも多く取り上げられています。主なトラブルポイントは以下です。
■原則として途中でやめられない
法定後見制度は一度開始されると、本人の判断能力が回復しない限り原則として途中でやめることができません。たとえご家族が「もう後見人は必要ない」と感じたとしても、家庭裁判所が認めない限り継続されます。
■専門家による横領なども発生
成年後見人には、本人の財産を管理する大きな権限が与えられます。その職務は家庭裁判所の監督下にありますが、残念ながら成年後見人(特に専門家)による財産の横領や不正な流用といった不祥事も発生しています。こうした事件はニュースでも報じられることがあり、制度への不信感につながる要因となっています。
■被後見人の財産が第三者に知られてしまう
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所が選任した専門家が後見人となったら、その専門家が被後見人の財産情報をすべて知ることになります。上記のように横領などのトラブルが起きていることから、「大切な家族の財産状況を他人に知られたくない」方も多くなっています。
成年後見制度を利用する前にできることは?
成年後見制度は判断能力が低下した方を守る大切な制度ですが、その一方で報酬の発生や一度開始すると原則として止められないといった運用上の問題点も抱えています。
特に、相続対策の観点からは、財産を有効活用した資産運用や節税策が困難となるため、注意が必要です。
これらの問題点を踏まえると、判断能力が十分にあるうちに将来に備えた対策を講じておくことが極めて重要です。ここでは、成年後見制度の利用をなるべく回避するために検討できる方法を解説します。

任意後見制度の検討
法定後見制度とは異なり、任意後見制度は本人がまだ元気で判断能力があるうちに、将来の自分の支援者(任意後見人)に、どのような支援をしてもらうか(支援内容)をあらかじめ契約しておけます。
ご自身の意志を十分に反映させることができるため、成年後見制度でより納得できる支援が受けられます。おひとりさまとして暮らし、不安な方も任意後見制度なら早めの対策としてもおすすめです。
生前贈与
相続対策として、安全に財産を次世代へつないでいきたい場合は生前贈与を検討しましょう。生前から自分の財産を相続人やその他の人に贈与することで、将来の相続財産を減らし、結果として相続税の負担を軽減する目的で行われます。
贈与税には、年間110万円の基礎控除枠があり、この範囲内であれば贈与税がかからず、申告も不要です。(暦年贈与)
この他にも、相続時精算課税制度や教育資金贈与などの方法もあります。生前贈与をしておけば将来本人の判断能力が低下しても、贈与された財産は贈与を受けた人(受贈者)の管理下に置かれているため、成年後見制度の管理対象から外れます。
関連記事:相続は「事前戦略」が9割!富裕層が選ぶ資産の承継術について
エンディングノートの活用
エンディングノートは法的な効力を持つ遺言書とは異なりますが、ご自身の「もしも」の時に備えて、希望や連絡先、財産情報などを書き残しておくノートです。判断能力が低下した際に、ご自身の財産状況や希望を家族が把握するために非常に役立ちます。
遺言書とは異なり自由に記載でき、パソコンで作成しても問題ありません。
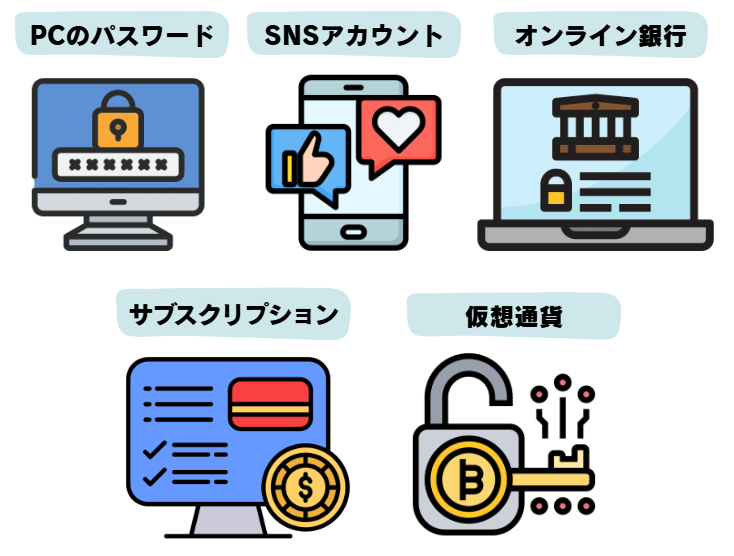
■デジタル資産の記載もおすすめ
デジタル資産に関する情報の記載です。パソコンやスマートフォンのパスワード、SNSのアカウント情報、オンライン銀行のログイン情報、サブスクリプションサービスの契約状況、仮想通貨のウォレット情報など、デジタル化された財産や情報が多岐にわたります。これらは、本人しか知らない場合が多く、もしもの時に家族がアクセスできず、利用停止や解約、あるいは相続手続きが滞る原因となります。
エンディングノートにこれらのアカウント情報やパスワードの管理方法、家族へのメッセージなどを記載しておくことで、デジタル資産の「終活」を行うことができます。
まとめ
本記事では、成年後見制度の問題点を踏まえ、判断能力が十分なうちにできる対策についても詳しく解説しました。
任意後見制度の活用や計画的な生前贈与、そしてエンディングノートによる情報共有は、ご自身の意思を尊重し、将来的な財産管理や相続を円滑に進めるための重要な手段です。高齢社会を家族と協力しながら明るく暮らしていくためにも、できる対策を早くから始めることが大切です。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼