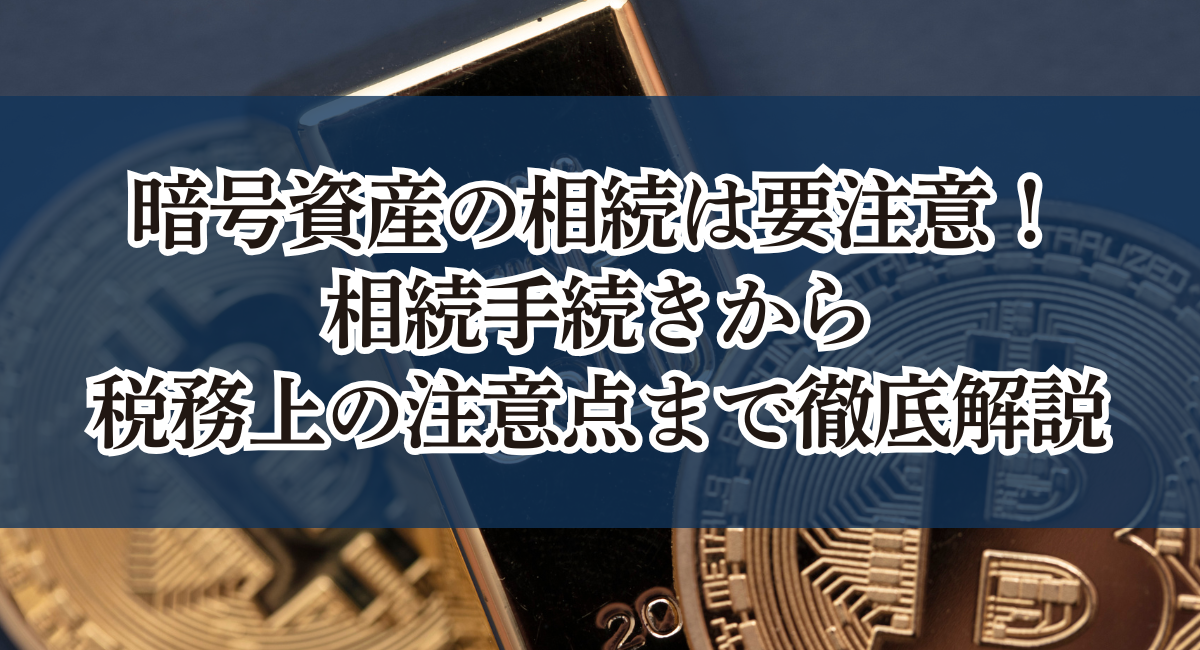暗号資産(仮想通貨)への関心は年々高まっており、新たな投資の選択肢として幅広い世代がすでに運用を始めています。しかし、現金や不動産のように現物がある資産ではないため、取り扱いについては慎重な方も多いでしょう。
価値が高まっている今だからこそ、相続時にはどのように扱うのかも、あらかじめ知っておく必要があります。そこで、本記事では暗号資産の相続について、手続きや税務上の注意点を徹底解説します。
※資金決済法により、国税庁などは仮想通貨を暗号資産の名称で統一しています。
関連記事:投資の遺産相続はどうする?NISA・iDeCo・FX・仮想通貨の相続方法を解説
デジタル資産時代に突入!新たな相続課題とは
インターネットとデジタル技術の進化により、私たちの生活や経済活動は目まぐるしく変化しています。私たちの「資産
の構成についても変化が大きく、不動産や預貯金、有価証券といったよくある資産だけではなく「デジタル資産」の増加も目立つようになりました。
ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の普及により、これまでの相続手続きとは異なる課題が急浮上しています。詳しくは以下のとおりです。
相続時は暗号資産ならではの特性に注意
暗号資産はブロックチェーン技術によって支えられる新たなデジタル資産です。その特性ゆえに、従来の相続財産とは異なる多数の課題を抱えています。
被相続人(亡くなった方)が暗号資産を保有していた場合、相続人にとって以下のような問題に直面することが少なくありません。
- 物理的な実体がないため放置される
不動産などのように形として存在するものであれば、現物や権利証などの書類から財産の存在を相続人が容易に把握できます。しかし、暗号資産はデジタルデータであり、物理的な実体がありません。
そのため、相続手続きの最初のステップである「相続財産の調査」で見つからない、見つけてもパスワードがわからないなどの問題が多発しています。宙に浮いた財産となってしまい、相続人にとって大きな損失につながる可能性が高いのです。場合によっては専門家へ相談しながら探す必要があります。
- 財産の評価が複雑
相続税を計算する際の「財産の評価」も難解です。暗号資産は2025年4月時点でも財産評価基本通達において明確なルールが整備されておらず、評価に精通した税理士の数も限られています。暴騰・暴落によって評価が大きく左右されるため、思わぬ課税負担が生じるリスクもあるのです。
暗号資産の相続税手続きはどう行う?3つのステップとは
暗号資産をお持ちの方が亡くなられた場合、暗号資産もその他の財産と同様に相続手続きを進める必要があります。遺産分割対象でもあるため、遺産分割協議時には漏れのないように協議を行いましょう。
相続税は必ずしも相続人全員に課税されるものではなく、基礎控除である「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を上回る場合に課税されます。正しい相続税の計算のためにも、まずは相続時の暗号資産の手続きも把握しておきましょう。この章では手続きを3つのステップに分けて解説します。
暗号資産の取引所などへ連絡
暗号資産の手続きは、各取引所などへ直接連絡します。要領は預貯金口座の相続等と同様で、相続人から連絡を入れて、各取引所のルールに沿って進めます。bitFlyerやCoincheckなどが広く知られていますが、その他にも多数の取引所などがあるため、念入りに調べましょう。
必要書類の準備
取引所側が相続手続きを受け付けると、メールや郵送で今後の流れを送ってきます。被相続人の除籍謄本等や、相続人の戸籍謄本等が指示されるため、準備を進めましょう。なお、必要書類も一般的な金融機関と同様です。
口座の送金を受ける
必要書類を整え郵送すると、審査後に暗号資産が日本円へ換算の上で送金されます。暗号資産のまま引き継ぐことも可能ですが、相続人名で新たな取引口座の開設が必要です。取引所などによって必要となる手続きや書類が異なるため注意しましょう。
相続税の評価方法を確認する
暗号資産は活発な市場も多いですが、創設されたばかりの新規市場もあります。活発な取引所の場合は相続開始日の残高証明書の金額を相続税評価に使用します。残高証明書には暗号資産の残高と日本円への換算レートが記載されており、相続税評価時に必要となるため保管しておきましょう。
新規市場やあまり動きがない市場は相続税評価が難しいため、税理士への相談が欠かせません。評価に時間がかかる可能性もあるため、早めの相談がおすすめです。
押さえておきたい暗号資産相続の注意点
暗号資産は相続税評価だけではなく、税務上の注意点も多いため注意が必要です。この章では3つの注意点を詳しく解説します。
相続手続き完了まで売買はできない
暗号資産を相続する場合、相続手続きが完了するまで売買や送金などの取引を行うことはできません。暗号資産は本人以外の取引は禁止されていること、遺産分割協議が終わるまで暗号資産を含む相続財産は各相続人が共有している状態となっているためです。
暗号資産は非常に変動が激しく、一日で大幅に価値が上昇することもあれば、急落することもあります。「今日売りたかったのに」と思われることもあるでしょう。しかし、手続き完了前に勝手な売買はできないと覚えておきましょう。
二重課税のおそれがある
相続した暗号資産を売却した場合、利益部分に関しては「所得税」が課税されます。この問題は俗に『110%課税』とも呼ばれる二重課税の問題が話題となっており、ご存じの方も多いでしょう。暗号資産の金額によっては、相続税(最高55%)と売却益に対する所得税・住民税(合計最高55%)がそれぞれ課されるため、二重課税が発生するのです。
次の項でご説明しますが、暗号資産向けの相続時の特例や控除はないため、非常に重い課税が発生するおそれがあります。
暗号資産に特化した特例や控除は用意されていない
不動産の相続においては、要件はあるものの相続税の負担を軽減するための特例や控除が用意されています。代表的なものとしては「小規模宅地等の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)売却の特例」などが用意されており、不動産相続時の税負担を軽減する制度が用意されています。株式についても取得費加算の特例の利用が可能です。
しかし、暗号資産に特化した特例や控除はありません。取得費加算の特例も対象外です。
配偶者の税額の控除や未成年控除など、相続人によって受けられる控除はあるものの、暗号資産は比較的新しい資産であるため、税制がまだ追いついていません。
現行法では不動産や株式のような税制上の優遇措置が設けられていないのです。
暗号資産を多額に保有している場合、他の相続財産に比べて相続税の負担が大きくなる可能性があることを意味します。例えば、同額の不動産と暗号資産を比較した場合、不動産であれば小規模宅地等の特例が適用されて評価額が大幅に減額される可能性がありますが、暗号資産にはそのような優遇措置はありません。
そのため、暗号資産を保有している方は利益を用いて別の資産を購入するなどの節税対策を積極的に検討し、税理士と相談しながら総合的な相続税対策を講じる必要があります。
将来的に税制が変わる可能性はありますが、現時点では優遇措置がないという前提で対策を進めるべきでしょう。
まとめ:暗号資産の相続は「事前の準備」と「専門家の力」で解決しよう
暗号資産は従来の相続財産とは異なる、多くの相続上の課題を抱えています。特に、その存在の把握や正確な財産評価は難解であり、事前の準備や専門家の力が不可欠です。
相続発生後に慌てないためにも、被相続人が元気なうちに、暗号資産の保有状況を整理し、アクセス情報を引き継ぐための用意をしましょう。また、相続を迎えた際には暗号資産に詳しい税理士や弁護士といった専門家のサポートが不可欠です。デジタル資産時代の新たな相続課題に適切に対応し、ご家族に円滑に財産を引き継ぐためにも、まずは信頼できる専門家へご相談ください。
【仮想通貨復元スペシャリストのご案内】
・スクリーンショットやテキストデータで残しておいたシークレットリカバリーフレーズや秘密鍵が見つからない
・リップル(XRP)やエイダ(ADA)が取り出せなくなった
暗号資産の復元のお困りごとにつきまして、「仮想通貨復元スペシャリスト」サービスをご検討ください。
私たちの専門チームは、以下のような特徴を持つ信頼できるサービスを提供しています。
- 豊富な復元実績(BTC/ETH/XRP/ADA)
- 秘密保持契約を締結し、お客様の秘密情報及び個人情報の保護を徹底
- 一部成功報酬型で対応
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得
まずは無料相談から承ります。経験豊富な専門家が、あなたの大切な資産の復元をサポートいたします。