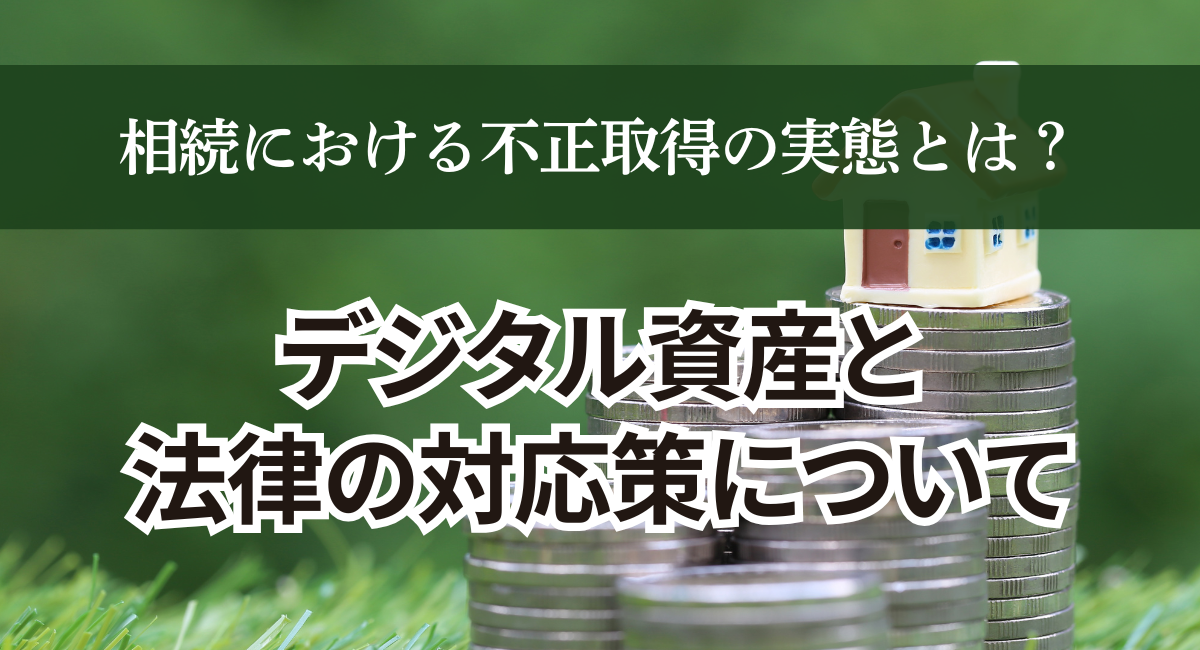近年、スマホやクラウドサービス、暗号資産などに代表される「デジタル財産」の重要性が急速に高まっています。個人の財産が物理的な形を持たずに、データとして、オンライン上に存在することが一般化しています。
このようなデジタル資産は、相続の現場でも無視できない存在です。しかし、従来の不動産や預貯金とは異なり、その存在自体が、周囲に知られにくい特徴があります。IDやパスワードの管理が個人に委ねられているため、相続人の場合でも、アクセスが困難です。デジタル資産は「見えにくい資産」として扱われます。
そのため、正当な手続きを経ずに、一部の相続人が秘密裏に取得するケースがあります。資産の存在が意図的に隠されてしまい、トラブルが起きやすい状況になるのです。不正取得や隠匿行為は、遺族間の信頼関係を深く傷つけます。
民事訴訟や遺産分割協議の無効請求など、深刻な法的紛争に発展するかもしれません。今回の記事では、デジタル財産に関する不正取得の実態や、被害を防ぐための対応策を解説します。トラブルを未然に防ぐための生前準備についても、紹介していきます。
「争族」問題はスマホにある?現代の相続の新たな火種とは
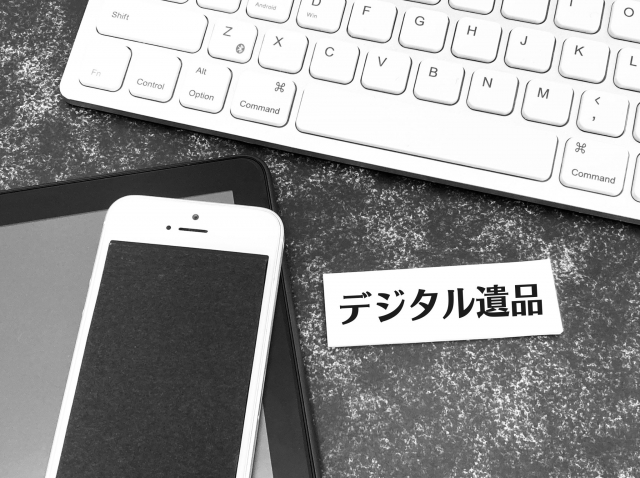
相続は「争族」とも呼ばれており、親族間での紛争の種です。近年、特に増加しているのが、デジタル資産を巡るトラブルです。新たな問題として、注目されています。
たとえば、仮想通貨やネット銀行口座、SNSアカウント、写真や動画データ、オンラインゲームのアイテムなどが、デジタル資産です。オンライン上の財産が含まれます。このような資産は、相続の対象になります。手続きが煩雑になり、トラブルが発生しやすい状況を生み出すのです。
家族を分断する相続トラブルの現実
相続をめぐる家族間の対立は、年々深刻化しています。相続に関するトラブルは、お金持ちだけの問題ではなく、一般の家庭にも広がっているのです。相続で家族が分裂する理由には、兄弟姉妹の間での意見や、立場の違いが挙げられます。
借金や古くなった不動産などが代表例です。引き継ぎたくない資産が絡むと、感情的な対立に発展しやすくなります。遺言書の内容に関しても、相続トラブルの要因です。生前に一部の相続人のみに贈与があった場合は、不信感が高まります。
親の介護に携わった人が「それに見合うだけの分け前をもらいたい」と考えても、法律上では、反映されにくい可能性もあります。相続の紛争が生じやすい背景には「自身の家族は大丈夫」と思ってしまう点です。
資産の全体像を家族が把握していない場合が少なくありません。家庭裁判所での調停や裁判が、長期化して何年にもわたって、トラブルが続く可能性があります。このような事態を避けるためには、何よりも「事前の話し合い」と「準備」が欠かせません。
資産の内容を早い段階で、家族同士で共有しましょう。遺言やエンディングノートなど、法的効力のある方法で、意思を明確にすることが大切です。相続に関する問題が起きた場合は、一人で抱え込んではいけません。早めに専門家に相談することで、スムーズな解決を目指せます。
| 相続トラブルが発生する原因と影響について | ||
| トラブルの項目 | 内容 | 影響・問題点 |
| 相続財産の不透明さ | 財産の全体像や内容が、家族に共有されていない | 疑心暗鬼、不信感の増加 |
| 遺言書の内容の不公平や不明確さ | 遺言書がない、または一部の相続人に偏っている | 不満やトラブルの発生 |
| 分割が困難な不動産の存在 | 不動産など、現金化困難な資産が含まれる | 平等分割困難、対立の原因 |
| 生前贈与や借金の有無 | 一部の相続人への生前贈与や、借金がある場合 | 不公平感や不信感の増大 |
| 介護など親の世話の負担 | 親の介護をした相続人の負担が、法律で反映されにくい | 感情的対立が起きやすい |
| 相続人間の関係性の希薄さ・疎遠 | 普段から家族間の関係が良好ではない | 話し合いが難航して、感情的な対立に発展 |
| 未確認の相続人や隠し子の存在 | 新たな法定相続人が判明することがある | 遺産分割が複雑化して、争いが長期化 |
相続のトラブルに発展しやすいデジタル資産
「デジタル資産」とは、形のない電子データで存在します。法律上、デジタルデータ自体は物理的所有権の対象ではありませんが、関連する権利や契約は、相続財産として認められます。たとえば、オンライン上の金融資産や暗号資産は、相続人が引き継ぎます。しかし、SNSのアカウントは、利用規約で個人専用にされている場合、相続できない可能性があるのです。
相続手続きでは、故人が所有するデジタル資産の全体像を把握しなければなりません。IDやパスワードなどの、アクセス情報を確保することが必要です。デジタル資産は、目に見えにくく、アクセスにはIT知識が求められます。
ポイントやマイルの一部は、相続可能なケースもありますが、各サービスによって異なるため、事前の確認が大切です。このように、デジタル資産は、従来の資産とは異なる特徴を持ちます。相続に備えて法的な理解を深めることが、資産の相続対策につながるでしょう。
親族間で起こるデジタル資産の不正取得とは
近年、仮想通貨やオンライン証券、SNSアカウントなどの「デジタル資産」が、生活に急速に浸透しています。しかし、デジタル資産は実際の形では見えません。相続の場合では、発見が遅れることも多く、サービスの利用規約や法律が、十分に対応しきれていないのが現状です。そのため、相続人の間で、混乱やトラブルも多く発生しています。
- パスワードや二段階認証の管理の不備、不正アクセス問題
デジタル資産は、認証情報によって保護されています。その取り扱いを巡って、相続人の間でトラブルが生じやすいです。故人のスマホやPCへの不正アクセスによる、資産の移動・処分も発生しています。
- デジタル資産の把握不足がもたらす相続トラブル
デジタル資産は実体のない資産です。たとえば、相続開始後に仮想通貨が発見された場合に、遺産分割や税務申告のやり直しが必要になるケースがあります。
- 追いつかない法律と規約
SNSやオンラインサービスの利用規約が、相続に対応していない場合があるのです。法整備が追いついておらず、海外サービスでは法的に不透明な部分が多いです。問題が複雑化しやすく、相続のトラブルが生じます。
| 相続におけるデジタル資産のトラブルについて | ||
| 分類 | 具体的な事例 | 問題点・背景 |
| 不正アクセス・資産の移動 | 故人のスマホ・PCを家族が無断操作して、仮想通貨などを送金・現金化 | 端末や認証情報を知っていれば、資産の移動が容易。不正発覚が後になることも多い |
| パスワード・認証情報の管理の不備 | 口頭で伝えられた認証情報を用いて、正規手続きを経ずに資産を取得する | 認証情報の管理ルールが不在。公正な分配がなされず、親族間に不信感が生じる |
| デジタル資産の存在・発見の遅延 | 相続手続き後に、仮想通貨や証券などの未発見の資産が判明する | 申告や分割協議のやり直しが必要になる。資産を一部相続人が、意図的に隠す可能性がある |
| サービスの利用規約・法整備の不備 | サービスの規約に死亡・相続対応の記載がなく、家族が引き継げない | 海外サービスの場合、日本の法律での対応が困難。不正ログインなど、違法行為が生じやすい |
| SNSアカウントやデータの扱い | SNSの削除や継承方針で、親族間の意見が割れて、不正アクセスが起こる | 財産的価値は低いが、心理的トラブルや個人情報の流出リスクもある |
| 税務・手続き上の問題 | 相続終了後に、多額のデジタル資産が発覚して、申告漏れ・遺産分割協議のやり直しが発生する | 相続財産の管理が煩雑になる。申告・納税の遅延リスクにつながる |
デジタル資産の法的課題とは?変わりゆく相続財産

先述の通り、近年では、相続財産の中に「デジタル資産」が存在しており、その重要性が高まっています。デジタル資産には、仮想通貨や電子マネー、オンラインゲームのアイテム、SNSのアカウントなどが含まれます。紙の証書や通帳がないため、すべてデジタル上で管理されている点が特徴です。
しかし、デジタル資産を相続する際には、さまざまな点に注意しなければなりません。パスワードや秘密鍵が分からない場合、遺族が資産にアクセスできない可能性があります。サービスの規約で、アカウントの名義の変更が、禁止される場合もあるのです。
このため、現代の相続対策では、デジタル資産も含めた、全体の財産を把握しなければなりません。一覧表の作成や、遺言書に明記することが求められています。早めに状況を整理して、適切な対策を取ることが重要です。
親の代から続く資産をどのように引き継ぐのか
親から受け継いだ資産を、遺族が引き継ぐ方法には、主に「相続」「生前贈与」「家族信託」の3つがあります。まず「相続」とは、親の資産や株式などを、配偶者や子どもなどの相続人が、引き継ぐ方法です。遺言書や資産の分け方の話し合いが行われて、相続税が発生する可能性があります。
相続人が複数人いる場合は、資産や経営権が分散しやすいため、遺言や事前の調整が欠かせません。「生前贈与」は、親が元気なうちに、資産を子どもに移す方法です。年間110万円までは贈与税が免除されているため、この制度を活用しながら、計画的に資産を移せます。
そして「家族信託」は、親の資産を信頼できる子どもに預けて、管理・運用してもらう仕組みです。これによって、親が認知症で判断能力が落ちても、資産管理が継続的に行えます。子どもや孫世代に、資産をスムーズに引き継ぐことができます。
会社や事業の資産を受け継ぐ場合は、株式の配分や議決権の調整も重要です。具体的には、資産の内容と価値を把握しなければなりません。相続や贈与の計画を立てて、必要に応じて、家族信託も利用します。この方法を活用することで、親から受け継いだ大切な資産を、将来に向けて守り続けられます。
| 資産の引き継ぎ方法と注意点 | |||
| 項目 | 相続 | 生前贈与 | 家族信託 |
| 概要 | 親が亡くなった際に資産を引き継ぐ | 親が生きているうちに資産を贈与する方法 | 信頼できる家族に管理・運用委託する仕組み |
| 手続きの流れ | 死亡診断書受取、相続人・遺産調査、遺産分割協議、名義変更、相続税申告など | 贈与契約書作成、名義変更、贈与税申告(必要時) | 信託契約作成、不動産登記変更、管理運用、信託報告 |
| 税金 | 相続税がかかる(10ヶ月以内に申告) | 年間110万円まで贈与税非課税、それ以上は贈与税が課税 | 信託開始時の税制は、基本的に通常の所有権と同じ |
| 税務上の注意 | 相続財産の評価・申告が必要 | 高額の贈与時には、贈与税負担に注意 | 管理・運用に伴う税務処理が複雑になる |
| 資産管理 | 相続開始後に管理・運用が引き継がれる | 贈与後は、受贈者が管理 | 受託者(子など)が管理・運用を継続 |
| メリット | 法律で定められた手続きによって、確実に資産移転できる | 計画的に贈与することで、税負担を軽減できる | 認知症時でも資産管理が滞らず、柔軟な承継が可能になる |
| デメリット | 手続きが煩雑で、時間がかかる場合も多い | 税負担や手続きの準備が必要になる | 契約設計や変更に専門家が必要。初期手続きが複雑 |
| 適している場面 | 親が亡くなった後に、一括で資産を引き継ぐ時 | 長期的に少しずつ資産を移したい場合 | 親の判断能力の低下に備えて、長期間の管理が必要な場合 |
| 会社・事業資産 | 議決権や株式分配の調整が重要 | 株式も贈与可能だが、税務や手続きが複雑 | 柔軟な配分や管理が可能。経営の継承に向いている |
知らない間に操作される?デジタル資産相続の「見えない不正」
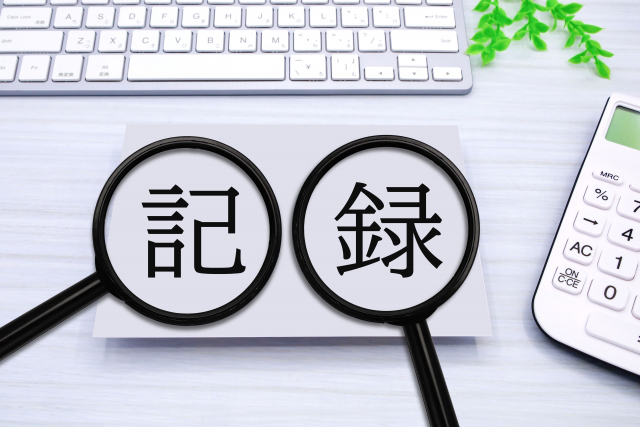
相続において不正が起こりやすい状況には、一定の共通点があります。それは、相続人の間で、情報に大きな差がある場合です。特に、デジタル資産はその存在が見えづらいため、事情に詳しい一部の相続人が、資産を独占する恐れがあります。勝手に操作するリスクが高まります。
デジタル資産は、実物として残りません。取引の履歴や残高の通知も、明確に届かないことが多いです。相続人全員で、資産の状況を細かく把握するのは難しいです。故人のスマホやパソコンにアクセスできる親族が、他の相続人に知らせずに、資産情報を無断で操作を行うケースも増加しています。
パスワードや認証情報が特定の親族に偏っていると、その情報を悪用して資産の不正引き出しが行われる恐れがあるのです。このような相続の問題は、デジタル資産で目立っています。家族間での情報共有の不足や、専門家による対策を行っていない場合、相続の不正が発覚しない危険性があります。
相続人同士の情報格差がもたらすトラブル
相続人の間で情報差があることは、さまざまな問題を引き起こすでしょう。故人の資産状況や希望が、一部の相続人だけに伝わっていると、情報の不均衡が生まれます。遺産の分割を話し合う段階で、疑念や争いが起こりやすくなります。認知症の人や、連絡がつかない相続人がいるケースも少なくありません。遺産分割の話し合いが長期化しやすく、必要な手続きが遅れて混乱が生じます。
ネット銀行やSNSなどのデジタル遺産は、本人のみが管理していることが多いです。相続人が、その存在やアクセス方法を知らないまま、手続きを終えると、後に相続トラブルにつながります。情報の格差が一段と大きくなるでしょう。
このような問題を減らすには、故人が生きている間に、すべての相続人へ資産や意向をきちんと伝えなければなりません。家族や親族の間で、話し合いをしておくことが大切です。デジタル資産の管理方法を、情報共有する必要があります。行政もデジタル化を進めて、情報の連携を円滑化することが求められています。
| 情報格差の内容と影響について | ||
| 課題の内容 | 説明 | 影響・結果 |
| 資産の情報不均衡 | 故人の資産状況や希望が、一部の相続人のみで共有されている | 遺産分割時の疑念や対立、不信感が増す |
| 連絡が取れない・認知症の相続人 | 認知症や連絡不通の相続人がいる場合 | 遺産分割協議が長期化、手続きの遅延や混乱 |
| デジタル資産の管理・共有の不足 | ネット銀行やSNSなどのデジタル資産は、故人が単独管理して、他の相続人は知らないことが多い | 手続き完了後に発覚し、相続トラブルに発展 |
| デジタルリテラシーの格差 | パソコンやスマホの扱いに慣れている相続人と、そうではない相続人の間で格差が生まれる | 情報所有に格差が生まれて、対立が深まる |
| 遺言内容の非共有 | 遺言内容が全員に周知されていない場合 | 急な遺言の公開で、疑問や反発が生じやすい |
| 行政の情報連携と支援不足 | 故人情報のデジタル化と、相続人への安全な情報伝達の仕組みが未整備 | 手続きの効率化が進まず、混乱が続く |
知られずに巧妙化する相続トラブル!名義変更とデジタル情報の悪用
相続に関するトラブルは、従来の不動産や現金にとどまりません。故人のスマホやパソコンに保管されたデジタル資産が絡むことで、より複雑で巧妙化しています。SNSのアカウントやオンラインバンキング、仮想通貨、FX口座などのデジタル情報は、特に注意が必要です。
デジタル資産は存在が分かりにくく、相続人も気づかない状態で放置されるかもしれません。資産の内容や規模によっては、損失や負債を負うリスクもあるでしょう。故人のSNSアカウントが悪用されて、なりすましや詐欺、個人情報流出などの問題を引き起こすことも多いです。
また、ログイン情報の管理や二段階認証の設定などが障壁になり、名義変更や資産の引き継ぎが困難になる場合もあります。このような問題を防ぐには、生前にデジタル資産の詳細を整理して、相続人へ情報を共有することが重要です。専門家に相談しながら、適切な対策を行うことで、相続トラブルの発生を防止できます。
不正行為の法的責任とは?横領・窃盗・不当利得の可能性

法的な観点で「不正」とは、他人の権利や利益を、故意または過失によって侵害して、不当に利益を得たり損害を与えたりする行為です。相続の分野では、このような不正行為は「横領」に該当する可能性があります。損害賠償請求や不当利得返還請求の対象になります。
相続における不正取得は、単なる民事トラブルにとどまりません。刑事問題に発展する可能性もある大きなテーマです。被害を受けた場合は、遺産分割協議の無効確認訴訟などの民事手続きを行う必要があります。証拠を揃えたうえで、専門家と対応を進めましょう。
| 相続における法的責任の概要 | ||
| 項目 | 内容 | 法的根拠・対応 |
| 不正取得の例 | 遺言書の偽造・改ざん、遺産の横領や使い込み、遺産分割協議の欺瞞的合意 | 遺言書の偽造は無効(家庭裁判所で無効確認申立て) |
| 民事問題 | ・詐欺や強迫、錯誤による遺産分割協議は、無効または取り消しが可能 ・不当利得返還請求や損害賠償請求が可能 | 民法(不当利得返還請求:民法703条など) |
| 刑事問題 | ・窃盗罪や横領罪に該当する場合は、罰金、懲役の可能性がある ・配偶者や直系血族等の親族間で、窃盗、横領は刑罰免除の特例がある – 不正アクセス禁止法違反などに該当する | 刑法235条(窃盗罪)、刑法244条(親族相盗例)など |
| 証拠準備 | 不正の証明には戸籍謄本、遺産目録、通帳・振込記録、遺産分割協議書の原本などが必要 | – |
| 法的手続き | ・遺産分割協議の無効確認訴訟 ・不当利得返還請求訴訟 ・刑事告訴・告発 | 裁判所(家庭裁判所、地方裁判所)への申し立てなど |
| 対策・注意 | ・公正証書遺言の作成の推奨 ・相続財産の凍結措置や、資産内容の共有で不正防止 ・弁護士や専門業者への相談が重要 | – |
法的な視点から「横領」と判断される行為とは
相続における横領とは、故人の預貯金や不動産などの資産を、無断で自身のものとして使用する行為です。たとえば、故人の預金口座から、お金を勝手に引き出して私的に使用するケースです。刑法上「他人の物を不正に自身のものにする行為」として、横領罪に該当します。実際には、親族間のトラブルであるため、刑事告訴が難しい場合が多いです。民事での返還請求や損害賠償請求によって、解決を試みることが一般的です。
民事訴訟や遺産分割協議の無効請求の対象になる
相続に関わる不正行為は、民事の訴訟対象になるだけでなく、遺産分割協議の無効を求める請求の対象にもなります。裁判所にその無効が認められた場合、その協議は取り消されます。新たに適切な協議を行う必要があります。
一部の相続人が他の相続人を意図的に除外し、遺産分割協議書を偽造した場合は、「遺産分割協議自体が存在しなかった」として訴訟を起こせるのです。また、他者の相続財産を不正に使用した場合には、不当利得返還請求や損害賠償請求を民事裁判で行えます。
一方で、裁判は時間と費用がかかり、家族関係が悪化する可能性も高いです。親族間でのトラブルは、証拠の収集や関係悪化のリスクがあります。そのため、早めに弁護士や、相続の不正調査を取り扱う専門家へ相談することがおすすめです。刑事・民事の面から、適切な対応を取ることが大切です。
| 不正行為の種類と適用される法律について | |||
| 不正行為の種類 | 内容・具体例 | 適用される法律・罪名 | 備考・注意点 |
| 横領罪 | 故人の資産管理を任されていた相続人が、無断で自身のものにする例 | 刑法252条 | 配偶者や直系親族、同居家族による場合は、刑罰軽減・免除の特例あり(刑法244条) |
| 窃盗罪 | 許可なく資産を持ち出す行為 | 刑法235条 | 親族間の特例は、横領と同様。非同居親族の場合は、刑事告訴が可能になる |
| 不正アクセス禁止法違反 | 故人のメールやネットバンキングに無断でアクセスして、不正の取得・操作を行う | 不正アクセス禁止法 | 重大な刑事罰の対象になる |
| 私文書偽造罪・詐欺罪 | 遺言書や遺産分割協議書を偽造・改ざんする | 私文書偽造罪、詐欺罪 | 遺言書の偽造は、3ヶ月以上5年以下の懲役刑もある |
| 介護・後見人による横領 | 裁判所が選任した後見人(親族含む)が財産を無断で使う | 業務上横領罪 | 親族間の軽減特例は適用されず、重い刑事責任が問われる |
| 民事責任(不当利得返還請求・損害賠償請求) | 不正行為によって得た利益の返還請求や、損害賠償請求 | 民法、不当利得返還請求など | 親族間のトラブルは、証拠収集や関係悪化リスクが高い。専門家への相談が推奨される |
| 刑事告訴の代理申立て | 配偶者や親族が、代理で刑事告訴が可能 | 刑事訴訟法231条 | 親告罪の場合、被害者や法定代理人の告訴で捜査・起訴が進む |
相続の不正問題を見逃さない!デジタル時代の相続対策と家族の準備

相続の場面において、生前の準備と相続発生後に家族が注意すべき点があります。生前の対策としては、デジタル資産の一覧を作成して、それを遺言書やエンディングノートに明記することが大切です。
信頼できる弁護士や司法書士などの専門家に、早めに相談しておくことで、親族間のトラブルが防げます。相続が発生した後は、デジタル資産のパスワードの取り扱いに十分注意してください。安易に使用したり処分したりせず、故人の資産を適切に管理しましょう。
冷静に内容を確認して、借金の有無も含めて、全体像を把握することが必要です。また、相続人の間で、デジタル資産の不正な取り扱いが疑われる場合には、相続の不正調査を行う専門業者への依頼もおすすめです。専門家のサポートを借りることで、トラブルの対応も進めやすくなります。
遺言書とエンディングノートの活用がおすすめ
エンディングノートは、自身の資産や相続に関する希望を、家族に伝えるための有効な手段です。しかし、法律上の効力はありません。そのため、エンディングノートの内容をもとに、相続の分配を強制することはできず、相続人が必ずしも従う必要はないのです。それに対して、遺言書は法的な効力を持っています。相続人は、遺言書の内容に従って手続きを行う義務があります。
エンディングノートは形式が自由です。資産の詳細や相続の希望はもちろん、医療や介護の要望、葬儀の希望、家族へのメッセージなども残せます。これによって、相続時のトラブルを減らして、家族間の理解を深めるきっかけになります。
一方で、銀行の暗証番号やネットサービスのパスワードなど、重要な個人情報をエンディングノートに直接書くのは、避けなければなりません。ノートの紛失や盗難によって、不正利用の危険が高まるためです。このような重要な情報は、別の安全な方法で管理してください。信頼できる家族や専門家に、保管場所を知らせておくのもおすすめです。
| 遺言書とエンディングノートの違い | ||
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
| 法的効力 | なし | あり |
| 内容の強制力 | 相続人は従う義務がない | 相続人は内容に従う義務がある |
| 形式 | 自由形式 | 法律で定められた形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など) |
| 記載できる内容 | 資産情報や相続に関する希望、医療・介護、葬儀、家族へのメッセージなど | 資産の相続方法や法的な指示のみ |
| 重要な個人情報の扱い | 銀行暗証番号やパスワードなどは、記載を避けるべき | 記載しない方が安全 |
| 主な目的 | 家族に希望や気持ちを伝えて、トラブルを減らす | 法的に遺産分割を指定して、確実に実行する |
| 作成の手軽さ | 簡単(自由に書ける) | 複雑(法律に則った形式が必要、専門家の助言が推奨) |
相続の不正には信頼できる専門家へ相談しよう
相続のデジタル資産の取り扱いには、注意が必要になります。デジタルリテラシーをはじめとした情報の格差によって、相続人の間で不正が発生するケースがあります。そのようなデジタル資産の不正調査や相談を行う場合は、弁護士や専門知識を持つ調査会社に依頼するのが安心です。
特に、相続におけるデジタル資産の不正調査会社に関しては、故人のスマホやパソコンに残されたデータを専門的に分析します。隠された資産や不正の証拠を見つけ出してくれます。ネット銀行の口座情報や、仮想通貨などの動きを調査するため、デジタル資産の不正が疑われる場合の大きな選択肢です。早めに相談することで、証拠保全がしやすくなり、迅速な問題の解決につながります。
まとめ

デジタル資産の普及によって、相続の現場では新たな問題が起きています。一方的に名義を変更したり、パスワードを不正に利用してアクセスしたりする「不正取得」は、深刻なトラブルにつながるケースも多いです。このような行為は、相続人同士の信頼関係を損なうだけではありません。
相続における分割の公平性を、揺るがす可能性があります。デジタル資産は目に見える形で残らないため、情報格差のある相続人にとっては、その存在自体に気づけません。不正が長期間、発見されないリスクもあります。
このような課題に対応するためには、相続人の法的な枠組みに関する理解と、専門家の支援を受けることが重要です。これからの相続は、紙の通帳や不動産登記だけではなく、クラウド上の資産や仮想通貨、SNSアカウントなどの管理も視野に入れなければなりません。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼