スマホには、写真や動画、連絡先や日記のようなメモ、銀行口座や契約情報まで、故人の「人生の記録」といえる大切なデータが数多く残されています。しかし、スマホのロック画面やデータ暗号化の壁によって、家族であっても、簡単にアクセスできないケースが多いです。このような課題を解決するために、活用されているのが「デジタルフォレンジック調査」の技術です。
本来は、犯罪捜査や企業不正の解明に用いられてきた、高度な解析手法です。しかし、近年では、相続や遺品整理の場面でも利用されるようになっています。デジタルフォレンジック専門業者の手によって、故人が残した大切な情報を安全かつ正確に取り出せるのです。
今回の記事では、相続でさまざまなトラブルが発生するデジタル資産の現状と、デジタルフォレンジック技術の進展について解説します。この技術を応用した、故人のスマホロック解除の重要性に関しても、紹介していきます。
少子高齢社会が直面するデジタル資産の現状

少子高齢社会において、私たちが直面する大きな課題のひとつが「デジタル資産の承継」です。現役世代が当たり前のように利用しているネット銀行の口座、電子マネーの残高、証券会社のオンライン取引口座、さらには、クラウド上で管理される各種契約情報や定額サービスの利用履歴など、目に見えない「デジタル資産」が急速に増えています。
しかし、これらのデジタル資産は、紙の通帳や印鑑のように物理的な痕跡を残さないため、相続の現場では、見過ごされがちです。結果として、家族が存在すら気づかないまま、放置される資産が出てくるのです。
パスワードやセキュリティ設定に阻まれて、凍結状態になるケースが後を絶ちません。実際に、数十万円から数百万円にのぼる資産が「行方不明」のまま、埋もれてしまうケースがあります。残された家族が、困難な手続きを余儀なくされる事例も増えています。
人口減少と高齢化が進む今だからこそ、こうしたデジタル資産の承継に、正面から向き合う必要があります。社会全体で取り組む仕組みづくりが、求められるでしょう。単なる相続の問題にとどまらず、次世代への財産の橋渡しを、円滑に行うための重要なテーマです。
家族にとってのデジタル資産の価値とは

家族にとってのデジタル資産は、目に見える財産以上の意味を持ちます。銀行口座や証券、暗号資産といった経済的価値を伴うものだけではありません。スマホやクラウドに保存された写真・動画、日記やメッセージなどには、故人の生きた証や家族との思い出が残されています。
それらは金銭的に換算できるものではありません。家族にとってかけがえのない心の遺産です。また、日常生活に必要な契約情報やアカウントもデジタル資産に含まれます。これらを適切に引き継ぐことは、家族の生活を守るうえで欠かせない課題です。デジタル資産は「経済的価値」と「精神的価値」の両方を兼ね備えており、家族に安心とつながりをもたらす大切な存在になります。
増加するデジタル資産の問題と注目されるフォレンジック技術

インターネットやスマホが生活の中心となった現代、端末は強固なパスワードや、暗号化技術で保護されているため、持ち主に不測の事態が生じると、家族でさえ簡単にアクセスできません。相続や手続きが滞るケースが急増しています。単に資産を失うだけでなく、故人の思い出や生活の記録に触れられなくなることは、残された家族にとって大きな心の負担です。
こうした問題に対して、近年注目されているのが「デジタルフォレンジック技術」です。サイバー犯罪の捜査や、訴訟における証拠収集を目的に発展した高度な解析技術ですが、デジタル資産の分野にも活用が広がりつつあります。暗号化されたスマホやクラウドデータを合法的かつ安全に解析します。
必要な情報を取り出すことで、家族の生活を守り、故人の意思や思い出を将来へとつなげます。増加し続けるデジタル資産の課題に対して、デジタルフォレンジック技術は、新しい可能性を切り開く存在になるでしょう。
デジタル時代を守るフォレンジックの基礎知識

私たちの行動や取引の多くは「見えないデジタルの記録」として蓄積されていきます。しかし、その利便性が高まる一方で、サイバー犯罪や情報漏えい、不正アクセスなどのリスクは、年々深刻さを増しています。個人・企業を問わず、重大な被害につながります。
こうした状況に対応するために、近年注目を集めているのが「デジタルフォレンジック技術」です。これは、パソコンやスマホ、サーバー、クラウドサービスなどに残されたデジタルデータを、科学的に調査・解析する手法です。
その真正性や改ざんの有無を明らかにします。たとえば、企業の場合では、従業員による内部不正や情報の持ち出しを調べる際に活用されます。通信履歴を復元して証拠を特定したり、外部からのサイバー攻撃の痕跡を追跡したりして、侵入経路を突き止めたりすることが可能です。
また、刑事事件や民事訴訟の場面においては、これらの調査結果が「動かぬ証拠」として活用されることが多いです。デジタルフォレンジックは、過去の出来事を明らかにするだけではありません。企業のリスク管理やコンプライアンス体制の強化、さらには将来的なセキュリティ対策の改善にもつながる、重要な役割を担っています。
フォレンジックの定義とスマホ解析の特徴

フォレンジックは、先述の通り、法的な証拠として利用できるように、科学的手法でデータや情報を分析・調査する技術です。特に、デジタル機器を対象とするデジタルフォレンジックは、パソコンやスマホなどに記録されている、データの解析や保全を行います。
スマホの解析は、デジタルフォレンジックの重要な分野のひとつです。スマホ端末に保存された画像や動画、メッセージ履歴、通話記録、位置情報、ウェブ閲覧履歴、アプリの利用状況など、さまざまなデータの抽出や復元が行われます。
さらに、消去されたデータの復元や、暗号化された情報の解析まで対応できます。最近では、スマホ本体だけでなく、iCloudやGoogleアカウントなど、クラウド上のデータも対象です。この技術は、犯罪捜査や社内不正の調査、情報漏洩防止など、多岐にわたって利用されています。
警察だけでなく、民間のデジタルフォレンジック専門業者もサービスを提供しているのが特徴です。証拠となるデータは、改ざん防止の観点から、厳重に管理されて、法的効力を持つように手続きが取られます。スマホ解析は、現代社会で証拠を確実に掴むための不可欠な技術として、幅広い分野で活用されているのです。
| 対象の項目 | 内容 |
| 対象データ | 画像、動画、メッセージ履歴、通話記録、位置情報、ウェブ閲覧履歴、アプリ利用状況 |
| 対応可能な技術 | 消去データの復元、暗号化データの解析 |
| 解析範囲 | スマホ本体・iCloud・Googleアカウントなど、クラウド上のデータ |
| 主な利用分野 | 犯罪捜査、社内不正調査、情報漏洩防止 |
| 実施主体 | 警察・民間のデジタルフォレンジック専門業者 |
| 証拠管理 | 改ざん防止の観点から、厳重に管理、法的効力を持たせるための手続きに対応 |
| 社会的な意義 | 証拠を確実に掴むための不可欠な技術として、多分野で活用 |
復元可能なデータの種類と限界

まず、デジタルフォレンジックでは、通常のデータ復旧と比較して、広範囲かつ精度の高いデータ復元が可能です。対象となるデータは、パソコンやスマホ、ハードディスク、USBメモリーなどの記憶媒体です。ブラウザの閲覧履歴など、圧縮された状態で保存されている情報も解析可能です。これによって、通常の復旧では難しい詳細なデータの復元が可能です。
一方で、デジタルフォレンジックには、技術的・運用的な限界も存在します。暗号化されたデータに、高度な暗号がかけられている場合、復号キーがなければ、復元は非常に困難です。また、クラウドストレージ上のデータ取得は、権限やサービス仕様、ログ保持期間に制約があり、データの完全な取得が難しいケースがあります。
| 分類 | 内容 |
| 復元可能なデータ | ・ハードディスクやUSB上のファイル(通常ファイル、圧縮データの解凍・復元を含む) ・スマートフォンの通話履歴、メール、位置情報など ・ネットワーク機器における通信記録、パケットデータ ・ブラウザの閲覧履歴や圧縮データフォーマットの展開復元 |
| 限界・困難なケース | ・強力に暗号化されたデータの復号は困難 ・SSD特有のガーベジコレクションで、削除データ復元の難易度が高い ・クラウドデータは、権限や保持期間に依存しており、復元に制約あり |
故人のパソコンやスマホのデータ復元に関わる課題

突然の別れの後、残されたスマホを前にして「残された写真や動画、連絡先だけでも取り出したい」と思う家族は少なくありません。そこには、日常の思い出や大切なメッセージ、まだ伝えられていない約束の記録が眠っていることもあります。しかし、現実には、パスワードや指紋認証、顔認証といった強固なセキュリティの壁が存在します。
家族であっても簡単にアクセスできないケースが多いです。また、問題を複雑にしているのは、単なる技術的な課題にとどまらないという点です。故人のスマホデータの復元には、法律やプライバシーなどの、社会的にセンシティブな問題も絡みます。
「誰がアクセスする正当な権利を持つのか」「故人以外の第三者の情報が含まれている場合、どこまで取り扱えるのか」などの問題が、議論の対象にもなっています。思い出を守りたい家族の気持ちと、情報の保護を優先する法令の問題は大きなテーマです。その狭間で揺れる「故人のスマホデータ」は、相続の現場でも無視できなくなっています。
パスワードロックと暗号化の壁

パスワードロックや暗号化は、故人のデジタル資産を相続する際に、大きな壁になります。特に、パソコンやスマホなどのデバイスは、パスワードやPIN、生体認証でロックされているため、遺族はアクセスが行えません。スマホ内の情報を把握・管理しづらい状況に直面します。
パスワードロックの場合、間違った入力によって、一時的にアクセスができなくなる制限も存在します。遺族がパスワードを知らなければ、解除することは困難です。多くの場合、解除には、故人の誕生日や記念日、よく使っていたパスワードを推測する方法が取られます。しかし、それでも成功する保証はありません。
スマホのロック解除に成功するケースは、比較的多いものの、専門的な知識や技術が必要となる場合が多いのも現状です。データが暗号化されている場合、単にロックを解除するだけでは、中身の閲覧や利用ができません。暗号化解除のためのキーやパスワードが、さらに必要になります。暗号化の問題は、相続の大きな壁になる可能性があります。
デジタルフォレンジック調査における費用の問題

相続に関するデジタルフォレンジックの依頼には、時間と費用の問題が重要なポイントです。一般的に、調査の規模や内容によって、費用は大きく異なりますが、数十万円から数百万円が相場とされています。調査の時間に関しては、パソコン1台であれば、数時間で完了することもありますが、相続に関わるデジタル資産は、多岐にわたるケースが多いです。
そのため、数ヶ月かかることも珍しくありません。パスワード解除やアクセス権限の問題がある場合は、より多くの時間が必要です。迅速な対応が必要な場合は、休日や夜間も対応している調査会社を選ぶのがおすすめです。
また、相続のデジタル資産は種類や数が多いため、整理や評価が複雑になります。オンライン上の資産やアカウントの名義変更など、多くの手続きが関わります。デジタルフォレンジック調査会社に依頼する場合は、調査範囲を明確にしてから、依頼することが大切です。
| 項目 | 内容 |
| 費用の相場 | 数十万円~数百万円(調査の規模・内容により大きく変動) |
| 調査の時間(PC1台の場合) | 数時間で完了する場合もある |
| 調査時間(相続の資産が多岐にわたる場合) | 数ヶ月かかることもある |
| 追加の要因 | パスワード解除やアクセス権問題がある場合は、さらに時間を要する |
| 迅速に対応してほしい場合 | 休日・夜間対応可能な調査会社を選ぶと良い |
デジタルフォレンジック調査でよみがえる故人の記録

デジタルフォレンジック技術によって、消えたはずの大切なデータがよみがえります。故人が日々使っていたパソコンやスマホ、クラウド上に保存された情報の中には、家族が普段目にすることのない形で、大切な情報が残っています。
契約や財産に関わる重要なデータも入っているかもしれません。データが削除されていたり、アクセスが制限されていたりする場合でも、デジタルフォレンジック技術を駆使することで、状況によっては復元することが可能です。見えなくなってしまったメールや写真、文書、連絡先などが確認できます。
家族の心の整理や相続手続きの支援、法的な問題解決のサポートになるでしょう。デジタルフォレンジック技術を活用することで、消えたはずの記録が再び姿を現します。悲しみの中にも新たな希望を見出して、故人の人生や思いを、改めて感じることができるのです。
デジタルフォレンジック調査における倫理と法の課題

デジタルフォレンジックと相続に関する問題は、法律と倫理の両方の視点から慎重に考える必要があります。法律の面では、デジタルの権利や利用できる権限も相続人に受け継がれるのが基本です。実際に、海外の裁判では、デジタルアカウントの契約が相続人に引き継がれるケースが認められています。しかし、アカウントの利用規約によっては、アクセスが制限される場合があり、ここに法的な問題があるのです。
倫理の面では、故人のプライバシーや人格を尊重することが大切です。デジタル資産には、個人的な情報が多く含まれています。相続人が、これらのデータを見るときは、故人の意志やプライバシーを、十分に考慮しなければなりません。
デジタルフォレンジックの役割は、相続に関係するデジタル資産を調べて、必要な証拠を集めることです。しかし、その際には、プライバシー権を侵害しないように、厳しい倫理ルールを守ることが大切です。アカウントサービスの利用規約と相続人の権利が対立することもあり、この問題を解決するために、法律の整備も求められています。
故人のプライバシー保護と遺族の知る権利
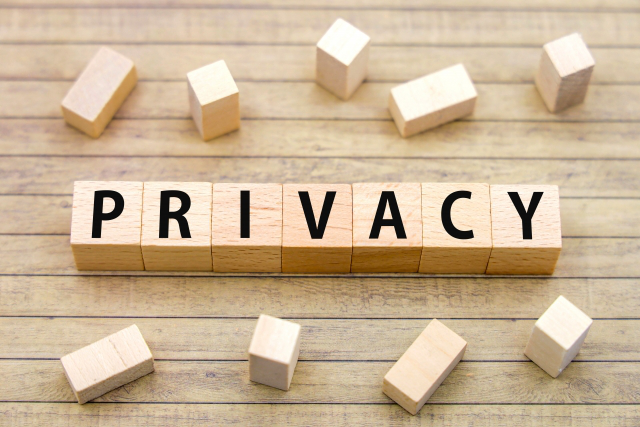
故人が残したデジタル資産は、パソコンやスマホに保存された写真や動画、連絡先、メール、オンライン口座や暗号資産などの金融情報まで、多岐にわたるでしょう。これらの情報にアクセスするには、パスワードやロック解除が求められることが多いです。そのため、専門的なデジタルフォレンジック技術を用いて、安全に解析して提供する専門業者が存在します。
法律的には、個人情報保護法は、生存する個人の情報を保護対象としているため、故人の情報自体は、法律上のプライバシー保護の対象にはなりません。そのため、家族が故人のデジタルデータを調査・閲覧すること自体は、原則として法的問題になりにくいです。
しかし、名誉毀損などの犯罪行為に関わる場合や、家族の個人情報が絡む場合は、注意しなければなりません。一方で、故人のデジタル資産には、遺族に伝えたい重要な情報と、逆に他者に知られたくないプライバシー情報が混在しています。家族の知る権利と故人のプライバシー尊重の間で、バランスを取ることが求められます。
故人が、生前にデジタル資産の管理や整理について、意思表示を行う「デジタル終活」も重要です。相続の場面で、スマホロック解除したい場合には、むやみにパスワードを試したり、端末を初期化したりすると、データが失われるリスクがあります。必要なデータを確認したい際は、デジタルフォレンジック専門業者への依頼も、検討した方が良いでしょう。
専門家が介入することで、故人のデジタル情報を安全に解析して、プライバシー面にも配慮した取り扱いが可能です。故人のデジタル資産は、遺族の知る権利と故人のプライバシー保護の双方を考慮しながら、法律や倫理に基づいて慎重に扱わなければなりません。最善の対応としては、故人が生前にデジタル資産について整理して、家族への引き継ぎの意思を、明確にしておくことです。
| 項目 | 内容のまとめ | 注意点 |
| 故人のデジタル資産 | 写真・動画・メール・連絡先、オンライン口座、暗号資産など多岐にわたる | スマホやPCに保存されて、アクセスにはパスワードやロック解除が必要 |
| アクセス方法 | デジタルフォレンジック技術を用いて解析が可能 | 専門業者が安全に対応 |
| 法律上の扱い | 個人情報保護法は「生存する個人情報」のみ対象 | 故人の情報自体は、保護対象外 |
| 法的リスク | 原則として家族が調査・閲覧しても問題になりにくい | 名誉毀損や他の家族の個人情報などには、注意が必要 |
| プライバシー | 故人の重要な情報と知られたくない情報が混在 | 家族の知る権利と、故人のプライバシー尊重のバランスが大切 |
| デジタル終活 | 故人が生前に整理・意思表示しておくことが重要 | 相続の場面で混乱を減らせる |
| データ保全 | 無闇なパスワード試行や端末初期化は危険 | データ喪失のリスクがある |
| 専門業者への依頼 | デジタルフォレンジック業者の活用が推奨 | セキュリティ・プライバシー配慮のもと、解析が可能 |
進化を続けるデジタルフォレンジック技術

急速に進化するデジタル社会の中で、デジタルフォレンジック技術も、日々革新を続けています。私たちの生活やビジネス活動は、かつてない速度でデジタル化が進んでいます。それによって、生成されるデータの量は、爆発的に増加しています。サイバー犯罪の手口もますます巧妙化・高度化しています。
こうした状況に対応するため、デジタルフォレンジックの分野では、より精度の高い解析手法の開発や、膨大なデータを効率的に処理するための自動化技術の導入が行われています。しかし、新しい技術の進歩は便利になる一方で、新たな課題も生み出しています。
クラウドサービスやIoT機器が広く使われるようになったことで、データが世界中に分散しました。どこにデータが保存されているのか、スマホ解析には、より高い技術が求められます。デジタルデータを、安全に解析して守ることが「遺産相続」や「証拠保全」などの場面でも、非常に重要になります。
AIや新技術の導入でデジタルフォレンジック技術も進展

AIや新技術の導入によって、デジタルフォレンジックの解析能力は大きく向上しています。AIのビッグデータ解析や機械学習の活用によって、証拠を効率的かつ高精度に抽出できるようになりました。暗号化データの解読技術の進化で、パソコンやスマホ、IoT機器など、さまざまなデバイスに対応したデジタルフォレンジック調査が行えます。
また、画像認識やディープフェイク検出、音声分析などのAI技術を活用した多角的な解析も進展しています。デジタル証拠の解析精度は、さらに高まっているのです。AIと新技術の導入によって、デジタルフォレンジック調査は高度化しています。サイバー攻撃の検出や、解析能力が強化されて、デジタル社会での重要な役割を果たしています。
家族向け相続支援サービスの充実と社会的な理解の向上

家族を支援する相続サービスは、大きく進化しています。葬儀社をはじめとする関連業界では、デジタル技術を活用したクラウドサービスの導入が進んでいます。家族がLINEやメールなどから、簡単に訃報連絡や弔電・供花の手配が行えるようになりました。これによって、相続の突然の準備で、家族の負担が大きく軽減されています。
さらに、デジタルフォレンジック技術の重要性も増しています。故人が残したパソコンやスマホのデータは、相続や財産管理において、重要な情報源です。パスワードが不明な場合でも、解析技術を活用して、データにアクセスできるケースが増えています。家族がデジタル資産を適切に取り扱うための支援も、社会的に認知され始めています。
一方で、こうしたサービスの充実には、社会的な枠組みや制度の整備も不可欠です。医療や福祉分野などでも、デジタルフォレンジックの認知を高めることが大切です。高齢社会が進むなかで、アクセスの難しいデジタル資産はさらに増えていくでしょう。デジタルフォレンジック専門業者との連携は、残された家族の負担軽減にもつながります。
デジタル資産管理の制度整備の動きについて

相続における、デジタル資産の制度問題は、日に日に注目されています。デジタル遺言書の制度化に向けた議論が、2025年現在も進められています。従来の紙の遺言書に代わって、パソコンやスマホでの作成・保管が可能な遺言書の仕組みが整備されつつあります。本人確認の方法や改ざん防止の技術面で、課題は残っていますが、利便性の向上が期待されています。
公正証書遺言の分野では、2025年から、オンラインで遺言を作成できる制度が導入される予定です。これによって、遠隔地に住む人や高齢者でも、公証人とビデオ通話を通じて遺言作成の手続きを進めることが可能になります。
このような法制度の動きは、家族の負担を軽減して、手続きの効率化につながります。一方で、デジタル資産そのものについては、明確な法律は整っていません。ネット銀行の残高や、仮想通貨のような一部のデジタル資産は、相続の対象です。しかし、SNSアカウントなどは、利用規約によって、相続が制限される場合があります。
企業ごとにルールが異なるため、デジタル資産の管理や、相続に関する共通ルールの整備が急がれます。デジタル遺言書の普及や、公正証書遺言のデジタル化は着実に進んでいます。法制度に関しては、少しずつ利便性が向上しているのです。デジタル資産に関する法律や、共通ルールの進展は、今後も相続の場面において、大きな課題になるでしょう。
| 分類 | 内容 | 現状と動向(2025年時点) | 課題と影響 |
| デジタル遺言書 | パソコンやスマホで作成・保管できる遺言書 | 制度化に向けた議論が進行中 | 本人確認の方法、改ざん防止の技術面に課題 |
| 公正証書遺言のデジタル化 | 公証人とビデオ通話を用いたオンライン作成 | 2025年より導入予定 | 遠隔地や高齢者の利便性向上、手続き効率化 |
| デジタル資産の相続 | ネット銀行口座、仮想通貨など | 相続対象として扱われる | 法整備不十分、各企業の規約が異なる |
| デジタル資産で相続制限のあるもの | SNSアカウント | 各サービスの利用規約で相続制限あり | 相続の統一ルールがなく、混乱の可能性 |
| 制度整備の必要性 | 共通ルール、法律の整備 | デジタル遺言や公正証書遺言の普及が進む | デジタル資産全般の法律・明確化が急務 |
| 期待される効果 | 家族の負担軽減、手続き効率化 | 制度進展に伴って利便性が向上 | 今後も大きな課題として、継続検討が必要 |
まとめ
デジタルフォレンジックは、単なる技術的な手法にとどまらず、私たちの生活やビジネス、社会全体の安全と信頼を支える重要な役割を担っています。技術革新によって、解析精度や効率は飛躍的に向上しています。
急速に進化するデジタル社会において、この技術を正しく理解して、倫理的・法的視点を踏まえて活用することが大切です。高齢化が進む日本では、サイバーセキュリティだけではなく、相続や証拠保全などの幅広い分野で、応用が期待されています。
特に、相続に関する問題において、デジタルフォレンジック技術の内容と可能性を深く理解することが重要です。故人のスマホを家族のみで解除するのは、セキュリティの観点から難しいでしょう。しかし、現代では、故人の大切な情報は、スマホ内にあることが多いです。
実際の相続の現場では、デジタル資産のトラブルが数多く発生します。家族間のトラブルが発生する前や、親族を巻き込む大きな問題になる前に、デジタルフォレンジック専門業者に相談してみることもおすすめです。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル資産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼

