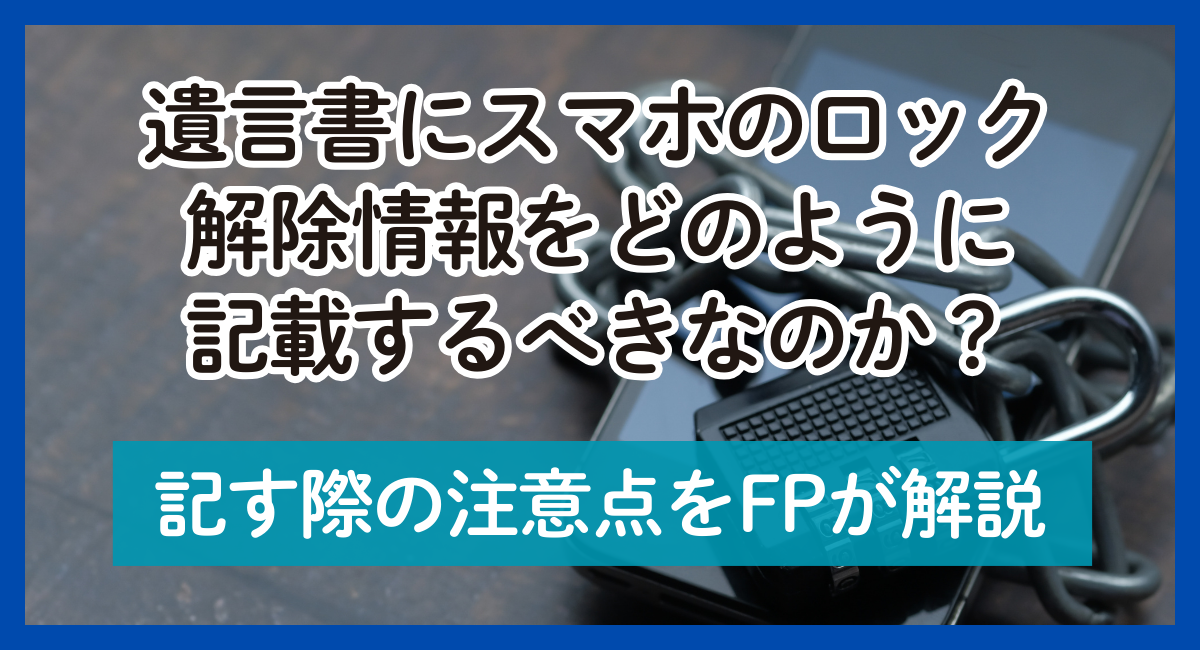スマホは今や財布や日記帳以上に、私たちの暮らしを映し出す存在になっています。写真や動画といった思い出の記録だけではありません。連絡先やスケジュール、金融機関のアプリやネット証券、電子マネーや各種サブスクリプション契約など、日常生活や資産管理に欠かせない情報が数多く保存されています。
しかし、万が一の時に、そのスマホがロックされたままで、家族が中身を確認できなかった場合、どうなるでしょうか。銀行口座の存在に気づけなかったり、継続的に課金される契約を止められなかったりするリスクがあるのです。大切な写真やメッセージが、二度と取り出せない可能性もあります。
こうした「デジタル資産」の存在が注目されるなか、遺言書にスマホのロック解除情報を残しておくことは、大切な相続対策と考えられるようになりました。しかし、単純にパスワードや暗証番号を遺言書に書き記すのは、情報漏れや悪用といったセキュリティ上のリスクを伴います。
今回の記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)の立場から、遺言書にスマホのロック解除情報を記す際の考え方と注意点について、わかりやすく解説していきます。
スマホには多くの資産や情報が保存されている

スマホには私たちの個人情報や資産に関わる重要なデータが多く保存されています。名前や住所、連絡先、メールアドレス、生年月日、勤務先の情報だけではありません。クレジットカード番号や各種サービスのID・パスワード、写真や動画、ウェブの閲覧履歴、自動ログイン設定のあるアプリの情報なども含まれています。
さらに、ビジネスで使われるスマホなら、顧客情報など企業の重要なデジタル資産が入っている場合もあるでしょう。そのため、スマホは、単なる連絡手段を超えている存在なのです。重要な情報資産の宝庫となっています。しかし、紛失や盗難、ウイルスやハッキングなどのリスクが伴います。情報漏洩や不正利用の危険が高まっているのです。
遺言書におけるスマホロック解除やデジタル資産の取り扱いが新たな課題に

デジタル資産の整理や相続がスムーズに進まず、家族が大きな負担を抱える事例が増加しています。その背景には、紙の通帳や現金といった、従来型の資産とは異なる「デジタル資産」の特性が深く関わっています。
デジタル資産の多くは、本人でないと分かりません。本人が管理しているIDやパスワードによって、情報が守られています。相続人であってもロックが解除できなければ、銀行口座や証券口座、仮想通貨ウォレットなどにアクセスできないでしょう。
資産の存在すら、確認できないケースが多いです。デジタル資産には、通帳や郵便物といった物理的な証拠が残らないため、相続人が「そもそも、その資産が存在すること」に気づきにくいです。その結果、資産の一部が埋もれたまま放置されたり、期限内に適切な手続きができずに、資産が失われたりするリスクが高まっているのです。
また、ネット銀行や証券会社、仮想通貨取引所の多くは、手続きがすべてウェブ上で行われますが、高齢の相続人や、デジタルに不慣れな家族にとっては、操作が複雑です。対応が難航するケースが増えています。相続開始後に新たなデジタル資産が発見されることも珍しくなく、遺産分割協議のやり直しや、相続税の追加申告が必要になるケースもあります。
家族間のトラブルや税務上の問題につながる事例も少なくありません。数百万円から数千万円規模の、仮想通貨ウォレットにアクセスできずに、資産を失うケースもあります。サブスクリプションサービスや通信契約が解約されず、不要な費用が延々と引き落とされる問題も挙げられます。
デジタル資産は、今後ますます増加する可能性が高いです。対策を怠れば、相続の現場で深刻な混乱を招きかねません。生前の準備をしておくことが、残された家族を守り、相続トラブルを未然に防ぐ確実な方法です。
| 故人のデジタル資産 | 具体的な内容 | リスクと課題 |
| 資産の把握が困難 | デジタル資産は、通帳や郵便物などの物理的な証拠が残らない | 資産の存在すら確認できず、相続財産から漏れる |
| アクセス制限 | 本人が設定したID・パスワードで保護されているため、相続人でも解除不可 | 銀行口座・証券口座・仮想通貨ウォレットにアクセスできず、資産を失う |
| 高齢者・非デジタル層の困難 | 相続手続きがウェブ上で完結するが、家族がデジタルに不慣れ | 操作に苦労して、手続きが遅延・放置される可能性がある |
| 相続開始後の新資産発覚 | 相続手続き後に、未発見のデジタル資産が判明 | 遺産分割協議のやり直し・相続税の追加申告が必要になる |
| 家族間トラブル | 資産発見の遅れ・不均衡な分配 | 相続人同士の争いや関係が悪化する |
| 多額の資産喪失 | 数百万円~数千万円規模の仮想通貨ウォレットにアクセス不可 | 資産消失という深刻な被害が発生する |
| 不要契約の放置 | サブスクリプションや通信契約が解約されない | 費用が長期間、引き落とされるかもしれない |
| 今後の拡大リスク | デジタル資産は今後さらに増加予測 | 生前対策を怠ると、混乱・損失が拡大する |
スマホに眠る「デジタル資産」

スマホには、普段使っているネット銀行の口座やSNSのアカウント、写真や動画、電子マネーなどの暗号資産といった「デジタル資産」が数多く保存されています。これらの資産は実体のないものですが、財産として非常に重要です。しかし、スマホに眠るデジタル資産は気づかれにくく、相続の際に問題になることがあります。
デジタル資産の取り扱いは、2025年現在の相続の法整備において、まだ十分ではありません。サービスごとの取り扱いや、利用規約に沿った対応が求められます。ネット銀行に眠る資産が10年以上動きがないと休眠預金として扱われ、指定活用団体を通じて公益活動に活用される可能性があります。
家族が知らなかったスマホ内の資産が、後で見つかることもあります。このようなトラブルを避けるためには、生前に自分のデジタル資産の種類やパスワードを整理しておき、遺言書やエンディングノートなどに、記録しておくことが大切です。スマホに保存されたデジタル資産は、現代の私たちの大切な財産であるため、適切な管理と対策が必要です。
写真・動画などの思い出

相続できる写真や動画は、故人がスマホやパソコンなどのデジタル機器に保存していたものが中心です。これらの写真や動画は、保存された機器の所有権とともに相続されるため、機器を相続した人が中のデータも管理・処分する権利を持ちます。
一方で、SNSなどのオンラインサービスに保存された写真や動画は、そのサービスの利用規約により、相続の対象外となる場合があります。デジタル写真や動画の相続では、保存されている場所やアクセス方法を整理して、家族に伝えておくことがトラブル回避のポイントです。
「スマホやパソコン内に保存された写真や動画」は遺品として相続可能ですが、オンライン上のサービスで管理されているものは、サービス規約により相続できないこともあるため、注意しなければなりません。
| 保存場所 | 相続の可否 | 理由・注意点 |
| スマホ・パソコンなどのデジタル機器内の写真や動画 | 相続可能 | 機器の所有権とともに、中のデータも相続対象となる。相続人が管理・処分する権利を持つ。 |
| SNSやオンラインストレージサービス上の写真や動画 | 相続不可の場合あり | 利用規約によっては、相続の対象外となる。サービスごとの規定に依存する。 |
| 全体的な注意点 | ― | 写真・動画がどこに保存されているか、アクセス方法を整理する必要がある。家族へ伝えておくことで、トラブル回避につながる。 |
金融アプリ(ネット銀行・証券口座)

ネット銀行やネット証券の口座は、通常の銀行口座や証券口座と同様に、相続の対象になります。しかし、店舗がないため、相続手続きは主に郵送や電話で行われます。まず、故人が取引していたネット銀行や証券会社を把握して、各社のコールセンターに死亡の報告をしなければなりません。その後、相続手続きに必要な戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が送付されるため、これらを準備して提出します。
証券口座の場合は、故人の口座から相続人の新しい口座へ資産を移管する手続きが必要です。その後、相続人が株式の売却や換金を行うことができます。ネット銀行は、通帳が発行されないこともあり、家族が口座の存在に気づかない場合があります。そのため、口座の有無を、早めに確認することが重要です。
サブスク契約(解約が必要なサービス)

故人が契約していたサブスクは、契約者が亡くなっても自動的に解約されるわけではなく、遺族が解約手続きを行う必要があります。解約せずにそのままにしておくと、料金が引き落とされ続けるため、注意が必要です。
まず、故人がどのサブスクを利用していたかを確認することが重要です。スマホやパソコン、メール、クレジットカードの明細、エンディングノートなどを調べて、契約状況を把握します。そのうえで、各サービスの解約方法を確認しましょう。これは家族が手続きを進める必要があります。
解約手続きには、死亡診断書や戸籍謄本、身分証明書などの書類が求められることが多いです。ログイン情報がわかれば、家族が直接マイページから解約ができますが、わからない場合は、必要書類を揃えて、サービスの問い合わせ窓口に連絡しなければなりません。
サブスクリプション契約は、家族が主体的に管理して解約する必要があります。トラブルを避けるためには、故人が生前に契約内容を整理しましょう。遺言書やエンディングノートなどに、記録しておくことが大切です。
| サブスク契約に関する項目 | 内容 |
| 自動解約の有無 | 契約者が亡くなっても自動的に解約されない。遺族が解約手続きを行う必要がある。 |
| 解約しない場合のリスク | 料金が引き落とされ続ける。 |
| 契約状況の確認方法 | ・故人のスマホ・パソコン ・メール ・クレジットカードの明細 ・エンディングノート |
| 解約方法の確認 | 各サービスごとに手続きが異なるため、解約方法を確認する必要がある。 |
| 必要書類 | 死亡診断書、戸籍謄本、身分証明書などを求められる場合が多い。 |
| 解約の手順 | ・ログイン情報がある場合:遺族がマイページから解約可能になる。 ・ログイン情報がない場合:必要書類を揃えて問い合わせ窓口に連絡する必要がある。 |
| 管理の注意点 | 家族が主体的に管理・解約しなければならない。 |
| トラブル回避の準備 | 契約者本人が生前に契約内容を整理して、遺言書やエンディングノートに記録しておくことが望ましい。 |
SNSやメールなどのアカウント
故人が使っていたSNSやメールアカウントは、相続の対象にならない可能性があります。SNSのアカウントが個人の権利とされて、多くのサービスがアカウントの譲渡や相続を認めていないためです。そのため、故人の家族がアカウントを引き継いで利用したり管理したりすることは、基本的にできません。
しかし、アカウントを放置すると、不正利用や悪用のリスクが高まります。そのため、家族は速やかにSNS運営会社に故人の死亡を伝えて、アカウントの削除や閉鎖、もしくは追悼アカウントへの移行手続きを、行わなければなりません。
たとえば、FacebookやInstagramでは、追悼アカウントに変更できる場合があります。手続きには、死亡証明書や遺族の身分証明書が求められます。ログイン情報が分からなくても、これらの書類を提出することで対応してもらえるのです。また、プライバシー保護の観点から、運営側が安易にアカウント情報を家族に開示しないことも多いため、専門家に相談する必要もあるでしょう。
なぜ遺言書でスマホロック解除を考える必要があるのか

遺言書でスマホのロック解除について考えておく理由は、先述の通り、スマホが故人の重要なデジタル資産を多く含むためです。スマホには、写真や連絡先、メッセージ、金融情報、パスワードなど、さまざまな個人データが保存されています。これらにアクセスできなければ、故人の家族は大切な情報を取り出せません。
スマホのロックがかかっていると、遺族が必要な手続きを進める際に支障が出たり、故人の思い出を確認できなかったりします。また、資産管理やアカウントの解除を行う際に、ロック解除ができないと、さまざまな問題が生じる可能性があります。
スマホのロック解除ができないと資産調査が進まない

スマホのロックが解除できないと、資産調査が思うように進められません。最近は、銀行口座や証券、仮想通貨ウォレットなどの金融資産の情報を、スマホで管理している人が多いです。調査に必要な取引履歴や口座番号、関連するメールなども、多くはスマホ内に保存されています。
そのため、ロック解除が行えないと、こうした情報にもアクセスできません。資産の全貌を把握できなくなってしまいます。もしロック解除ができない場合は、まず、パスコードや生体認証の方法を、再度確認しましょう。家族や関係者による共有設定や、代理アクセスが可能なのかも調べてください。
また、非公認のソフトやハッキングなど、不正な方法でロック解除を行うのは、違法となる可能性があります。必ず正規の方法で、スマホロック解除を試みましょう。ロックを繰り返し間違えると、端末によっては、中のデータが消去される場合があるので、慎重に対応することが大切です。困ったときは、スマホロック解除の専門家へ相談するのもおすすめです。
金融機関に預けている資産の行方

故人のIDやパスワードが分からない場合、金融機関に預けている資産の解約や、引き出し自体ができないわけではありません。しかし、オンラインで通常通りログインして手続きをすることは、不可能です。そのため、金融機関の窓口で直接「相続手続き」を進める必要があります。
故人が亡くなったことが判明した時点で、金融機関は、故人名義の口座を凍結します。IDやパスワードが分からなくても、相続人が除籍謄本や戸籍謄本、印鑑証明などを金融機関に提出することで、資産の解約や払い戻し手続きが進められます。こうした手続きには、一定の期間を要するケースが多いです。すぐに引き出しができるわけではありませんが、正規の相続手続きを踏めば、最終的に資産が受け取れます。
また、葬儀費用や急な支払いが必要な場合には、一部現金を事前に引き出せる「仮払い制度」が設けられている金融機関もあります。IDやパスワードが不明でも、慌てる必要はありません。必要な書類を揃えて、金融機関へ相談することで、故人の資産の解約や引き出しが進められます。
| 金融機関に預けている場合 | 内容 |
| ID・パスワード | 情報が分からない場合、オンライン手続きが困難になる。 |
| 金融機関の対応 | 故人の死亡が判明した時点で、口座が凍結される。 |
| 手続き方法 | 相続人が金融機関の窓口で「相続手続き」を申請する必要がある。 |
| 必要書類 | 除籍謄本、戸籍謄本、印鑑証明などが必要になる。 |
| 手続き期間 | ある程度の時間を要するため、すぐの引き出しはできない。 |
| 資産の引き出し・解約 | 正規の相続手続きを踏むことで、最終的に可能になる。 |
| 特別制度 | 葬儀費用や急な支払いに備えて、一部現金を事前に受け取れる「仮払い制度」を設けている金融機関もある。 |
| 注意点 | IDやパスワードが不明でも慌てない。必要書類を揃えて、金融機関に相談することが重要になる。 |
遺言書での記載方法と注意点
遺言書にスマホのロック解除に関する内容を記載する場合には、さまざまな点に注意しなければなりません。まず、ロック解除に必要なパスワードやPIN、パターンなどの情報を記す必要があります。一方で、セキュリティ上の理由から、これらの情報を遺言書に直接書かないようにしてください。別の安全な場所にメモとして保管して、その所在を遺言書に記載するのがおすすめです。
また、スマホやその中にあるデジタル資産を、誰に相続させるのかを明確にしておくことで、相続時のトラブルを防げます。さらには、パスワードの変更や紛失があった場合の対応方法や、連絡先を遺言書に示しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。併せて、スマホ内の個人情報の取り扱いについての指示を残しておくことも、大切なポイントです。
さらに、遺言書はできるだけ公正証書遺言など、法的効力の確かな形式で作成するのが良いでしょう。自筆証書遺言の場合、内容の伝達に不確実性が残ることがあるため、注意が必要です。遺言書に直接パスワードを書き込むと、家庭裁判所での開示時に、第三者に知られるリスクがあります。そのため、解除情報の保管場所だけを、記しておく方が安全です。スマホのロック解除に関する情報を、遺言書に整理して記載することで、家族の間でのトラブルが避けられます。
スマホロック解除に関する遺言書の書き方
遺言書を書く際には、相続させたい人や財産をできるだけ具体的に記載しましょう。たとえば、「私の全財産を長男に相続させる」や「土地と建物は、長女に相続させる」といったように、誤解の余地が出ないように、明記してください。また、遺言書の全文、日付、署名は、すべて自筆で書く必要があります。押印も忘れずに行ってください。
財産の内容が複雑な場合や、特に注意したい点があるときは、専門家に相談することもおすすめです。また、大切なデータを家族が確実に受け取れるように、遺言書やその別紙、エンディングノートなどに、スマホのロック解除コードやパスワード、操作方法のヒントを記載しましょう。
パスワードを伝える方法は、慎重かつ安全に選び、信頼できる家族や専門家に預けておくのも良いでしょう。遺言書には、法的要件を満たすことだけではなく、家族が困らないように、丁寧な情報や工夫を盛り込むことが大切です。スマホやデジタル資産の対策も、現代の相続において、工夫しなければならない要素です。
| 項目 | 内容 | 具体例・注意点 |
| 相続人・財産の記載 | 相続させたい人や財産を具体的に記載する | 「私の全財産を長男○○に相続させる」 「東京都○○区○○の土地と建物は長女△△に相続させる」 |
| 法的要件 | 遺言書は、全文、日付、署名をすべて自筆で書く必要がある | 押印も忘れずに行う |
| 専門家の活用 | 財産が複雑な場合や特別な注意点があるときは、専門家に相談する | 弁護士・司法書士などに依頼すると安心 |
| デジタル資産の対策 | スマホやPCにあるデータも、重要な遺産となる | 写真、連絡先、アカウント情報など |
| スマホ情報の引き継ぎ | 遺言書や別紙、エンディングノートにパスワードのヒントを記載する | パスワードが書かれたメモの場所を記載 |
| パスワード管理 | 伝達方法は慎重・安全に選ぶ | 信頼できる家族や専門家に預ける方法もある |
必要なパスワードは安全な場所で管理する
相続において、信頼できるパスワード管理ツールを活用して、パスワードを一元管理するのも有効です。たとえば、エンディングノートには、そのツールのアクセス方法や、マスターパスワードを記載することで、安全かつスムーズに、デジタル資産の管理が可能になります。デジタル資産には、金融口座や暗号資産、電子マネー、NFTなど、多岐にわたる資産が含まれます。
これらの情報は、暗号化メモやパスワード付きの記録媒体に保存しましょう。生前に整理しておくことで、相続時のトラブルや、情報漏洩のリスクを大きく減らせます。家族に見せたい情報のみを、共有フォルダやクラウドの共有機能にまとめるのもおすすめです。
それ以外のデータは、厳重にパスワード管理しておくことで、見せる範囲を明確に区別できます。エンディングノートに、直接パスワードを書き込むのは避けてください。パスワード管理ツールや、暗号化メモの保管場所や利用方法を記載しましょう。生前にデジタル資産の整理・管理を行うことで、相続の際に家族が困らず、情報の安全性も保たれます。これらは、デジタル遺産の円滑な相続のために、欠かせない準備です。
公正証書遺言と組み合わせることで安全性と確実性を高める
公正証書遺言と故人のスマホロック解除の情報を組み合わせることで、安全性と確実性を大幅に高められます。スマホには、パスワードや指紋認証など複数のロック解除方法があり、これらを解除するには、故人が設定した情報が必要です。しかし、家族が故人のスマホを確実に開けるようにするためには、単にパスワードを知っているだけでは不十分です。
相続人全員の同意や、法的な手続きの根拠も重要になります。そこで、公正証書遺言にスマホのロック解除情報や、デジタル資産の取り扱いについて、明確に記載することが効果的です。この方法によって、家族はスマホのロック解除をスムーズに行えます。
資産の管理や契約の解約など、相続手続きの悩みが大きく軽減できるでしょう。また、解除失敗によるデータ消去のリスクを避けられます。公正証書遺言でデジタル資産の取り扱いを明確にしておくことは、故人のスマホロック解除の安全性と確実性を高めます。家族間のトラブル防止と、相続手続きの円滑化につながるのです。
専門家にスマホロック解除の相談を行うべきケース
故人のスマホがロック解除できない場合、専門業者への依頼を検討しましょう。専門業者は、特殊な機器や解析技術を使って端末のロック解除を試みるため、一般的な方法では、解除できない場合でも対応してくれます。一方で、ロック解除の依頼には、法定相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類を、用意しなければなりません。
また、専門業者に依頼した場合でも、100%解除できるとは限りません。そのため、まずは故人のパスワードのヒントを探してください。パスワードが分からず、それでも解除できない場合は、信頼できる専門業者を選びましょう。個人情報の取り扱いや実績などを確認したうえで、スマホロック解除の依頼を行うのがおすすめです。
高額なデジタル資産(暗号資産、証券口座など)がある場合
高額なデジタル資産を所有している場合は、専門家に相談することが非常に大切です。暗号資産や証券口座などのデジタル資産は、相続や税務の手続きが複雑で、専門的な知識が求められます。スマホロック解除の専門業者や弁護士などに相談することで、円滑な遺産分割が可能になり、トラブルを防ぐことができます。
特に、仮想通貨は価格の変動が大きいです。故人の保有していた仮想通貨の現状について、早めに確認しなければなりません。専門家のサポートを借りることが安心です。また、デジタル資産は、それぞれのサービスごとに相続手続きが異なり、資産の所在や評価が難しくなります。資産の詳細を専門家にきちんと伝えて、適切な管理や準備を進めることが必要です。
家族間でトラブルが予想される場合

家族でトラブルが予想される場合には、早期に専門家に相談することがおすすめです。遺産分割や感情的な対立が激しくなる場合は、弁護士への相談が良いでしょう。弁護士は、調停や審判、訴訟など、法的手続きの代理が可能です。遺言書の有効性や、遺留分の問題などにも対応できます。
その一方で、故人のスマホのロック解除は、相続の場面においても、難しい問題です。家族が解除を試みると、何度も間違えることでロックが強化されます。解除不能になるリスクが高まります。スマホロック解除の専門業者は、スマホの機種ごとに異なる解除方法やパスワード解析技術を熟知しています。データ復旧やデジタル資産整理の実績も豊富です。
一方で、解除にかかる費用が業者によって異なるため、相談や見積もりの依頼を行いましょう。なお、悪質な宣伝や非正規のツールには十分注意してください。実績のある信頼できる業者に依頼することが重要です。トラブルを回避して、確実に故人のデータにアクセスするためにも、専門の業者への相談が大切になります。
| 項目 | 専門家の対応と内容 | 補足 |
| 家族トラブル発生時の対応 | 専門家への相談がおすすめ | 感情的な対立や遺産分割で、紛争が激化する前に、相談するのが望ましい |
| 弁護士に依頼するメリット | ・調停、審判、訴訟など法的手続きの代理を行う ・遺言書の有効性を確認する ・遺留分問題の対応を進める | 相続トラブルの際にサポートが受けられる |
| スマホロック解除の課題 | ・家族が無理に解除を試みると、失敗回数でロックが強化される ・解除不能になるリスクあり | 安易な操作は避けた方が良い |
| スマホロック解除の専門業者に依頼するメリット | ・機種ごとの解除方法と解析技術を熟知している ・データ復旧やデジタル資産整理の実績がある | 安心して故人のデータにアクセスできる |
まとめ
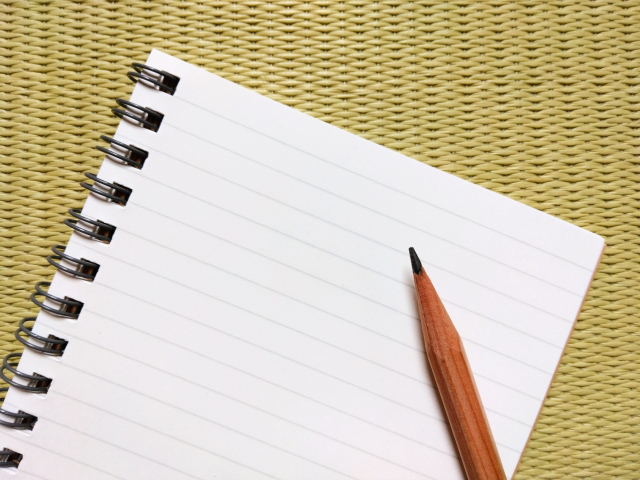
デジタル社会が進むなかで、相続の現場では「スマホのロック解除」は避けて通れない課題です。従来の相続準備では想定されなかった、データ管理やパスワードの引き継ぎは、これから重要性を増していくでしょう。生前のうちに準備を整えることが大切です。
スマホロック解除で大切なのは「残された家族が困らないように準備しておくこと」です。相続の形が紙からデジタルへと変わる時代だからこそ、安心できる承継の仕組みを整えていきましょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル資産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。