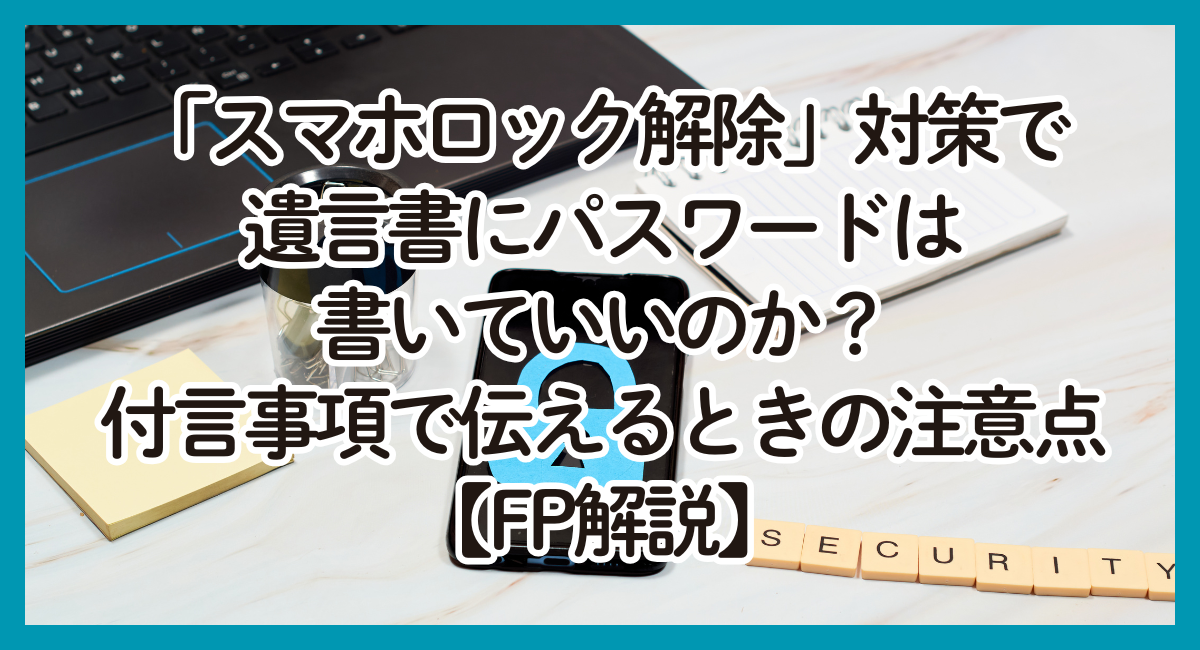いざというとき、故人のスマホロック解除が行えず、大切な情報にアクセスできないのは避けたいところです。しかし、近年、こうしたトラブルが相続の現場で増えています。スマホには、写真や動画といった思い出だけでなく、銀行口座や各種契約の確認メールなど、相続に欠かせない「カギ」が数多くあります。しかし、その入り口を守るのがパスワードです。
「遺言書にスマホのパスワードを書いておけば、安心なのでは?」と考える方もいるかもしれません。実はそこには、情報漏洩や法的リスクといった、大きな落とし穴があります。今回の記事では、遺言書の付言事項の活用方法にも焦点をあてて、スマホロック解除の対策をどのように講じるべきかを、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点からも解説します。
デジタル時代に急増しつつある「パスワード解除」の課題

スマホやパソコン、ネット銀行や証券口座、電子マネーやポイントサービスは、私たちの暮らしに大きく根付いています。いまや数多くの「デジタル資産」に大きく依存している状況です。買い物や送金、投資、日々のコミュニケーションまでもが、オンラインで完結する時代になっています。こうした資産は、もはや現金や不動産と同じくらい、大切な財産のひとつです。
しかし、その多くはIDやパスワードによって厳重に守られており、所有者の本人以外は、簡単にアクセスできません。そのため、本人が亡くなった後、相続人がログインできずに、銀行口座の残高や証券口座の資産を確認できないケースが増えています。スマホに保存された写真や連絡先にも、アクセスできない事例が多いのです。
そのような状況から、相続手続きや資産の整理が大幅に遅れる、資産そのものの存在に気づかれず、事実上「失われてしまう」といった問題も起こっています。
先ほどのように、「遺言書に、パスワードを書いておけば安心だろう」と考える方もいます。確かに一見すると、相続人が迷わずアクセスできるようになり、便利な方法に思えるかもしれません。しかし、遺言書にパスワードを直接記載することには、大きなリスクが潜んでいます。
遺言書の付言事項とは?「家族へのメッセージ欄」を上手く活用しよう

遺言書には、大きく分けて2つの要素があります。ひとつは、どの財産を誰に相続させるかといった具体的な分け方を記載する「本文」です。こちらは、法律的な効力を持ちます。家庭裁判所でも、有効性が確認されて、実際の遺産分割にも直接影響します。
もうひとつが「付言事項」です。付言事項には、法的な拘束力こそありません。一方で、相続人に対して、自身の思いや考え方、財産の分け方に込めた背景が伝えられます。これは、残された家族が遺産分割を話し合う際に、大きな参考となるものです。
たとえば「長男に自宅を相続させるのは、同居して介護をしてくれたことへの感謝の気持ち」と書いておけば、他の家族も納得するでしょう。配分の理由を伝えることで、不公平感や誤解が生まれるのを、防ぐ効果も期待できます。
付言事項は、単なる形式的な補足ではなく、相続人同士の理解を深めるきっかけです。円滑な遺産分割を進めるための「心のメッセージ」として大切な役割を果たします。
| 付言事項の項目 | 内容 |
| 付言事項とは | 遺言書において、法律的効力はないが、遺言者の背景・気持ち・希望などを補足的に記載できる |
| 遺言事項との違い | 遺言事項は法的拘束力を持つが、付言事項は法的拘束力を持たない |
| 役割 | ・遺言者の真意を伝える ・相続に関する争いの防止や緩和に役立つ |
| 遺留分との関係 | ・一部の相続人に多くの財産を遺す理由を説明できる ・他の相続人に「遺留分の請求を控えてほしい」と希望を表すことができる(ただし強制力はない) |
| 効果 | ・法的に効力はないが、遺言者の気持ちを理解してもらいトラブル防止につながる ・相続人の納得を促す |
| 記載例 | ・「長女に多く遺す理由」 ・「遺留分を請求しないでほしい」 ・治療や尊厳死に関する希望 ・感謝の言葉 ・葬儀方法の希望など |
相続で知っておきたい「遺留分」を簡単に解説

相続では、故人の財産をどのように分けるかが大きな関心事です。その際に重要な役割を果たすのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、法律によって相続人に保障されている最低限の取り分のことを指します。
たとえ故人が「全財産を特定の人に相続させる」と遺言を書いても、配偶者や子ども、親など一定の相続人には、法律で守られた「遺留分」があります。遺留分を侵害する内容の遺言は、そのままでは実現できません。
遺留分があるのは、配偶者、子ども(または孫などの代襲相続人)、直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。もし遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合、相続人は「遺留分侵害額請求権」が活用できます。不足分を金銭で請求できるのです。請求が行える期限は、相続の開始と侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内です。遺留分は、相続人の生活を守り、不公平な遺産分割を防ぐための、大切な制度になります。
| 遺留分について | 内容 |
| 遺留分とは | 相続において、法律で一定の相続人に保障された最低限の取り分 |
| 制度の意義 | ・遺言で「全財産を特定の人に」とされても保障される ・相続人の生活を守る ・不公平な遺産分割を防ぐ |
| 遺留分がある相続人 | ・配偶者 ・子ども(または孫など代襲相続人) ・直系尊属(父母など) |
| 遺留分がない相続人 | 兄弟姉妹 |
| 遺留分を侵害した場合 | 相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使できる |
| 請求方法 | 不足分を金銭で請求が可能 |
| 請求期限 | ・相続の開始と侵害を知った日から1年以内 ・または相続開始から10年以内 |
遺言書における「付言事項」の役割と「遺留分」の対処法

先述の通り、付言事項には法的拘束力はありません。つまり、記載されている内容を、必ず実行する必要はありません。しかし、付言事項は、遺言者の真意や思いを相続人に正しく伝えるための重要な手段です。相続に関するトラブルや争いを未然に防ぐうえで、大いに役立ちます。特に、遺留分に関わるケースでは、付言事項が活用されることが多く見られます。
たとえば、一部の相続人に多くの財産を遺贈する理由や、その決定に至った背景を丁寧に記すことで、他の相続人が納得しやすくなります。また「遺留分請求を行わないでほしい」という希望を付言事項として、書き添える場合もあります。
もちろん、これは法的に遺留分の請求を禁止するものではありません。しかし、遺言者の考えや感謝の気持ち、配慮の意図などを示すことで、相続人が互いの立場や想いを、理解しやすくなります。争いを和らげる効果が期待できるのです。
特定の財産の管理方法や遺産分割の希望、家族間で大切にしてほしいことなどを明記しておくことで、相続人が迷うことなく、手続きが進められます。繰り返しになりますが、付言事項は、法律上の強制力は持たないものの、遺言者の思いや意図を相続人に伝えるうえで、有効な手段です。
遺言書に「スマホロック解除」のパスワードを直接書くリスク

付言事項にパスワードをそのまま記載することは、ファイナンシャルプランナー(FP)の立場からもおすすめできません。一見すると「家族が迷わなくて便利そう」と思えるかもしれません。しかし、実際には下記の大きなリスクを抱えています。
- 情報漏洩の危険性:家庭裁判所の検認手続きで関係者の目に触れる
- 法的リスク:相続人が検認前にアクセスすれば、不正アクセス禁止法に抵触する可能性
- 家族間トラブル:誰かが勝手に利用すれば資産流出や相続争いの火種に
第一に、情報漏洩の危険性です。遺言書は本人の死後、家庭裁判所の検認手続きを経て、相続人全員に内容が開示されます。そのため、そこにスマホやネット銀行のパスワードが記載されていれば、相続に関係のある人なら、誰でも目にできる状態になるでしょう。
家族以外の第三者に知られる可能性もゼロではなく、漏洩リスクは、高いと言えるかもしれません。次に、法的なリスクになります。仮に相続人のひとりが、検認前に遺言書を開封して、そこに記載されていたパスワードを使ってアクセスした場合、法律上は「不正アクセス禁止法」に抵触する可能性があります。
善意の場合であっても、時期や方法を誤ると、違法行為とみなされてしまうため、注意しなければなりません。家族間のトラブルにもつながります。誰かが先にパスワードを利用してデータや資産にアクセスすれば、「勝手に資産を動かした」といった疑念を生みます。相続争いの火種になる可能性が高いです。
信頼関係が損なわれれば、相続手続きがスムーズに進まず、家族間の関係を悪化させる結果になりかねません。つまり、遺言書にパスワードをそのまま記載するのは「書いておけば安心」どころか、情報漏洩・法的リスク・家族間トラブルを同時に引き起こしやすい、危険な方法なのです。大切な資産を守るつもりが、結果として、家族を困らせるかもしれません。
| 区分 | 内容 |
| 情報漏洩の危険性 | 家庭裁判所での検認手続きにより、関係者の目に触れる可能性が高い |
| 法的リスク | 相続人が検認前に遺言書等へアクセスすれば、不正アクセス禁止法に抵触するおそれがある |
| 家族間トラブル | 誰かが勝手に利用すれば、資産の流出や相続争いの火種になる可能性がある |
付言事項に書くべきはパスワードではなく「方針」

実際のパスワードをそのまま遺言書に書き残すのではなく、管理方針や希望を明確に伝えることが大切です。付言事項は法的拘束力こそありませんが、相続人がどのように動けばよいかを考える上で、大きな道しるべとなります。
たとえば、次のような内容が考えられます。
- 「私のスマートフォンやパソコンに保存された写真や動画は、家族で整理して、思い出として共有してほしい」
- 「ネット銀行や証券口座などのデジタル資産は、弁護士を通じて正式な手続きを進めてほしい」
- 「具体的なパスワードやログイン情報は、別途保管している書面にまとめてあるので、弁護士に確認してほしい」
このように記載すれば、家族は「どのように対応すればよいのか」という方向性を理解できるでしょう。相続を進めるときの、迷いや混乱が避けられます。パスワードを直接書かないことで、セキュリティリスクも抑えられます。
付言事項はあくまでも、心のメッセージです。家族に対する思いや配慮を残す部分です。そこに、具体的な情報を記すのではなく「どこに託したのか」「どのように扱ってほしいのか」といった方針を示すことで、残された家族は、安心して行動できます。結果として、スムーズな相続手続きや、デジタル資産の整理につながるのです。
エンディングノートで守れる?大切なデジタル資産のパスワード管理方法
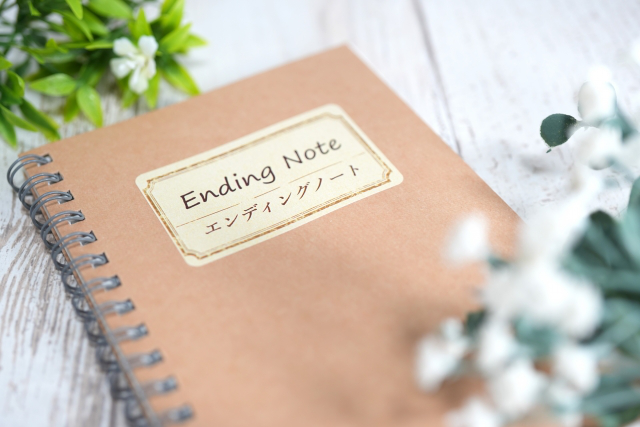
大切なデジタル資産のパスワード管理は、終活において非常に重要なテーマです。スマホやクラウドサービスの普及により、銀行口座やSNS、写真データなど、多くの情報がデジタル空間に保存されています。万が一に備えて、家族がこれらの資産にアクセスできるように、安全かつ確実なパスワード管理が必要になるでしょう。
エンディングノートを活用することで情報を一元化し、家族に引き継ぎやすくなります。ただし法的効力はないため、遺言書と併用するのが望ましいです。しかし、ただパスワードを書き記すだけでなく、防犯性を考慮した管理方法や、デジタル終活に適したツールの活用も欠かせません。
| 項目 | 内容 |
| 重要性 | スマホやクラウドの普及で、銀行口座・SNS・写真データなど、多くの情報がデジタル資産として存在する。家族がスムーズにアクセスできるように、安全で確実な管理が必要になる。 |
| 活用方法 | エンディングノートに情報を一元化することで、家族への引き継ぎがしやすくなる。防犯性やツールの活用も重要である。 |
| メリット | ・家族にデジタル資産の「存在を伝えられる」 ・一覧化することで資産の把握が容易になる |
| デメリット | ・紙に書く場合、盗難・紛失リスクがある ・パスワード変更に対応するため、書き直しが必要になる ・法的効力がなく、遺言書の代わりにはならない |
スマホロック解除のパスワードを書くときの注意点

エンディングノートにパスワードをそのまま書き残すことは、セキュリティ上のリスクが非常に高いため、避けるべきです。代わりに、まずは「自分がどのサービスを利用しているのか」を記載しておくと良いでしょう。たとえば、銀行口座、証券会社、クレジットカード、サブスクリプションサービスなど、利用しているサービスを一覧にまとめておいてください。それだけでも、残された家族がデジタル資産を把握しやすくなります。
一方で、実際のパスワードまでは、エンディングノートに書かず、別の方法で安全に管理することが重要です。たとえば「パスワード管理アプリを活用する」「暗号化したUSBや、外付けハードディスクに保存する」などの方法が考えられます。これらを利用することで、セキュリティを確保しつつ、必要なときにアクセスできます。
保管場所や伝え方にも工夫が必要です。「信頼できる家族のみに知らせる」「専門家に相談して適切な方法を取る」など、万が一に備えて、安全な伝達方法を決めておきましょう。そして、エンディングノートに情報を残す際には、必ず「更新日」を記載してください。古いパスワードがそのまま残っていると、後で家族が混乱してしまう可能性があります。
定期的に見直して、優先度の高いサービスから、順に最新の情報を記録することがおすすめです。たとえば、銀行や証券口座などの金融関連サービスは、最も優先度が高いと考えられます。次に、メールアドレスやスマホのロック解除の方法、最後にSNSサービスといった具合に、整理すると分かりやすいでしょう。
情報の性質に応じたエンディングノートの書き方

エンディングノートの活用で大切なのは、情報の性質によって、扱いを分けることです。「利用しているサービス名」や「ユーザーID」のように、ある程度公開しても良い情報は、エンディングノートに直接記載しても、問題ありません。一方で「パスワード」や「復旧用の秘密の質問」などの機密性が高い情報は、別の安全な方法で管理する必要があります。
役割を分けることで、家族に必要な情報を確実に残しつつ、セキュリティリスクが抑えられます。エンディングノートには、パスワードそのものではなく「どのサービスを利用しているか」という観点で書き残すのが大切です。安全な管理方法を併用することで、安心と利便性の両立が可能になります。
| 項目 | 内容 | 補足・注意点 |
| 記載する内容 | 利用しているサービス名やIDのみ | パスワードは書かない |
| パスワード管理 | パスワード管理アプリ、暗号化USBなど、別の安全な方法で保管する | 紛失・漏洩を防ぐため、エンディングノートには記載しない |
| 保管場所・伝え方 | 信頼できる家族のみに伝える、貸金庫に保管、専門家に相談する | 広範囲に知らせない、限られた相手だけにする |
| マスターパスワード・復旧方法 | 必要最低限の人に伝える、暗号化して残す | 紛失時の復旧手段を、同時に明記しておく |
| 更新日 | 必ず記載する | 古い情報が残って、無用なトラブルにならないようにする |
| 記載の順序 | 優先度の高いサービスから順に書く | 銀行・年金・保険など、重要度が高いものから記載する |
相続対策に役立つパスワードマネージャーの選び方と活用法

相続対策としてパスワードマネージャーを利用する際には、相続人がアクセスできる「緊急アクセス機能」があることが重要です。GoogleやAppleなどの純正パスワードマネージャーは、操作が簡単で無料で使用できますが、2025年現在、相続に必須の緊急アクセス機能がありません。そのため、別途アクセスする方法を考える必要があります。
相続を見据えたパスワードマネージャーの選定では、緊急アクセス機能の有無を重視しつつ、普段使いやすくセキュリティが高いツールを選ぶことが大切です。また、パスワードマネージャーのマスターパスワードは、信頼できる家族に伝えて、紙など物理的な方法でも、管理しておくと安心です。
FPが勧めるスマホロック解除の「安全なパスワード管理」

デジタル資産の相続に備えるには、単にスマホロック解除のパスワードを書き残すだけでは不十分です。重要なのは、相続人が迷わず、アクセスできる仕組みをあらかじめ整えておくことです。
- 紙に書いて封筒で保管:金庫や貸金庫に入れて、遺言書で所在を明示する
- パスワード管理アプリ:マスターパスワードを家族に伝える
- 専門家や信託サービスに預ける:弁護士や信託会社に委託して、安全に引き継ぐ
FPの立場からおすすめする方法としては、まず紙に書いて封筒で保管する方法があります。パスワードやログイン情報を封筒に入れて、金庫や貸金庫などで保管するのです。たとえば、遺言書の付言事項で「封筒は自宅の金庫にある」と所在を明示しておくことで、相続人は迷わず、確認できるでしょう。
パスワード管理アプリの活用も有効です。複数のアカウントやログイン情報を一括管理できるアプリを利用して、マスターパスワードのみを家族に伝える方法になります。この場合、どのアプリを使用しているのか、操作方法、マスターパスワードの所在を明確にしておくことが、スムーズな相続のためには重要です。
また、弁護士をはじめとした専門家に預ける方法もあります。専門家に委託することで、安全性を確保しつつ、確実に相続人に引き継ぐことができます。資産が多い場合や、家族間でトラブルになりやすい場合には、第三者に管理を任せるのが安心です。
どのような方法でも「家族が迷わずアクセスできる形にしておくこと」です。情報を単純に残すだけでは、相続人が混乱するかもしれません。場合によっては、トラブルにつながる可能性が高いです。そのため、遺言書や付言事項で、所在や引き継ぎ方を明示して、アプリや専門家サービスを組み合わせて、安全性を高めるのが大切です。
家族に対して、事前に使い方や確認の手順を伝えておくことで、スマホやデジタル資産の相続も、安心して任せられます。FPとしては、こうした準備を早めに始めることをおすすめします。デジタル資産の管理は、家族の負担を減らして、円滑な相続を実現するための重要なステップです。
| 方法 | 内容 | メリット | 注意点・ポイント |
| 紙に書いて、封筒で保管 | パスワード・ログイン情報を紙に記録していく。封筒に入れて、金庫や貸金庫で保管する。遺言書の付言事項で、所在を明示する。 | ・シンプルで確実に管理できる ・専門知識不要 ・相続人が迷わない | ・盗難・火災リスクがある ・情報更新のたびに書き直しを行わなければならない |
| パスワード管理のアプリを活用 | アプリで複数のアカウントを、一括管理できる。マスターパスワードを家族に伝えておく。 | ・利便性が高い ・変更や更新が手軽 ・運用コストが小さい | ・マスターパスワードの管理が重要になる ・アプリの利用方法を、相続人に明確に伝える必要がある |
| 専門家(弁護士・信託会社等)に預ける | 専門家に資産情報やアクセス方法を託す。 | ・安全性が高い ・公平性・確実性が担保される ・トラブル防止につながる | ・費用がかかる ・信頼できる専門家選びが、必須になる |
| 共通のポイント(FPの視点) | 家族が、迷わずアクセスできるように工夫する。 | ・遺言書や付言事項で所在を明示できる ・アプリや専門家サービスを組み合わせると安心できる ・事前に家族へ使い方・手順を伝えておく | ・情報が残っていても、相続人が理解できなければ、意味がない |
デジタル資産の取り扱いに迷ったら専門業者に相談してみよう

スマホには、故人が日常的に残してきた写真や動画、メールのやり取りの記録が数多く保存されています。また、銀行口座や証券口座、クレジットカードの管理アプリ、公共料金や保険など、生活に直結するサービスがスマホを通じて利用されています。そのため、故人の暮らしと人生の記録が凝縮された「デジタル資産」の代表格です。
しかし、このスマホロック解除ができなければ、大切なデータに相続人がアクセスできません。暗証番号やパターンロックを忘れていたり、本人以外が知らないまま亡くなってしまったりすると、相続人が端末を開くことは、非常に難しくなります。
そのような場合には、専門の業者にスマホロック解除を依頼するという選択肢があります。自力で解決するのが困難なスマホのロック解除でも、専門業者の技術によって、データを残したまま端末にアクセスできるのです。相続人にとっても、資産の整理や手続きを、円滑に進められます。専門業者への依頼は、故人の残した大切な思い出を守り、デジタル資産を受け継ぐための有効な手段です。
相続のスマホロック解除で活用されるデジタルフォレンジック

故人のデジタルデータは、相続や資産の整理において、重要なテーマです。しかし、その情報はスマホのロック解除ができなければ、確認できません。こうしたデジタル資産を、安全かつ効率的に確認できるのが「デジタルフォレンジック」と呼ばれる技術です。
デジタルフォレンジックとは、電子機器に保存されたデータを解析・復元・保全する技術です。もともとは、サイバー犯罪の捜査や企業の情報漏洩調査で発展した技術になります。しかし、近年では、故人のスマホやパソコンのデータを整理して、相続や遺産管理に役立てるケースが増えています。
具体的には、故人のスマホやパソコンに残された写真、動画、メッセージ、通話履歴、メールなどを復元して、大切な情報を家族が確認できるようにするのです。削除されたデータや暗号化されたファイルも、条件によっては復元が可能です。ただし、最新機種では復元できないケースも多くあります。
また、銀行口座アプリや電子マネー、暗号資産(仮想通貨)、契約情報やポイント残高など、さまざまなデジタル資産を把握できるのです。これにより、相続人は故人の資産の全体像を把握しやすくなり、遺産分割や遺言の意図を確認する際の、補助として役立ちます。
| デジタルフォレンジックについて | 内容 |
| 背景 | スマートフォン・パソコン・クラウドサービスの普及により、故人のデジタルデータも重要な資産となっている。 |
| 定義(デジタルフォレンジック) | 電子機器に保存されたデータを解析・復元・保全する技術である。 |
| 本来の活用分野 | サイバー犯罪捜査、企業の情報漏洩調査などが該当する。 |
| 相続分野での活用 | 故人のスマホやパソコンのデータを整理し、遺産管理や相続に役立てる。 |
| 具体的な復元・確認できる対象 | 写真、動画、メッセージ、通話履歴、メールなどが含まれる。 |
| 復元の可能性 | 削除されたデータや暗号化されたファイルも、条件次第で復元が可能になる。 |
| デジタル資産の把握 | ・銀行口座アプリ ・電子マネー ・暗号資産(仮想通貨) ・契約情報やポイント残高 など。 |
| メリット | ・故人の財産の全体像を把握しやすくなる ・遺産分割や遺言の意図確認の補助となる ・大切な思い出(写真・メッセージ等)を家族が共有できる |
「スマホロック解除」専門業者を選ぶ際の注意点

相続に関わるスマホデータを扱うため、業者選びは特に慎重に行う必要があります。
- 本人確認や相続人確認の徹底(戸籍謄本や死亡診断書を求める業者は信頼性が高い)
- 契約書や利用規約で「個人情報の取り扱い」の明記
- 料金の明確さ(成功報酬のみといった不透明な料金体系は注意)
- 相続やデジタル遺産に関する実績
相続において故人のスマホロック解除は「感情面の整理」だけではありません。「相続手続きの円滑化」にも直結します。しかし、相続人であっても、安易に解除できるものではなく、専門的な技術を要するケースがほとんどです。
必要書類を準備したうえで、信頼できるスマホロック解除専門業者に依頼することで、大切な思い出や重要な情報を、安全に引き継ぐことができます。相続の一環として、スマホのデータもきちんと整理していくことが、これからの時代には欠かせないポイントです。
まとめ

現代では、スマホやパソコン、ネット銀行、証券口座、ポイントサービスなど、さまざまな形で資産がデジタル化しています。相続の場面でも、デジタル資産が今後も増える可能性があります。特にスマホロック解除問題で悩まないためにも、遺言書の付言事項やエンディングノートの活用がおすすめです。
また、FPの視点から特に重要なのは「どのような方法を選ぶ場合でも、家族が迷わずアクセスできる形にしておくこと」です。情報をただ残すだけでは、相続人が混乱して、思いがけないトラブルに発展するかもしれません。
遺言書の付言事項で、所在や引き継ぎ方を示したり、アプリや専門業者を組み合わせたりして、万が一に備えた対策を行うのが大切です。最後に、こうした準備は早めに始めることが肝心です。デジタル資産の管理やパスワードの所在を整えておくことで、相続の際に、スマホロック解除の問題も発生しないでしょう。家族の負担を軽減して、トラブルのない相続手続きが実現できます。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル資産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。