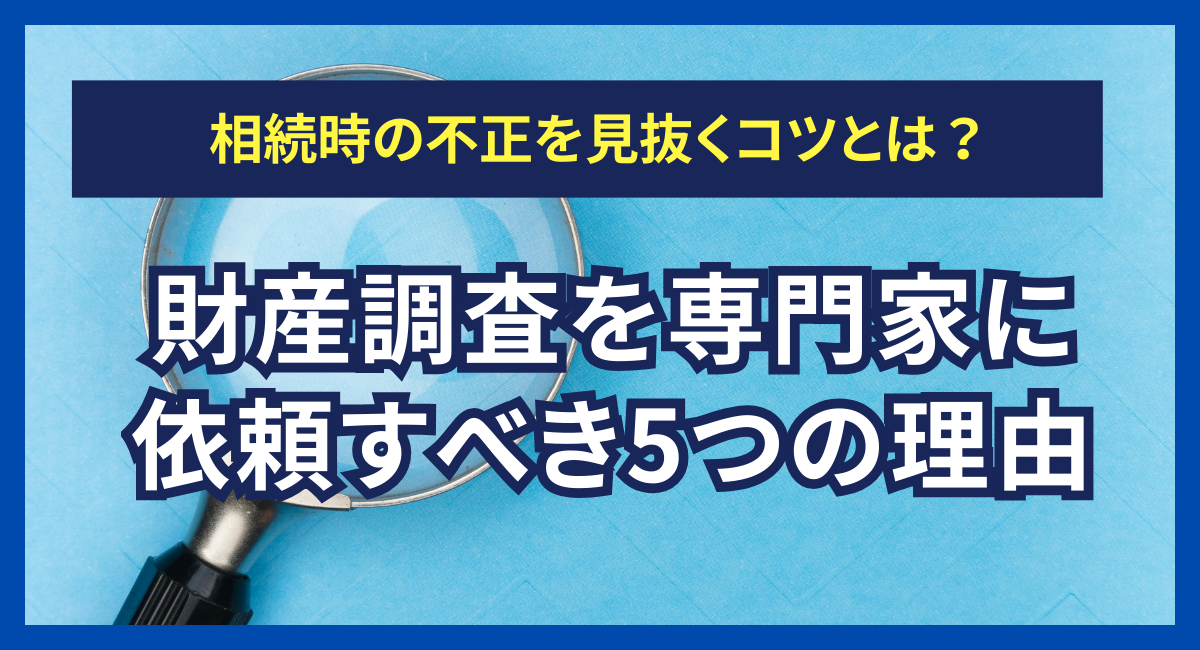相続は家族の財産を適切に引き継ぐための、ライフイベントの一つです。しかし、悲しみの中で手続きを進める必要があるため、冷静さを欠いたまま遺産分割や相続税申告に臨んでしまうケースも少なくありません。
さらに、相続の場面では「財産隠し」や「不正な引き出し」などのトラブルが起きることもあり、親族間の信頼関係に深い溝が生まれることもあります。
こうした不正を防ぎ、公平で円滑な相続を実現するためには専門家による「財産調査」が欠かせません。本記事では、相続時に見落としやすい不正の兆候や、専門家に財産調査を依頼すべき理由について解説します。
なぜ相続時の財産調査が重要なのか

相続が開始されると、複数の相続人がいる場合は被相続人の財産を分けるために「遺産分割協議」が必要です。被相続人の財産の種類や総額を確定させた上で話し合いを行い、相続人全員の同意の下で遺産分割協議を完了させます。
しかし、財産の一部が漏れていたり、過小評価されていたりすると、分割の公平性が失われてしまうため協議が紛糾してしまいます。そこで、この章では相続時に欠かせない財産調査について、重要性を解説します。
遺産分割協議や相続税申告に必要となるため
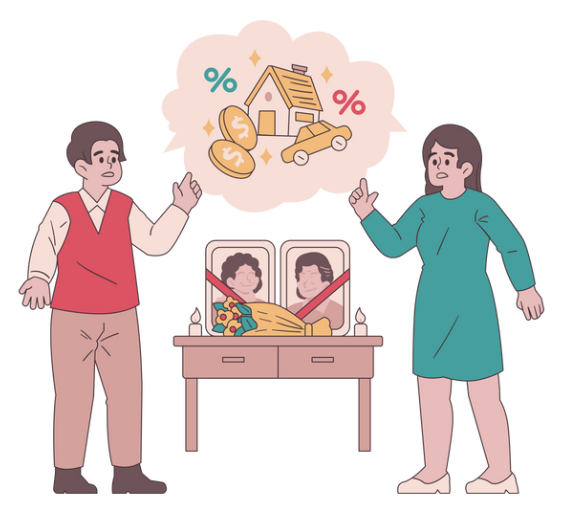
被相続人がなくなったら、所有していた以下の財産を調査し、財産の内容を確定させる必要があります。
- プラスの財産…預貯金や不動産、仮想通貨、車両など
- マイナスの財産…ローンや消費者金融等からの借入、連帯保証、滞納税など
財産を把握した上で、遺産分割協議を行い、さらに必要に応じて相続税申告を行います。
不当な財産隠しを見つけるため
相続時にトラブルになりやすいのが「財産隠し」です。こうした場合、家庭裁判所での調停や不当利得返還請求といった法的手続きに進むケースもあります。
こうした不正を見抜くには、専門的な調査力と第三者の視点が欠かせません。財産調査を行うことで、不正が早い段階で発覚できるため適切な遺産分割協議が可能です。また、疑わしい事態が発覚した段階で、速やかに調停や損害賠償請求、不当利得返還請求を行うこともできます。
相続時に見落としがちな不正の兆候とは


「兄から、父親の財産の内訳を聞いたけど本当に正しいのだろうか」



「母と同居していた長女が、生前に母の口座からお金を出していなかったか気になる」
相続時の財産調査では、すでに被相続人が亡くなられており、生前に保有していた財産の保管場所や金額を直接聞きだすことができません。そこで、この章では相続時に見落としがちな、相続財産への不正について兆候をわかりやすく紹介します。
預貯金口座から不審な引き出しがある


相続開始直前に多額の引き出しが行われている場合、相続人の誰かが被相続人に承諾を得ずに無断で資金を動かした可能性があります。特に「定期的に生活費として使う範囲や、介護・医療への支払いを超えた金額」が動いている場合は注意が必要です。
また、定期的に資金を移している場合、金融機関などの取引履歴に記録が残されていることがあります。「被相続人の財産が思っているよりも少なかった」と感じたら、不正な引き出しなどの財産移転がなかったか調査が必要です。
中身がない金庫や貸金庫がある
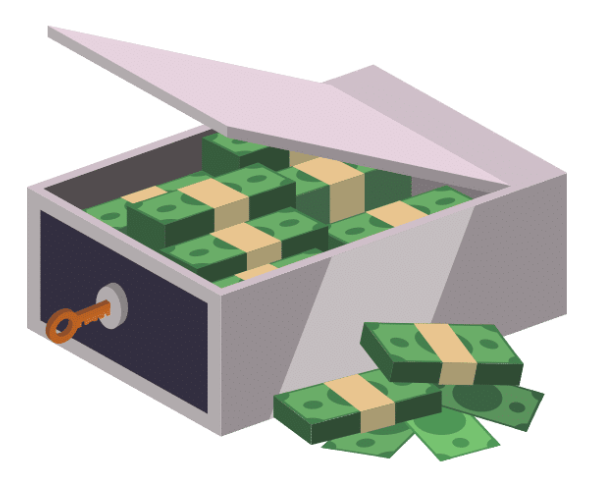
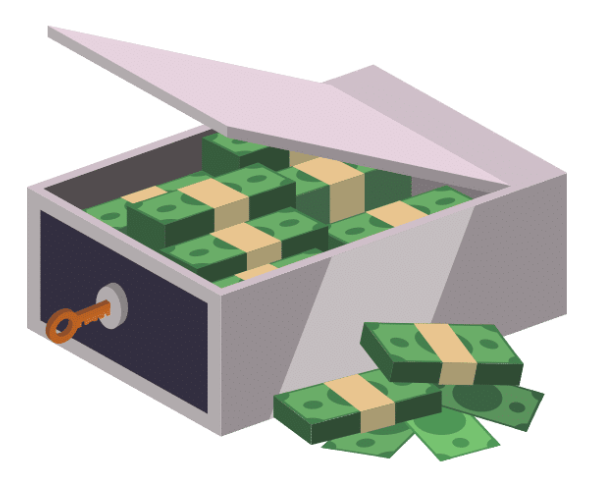
被相続人が金庫を所有していたのに、中身が空になっているケースにも注意が必要です。預貯金通帳や証券口座に関する情報、金融資産が記録されていたエンディングノートや遺言書などが破棄されたおそれがあります。
貸金庫も同様で、亡くなる直前に財産が移動されている可能性があるため、契約履歴や利用状況を確認することが大切です。
生前に聞いていたはずの財産がない





「父がネットバンキングにも口座を持っていると言っていた」



「亡くなった子から、生前に仮想通貨があると聞いていた」
生前の会話で存在を知っていた財産が、相続手続きの段階で確認できないことがあります。こうした場合、名義変更や財産隠し、不当な売却が行われていないかを徹底的に調べる必要があります。
不明になっているデジタル資産がある


近年増えているのが、暗号資産やネット証券口座といった「デジタル資産の見落とし」です。紙の通帳や証書が残っていない、あるいは発行されていないことが多く、相続人が気付かないまま放置されるおそれがあります。調査ではインターネット上の取引履歴や端末データの確認も重要です。
相続財産の調査を専門家に依頼すべき5つの理由
不正な行為を迅速に見抜き、適切な相続手続きを行うためには、被相続人の財産に関する調査を専門家へ依頼することがおすすめです。そこで、本章は専門家へ依頼すべき5つの理由をわかりやすく解説します。
1.ご親族が見落としやすい財産が見つかる
家族や親族だけで調査を行うと、現物で確認できる預貯金や不動産などの表面的な財産しか把握できないことがあります。
デジタル資産の発見にも精通している専門家はスマホやパソコンなどのデバイスの中にも調査を行えるため、相続財産の見落としを防ぐことができます。
2.専門的な手法で調査できる
財産調査の専門家は、専門機器を用いた財産調査ももちろんですが、過去の経験に基づいた調査も行っています。一部の端末やアカウントについては専門技術により調査可能な場合がありますが、最新機種では解除が困難なこともあります。
3.隠されていた財産が見つかる可能性がある
相続人等の親族によって意図的に隠された財産も、専門的な調査を通じて発覚することがあります。隠した相続人をいくら追及しても、証拠がなければ回答に応じないことは少なくありません。しかし、専門家の調査で証拠が見つかれば返金や分割に応じる可能性は高いでしょう。
4.調査にかかる時間を短縮できる
相続人自身がすべてを調べるのは膨大な労力と時間がかかります。特に財産の種類が多い場合は、1つひとつ見つけていく必要があるため、大変な負担です。そこで、デジタル資産など一部でも調査を専門家に依頼すれば、効率的に情報を集められ、余計な負担を軽減できます。
5.相続手続きの期限内に解決できる
相続税申告には期限があります。遺産分割協議には期限が設けられていませんが相続税申告や相続登記にも影響するため、できる限り早期に話し合いを解決することが重要です。
専門家に依頼することで、期限内に必要な調査を終えられるため、余計なトラブルやペナルティ(追徴課税)を避けられます。


デジタル資産は隠されやすい!やるべき2つのコツ
近年急増しているのが「デジタル資産をめぐる相続トラブル」です。仮想通貨やネット証券口座、電子マネー、ポイントなどは通帳や書面に残らないため、存在自体に気づけないケースが多く、デバイス管理やオンライン上の資産に精通した相続人に財産を隠されるケースも多発しています。
「パスワードがわからない」「なぜかスマホやパソコンにログインできない」という理由から、デジタル資産の不正調査を行わず、泣き寝入りしてしまう相続人もいます。
しかし、こうしたデジタル資産も調査や専門家の介入によって見つけ出すことが可能です。泣き寝入りの前にすべき2つのコツを紹介します。
相続財産不正調査の専門家へ依頼


デジタル資産を含めた財産調査は、相続調査の専門家へ依頼することで、正確な財産の種類や金額が確定できる可能性が高くなります。
相続財産不正調査2.0のような、相続時の不正行為追及に経験と実績がある専門家なら、資産の隠匿や過少申告にも毅然と調査を通して立ち向かうことが可能です。
※ここへ相続財産不正調査2.0のリンクがおすすめ
調停や訴訟は弁護士に依頼


もしも親族の誰かの手によって財産隠しや不正が発覚した場合、相続人同士の話し合いでは解決できないケースもあります。その場合は家庭裁判所での調停や訴訟に発展することもあり、ここからは弁護士の力が必要です。証拠を基に法的に主張を行うことで、正当な相続権を守ることができます。
まとめ
本記事では相続時の財産調査を専門家へ依頼すべき5つの理由をわかりやすく解説しました。相続は家族の未来を左右する重要な手続きです。
しかし、財産調査を怠れば、不正や財産隠しを見抜けず、結果的に正当な権利を失ってしまう可能性があります。特にデジタル資産のように「隠されやすい資産」は早めの対応が欠かせません。
泣き寝入りせず、公平な相続を実現するためには、まずは専門家へのご相談がおすすめです。お気軽に「相続財産不正調査2.0」へお問い合わせください。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼