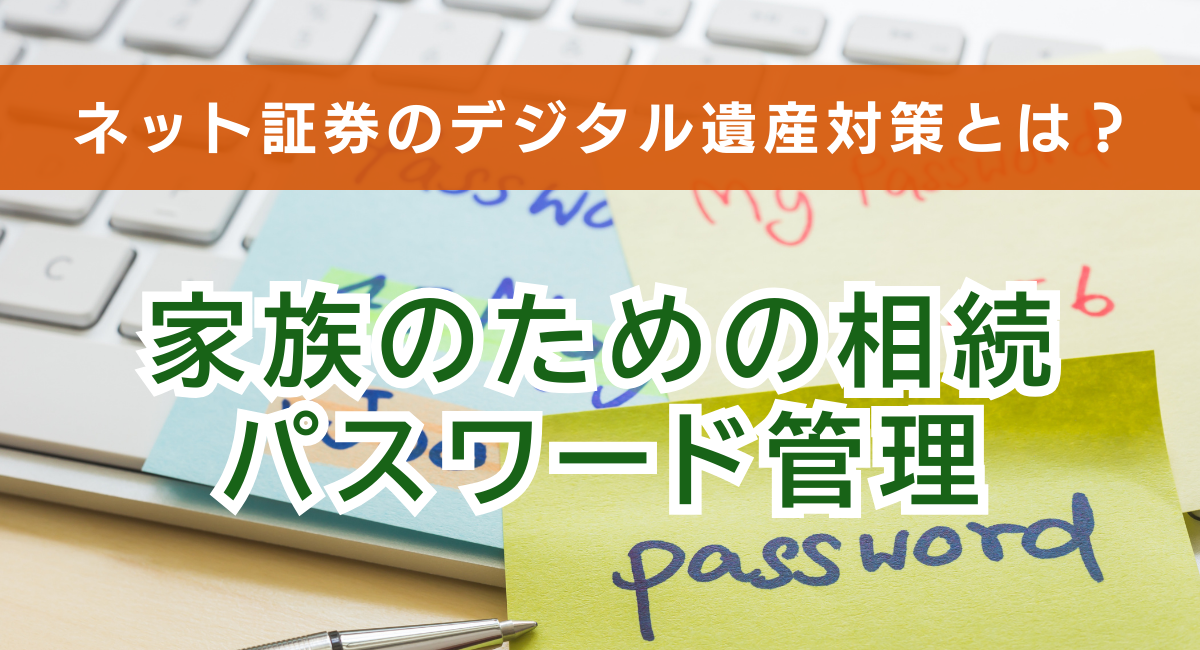スマホやPCから簡単に取引ができるネット証券は、現代のお金の運用において欠かせない存在となっています。店舗に出向く必要がなく、少額から投資を始められる手軽さや、取引スピードの速さ、手数料の安さなど、多くのメリットがあります。
一方で、こうした利便性の高さは「相続」という場面において、特有の課題を生むこともあります。たとえば、故人がどのネット証券に口座を開設していたのか、またどのような商品に投資していたのかが分からないケースは珍しくありません。さらに、ログインに必要なIDやパスワードが不明な場合、家族が残された遺産の存在を把握することは難しいです。
相続の手続きが、大幅に遅れてしまう可能性があります。紙の取引明細が送付されることが少ないため、口座や保有遺産が「見えにくい」という点が大きな障害になりやすいのです。
こうしたリスクに備えておくには、あらかじめ相続発生時に必要となる手続きや提出書類を理解しておかなければなりません。一般的には、故人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になります。証券会社ごとに指定の書類が求められるケースもあり、事前に確認しておくことがスムーズな手続きにつながります。
また、パスワードや口座情報の管理方法についても工夫が必要です。セキュリティ上のリスクを避けつつ、もしもの時に家族が速やかに遺産を確認できるよう、信頼できる方法で記録を残しておくことが望まれます。ネット証券を利用している方にとって、相続の準備は「まだ先のこと」と思われがちですが、予期せぬ事態はいつ訪れるか分かりません。
口座情報の整理や、家族への共有方法を見直しておくことで、残された家族が安心して遺産を引き継ぎ、無用なトラブルを避けることができます。今回の記事では、ネット証券における相続手続きの具体的な流れや必要書類、安心できるパスワード管理のポイントを分かりやすく解説します。
ネット証券口座の相続をめぐる現状

近年、スマホやパソコンを利用した投資が一般的です。多くの人がネット証券の口座を開設しています。ネット証券は手数料が比較的安く、オンラインでいつでも取引が可能です。しかし、相続の場面では、さまざまな課題が存在します。特に、故人のIDやパスワードが不明な場合には、相続人がネット証券口座にアクセスできず、遺産の正確な把握や管理が難しくなります。
この問題によって、相続手続きが著しく遅れるケースが多発しているのです。相続手続きにおいては、単に口座を一時的に凍結したり、名義変更を行ったりするだけでは、完結しません。多くの場合、過去の取引履歴や残高、保有している株式や投資信託の種類など、詳細な内容を把握しなければなりません。たとえば、故人がさまざまな銘柄に分散投資していた場合、それらの管理状況を一つひとつチェックして、適切な評価を行う必要があります。
また、ネット証券口座は紙の通帳や取引明細が存在しないことが多く、オンライン上の情報に頼らざるを得ません。そのため、故人が利用していたメールアドレスやID、パスワードの保管状況が、相続手続きの成否を大きく左右するのです。ログイン情報が分からなければ、相続人が遺産の種類や金額を知ることができず、結果的に遺産の一部が、未発見のまま残ってしまうリスクもあるでしょう。
さらに、近年、ネット証券口座をめぐる不正アクセスの事例も報告されており、相続時には特に注意が必要です。こうした背景から、ネット証券の相続手続きは、財産移転の問題にとどまらず「遺産の安全管理」や「リスク対策」としても重要視されています。
相続手続きで直面する問題

相続手続きを進める中で、多くの家族が直面するのが、「故人が利用していたネット証券口座にアクセスできない」という問題です。紙の通帳や取引明細といった「目に見える形」で残る情報が少ないため、相続手続きを開始した段階で、口座の存在自体を把握できません。
特に大きな問題となるのが、IDやパスワードなど、ログインに必要な情報が不明な場合です。この結果、ネット証券に連絡を入れるまでに時間がかかり、その間に口座は自動的に凍結されます。すべての取引が停止することになります。
相続人が手続きを急ごうとしても、本人確認書類や戸籍関係の必要書類が整うまでは手続きが進みません。遺産の移動も処分もできない状況に陥るのです。さらに、ネット証券は、店舗窓口を持たないところが多いため、家族が直接出向いて相談することができません。問い合わせは、電話や郵送、オンライン上で行うことになります。
しかし、証券会社ごとに手続きの流れや必要書類が異なるため、相続人が混乱してしまう場面も多く見られます。特に、複数のネット証券に口座を保有していた場合は、それぞれの会社に対して、手続きを行わなければならず、労力も時間もかかります。
こうしたトラブルを避けるためには、故人が生前から家族にある程度の情報を伝えておくことが重要です。また家族も「必要な情報がすぐには得られないかもしれない」という前提で冷静に行動しなければなりません。
相続で時間を取られることが多いのは、情報不足や書類不備による手続きの停滞です。事前に一般的な流れや必要書類を把握しておけば、証券会社への連絡や、書類の準備を効率的に進められます。
ネット証券口座にアクセスできない問題

相続が開始すると、証券会社は、本人の死亡を確認した時点で口座を凍結します。凍結されると、株式や投資信託の売買、出金などの一切の取引が一時停止されて、相続人であっても、自由に操作することはできません。
本来であれば、遺産の内容や評価額を確認してから、相続の分配方法を検討するはずです。しかし、ログインができない、遺産情報を取得できない状況では、具体的な相続手続きを進めることが難しくなってしまいます。
故人が、複数のネット証券に口座を開設していた場合は、特に注意しなければなりません。証券会社ごとに、相続に必要な書類や手続きの流れが異なるため、それぞれに対応する手間と時間がかかる点も、大きな負担になります。
このように、ネット証券の利用は非常に便利である一方で、相続が発生した際には「情報が見えにくい」「アクセスができない」という問題が立ちはだかります。
相続手続きにおける証券会社ごとの違い

ネット証券会社によって、相続手続きの具体的なフローや必要となる書類、さらには完了までの期間は大きく異なります。従来の金融機関のように、窓口での案内は受けられません。手続き方法は、会社ごとに独自に定められているため、相続人にとっては分かりにくく戸惑う場面も多いでしょう。
たとえば、ある証券会社では、戸籍謄本や印鑑証明書の提出が必須となっていたり、別の証券会社では、相続人全員の署名・実印を揃える必要があったりするのです。特に注意すべきなのは、パスワードが分からないケースです。通常であれば、本人としてログインすれば、保有遺産や取引履歴をオンライン上で確認できます。しかし、一部の証券会社では、相続手続きが開始されると、本人によるログインが不可能になります。
そのため、家族が状況を把握しようとしても、すぐに残高や銘柄をチェックできない場合が多いです。必要な証拠書類をそろえなければ、情報を開示してもらえない仕組みなのです。こうした点も「ネット証券ならではの相続の壁」といえるでしょう。
手続きに要する期間も証券会社によって異なります。早ければ、数週間で完了するケースも多いです。書類の不備や遺産分割協議書がまとまらないと、数か月以上にわたって、手続きが長引く可能性があります。そのため、相続手続きをできるだけスムーズに進めるには、最初の段階で各証券会社の「相続専門窓口」に連絡を入れて、詳細な流れや必要書類を確認することが、非常に大切です。
| 証券会社 | 相続開始時の連絡 | 必要書類(例) | 残高の把握方法 | 相続手続き内容 | 注意点 |
| SBI証券 | コールセンターへ相続発生の連絡(口座番号不要でも可) | 戸籍謄本・除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書など | 残高証明書の発行依頼が可能 | 名義変更、または全額売却して現金精算 | ログイン不要。相続手続き専用部署あり |
| 楽天証券 | 専用ダイヤルへ「相続発生の連絡」 | 同上(除籍謄本・相続人全員の印鑑証明など) | 必要に応じて「残高証明書」発行 | 名義移管、売却・現金化 | ネット経由ではできない。郵送のみでやり取り |
| 松井証券 | 相続受付専用の窓口へ連絡 | 戸籍関係一式、印鑑証明、協議書 | 残高証明書の取り寄せが可能 | 名義変更、または売却清算 | 比較的シンプルな手続きだが、書類不備に厳密 |
| マネックス証券 | 問い合わせフォーム、もしくはコールセンターに連絡 | 戸籍一式、相続人の身分証明書など | 残高証明を発行 | 名義変更、換金清算 | 外貨建て商品あり、評価計算に注意 |
デジタル遺産の相続でパスワードがある場合とない場合の違い

相続手続きを進めるうえで、パスワードの有無は「口座の中身を速やかに把握できるか」を決定づける重要なカギとなります。
もしパスワードが分かっていれば遺産状況を把握しやすくなりますが、相続人が本人になりすまして操作を行うのは不正アクセス禁止法に抵触する可能性があるため、確認用途にとどめ、正式な手続きは証券会社を通じて行う必要があります。具体的には、オンラインにログインして残高や保有銘柄の一覧、過去の取引履歴を閲覧できます。故人がどの証券会社に、どの位の遺産を保有していたのかを、迅速に調べられます。これにより、遺産分割の協議や相続税の申告なども、効率的に進められるでしょう。
一方で、相続開始後に、家族が故人の口座へ無断でログインして、売買や出金などの取引を行うことは「不正利用」にあたる可能性があります。あくまで遺産状況を確認する用途にとどめて、正式な相続手続きについては、証券会社の指示に従いましょう。
パスワードが分からない場合には、家族が自力でオンラインにアクセスして、遺産状況を確認することはできません。そのため、証券会社の「相続窓口」に連絡を取り、必要書類を提出する形で、遺産の照会や相続手続きを行います。
この方法はどうしても、時間と手間がかかります。パスワードの有無によって「迅速に情報収集ができるか」「時間と労力をかけて正式な確認手続きを取らざるを得ないか」という点に、大きな違いが出るのです。
デジタル遺産でパスワードが分かると便利なこと

パスワードが分かる場合、相続人はオンライン上で故人の口座にログインして、遺産状況や取引履歴を直接確認できます。従来の紙ベースの確認作業に比べて、遺産の全体像を、短期間で把握できる点は大きなメリットです。結果的に、遺産分割に関する判断や、相続税の申告に必要な資料の収集が、格段にスムーズになります。
- 遺産全体の把握が容易になり、遺産分割協議が円滑になる
相続において重要なのは、まず「故人がどの証券会社に、どの程度の遺産を保有していたのか」を正確に把握することです。
パスワードがあれば、ログインするだけで一目で遺産内容を確認できるため「どのような遺産があるのか分からない」という不安を解消できます。相続人同士の協議がスムーズになり、不必要なトラブルも避けられます。
- 相続税申告に必要な証明資料の準備が迅速化
相続税の計算や税務署への申告には、証券口座の取引報告書や残高証明書といった証拠資料が不可欠です。
パスワードが分かれば、オンライン上から迅速に取引履歴や残高報告書をダウンロードできます。資料準備にかかる期間を大きく短縮できるのです。これにより、延滞税や加算税といった余計なリスクを回避できます。
- 投資信託や株式の評価額を正確に確認できる
相続税の計算では、相続開始時点における株式や投資信託の評価が重要です。パスワードがあれば、保有銘柄の数量や時価評価額をすぐに把握できます。
専門家に依頼して、評価額を算出する際にも正確なデータを提供できるのです。これにより、遺産の過不足や申告漏れといったミスを防ぎ、より正確な税務処理が可能です。
| 項目 | 内容 | メリット |
| 遺産分割協議 | 正確な内容を、即時に共有できる | ・相続人同士の協議が円滑に進む ・不必要なトラブルを回避 |
| 相続税申告用資料の収集 | オンラインから、取引履歴や残高証明書をダウンロードできる | ・資料収集が迅速化 ・延滞税や加算税のリスク回避 |
| 評価額の確認 | 株式・投資信託などの数量や、時価評価を把握できる | ・正確な評価データで税務処理が可能 ・遺産の過不足や申告漏れを防止 |
パスワードが分からなくても進められる相続手続き

パスワードが分からない場合であっても、相続人は諦める必要はありません。証券会社に対して正式に「相続手続きの申請」を行えば、故人の口座にある遺産の移管や解約といった手続きが進められます。これは、ネット証券であっても、原則的には従来の金融機関の相続と同様に、法的な手続きを踏むことで、遺産を引き継ぐ仕組みになっているためです。
一方で、パスワードが分かっている場合に比べると、手続きは格段に複雑になりやすいです。時間がかかってしまう点には注意してください。オンラインにログインして、遺産状況を即時に確認することができないため、証券会社の相続窓口を通じて、一つずつ手続きを進める必要があります。
そのため、相続人が「口座の中にどのような銘柄や遺産があるのか」を知るのは、書類審査の後になるケースが多いです。こうした手続きは、確かに手間も時間もかかりますが、裏を返せば「法的に正しい流れで遺産を継承できる」のです。面倒に感じたとしても、正規の書類を揃えて、証券会社に提出するプロセスをしっかり踏むことで、相続人にとっても、安全で確実な方法になります。
| 項目 | 内容 | ポイント |
| 相続手続きの可否 | 相続人は諦める必要はなく、証券会社に正式に申請すれば、遺産移管や口座解約が可能になる | ネット証券でも従来の金融機関と同様、法的手続きに基づいて、遺産相続できる |
| 手続きの進め方 | 証券会社の相続窓口を通じて、必要な書類を提出しながら、一つずつ進める | 主に書類審査ベースで進行する |
| 遺産内容の確認 | ログインできないため、証券会社での書類審査後に、初めて把握できるケースが多い | 遺産全体の確認に時間を要する |
| メリット | 正規の書類を揃えて進めるため、法的に正しい流れで安全・確実に遺産を継承できる | トラブル防止や法的安定性につながる |
相続における安全なパスワード管理の方法

故人のネット証券口座を相続する際に、重要なポイントのひとつが「パスワードの管理方法」です。これは、相続手続きを効率よく進めるための要素にとどまりません。故人の大切な遺産を守るうえで、不可欠なセキュリティ対策でもあるのです。
パスワード管理が十分でない場合、相続人が故人の遺産を確認できずに、手続きが滞る可能性があります。確認や申請が遅れることで、経済的なリスクにつながります。さらに、パスワードが、不用意に第三者の目に触れる形で保管されていた場合には、情報漏洩や不正利用といった深刻なトラブルが発生するかもしれません。
ネット証券をはじめとしたデジタル遺産のパスワード管理は、相続の効率性と安全性の両方に大きな影響を与えます。故人が生前から、どのように整理・保管しておくかが、非常に重要です。
たとえば、エンディングノートにログイン方法をまとめておく、パスワード管理アプリやデジタル遺産管理サービスを利用する、信頼できる弁護士や信託機関に情報を託すといった方法が考えられるでしょう。これにより、情報が行方不明になるリスクを減らして、無用な漏洩や不正アクセスを防ぎます。
遺言書やエンディングノートでの注意

相続や終活を意識するなかで、遺言書やエンディングノートに、ネット証券口座のパスワードを書き残したいと考える方は多いです。しかし、この方法は、一見すると分かりやすいようで、非常に危険な行為になります。それは、遺言書やエンディングノートは、保管場所によっては、紛失や盗難のリスクが高く、他人の目に触れる可能性もあるためです。
もし、パスワードが第三者に流出した場合、故人の大切な遺産が不正利用される恐れがあります。結果的に、家族に大きな被害が及ぶことになるのです。そのため、パスワードを直接書き残すのは、避けなければなりません。家族が安全かつ正当な手続きを通じて、アクセスできる形で管理しましょう。
安全な管理方法として近年注目されているのが、以下のような仕組みです。
- パスワード管理アプリの活用
信頼性の高いパスワード管理アプリに、ログイン情報を保存しておく方法が、一般的になっています。これにより、複数のネット証券や金融口座のパスワードを、一括で安全に保管できます。家族には、そのアプリへアクセスするための「マスターパスワード」や、復旧手順だけをエンディングノートなどに記載しておけば十分です。直接、パスワードを書く必要がないため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
- 暗号化USBやセキュアクラウドの利用
もう一つの方法として、暗号化機能を備えたUSBメモリや、セキュリティ性の高いクラウドサービスに、パスワードを保管するという手段があります。暗号化された記録媒体やクラウドは、不正アクセスを受けにくく、万が一データが盗まれても、第三者が内容を解読するのは非常に困難です。この場合も、家族には保存先や復旧方法、必要な認証情報などを伝えておくことで、本人が亡くなった後でも、安全にアクセスできます。
| 方法 | 概要 | メリット | 注意点 | エンディングノートに書くべき内容 |
| パスワード管理アプリ | 各口座のログイン情報を暗号化してアプリに一括保存。家族には「マスターパスワード」や復旧方法を伝える。 | ・複数口座を安全に一元管理 ・自動で暗号化 ・パスワード変更も容易 | ・マスターパスを忘れると、全口座にアクセスが不能 ・アプリの信頼性を確認する必要あり | ・口座を保有している証券会社名 ・「パスワードは管理アプリに保存済み」 ・マスターパスワードの保管場所 |
| 暗号化USB、セキュアクラウド | ログイン情報を暗号化USBやクラウドに保存して、認証情報や保存場所を家族に伝える。 | ・物理デバイスとして残せる(USB) ・クラウドなら場所に依存せず、利用可能 | ・USBは紛失リスクあり ・クラウドは二段階認証の設定が必須 | ・どこに保存しているのか(USBの保管場所、クラウドのサービス名) ・復旧手順や認証方法 |
| 金融機関の相続手続きに基づく | 実際には、証券会社に死亡届が提出されれば、家族が正式に相続手続きを行える。パスワード不要。 | ・セキュリティリスクゼロ ・正規の手続きで安全 | ・手続きに時間がかかる ・口座の存在を家族が知らないと、発見が遅れる | ・どの証券会社、銀行に口座があるか一覧化 ・「相続手続きで利用可能」と明記 |
ネット証券の相続手続きチェックリスト

ネット証券口座は、銀行や不動産に比べると、相続手続きの流れがわかりにくく、家族が戸惑うことも少なくありません。特に、パスワードや取引履歴、複数の証券会社に分散された口座など、デジタル遺産ならではの課題があります。
相続手続きをトラブルなく進めるためには、必要な書類や確認すべきポイントを整理することが重要です。ここでは、ネット証券での必要な手続きを、チェックリスト形式でまとめました。
1. 初期対応
□ 証券会社の相続窓口へ連絡・問い合わせ
2. 必要書類の準備
□ 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのもの)
□ 遺産分割協議書(相続人全員の合意が必要)
□ 印鑑証明書(相続人分)
□ その他、証券会社指定の書類(例:相続届出書のフォーマットなど)
3. 手続き
□ 証券会社所定の「相続届出書」を記入・提出
□ 口座の凍結解除を依頼
□ 遺産の移管(名義変更)または解約・換金の手続きを選択して実施
4. 相続税関連
□ 相続税申告用に「取引履歴」や「残高証明書」を取得(必要に応じて)
5. オンライン関連の確認
□ ID・パスワードが分かる:口座状況をオンラインで確認可能
□ ID・パスワードを分からない:証券会社経由で情報取得が可能
デジタル遺産の相続でよくあるトラブルと注意点

相続手続きにおいて、ネット証券口座に関するトラブルは少なくありません。代表的なものとして、以下のようなケースが挙げられます。
- パスワード未整理による相続の遅延
ネット証券では、口座にアクセスするためのIDやパスワードが必須です。生前にこれらが整理されていなかった場合、先述の通り、相続人は遺産内容を確認することができません。結果として、遺産分割協議がスムーズに進まず、相続税の申告期限(原則10か月以内)に間に合わせるため、慌ただしくなるでしょう。
精神的な負担も大きくなります。パスワードが整理されていない状態は、円滑な相続の妨げとなり、経済的にも大きなリスクにつながります。
- ネット証券のオンライン取引中の死亡
故人が亡くなったタイミングによっては、株式や投資信託の売買注文が、すでに出されている段階かもしれません。このような場合、その注文が「実行済みなのか」「未約定なのか」によって、遺産評価額が変わります。
そのため、相続人と証券会社の間で、認識を合わせる必要があるのです。相場が大きく動いている局面であれば、デジタル遺産価値に数十万円、場合によっては、数百万円単位の差が生じる可能性があります。
| 項目 | パスワード整理済み | パスワード未整理 |
| 遺産状況の把握 | ログインして即時に残高・評価額を確認できる | 書類提出・照会が必要で、確認まで数週間〜数か月に及ぶ |
| 遺産分割協議 | 遺産内容が明確なため、スムーズな話し合いが行える | 遺産総額が不明確なため、協議が停滞・混乱しやすい |
| 相続税申告用資料 | オンラインで取引履歴・残高証明を迅速に取得できる | 証券会社から郵送で取り寄せ、資料準備に時間を要する |
| 相続税期限への対応 | 必要資料が早く揃うため、余裕を持って申告が行える | 書類整理に時間を取られて、10か月の期限に追われやすい |
| 精神的負担 | 「すぐに確認できる安心感」がある | 不透明さから不安が強く、家族間トラブルにつながりやすい |
| 経済的リスク | 正確な評価額で税務処理が可能、申告漏れや延滞リスクを防止する | 評価額の確定に時間がかかり、遅延・申告漏れのリスクが増大する |
| 準備方法 | パスワード管理アプリ、暗号化USB、専門家への委託などが有効になる | 相続発生後に、書類手続きで対応する必要がある |
パスワードで困ったら専門業者へ相談しよう

ネット証券の相続で、最初のハードルとなるのが「パスワード問題」です。無理に家族で解決しようとすると、誤った操作によるアカウントのロックや、重要なデータの消失といった新たなトラブルを招く恐れがあります。相続手続きは、限られた期限の中で進めなければならないため、時間を浪費してしまうことも大きなリスクです。
そこで頼りになるのが、デジタル遺産を専門とする業者です。専門の知識と技術を持つ業者に相談すれば、スマホをはじめとしたデバイスから、安全に情報を抽出して、必要な情報を特定できる可能性が高まります。
また、相続手続きに必要な証拠資料を整理してくれる場合もあり、結果として家族の負担を大幅に軽減できるでしょう。相続におけるパスワードの問題は、家族だけで抱え込むと、解決が難しいものです。困ったときは早めに専門業者に相談するのもおすすめです。スムーズに相続手続きを進めて、大切な遺産を守ることにつながります。
| 項目 | 内容 |
| 主な課題 | ネット証券口座の「パスワード問題」が最初のハードルとなる |
| 家族で無理に対応した場合のリスク | ・誤操作によるアカウントロック ・重要データの消失 ・限られた相続期限の中での時間浪費 |
| 解決の方向性 | デジタル遺産を扱う専門業者に相談する |
| 専門業者ができること | ・スマホやPCから安全に情報を抽出 ・必要なデータを特定 ・相続に必要な証拠資料を整理 |
| 家族にとってのメリット | ・余分なトラブルを防止 ・実務負担の大幅軽減 ・スムーズな相続手続きにつながり、大切な遺産を守れる |
まとめ

ネット証券口座を相続する際、最大の分かれ目となるのが「パスワード」です。生前に故人がパスワードを整理して、安全に管理していた場合、相続人はすぐに口座へアクセスして、残高や評価額を確認できるでしょう。結果的に、相続手続きが効率的に進められます。
相続税の申告も、余裕を持って対応できます。一方で、故人のネット証券口座を調べる前に、スマホロック解除のパスワードが分からないケースも多いです。そのような場合には、早めに専門業者へ相談しましょう。デジタル遺産やパスワードの解析に対応できる業者であれば、安全な方法で情報を抽出してくれます。必要な証券口座の特定や手続きのサポートを行ってくれます。
ネット証券口座の相続では「パスワードがなくても手続きは可能だが、時間と労力がかかる」という点と、「パスワードが整理されていれば、手続きが大幅に楽になる」という両面を理解してください。
そして大切なのは、故人が生前から計画的にパスワードを管理して、家族が困らない環境を整えておくことです。その準備次第で、相続のスピードと安全性は大きく変わります。将来の家族の負担を軽減するためにも、今できる対策を考えておきましょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
デジタル資産バトンの紹介
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼