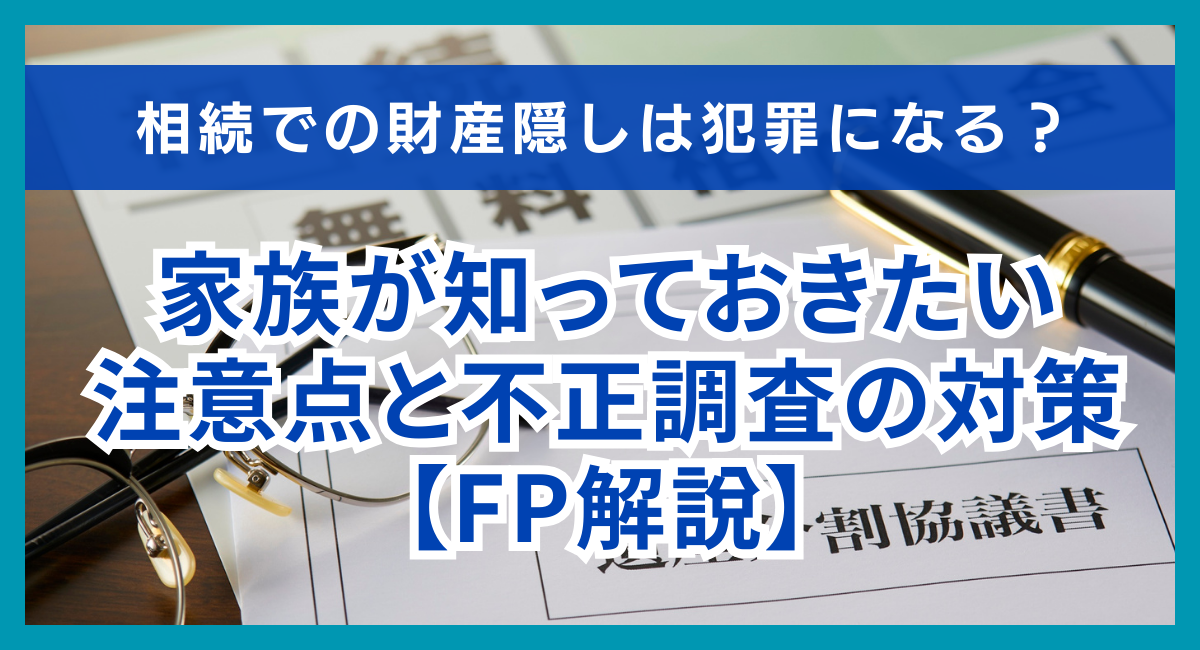相続の場面でトラブルになるのが「財産隠し」です。残念ながら、現実には一部の相続人が故意に財産を申告せず、自身だけの利益を得ようとするケースが少なくありません。しかし、こうした行為は民法上の『相続欠格事由』や刑法上の『詐欺罪』などに該当する可能性があり、思わぬトラブルや処罰に発展するでしょう。
FPの立場から見ても、財産隠しは「家族の信頼を壊すリスク」と「法的リスク」の両方を抱える危険な行為です。円満な相続を実現するためには、資産の透明性を保ち、相続人全員が納得できる形で、手続きを進める必要があります。今回の記事では、相続財産隠しが犯罪になる場合と、不正調査の予防策について解説していきます。
相続に潜む身近な財産隠しのリスク

相続が発生すると、資産の内容や分け方をめぐって、家族の間で思わぬトラブルに発展することが少なくありません。特に、深刻な問題として挙げられるのが「財産隠し」です。相続財産を意図的に隠す行為は、親族間に深い不信感を生み出す引き金になります。
たとえば、親が亡くなった直後に、特定の相続人が預金を勝手に引き出したり、不動産や株式、生命保険の存在を、他の家族に知らせなかったりするケースがあります。こうした行為は「少しぐらいなら問題ないだろう」「長年世話をしてきた自身が使っても当然だ」という、安易な気持ちから始まることも多いです。
しかし一度でも発覚すれば、残された家族の間に強い疑念が生じます。関係が修復不可能なほど、悪化してしまう可能性があるのです。
実際、相続開始前までは、親族同士が円満に見えていた家庭でも、財産の存在や分け方をめぐって隠し事が明らかになった瞬間から、互いに責め合いが始まります。最終的に絶縁状態に陥ってしまうことは、決して珍しくありません。資産は単なる「お金やモノ」にとどまらず、親の思い出や家族の歴史と強く結びついています。隠された財産の発覚は、精神的な裏切りと受け止められやすいのです。
さらに重要なのは、財産隠しが単なる「家族の揉め事」では済まされない点です。相続は法律によって、厳格にルールが定められており、民法上の問題に直結します。悪質な場合は、横領罪や詐欺罪といった刑事事件に発展して、裁判にまで進むかもしれません。このようなケースでは、もはや家族関係が破壊されるだけでなく、時間的・経済的にも大きな負担を背負うことになります。
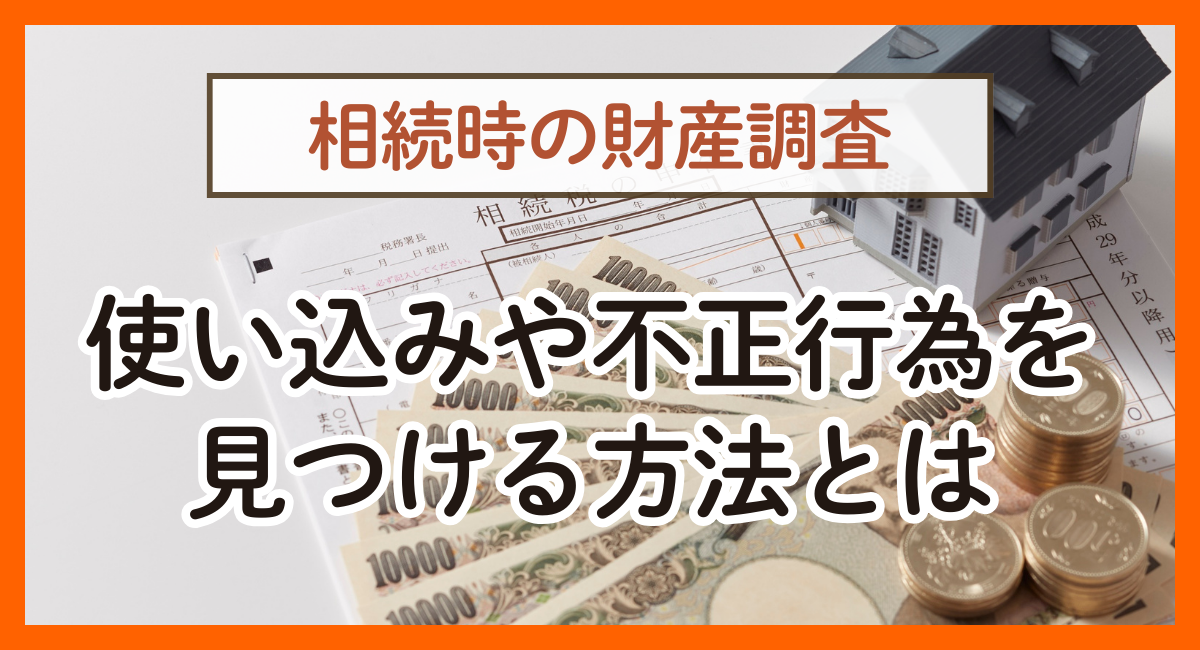
そもそも相続における財産隠しとは?
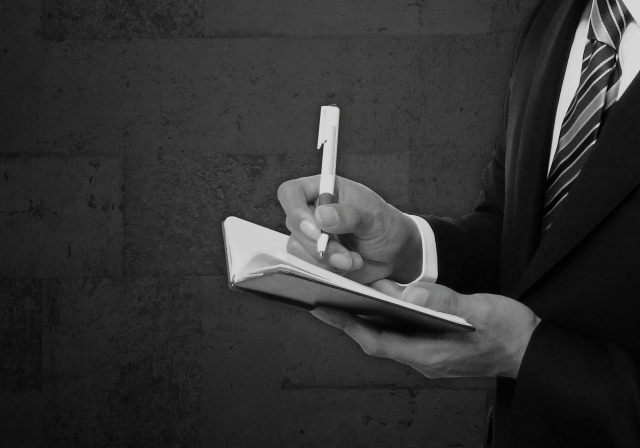
相続における「財産隠し」とは、他の相続人に知らせることなく、自身だけの利益を得ようとする不正な行為を指します。たとえば、預貯金や株式、不動産などの財産を申告せずに隠したり、相続手続きが始まる前に、一部を処分してしまうことなどが挙げられます。
このような行為は、相続人間の信頼関係を大きく損ない、深刻なトラブルや訴訟に発展する可能性が高いです。そのため、相続においては、すべての財産を正確に把握して、公正かつ誠実な対応を行うことが重要とされています。
なぜ相続で財産隠しが発生するのか?

相続における財産隠しは、単なるずるい行為ではなく、法律・心理・家族関係など複合的な要因によって引き起こされます。まず、相続税の負担を減らしたい、自身の取り分を増やしたいといった経済的な動機が挙げられるでしょう。
多額の財産がある場合、相続税の負担を避けるために、財産を意図的に隠すケースがあるのです。家族間の対立や、信頼関係の欠如も背景にはあります。遺言書がない場合や手続きの透明性が低い場合も、財産隠しが起きやすい要因です。
また、誰にどのくらい相続されるのか、不明確だと後から財産を隠す動機が生まれやすくなります。口座や不動産登記などの情報が、家族に知られていないと、簡単に隠すことが可能です。心理的・感情的な要因も見逃せません。生前の親への反感や兄弟間の嫉妬心、あるいは秘密を握ることによる優越感などが、財産隠しの引き金になることがあります。
財産の形態によっても、隠しやすさは異なるでしょう。現金や預金は簡単に隠せますが、不動産や株式、仮想通貨のように、管理や名義変更が複雑なものは、知られにくく隠されやすい傾向があります。このように、財産隠しは単なる利己的な行為ではなく、税務上の負担や家族関係、遺言書の有無など、さまざまな要素が絡み合って発生するのです。
| 財産隠しの要因 | 詳細 | 内容・例 |
| 経済的動機 | 相続税の負担回避、自分の取り分を増やす | 相続税を減らすため・自身の利益のために、財産隠しが生じる |
| 家族関係 | 対立・信頼関係の欠如 | 家族内の争いや信頼性のない関係性が、財産隠しの背景になる |
| 法律・手続状況 | 遺言書の有無、手続きの不透明さ | 遺言書がない・手続きが非公開だと、財産隠しが発生しやすい |
| 情報の透明性 | 相続財産の把握の難しさ | 金融口座や不動産などが家族に知られていない場合、隠しやすい |
| 心理的・感情的要因 | 反感・嫉妬・優越感など | 親や兄弟への感情的な対立、秘密を持つ優越感が動機になる |
| 財産の形態 | 現金や預金は隠しやすい、不動産や株式は複雑 | 管理が簡単な財産は隠しやすく、把握が難しいデジタル資産や名義変更は、隠蔽の温床 |
相続の「財産隠し」の典型的な事例

相続では、本人の財産を正しく申告して、相続人全員で公平に分けることが大切です。しかし、実際には、不正に財産を隠そうとする行為が起こることがあります。また、葬儀の混乱に乗じて、金庫やタンスに入っている現金や貴金属を持ち出すこともあるのです。このような行為は、相続人の権利を侵害する重大な問題で、違法行為につながることもあります。
| 財産隠しの手口 | 具体的な内容 |
| 預金の引き出し | 本人が亡くなる前後に、銀行口座から現金を勝手に引き出す |
| 不動産の隠匿 | 相続手続きを行わず、名義変更や登記をせずに所有を隠す |
| デジタル遺産・デジタル資産の隠蔽 | ネット銀行口座、証券口座、仮想通貨ウォレットなどの存在を、他の相続人に知らせない |
| 現金・貴金属の持ち出し | 葬儀の混乱に乗じて、金庫や自宅に保管されている現金・貴金属を持ち出す |
相続財産を隠した場合の民事上のリスク

相続財産を意図的に隠す行為は、他の相続人との信頼関係を壊すだけでなく、発覚した際には、法律上の大きな不利益を招きます。軽い気持ちで行ったとしても、深刻な結果につながりかねません。財産隠しが発覚すると、相続における取り分に大きな影響が及びます。
- 特別受益として扱われる
隠していた財産は「すでにその相続人が受け取ったもの」とみなされ、相続分から差し引かれます。結果的に、取り分が大きく減ってしまうのです。 - 資産分割協議が無効になることもある
隠し財産が発覚した場合、それを前提に行った資産分割協議は無効と判断される可能性があります。再度話し合いや調停をやり直す必要があり、時間も費用もかかります。 - 相続欠格にあたる可能性がある
特に悪質な財産隠しは、民法第891条に規定される「相続欠格」にあたり、相続人としての資格を失うのです。つまり、隠した本人は一切相続できなくなります。
| 影響・リスク | 内容 |
| 特別受益として扱われる | 隠していた財産は「すでに相続人が受け取ったもの」とみなされる。相続分から差し引かれる。その結果、取り分が大きく減る可能性がある。 |
| 資産分割協議が無効になる可能性 | 隠し財産が発覚した場合、それを前提に行った資産分割協議は、無効とされる可能性がある。再度の話し合いや調停が必要になり、時間や費用がかかる。 |
| 相続欠格にあたる可能性 | 悪質な財産隠しは、民法第891条に規定される「相続欠格」に該当する。その場合、当人は相続権を失い、一切相続できなくなる。 |
相続財産を隠すと刑事事件に発展することもある

財産隠しは、単なる民事上のトラブルに収まりません。刑事罰の対象となる可能性があります。たとえば、他の相続人をだまして、不当に財産を得た場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。10年以下の懲役が科される可能性があるのです。
また、財産を管理する立場にある相続人が、勝手に財産を処分したり流用した場合は、横領罪(刑法252条)にあたり、5年以下の懲役が定められています。故人の現金や宝飾品などを持ち出す行為は、窃盗罪(刑法235条)に該当して、10年以下の懲役に処されることがあります。
実際に、これらの罪で立件されたケースも存在しており「家族間のことだから罪にはならない」という考えは通用しないのです。相続に関して不正を行うと、重大な刑事責任を問われることを理解しなければなりません。
| 犯罪名 | 適用される状況 | 法律条文 | 刑罰 |
| 詐欺罪 | 他の相続人をだまして、不当に財産を得た場合 | 刑法246条 | 10年以下の懲役 |
| 横領罪 | 資産を管理している立場の相続人が、財産を勝手に処分・流用した場合 | 刑法252条 | 5年以下の懲役 |
| 窃盗罪 | 本人の死亡後に、現金や貴金属・宝飾品などを無断で持ち出した場合 | 刑法235条 | 10年以下の懲役 |
相続で起こりがちな財産隠しのパターン

相続の場面では、身近な家族であっても、深刻な争いになるケースは多いです。代表的な事例としては「預貯金の引き出し・使い込み」があります。本人が亡くなった直後に、特定の相続人が預金を勝手に引き出してしまうケースです。
「介護費用に使った」「本人から頼まれていた」と説明されることもあります。しかし、客観的な証拠がなければ、財産隠しと判断される可能性があるのです。また、資産目録を作成する際に特定の財産を申告せず、他の相続人に知らせないケースも多く見られます。
特にネット証券口座や仮想通貨など、存在が分かりにくい資産は見落としやすいです。意図的に隠されることもあります。不動産に関しても、協議を経ずに、一部の相続人が単独で名義変更を行ってしまう事例も挙げられます。
登記簿で後に発覚しやすいものの、資産分割協議を無視した行為であれば違法です。さらに悪質な場合は、資産分割協議書を偽造・改ざんして、他の相続人に無断で署名を作り上げるといった行為もあるのです。これらが発覚すれば、刑事事件に発展しかねません。
生命保険や死亡退職金なども、誤解を招きやすいポイントです。法律上は、受取人が指定されている場合、その財産は「受取人固有のもの」とされることが多いです。しかし、情報を隠すことで、かえって不信感を生むことがあります。
また、自宅にある現金や宝飾品、貴金属など、相続開始の直後に、一部の家族が持ち出してしまうケースも後を絶ちません。こうした財産隠しは、単に家族間の問題にとどまらず、横領罪や詐欺罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。
| 項目 | 財産隠しの典型的な行為 | トラブル・リスク | 法的評価・影響 | 対応策 |
| 預貯金 | ・死亡直後に口座から無断引き出し ・介護費用等と主張するが領収証なし | ・他の相続人から「横領」と疑われる | ・資産分割の対象財産に不当に使われた場合は「持ち戻し」や損害賠償対象 ・横領罪に発展の可能性 | ・死亡後は速やかに口座凍結・残高証明取得 ・出入金履歴を全員で確認 |
| 資産目録・隠匿 | ・ネット証券口座、仮想通貨、タンス預金、貴金属などを、申告せず不記載 | ・発覚した時点で不信感が大きくなる | ・故意の隠匿は「相続欠格事由」にもなり得るケースあり | ・相続人全員で調査 ・金融機関や証券会社への網羅的照会 |
| 不動産 | ・資産分割協議をせず、単独で名義変更 | ・登記簿で後に発覚して、大きく紛争化 | ・資産分割協議が無ければ、無効登記 ・不当利得返還の対象 | ・不動産登記事項証明書を全員で取得 ・名義変更は弁護士・司法書士を経て公正に |
| 文書関係 | ・資産分割協議書の改ざん・署名偽造 | ・発覚すれば、家族関係は完全に破綻 | ・有印私文書偽造・詐欺罪など、刑事事件化 | ・必ず署名押印は対面で確認 ・専門家立会いで作成 |
| 保険金・死亡退職金 | ・存在を知らせない、受取額を伏せる | ・「隠しているのでは」と不信感をあおる | ・原則「受取人固有の財産」だが、紛争の火種に | ・保険会社に確認手続き ・金額・受取人を透明に開示 |
| 現金・貴金属など | ・自宅から勝手に持ち出す | ・後になって「消えた」と騒動化 | ・窃盗や横領罪に該当する場合あり | ・資産整理は相続人全員で実施 ・できれば専門業者の立会い |
財産隠しを防ぐために家族ができること

相続におけるトラブルの多くは、故人の財産状況が、正確に把握できないことから発生します。財産隠しや申告漏れがあると争いが生じるだけでなく、相続人同士の信頼関係にも深刻な影響を与えるでしょう。
FPの視点から見ると、こうしたリスクは、日頃の準備と整理によって、大きく軽減できる可能性があります。たとえば、故人が亡くなる前に、預貯金や不動産、証券などの資産を種類ごとに整理して、適切に管理することが挙げられます。そして、これらの情報を信頼できる方法で、家族に共有することが大切です。
このような事前の取り組みは、将来のトラブルを未然に防ぐ効果があります。ここからは、相続時の「財産隠し」を防ぐために、家族が取り組める具体的な方法とポイントを、分かりやすく紹介します。
財産目録の作成

相続において最初のステップとして非常に有効なのが、財産の全体像を正確に把握することです。どれだけ多くの財産があっても、一覧として整理されていなければ、相続人同士で「本当にすべてが明らかになっているのか」という疑念が生まれやすくなります。
具体的には、銀行の預金口座や自宅・土地などの不動産、株式や投資信託です。また、生命保険や損害保険などの資産も、対象に含めて整理しておくと安心です。
一方で、仮想通貨やネット証券口座など、デジタル環境に紐づいた「デジタル資産」は、見落とされやすいポイントとなっています。こうした資産は、パスワードや専用アプリが必要なため、相続人が気づかないまま放置されてしまうのです。
そのため、紙の財産だけでなく、デジタル資産も含めた「財産目録」を定期的に作成・更新しておくことが重要です。財産目録を整備しておけば、家族が後から「知らなかった」「隠されていた」と感じないでしょう。財産目録は「家族の安心」と「将来設計」の両方を守るための基盤になります。
エンディングノートの活用
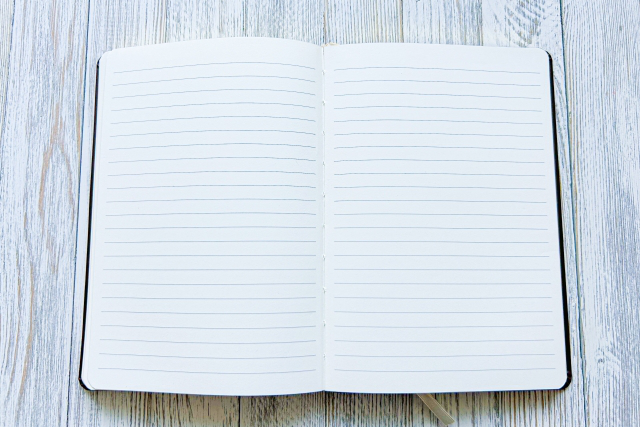
財産に関する情報を本人が自らまとめ、きちんと残しておくことは、相続の混乱を防ぐうえで、非常に効果的な方法です。その手段の一つとして広く利用されているのが「エンディングノート」です。エンディングノートには、財産の所在や取引先の連絡先を記録できるだけでなく、意思や希望を言葉として残せます。
近年では、デジタル資産を持つ人も増えています。エンディングノートに、こうした資産の存在や利用しているサービス名を残すことは、資産の見落としを防ぐうえでも、重要な意味を持つのです。もちろん、エンディングノートには、遺言書ほどの法的拘束力はありません。しかし、相続人にとっては、本人の意向や相続の不正を直接知る手がかりにもなります。
家族間での情報共有

財産を「見える化」しただけでは、相続に備えるうえで十分とは言えません。大切なのは、その情報を家族全員で共有して、認識を一致させることです。たとえば、定期的に家族会議や話し合いの場を設けて「どの銀行にどれくらいの預金があるのか」といった具体的な情報を確認しておきましょう。
情報の透明化は、相続人同士の誤解や疑念を解消できます。こうした取り組みは「財産を隠さない」「不公平を生まない」という家族の姿勢を示すことにもなり、円満な相続の実現に直結するでしょう。
弁護士や司法書士、FPなどへの相談
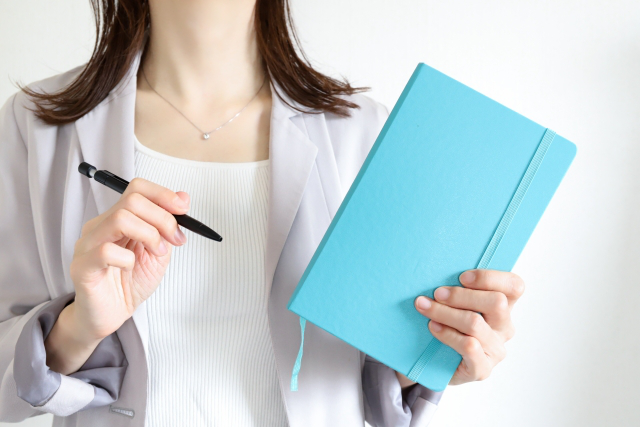
相続は法律・税制・制度が複雑に絡み合う分野であり、一般の方にとっては分かりづらい部分が多いです。そのため、弁護士やFPなどの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、財産の洗い出しや分割方法に関する助言だけでなく、予想されるトラブルや落とし穴を事前に指摘してくれます。より安心して、相続の準備を進めることができるでしょう。第三者が関与することで「公平性」が担保されて、家族間の不信を防ぐ効果も期待できます。
| 取り組み | ポイント | 効果・メリット |
| 財産目録の作成 | 預金口座・不動産・株式・投信・保険・仮想通貨・ネット証券などを一覧化し、定期的に更新 | 財産の全体像を把握でき、不信感や「隠されていた」という疑念を減らし、透明性を確保できる |
| エンディングノートの活用 | 財産の所在や連絡先、本人の意思・希望を記録(例:通帳はどの銀行、証券口座はどの会社など) | 遺言ほどの法的効力はないが、相続時に家族が迷わず手続きを進められ、“本人の意向”を形に残す役割 |
| 家族間での情報共有 | 定期的に話し合いを行い、財産の所在や内容を家族で共有 | 誤解や疑念を解消し、信頼関係の維持につながる。早期の情報交換が後々の安心に結びつく |
| 専門家への相談 | 弁護士、司法書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどに相談 | 財産整理や分割方法の助言、トラブル予防、公平性の担保により安心して準備可能 |
相続で財産隠しが見つかったときの対処法

財産隠しが万が一発覚した場合、驚きや裏切られた思いから、強い感情に支配される可能性があります。しかし、感情的になったり相手を責め立てたり、独断で行動してしまうと、その後の手続きが複雑化するかもしれません。かえって問題を深刻化させてしまう恐れがあります。大切なのは冷静に、段階を踏んで対処していく姿勢です。そのためには、以下のような対応を心がけることが重要です。
- 証拠を確認する
まず行うべきは、事実の確認になります。「憶測」だけで相手を責め立ててしまうと、信頼関係がさらに悪化してしまいます。
具体的には、預金通帳の入出金記録、金融機関の取引履歴、不動産登記事項証明書、保険の契約内容、さらには振込履歴や電子メールの記録などを収集しましょう。客観的な証拠を揃えることが求められます。
特に、デジタル資産の場合には、パソコンやスマホの履歴、オンライン取引の証明書なども、重要な手がかりです。証拠を持つことで初めて「本当に財産隠しが行われたのか」「単なる誤解ではないのか」を明確に判断できるでしょう。 - 話し合いの場を持つ
証拠によって、疑念が確かなものになった場合でも、すぐに法的手段に訴えるのではなく、まずは、相続人同士で冷静に話し合う姿勢が必要です。この段階で円満な解決になれば、時間的にも経済的にも大きな負担が避けられます。
ここで気を付けたいのは、感情的にならず、事実に基づいた協議を行うことです。「なぜその行為をしたのか」「どのような方法で公平な分割ができるのか」といった建設的な話し合いを目指さなければなりません。 - 家庭裁判所の調停を利用する
話し合いで解決が難しい場合、家庭裁判所の資産分割調停を申立てられます。家庭裁判所で行われる調停は、中立な立場の調停委員が介在します。当事者同士が冷静に主張が行える場所です。
裁判と異なり、柔軟な話し合いが可能であるため、多くの相続トラブルは、調停を通じて合意が進められます。これにより、法的に有効な形で解決できるのです。 - 弁護士に相談する
相手の行為が悪質であったり、どうしても話し合いや調停で収拾がつかない場合には、弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は財産隠しをめぐる法的な評価を整理して、必要に応じて、民事訴訟や仮処分の手続きを進めます。
横領や詐欺にあたる可能性がある場合は、刑事事件として、警察に告訴することも視野に入れなければなりません。こうした場面では、専門的な知識が必要です。
| 段階 | 具体的な行動 | ポイント・注意点 | 効果・目的 |
| 証拠を確認する | 預金通帳、金融機関取引履歴、不動産登記事項証明書、保険契約、振込履歴、メール記録、デジタル資産(PC・スマホ履歴、オンライン証明書)を収集 | 憶測で非難せず、客観的証拠を集めること | 財産隠しか誤解かを、明確に判断できる |
| 話し合いの場を持つ | 相続人同士で冷静に協議 | 感情的にならず、事実に基づいて「理由」や「公平な分割方法」を議論 | 円満解決できれば時間・費用の負担を軽減 |
| 家庭裁判所の調停 | 家庭裁判所に資産の分割調停を申立て、中立な調停委員を介して協議 | 裁判より柔軟な対応が可能 | 法的に有効な形で、多くのトラブルの解決が可能 |
| 弁護士に相談する | 弁護士が法的評価や対応を整理して、必要なら民事訴訟・仮処分へ | 横領・詐欺に該当する場合は、刑事事件として告訴の可能性 | 法的な視点から対応、専門知識で強制力ある解決が可能 |
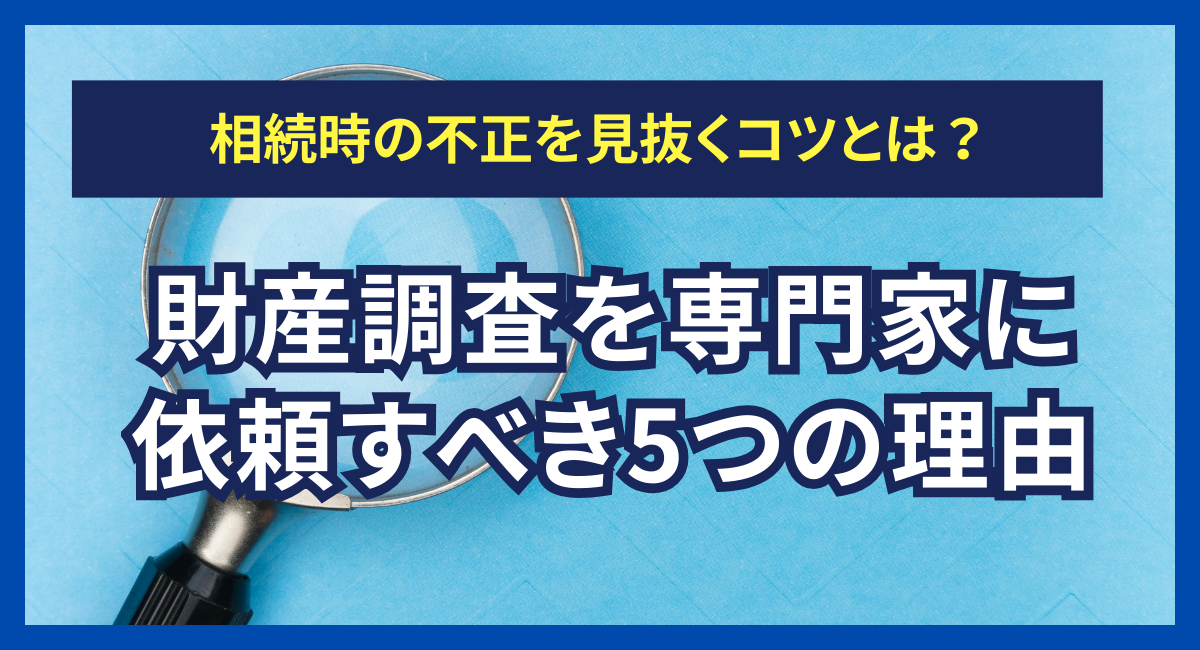
財産隠しを疑う場合には「相続の不正調査」がおすすめ

相続の手続きで「財産が隠されている気がする」と感じることは珍しくありません。故人の通帳の動きが不自然だったり、投資をしていたはずなのに、証券口座の情報が見つからなかったりと、家族で疑問が生じるケースがあります。こうした疑いを放っておくと、相続人同士の信頼関係が壊れてしまい、深刻なトラブルにつながる恐れがあるのです。
そこで役立つのが「相続の不正調査」です。銀行や証券口座、不動産などの調査はもちろん、最近ではデジタルフォレンジック専門業者に依頼して、故人のスマホやパソコンを解析するケースも増えています。
専門の技術を活用することで、消されてしまった取引履歴やアプリの利用状況、仮想通貨や電子マネーの痕跡まで、細かく確認できる可能性があります。現代の相続において、デジタル資産が関わることは当たり前になりました。相続の不正調査に関して、デジタルフォレンジック専門業者に依頼することは、家族を守るための有効な手段になるでしょう。
デジタルフォレンジック技術は「相続の不正調査」に役立つ

相続の不正調査では、単なる聞き取りや資料確認だけではありません。専門的な技術を駆使して、財産の全体像を明らかにします。その代表的な技術が「デジタルフォレンジック」です。これは、故人が利用していたスマホやパソコンを、専門の機器で解析するのです。
削除された取引履歴やログイン記録、メールやクラウドに残された金融情報を復元する技術です。たとえば、証券アプリの利用履歴や仮想通貨ウォレットの存在を突き止めることも可能になります。
こうした技術的な調査を、相続での財産隠しに活用することで、客観的に故人の財産を確認できます。公正な資産分割を進める大きなサポートになるのです。
| 項目 | 内容 |
| デジタル資産 | パソコン・スマホなどに残るデジタル資産(ネット銀行・証券、暗号資産、電子マネー、写真動画など) |
| 調査対象 | 機器データ、オンライン口座、SNSアカウント、アプリ履歴、メール履歴 |
| フォレンジック技術 | パスワード解除・消去データ復元、改ざん痕跡調査、不正出金などの記録抽出 |
| 財産隠し対策 | 相続人間のトラブル時、専門業者による証拠保全と報告書作成で法的証拠化 |
| 注意事項 | 無断の機器アクセスは、不正アクセス禁止法に抵触。専門家・弁護士と連携が大切 |
| 依頼先 | デジタルフォレンジック専門業者 |
まとめ

相続における財産隠しは、家族の間で修復困難な溝が生まれるかもしれません。実際、財産隠しがきっかけで「もう二度と顔を合わせたくない」というほど、関係が壊れてしまうケースも多いです。本来なら、大切な人を見送る相続の場面が、争いと不信の場になる恐れがあります。これは、財産の大小に関わりません。数万円の預金を、無断で引き出したことから深刻な不信感が生まれて、それが数百万円単位の請求や訴訟につながることも起きています。
そのため、相続を控えている家庭にとって「透明性」と「準備」が非常に大切です。資産を分ける話し合いは、どうしても感情が交錯しやすいです。事前に財産を一覧化して、預金・不動産・株式・保険・デジタル資産など、漏れなく整理することが大切です。「知らなかった」「教えてもらえなかった」という行き違いを防ぎましょう。
家族間で、財産に関する情報をオープンに共有することも重要です。定期的に話し合いの場を持ち、相続について率直に意見を交わす習慣をつけてください。相続の話題は後回しにされがちですが、元気な時に家族で確認することが、安心をつくるための第一歩になります。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル資産や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
相続財産不正調査2.0の紹介
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼