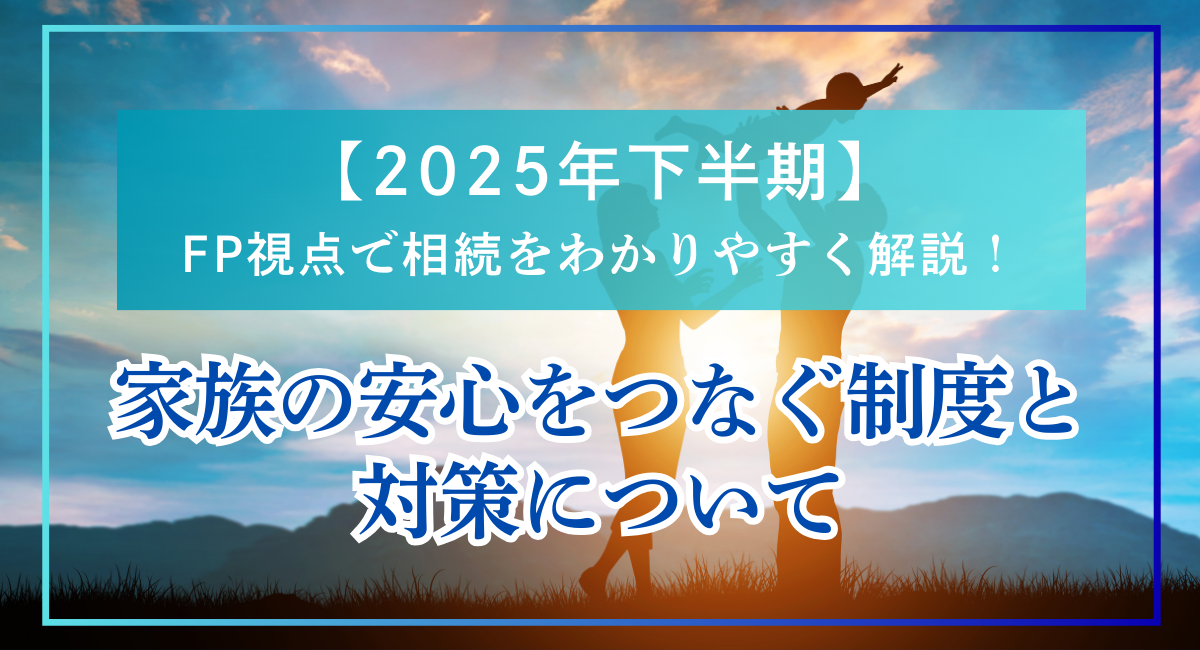「相続税はお金持ちだけのもの」というイメージをお持ちの方は少なくありません。確かに一昔前までは、高額な資産を持つ一部の富裕層だけが、関わる税金という印象でした。
しかし、2025年現在の状況を見てみると、必ずしもそうとは言えなくなっています。特に都市部においては、不動産価格の上昇や土地評価額の高騰により、ごく一般的な家庭であっても、相続税が課されるケースが増えているのです。住宅ローンを完済したマイホームや、ご両親から引き継いだ土地などが、思いのほか高額と評価されるケースがあります。
預貯金や金融資産と合わせると基礎控除額を超えてしまう、という状況は珍しくありません。相続税の問題は、今後のライフプランにも関わる重要なテーマです。相続発生時に慌てて対応するのではなく、早めに制度を理解する必要があります。状況に合わせた対策を検討しておくことが、将来の安心につながるでしょう。
今回の記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、2025年下半期の相続税制度のポイントや最新情報を整理します。一般家庭ができる有効な備えや対策についても、解説していきます。
相続税が家計に与える影響と対策の基本

相続税は、簡単に説明すると、故人が残した財産を家族が受け継ぐ際に、その受け取った財産の額に応じてかかる税金のことです。対象となるのは、現金や預金といったお金だけでなく、不動産や株式、生命保険金、美術品など幅広いものが含まれます。
ファイナンシャルプランナー(FP)の視点で、最初に注意しなければならないポイントがあります。それは、相続税の納付は原則として「現金」で行わなければならない点です。手元に現金が不足している場合、故人が住まいや大切な土地を残そうと思っても、納税資金をまかなうために、家族は手放さなければならない可能性があります。
早めに制度を理解して、遺言書の作成や生前贈与の活用、納税資金の準備といった具体的な取り組みを検討しましょう。家族の安心を確保しながら、将来のリスクを軽減できます。
| 相続税の基本の観点 | 内容 |
| 相続税の概要 | 亡くなった人の財産を相続人が受け継ぐ際、取得財産の額に応じて、課される国税 |
| 課税対象 | 現金・有価証券・生命保険金・美術品など、幅広い資産が対象になる |
| 税負担の特徴 | 財産評価が高額になると、多額の税負担が発生することがある |
| FP視点での重要性 | 相続税は「一度の出費」ではなく、残された家族のライフプランに大きな影響を与える |
| 納税方法の問題 | 原則「現金」での納付が必要。不足すれば、不動産・株式を売却せざるを得ない場合がある |
| 家族への影響 | 大切な住まいや土地を、手放す可能性がある |
| 分割に関するリスク | 思惑の違いから「争族」に発展し、親族関係が悪化する場合がある |
| 心情・生活面への影響 | 単なる税負担にとどまらず、家族の感情や生活に深刻な影響を及ぼす |
| 対策の基本姿勢 | 単なる「節税」ではなく「資産を守り次世代につなげる仕組みづくり」として考える必要がある |
| 具体的な取り組み | 制度理解、遺言書の作成、生前贈与の活用、納税資金の準備などがある |
相続税率と基礎控除のポイント

相続税は、受け取った財産の金額に応じて税率が上がる「累進課税」の仕組みです。税率は10%から最高55%まで段階的に上昇するため、財産が多いほど、負担も大きくなります。
しかし、すべての財産に課税されるわけではなく「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があります。基礎控除は次の計算式で求められます。
- 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、基礎控除額は下記の内容です。
- 3,000万円+600万円×3=4,800万円
この金額以内の遺産には税金がかかりません。
しかし、都市部では不動産の評価額が高く、この枠を超える可能性があります。たとえば、都内に評価額5,000万円の自宅と、預金1,500万円がある場合、合計で6,500万円となり、基礎控除を上回る1,700万円が課税対象になるのです。
このように、特別に資産家でなくても、都市部で持ち家を持っている一般家庭が、相続税の対象になるケースは少なくありません。地価の上昇や金融資産の増加も重なり、多くの家庭にとって、身近で重要な問題となっています。
| 相続税率と基礎控除について | 内容 |
| 課税方式 | 累進課税方式(取得金額に応じて10%〜55%が適用) |
| 税率の仕組み | 一定額を超えると段階的に税率が上がるため、資産規模が大きいほど負担が増す |
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 基礎控除の例 | 相続人が配偶者+子ども2人(計3人) の場合、 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円になる |
| 非課税ライン | 配偶者と子ども2人のケースで、相続財産が4,800万円までなら、課税がかからない |
| 都市部での問題点 | 不動産評価額が高く、基礎控除を超えやすい |
| 具体例 | ・自宅不動産:5,000万円 ・預金:1,500万円 ・合計:6,500万円 |
| 課税対象額 | 6,500万円 − 4,800万円 = 1,700万円 |
| 結果 | 相続税の申告・納付が必要になる |
| 背景 | 都市部では一般家庭でも課税対象となる事例が増加している |
| 重要性 | 「相続税は富裕層の問題」という従来の認識は変化し、多くの家庭にとって対策が不可欠である |
相続税は変わらないけど制度は変わる!2025年の注目改正

2025年下半期時点では、相続税そのものの税率や基礎控除額について、大きな変更はありません。しかし、相続に関連する制度は、改善や見直しが行われています。これらは「相続税対策」という枠を超えて、資産管理や承継計画に直結する恐れがあります。
まず注目すべきは、生前贈与制度の見直しです。なかでも「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置」は、2027年3月まで延長されることが決まっています。これは、祖父母や親などから、子や孫へまとまった資金を非課税で贈与できる仕組みです。住宅取得や教育資金の贈与と並び、将来を見据えた資金移転の有効な手段となります。
次に、非上場株式に関する納税猶予制度の緩和は、中小企業の経営者やその家族にとって大きなメリットがあります。これまでは、事業を引き継ぐ際に、多くの相続税が発生して、会社の存続や雇用に悪影響を与えることが心配されていました。しかし、制度が緩和されたことで、一定の条件を満たせば、相続税の納税を先送りできる範囲が広がったのです。
また、2024年に施行済みですが、相続登記の義務化も重要なテーマになります。これまでは、相続した不動産をすぐに名義変更する必要がなかったため、放置されるケースが多くありました。「所有者不明の土地」という社会問題の原因になっていたのです。しかし、不動産を相続した人は3年以内に登記することが義務となり、違反した場合、罰則(過料)が科されます。そのため、相続人全員が遺産を正しく把握して、名義変更や話し合いを早めに進めることが必要になりました。
| 2025年の相続制度について | 内容 | 影響・目的 |
| 相続税の基本制度 | 税率・基礎控除額に大きな変更なし | 制度は従来どおり累進課税を維持 |
| 生前贈与制度(結婚・子育て資金一括贈与) | 2027年3月まで延長 | ・祖父母・親から子や孫へ非課税でまとまった資金移転可能 ・住宅取得や教育資金に加えライフイベントに応じた活用が可能 ・世代間の資産移転を円滑化 |
| 非上場株式の納税猶予制度(事業承継税制の緩和) | 一定要件下で猶予範囲を拡大 | ・中小企業の事業承継時に多額の税負担を軽減 ・経営基盤や雇用の継続を支援 ・地域経済の安定に寄与 |
| 相続登記義務化(2024年施行済み) | 相続による不動産取得から3年以内に登記が義務化。違反は過料対象 | ・「所有者不明土地」問題への対処 ・相続人の特定を明確化 ・家族内での資産把握と話し合いの促進 |
| 制度改正全体の意義 | 単なる税制改正にとどまらず、資産管理・承継全体に影響 | ・「家族の資産を守り、どのように次世代に引き継ぐか」というライフプランへ直結 ・早期準備と制度理解が安心につながる |
FP直伝!失敗しない相続税対策の基本
ファイナンシャルプランナー(FP)として特におすすめしたいのは、いわゆる小手先の「節税テクニック」ではありません。家族のライフプランにそって無理のない形で資産を守り、円滑に承継できるようにする「総合的な対策」です。まず、活用したいのが生前贈与になります。暦年贈与を利用すれば、毎年一定額を少しずつ贈与することで、将来の相続財産を計画的に減らしていくことが可能です。
次に、生命保険の活用も効果的です。生命保険には「500万円 × 法定相続人」という非課税枠が設けられており、まとまったお金を受け取れるだけでなく、そのまま相続税の納税資金として使える点がメリットです。また、不動産の特例を知っておくことも重要です。代表的なものに「小規模宅地等の特例」があります。
条件を満たすと、自宅や事業用不動産の評価額を、最大80%減額できる場合があります。土地の評価額は、相続財産全体に占める割合が大きいため、この特例を適用できるかどうかは税額に直結します。都市部にマイホームを持つ家庭にとっては、特に恩恵の大きい制度です。
そして忘れてはならないのが、家族間での話し合いと情報共有です。どのような有効な制度を知っていても、家族の間で財産の全体像が把握されていなかったり、意見の食い違いがあったりすると、円満な相続は難しくなるでしょう。いわゆる「争族」を防ぐためには、相続人全員が同じ情報を共有しなければなりません。早めの段階から、意思をすり合わせておくことが必要です。
| 対策 | 内容 | 効果 |
| 生前贈与の活用 | 暦年贈与により毎年少しずつ資産を移転する | 相続財産を減らし、課税対象額を圧縮できる |
| 生命保険の活用 | 「500万円 × 法定相続人」の非課税枠を利用 | ・非課税財産の拡大 ・納税資金の確保に有効 |
| 不動産の特例活用 | 小規模宅地等の特例を利用し、自宅や事業用不動産を評価減 | 評価額を大幅に下げ、相続税の負担軽減につながる |
| 家族会議と情報共有 | 財産の把握や分割方法を早めに話し合う | 相続税対策だけでなく、争族(相続争い)の防止に効果的 |
実際のケースで学ぶ相続税の対策!贈与・事業承継の工夫
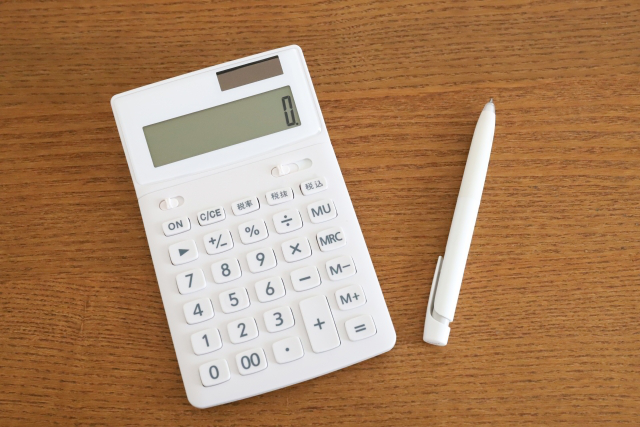
相続は、家族にとって大きな転機です。資産の承継だけでなく、税金や納税方法への備えが欠かせません。特に、不動産や預金、事業資産を持つ家庭では、準備の有無によって残された家族の生活や事業の継続に、大きな影響を与えることがあります。ここでは、生命保険や生前贈与、納税猶予制度を活用して、円滑に資産承継を行った家庭の事例をご紹介します。
- 事例1:都内に自宅と預金を持つ家庭
東京都内に自宅(評価額5,000万円)と預金2,000万円を所有していた家庭では、合計で7,000万円の相続財産がありました。相続人は配偶者と子ども2人の3人であり、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
これを超える2,200万円が課税対象となります。現金一括で納付が必要になるため、不動産を手放さざるを得ない恐れもありましたが、生命保険を上手に活用できました。生命保険金には「500万円×法定相続人分」の非課税枠があります。
この制度を利用して、配偶者と子ども2人あわせて1,500万円まで非課税となるよう、保険金を設定したのです。これにより、相続税の納税資金を無事に確保できました。大切な自宅を手放さずに済んだ事例です。
- 事例2:生前贈与をコツコもありましたがツ続けた家庭
別の家庭では、両親が生前からコツコツと暦年贈与(年間110万円まで非課税)を活用していました。子ども一人あたり毎年110万円を渡し、合計で2,200万円の資産移転に成功しました。
これにより、将来的に相続財産として計算される金額を大幅に圧縮できたのです。突然の相続発生で、相続人が大きな税負担を抱えるのではなく、無理のない形で資産を移転できました。子ども世代にとっても、生活や教育費に役立ち、双方にとって、納得感のある資産承継が実現できた事例です。
- 事例3:不動産と事業承継を抱える家庭
中小企業を経営している方のケースです。不動産と非上場株式を、子に引き継ぐ必要があった家庭では、多額の相続税負担が想定されました。そのままでは、事業資金を税金で消耗してしまい、経営の継続に支障をきたします。そこで活用したのが非上場株式の納税猶予制度です。
この制度を利用することで、一定の条件を満たす限り、相続税の一括納付を先送りできます。納税のために、株式を売却したり事業資金を削ったりする必要がなくなりました。その結果、家族資産の承継と事業継続の両立が可能になりました。従業員の雇用や地域経済への貢献を守ることにもつながったのです。
2025年下半期の相続を取り巻く時代の流れ
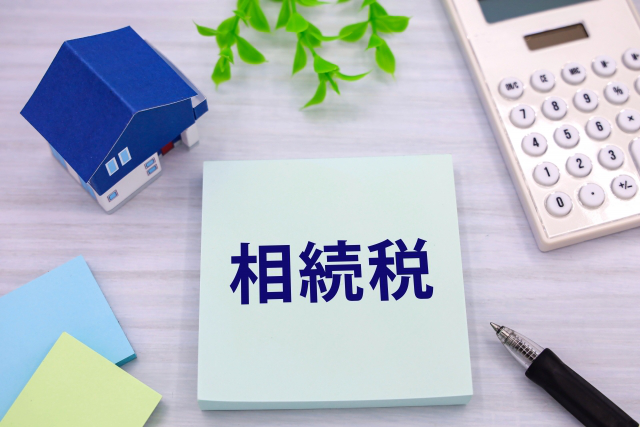
2025年下半期の相続をめぐる環境は、これまで以上に急速に変化しています。「知らなかった」「準備していなかった」では済まされない状況です。また、金融資産の電子化によって、相続人が故人の財産を把握できないまま、放置されるケースも増加しています。
日本社会では、高齢化と単身世帯の増加が進み、従来以上に相続トラブルや「争続」へと発展しやすい土壌が広がっています。相続の場面では、もはや「節税対策」だけでは、不十分です。家族の生活や安心を、確実に守る仕組み作りが必要になります。
相続の準備を後回しにすると、残された家族に、大きな負担や不利益を背負わせることになりかねません。「まだ大丈夫」と思って、何もしないことが最大のリスクです。相続について真剣に考えて、具体的な対策を始めることが重要です。
「相続の大波」が押し寄せる時代
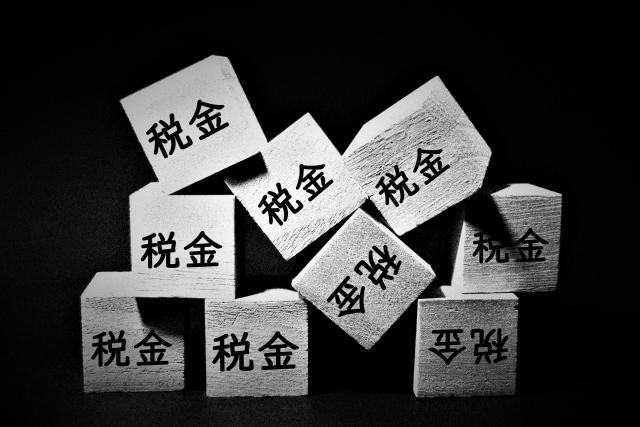
団塊世代が本格的に高齢期を迎える2025年以降、日本はついに「大相続時代」へ突入しました。これは単なる世代交代ではなく、社会全体を揺るがす規模の、資産移転になります。住宅や土地・金融資産が一斉に次世代へ受け渡される過程で、地域経済や生活環境に深刻な影響を与える可能性があります。
すでに都市部を中心に、自宅や実家を相続したものの誰も住まない「空き家相続」が急増しています。放置されれば、地域の景観悪化や防犯リスク、資産価値の急落といった連鎖的な問題を引き起こすかもしれません。また、相続人同士の意見の対立による「資産分割トラブル」は避けられない状況です。遺言や事前の話し合いを怠れば、兄弟姉妹の関係崩壊や、裁判沙汰に発展するケースも現実に起きています。
さらに、新たな脅威として浮上しているのが「デジタル遺品」です。スマートフォンやパソコンに残された写真・動画・連絡先だけでなく、ネット銀行や仮想通貨など、存在にすら気付かれないまま放置されるケースがあります。解約不能・不正利用・費用の垂れ流しといった新たなトラブルを生み出すでしょう。
このような課題に直面して、デジタル遺品整理業者や専門サービスを利用する家庭も、増加しています。実際に、これを後回しにすれば、財産の散逸や家族への重い精神的・金銭的負担が避けられません。相続の「大相続時代」を生き抜くためには、具体的な相続準備を始める必要があります。
| 「大相続時代」の問題について | 内容 |
| 大相続時代の到来 | 2025年以降、団塊世代が高齢期に入り、大規模な資産移転が始まる。住宅・土地・金融資産が一斉に次世代へ受け渡されて、社会全体に影響を与える。 |
| 空き家相続 | 都市部を中心に増加。誰も住まない家が放置されると、景観悪化、防犯リスク、資産価値下落につながる。 |
| 資産分割トラブル | 相続人同士の意見対立が増加。遺言や事前の話し合いを怠ると、兄弟姉妹の関係破綻や裁判沙汰に発展するかもしれない。 |
| デジタル遺品問題 | スマホ・PCに残された写真・動画・連絡先、ネット銀行や仮想通貨などが放置されるケースがある。存在に気づかれず、不正利用や費用垂れ流しの恐れがある。 |
| 新たなサービス利用 | デジタル遺品整理業者や専門サービスの利用が増えている。未整理の場合、財産散逸や家族への精神的・金銭的負担が発生する。 |
| 相続の重要性 | 相続は、もはや一部の資産家の問題ではなく、誰もが備えるべき課題。具体的な相続準備を始める必要がある。 |
路線価上昇がもたらす相続税負担の増加

2025年現在の路線価(相続税などの計算に使われる土地の評価額)は、全国平均で前年比+ 2.7%と上昇が続いています。特に、東京都心や再開発エリアでは、不動産の価値が大きく押し上げられているのです。
地価の上昇は一見プラスに思えますが、相続の場面では注意しなければなりません。なぜなら「土地の評価額が上がる=相続財産が増える」と見なされるためです。結果として、相続税の負担が重くなります。
たとえば、自宅を1件所有している場合、地価が数%上がるだけで、資産評価額が数百万円に増えることもあるのです。このような変化は、都市部だけではありません。地方の主要都市や駅近のエリアなどでも広がっており、土地を持っているだけで、基礎控除を超えて相続税の対象になる家庭が増えます。
そのため、不動産を持つ家庭では「知らないうちに相続税がかかる」状況になりやすいのです。「現金は少ないのに土地だけある」という場合には、相続税を払うために、やむを得ず不動産を売却する必要があります。このような事態を避けるためには、事前に不動産の評価額を確認しましょう。相続税を軽減できる特例を知っておくこと、納税資金を準備しておくことがますます重要になっています。
| 相続税負担に関するテーマ | 内容 |
| 路線価の動向 | 2025年の全国平均は前年比+ 2.7%上昇。東京都心や再開発エリアで特に上昇。 |
| 地価上昇の影響 | 土地の評価額が上がる=相続財産が増えると見なされる。 |
| 具体例 | 自宅一件の所有でも、地価数%上昇で、資産評価額が数百万円増加することがある。 |
| 対象地域の広がり | 都市部だけでなく、地方主要都市や駅近エリアにも波及。 |
| 家庭への影響 | 土地を所有するだけで、基礎控除を超える恐れがある。 |
| リスク | 「現金は少ないのに土地だけある」場合、相続税支払いのために、不動産売却が必要になることがある。 |
高度化する相続サービスと専門相談の拡大

現在、相続の相談サービスは大きく進化しています。以前は「相続税の申告」や「節税対策」が中心でした。今では家庭ごとの事情に合わせた、より細かいサポートができるようになっています。
たとえば、下記の状況に応じて、専門的なアドバイスが受けられます。
- 医師家庭の場合の、クリニックや医療法人の承継
- 経営者家庭の、非上場株式や事業用不動産の扱い
- 障害のある家族がいる場合は、生活支援や信託制度の活用
オンライン相談サービスの普及によって、地方に住んでいても、都市部のFPや税理士などに、手軽に相談できるようになりました。この柔軟な変化によって、これまで多くの人が感じていた「相続は難しい」「専門家は遠い存在」という心理的な壁は、着実に低くなってきています。
相続税の課税対象が広がる時代

2025年に相続税を申告する人の割合は、全国平均で約9%を超えています。これはすでに10人に1人が相続税を支払う時代になったことを意味します。もはや「相続税は一部の富裕層だけの問題」という時代は、終わりを迎えています。
この背景には、2015年の税制改正によって、相続税の基礎控除額が大きく引き下げられたためです。これにより、従来なら課税対象にならなかった一般家庭であっても、相続税の対象となるケースが急増しました。近年は、地価や株価の上昇、高齢世帯における資産蓄積などが重なり、課税割合は、右肩上がりの傾向を続けています。
FPの今後の見通しとして、この流れは一時的なものではありません。たとえば、2030年付近には、一部の都市部で課税割合が、2割近くまで達する可能性があります。家庭の2軒に1軒が「相続をきちんと準備しなければならない」といった社会情勢が訪れても、不思議ではないでしょう。
家族が見落としがちなデジタル資産の存在

デジタル社会で私たちの暮らしは、オンラインサービスやデバイスなしには、ほとんど成り立たなくなっています。ネット銀行の口座や証券取引アプリを通じた資産管理、日々の思い出を保存しているクラウドなど、多くの仕組みが生活と密接に結びついています。また、ゲームの課金アイテム、電子書籍やデジタルコンテンツの購入履歴なども、多くの人にとっては欠かすことのできない「財産」です。
こうしたデジタル資産は、実際の形が見えません。その結果、利用料や課金が継続されて思わぬ負担が発生したり、残された大切なデータが失われたりするリスクが生じます。法的に相続対象となる場合もあるため、トラブルや混乱を招く可能性も指摘されています。
相続トラブルや申告漏れリスク

相続手続きは、多くの人にとって、人生で何度も経験するものではありません。ほとんどの方にとって、初めて直面する複雑な手続きです。戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議など多岐にわたる作業が必要となります。法律や税務に関する専門的な知識が求められるため、思いがけないトラブルに発展するケースも多いです。
相続税の申告は、どうしても申告漏れが起きやすい分野です。もし申告に漏れがあれば、税務署からの指摘を受けて、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。思わぬ経済的損失を被る可能性があるのです。相続税の申告漏れが原因で、相続人同士の不信感が生まれて、親族間のトラブルや争いに発展することも少なくありません。
近年は、税務署の調査体制も進化しており、AIやデータ分析を活用することで、過去なら見逃されていた小さな誤りや申告漏れも簡単に見つかります。そのため、これまで以上に正確で、丁寧な申告が求められる時代になっているのです。
このようなリスクを避けるためには、事前に相続の知識を身につけることが大切です。さらに、不安があれば専門家に相談することで、余計な負担を軽減できます。安心して相続手続きを進めるには、専門家の力を借りつつ、正しい情報を相続人全員で共有しましょう。
2025年のデジタル遺品業者の役割について

相続税の申告漏れリスクを避けるためには、デジタル遺品業者に依頼する方法もありますが、法的な制約に留意する必要があります。デジタル遺品業者は、故人が使用していたパソコンやスマートフォンの解析を行い、その中に残された情報を丁寧に調べ上げます。
クラウドやメールのログイン履歴、各種アカウントのデータを調査することで、家族だけでは気づきにくいデジタル資産を発見できるのが特徴です。暗号資産や電子マネー、ネット証券といったオンライン上に存在する資産は、一般の相続人にとって、把握が難しいです。
専門知識がなければ、アクセス方法や資産の管理状況を確認できず、見過ごされてしまう危険もあります。しかし、デジタル遺品業者であれば、このような資産の手がかりを、システムログや取引履歴から突き止めます。相続手続きに必要な情報を整理して提示してくれます。
デジタル遺品業者のサポートを受けることで、相続人全員が、正確な資産状況を把握できるでしょう。その結果、申告漏れを防ぎ、税務署から指摘を受けるリスクを軽減できます。デジタル社会における相続では、こうした第三者の力を借りることが、円滑かつ安心した手続きを進めるうえで重要です。
| デジタル遺品業者の役割 | 内容 |
| 業者の役割 | ・パソコンやスマホの解析 ・クラウドサービスやメールの調査 ・各種アカウントに保存されたデータの確認 |
| 特徴 | 家族では気づきにくいデジタル遺品を発見できる |
| 特に重要な資産 | 暗号資産、電子マネー、ネット証券などオンライン上の資産 |
| 相続人にとっての課題 | ・アクセス方法や管理状況の把握が難しい ・価値がある資産を見過ごす危険がある |
| デジタル遺品業者の強み | システムログや取引履歴から資産の手がかりを発見して、相続に必要な情報を整理する |
| 得られる効果 | ・正確な資産状況の把握 ・申告漏れの防止 ・税務署からの指摘リスクを軽減 ・相続人間のトラブル回避 |
まとめ

2025年の下半期では、相続税制度自体について、大きな変更はありません。しかし、登記義務化や周辺制度の改正など、家族のライフプランに直結する動きが進んでいます。また、制度以上に注目すべきは「社会全体の相続環境の変化」です。大相続時代の到来、地価や路線価の上昇、相続関連サービスの高度化といったトレンドは、すべての家庭に少なからず影響を与える可能性があるでしょう。
FPの視点から強調したいのは、相続対策とは単なる「節税」ではなく、家族の安心と資産承継のリスク軽減です。資産状況や家族構成によって、最適な方法は異なるため、早めに準備を始めることで、納税や承継への不安を大きく減らせます。
相続は、家族にとって大きなイベントです。税金の額を抑えることだけでなく「家族が円満に未来を迎える準備」として、取り組むことが重要です。このような準備が、これからの時代に求められる相続対策だといえるでしょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼