故人のiPhoneロック解除は慎重に行う必要があり、初期化されるリスクもあるため専門家への相談も検討しましょう。本記事では安全な解除方法や知っておきたい生前対策を解説します。
被相続人(故人)は生前にiPhoneを使用されていた場合、その中には連絡先や写真、メッセージだけではなく、金融資産に関する情報など「相続手続き
に必要な情報が保存されている可能性もあります。
しかし、iPhoneをはじめとするデバイスはたとえ配偶者や子などの同居のご家族であっても暗証番号がわからず、ロックの解除ができないケースは少なくありません。また、以前の記事でもご紹介のとおり「不正アクセス禁止法
に抵触する可能性があるため、正当な手続きを踏むことが求められます。
そこで、本記事ではiPhoneのロック解除について、不正アクセス禁止法の概要にも触れながら安全な方法と注意点を詳しく解説します。
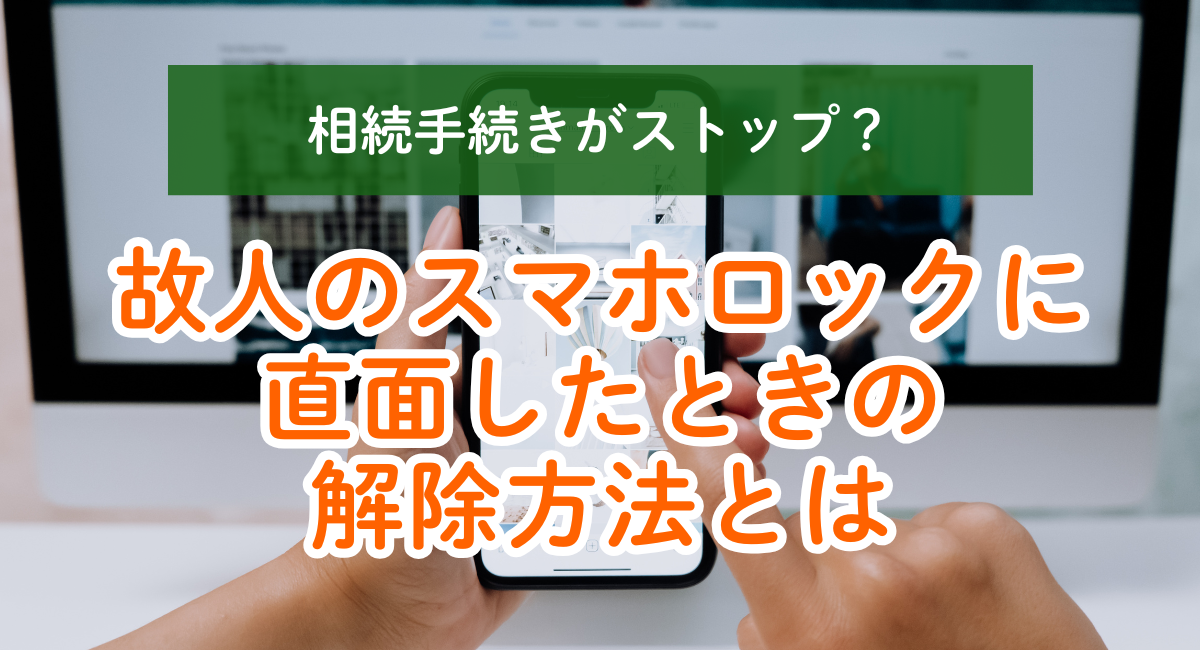
被相続人(故人)のiPhoneロック解除の基本的な方法
被相続人が生前にiPhoneをご利用されていた場合、その中に含まれている情報が相続手続きに必要となる可能性があります。
特に近年はネットバンキングやオンライン証券だけではなく、暗号資産や副業に関するアプリなどもお持ちの方が多いため、大切な資産を把握するためにもiPhoneを適切に扱う必要があります。では、ご逝去後のロック解除はどのように行うのでしょうか。この章ではロック解除の基本的な流れを解説します。
パスコードを入力する
被相続人が生前に使用していたパスコードがわかる場合、ロック解除は可能です。パスコードは、エンディングノートやメモに書かれていることがあったり、パソコンなど他のデバイスと共通したものを利用しているケースもあります。
Apple IDの管理連絡先を利用する
iOS 15.2以降「故人アカウント管理連絡先
を設定していた場合、事前に生前故人が作成していたアクセスキーと死亡証明書を提出することで、故人のApple IDにアクセスできる可能性があります。この方法は家族に限られておらず、個人アカウント管理連絡先であると証明できればご友人でも可能です。
詳細はAppleの公式サポートページをご確認ください。
参考URL: Apple 亡くなったご家族のApple Accountへのアクセスを申請する方法
指紋認証や生体認証によるロック解除はできない
iPhoneは指紋認証や生体認証によるロックの設定も可能ですが、iPhoneの持ち主が亡くなられたら解除できなくなります。
知っておきたい「不正アクセス禁止法」とは
写真や連絡先だけではなく、さまざまな種類の電子マネーなども収められているiPhoneですが、相続開始後であっても、無断でロック解除を試みる行為は『不正アクセス禁止法』に抵触する可能性があり、法的トラブルにつながる場合があります。この章では不正アクセス禁止法について、簡潔にご説明します。
デジタル遺産と不正アクセス禁止法
iPhoneをはじめ、被相続人が所有していたデバイスは資産価値があるものの場合、相続財産の対象です。つまり、被相続人の死後は相続人全員の共有状態となります。
ただし、契約者本人とだけ有効な「一身専属性」の契約は相続できません(民法896条)。一身専属性のアカウントに本人以外がアクセスしたり権限を使ってサービスを利用したりすると、デジタル遺品の場合は「不正アクセス禁止法」に抵触するおそれがあります。
デジタル遺産と相続手続きの注意点
上記で触れたように、被相続人の死後に遺産分割協議で誰が何を相続するか決めていない場合は、デバイスは相続人全員で共有している状態です。遺産分割協議を経る前に、iPhoneにアクセスし、金融資産や電子マネーなどの情報を得ている場合は、その他の相続人が不正利用を疑うおそれがあります。この問題は不正アクセス禁止法とは別で、相続トラブルにつながるおそれがあるため注意が必要です。iPhoneのロック解除については、その他の相続人にも伝えた上で行うことが望ましいでしょう。
ここに不正調査の広告を入れてください。
被相続人のiPhoneのロック解除に困った時の対処法
被相続人のiPhoneのロック解除に困った場合、一部の専門業者ではロック解除やデータ復旧をサポートしている場合もありますが、最新機種では対応できないケースも多いため注意が必要です。
しかし、業者によっては高額な費用がかかる場合や、データが復旧できないリスクもあります。業者を選定する際は、信頼性や実績を確認し、慎重に判断することが重要です。
ただし、iPhoneのロック解除は非常に難しいことを覚えておきましょう。Apple社は強固なセキュリティ設計を採用しておりパスコードを何度も間違えると、最終的には端末が初期化されます。必要に応じて弁護士に相談の上で、裁判所からの開示命令による安全な相続手続きも検討しましょう。
ロック解除の専門業者への相談がおすすめ
被相続人のiPhoneのロック解除は、データ消失につながるおそれもあり、慎重に進める必要があります。法律面も踏まえる必要があるなど、多種多様なリスクを避けながらロック解除を進めるためには、専門家へ依頼することがおすすめです。
例として、GOODREIではデジタル遺品整理・フォレンジックの専門サービスを提供しており、故人のスマホやクラウドデータの復旧、パスワード解析、ネットサービスのアカウント確認などを、法律やプライバシーに配慮した安全なフレームワークでサポートしています。
知っておきたい!生前からのiPhoneの相続対策とは
私たちの生活に欠かせない存在となったiPhoneは、写真や動画、メール、LINEのやり取り、さらには銀行アプリや電子マネーなど、非常に多くの個人情報や財産的価値を持つデータが保存されています。そのため、iPhoneは最新のセキュリティを搭載して頑丈にロックされており、たとえ相続人であっても簡単にはロック解除ができません。
相続時のこうした問題を避けるためには、生前から「デジタル資産」の整理や相続対策を考えておくことが大切です。ここでは、その具体的な方法を解説します。
「故人アカウント管理連絡先」とは
Apple社は先述のとおり、「故人アカウント管理連絡先」というしくみを提供しています。これは、生前に信頼できる家族や友人を「連絡先」として登録しておくことで、その人が亡くなった後にiCloudに保存されている写真やメモなどのデータにアクセスできる仕組みです。
指定される方はiPhoneやAppleアカウントを所有していなくても共有でき、また、複数人の方が連絡先に指定されることも問題ありません。(ただし、13歳以上にならないと連絡先指定者にはなれません)
設定は以下の①~③の手順です。
①iPhoneの「設定」アプリから簡単に行うことができ、ユーザー名をタップします。
②「サインインとセキュリティ」をタップし、「故人アカウント管理連絡先」を開きます。
③「故人アカウント管理連絡先」をタップし、実際に指定します。
連絡先に選ばれた人には特別な「アクセスキー」が発行されます。死亡後にこのキーと被相続人死亡証明書を提出すれば、Appleの公式な手続きを通じてデータへアクセスできるようになります。
エンディングノートの利用
もうひとつ有効な方法が「エンディングノート」です。エンディングノートとは、自分の死後に備えて家族に伝えておきたい情報をまとめておくノートのことで、相続の生前対策として遺言書よりも簡単に作れるため、中年層にも広まっています。紙媒体でもデバイス上でも構いませんが、デバイスはロックがかかるおそれがあるため注意しましょう。
iPhoneのパスコードやApple ID、クラウドサービスのログイン情報などをエンディングノートに記録しておけば、相続人がスムーズに手続きを進められます。ただし、セキュリティ上のリスクもあるため、ノートの保管場所には注意が必要です。
エンディングノートは書きやすい書式のノートが販売されていますが、法的な制約を受けるものではないため、日記帳など別の買いやすいノートも選択できます。
遺言書を利用する方法もある
より法的に強い効力を持たせたい場合は「遺言書」による対策が効果的です。遺言書に明記しておけば相続人間のトラブル回避には有効ですが、Appleの利用規約上はアカウントの譲渡が認められない可能性がある点に留意が必要です。特にデバイス内に高額の暗号資産やデジタル資産がある場合は、遺言書を利用することを検討しましょう。
また、遺言書は公正証書遺言として公証役場で作成しておくと安心です。相続人が「デジタル遺品を誰がどう扱うか」を明確に把握でき、余計なトラブルを避けられます。
弁護士や司法書士など専門家に相談しながら、財産だけでなく「デジタル資産」も含めた総合的な相続対策を検討することもおすすめです。
まとめ
iPhoneには、思い出の写真や連絡先、重要な情報が詰まっています。そのため、ロックが解除できないと相続人は大きな不便やストレスを抱えることになります。こうした事態を防ぐためには、生前から「故人アカウント管理連絡先」の設定を行ったり、エンディングノートにパスワードを記録しておいたり、遺言書で明確に指示を残すことが重要です。
しかし、現実には「すでに故人が亡くなりロック解除ができない」という状況に直面するケースも少なくありません。不正アクセス禁止法に抵触する可能性もあるため、自己判断で強引に解除するのは危険です。
解除やデータの取り出しが必要な際には、デジタル遺品整理を専門に扱うプロフェッショナルの力を借りるのが最も安全です。「手続きに不安がある」と感じたら、無理をせず専門家へご相談ください。

