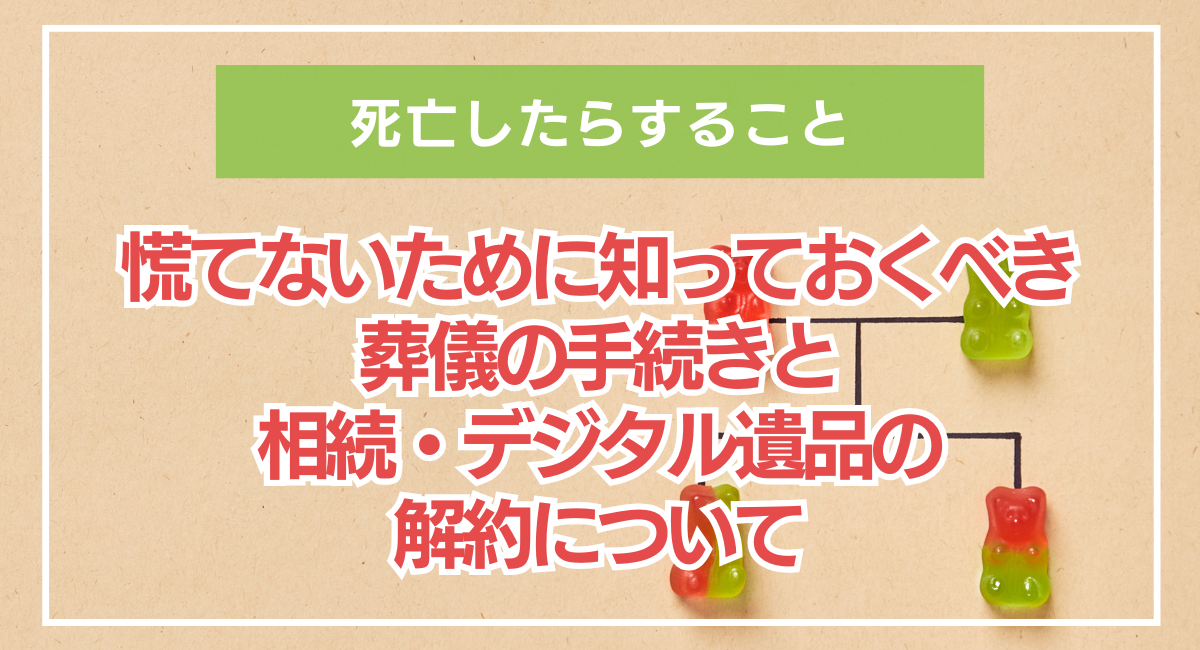身近な人が亡くなると、深い悲しみと同時に、すぐに対応しなければならない数多くの手続きに直面します。葬儀の準備や役所への届け出、相続の手続きだけではありません。近年では、スマホやSNS、ネット銀行といった「デジタル遺品」の解約や整理も避けて通れません。
突然の事態に慌てないためには、事前に流れを理解して、必要な準備を知っておくことが大切です。今回の記事では、葬儀から相続、そしてデジタル遺品の解約まで、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
【親や身内が死亡したらすること】遺族の戸惑いと悩み

親や身内の死が突然のことで、遺族は何を優先すればよいのか、誰に連絡したらよいのか戸惑うことも多いでしょう。葬儀の準備だけでなく、役所への届出や各種登録手続き、相続の整理、さらにスマホやパソコンなどに残されたデジタル遺品の整理も、必要になります。
葬儀の段取りでは、葬儀社との打ち合わせで、日程や場所、規模を決めて、火葬や法要の手配も同時に進めなければなりません。しかし、精神的な負担と時間的な制約が重なるため、冷静に手続きを行えない場合があります。
親や身内が亡くなった際によくある困りごと

親や身内が亡くなった場合、突然の出来事で、遺族は戸惑いが生じてしまいます。しかし、「死亡したらすること」の事前対策を行っていないと、火葬許可証の取得、健康保険・年金の手続き方法など、分からないケースが多いのが現状です。必要な書類と期限が細かく決まっているため、遺族だけで行うのは大変な負担になります。
また、故人の財産や遺言書の有無などの情報がすぐに分からず、親族間で誤解やトラブルが起きることへの心配もあります。銀行口座や保険契約、公共料金の解約・名義変更の順序も分かりにくいため、どこから手をつければよいか迷うことが多いです。
葬儀や法要の準備に関しても、規模の決め方や費用の見積もり、火葬や初七日・四十九日といった法要の手配、仏壇やお墓の準備など、経験や知識がないと対応は非常に難しいです。
| よくある問題 | 内容 |
| 連絡の順序に迷う | 親族や葬儀社、勤務先など、誰にどのタイミングで連絡すればよいか分からない |
| 行政手続きが複雑 | 死亡届、火葬許可証、保険・年金手続きなど、必要書類や期限が多く混乱する |
| 財産・相続の確認が不安 | 遺言書の有無や財産の種類が把握できず、相続トラブルに発展する |
| 契約・金融手続きが分からない | 銀行口座、保険契約、公共料金の手続きを、どこから始めればよいのか判断が困難になる |
| 葬儀・法要の費用や準備に戸惑う | 葬儀の規模や火葬・法要のタイミング、仏壇・お墓の準備など、情報の不足から不安になってしまう |
【死亡後すぐ】最優先でやるべき手続きと流れ
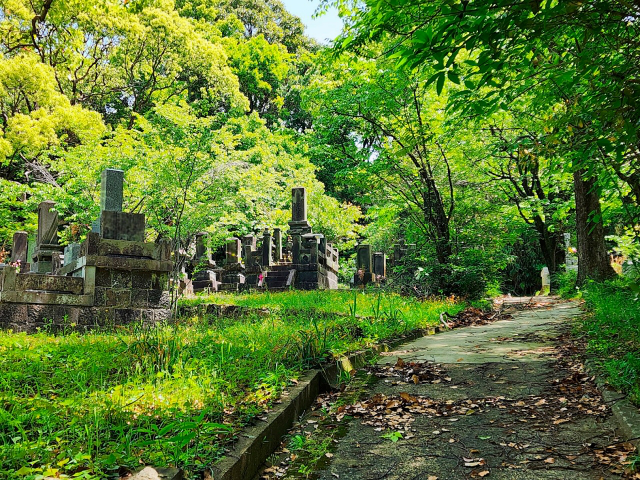
遺言書がある場合は、まずその内容をしっかり確認することが大切です。遺言書は、故人が自身の財産の分け方や、相続の方法を示した意思表示で、相続人同士のトラブルを防ぐ役割があります。
そのため、もし遺言書を見つけた場合、勝手に開封せずに、家庭裁判所で検認手続きを受けてください。検認は、遺言書が本物か、改ざんされていないかを確認するための手続きです。これを通して、遺言書の内容を相続人全員で正式に共有します。
検認の手続きには、書類の提出や、家庭裁判所への申し立てが必要です。遺産分割協議書は、遺言書がない場合に、相続人全員で決めた遺産の分け方を書面にしたものです。これにより、相続後のトラブルを防いで、相続手続きを明確にします。
初めに行う連絡と搬送の流れ

死亡が確認された直後に最も優先すべきは、関係者への連絡と搬送の手配です。まずは親族や特に近しい方へ訃報を伝えます。突然の知らせに動揺を与えないよう、落ち着いた口調で状況を簡潔に伝えることが大切です。
同時に、葬儀社への連絡を行い、遺体の搬送を依頼します。葬儀社によっては、24時間対応しているところも多いです。そのため「どこに搬送するのか」「通夜・葬儀をどのようにするのか」の方向性を、遺族間で簡単に確認しておくと、手配がスムーズです。
また、勤務先や学校など、社会的なつながりがある場所へは、まず「死亡の事実」と「葬儀の日程が決まり次第、改めて連絡する」旨だけを伝えてください。詳細な日程や式の内容は、正式に決まった段階で共有すれば、全く問題ありません。
死亡診断書と死体検案書の取得

医師による死亡確認を経て、必ず「死亡診断書(病院で亡くなった場合)」または「死体検案書(自宅や施設で突然亡くなった場合)」を取得しましょう。
死亡診断書は、病院での死亡や持病が原因の死に対して、担当医師が発行する書類です。これに対して、死体検案書は、事故死や事件死、異状死の疑いがある場合に、警察の監察医や警察医が検案を行ったうえで発行されます。
どちらも、火葬許可証の申請や死亡届の提出、各種保険金の請求など、すべての死亡後の手続きで、必須となる重要な書類です。遺族は取得後、必要な手続きに備えて、複数枚のコピーを用意しておくと良いでしょう。
死亡届の提出・火葬許可証の取得

死亡届は、故人の死亡を知った日(通常は医師から死亡診断書を受け取った日)から、7日以内に市区町村の役所に提出しなければなりません。この死亡届の提出により、火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、葬儀や火葬の手配に必須の書類であり、許可証がなければ、火葬場の利用や葬儀の実施ができません。
提出期限を過ぎると、手続きが滞る恐れがあります。葬儀の日程にも影響が出るため、注意が必要です。死亡届は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村で提出できます。また、土日祝日や年末年始が期限にかかる場合は、翌開庁日までに提出すれば問題ありません。提出は、遺族でなくても可能で、多くの場合は葬儀社が代行することもあります。
遺言書・遺産分割協議書の有無を必ず確認

遺言書が見つかった場合は、まずその内容をしっかり確認して、故人の意思を尊重することが大切です。遺言書は財産の分け方を明確に示しているため、相続人同士の不要な争いを未然に防ぐ効果があります。また、遺言書があっても、状況に応じて相続人全員で話し合いを行ってください。その合意内容を「遺産分割協議書」として、文書にまとめることがおすすめです。協議書を作成しておけば、後々「言った・言わない」といったトラブルを避けられます。
遺言書や遺産分割協議書がない場合に、相続人間での話し合いが難航したり、法律上の解釈で行き詰まったりするケースも少なくありません。そのようなときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、公平性を確保しながら、スムーズに相続手続きが行えます。専門家の助言を受けることで、遺族間の感情的な衝突を避け、安心して手続きが完了できます。
親や身内が「死亡したらすること」でやってはいけない対応

「死亡したらすること」で、やってはいけない対応として代表的なのが、遺産を勝手に引き出したり処分したりすることです。こうした行為は、相続人同士の争いの火種になり、法的な問題に発展する恐れがあります。さらに、不要な契約を慌てて解約するのも、注意が必要です。
契約内容によっては、解約手続きが相続に関わる場合があり、正しい順序を踏まなければ、トラブルにつながりかねません。また、遺言書や重要書類を意図的に隠したり破棄したりすることは、重大な違法行為となります。相続手続きそのものを、混乱させる結果となるのです。
| 時期 | 手続き・行動 | 内容 |
| 死亡直後 | 親族への連絡 | 近しい親族に訃報を落ち着いた口調で伝える |
| 葬儀社へ連絡・搬送手配 | 24時間対応の葬儀社に連絡して、遺体搬送を依頼する | |
| 勤務先・学校へ連絡 | 「逝去の事実」と「日程は後日連絡」を簡潔に伝える | |
| 医師確認後 | 死亡診断書の受け取り | 病院で亡くなった場合、担当医師から取得する |
| 死体検案書の受け取り | 自宅死・事故死・異状死の場合、監察医や警察医が発行する | |
| 書類のコピー保存 | 各種手続き用に、複数枚コピーを作成して保管する | |
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 本籍地、死亡地、届出人住所地の役所へ提出する |
| 火葬許可証の取得 | 死亡届受理により、交付、葬儀・火葬が必須になる | |
| 葬儀前後 | 葬儀の準備 | 通夜・葬儀の日程や形式を遺族で決定していく |
| 火葬許可証の利用 | 葬儀・火葬の実施に使用する | |
| 葬儀後〜相続開始 | 遺言書の確認 | 遺言書があれば、家庭裁判所で検認する。開封して相続人で共有を行う |
| 遺産分割協議書の作成 | 遺言書がない場合や不足がある場合、相続人全員で作成・署名押印する | |
| 随時 | 専門家への相談 | 弁護士・司法書士・行政書士などに相談して、手続きを円滑化させる |
| 禁止事項(いつでも) | 勝手な財産処分 | 遺産の引き出し・処分は禁止である |
| 早急な契約解約 | 不要な契約を慌てて解約しない | |
| 遺言書や書類の隠匿・破棄 | 大きなトラブルにつながるため、隠匿や破棄は厳禁である |
【役所と会社】公的手続き・届け出に必要な書類一覧

身近な方が亡くなった後には、さまざまな手続きや届け出が必要となります。期限や必要書類が細かく決められており、速やかかつ正確に、対応しなければなりません。特に、死亡届や火葬許可証の提出、国民健康保険や介護保険の資格喪失届、年金の停止や遺族年金の申請などは、遺族の生活に直結する重要な手続きです。
また、故人が会社員の場合には、健康保険証の返却や雇用保険手続き、退職金や未払い給与の確認も欠かせません。公共料金や運転免許証、電気・水道・ガス・携帯電話などの契約解約や名義変更も、一連の作業となります。ここでは、役所と会社で必要となる主な手続きと必要書類をわかりやすく整理しました。
役所に提出する主な手続き(世帯主変更・資格喪失届など)
- 死亡届、火葬許可証
- 国民健康保険資格喪失届
- 介護保険資格喪失届
- 世帯主の変更届
年金・健康保険・介護保険の停止・変更・受給申請
- 遺族年金・寡婦年金・遺族厚生年金の申請
- 高額療養費の請求や未受給分の精算
会社員の場合の手続きと必要書類(健康保険・雇用保険等)
- 健康保険証の返却
- 雇用保険の手続き
- 退職金や未払い給与の確認
公共料金・証明書(運転免許証・パスポート等)の返還
- 電気・水道・ガス・携帯電話などの解約・名義変更
- 運転免許証やパスポートの返納
| 区分 | 手続き内容 | 主な書類・ポイント |
| 役所関係 | 死亡届を提出した後に、火葬許可証の取得 | 死亡届、医師の死亡診断書 |
| 国民健康保険資格喪失届 | 健康保険証、死亡診断書の写し | |
| 介護保険資格喪失届 | 介護保険証 | |
| 世帯主変更届 | 戸籍謄本、住民票、印鑑 | |
| 年金・健康保険・介護保険の停止・変更・受給申請 | 年金手帳、健康保険証、印鑑 | |
| 遺族年金・寡婦年金・遺族厚生年金の申請 | 年金証書、戸籍謄本、住民票、振込口座情報 | |
| 高額療養費の請求・未受給分の精算 | 領収書、健康保険証、世帯主名義口座 | |
| 会社員関連 | 健康保険証の返却 | 勤務先を通じて返却 |
| 雇用保険の手続き | 雇用保険被保険者証、離職票など | |
| 退職金や未払い給与の確認 | 勤務先の人事・総務へ申請 | |
| 契約・証明書類 | 電気・水道・ガス・携帯電話など契約の解約・名義変更 | それぞれの契約番号・検針票・死亡診断書写し |
| 運転免許証やパスポートの返納 | 免許証原本・パスポート原本・死亡診断書写し |
【金融・財産】銀行、保険、契約の名義変更・解約方法

身内や親の「死亡したらすること」において、銀行口座や保険、公共料金に関する名義変更や解約も重要です。不動産や自動車といった相続財産の名義変更など、多岐にわたる事務的な手続きが必要になります。
これらは放置してしまうと口座が使えなくなったり、請求期限を過ぎて保険金を受け取れなくなったり、思わぬトラブルにつながる可能性があります。ここでは、死亡後に重要となる金融機関・保険・契約関係・相続財産について、簡単にまとめました。
- 銀行口座・クレジットカードの凍結と解約手順
死亡を銀行に届け出ると、口座は凍結されます。相続人は、必要書類を揃えて名義変更や解約手続きを行います。口座凍結後に、勝手に引き出すと法律違反となるため、注意が必要です。
- 生命保険・損害保険金の請求・支給申請
保険会社に連絡して必要書類を提出すると、死亡保険金や損害保険金を受け取れます。申請期限や必要書類は、保険会社によって異なるため、事前確認が重要です。
- 公共料金・スマホ等 各種契約の解約・変更
ライフラインや通信契約は、解約や名義変更を忘れないようにしましょう。早めに連絡して、未払い料金や違約金の確認も行ってください。
- 自動車や不動産など相続財産の名義変更・登記申請
不動産や自動車は、相続登記や名義変更を行う必要があります。期限や必要書類を確認して進めましょう。登記手続きは、司法書士に依頼するとスムーズです。
| 区分 | 手続き内容 | 主なポイント・必要書類 |
| 銀行口座・クレジットカード | 口座の凍結と凍結解除の手続き | ・死亡を銀行に届け出ると、口座は凍結される ・凍結解除は、相続人などが銀行窓口で申請する ・必要書類は、銀行や相続状況で異なる ・口座の勝手な引き出しは、法律違反になる |
| 保険金請求 | 生命保険・損害保険金の請求・支給申請 | ・保険会社へ連絡して、必要書類を提出する ・申請期限や書類は、保険会社により異なる ・死亡保険金、損害保険金の受け取り手続きを行う |
| 公共料金・通信契約 | 電気・水道・ガス・携帯電話など契約の解約・名義変更 | ・早めに各社へ連絡 ・未払い料金や違約金を確認 ・解約や名義変更の手続きを実施 |
| 相続財産 | 自動車や不動産の名義変更・登記申請 | ・相続登記や名義変更が必要になる ・手続きの期限や必要書類を確認する ・専門家に依頼するとスムーズに進む |
相続人が困らないための事前準備

相続手続きは、多くの書類の収集や期限の管理が必要となり、準備が不十分だと、遺族に大きな負担やストレスがかかります。特に、銀行口座の凍結や保険金請求、不動産の名義変更などは、相続人の確定から戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など、多岐にわたる書類が求められます。ひとつひとつを揃えるだけでも、相当な時間と労力が必要です。
このような手続きの煩雑さを軽減するためには、生前から財産の一覧表を作成しておくことが重要です。たとえば、銀行口座、保険契約、証券口座、不動産の権利関係などを普段から整理し、どこに何があるのか明確にしておけば、相続人は、情報収集や必要書類の提出がスムーズに進められます。
その財産ごとに金融機関名や証券会社名、契約番号、不動産登記簿番号などを、一覧表としてまとめておけば、専門家への依頼や金融機関、役所への提出の際にも迅速に対応できます。大幅な時間短縮につながるのです。
また、遺言書やエンディングノートを生前から準備しておくことで、自身の財産の分け方や相続に関する希望をしっかりと伝えられます。これらの書類は、単なる財産分割の指示だけでなく、遺族へのメッセージや相続人同士のトラブルを防ぐ効果も持っています。生前整理の小さな積み重ねは、遺族にとっても大きな安心材料です。突然のお別れがあった場合にも、心強いサポートになります。
【相続・税金】トラブル防止のための重要ポイント
相続や税金に関する手続きは、適切に行わないとトラブルの原因です。重要なのは、正確な相続人調査と遺産分割協議書の作成、そして専門家のサポート活用です。相続税の申告・納税は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内と期限が厳格に定められています。
遺産の評価や控除を、確実に行わなければなりません。借金をはじめとした負債がある場合には、相続放棄や限定承認といった検討が必要です。ここでは、相続トラブルを防ぎつつ、相続税や各種申請の期限・方法を押さえた重要ポイントをまとめました。
- 相続人調査と協議書の作成・弁護士・専門家の活用法
専門家は相続人を正確に調査して、遺産分割協議書を作成します。弁護士や税理士に相談することで、相続トラブルのリスクを大幅に減らせます。
- 相続税・確定申告・納税の期限と申告方法
相続税は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告・納税しなければなりません。遺産評価や控除を確認して、正確に申告しましょう。
- 相続放棄・限定承認の注意点と申請手順
負債がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。この期限は、自身のために相続が発生したことを知ってから3か月以内なので、注意が必要です。
- 遺族年金・遺産分割・高額療養費等の追加請求
年金や医療費の請求漏れがないように確認しましょう。必要に応じて、社会保険事務所や市区町村に相談することも大切です。
| 区分 | 内容 | 期限・ポイント | 主な手続き・必要書類 |
| 相続人調査・協議書作成 | 相続人を正確に調査して、遺産分割協議書を作成 | 弁護士・税理士など、専門家の活用でトラブル防止 | 戸籍謄本など、相続人確認書類、遺産分割協議書 |
| 相続税・確定申告・納税 | 相続税の申告・納税 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内に、申告・納税が必要 | 遺産評価書、控除証明書、申告書類 |
| 相続放棄・限定承認 | 借金等負債がある場合の相続方法 | 自身のために相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に申請。期間延長申請も可能 | 申立書、戸籍謄本、住民票、利害関係証明など |
| 遺族年金・遺産分割・高額療養費請求 | 年金・医療費等の請求漏れを防止 | 速やかに確認・必要に応じて、社会保険事務所などに相談 | 年金証書、医療費領収書、申請書類 |
デジタル遺品専門業者に依頼するメリットと安心感
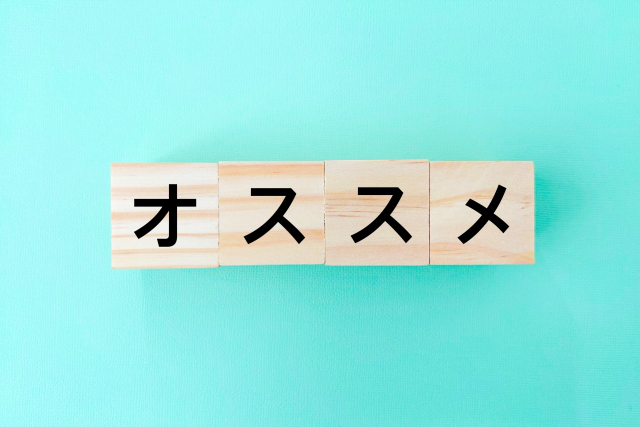
スマホやパソコン、SNS、ネット銀行など、相続の場合では「デジタル遺品」の整理が、避けて通れない課題になりつつあります。最近では、専門の「デジタル遺品整理業者」に依頼するケースが多いです。専門業者への依頼によって、安全かつ確実にデータの削除やアカウントの整理を行えます。
遺品調査では、ネット銀行や仮想通貨の確認もサポートできます。遺族の心理的な負担を大幅に軽減できるのです。これにより、デジタル遺品に伴うトラブルや、情報漏れのリスクを最小限に抑えつつ、安心して整理を進められます。
デジタル遺品業者ができること

デジタル遺品業者は、故人が残したスマホやパソコン、SNS・クラウドなどのデジタル関連資産・サービスに安全かつ確実にアクセスし、整理・管理の支援を行う専門事業者です。
一部の機器については、専門知識を活用してデータを取り出せる場合もありますが、正規サポートを通じる必要があるケースが多いため注意が必要です。故人が契約していたネット証券や仮想通貨・サブスクリプションの有無確認、不要となったSNSやブログアカウントの削除・退会の手続きなどが含まれています。
また、発見した資産や契約内容を分かりやすく整理し、相続手続きに利用できる形で、報告書としてまとめるサービスも提供しています。個人情報の漏洩や資産の見落としを防ぎ、遺族が速やかかつ安心してデジタル資産を管理できるよう、専門知識と技術でサポートするのです。
| カテゴリ | 対象・作業内容 | 詳細・補足 |
| 機器のロック解除 | パソコン/スマホ | パスワード解除 |
| データ取り出し | 写真・文書・連絡先データ | バックアップ・移行 |
| アカウント整理 | SNS・ブログ・金融サービス | 削除申請・リスト化 |
| 契約や資産の調査 | FX・仮想通貨・オンライン証券 | 有無調査・一覧表作成 |
| 遺品機器の初期化等 | パソコンの初期化・再セットアップ | データ消去&セキュリティ設定 |
| 機器の処分・証明書発行 | パソコン/HDD破壊・証明書 | 代理リサイクル、証明書発行 |
| 作業報告書作成 | 作業全般 | 調査・整理内容をレポート |
デジタル遺品業者に依頼する注意点

最も重要なのは、信頼できる業者を選ぶことです。デジタル遺品には、個人情報や金融データが多く含まれるため、セキュリティ体制が不十分な業者に依頼すると、情報漏洩やトラブルにつながる恐れがあります。認定資格や利用者からの口コミなどを確認し、信頼性を確かめることが欠かせません。
料金体系の明確さも注意すべきポイントです。データ復旧やアカウント削除、契約解約のサポートなど、作業内容によって、費用は大きく変わります。中には「基本料金は安いけれど、実際は追加費用がかかる」ケースもあるため、事前に見積もりを取ることが大切です。どこまで対応してもらえるのかを確認しておくと安心です。
また、プライバシー保護への配慮も忘れてはいけません。業者がどのようにデータを取り扱うのか、守秘義務契約があるのかを確認することで、故人や遺族のプライベートな情報を安心して任せられます。
依頼前に対応範囲を確認することも重要です。業者によっては、スマホやパソコンのみ対応という場合もあれば、SNSアカウントやクラウドサービス、サブスクリプション契約の解約まで幅広くサポートしてくれるところもあります。
遺族の状況に応じて、必要な範囲をきちんとカバーできる業者を選ぶことが大切です。デジタル遺品業者を上手に活用することで、遺族の負担を大きく減らせます。安易に依頼するのではなく、信頼性・料金・対応範囲・セキュリティをしっかりと見極めることが、安心につながる第一歩です。
| 選ぶポイント | 内容 |
| 信頼できる業者選び | 個人情報・金融データを扱うため、認定資格や公的登録実績、口コミを確認して、信頼性を確かめることが重要。 |
| 料金体系の明確さ | 基本料金だけでなく、追加費用の有無を見積もりで確認する。作業内容ごとの費用が明確であることが安心につながる。 |
| プライバシー保護の配慮 | データの取り扱いや守秘義務契約の有無を確認。故人や遺族のプライベート情報が安全に管理される業者を選ぶこと。 |
| 対応範囲の確認 | スマホ・PCだけでなく、SNSアカウント、クラウド、サブスク契約の解約など、幅広いサポートが受けられるのかを確認する。 |
| 業者の実績・評判 | 実績の豊富さや専門資格の有無、利用者の口コミ・評判を参照して、技術力や信頼性を見極めることが重要。 |
【葬儀・法要】葬祭の流れと必要な準備・費用

葬儀や法要は、故人を見送り、遺族や親族が心を落ち着けるために欠かせない大切な儀式です。しかし実際には、短い期間の中で多くの準備や手続きが必要です。流れを知っておくことが安心につながります。葬儀社との打ち合わせで日程や規模を決めて、火葬や法要の手配を進めなければなりません。
そして、仏壇やお墓、位牌の準備も早めに考える必要があります。最近では、直葬や家族葬など、費用や形式を抑えた葬儀を選ぶ人も増えています。ここでは、葬祭の流れと準備のポイント、費用の目安をまとめました。
- 葬儀社・火葬・法要(四十九日法要含む)の手配
葬儀社との打ち合わせで日程・場所・規模を決めます。火葬や法要の手配も同時に進めることで、滞りなく儀式を終えることが可能です。
- 仏壇・お墓・位牌などの実施すべき準備
仏壇やお墓の購入・設置、位牌の作成なども、計画的に進めます。費用や場所の確認、親族との相談も早めに行いましょう。
- これからの葬儀(直葬、遺族葬など)選択肢のトレンド
近年は直葬や遺族葬など、小規模で費用を抑えられる葬儀の需要が増えています。遺族の希望や事情に合わせて柔軟に選べます。
| 区分 | 内容 | ポイント・詳細 |
| 葬儀社との手配 | 日程・場所・規模の決定 | 葬儀社と打ち合わせし決定。火葬や法要と並行して手配を進めるのが望ましい。 |
| 火葬の手配 | 火葬許可証の申請・取得・火葬当日の流れ | 死亡届の提出時に火葬許可証申請。火葬は死亡確認後24時間経過が必要。納めの式・出棺・火葬・骨上げの順で行う。 |
| 法要(四十九日含む) | 法要日程の調整・会場手配 | 葬儀後に四十九日法要などの計画。場所選定、親族と日程調整を早めに行う。 |
| 仏壇・お墓・位牌の準備 | 購入・設置、位牌作成 | 費用や設置場所を確認し親族と相談。遺骨の納骨に向けて準備する。 |
| 葬儀のトレンド | 直葬、遺族葬などの選択肢 | 小規模・費用節約型の葬儀の需要増加。遺族の希望や状況に応じた選択が可能。 |
将来に向けた生前整理

現代では、スマホやパソコンに保存された写真・動画、SNSアカウントやネット銀行など、いわゆる「デジタル遺品」が増えています。先述のように、これらを放置すると遺族がログインできずに、大切な思い出や資産にアクセスできないなどのトラブルが起こることも多いです。
そのため、生前からID・パスワードの一覧を安全に管理したり、信頼できる遺族に引き継いだりするのは大切です。ネット銀行や証券口座などの情報は、相続の際に必要になるため、整理してわかりやすく残しておくと安心です。
エンディングノートの活用や専門の「デジタル遺品業者」を利用することで、デジタル面だけでなく、日常生活の持ち物や契約関係も整理しやすくなります。このような取り組みは、自身の安心だけでなく、残される遺族の負担を軽減する大切な備えになるでしょう。
まとめ

死亡したらすることにおいて、遺族は関連する手続きと期限が多く、大きな負担になります。突然のことで、何を優先すればよいか迷うことも少なくありません。そのような時は、手続きの優先順位を決めて、少しずつ効率よく進めることが大切です。期限が迫っているものから順に対応して、書類や期限を整理しておくと、抜けや漏れの心配を減らせます。
手続き中に不安や疑問が生じたときは、一人で抱え込まず専門家に相談しましょう。弁護士や税理士、行政書士、葬儀社、デジタル遺品業者などの専門家は、相続に関する手続きのサポートをします。遺族同士のトラブルを防ぐうえで、非常に頼りになります。遺族の心の負担を軽くして、落ち着いて手続きを進められるでしょう。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼