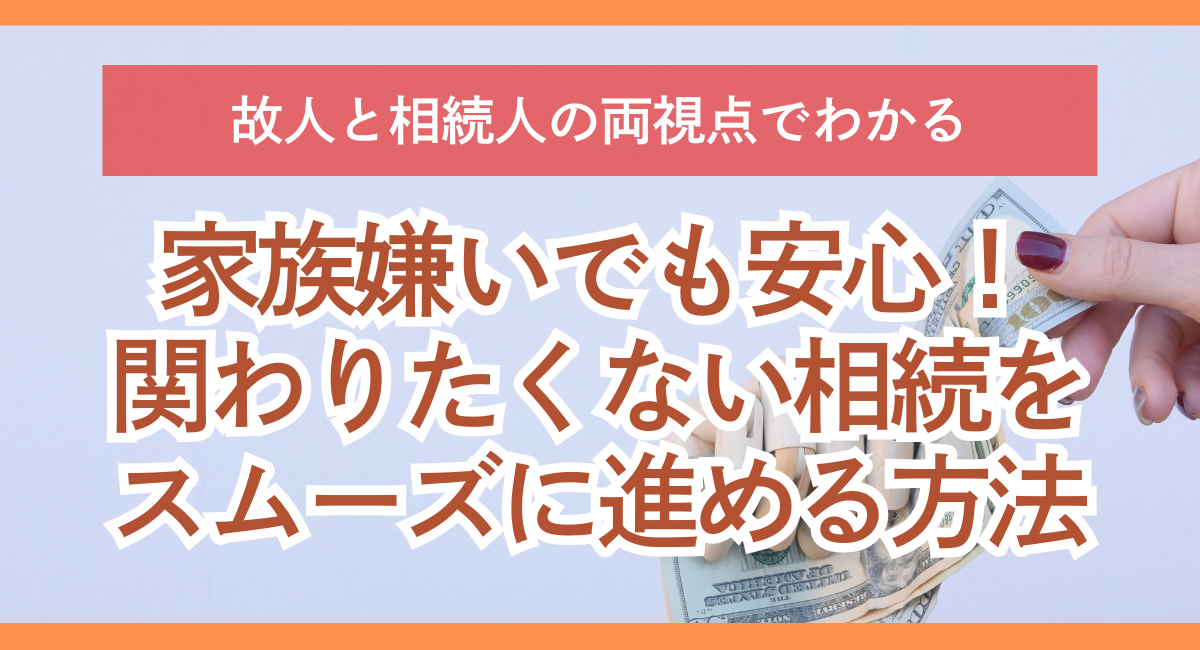家族と関わりたくない、できるだけ関わらずに相続を進めたいという声も、決して少なくありません。 相続は、法律上避けて通れないものですが、現実には「家族との関係が希薄で疎遠になっている」「過去のトラブルや不仲があり顔を合わせたくない」といった状況も多いです。
そのような場合、資産の分割や名義変更などの手続きにおいて、必要以上にストレスや心理的負担を抱えてしまうことがあります。今回の記事では、家族嫌いでも安心して相続を進められる方法を徹底解説します。遺言書を事前に準備する際のポイント、専門家に依頼して手続きを代行してもらう方法を紹介します。
デジタル遺品業者を活用して、オンライン上の資産や契約を安全に整理する流れについても、実務的な観点から詳しく解説していきます。「できるだけ家族と関わらず、トラブルを避けて相続を完了したい」と考える方は、是非最後までチェックしてみてください。
家族嫌いでも避けられない相続の課題

相続は、誰にとっても避けることのできない現実です。しかし、家族との関係が良好でない場合や、疎遠・不仲といった事情を抱えている場合、相続は単なる手続きにとどまりません。精神的な負担や、人間関係のトラブルの火種になりやすいものです。資産分割の話し合いひとつとっても、顔を合わせるだけでストレスを感じたり、意見の食い違いから、感情的な衝突に発展してしまうことも珍しくありません。
遺産をめぐって起こり得るトラブル

家族との関わりをできるだけ避けたい方にとって、相続は大きな心理的負担につながります。実際には、遺産をめぐって次のようなトラブルが起こることがあります。
- 遺産分割を巡る感情的な争い
たとえば、兄弟姉妹の間で不動産の評価額や処分方法について、意見が対立し、話し合いが激しい口論に発展することがあります。売却か住み続けるかをめぐる意見の食い違いは、修復しがたい溝を生むことも少なくありません。
- 資産隠匿の疑いによる親族間トラブル
特定の相続人が、預貯金の移動や物件の処分を事前に行っていた場合、「資産を隠しているのではないか」と疑われることがあります。実際に、国税庁による調査でも、実務上、遺産をめぐる争いの多くは不動産に関連するとされており、専門家の報告では全体の約3割を占めるとの指摘もあります。隠匿や評価額の偏りをめぐって、訴訟に至る例もあるのです。
- 遺言書がない場合の手続き長期化
故人が遺言を残さなかった場合には、全員の合意を得る遺産分割協議が必要となります。相続人の人数が多かったり、疎遠な親族が含まれていたりすると協議は難航します。場合によっては、半年〜1年以上かかる可能性が高いです。時間がかかる間に感情的な対立が深まり、解決がさらに難航化するかもしれません。
- デジタル遺品をめぐる混乱
ネット銀行口座、証券口座、暗号資産、クラウド上のデータなど、従来の相続資産にはなかったデジタル遺品の扱いが、問題になるケースが増えています。暗証番号や秘密鍵が分からず、アクセスできない場合、資産が事実上失われるリスクがあるのです。家族間で責任の押し付け合いが起きることもあります。
上記のトラブルは、利害関係だけでなく、長年の感情的な対立を表面化させやすいです。特に「家族嫌い」の人にとっては大きなストレスとなり、相続そのものが重荷と感じられる要因となっています。
心理的負担の影響

家族との関わりを避けたい方にとって、相続手続きは大きな心理的負担を伴います。「家族嫌い」という感情が強い場合、その負担はさらに増幅されるでしょう。冷静な判断や円滑な手続きを妨げる要因となります。
- 直接家族と会うことによる不快感
普段は距離を置いている家族と、顔を合わせること自体がストレスになる方も少なくありません。会話のたびに過去の確執が思い起こされて、不信感が募るケースもあります。
- 遺産分割協議での説得や圧力
協議の場では、他の相続人から特定の分割方法を迫られたり、強い口調で説得されたりする場面もあります。そのような状況では、自身の意見が言いにくく、心理的に追い詰められるケースが多いです。
- 資産内容の把握や情報開示に伴う不安
預金や不動産に加えて、ネット銀行口座や暗号資産など、見えにくい資産も増えています。全体像をつかむには、多大な労力が必要です。「他の相続人が情報を隠しているのでは」といった疑念も生じやすくなります。
相続手続きは、心理的な摩擦を引き起こす場面が非常に多いのです。そのため、事前に基本的な法律知識を身につけておくことや、相続に詳しい弁護士・司法書士といった専門家へ相談することが大切です。
また、デジタル遺品の整理に特化した業者を活用することで、オンライン資産の調査や管理を任せられます。自身が直接対応する場面が大きく減らせるのです。結果として、家族と向き合う場面や情報のやりとりを最小限に抑えて、心理的負担を軽減しながら、相続手続きを進められます。
家族と関わらず相続手続きを進める基本ルール

相続の手続きは、原則として相続人全員の合意や関与が必要となるため、家族と距離を置きたい人にとっては、大きな負担となりがちです。しかし、法律や制度を正しく理解して、専門家や第三者をうまく活用すれば、直接的な関わりを最小限に抑えながら、手続きを進めることは可能です。ここでは、家族嫌いでもなるべく接触せずに、押さえておきたい相続のルールや考え方を整理します。
法定相続人と遺産分割の基本

相続の手続きには、必ず守らなければならない法律上のルールがあるのです。特に、誰が相続人になるのか、どのように資産を分けるのかは明確に定められています。つまり、家族嫌いで関わりたくない場合や、個人的な感情だけでは避けられません。
- 法定相続人の順位
民法により「誰が相続するのか」の順位が決まっています。まず、配偶者は常に相続人になります。その上で、第一順位は子ども、子がいなければ、第二順位の親、さらにそれもいない場合には、第三順位として兄弟姉妹が対象です。家族との関わりを避けたいと思っていても、自身が法定相続人に該当する以上は、関係を持たざるを得ないのです。
- 遺産分割協議の原則
遺産をどのように分けるかは、あらかじめ定められた「法定相続分(取り分の割合)」を基準に、相続人全員で協議をして決めます。この協議は、一人でも欠けると成立しません。疎遠な親族や関わりたくない相手ともやむを得ず、話し合う必要が出てきます。感情的なしこりが残っている場合には、大きなストレスとなる場面です。
- 遺言書がある場合の優先
故人が生前に遺言書を残していた場合、その内容が優先されます。ただし、相続人の遺留分を侵害する内容は無効とされる場合があります。分割方針が明確であれば、相続人同士の衝突を最小限に抑えられます。相続手続きが、比較的スムーズに進むという利点があるのです。
このように、相続は「誰が相続人になるのか」と「どのように分けるか」が厳格に指定されています。個々の感情や人間関係の良し悪しにかかわらず、必ず進めなければなりません。家族嫌いであっても、自身が法定相続人である以上は、手続きを放置することはできず、場合によっては、不利益を被る可能性もあります。
手続きの期限と証拠の重要性

相続の手続きには法律で定められた期限や、客観的に証明できる書面を整えることが重要です。特に「家族と極力関わりたくない」という場合には、後々のトラブル防止のためにも、証拠を残す姿勢が非常に大切になります。
- 相続税申告の期限
故人の死亡後に、相続税の申告と納税を行う必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されるため、注意しなければなりません。相続税の対象になる資産があるかを早めに確認して、期限内に対応できるよう、準備することが求められます。
- 遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方を決めた場合、それを文書化した「遺産分割協議書」が必須です。この書類がなければ、銀行口座の解約や相続預金の払い戻し、不動産の名義変更を行うことができません。口頭の合意だけではなく、必ず書面で残してください。
- 資産目録の作成
相続資産を明確にするためには「資産目録」を作成しましょう。内容には、現金、預貯金、株式、投資信託、不動産などの資産です。近年においては、デジタル遺品(ネット銀行口座、暗号資産、ネット証券、電子マネー残高など)も含める必要があります。漏れがあると、税務調査や親族間の疑念につながりやすいです。
- 証拠を残す重要性
家族と関わらずに手続きを進めようとすると、他の相続人から「勝手に進めているのではないか」と疑念を持たれる場合があります。そのため、専門家へ正式な委任状を渡して、手続きを任せることが有効です。客観的な証拠を積み上げることで、後々のトラブルが避けられます。
相続においては、期限を守ることと証拠を残すことが両輪です。特に、心理的に家族と接触したくない人ほど、文書や専門家の力を活用することで、負担を軽減しつつ、安全に手続きを進められます。
【故人の視点】遺言書で家族との関わりを回避

相続人だけでなく、故人が家族嫌いで関わりたくないケースも少なくありません。距離を置きたい、関わりたくないという気持ちが強いと、相続の場面で思わぬトラブルに発展します。そのような状況を防ぐために有効なのが「遺言書」を活用する方法です。遺言書を正しく残すことで、故人の意思を明確に示し、望まない争いや不必要な接触を最小限に抑えられます。
遺言書の種類と特徴
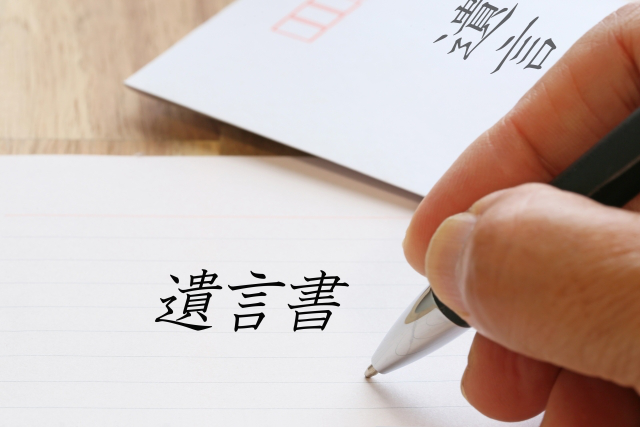
遺言書には、3つの種類があり、それぞれに特徴やメリット、注意点が存在します。
まず、自筆遺言は、自身で全文を手書きして作成するものです。費用がかからず、手軽に作れる点が大きなメリットです。一方で、日付や署名、押印などの形式に不備があると、無効になるリスクがあります。そのため、形式的な要件を正しく満たすことが重要です。
2つ目の公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら、作成する遺言書です。公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、法的にも最も効力が強いです。安全性の高い方法といえます。しかし、作成の際には公証人手数料などの費用が必要になります。
最後に、秘密証書遺言です。秘密証書遺言は、自身で遺言の内容を作成し、封印した上で、公証人に提出して本人確認を受ける形式です。内容自体は公証人に開示されません。内容を秘密にできる点に特徴があり、誰にも見られたくない場合におすすめです。
しかし、この方法でも公証人に預けるための費用がかかります。方式に不備があると、無効となる可能性もあるのです。遺言には、それぞれ一長一短があります。自身のニーズ(費用を抑えたいのか、安全性を重視するのか、内容を秘密にしたいのか)に合わせて選択することが大切です。
| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
| 自筆遺言 | 自身で全文を手書き | 費用がかからず、手軽に作成可能 | 書式不備があると、無効になるリスク |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・保管 | 法的に最も安全で確実 | 作成に公証人費用が必要 |
| 秘密証書遺言 | 封印した内容を公証人に預託 | 内容を秘密にできる | 公証人費用が必要、方式不備のリスクがある |
遺言書作成のポイント
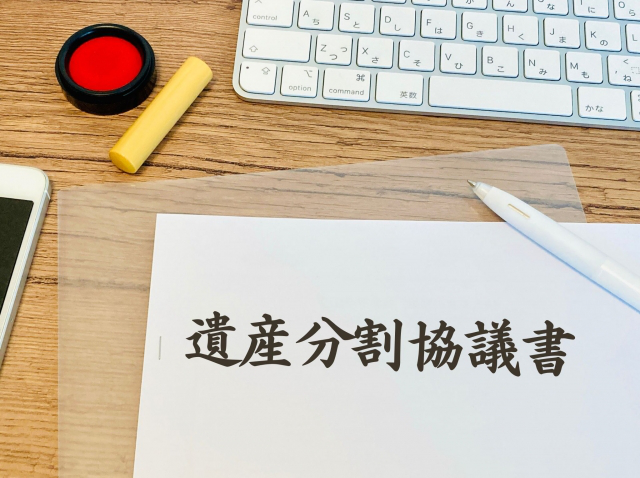
家族に一切頼りたくない、関わりたくないという人にとっても、遺言書は有効な手段です。遺言書は、家族に直接会わずに作成できます。自筆遺言なら、一人で完結できるでしょう。公正証書遺言でも、弁護士や司法書士に依頼すれば、親族と顔を合わせる必要なく、手続きを進められます。
現金や預貯金、不動産、株式といった資産をあえて家族ではなく、信頼できる友人やお世話になった人、自身の応援したい団体に遺すことも可能です。その場合も、遺言書に具体的に書き残しておけば、家族が勝手に介入する余地を封じて、自身の意思を確実に反映できます。
また、見落とされやすいのがデジタル遺品です。証券口座や暗号資産、SNSアカウント、クラウドサービスなど、家族に握られることを避けたい場合は、所在や取り扱いを遺言に明記しておく必要があります。
それによって、信頼できる友人や専門家に処理を託したり、特定の団体へ資産を残したりできます。遺言は「家族に資産を渡すため」だけの仕組みではありません。むしろ、自身の意思を最後まで貫き、資産を望む相手へ確実に託すための有効な手段になります。
故人が家族に知られずに資産を整理する方法

家族とできるだけ関わりたくない、資産のことを知られたくないという方にとって、生前の資産整理は大きな課題になります。特に「家族に一切知られずに、自身の意思で管理したい」と考える場合、方法を誤ると、相続時に不要なトラブルを招いてしまうこともあります。
そこで重要になるのが、家族に気づかれずに、安全かつ計画的に資産を整理する工夫です。信頼できる専門家や適切な制度を活用すれば、自身の思い通りに資産を整理して、望まない関わりを避けることが可能になります。
生命保険・銀行口座・不動産の整理

家族に一切の干渉を受けたくない場合には、生前から自身の意思で資産を整理する必要があります。生命保険については、受取人をあらかじめ指定しておけば、相続の場で、家族が勝手に口を出す余地を与えずに済みます。保険金は、契約に基づいて直接受取人に支払われるため、通常は相続財産とは切り離されます。ただし、受取人が『相続人』とだけ指定されている場合などは、相続財産として扱われることがあります。一定の条件はありますが、自身が望む相手へ資産を渡せるのです。
銀行口座や定期預金は、名義人の死亡後に凍結されて、家族に知られた上で相続手続きに組み込まれるのが通常です。そのため、生前のうちに整理や解約を進めて、必要であれば、信頼できる第三者や団体に資金を移しておくことが賢明です。
こうした準備を整えておけば、死後に家族に勝手に扱われることを防ぎ、望まない関与を避けられます。不動産は分割が難しく、相続時に家族と争いの火種になる可能性があります。そのような問題を避けたい場合、生前に信託を設定して承継方法を指定するか、あらかじめ贈与して、希望する相手に名義を移しておくことが有効です。これにより、家族が勝手に介入する余地を断ち切り、自身の意思通りに資産を移転できます。
デジタル遺品の整理

家族との関わりを避けたい、あるいは、疎遠なために資産やアカウントを自身で整理しておきたいというケースでは、デジタル遺品の取り扱いが大きな課題です。ネット銀行の口座やクラウドサービスの有料契約、SNSやメールといったアカウントなどは、家族がパスワードや認証手段にアクセスできなければ、死後に管理や解約が極めて困難となります。
特に、暗号資産は、秘密鍵を第三者が把握していない場合、永遠に資産を引き出せなくなるリスクがあるため、慎重な整理が欠かせません。こうしたデジタル遺品を「家族に任せたくない」「知られたくない」と考えるのであれば、自身で定期的に契約や口座を見直して、不要なものは早めに解約・処分しておくことが大切です。
しかし、専門的な知識が求められるケースや、一人での管理に限界を感じる場合には、デジタル遺品やデジタル相続に対応した専門業者や専門家を活用する方法がおすすめです。第三者に依頼することで、家族に一切関わらせずに、契約の解約やデータ整理が進められます。
デジタル遺品業者で家族トラブルを避ける
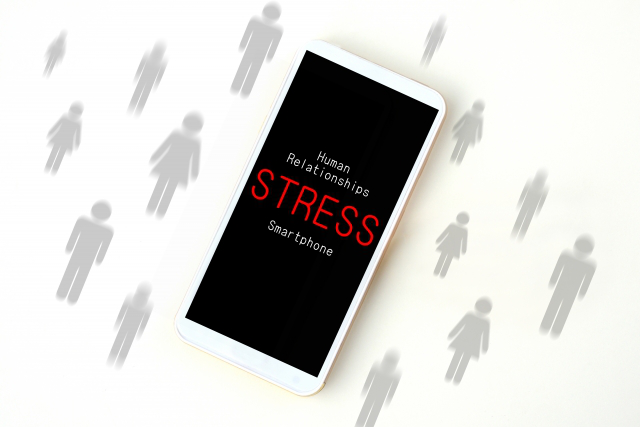
近年、スマホやパソコン、クラウドサービスなどに資産や契約情報を残したまま、亡くなるケースが増えています。これらのデジタル遺品を放置すれば、「どのサービスを契約していたのか分からない」「大切なデータが消えてしまう」「勝手にログインしてトラブルになった」など、家族の間で不要な混乱や争いを生みかねません。
特に、もともと家族との関わりを避けたいと考えている人にとっては、死後にデジタル遺品を巡って、親族が勝手に探り合うこと自体が望ましくない状況でしょう。こうしたリスクを避けるうえで有効なのが、デジタル遺品業者への依頼です。
専門の業者を活用すれば、パスワードの解析やアカウント解約、データ整理を第三者が中立的に行ってくれるため、相続人同士が直接やり取りする必要を最小限に抑えられます。つまり、残された家族に余計な口出しや干渉を許さず、自身の意思に沿った形でデジタル情報を処理できるのです。
デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、亡くなった人が生前に利用していたインターネット上のサービスや電子的な資産です。具体的には、ネット銀行や証券会社などのオンライン口座、FacebookやX(旧Twitter)、InstagramといったSNSアカウント、Google DriveやiCloudなどのクラウド契約、さらにビットコインやイーサリアムに代表される暗号資産などが含まれます。
これらは紙の遺品と異なり、存在が分かりにくく、家族がパスワードや認証情報を知らなければ、解約・継承・整理が難しいのが特徴です。そのため、デジタル遺品は、生前からの適切な管理や、引き継ぎ方法の準備が重要となります。
専門業者を活用するメリット

デジタル遺品に対応した専門業者を活用することで、さまざまなメリットがあります。まず、家族に知られずに安全に資産やアカウントを整理できるため、プライバシーを守りたい人にとって、非常に有効です。特に「家族には一切関わらせたくない」「死後に勝手に中身を覗かれるのは不快だ」という思いがある場合、第三者に依頼することで、望まない干渉を防げます。
また、パスワードが不明な状態であっても、専門的な技術を用いてアクセスやデータ抽出を行えるケースがあり、自身では解決できない問題にも対応できます。情報漏れ防止のためのセキュリティ体制が徹底されており、個人情報や資産情報が、家族を含めた外部に流出するリスクを、最小限に抑えられます。
複雑になりがちな解約・名義変更・整理の手続きを、効率的に進めてくれるため、余計な時間や手間をかけずに済むのも利点です。家族との不要なやり取りを避けて、デジタル遺品を処理したい人にとっては、専門業者の存在は大きな支えとなるでしょう。
デジタル遺品業者への依頼の注意点

デジタル遺品業者に依頼する際に、あらかじめ注意点も押さえておく必要があります。まず、作業内容に応じて、費用が大きく変わるため、料金体系を事前に確認しなければなりません。追加料金の有無や見積もりの内訳を、明確にしておくことが重要です。
また、業者ごとに対応できる分野が異なるため、どの範囲まで対応してもらえるのか(SNSアカウントの削除、暗号資産のアクセス、クラウド契約の解約など)をしっかり把握しておきましょう。将来のトラブル防止のために、遺言書やエンディングノートに、デジタル遺品の整理方針や業者の活用について明記するのもおすすめです。
| 注意点 | 内容 | ポイント |
| 費用確認 | ・作業内容に応じて、料金が大きく変動 ・追加料金の有無や、見積もり内訳を必ず確認 | ・契約前に料金体系を明確化することで、トラブル防止 |
| 対応範囲 | ・業者ごとに対応分野が異なる (SNSアカウント削除、暗号資産アクセス、クラウド契約解約など) | ・依頼する範囲を事前に把握して、ニーズに合う業者を選ぶ |
| 事前準備 | ・遺言書やエンディングノートにデジタル遺品の整理方針を記載 ・業者の活用についても明記 | ・家族間の混乱や将来のトラブルを防げる |
専門家を活用して家族と関わらず相続を進める
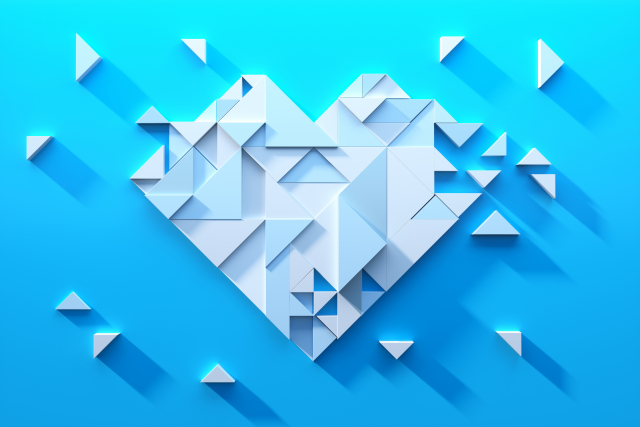
家族と関わりたくない、相続の過程で余計な摩擦や心理的負担を避けたいという場合には、デジタル遺品業者に加えて、弁護士や税理士などの専門家に依頼するのも重要です。
たとえば、弁護士に依頼すれば、遺言書の作成や遺産分割に関する法的アドバイスを受けられます。相続人同士が対立したときにも、代理人として交渉を任せられるため、本人が直接家族とやり取りする必要がありません。
司法書士は、不動産の登記や名義変更といった、専門的な手続きを正確に代行してくれるため、面倒な書類作成や、役所とのやり取りの手間がなくなります。また、税理士を通じて、相続税の計算や申告を行えば、複雑な税務処理を安心して任せられます。申告漏れや税務調査のリスクも大きく軽減できるでしょう。
このように、法的・税務的に信頼できる第三者に任せることで、家族と直接顔を合わせたり、話し合いをしたりすることなく、相続の手続きを安全に進められます。結果として、不必要な感情的対立を避けられるだけでなく、自身の意思に沿った形で資産の承継が行えます。
チェックリスト:家族と関わらず相続を進めるために

家族と関わらずに相続を進めたいと考えていても、手続きの多さや法的な制約から「どこから始めればいいのか分からない」と悩む方は多いです。感情的な摩擦を避けながら、必要な流れを確実に踏むためには、ポイントを整理して一つずつ確実に進めることが大切です。
そこでここでは、家族との接触をできるだけ減らしながら、相続手続きを進めるためのチェックリストを、故人と相続人視点の2タイプを用意しました。必要な準備や、専門家への依頼のタイミングを確認しながら進めれば、余計なストレスを抱えずに、相続を終える道筋が見えてくるでしょう。
【故人が家族と関わりたくないケース】相続手続きチェックリスト

□ 資産目録を作成
現金・預金・不動産・有価証券・保険契約・動産・デジタル遺品などを一覧化する。
※家族に知られたくない資産がある場合は、信頼できる第三者や専門業者にのみ情報を共有して、家族には開示しない方法を検討する。
□ 遺言書を作成(公正証書推奨)
相続人間の争いを避けるため、法的効力の高い公正証書遺言を用意する。
※家族に一切任せたくない場合は、友人や団体を受取人に指定することも可能である。証人も専門家に依頼すれば、家族の関与を避けられる。
□ デジタル遺品の整理
ネット銀行口座、暗号資産、クラウド契約、SNSアカウントをリスト化し、不要なものは解約・整理しておく。
※家族に中身を見られたくない場合は、デジタル遺品業者に依頼して、第三者処理を徹底する。
□ 専門家に相談(弁護士・司法書士・税理士)
・弁護士:遺言作成や紛争防止の法的サポート(家族に知られずに依頼可能)
・司法書士:不動産登記や名義変更代行(家族を介さずに委任できる)
・税理士:相続税の試算や申告サポート(家族抜きで手続きを完結可能)
□ 相続税の申告準備
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、必要書類を揃えて、税理士に依頼、または自身で申告する。
※「家族に手続きさせたくない」という場合でも、専門家を窓口にすれば、直接関わる必要がない。
□ 遺産分割協議書の作成
通常は相続人全員で作成するが、家族と関わりたくない場合は、事前に遺言や信託を整えておくことで、協議そのものを不要にできる。
【相続人が家族と関わりたくないケース】相続手続きチェックリスト

□ 相続放棄の検討
自身のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行えば、借金を含めて、一切の相続を拒否できる。
※家族と揉めるのも避けたい場合は、相続放棄で関係を断ち切るのも有効。
□ 専門家を代理人に立てる
弁護士や司法書士に依頼すれば、家族と直接やり取りせずに、手続きを進められる。
※書類の受け渡しや連絡も代理人経由にできるため、不要な接触を避けられる。
□ 遺産分割協議への対応
相続人全員で行う必要があるが、弁護士を代理人に立てれば、直接顔を合わせずに済む。
※どうしても協議に参加したくない場合は、遺産分割調停や審判に移行させて、裁判所を通じて対応する方法もある。
□ 相続財産の確認
預金・不動産・保険・有価証券・デジタル遺品などの情報を、必要最低限だけ確認する。
※「何があるのかすら家族に聞きたくない」という場合は、専門家に財産調査を依頼する。
□ 相続税・各種手続き
課税対象になる場合は、税理士に依頼して、家族に知られずに申告・納付を進める。
※不動産や口座の名義変更も、司法書士を通じて代行が可能。
□ 不要な財産やデジタル遺品の処理
相続したくない動産やデジタル遺品は、専門のデジタル遺品業者に依頼して処理する。
※家族に触られたくないデータは、特に早めに削除・解約を依頼する。
まとめ

相続は避けられない手続きですが、家族と関わりたくない場合でも、適切な準備と工夫によって、スムーズに進められます。遺言書の作成や専門家への依頼、デジタル遺品の整理といった事前の取り組みは、不要なトラブルを防ぎます。心理的な負担も軽減してくれます。
「家族嫌いだからこそ不安」という方でも、専門家や業者の力を借りれば、直接的な関わりを最小限に抑えながら、安全・安心に相続手続きが行えます。相続は一人で抱え込むものではなく、外部の力をうまく活用して乗り越えていくものだと意識することが、後悔しない解決への第一歩です。
この記事の監修者
石坂貴史

マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼