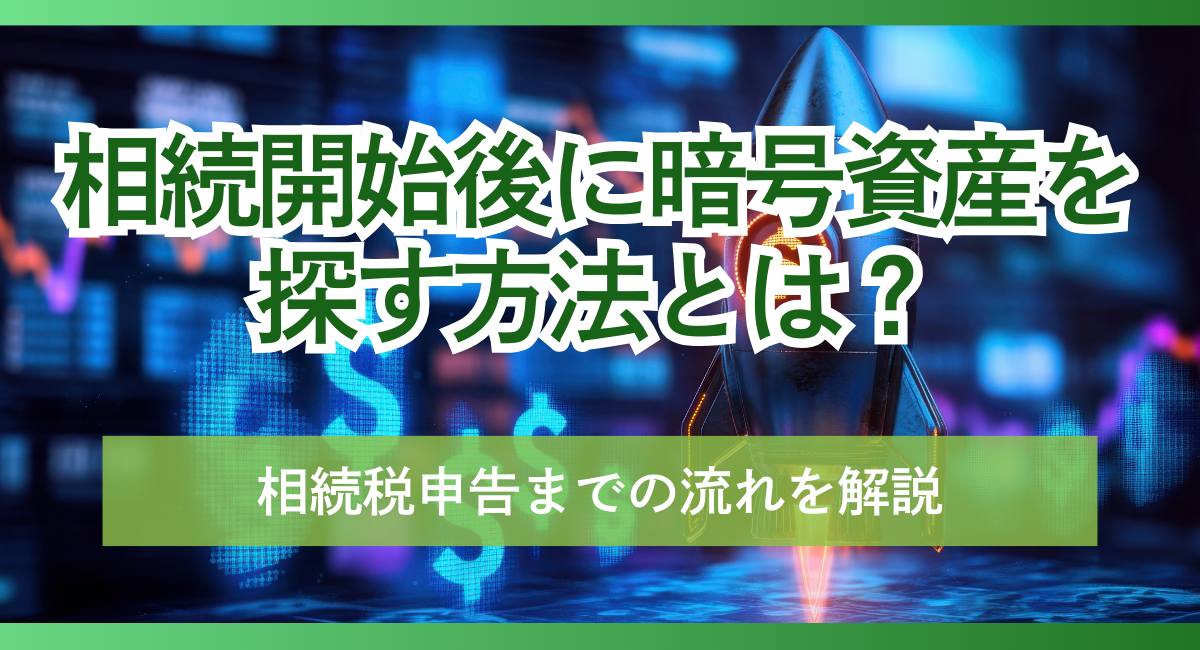近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)は投資手段の1つとして広く定着しています。
しかし、暗号資産の所有者が亡くなった場合、その存在に気づかれずに放置されるケースも少なくありません。暗号資産は預金や不動産と同じく相続財産に含まれるため、正しく把握して相続税申告を行う必要があり、見つからないまま申告してしまうと「税務調査」を受けるおそれがあります。
そこで、本記事では、相続開始後に暗号資産をどのように探すのか、具体的な方法から相続税申告までの流れ、実際の相談例を交えた注意点を詳しく解説します。
相続時の暗号資産の取り扱いとは
相続時には預貯金や現金、不動産のような財産だけではなく暗号資産や電子マネーのような現物がない資産についても相続財産に含むため、十分に注意する必要があります。本章では相続時における暗号資産の取り扱いについて詳しく解説します。
暗号資産も相続対象になる
民法上、暗号資産は金銭的価値のある財産とみなされ、現金・預貯金・株式と同様に相続財産に含まれます。相続税法上も課税対象であり、被相続人が暗号資産を生前に保有していた場合は相続開始時点の時価で評価して申告する必要があります。
暗号資産の特徴
相続財産に暗号資産が含まれる場合、暗号資産の以下の特徴をしっかりと把握しておく必要があります。
- 物理的な形がないため、発見が難しい
- ウォレットの秘密鍵や取引所のログイン情報がなければ引き出せない
- 価格変動が大きく、評価額の算定に注意が必要
このような特徴から、相続人が暗号資産の存在を知らずに放置してしまうリスクがあります。
相続開始後に暗号資産を探す方法
暗号資産は銀行口座のように通帳や印鑑が保管されている金融資産ではないため、相続人が主体的に調べる必要があります。被相続人が生前に家族に対して暗号資産の運用を知らせているとは限らないため、「生前に暗号資産は持っていなかったはずだ」と決めつけるのではなく、まずは他の相続財産と同様に探すことが大切です。
被相続人のパソコン・スマホを確認する
暗号資産の所有の有無を調べるにあたっては、まずは被相続人のパソコンやスマホなどデバイス内を調べることが大切です。
- 暗号資産取引所(例・bitFlyerやCoincheckなど)のアプリやブックマークを確認する
- 取引所からのメール通知を検索する
- ウォレットアプリやハードウェアウォレット(保管するためのデバイス)が保存されていないか確認する
確定申告書類を調べる
暗号資産を取引していれば、雑所得として申告している可能性があります。申告書や計算明細を確認すると、保有している取引所名や取引額の手がかりとなるため調べることがおすすめです。
専門家へ相談してサポートを受ける
相続時の暗号資産については、2つの相談先が挙げられます。1つはデジタル資産に強い専門家、もう1つは士業です。
①デジタル資産に強い専門家
相続時のデジタル資産の扱いについては、デバイスのロック解除などの問題が複合的に絡み合うケースが少なくありません。そこで、相続財産の調査時に暗号資産の調査やデバイス内の資産・データなどを調べるために専門業者へ依頼する方法があります。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼
②士業
士業の場合、相続時に遺産分割協議や相続税申告でサポートすることが多く、暗号資産の扱いについてもあわせて相談するケースが少なくありません。
遺産分割協議で争いがある場合などは弁護士、土地の相続登記がある場合は司法書士、相続税申告は税理士へ依頼することが多いですが、すべての士業が暗号資産の取り扱いに精通しているわけではないため注意が必要です。
相続税申告までの流れ(基礎控除を超える場合)
暗号資産を発見した場合、その他の相続財産と合わせると「相続税申告」が必要となる可能性があります。ただし、相続税申告は基礎控除を超える場合に課税されるため、まずは計算をしてみましょう。
・相続税の基礎控除 「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」
例として、配偶者と子1名が相続する場合、上記式に沿って計算すると4,200万円までは基礎控除が受けられます。
暗号資産は評価額の確定に注意
暗号資産は株式などと同様で評価が常に変動している資産のため、相続税申告時には評価額の確定に注意が必要です。相続や遺贈で取得した暗号資産は財産評価基本通達に暗号資産の評価方法が定められておらず、評価方法の定めのない財産の評価という項目を用いて評価します。
活発な市場が存在するかどうか、が1つの評価方法の目安となっており、有名な暗号資産は基本的に活発な市場があるため「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引評価」が採用されます。活発な市場がない場合は個別評価となるため注意しましょう。
評価の基準日は「相続開始日(被相続人が亡くなったことを知った日)の時価」です。
相続財産の全体像を把握する
暗号資産に限らず、現金・預金・株式・不動産などを含めて相続財産を整理します。ローンなどの債務がある場合は「債務控除」が受けられます。プラスの財産と同様に相続する必要があるため、債務も漏れなく計上しましょう。
遺産分割協議と解約
暗号資産自体は相続財産として承継できますが、日本国内の多くの暗号資産交換業者では、代表相続人の口座へ移管するか、日本円に換算して払い出す対応となります。暗号資産交換業者側は相続開始を把握した時点で口座を凍結しており、暗号資産を代表相続人の口座へ移管する、もしくは日本円に換算して送金します。
参考までに、bitFlyerでは被相続人のアカウント残高の日本円や暗号資産をそのまま代表相続人へ移管しており日本円に転換していません。
移管方法は各取引所等によって異なるため、事前に確認されることがおすすめです。
参考URL bitFlyer 相続手続きの流れについて教えてください。
相続税申告のスケジュール
- 相続開始から10か月以内に申告が必要
- 評価額を含めた申告書を作成し、税務署に提出
準確定申告のスケジュール
生前に被相続人が以下の要件に該当している場合は、準確定申告が必要となる可能性があるためご注意ください。準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から、4か月以内に行う必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超えている
- 源泉徴収されていない所得の合計額が20万円を超えている
- 給与を複数から受けていてメインの給与以外の所得合計金額が20万円を超えている
- 公的年金等の収入金額が400万円を超えている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えている
- 土地や建物を売却して受け取った譲渡所得金額が20万円を超えている
- 生命保険の満期保険金で受け取った課税対象額が20万円を超えている
暗号資産の相続時|よくあるお悩みとは
暗号資産は資産の性質上「見つけにくい」という性質があります。Goodreiでは日頃から相続後のデジタル資産調査に関するお悩みを多くお受けしていますが、暗号資産については相続時点で価格が下落していると納税資金が不足するおそれがあるため注意が必要です。本章では実際の相談例を活用しながら、よくあるお悩みをご紹介します。
相談事例:突然の事故でご主人を亡くされたケース
30代のご主人を不慮の事故で亡くされた奥様から、金融資産調査と新婚旅行の写真データ救出のご依頼を受けました。遺された最新iPhoneはパスコード不明で解除困難でしたが、旧モデルのスマートフォンは専門ツールにより解析可能で、ロック解除に成功しました。
結果、ご要望の写真や動画の一部、ネット銀行・NISA・暗号資産取引所のアプリを確認できました。しかし各サービスはSMSによる2段階認証が必要で、既に解約済みの電話番号が利用できず、資産の全容把握には至りませんでした。最終的に写真データの救出は実現しましたが、デジタル資産の詳細調査は困難な結果でした。
生前に利用サービスの一覧や緊急連絡先をエンディングノートや遺言書などに残していれば、より多くの資産解明につながった可能性がある事案です。
このように、優れた技術を生かしてもデジタル資産の特定が難しい場合があります。ただし、取引がある程度確定できたら、被相続人・相続人に関する必要書類を整えることで相続手続きが進む可能性はあります。まずはお一人で悩むのではなく、専門家へご相談いただくことがおすすめです。生前の対策については以下もご一読ください。
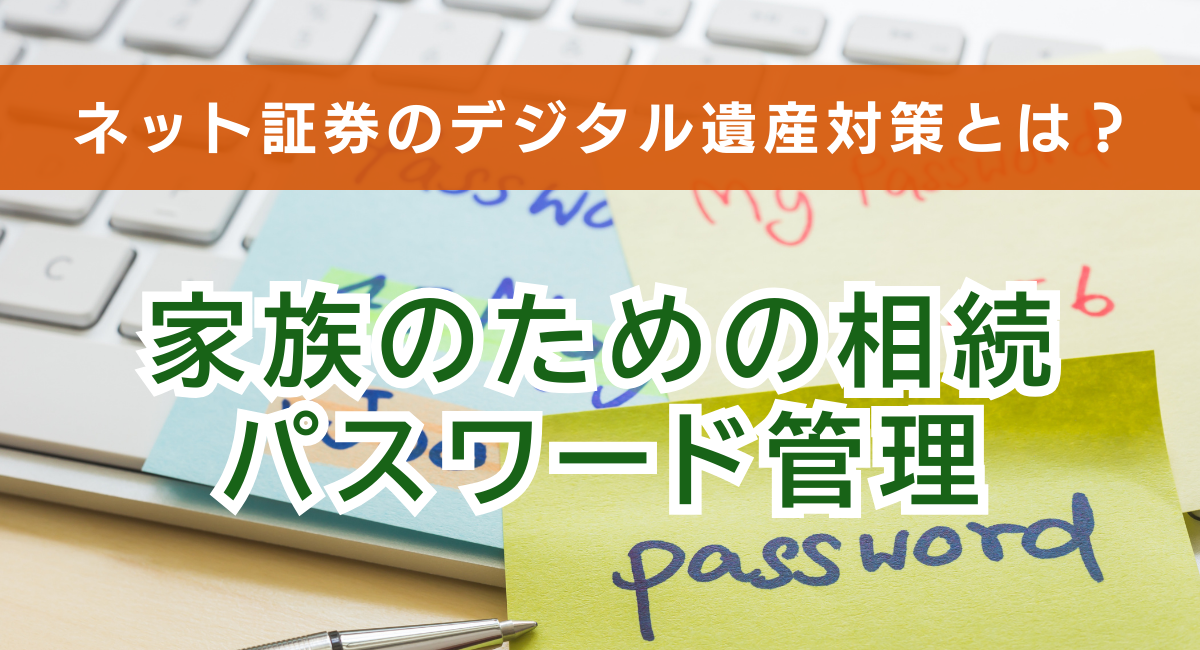
まとめ
暗号資産は形のない財産であるため、相続人が気づかずに放置されてしまうリスクが高い資産です。
相続開始後は、デバイスや確定申告書類などを確認し、存在を突き止めるようにしましょう。特に暗号資産の取引が合った場合は、準確定申告にも備える必要があります。
暗号資産の相続はまだ制度も発展途上であり、今後相続税などの評価方法も変わる可能性があります。常に情報をアップデートし、正しい理解と備えをしておくことがおすすめです。
相続後にデジタル資産に関してお悩みを抱えたら、まずはお気軽にGoodreiへお問い合わせください。