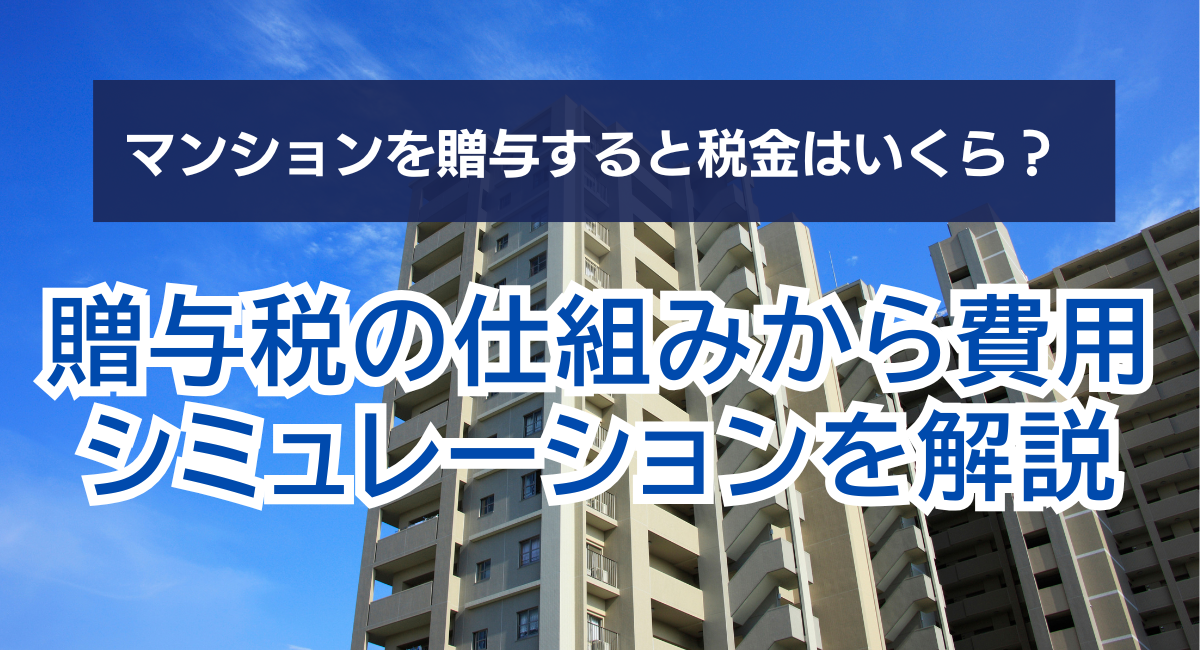親から子へマンションを譲りたいと考えたとき、多くの方が相続ではなく「生前贈与」という方法を検討します。これは、将来の相続時に発生する相続税の負担を軽減したい、あるいは早めに子どもに資産を移して活用してほしいといった思いから選ばれることが多い方法です。
しかし、生前贈与を行う際に必ず関わってくるのが「贈与税」です。不動産、特にマンションは評価額が大きくなりやすいため、単純に贈与してしまうと、数百万円から場合によっては1,000万円以上の贈与税がかかるケースもあります。
税金の負担を最小限に抑えるためには、贈与税の仕組みや控除制度、特例の活用方法などをしっかり理解しておく必要があるでしょう。
また、マンションを贈与する場合には、評価額の算定方法、名義変更にかかる登録免許税や、司法書士費用などの諸経費も考慮しなければなりません。住宅取得等資金贈与の特例や、相続時精算課税制度の活用によっても、最終的な税負担は大きく変わります。
そこで、今回の記事では、マンションを生前贈与する際の贈与税の仕組みや計算方法、具体的なシミュレーションによる税額の目安、注意点などについてわかりやすく整理します。生前贈与を検討している方が「どのような方法が自身や家族にとって最も有利なのか」を判断できるように、役立つ情報を詳しく解説していきます。
マンションを贈与するとは?

マンションを子どもや家族に贈与するというのは、単なる「名義の移し替え」ではなく、大きな財産の移転を意味します。現金の贈与とは異なり、不動産特有の評価方法や登記の手続き、さらには贈与税や登録免許税といった税金が関わってくるため、しっかりと仕組みを理解しておきましょう。そもそも「マンションを贈与する」とはどのような行為なのか、その基本的な考え方を整理することが大切です。
贈与と相続の違いとは?
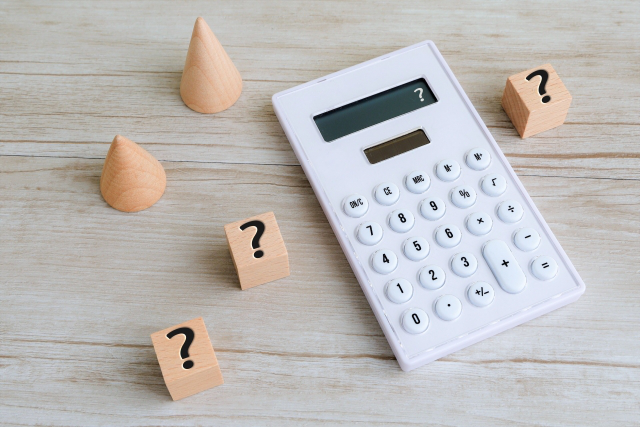
不動産を子どもや家族に引き継ぐ方法には、大きく分けて「贈与」と「相続」の2つがあります。贈与とは、財産を持つ人が生きている間に、その財産を他人に無償で譲り渡すことを言います。たとえば、親が所有しているマンションを子どもに移転する場合、生前贈与として名義変更を行えば、贈与税の課税対象です。
贈与の特徴は、タイミングを自身で決められる点にあります。将来の相続を見据えて、早めに資産を移動できるメリットがあるのです。一方で、金額が大きくなりやすい不動産の贈与は、多額の贈与税が発生する可能性があり、税制上の仕組みや特例を正しく理解して進めることが重要です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人が持っていた財産や権利を、配偶者や子どもなどの相続人が受け継ぐことを言います。こちらは「相続税」の課税対象となります。相続の場合は、法律上のルールや遺言書の内容に基づいて、財産の分配が行われるのが特徴です。
このように、贈与と相続は「生前に行うのか」「死亡後に行うのか」というタイミングの違いが大きなポイントです。贈与は、資産の移転を早められる反面、贈与税の負担が重くなる可能性があります。相続は、税制上の控除や特例が活用できる反面、遺産分割をめぐって、家族間でトラブルが起こることも少なくありません。
| 項目 | 贈与 | 相続 |
| 定義 | 財産を持つ人が生きている間に、自分の意思で無償で財産を譲り渡すこと | 人が亡くなったときに、その人の財産や権利を相続人が受け継ぐこと |
| 代表例 | 親が所有するマンションを生前に子へ名義変更して譲る | 親が亡くなった後に、遺産としてマンションを子が引き継ぐ |
| 課税対象 | 贈与税 | 相続税 |
| 特徴 | ・タイミングを自分で決められる ・将来の相続を見据えて早めに資産を移せる | ・本人の意思よりも法律や遺言に基づく分配 ・死亡を契機として財産移転が発生する |
| メリット | ・早めに資産を移すことができる ・計画的な相続対策につながる | ・相続税に控除や特例が活用できる ・一括して遺産整理ができる |
| デメリット | ・不動産は評価額が高いため贈与税が多額になる可能性がある | ・遺産分割をめぐり |
マンション贈与の一般的なケース

マンションを贈与する場面として、よく見られるのが、親が所有するマンションを子どもに名義変更するケースです。たとえば、将来の相続を見据えて、早めに資産を整理したいと考えたときに、子どもへ所有権を移しておく方法になります。
この場合、相続時の手続きが簡単になったり、子どもがすぐにマンションを活用できたりするメリットがあります。ただし、名義変更に伴う贈与税や登録免許税などの負担が発生するため、事前の準備が欠かせません。
もう一つの典型的なケースは、祖父母が孫に対して、住宅取得のためにマンションを贈与するケースです。新生活や結婚などのタイミングで行われることが多いです。この場合、「住宅取得等資金贈与の特例」や「相続時精算課税制度」などの制度を上手に活用することで、税負担を抑えながら、スムーズな資産移転が可能になります。
このように、マンションの贈与には、親子間だけでなく、祖父母から孫への支援という形もあります。どのケースにおいても、事前に制度や費用を正しく理解しておくことが、贈与を成功させるための大きなカギです。
マンションを贈与する3つの理由

マンションを贈与する背景には、単なる資産移転以上のさまざまな動機があります。相続税対策として早めに資産を分けたい、子や孫の生活を安定させたいなど、その理由は、背景や状況によって異なります。マンションのような不動産は価値が大きく、贈与のタイミングや方法によって、税負担や家族関係に大きな影響を与えるため、贈与の理由を明確にしておくことも大切です。
- 相続税の節税対策
最も多い理由のひとつが、相続税の節税を目的としたものです。相続の際に、一度に多額の財産を受け継ぐと、相続税の負担が大きくなる可能性があります。そこで、生前に少しずつ資産を分散させておくことで、将来の相続税の課税対象を減らして、結果的に、家族全体の税負担を軽減できます。不動産は評価額が高額になるため、節税効果を期待して、計画的に贈与を行うケースが多く見られます。
- 早めに資産を承継
もう一つの動機は、親が元気なうちに資産を移しておきたいという考えです。生前に贈与をしておけば、相続時に「誰がどの財産を受け継ぐのか」を明確にできます。また、贈与後も親子間で相談しながら、財産の活用方法を決められるため、親として安心感が持てるのもメリットです。
- 子や孫の生活支援
子や孫の生活を支援する目的で、マンションを贈与するケースも少なくありません。たとえば、子どもが結婚や独立を機に新しい住まいを必要としている場合や、孫が住宅を取得しようとしている場合に、マンションの贈与が大きな助けとなります。このときに「住宅取得等資金贈与の特例」を活用することで、贈与税の負担を軽減できる可能性もあります。
このように、マンション贈与には、節税・円滑な承継・生活支援という複数の目的があり、それぞれに応じた方法や制度の活用が重要です。
マンションにかかる贈与税の仕組み

マンションを子や孫に贈与する場合、必ず考えておかなければならないのが「贈与税」です。現金とは異なり、不動産には評価方法や登記の手続きが関わるため、仕組みを正しく理解していないと、予想外の税負担が発生することがあります。
特に、マンションの場合は、固定資産税評価額や路線価をもとに税額が算出されるため、実際の市場価格とは、異なる点に注意が必要です。まずは、贈与税の基本的な仕組みを押さえることが、賢い贈与の第一歩となります。
贈与税の課税方法

マンションを贈与する際に避けて通れないのが「贈与税」の課税方法です。贈与税には大きく分けて 「暦年課税」 と 「相続時精算課税制度」 の2つの制度があり、それぞれ仕組みやメリット・デメリットが異なります。
暦年課税

もっとも一般的に利用される制度で、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して課税されます。110万円までは非課税となるため、毎年少しずつ贈与することで、贈与税の負担を抑えられるのが大きな特徴です。
課税額を超えた部分に対して、10%から最大55%までの累進課税が適用されて、贈与額が大きくなるほど、税率も上がります。そのため、多額の不動産を一度に贈与する場合は、税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。
相続時精算課税制度

もう一つの選択肢が相続時精算課税制度です。これは、親や祖父母から子や孫へ贈与する際に、2,500万円までの贈与を非課税で受け取れる制度です。2024年度以降は、暦年課税との併用が一部可能となる見直しが行われています。2,500万円を超える部分については、一律20%の税率で課税されます。暦年課税と比べると、贈与時点での税負担は少額に抑えられることが多いため、まとまった資産を早めに移転したい場合に有効です。
しかし、この制度を選択すると暦年課税に戻すことはできず、将来の相続時に、贈与分を含めて精算される仕組みとなっています。そのため、長期的な相続税の負担を見据えたうえで、活用することが重要です。
このように、どちらの課税方法を選ぶかによって、贈与時の負担額や将来の相続税への影響が大きく変わります。マンションのように、評価額の大きい不動産を贈与する場合は、単純に非課税枠だけで判断せず、相続全体を見据えて制度を選択することが欠かせません。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
| 非課税枠 | 年間110万円まで非課税 | 生涯で2,500万円まで非課税 |
| 課税方法 | 110万円を超える部分に対して累進課税(10%~55%) | 2,500万円を超える部分に対して、一律20%課税 |
| 特徴 | ・毎年少しずつ贈与することで贈与税を抑えられる ・柔軟に利用できる | ・まとまった資産を一度に移転可能 ・贈与時の税負担は、比較的少額で済む |
| 注意点 | ・不動産などの大きな財産を一度に贈与すると高税率で課税される | ・一度選ぶと暦年課税に戻せない ・将来の相続時に贈与分を含めて精算される |
| 向いているケース | ・毎年計画的に贈与したい場合 ・少額ずつ資産移転したい場合 | ・マンションをはじめとした高額な資産を、早めに移したい場合 ・将来の相続まで見据えて、資金移転したい場合 |
基礎控除110万円のルール

暦年課税における大きな特徴のひとつが「基礎控除110万円」です。これは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を差し引いた残りの部分に対して、課税される仕組みになります。つまり、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は一切かからず、申告の必要もありません。
この制度を活用すれば、たとえば、毎年100万円ずつ現金を子どもや孫に贈与していけば、税負担を生じさせずに、少しずつ資産を移せます。長期的に計画して資産を承継したい場合には、非常に有効な方法といえるでしょう。
しかし、注意しなければならないのは、マンションや土地といった不動産のように、評価額が大きい資産を一度に贈与する場合です。不動産は数千万円規模になることが多く、110万円の控除を差し引いても、大部分が課税対象となってしまいます。
しかも、贈与税は累進課税が採用されており、金額が大きくなるほど、税率も高いです。最大で55%に達することもあります。そのため、高額資産の贈与を行う際には「基礎控除があるから安心」と考えるのではなく、控除を超える部分の課税負担を、十分に見込んでおくことが重要です。また、この基礎控除は「贈与を受けた人ごと」に適用されます。複数の子や孫に分けて、贈与することで、控除枠を有効に使うことも可能です。
マンションの評価額の算定方法

マンションを贈与する際に基準となるのは「評価額」です。この評価額は、市場で実際に売買される価格(時価)ではなく、税務上のルールに基づいて算定される点が重要なポイントです。まず、マンションの敷地である土地部分については、「路線価」に基づいて計算されます。
路線価とは、国税庁が毎年公表するもので、道路に面した土地1㎡あたりの価格を示しています。この路線価に、土地の面積を掛け合わせることで、土地の評価額が算出されるのです。実際の市場価格よりも低めに設定されていることが多いため、土地の評価は、実勢価格と差が出やすいのが特徴です。
マンションの建物部分の評価額は「固定資産税評価額」によって決まります。これは市区町村が、固定資産税を課すために算定している価格であり、一般的に、市場価格の7割程度になることが多いです。築年数が古い建物ほど、評価額は低くなります。そのため、新築マンションと築20年のマンションでは、同じ立地でも大きな差が生じることがあります。
このように、マンションの評価額は、「土地=路線価」と「建物=固定資産税評価額」によって定められるため、実際の売買価格とは異なります。そして、この評価額を基準に贈与税や登録免許税などが計算されるため、算定方法の違いや数値の確認が、税負担に大きな影響を与えるのです。
| 区分 | 評価基準 | 算定方法 | 特徴・注意点 |
| 土地部分 | 路線価 | 路線価 × 土地面積 で算出 | ・国税庁が毎年公表する価格 ・市場価格より低めに設定されることが多い ・実勢価格との乖離が生じやすい |
| 建物部分 | 固定資産税評価額 | 市区町村が算定した固定資産税評価額を使用 | ・市場価格の約7割程度が目安 ・築年数が古いほど評価額が下がる ・同じ立地でも築年数で大きな差が出る |
| 評価額全体の特徴 | 税務上の評価 | 土地評価額+建物評価額 | ・市場での売買価格(時価)とは異なる ・この評価額を基準に贈与税や登録免許税が計算される ・算定差で税額が数百万円単位で変動する可能性あり |
マンション贈与税の計算例

マンションを贈与する際に最も気になるのが「実際にどのくらいの贈与税がかかるのか」という点ではないでしょうか。制度や仕組みを理解していても、具体的な金額がイメージできなければ、負担の大きさや対策の必要性を実感しにくいものです。
そこで、ここでは、評価額をもとにしたマンション贈与税の計算例を取り上げて、どのように税額が算出されるのかを、わかりやすく解説していきます。贈与を検討している方にとって実際の数字を知ることは、節税対策を考えるうえで、大きなヒントになるでしょう。
マンション贈与を暦年課税で行うケース

マンションを子どもに贈与する場合、現金の贈与とは異なり、まとまった評価額がそのまま課税対象になります。高額な贈与税が発生するケースも少なくありません。特に、一度に贈与する場合は、税負担が非常に大きくなるため、事前に具体的な税額シミュレーションを行うことが重要です。ここでは、暦年課税のケースについて、簡単に紹介します。
評価額3,000万円のマンションを子どもに贈与した場合
- 課税価格:3,000万円 − 基礎控除110万円 = 2,890万円
- 贈与税率:45%(控除265万円)
- 贈与税額:2,890万円 × 45% − 265万円 = 約1,036万円
このような場合、マンションを一度に贈与すると、贈与税の負担は非常に大きくなります。分割して贈与する方法もありますが、不動産の場合は、登記や管理の手間も考慮しなければなりません。
相続時精算課税制度を活用する場合

マンションを贈与する際には、「相続時精算課税制度」を利用する方法も選択肢の一つです。この制度を活用することで、2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。それを超える部分についても、一律20%の税率で計算されるため、暦年課税に比べて税負担を大幅に抑えられる可能性があります。
- 非課税枠2,500万円まで適用
- 課税額:(3,000万円 − 2,500万円) × 20% = 100万円
暦年課税と比べると、税額が大幅に下がることがわかります。しかし、この制度は贈与者の死亡時に相続税で精算されるため、長期的な視点で計画する必要があります。
実際にかかるマンション贈与税の費用シミュレーション

マンションを贈与する際には、贈与税そのものに加えて、登録免許税や専門家への諸費用も発生します。つまり、単純に「贈与税だけを払えば良い」というわけではなく、トータルでどれくらいの負担になるのかを、事前に把握しておくことが大切です。
不動産の贈与は、金額が大きくなりやすいため、想定以上の費用が必要になるケースも少なくありません。ここでは、マンションの評価額をもとに、贈与税と手続き費用を合わせたシミュレーションを行っていきます。実際に、どの程度の出費が想定されるのかを、具体的に確認していきましょう。
贈与税以外に必要な費用

マンションを贈与する場合、贈与税以外にも、さまざまな費用が発生します。代表的なものとして、挙げられるのが登録免許税です。固定資産税評価額の2%が課税されて、所有権移転登記の際に、必ず必要となります。
また、登記の手続きや書類作成で司法書士へ依頼する場合、一般的に、5万円から15万円ほどの費用がかかるでしょう。マンションの取得に伴い、不動産取得税も発生します。原則3%ですが、住宅用家屋については特例措置により軽減または非課税になる場合があります。
一方で、居住用の住宅については、特例措置が設けられており、税額の軽減や免除が受けられることもあります。このように、マンションを贈与する際には、贈与税以外にもまとまった金額が必要となるため、事前に費用の内訳や、軽減制度を確認することが重要です。
トータル費用の試算

マンションを贈与する際に、どの程度の負担になるのかを、具体的にイメージすることは大切です。ここでは、評価額3,000万円のマンションを贈与した場合を例に、合計でどのくらいの費用が発生するのかを試算していきます。
評価額3,000万円のマンションを贈与(暦年課税の場合)
- 贈与税:約1,036万円
- 登録免許税:約60万円
- 不動産取得税:約90万円(軽減なしの場合)
- 司法書士報酬:約10万円
- 合計:約1,196万円
評価額3,000万円のマンションを、暦年課税によって、子どもに贈与するケースを想定します。まず、大きな負担となるのが贈与税です。この場合は、約1,036万円もの税額になります。これに加えて、所有権移転登記に必要な登録免許税が、評価額の2%で約60万円かかります。
また、贈与で不動産を取得したことに伴い、不動産取得税が課税されます。軽減措置を使わない場合には、3%で約90万円が必要です。これらの手続きについては、司法書士をはじめとした専門家に依頼するのが一般的になります。たとえば、司法書士の場合、報酬として平均10万円前後を見込む必要があるでしょう。
これらを合計すると、贈与税と各種費用を合わせて、総額約1,196万円となります。贈与税以外の負担も、決して無視できない金額です。マンションの贈与は、相続対策などに有効ですが、こうしたトータルコストを踏まえて、資金計画を立てることが不可欠です。
マンション贈与のメリット・デメリット

マンションを生前に贈与することには、相続税の節税や早めの資産承継といったメリットがあります。一方で、高額な贈与税の発生や、将来の相続への影響といったデメリットも存在するのです。
贈与は一度行うと、簡単に取り消すことができないため、長期的な資産計画や家族の状況を踏まえたうえで、判断することが欠かせません。ここでは、マンション贈与の代表的なメリットとデメリットを整理して、実際に贈与を検討する際に、注意すべきポイントを紹介します。
| メリット | デメリット |
| 相続税の節税につながる | 高額な贈与税負担が発生する可能性 |
| 生前に資産を承継できる | 登記費用・不動産取得税など諸費用がかかる |
| 将来の相続トラブルを回避できる | 贈与後も親が無償で住み続けている場合、形式的な贈与と判断され、相続財産とみなされる可能性があります。 |
| 贈与のタイミングや方法を工夫すれば、税負担を抑えつつ資産を移せる | — |
特例・控除を活用してマンションの贈与税を抑える方法
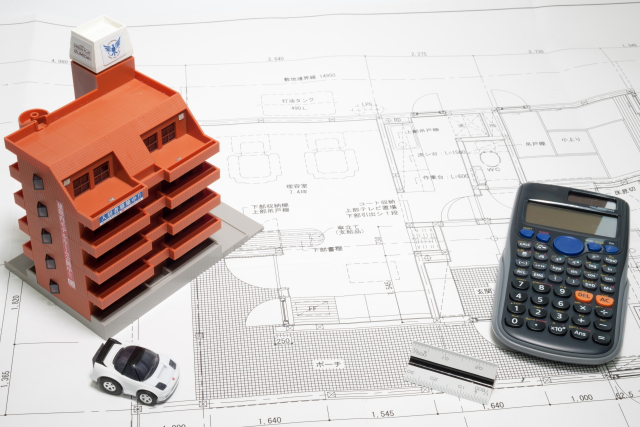
マンションの贈与では、評価額が大きくなることから贈与税の負担も高額になりやすいのが現実です。しかし、贈与税には国が定めたさまざまな 特例や控除制度があり、条件を満たせば、税負担を大きく抑えることが可能です。
たとえば、住宅取得を目的とした贈与には「住宅取得等資金贈与の特例」があり、一定の要件をクリアすることで非課税枠が拡大されます。また、先述でも説明した長期的な資産承継を前提にした「相続時精算課税制度」もあります。特例制度を組み合わせることで、贈与税の負担を大きく軽減できる場合があるのです。
| 制度名 | 内容 | 非課税枠・効果 | 主な条件 |
| 相続時精算課税制度 | 将来相続時に精算する前提で生前贈与が可能 | 2,500万円まで贈与税が非課税 | 60歳以上の親から20歳以上の子・孫への贈与など |
| 住宅取得資金の非課税制度 | 住宅建築・購入資金の贈与に利用できる制度 | 一定条件で最大1,000万円超の非課税枠 | 住宅が一定の床面積・築年数要件を満たすこと |
| 夫婦間の居住用不動産贈与の特例 | 配偶者への居住用不動産(または購入資金)の贈与 | 贈与税が非課税となる場合あり(最高2,000万円まで評価控除) | 婚姻期間20年以上の夫婦であること、居住用不動産が対象であること |
マンション贈与の手続きの流れ

マンション贈与において、手続きを誤ったり必要書類が揃っていなかったりすると、余分な時間や費用がかかるだけでなく、税務上のトラブルにつながります。そのため、事前に全体の流れを把握しておくことが非常に重要です。手続きが複雑な場合は、司法書士や税理士に依頼すると安心です。
| 手続き | 内容 | 注意点 |
| 贈与契約書の作成 | 親から子ども・孫へ贈与する旨を明記し、必ず書面として残す | 口約束では無効扱いになる可能性があるため、署名・押印を確実に行う |
| 登記の変更(名義変更) | 法務局で所有権移転登記の手続きを行う | 登録免許税が必要。書類不備があると申請が受理されない |
| 贈与税申告と納税 | 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に税務署へ申告・納税 | 期限を過ぎると加算税や延滞税の対象となるため注意 |
| 専門家への依頼 | 手続きが複雑な場合、司法書士や税理士に依頼可能 | 追加で報酬が必要だが、トラブル防止や正確な申告につながる |
贈与税をめぐる注意点

マンションを贈与する際には、贈与税の仕組みや計算方法を理解していても、思わぬ落とし穴や注意点が存在します。税務署への申告漏れや評価額の誤算、家族間での認識の違いなど、小さな見落としが後々大きな負担やトラブルにつながることも少なくありません。
| 注意点 | 内容 | リスク・留意点 |
| 名義預金や形式的な贈与と判断されないよう注意 | 実際には資金移動や所有権移転が行われていないと、贈与と認められない | 贈与税の否認や追徴課税が発生する可能性がある |
| 親が贈与後も住み続けるケース | 贈与したとされる不動産に親がそのまま住んでいると「名義貸し」とみなされる場合がある | 贈与ではなく相続財産と判断され、課税対象になるリスクがある |
| 税務署からの調査ポイントを理解し記録を残す | 贈与契約書や資金移動の証拠を整理し、書面で管理 | 調査時に説明や証明ができないと追加課税やトラブルにつながる |
マンション贈与を検討するときの相談先

マンションの贈与は、個人だけで進めると、手続きミスや税務上のトラブルが起きる可能性もあります。贈与を検討する際には、信頼できる専門家に相談することが重要です。専門家に相談することで、税負担や手続きミスを防ぎ、安心して贈与が進められます。
また、不動産と同じように見落とせないのが「デジタル資産」の整理です。ネット銀行や証券口座、クラウド上の契約情報などは、万が一の際に家族が把握できず、相続や贈与手続きが滞るリスクがあります。こうした情報を安全かつ確実に整理するには、デジタル遺品業者に依頼するのも有効です。専門業者のサポートを受けることで、目に見えない資産の漏れを防ぎ、家族間のトラブルや手続きの遅延を回避できます。
| 専門家 | 主な役割 | 相談するメリット |
| 税理士 | 贈与税や不動産取得税などの税金計算、申告書の作成・提出をサポート | 税額計算の誤りや申告漏れを防ぎ、特例制度の活用による節税が可能 |
| 司法書士 | 所有権移転登記や名義変更など、法務局での手続きを代理 | 書類不備や登記ミスを防ぎ、スムーズな名義変更が実現できる |
| 不動産会社 | マンションの適正な評価額の算定、贈与後の活用方法や市場価値の相談 | 公正な評価額をもとに贈与の計画が立てやすく、将来的な売却や賃貸運用の選択肢も広がる |
| デジタル遺品業者 | ネット銀行口座、証券口座、クラウドサービスなどのデジタル資産の整理 | 不動産以外のデジタル資産を含めた相続・贈与の全体像を把握できる |
まとめ

マンション贈与には、節税効果や将来の相続トラブル回避といった大きなメリットがあります。一方で、贈与税や登録免許税など、さまざまな費用がかかるため、慎重に計画を立てなければなりません。贈与手続きには、不動産登記や契約書作成などの専門的な知識が必要です。
そのため、不動産の贈与を検討する際は、税務や登記の専門家に、早めに相談することが不可欠です。専門家の助言を受けながら、評価額や家族構成、将来の資産計画を踏まえた最適な方法を選ぶことで、安心して贈与が進められます。マンション贈与を成功させるためには、計画的な準備と信頼できる専門家のサポートが、何よりも重要なポイントです。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼