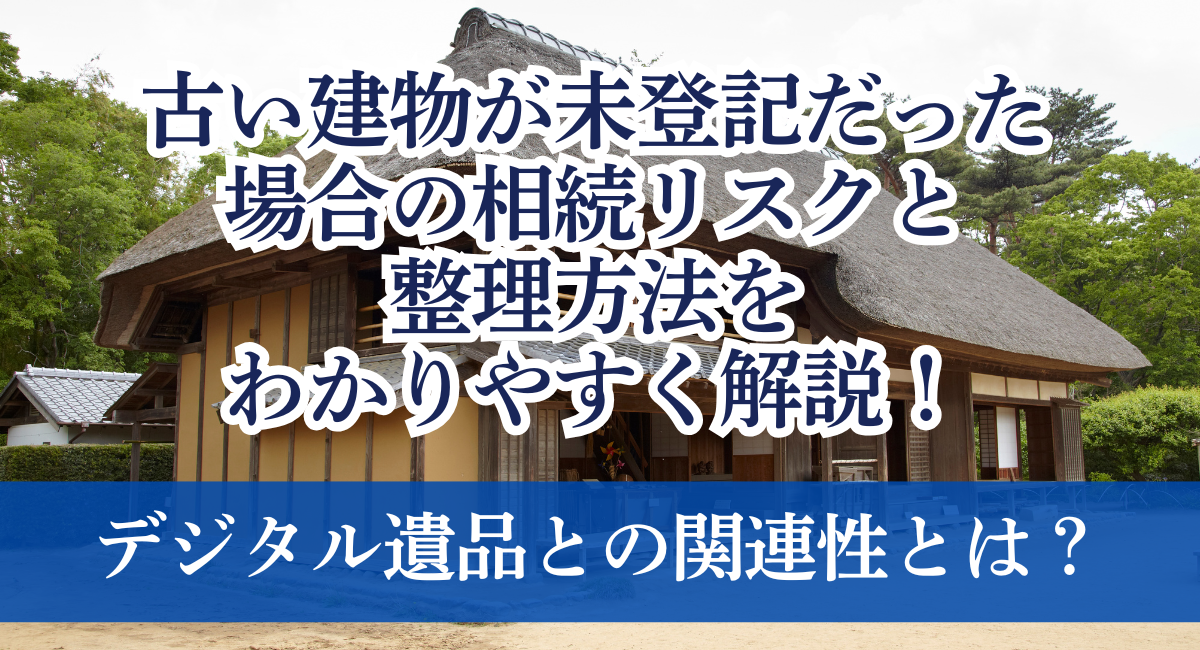古い建物の中には、長年建っているにもかかわらず、登記されていない「未登記建物」が存在します。法律上の権利関係が明確でないため、相続時に大きなトラブルの原因につながります。 現代では、不動産関連の契約書や、設計図などの資料がデジタル上に存在しているケースも増えています。
そのため、単に建物の登記だけでなく、デジタル遺品の整理も不可欠です。今回の記事では、未登記建物を相続する際の注意点や登記手続き、デジタル遺品管理との関わり、相続トラブルを防ぐ方法まで、専門家の視点を交えて解説します。
古い建物が未登記の問題点とは

日本には築年数が古く、長年にわたって登記手続きを行っていない建物が数多く存在します。一見すると、何の問題もないように見えるこれらの未登記物件ですが、法律上の所有権や権利関係がはっきりしていないため、売買や贈与、相続の場面で思わぬトラブルを招くのです。
たとえば、相続時に相続人間での権利確認が難航したり、金融機関からの融資や住宅ローンの審査が通らなかったりするケースがあります。固定資産税や贈与税など、税務面での不利益が生じる場合もあり、未登記であることは、単なる手続き上の遅れでは済まされない問題なのです。
未登記建物とは何か?法律上の位置づけ

未登記建物とは、建築されて実際に存在しているにもかかわらず、法務局における登記簿に、その所有権や所在が反映されていない建物になります。一般的に不動産である建物や土地は、登記を行うことで所有権や賃借権といった権利関係を第三者に明示できます。
しかし、古い建物や農村部の古家などの中には、建築後も登記を行わずに、そのまま使用されているケースがあるのです。これが「未登記建物」です。建物の所有権は登記によって生じるのではなく、建築された事実によって発生します。登記は第三者に対抗するための手続きであり、未登記でも所有権自体は存在します。
未登記建物がもたらす相続上のリスク

古い建物が未登記のまま残っている場合、相続の際にはさまざまなリスクが生じます。登記簿に記録されていないことで、誰が正確に所有権を持つのかが不明確になり、相続人間でのトラブルの原因につながります。具体的に、どのような相続上のリスクがあるのかを整理して、未登記建物が抱える問題点を詳しく見ていきます。
- 相続人間のトラブル
未登記建物は登記簿に記録がありません。「誰が所有しているのか」「相続分はどれくらいなのか」が明確でなくなります。兄弟間で「自身が建物を管理してきたから権利がある」と主張しても、法的には証明が難しく、争いに発展する可能性があります。
- 売却や担保設定が難しい
未登記建物は法律上の証明が不十分なため、金融機関は担保として認めない場合があるのです。その結果、資産を売却したりローンの担保にしたりすることが困難になります。
- 固定資産税や評価額の不明瞭さ
未登記建物であっても、市町村の固定資産課税台帳に登録されれば固定資産税の課税対象となります。しかし、登記簿が存在しないことで正確な評価額の算定が難しく、相続税申告時に問題が生じる場合があります。
| リスクの種類 | 内容 |
| 相続人間のトラブル | 登記簿に記録がないため、所有者や相続分が不明確になり、相続人同士で争いが発生しやすい |
| 売却・担保利用の困難 | 法的証明が不十分なため、金融機関から担保として認められず、売却やローンの担保設定が難しい |
| 固定資産税・評価額の不明瞭さ | 登記がないままでも課税対象だが、正確な評価額を出しにくく、相続税申告で問題が生じる可能性がある |
未登記建物を相続するときの注意点

未登記建物を相続する際には、通常の不動産と比べて、手続きが複雑になりやすいです。登記簿に記載がないため、まずは「その建物が確かに存在して、故人が所有していた」という事実を証明する必要があります。
証明資料を揃えたうえで、相続人同士の合意をきちんと形成しておかないと、後に相続登記や利用方法をめぐって、争いが生じるリスクも大きくなります。そのため、未登記建物を相続する場合は、必要書類の確認と、相続人間での権利関係の調整が特に重要です。
相続手続きで必要な書類と調査のポイント

未登記建物を相続する場合、先述のように、通常の登記済み不動産の相続と比べて「建物の存在自体」を証明することが大きな課題です。登記簿に記録されていないため、建築確認済証や工事記録、固定資産税の納付書といった客観的な資料を揃えなければなりません。
故人がその建物を所有していたことを、裏付ける必要があります。相続人間で権利関係を明確にして、事前に合意形成をすることで、後々の登記や財産分割におけるトラブルを回避できます。
| 確認事項 | 内容 | 必要となる書類・資料 | 目的・留意点 |
| 建物の存在証明 | 登記簿に記載がないため、客観的資料で存在を示す必要がある | 建築確認済証(あれば)、工事記録、設計図 | 建物が実在し、被相続人の所有であったことを裏付けるため |
| 所有関係の裏付け | 誰が所有していたかを客観的に明確にする | 固定資産税納付書 | 税の納付者が被相続人であることを示すことで所有権を証明しやすくなる |
| 相続人間の権利確認 | 相続人全員で権利関係を共有し、トラブルを防止 | 相続関係説明図 | 相続人の範囲を明確にし、遺産分割協議の基礎資料となる |
| 合意形成 | 相続人全員の合意を得る | 遺産分割協議書(必要に応じて) | 後日の争いを避け、円滑な登記・財産分割につなげることができる |
評価額や固定資産税の扱い

評価額を算定する際には、建物の面積や築年数、建物の状態、立地条件などを正確に把握することが重要です。これらの情報をもとに、固定資産税評価額や相続税評価額を算出する必要があります。しかし、登記簿に情報がない分、自己判断で評価すると誤差が生じやすく、税務上のトラブルにつながる可能性もあります。
そのため、場合によっては、税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼して、正式な評価額を算定してもらうことが安心です。専門家による評価を受けることで、相続税申告や資産管理の際に、正確かつ適切な対応が行えます。将来のトラブルを未然に防げるでしょう。
相続放棄や限定承認を検討すべきケース

相続財産の中に古い未登記建物が含まれている場合、その扱いには注意が必要です。未登記建物は、すでに老朽化が進んでいて、修繕費や維持費がかかるうえ、登記を行わないと売却や担保利用ができません。相続後に思わぬ負担となることがあります。倒壊の危険性があれば、管理責任を問われる可能性もあるでしょう。そのため、相続人が必ずしもプラスの財産を得られるとは限りません。
こうしたケースでは、相続放棄や限定承認といった制度を検討することが有効です。相続放棄を選択すれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、老朽化した未登記建物や関連費用の負担から解放されます。一方で、「限定承認は、相続した財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ制度で、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。仮に負債が財産を上回っていた場合でも、自身の財産から補填する必要がありません。
これらの選択肢をうまく活用することで、予想外の債務や修繕コスト、管理上のトラブルを回避して、相続によるリスクをコントロールできます。未登記建物がある場合は、事前にその状態と費用負担をよく調べたうえで、相続方法を慎重に検討することが重要です。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
| 引き継ぎ範囲 | プラスもマイナスも一切引き継がない | 相続財産の範囲内でのみ、負債を引き継ぐ |
| 効果 | 遺産や負債の両方から完全に解放される | 負債が財産を超えても、自身の財産から補填が不要 |
| メリット | 老朽化した未登記建物や費用負担から解放される | プラスの財産を残しつつ、リスクを限定できる |
| デメリット | プラスの財産も一切相続できない | 手続きが複雑で、相続人全員の合意が必要 |
| 相続の場面 | 未登記建物や負債など「負の財産」が明らかに多い場合 | プラス財産もあるが、負債リスクも存在する場合 |
デジタル遺品業者との関わり

近年では、不動産に関連する資料や情報が紙だけでなく、クラウドやメール、PDFなどのデジタル形式で残されていることが増えています。設計図や契約書、建物の修繕記録、写真データ、住宅ローンや保険関連の書類など、相続や登記手続きに必要な情報は多岐にわたります。
しかし、こうしたデジタル遺品は、複数の端末やサービスに分散しており、家族だけで整理・管理するのは非常に手間がかかります。場合によっては正確に把握できないことも少なくありません。
そこで活用したいのが、デジタル遺品業者です。専門業者は、正規の手続きや相続人の同意のもとで、必要なデータの整理を支援します。未登記建物に関わる手続きを一元管理することで、相続人間で情報格差が生じにくくなり、相続手続きの円滑化やトラブル防止にもつながるでしょう。
不動産に関連するデジタル遺品の整理

不動産に関連する資料が紙だけでなく、デジタル形式で存在するケースが増えています。登記に必要となる設計図や売買契約書、火災保険・地震保険といった契約情報まで、クラウドサービスやメール添付ファイル、PDFファイルで残されていることも多いです。これらのデジタルデータを、適切に整理しないまま相続が始まると、相続の場面において、重要な情報を見落としてしまう恐れがあります。
こうした課題に対応するのが、デジタル遺品業者の役割です。デジタル遺品業者は、故人のPC・スマホ・クラウド・外部記録媒体などに保存された各種ファイルを安全に抽出・整理します。これにより、未登記建物に関する契約資料や修繕記録などを正しく把握できるのです。
古い建物が未登記だった場合の相続リスクに対しては「登記による権利関係の確定」と「デジタル遺品の整理」を組み合わせることが重要です。紙の資料とデジタル資料の両面を整えておくことで、家族が迷わず相続手続きを進められます。無用なトラブルや時間的負担を、大きく減らすことができるのです。
家族だけでは難しい情報整理のサポート

未登記建物に関する権利関係や契約記録は、紙の書類だけに限らず、今ではPCやスマホなど、複数の場所に分散して存在していることが少なくありません。相続が始まった際、これらの情報を家族だけで探し出そうとすると、どの端末にどのようなデータが残っているのか分からず、重要な契約書や修繕履歴などを見落としてしまう危険性があります。
こうした状況で、おすすめなのがデジタル遺品整理の専門業者です。専門業者は、故人が利用していた端末やクラウドサービスに安全にアクセスできるよう、パスワード管理やアクセス権の調整を行いながら、効率的に情報を抽出・整理します。
抽出されたデータを相続手続きに役立つ形で、整理して提供してくれるため、未登記建物の事後登記や資産評価、契約の解約や更新といった手続きをスムーズに進められます。家族だけでは対応が難しい「デジタルに分散した情報の整理」を専門的にサポートするのがデジタル遺品業者の特徴です。未登記物件を含む不動産相続の現場でも、大切な役割を果たしています。
| 項目 | 内容 |
| 情報の所在 | 紙の書類に加えて、PC・スマホ・クラウド・メール・外部HDDなどに分散 |
| 問題点 | どこに何があるか分からず、契約書や修繕履歴を見落とす危険がある。パスワードなどでアクセスできないケースも多い |
| 解決手段 | デジタル遺品整理業者を活用する |
| 業者の役割 | パスワード管理やアクセス権調整を行い、安全・効率的に、情報を抽出・整理する |
| 整理の効果 | データを相続手続きに役立つ形で提供して、登記や資産評価、契約解約、更新を円滑化させる |
未登記建物の登記・整理方法

古い建物が未登記のまま放置されていると、思わぬトラブルにつながります。登記がされていない建物は、法務局の登記簿に反映されないため、第三者に権利を主張することが難しくなるケースがあります。相続人同士の合意形成や売却・活用の妨げになることも多いです。先述の説明の通り、不動産に関連する資料や情報は、紙だけでなくデジタルデータとして残されている場合も多いため、「未登記建物の整理」と「デジタル遺品管理」を合わせて考えなければなりません。ここでは、未登記建物の登記・整理方法と、相続時に直面するリスクについて紹介します。
事後登記の手順と必要書類

未登記建物とは、建物を新築・増築した際に、法務局への登記が行われていない状態を指します。こうした未登記建物がある場合、そのままでは資産として正式に認められず、相続や売却の際に手続きが複雑になるのです。そのため、相続のタイミングで事後登記を行い、建物の権利関係を明確にしておくことが重要です。
事後登記を行うためには、さまざまな必要書類を揃える必要があります。代表的な書類としては、次のようなものがあります。
- 建築確認済証(可能な場合)
- 固定資産税納付書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 建物調査報告書(土地家屋調査士が作成)
上記の書類をもとに、法務局へ登記申請を行いましょう。書類の内容や建物の状況によっては、追加資料が必要になる場合もあります。たとえば、古い建物で建築確認資料が残っていないケースも多く、その場合は、土地家屋調査士による現地調査や、建物図面の作成が必要です。
実際の登記申請手続きでは、専門知識が求められる場面も多いため、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に、依頼することがおすすめです。専門家に相談することで、必要書類の不備や申請書の記載ミスによる却下を防ぎ、円滑に登記を完了させることができます。
| 項目 | 内容 |
| 未登記建物とは | 建物を新築・増築したのに法務局で登記されていない状態 |
| 問題点 | 登記がないと資産として正式に認められず、相続・売却時に手続きが複雑になる |
| 基本対応 | 相続のタイミングで事後登記を行い、権利関係を明確化することが重要 |
| 主な必要書類 | ・建築確認済証(あれば) ・固定資産税納付書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続関係説明図 ・建物調査報告書(土地家屋調査士作成) |
| 書類不足時の対応 | 建築確認資料がない場合は、土地家屋調査士による現地調査・建物図面作成が必要 |
| 専門家の関与 | 司法書士・土地家屋調査士に依頼することで、不備や記載ミスによる却下を防ぎ、円滑化できる |
| 登記を怠った場合のリスク | 相続人間で共有状態が曖昧になり、売却・担保・再建築などに支障が出る |
| 登記の意義 | 相続を契機に正式に登記することで、資産として整備して、将来のトラブルを回避できる |
専門家に依頼するメリット(司法書士・土地家屋調査士)

司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼することは、未登記物件の整理や相続登記を行う際に大きなメリットをもたらします。未登記のまま放置された建物で、正確かつ円滑に手続きを進めるためには、専門家の知識と経験が欠かせません。
まず、司法書士や土地家屋調査士に依頼することで、正確でスムーズな登記手続きが可能になります。特に、土地家屋調査士は、建物の現況を調査して、図面や調査報告書を作成するプロであるため、未登記建物をきちんと登記簿に反映するための実務を、確実に進められます。相続税評価や権利関係の整理サポートが受けられる点もメリットです。
未登記の建物は、固定資産税や相続税の評価額と結びついているため、正しく資産を把握することが、相続税申告にも直結します。司法書士は、法律面から権利関係を整理して、持分比率や名義の明確化を支援するため、将来の法的リスクが避けられます。
相続人間の合意形成に関するアドバイスも、専門家の重要な役割です。相続に関しては、感情的な対立や認識の違いが生じやすく、不動産のように分割しにくい資産では、トラブルが発生する可能性が高いです。司法書士は、法的に適切な遺産分割方法を提示して、土地家屋調査士が、現地調査に基づいた事実を示すことで、相続人全員が納得しやすい相続手続きになります。
このように、古い建物や未登記の物件整理を、専門家に依頼することは、単純な登記情報の補正にとどまりません。相続税・権利関係の把握から、相続人同士の合意形成まで、幅広いサポートが受けられます。結果として、家族が安心して相続手続きを完了できるだけでなく、将来の財産管理や資産活用においても、安定した基盤が築けるのです。
| 項目 | 内容 |
| 専門家に依頼する理由 | 未登記物件の整理や相続登記を、正確かつ円滑に進める上で、知識と経験が必要になる。 |
| 登記手続き | ・土地家屋調査士:現況調査、図面・報告書作成、未登記建物を登記簿に反映させる。 ・司法書士:法律面から登記申請を代行、書類不備やミスを防止する。 |
| 相続税評価への影響 | 未登記建物の有無が固定資産税・相続税評価額に直結する。正確な資産把握で適切な申告が可能になる。 |
| 権利関係整理 | 司法書士が持分比率・名義を明確化し、将来の法的リスクを回避する。 |
| 相続人間の調整 | ・司法書士:法的に適切な遺産分割方法を提示する。 ・土地家屋調査士:現地調査の事実に基づき、相続人同士の納得へと導く。 |
| 総合的な効果 | 相続税対応・権利関係整理・合意形成を支援。安心して相続手続きが完了できる。 |
| 将来的なメリット | 財産管理や資産活用において、安定した基盤を構築できる。 |
相続時の登記トラブルの事例
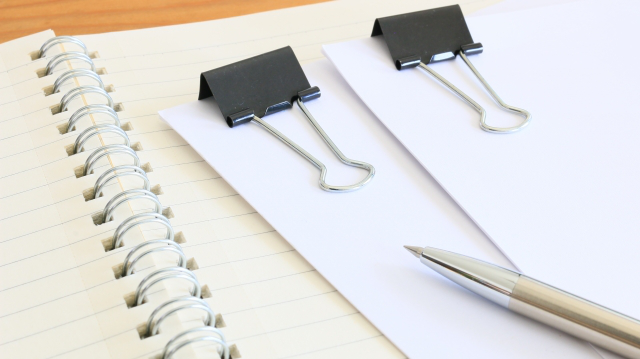
相続の場面では、未登記建物を放置していたことが原因で、さまざまなトラブルが実際に起こり得ます。たとえば、父名義の古い家屋が未登記のまま残されていたケースでは、相続が発生した後に、兄弟の一人が「自身が住んでいたから自身のものだ」と主張しました。しかし、他の相続人は「遺産だから公平に分けるべきだ」と反発したのです。所有権をめぐる争いに発展して、遺産分割協議が長期化してしまいました。
別の事例では、老朽化した未登記の家で雨漏りが発生しており、修繕費用を誰が負担するのかで兄弟間に意見の食い違いが生じました。「住んでいる人が払うべきだ」という意見と「共有財産なのだから、全員で負担すべきだ」という意見がぶつかり、家族関係が悪化したのです。
その他の事例では、相続人の一人が、事業資金を調達するために実家を担保に入れようとしたものの、建物が未登記の状態でした。そのため、金融機関から担保として認められず、融資を受けられなかったのです。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前のうちに登記を済ませて、権利関係を整理しておくことが効果的です。「デジタル遺品管理サービス」も普及しつつあり、相続時に必要な情報を迅速に確認できる仕組みとして注目を集めています。
未登記建物を相続するリスクは、法律的な権利の曖昧さだけでなく、家族間の合意形成や資産活用、税務処理にまで影響を及ぼします。しかし、登記手続きと情報整理をあらかじめ行っておけば、こうした問題を未然に防ぎ、スムーズで安心な相続が実現できます。
| 登記トラブルの事例 | 内容 |
| 所有権争い | 父名義の古い家屋(未登記)の名義変更をせず放置。父の死後、兄弟の一人が「自分が住んでいたから自分の物だ」と主張した一方、他の相続人は「遺産だから分割対象だ」と反発。結果として、遺産分割協議が長期化。 |
| 修繕費用トラブル | 未登記で老朽化した家の雨漏りが発生。修繕費用の負担で兄弟間で対立。「使っている者が払え」「共有財産だから皆で負担すべきだ」と意見が割れて、関係が悪化。 |
| 担保として利用できない問題 | 相続人の一人が事業資金を得るため、実家を担保に融資を受けようとしたが、建物が未登記。金融機関から正式な担保として認められず、融資が不可能に。 |
| 遺産分割協議の混乱 | 祖父の残した古い家が未登記のまま、相続人に引き継がれたケース。誰が所有者か明確でなく、「共有なのか」「一人に譲るのか」でもめて協議がまとまらず、相続登記も進まないまま、数年が経過。 |
| 税務トラブル | 未登記物件の固定資産税通知が誰宛てになるか不明確で、納税義務について、相続人間で押し付け合い。相続税申告をする際も、評価額の調整が難航して、税務署への提出が遅れた。 |
相続とデジタル遺品管理を組み合わせた安心な整理方法

相続の手続きでは、不動産や預貯金といった目に見える財産だけでなく、近年はデジタル遺品の整理も、避けて通れない課題です。古い建物が未登記のまま残されている場合、相続人間での分配や活用に大きな支障をきたす恐れがあります。
建物の契約書類や重要な資料が、紙とデジタルに分散して存在するケースが増えており、情報の管理不足が、そのまま相続トラブルを招く要因になっているのです。安心して整理を進めるためには、未登記建物の登記・整理方法とデジタル遺品管理をあわせて行うことが重要です。ここでは、デジタル遺品管理にスポットを当てて、リスクと解決策について解説します。
資産の「見える化」で相続をスムーズに

資産の「見える化」を行うことで、相続手続きは格段にスムーズになります。未登記建物だけでなく、デジタル上に残る契約書や設計図、修繕記録、写真データ、ローンや保険関連の資料なども整理することで、相続資産全体を把握できます。
こうしたデジタル遺品の管理を含めた資産整理により、相続人間での情報格差が生まれにくくなり、遺産分割や手続きの際に生じやすい誤解や、トラブルを未然に防ぐことが可能です。また、デジタル情報を整理・可視化しておくことで、後から必要な書類や証拠を探す手間も減ります。
相続手続き全体の負担を軽減できるのです。専門家の支援を受けながら、紙・デジタル両方の資産を一元的に整理することが、安心して資産を次世代に引き継ぐための、重要なステップとなります。
デジタル遺品業者が果たす役割

デジタル遺品業者は、相続や資産整理において、重要なサポートを担います。故人が使用していたスマホやPCに残された電子データの抽出と整理を行い、必要な情報を確実に取り出せるようにします。
司法書士をはじめとした専門家だけでなく、デジタル遺品業者による調査を加えることで、未登記建物や、複雑な資産構成を含めた資産全体が「見える化」できるのです。専門家の力を借りながらデジタル遺品を整理することは、現代の相続準備において、欠かせないステップになります。
| 項目 | 内容 |
| デジタル遺品業者の役割 | 故人のスマホやPCに残された電子データを抽出・整理し、必要な情報を取り出せるようにする |
| 専門家との連携 | 法律や登記の専門家に加えて、デジタル遺品業者の調査を組み合わせることで、情報が網羅的に把握できる |
| 効果 | 未登記建物や複雑な資産を含めた資産全体を「見える化」する |
| 専門家に依頼する意義 | 相続準備において不可欠なサポートであり、安心かつ円滑な手続きを支える |
まとめ

古い建物の未登記は、相続の場面で大きなトラブルや不要な争いを招く可能性が高いです。そのまま放置しておくことは、非常に危険で思いがけない問題を招くかもしれません。しかし、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に加えて、デジタル遺品業者のサポートを活用することで、登記手続きや資産の整理が、安全かつ確実に進みます。
紙の書類だけでなく、クラウド上やデジタル形式で残る資産も含めて、整理・可視化することで、相続人同士の不満や亀裂も、大きく減らせるでしょう。事前に資産の現状を把握しておくことで、遺産分割の判断や手続きが迅速に行えるため、相続全体の負担を軽減できます。古い建物の未登記の資産整理は、将来のトラブルを避けるための重要な準備です。早めに専門家に相談することが、家族の安心につながります。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼