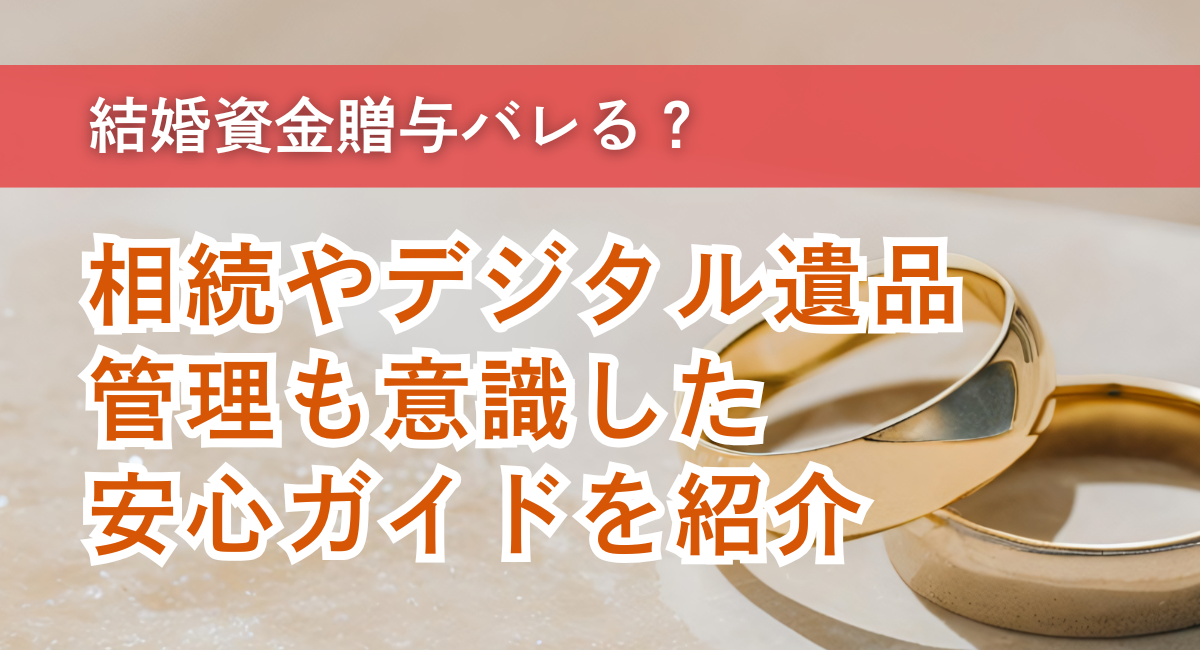親から子へ「結婚のお祝い」として資金を贈ることは、日本の家庭でもよく行われることです。現在は国の制度を活用すれば、一定額までは非課税で贈与することもできます。しかし一方で、「税務署にバレてしまうのでは?」「将来の相続でトラブルにならないだろうか」と不安に感じる方も少なくありません。
さらに、銀行振込や電子マネーなど、デジタルでのやり取りが増えているため、証拠としてデータが残りやすい点にも注意が必要です。今回の記事では、結婚資金贈与がバレる理由、安心して行うための方法、相続におけるリスク、そしてデジタル遺品管理の重要性について、わかりやすく解説していきます。
結婚資金贈与がバレる仕組みとは?

結婚資金として親や親族から大きなお金を受け取ると、「贈与」として税務の対象になることがあります。見た目には内緒でも、銀行の入出金記録や支払いの履歴、税務署の調査などを通じて、資金の出どころが明らかになることが多いです。無申告だと、追徴課税や加算税のリスクが生じます。
贈与税の仕組みと申告義務

親や祖父母からお金をもらった場合、その年に受け取った合計額が110万円を超えると、贈与税の申告が必要になります。逆に110万円以内であれば、申告は不要です。
また、「結婚や子育てのための資金」としてもらう場合は、条件を満たせば、一定額まで非課税になる特例制度があります。非課税にするには、税務署へ申告して書類を出すことが必要です。
贈与税がかかる例
- 父 → 長男に500万円贈与した場合
→ 500万 − 110万 = 390万円が課税対象 - 母 → 長女に200万円贈与した場合
→ 200万 − 110万 = 90万円が課税対象
「もらったことを言わなければバレないのでは?」と思うかもしれません。しかし、申告しないまま贈与が発覚すると、追徴課税(本来の税金に加えて追加の税金)や無申告加算税・延滞税がかかり、結果的に大きな負担になります。特に、高額な贈与は、税務署のチェック対象になりやすいので、注意が必要です。
金融機関の記録で見える贈与

銀行振込や現金取引、さらには電子マネーやオンライン送金など、今日のあらゆる金融取引は、ほぼすべて記録として残っています。金融機関は、取引データを保存しており、税務署は必要に応じて、これらの情報を照会できます。大きな金額の贈与は、自然と監視対象になるのです。結婚資金のようにまとまった金額が動く場合は、その履歴が明確に残るため、「隠し通す」のが難しくなります。
- 銀行の振込明細:振込元と振込先、金額、日時が明確に記録される
- ネットバンキングの取引履歴:オンライン上で行った送金や引き出しもすべて残る
- 電子マネー・QR決済の送金履歴:キャッシュレス決済の利用履歴も金融機関や決済事業者に保存される
これらの記録は、単に日常的な管理にとどまらず、税務署の調査や将来の相続時にも「証拠」として利用されることがあります。たとえば、相続が発生した際に「長男だけが親から結婚資金をもらっていたのではないか?」と兄弟間で不公平感が生じた場合、過去の金融取引記録を根拠として、議論が展開されるケースも多いです。
「現金で渡したから大丈夫」「電子マネーだからバレない」といった考えは通用せず、どの方法であっても、取引の痕跡は残り続けます。結婚資金の贈与を受ける場合には、こうした実態を理解したうえで、正しい申告や非課税制度の利用を行うことが重要です。
| 記録の種類 | 記録される内容 | 活用されるシーン | 注意点・ポイント |
| 銀行の振込明細 | 振込元、振込先、金額、日時 | 日常的な取引確認、税務調査、相続時の証拠 | 現金ではなく銀行を経由する限り必ず証拠が残る |
| インターネットバンキングの取引履歴 | オンライン送金や引き出し履歴 | 税務署の調査、資産管理、相続時の確認 | 電子的に履歴が残る |
| 電子マネー・QR決済の履歴 | キャッシュレス決済の利用履歴 | 金融機関・決済事業者が保存して、調査や相続時に利用可能 | 「電子マネーだからバレない」というわけではない |
| 取引記録全般 | 金銭授受の痕跡 | 相続時(例:長男だけが資金援助を受けたなど不公平感)、税務署調査 | 贈与では、正しい申告が必要になる |
将来的な相続で問題になるケース
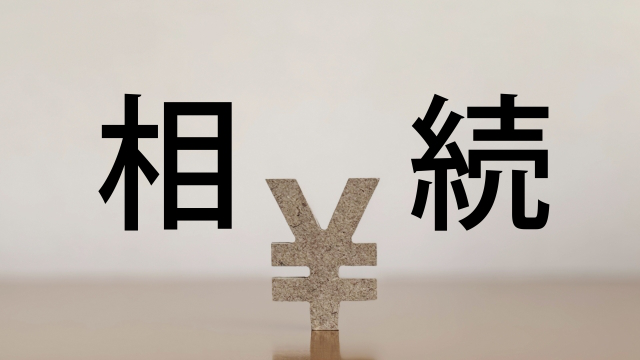
結婚資金として渡したお金でも、生前贈与として扱われる可能性があります。場合によっては、相続財産に加算されます。兄弟間の公平性が重要視される相続では、この問題がトラブルの原因になりやすいのです。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 父が長男に1,000万円の結婚資金を贈与した
- 父が亡くなり、遺産をめぐって次男が相続分の増額を主張した
- 贈与の金額や経緯が書面や記録として残っていない場合、事実確認が難しくなり、兄弟間で争いに発展
このようなトラブルを防ぐためには、贈与の事実を明確に残すことが重要です。具体的には、贈与契約書の作成や振込明細の保管、受領の証明書など、「いつ・誰が・いくら受け取ったのか」を証明できる記録を整えておきましょう。
こうした手続きを事前に行っておくことで、将来的な相続争いを防ぐだけでなく、贈与税の非課税制度を適用する場合にも、必要書類として利用できます。税務上の安心にもつながります。結婚資金贈与は、単にお金を渡すだけでなく、記録や書類をきちんと残すことが、家族全員の安心につながる贈与と言えるでしょう。
バレずに贈与することは可能?合法的な方法と注意点
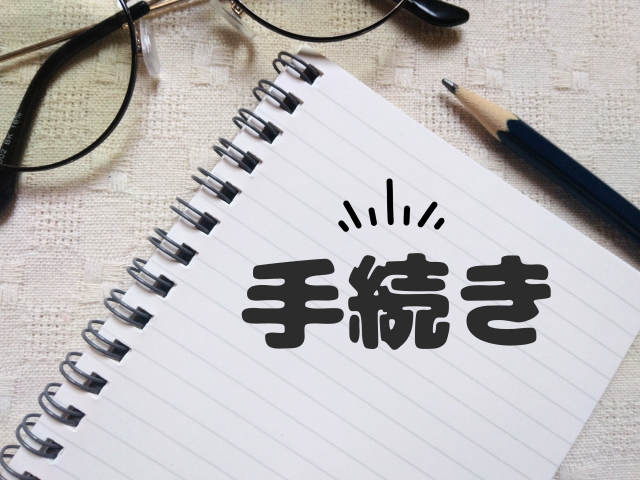
結婚資金の贈与を考えるとき、「できれば税務署にバレずに渡せないか」と考える方もいるかもしれません。しかし、贈与には、法律上のルールがあります。無申告や隠したままの贈与は違法です。そこで重要なのは、合法的な方法で贈与を行い、かつ将来のトラブルを避けることです。ここでは、結婚式や結婚資金の贈与において、合法的に非課税枠を活用する方法と、注意すべきポイントを紹介します。
非課税枠の活用

結婚資金を親からもらう場合、条件を満たせば、非課税で贈与できる制度があります。結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度は、2023年12月末で終了しました。2025年現在は利用できませんので、贈与は暦年課税(基礎控除110万円)を前提に考える必要があります。
- 贈与したお金が結婚に直接関わる費用であること(結婚式や新生活の準備など)
- 贈与契約書や振込記録など、証拠をきちんと残しておくこと
これらを整えておけば、贈与税がかからず、税務署にバレるリスクも大幅に減らせます。また、将来の相続で兄弟間に不公平感が出た場合も、記録があればトラブル防止になります。結婚資金の贈与は「お金を渡すだけ」ではなく、手続きを正しく行い、記録を残すことが安心につながるポイントです。
記録を正しく残すことの重要性

結婚資金の贈与は、非課税制度を活用すれば、贈与税の負担を避けられます。その際に、贈与の事実や金額を証明できる記録を残してください。記録を残すことで、税務署による確認や、将来の相続トラブルを防げます。
- 贈与契約書:贈与者・受贈者・贈与金額・贈与の目的・日付を明記し、両者で署名しておくことで、正式な証拠として利用できます。
- 銀行振込明細:振込日・金額・送金元・送金先をはっきり記録しておくと、贈与の事実を客観的に証明できます。
- メールやメッセージの保存:送金の目的とやり取りを残すことで、「結婚資金として贈与した」という意図を明確に示せます。
これらの記録は、紙とデジタルの両方で保管しておくとより安心です。紙の契約書や明細書に加えて、メールや写真など、デジタルデータも整理しておきましょう。将来、税務署の確認や相続時の争いが発生した場合でも、迅速かつ正確に対応できます。
| 記録の種類 | 記録の内容 | 証拠としての役割 | 保管方法 |
| 贈与契約書 | 贈与者・受贈者・贈与金額・贈与の目的・日付を明記、両者署名 | 贈与の正式な証拠となる | 紙で署名捺印、スキャンしてデジタルで保存 |
| 銀行振込明細 | 振込日・金額・送金元・送金先 | 贈与の事実を客観的に証明 | 銀行発行の明細を保管、ネットバンキング画面をPDF保存 |
| メール・メッセージ | 結婚資金の贈与であることを示すやり取り | 贈与の目的・意図を明確に示す | メールフォルダ保管、スクリーンショットやテキスト保存 |
贈与契約書やエビデンスの作り方
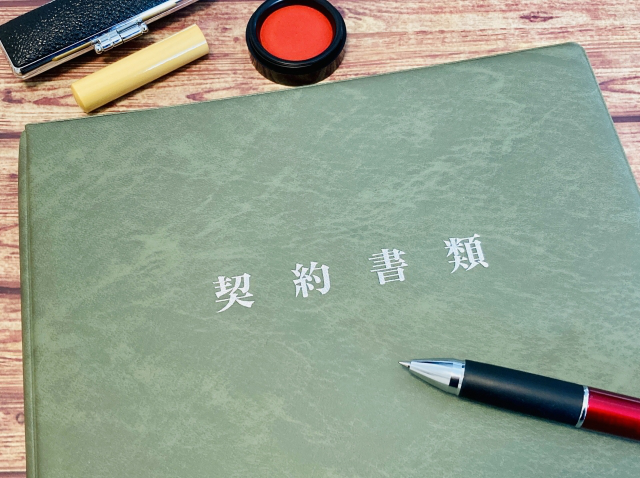
贈与契約書は、特別な形式でなくても構いませんが、公証役場で証明を付けるとさらに安心です。公証を付けることで、税務署や相続の場でも信頼できる証拠になります。契約書に書くべき基本ポイントは次の通りです。
- 贈与者・受贈者の名前:誰から誰への贈与かを明確にする
- 贈与金額と目的:用途をはっきり書く
- 贈与日:お金を渡した日を記録
- 署名・押印:両者が合意したことを証明
この契約書と、銀行振込明細やメールのやり取りなどの記録を一緒に残しておくと、税務署への説明や相続トラブルの防止に、とても役立ちます。つまり、贈与契約書は単なる書類ではなく、安心して結婚資金を渡すための大切な証拠と考えましょう。
| 贈与契約書に関するポイント | |||
| 項目 | 記載内容 | 役割 | 補足 |
| 贈与者・受贈者の名前 | 誰から誰へ贈与するのかを明確化 | 贈与の当事者を特定 | 相続時や税務署の確認で重要 |
| 贈与金額と目的 | 金額と用途(例:結婚資金)を明確に記載 | 贈与の内容を具体化 | 贈与税非課税制度利用時の根拠 |
| 贈与日 | 実際にお金を渡した日 | 贈与の成立時期を証明 | 振込明細と一致させると有効 |
| 署名・押印 | 贈与者・受贈者双方の署名・押印 | 合意の成立を証明 | 実印+印鑑証明があると強力 |
| 公証人の証明(任意) | 公証役場で認証を受ける | 信頼性をさらに高める | 税務署・相続時の証拠力が強化 |
相続の観点から考える結婚資金贈与
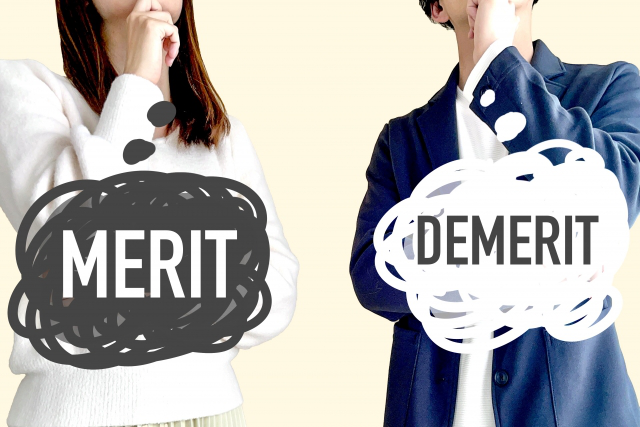
結婚資金として親や祖父母からお金をもらうことは、多くの家庭で行われています。しかし、相続の観点から見ると、結婚資金の贈与も将来の遺産分割に影響する可能性があるのです。特に、贈与の記録が残っていなかったり、贈与税の非課税制度を適切に利用していなかったりした場合、さまざまなトラブルにつながります。ここでは、結婚式や新生活のための贈与が相続にどのように影響するのか、深掘りしていきます。
将来の相続時に贈与が影響する理由

結婚資金の贈与は、一見すると単なる「お祝い」と思われがちですが、将来の相続に大きく影響する場合があります。兄弟姉妹が複数いる家庭では、特定の子どもにまとまった贈与をした場合、相続時に不公平感が生じやすいです。
たとえば、父母が長男のみに結婚資金を贈与していた場合、次男や三男は「なぜ自身には贈与がなかったのか」と感じるかもしれません。こうした不公平感は、相続の際に、遺産分割協議で問題になることがあります。
公平な相続を守るための生前贈与の整理
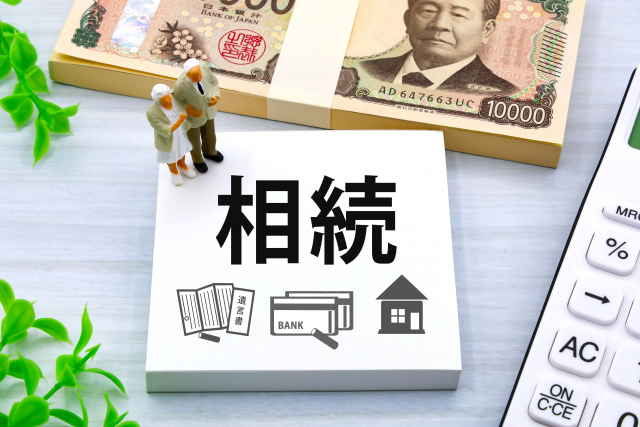
将来の相続で家族が揉めないために、生前贈与を整理して透明性を保つことが大切です。結婚資金や教育資金など、特定の子どもにまとまったお金を渡す場合でも、事前に整理しておけば、相続時の公平性を保ちやすくなります。
具体的には次のような方法があります。
- 生前贈与の内容を整理して家族で共有する
誰にいくら贈与したのか、何のためなのかを明確にすることで、相続の不公平さや疑問が解消できます。 - 贈与の記録を残す
贈与契約書や振込明細、メールなどを保存しておくと、税務署への対応や将来の相続での説明に役立ちます。 - 贈与額や時期を一覧表にまとめる
子どもや年度ごとに表にして管理すれば、相続時の計算や確認が簡単です。また、贈与税の申告が必要になった場合にも、素早く対応できます。
生前贈与を整理して、記録をきちんと残しておくことは、相続時のトラブル防止と家族間の公平性を守るための基本です。結婚資金の贈与も含めて、贈与を行うときは「整理と記録」をセットで考えましょう。
| 生前贈与の整理のポイント | ||
| 方法 | 内容 | 効果とメリット |
| 生前贈与の内容を整理して、家族で共有する | 誰に・いくら・何のために贈与したのかを、明確にする | 相続時の不公平感や疑問を防ぐ |
| 贈与の記録を残す | 贈与契約書、振込明細、メールなどを保存する | 税務署対応や相続時の説明に役立つ |
| 贈与額や時期を一覧表に考える | 進歩ごと、年度ごとに表で管理する | 相続時の確認・計算が簡単に行える。贈与税申告にも迅速に対応できる。 |
専門家に相談するメリット

結婚資金の贈与を行う際には、税理士や弁護士などの専門家に相談することもおすすめです。専門家のサポートを受けることで、単に書類を作るだけでなく、税務や相続の観点からも、適切に贈与が進められます。
具体的なメリットは次の通りです。
- 贈与税・相続税の正確な計算
贈与額や過去の贈与履歴に応じて、課税対象額や税率を正確に計算してもらえるため、税務署に指摘されるリスクを減らせます。 - 贈与契約書の適正な作成
契約書の内容や形式、必要な証拠書類を適切に整えてもらえるため、税務署や将来の相続での証拠として、信頼性の高い書類が残せます。 - 家族間のトラブル防止のアドバイス
兄弟間の公平性や将来の相続争いを見越したアドバイスをもらえるため、家族間での誤解や不満を事前に防止できます。
結婚資金贈与は、大きな金額が動くことが多いです。税務署や将来の相続に影響する可能性があります。そのため、専門家に関与してもらうことで、安心して贈与や資産管理を進められます。特に「結婚式贈与はバレるのではないか」と不安に思う場合も、専門家のサポートがあれば、正しく手続きを行い、リスクを最小限に抑えられるのです。
| 専門家に相談するメリット | 内容 | 効果 |
| 贈与税・相続税の正確な計算 | 贈与額や過去の贈与履歴をもとに、対象額や金額を正しく計算 | 税務署からの指摘やトラブルを防ぐ |
| 贈与契約書の作成 | 契約内容・様式・証拠書類を、専門家が整備 | 相続時に信頼性の高い証拠となる |
| 家族間トラブルの防止 | 兄弟間の公平性と、将来の相続に備えたアドバイスを提供 | 不満の防止や公平な相続の実現 |
デジタル遺品業者を活用した記録・証拠管理

結婚資金の贈与は、銀行振込や電子マネーなど、さまざまな方法で行われます。ここで役立つのが、デジタル遺品業者のサポートです。デジタルデータやオンライン送金履歴、メール、メッセージなどの証拠を、整理・保管してくれるため、安全かつ効率的に管理できます。ここでは、結婚式贈与において、デジタル遺品業者を活用するメリットをわかりやすく解説します。
デジタルデータで残る贈与記録の整理

結婚資金や結婚式費用の贈与は、銀行振込や電子マネー、メール、メッセージなどの幅広い方法で行われますが、これらは、すべてデジタルデータとして記録が残ります。このデジタルデータは、相続トラブルを防ぐための重要な証拠です。特に高額な贈与や兄弟間で公平性が問題となる場合には、データを整理して安全に保管しておくことが大切です。
- 通帳のデジタルデータ化:銀行の通帳や振込明細をスキャンしてデジタル化しておくと、紙の管理が不要になり、紛失リスクも減ります。
- ネットバンキングの取引履歴保存:オンライン送金や振込の履歴を定期的にダウンロードして保管しておくと、贈与の証拠として活用できます。
- メール・メッセージの保存とバックアップ:贈与のやり取りや目的を示すメールやチャットのスクリーンショットを保存し、クラウドや外付けHDDなどに、バックアップしておくことが重要です。
こうしたデジタルデータの整理は、単に記録を残すだけでなく、税務署や相続時に説明が必要になった場合でも、すぐに証拠として提示できるメリットがあります。贈与を安心して行うためには、デジタルデータを体系的に整理・保管することが欠かせません。
| デジタルデータの整理方法のポイント | |||
| 方法 | 内容 | メリット | 補足 |
| 通帳のデジタルデータ化 | 銀行通帳や振込明細をスキャンして保存 | 紙の管理不要・紛失リスクの減少 | PDF形式や画像で保存すると便利 |
| ネットバンキング履歴保存 | オンライン送金・振込履歴を定期的にダウンロード | 贈与の客観的な証拠になる | CSVやPDFで保存し、日付順に整理 |
| メール・メッセージ保存 | 贈与目的ややり取りをスクリーンショット・保存 | 意図を明確化し、後で提示が可能 | クラウドや外付けHDDにバックアップ |
デジタル遺品業者に依頼するメリット

結婚資金の贈与の場面で役立つのが、デジタル遺品業者の活用です。専門業者に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- デジタルデータの整理とバックアップ:銀行口座の取引履歴や電子マネーの履歴、メールやチャットのやり取りなどを、体系的に整理することで、紛失やデータ破損のリスクを減らせます。
- 紛失リスクの低減:複数の端末や、サービスに分散したデータを一元管理することで、重要な証拠を失うリスクを最小限にできます。
- 安全に記録・削除が可能:必要なデータは適切に保管して、不要なデータは安全に削除することで、情報漏れのリスク軽減が可能です。
- 家族に負担を残さず、相続時もスムーズ:贈与や資産の記録が整理されていれば、相続手続きの際に家族が困ることなく、スムーズに対応できます。
複数の銀行口座やオンラインサービスを利用している場合、個人での管理には限界があります。そのため、デジタルデータの整理や取り扱いに困った場合は、専門業者に依頼することが重要です。デジタル遺品業者は、正確かつ効率的にデータの整理・保管が行えます。将来的な税務確認や、相続トラブルにも安心して備えられるのです。
| デジタル遺品業者 | 内容 | 効果・メリット |
| デジタルデータの整理とバックアップを行う | 口座銀行の取引履歴、電子マネー履歴、メールやチャットの取引を整理・保管する | データ破損のリスクを軽減 |
| 安全に記録・削除する | 必要なデータは保管、不要なデータは安全に削除する | 情報漏えいリスクを軽減 |
| スムーズな相続が実現する | 相続時の贈与・資産の整理が簡単になる | 家族の負担が大幅に軽減 |
家族に負担を残さない贈与・資産管理の方法

結婚資金の贈与や資産管理を行う際には、将来の相続で家族に負担を残さないことが非常に重要です。そこで、以下の方法で贈与や資産を管理することが効果的です。
- 贈与記録を紙・デジタル両方で保管
贈与契約書や振込明細などの紙資料だけでなく、銀行取引履歴やメール・メッセージなどの、デジタルデータも整理・保存しましょう。両方の記録を証拠として確実に残せます。 - 贈与記録を紙・デジタル両方で保管
贈与契約書や振込明細などの紙資料だけでなく、銀行取引履歴やメール・メッセージなどの、デジタルデータも整理・保存しましょう。両方の記録を証拠として確実に残せます。 - デジタル遺品業者で整理・バックアップ
複数の銀行口座やオンラインサービスを利用している場合、個人だけでの管理は煩雑になりがちです。専門業者に依頼すれば、デジタルデータを安全に整理・バックアップできます。紛失やデータ破損のリスクが、大きく減らせるのです。 - 相続時に家族間で透明性を確保
贈与の内容や金額を一覧表などでまとめて、家族で共有しましょう。将来的な相続の場で、誤解や争いを防げます。
これらの方法を組み合わせることで、将来の相続トラブルを未然に防止できます。「結婚資金贈与が税務署にバレる」という漠然とした疑問も払拭できるでしょう。贈与は単にお金を渡すだけではありません。正しい記録と整理を行うことが、家族全員にとっての安心につながります。
| 方法 | 内容 | 効果・メリット |
| 贈与の記録を紙・デジタル両方で保管 | 契約書・振込明細などを紙で保存しつつ、デジタルデータも整理・保存 | 証拠を確実に残せるため、相続手続きでの説明に有効 |
| デジタル遺品業者で整理・バックアップ | 複数のログインやオンラインサービスを、業者が安全に整理・バックアップ | データ破損のリスクを軽減して、効率的な資産管理が可能 |
| 相続時に家族間で透明性を確保 | 贈与の内容と金額を、一覧表にして家族で共有 | 相続での公平性が担保 |
結婚資金贈与の注意点とトラブルの事例

結婚資金の贈与は、非課税枠を活用すれば税金を抑えられますが、制度のルールや記録の取り扱いを誤ると、思わぬ税負担や家族間のトラブルに発展します。ここでは、実際に起こり得るケースを通して、注意すべきポイントとトラブル回避の方法を紹介していきます。
- ケース1:非課税枠を超えた贈与で追徴課税
- ケース2:相続争いに発展した結婚資金贈与
上記の事例をもとに、結婚式贈与を行う際の、贈与額の管理や契約書・銀行明細などの重要性が見えてきます。
非課税枠を超えた贈与で追徴課税

Aさん(60代)は、長男の結婚を祝って1,500万円を一括で贈与しました。本人としては「結婚資金の贈与には、非課税枠があるから大丈夫」と考えていました。しかし、実際の非課税枠は、直系尊属からの贈与で1,000万円までになります。結果として、500万円分が課税対象となってしまったのです。
税務署からの指摘により、500万円に対する贈与税50万円に加えて、申告漏れによる加算税10万円も発生しました。これにより、合計60万円の追徴税を支払うことになったのです。
事前に非課税枠を確認して、残りの500万円を複数年に分けて贈与すれば、このような追徴課税は避けられました。贈与契約書や振込明細を整えておけば、資金の性質を明確にできます。税務署からの指摘リスクも下げられます。
このケースからわかるように、結婚資金の贈与は「非課税枠の正しい理解」と「分割贈与・記録の徹底」が大切なポイントです。
| 項目 | 内容 | ポイント |
| 贈与の内容 | Aさん(60代)が長男へ結婚資金として1,500万円を一括贈与 | 一括贈与の金額が大きい |
| 非課税枠 | 直系尊属からの結婚資金贈与は1,000万円まで非課税 | 超過分500万円が課税対象 |
| 税務署の指摘 | 500万円に対する贈与税は累進課税により計算され、続柄や控除額によって税額が変わります。申告漏れの場合は加算税や延滞税が加わるため、余計な負担が発生します。 | 合計60万円の追徴税 |
| 問題点 | 非課税枠を正しく把握していなかった | 「大丈夫」と思い込みによるミス |
| 防げた対策 | ・事前に非課税枠を確認 ・500万円を複数年に分けて贈与 ・贈与契約書や振込明細を準備 | 税務署指摘リスクを軽減 |
| 学べる教訓 | 結婚資金贈与は「非課税枠の正しい理解」と「分割贈与・記録の徹底」が重要 | 追徴課税を回避できる |
相続争いに発展した結婚資金贈与

Bさん(70代)は、長男の結婚にあたり「新生活の助けになれば」と考えて、結婚資金として500万円を一括で贈与しました。しかし、その際に贈与契約書を作成せず、銀行振込の記録や明確な証拠も残しませんでした。
数年後、Bさんが亡くなり相続の話し合いが始まると、次男が「長男に多額の資金を渡したのは不公平だ」と不満を表明したのです。話し合いはこじれて、最終的には、相続訴訟にまで発展してしまいました。兄弟間の関係は悪化して、相続手続きも長期化しました。また、弁護士費用の負担も大きく、家族全体にとって、大きなストレスとなったのです。
もしこの時、Bさんが贈与契約書を作成して、銀行振込明細やメールのやり取りを残していれば、500万円は「結婚資金として贈与済み」であることを証明できました。この証拠によって、次男の不満を抑えることができたでしょう。
この事例からわかるのは、結婚資金の贈与は、ただ渡すだけでは不十分です。そして「記録を残すこと」が、将来の相続トラブルを防ぐ最も有効な手段になるということです。特に、兄弟間で不公平感が生じやすいケースでは、契約書や銀行明細を整理・保管しておくことが欠かせません。
| 項目 | 内容 | ポイント |
| 贈与の内容 | Bさん(70代)が長男へ結婚資金500万円を一括贈与 | 「新生活の助け」として贈与 |
| 記録の有無 | 契約書なし、銀行振込記録や証拠もなし | 贈与の証明不十分 |
| 相続時の問題 | Bさん死去後、次男が「不公平」と主張 | 兄弟間の不満が表面化 |
| 結果 | 相続訴訟に発展、兄弟関係悪化、手続き長期化、弁護士費用発生 | 家族に大きなストレス |
| 防げた対策 | ・贈与契約書を作成 ・銀行振込明細の保存 ・メールやメッセージによる意図の記録 | 「結婚資金として贈与済み」を明確化できた |
| 学べる教訓 | 結婚資金の贈与は「渡すだけでは不十分」 証拠を残すことで相続トラブルを防止可能 | 特に兄弟間で公平性が問題になりやすい |
まとめ

結婚資金の贈与は、非課税枠を活用すれば、合法的に行えます。しかし、銀行振込や電子マネーなどの取引は、すべて記録として残るため、税務署や将来の相続で確認される可能性があります。高額の贈与や兄弟間で差がある場合は、相続トラブルに発展することもあるため、注意しなければなりません。
贈与税の仕組みを理解して、非課税枠や課税対象額を正しく把握することで、税務リスクを回避できます。また、贈与契約書や銀行振込明細などのデジタルデータを整理・保管しておくことで、将来の証拠として活用できるでしょう。
特に、デジタル遺品業者を活用して、デジタルデータの整理やバックアップを行うことで、効率的かつ安全に、贈与や資産管理を進められます。今回紹介したポイントを意識して実践すれば、結婚資金贈与がバレる不安を軽減できるだけでなく、相続の不安も大きく減らせるでしょう。贈与の場面においても、記録と整理を一緒に行うことで、家族全員にとって安心な資産管理が実現できます。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼