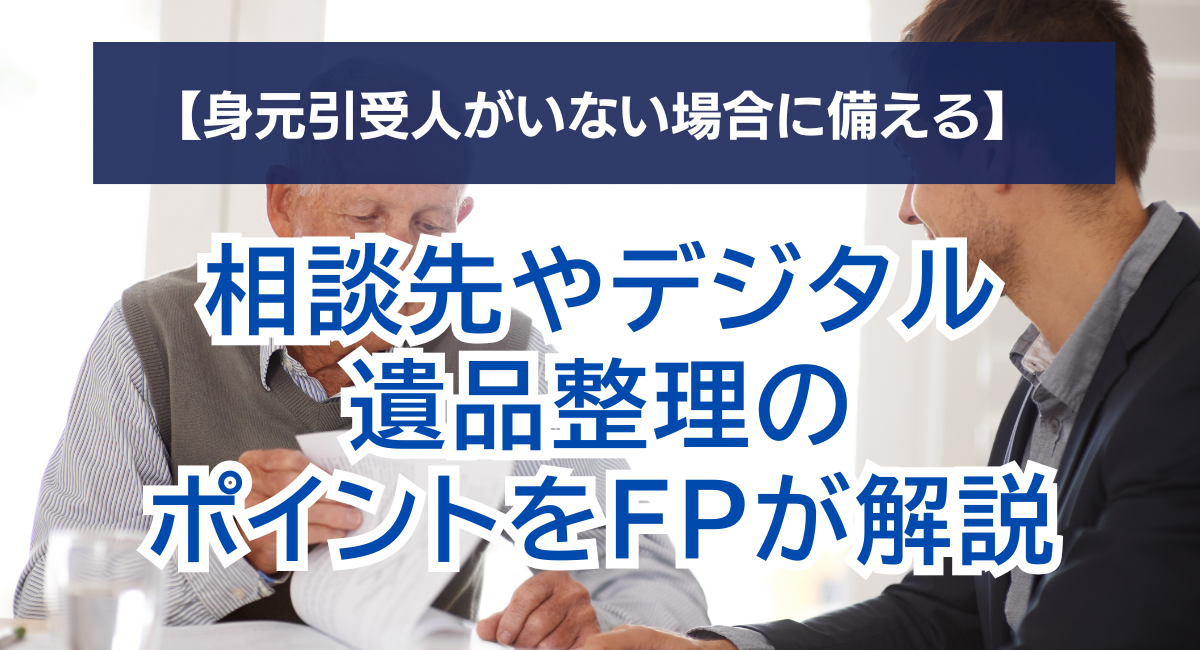高齢者や独身の方の中には、「自身に万が一のことがあったとき、誰が手続きをしてくれるのか分からない」と不安に感じる方も少なくありません。身元引受人がいない場合、入院や施設入所、緊急時の対応などに影響が出る可能性があります。
今回の記事では、身元引受人がいない場合の具体的な対処法、安心して相談できる窓口やサービス、さらに資産やデジタル遺品の整理まで詳しく解説します。これを読めば、将来への不安を軽減するための具体的な行動がわかります。
身元引受人とは?その役割と必要性

入院や介護施設への入居、賃貸住宅の契約など、私たちの生活の中には「身元引受人」が必要とされる場面が意外と多くあります。普段の生活では、あまり耳にしない言葉ですが、いざというときに「誰にお願いできるのか」「家族以外でも対応できるのか」といった疑問に直面する人は少なくありません。
特に単身者や高齢者にとって、身元引受人がいないことは、医療や住まいの選択肢を狭めてしまう大きなリスクとなります。だからこそ、その役割や責任の範囲、そしてなぜ必要とされるのかを正しく理解しておくことが、安心して暮らすための第一歩です。
| 項目 | 内容・役割 | 責任範囲 | 注意点・補足 |
| 身元引受人の主な役割 | 入院や介護施設入居時の身柄引き取り、退去手続き、残置物片付け | 道義的な責任。債務履行の連帯責任が発生するケースもあり | 法律で明確に定義された責任は少なく、道義的責任が中心 |
| 身元引受人の責任 | 退去手続き、未払い費用清算、身柄引取など | 法的責任は少ないが、道義的責任は重い | 身元引受人の負担感から、引き受けを嫌がる例も多い |
| 身元保証人との違い | 労働契約や賃貸契約などにおいて金銭的責任や損害賠償責任を負うなど、法的責任が重い | 金銭的責任、損害賠償責任を負う | 身元保証人は、契約書で責任範囲が明示される |
| 誰がなりやすいのか | 同居家族が基本。遠方親族や知人、弁護士も可能 | 常に本人を監督・監視できる人が望ましい | 遠方の人でも法律上は可能だが、緊急時対応が困難なため施設や病院が断るケースあり |
| 注意点 | 引き受ける際は、契約内容の確認が必須。安易な承諾によるトラブルが多発している | 責任範囲により、負担が大きく異なる | 施設ごとに取り扱いが異なるため、個別確認が必要 |
身元引受人の基本的な役割

身元引受人とは、病院や高齢者施設に入院・入所する際に、契約や各種手続きを代行したり、利用者の生活を支える役割を担ったりする人のことを指します。たとえば、入院や手術を受ける際に必要となる同意書への署名、施設入所契約や医療・介護サービスに関する各種契約の代行、緊急時の連絡窓口など、本人にとって欠かせない存在です。
また、身元引受人は、法律で必ず置かなければならないものではありません。しかし実際には、ほとんどの医療機関や介護施設が契約時に求めており、スムーズな入所やサービス利用のために、重要な役割を果たしています。独身の方や身寄りの少ない高齢者にとっては、身元引受人が不在であることが、入院や施設入所の大きな障害となるケースも多いです。
医療・入院時に身元引受人が必要なケース

独居高齢者にとって、医療や介護の現場で「身元引受人がいない」という状況は大きな問題となります。たとえば、急な病気やけがで入院や手術が必要になった際、医療契約や同意書に署名する人がいないと、処置や治療の開始が遅れてしまう恐れがあります。病院によっては、緊急時の判断を、家族や身元引受人に求める場合も多いです。本人だけでは、十分に対応できないケースが少なくありません。
介護施設や高齢者住宅に入居する際も同様で、契約書への署名や緊急時の連絡先として、身元引受人の存在を、前提にしている施設が多いのも現状です。そのため、身元引受人がいない独居高齢者は、医療や介護サービスを受けにくくなり、結果として、生活の安心や安全が損なわれる可能性があります。
身元引受人がいない場合に起こり得るリスク

身元引受人がいない場合、日常生活や将来の備えにおいてさまざまなリスクが生じます。まず代表的なのが、先述の通り、入院や介護施設への入所がスムーズに進まないという点です。多くの医療機関や施設では、契約時に身元引受人の署名や緊急時の連絡先を必須としているため、用意できなければ、受け入れを断られるケースさえあります。
また、手術や治療に関する同意書など、重要な医療判断を求められる場面でも、代理で署名できる人がいないと対応が滞り、適切な医療が遅れてしまう可能性があります。財産の管理や生活に関する意思決定についても、判断を委ねられる人がいなければ、本人の希望通りに、物事を進められなくなるリスクが高まるのです。
身元引受人がいないことは、医療や介護だけでなく、生活全般に大きな影響を及ぼします。選択肢を狭めてしまう要因になります。そのため、いざというときに備えて、信頼できる人に依頼する、専門サービスを利用するなど、あらかじめ対応策を検討しておくことが、とても重要です。
| リスク | 具体的な内容 | 生活や医療に与える影響 | 対策と重要なポイント |
| 入院・施設入所の制約 | 入院や介護施設の契約で身元引受人が必要とされる。これがないと、受け入れ拒否の可能性がある | 医療や介護サービスの利用が制限される | 成年後見制度や民間身元引受サービスの利用を検討 |
| 医療同意・契約問題 | 手術や治療の同意書に代理署名者がいない場合、医療対応が遅延するリスクがある | 緊急医療対応の遅れや、不適切な治療の恐れがある | 事前に医療同意に関する意思表示を整理・共有 |
| 財産管理・意思決定不備 | 判断できる代理人がいないと、財産管理や生活上の契約が滞るリスクがある | 財産の凍結や生活基盤の不安定の恐れがある | 信頼できる代理人の設定や、法的支援制度の活用 |
| 孤立リスク | 緊急時の連絡先や支援者不在で、孤独死や対応遅延の恐れがある | 自己管理不能時の問題が深刻化する | 見守りサービスや、地域支援ネットワークの活用 |
身元引受人がいない場合の選択肢

身元引受人がいないからといって、必ずしも医療や施設入所を諦めなければならないわけではありません。現代では、公的な支援や民間サービス、さらには、専門家への依頼など、さまざまな選択肢が用意されています。自身の状況や希望に合った方法を知っておくことで、将来の不安を軽減して、安心して生活を続けることができるでしょう。ここでは、代表的な対応策をわかりやすく紹介します。
行政や福祉サービスを利用する

行政や福祉サービスを上手に活用することは、高齢者や独居で暮らす方にとって、安心して生活を続けるための大切な手段です。市区町村では、高齢者を対象にしたさまざまな支援制度を用意しており、生活面から医療・介護、緊急時の対応まで、幅広くカバーしています。
たとえば、生活支援相談窓口では、日常生活の困りごとや、入院・入所に関する手続きについて相談できます。必要に応じて、専門機関やサポート団体につないでもらえます。また、高齢者相談センターでは、医療機関や介護施設などの情報提供を行っており、本人や家族が適切な選択をできるよう支援してくれます。
さらに、緊急通報サービスを利用すれば、自宅で体調不良や転倒が起きたときにすぐにつながる体制が作れます。孤独死や一人での長時間放置といったリスクを大幅に減らせるのです。こうした制度は、自己申請が基本であるため、自ら積極的に調べて活用することが重要です。独居高齢者や近隣に頼れる家族がいない方にとっては、行政サービスを事前に理解して、連絡先を確認しておくことが、将来の安心につながります。
民間の身元引受サービスを利用する

民間の身元引受サービスを利用するという選択肢も、近年注目を集めています。従来は家族や親族が担っていた役割を、専門の民間企業が代行してくれる仕組みです。独身の方や身寄りが少ない方にとって、大きな安心になります。サービス内容は、入院や高齢者施設への入所時に必要となる、契約手続きの代行から、緊急時の連絡・駆けつけ対応まで、幅広く対応しているのが特徴です。
月額利用料や契約初期費用がかかる場合が多いものの、その分、専門のスタッフや専門家が制度を理解した上でサポートを行うため、手続きがスムーズに進みやすいです。法的なトラブルや、契約上のミスを回避できるメリットがあります。
また、病院や施設側から見ても「身元を引き受けてくれる専門機関がいる」という点は、信頼につながります。入所や入院を断られにくくなる効果も期待できるでしょう。身近に頼れる家族がいない方や、子ども世代に負担をかけたくないと考える高齢者にとっては、こうした民間サービスの存在が、将来の安心を支える強力な選択肢となります。
信頼できる知人や専門家に依頼する

身元引受人が身近にいない場合でも、信頼できる知人や専門家に依頼するという方法があります。たとえば、家族や親しい友人がいない場合、行政書士や社会福祉士といった専門資格を持つ人に依頼することで、契約や入院・施設入所の手続きを安心して任せられます。
こうした専門家は、契約事務に精通しているだけでなく、法的観点から適切な判断をしてくれるため、後々のトラブルを防ぐうえでも有効です。また、専門家に依頼する場合は、事前に契約内容や費用の詳細を確認しておくことが重要です。依頼範囲や費用体系などを明確にしておけば、万が一の際にも、安心してサポートが受けられます。守秘義務からプライバシーが守られるのも、大きなメリットです。
身元引受人がいない場合、相談先はどこが安心?

身元引受人がいない場合でも、不安や悩みを一人で抱え込む必要はありません。行政の窓口や地域の支援団体、さらには専門家など、状況に応じて頼れる相談先は、複数存在します。どこに相談すればよいのかを知っておくことで、医療や生活に関する問題を早めに解決できます。将来の安心にもつながります。
市区町村の高齢者相談窓口

身元引受人がいない場合、各市区町村には、高齢者や独居者を支援するための相談窓口が設けられています。生活や医療、介護に関する情報を提供するだけでなく、身元引受人がいないケースへの対応策についても、丁寧に案内してもらえます。
たとえば、生活支援センターでは、日常生活における困りごとや入院・施設入所などの相談を受け付けているのが特徴です。適切な支援制度やサービスに結びつけてくれます。
高齢者相談センターでは、医療機関や介護施設の利用方法、利用できる地域サービスについて、具体的にアドバイスが受けられます。また、地域包括支援センターは、医療・介護・生活支援といった分野を総合的にカバーしており、身元引受人が不在であっても、今後のサポート体制を一緒に検討してもらえるのがメリットです。
このような公的相談窓口を活用することで、家族や身寄りがいなくても、自身に合ったサービスにつながります。事前に窓口の場所や連絡先を確認しておけば、いざという時にも安心できるでしょう。
| 相談窓口名 | 対応内容 | 特徴・メリット | 利用時のポイント |
| 生活支援センター | 日常生活の困りごと相談、入院・施設入所相談 | 生活支援制度やサービスにつなげる | 相談者の状態に合わせて、適切な支援を紹介 |
| 高齢者相談センター | 医療機関や介護施設利用のアドバイス、地域サービス案内 | 地域の医療・介護ネットワークとの連携支援 | 利用者の具体状況に応じた、きめ細かい相談が可能 |
| 地域包括支援センター | 医療・介護・生活支援の総合相談、サポート体制検討 | 身元引受人が不在でも、代替支援策の検討が可能 | 多様な専門職の連携で、包括的な支援を実現 |
| 社会福祉協議会 | 高齢者の生活相談や支援サービス案内 | 地域の福祉ネットワークと連携して、地元密着の支援 | 生活全般の支援を広くカバー |
| 司法書士・弁護士事務所 | 成年後見制度の相談・手続き支援、法的代理 | 法的専門家による安心・確実な支援が受けられる | 経験豊富な専門家の選定が重要 |
| 民間身元保証サービス | 緊急対応、契約代行、生活支援などの代行サービス | 家族がいなくても、専門スタッフが多面的にサポート | 契約条件や費用などを事前に、十分確認することが必要 |
| 保健福祉事務所 | 医療・福祉・介護に関わる相談対応 | 公的な支援情報の提供や連携調整を実施 | 他機関との橋渡し役として、フレキシブルに対応 |
NPOや民間団体の支援サービス

身元引受人がいない場合でも、近年はNPOや民間団体による支援サービスを利用できるようになっています。特に、独居高齢者や身寄りの少ない方に向けた活動が広がっており、生活上のちょっとした相談から、入院や施設入所の際に必要となる契約手続きの代行を提供しているのが特徴です。また、緊急時の連絡や駆けつけ対応など、多角的なサポートを行ってくれます。
たとえば、独居高齢者向けの生活支援を専門にするNPOでは、日常生活に関する見守りや買い物支援、行政サービスへのつなぎ役といった身近なサポートを受けられます。民間の身元引受サービス団体では、病院や施設との契約を、スムーズに進められるように支援してくれるのです。本人の不安や家族の負担を軽減してくれます。
専門家(弁護士・行政書士・FP)への相談

身元引受人がいない場合、医療契約や施設入所、財産管理など、日常生活や将来の判断に関わる重要な手続きがなかなか進みません。こうした場合には、弁護士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談することが有効です。専門家は、法律や契約の知識を活かして、医療同意書の手続きや入院契約の代理、財産管理の方法などを適切にサポートしてくれます。
また、成年後見制度を活用すれば、身元引受人がいなくても、法的に認められた後見人が、本人の代わりに生活や財産の管理を行えるため、安心して日常生活を送ることが可能です。将来のトラブルや法的リスクを未然に防ぎ、親族や関係者にとっても、大きな安心につながります。
身元引受人がいない場合の資産・デジタル整理

現代の生活では、資産や個人情報だけでなく、スマホやパソコン、クラウドサービスに残るデータも、重要な財産の一部です。しかし、身元引受人がいない場合、こうした将来的なデジタル遺品や契約情報は、相続の際に滞りやすく、親族や関係者に大きな負担やリスクが生じることがあります。
特に、パスワード管理や複数のサービス情報の把握は、個人だけでは難しくなります。スマホやクラウドサービスの場合、誤操作や情報漏れの危険もあるでしょう。ここでは、デジタル遺品の基本から整理の難しさ、業者選びのポイントまでを詳しく解説します。
デジタル遺品とは何か

デジタル遺品とは、スマホやパソコン、クラウドサービス上に残された個人情報や契約データの総称です。従来の紙の通帳や契約書と違い、デジタル化が進んだ現代では、財産や大切な記録の多くがオンライン上に存在しており、その整理が大きな課題となっています。
たとえば、ネットバンキングや証券口座、暗号資産といった金融関連のデータだけでなく、SNSアカウントやメール、オンラインショッピングの契約情報、クラウドに保存された写真や文書なども含まれます。こうしたデジタル遺品は、本人が亡くなった後に、家族や関係者がすぐに把握するのが難しいという特徴があります。パスワードやIDが分からなければ、アクセスできないケースが多いです。
このような事態になると、家族が資産を確認できずに、相続手続きも止まってしまいます。デジタル遺品に気づかないまま、利用料やサブスクリプション料金が引き落とされ続けるといったトラブルも発生します。そのため、近年ではデジタル遺品の整理・管理が「新しい相続準備の一環」として重要性を増しているのです。
個人で対応する難しさと注意点
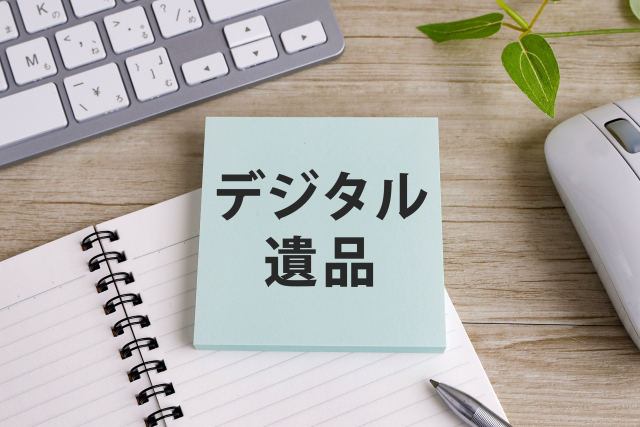
身元引受人がいない状況では、デジタル遺品の整理を、家族や信頼できる人に任せることが難しいです。生前のうちに、自身でデータを整理する必要があります。何も対処しないまま、亡くなった後に親族や関係者がデジタル遺品を発見した場合、限られた範囲や条件のなかで、調べなければなりません。
しかし、デジタル遺品の管理は想像以上に複雑であり、個人の力だけでは対応が困難です。スマホやパソコンに保存されたデータだけでなく、ネットバンキングや証券口座、サブスクリプション契約、SNSアカウントなど、複数のサービスにまたがって情報が存在します。
それぞれのID・パスワードを整理するだけで、莫大な手間と知識が必要となります。加えて、無理にパスワードを解除を試みて、専門知識のないまま操作をした結果、大切な情報が消去されてしまう危険性もあります。安易にメモやファイルにパスワードを記録してしまうと、第三者による不正アクセスや、情報漏れにつながるリスクも否定できません。
デジタル遺品業者に依頼するメリット

身元引受人がいない場合でも、デジタル遺品業者に依頼することで大きな安心を得ることができます。デジタル遺品の整理は、スマホやパソコンのパスワード解除、クラウドサービスやSNSアカウントの確認・削除、ネットバンキングや有料契約の解約など、多岐にわたる作業が必要です。
専門知識のない人が無理に対応しようとすると、誤操作でデータを消してしまったり、セキュリティ面で情報が流出するリスクを伴います。その点、デジタル遺品業者は、相続人の同意や正規の手続きを経て、安全にアカウントやデータを整理します。
依頼することで、家族や信頼できる人がいなくても、整理作業を円滑に進めてもらえるため、残された人に負担をかけずに済むという大きなメリットがあります。さらに、個人情報や金融関連のデータが外部に漏れないよう、セキュリティに配慮した方法で対応してくれるため、情報漏れのリスクを最小限に抑えられるのも安心材料です。
パスワードが分からないまま放置されたアカウントや、有料サービスの解約忘れは、長期的に負担やトラブルの原因となり得ます。デジタル遺品業者に依頼すれば、こうした問題を事前に解決できます。資産や情報の見落としを防げる点も、大きな強みといえるでしょう。
デジタル遺品業者の選び方

信頼できる事業者を選ぶためには、さまざまなポイントを確認する必要があります。まず、その業者がどれだけの実績を積んでいるのか、過去の依頼者からの口コミや評価を確認しましょう。経験豊富な業者であれば、多様なケースで柔軟に対応できる可能性が高まります。
デジタル遺品には、金融情報やプライベートな記録が含まれます。作業後に「どのようなデータを整理・削除したのか」を明確に記録した報告書や証明書を発行してくれる業者を選ぶと、後々の相続手続きやトラブル防止にも役立つでしょう。
突然のトラブルや、緊急対応の必要性も考慮すべき点です。急な入院や死亡時に預けられていたアカウントや、契約情報を速やかに対応してくれる体制があるかは、安心感を左右する重要な要素になります。こうした観点を踏まえて、事前に複数の業者を比較して、自身の状況に合った信頼できるサービスを選ぶことが、後の安心と円滑な相続整理につながるのです。
事前にできる準備と安心のための行動

将来に備えて安心した生活を送るためには、身元引受人がいない場合でも、自身でできる準備を、あらかじめ整えておくことが大切です。エンディングノートや遺言書を活用して希望や資産情報を明確に残すことで、行政や専門家が適切に対応しやすくなります。また、デジタル遺品の整理や契約手続きの見直しを行うことで、緊急時でも混乱を避け、安全かつスムーズに手続きを進められます。
エンディングノートや遺言書で希望を明確に
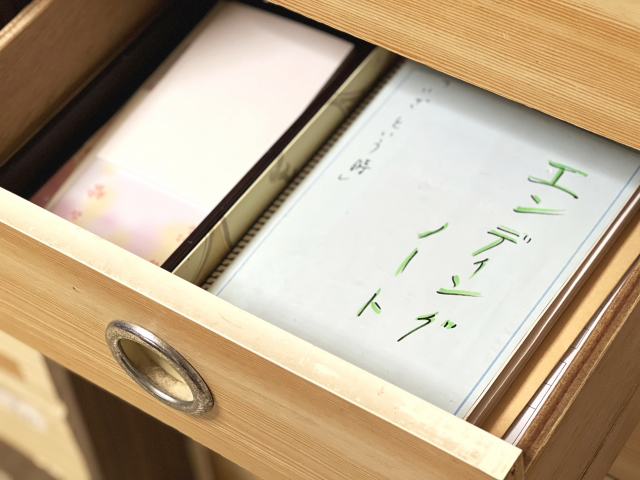
身元引受人がいない場合でも、事前にエンディングノートや遺言書を準備しておくことで、自身の希望や資産状況を、きちんと残すことが可能です。これらの書類は法的拘束力の違いはあるものの、いずれも本人の意思を示す大切な手段であり、行政機関や専門家がスムーズに対応するための大きなサポートとなります。
特にエンディングノートは形式や書き方に制限がなく、生活や介護に関する要望から財産情報、葬儀の希望などまで、幅広く自由に記録できます。将来に備えた準備として有効です。具体的に書いておくと役立つ内容には、たとえば「生活や介護の方針」「延命治療に関する考え方」などの医療・介護面での希望があります。
「口座・証券・保険の財産情報」「利用しているSNSやクラウドサービスのアカウント情報」などのデジタル遺品も含まれます。「緊急時に連絡してほしい人の情報」や「信頼できる専門家の連絡先」をまとめておけば、万が一の時にも、行政や専門機関が速やかに動ける体制が整うでしょう。
こうした情報をきちんと残しておくことは、身元引受人がいないことによる不安を和らげるだけではありません。後に対応を担う人々の負担を大きく軽減します。エンディングノートは、あくまで補助的な役割ですが、法的効力を持つ遺言書と合わせて準備しておくことで、自身の意思を確実に反映させられます。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
| 法的効力 | なし。本人の意思や希望を、自由に記録できる。 | あり。法律に基づく法的拘束力を持ち、資産分配などが確実に実現する。 |
| 記載内容 | 医療・介護の希望、生活方針、葬儀の希望、財産情報、デジタル遺品情報、緊急連絡先など、幅広く記載できる。 | 資産の分配方法、相続人の指定、遺言執行者の指定など、法定形式で記載できる。 |
| 形式・書き方 | 制限なし。自由に書き方や内容をカスタマイズできる。 | 法律で定められた厳格な形式に従う必要がある。 |
| 役割 | 家族への大切な指針や本人の意思伝達ツール。 | 相続手続きの法的根拠となる文書。 |
| 活用時の特徴 | 死亡の前後に関係なく、他者が内容を確認・共有できる。 | 死亡時に開封されて、法的手続きが必要になる。エンディングノートと併用が効果的。 |
デジタル遺品の整理と管理方法
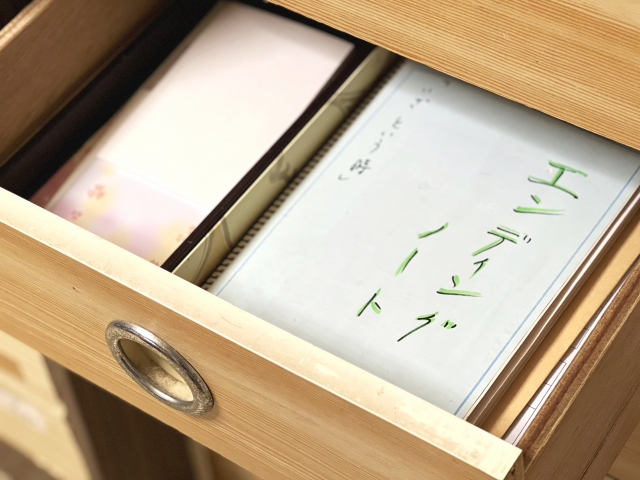
身元引受人がいない場合でも、デジタル遺品をきちんと整理・管理しておくことで、将来のトラブルを大幅に減らせます。特に、インターネットを通じて多くのサービスを利用している現代においては、パスワードや契約情報が散在していると、いざという時に、誰も把握できません。解約できない有料サービスや、放置された資産が、そのまま残ってしまう恐れがあります。
効果的な方法としては、まずパスワード管理アプリを活用して、すべてのログイン情報を、安全に一元管理することが挙げられます。暗号化された形で保存できるため、万一の際にも、セキュリティを保ちながら、必要な情報をまとめて整理できます。
さらに、利用中のサービスや契約の一覧を作成しておくことで、口座情報やSNS、クラウド、サブスクリプションなどの所在が、一目で分かります。誰かに引き継いでほしい場合にもスムーズに対応してもらえます。
また、情報は一度まとめただけでなく、定期的に更新して最新状態を保つことが大切です。サービスの追加や解約、パスワード変更があるたびに更新を怠ると、必要な時に役立たない可能性があるのです。身元引受人が不在の場合でも、こうした準備を先んじて行っておけば、行政や専門家に依頼した際に、迅速に対応が進みやすくなります。余計な手間やコストを減らせるのです。
身元引受人がいなくても安心できる契約や手続き

身元引受人がいない場合でも、安心して生活できるように、さまざまな準備やサービスを利用しておくことが大切です。まず、成年後見制度という、公的な制度を使う方法があります。これは、判断力が低下した時に、法律の専門家が代理で、財産管理や契約手続きをサポートしてくれる制度です。
次に、最近増えている民間の身元引受サービスに事前登録する方法もあります。これは、契約手続きや緊急時の対応を専門のスタッフが代わりに行ってくれるサービスで、一人暮らしの高齢者や身寄りのない方に適しています。
さらに、日常生活や医療に関わる契約(医療保険や介護サービス、住居契約など)をあらかじめ整理して、重要な書類や連絡先をまとめておくと、万が一のときに、スムーズに対応ができます。これらの準備をしておくことで、家族や身寄りがいなくても、行政や専門家が円滑にサポートできる環境が整います。急な入院や施設入所、緊急時にも安心して過ごせるようになるでしょう。
大切なのは、これらの制度やサービスの内容、費用、契約条件をよく理解して、納得した上で利用することです。信頼できる専門家や周囲の人と、相談しながら準備を進めることで、将来の不安を軽減できます。
| 項目 | 内容 | 効果・ポイント | 注意点・補足 |
| 成年後見制度 | 判断能力が低下した際に、法律専門家が、財産管理・契約手続きを代理 | 法的根拠があり、財産管理や医療契約のサポートが確実 | 手続きに時間がかかる場合がある |
| 民間身元引受サービス | 専門スタッフが契約手続き・緊急対応を代行する有料サービス | 家族がいない高齢者の安心確保、入院・施設入所時のサポート | サービス内容や費用、契約条件は、事前に詳細な確認が必要になる |
| 生活・医療契約の整理 | 医療保険、介護サービス、住居契約など、重要書類・連絡先の整理 | 緊急時の対応がスムーズに、生活基盤を守る | 書類の定期的な見直し推奨される |
| 事前準備と情報共有 | 制度・サービスの内容理解と信頼できる専門家・周囲との相談 | 不安軽減と安心できる生活につながる | 契約前に、複数の選択肢検討が望ましい |
まとめ

身元引受人がいなくても、行政や専門家、民間サービスを上手に活用すれば、安心して暮らせます。デジタル遺品も含め、事前に情報や契約を整理しておくことで、家族や関係者の負担を大きく軽減できます。重要なのは、早めに相談窓口や専門サービスを利用して、自身の意思や希望を書面にまとめることです。これにより、緊急時や万が一の際にも、スムーズに対応が進みます。
また、エンディングノートやデジタル遺品整理を前もって準備しておくことで、将来の不安を大幅に軽減できるでしょう。安心して日々を過ごすための、有効な対策になります。大切な情報や希望を整理しておくことで、周囲の人が最善の対応を取れる環境を作れるため、ぜひ早めの取り組みをおすすめします。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【運営サイト】https://moneyships.biz
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼