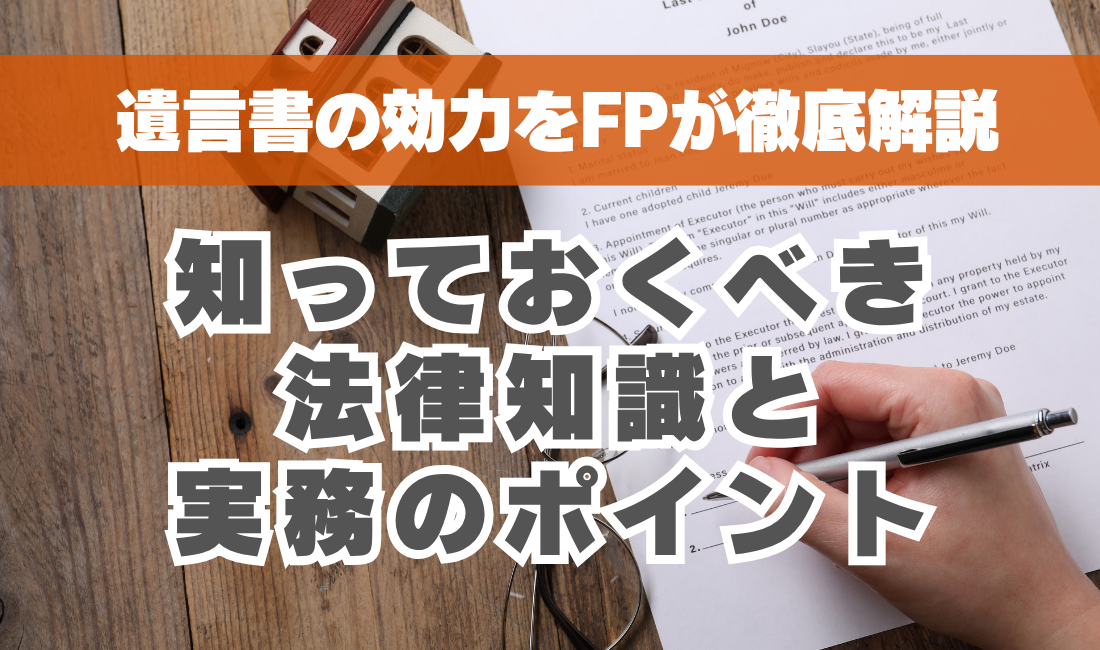人生や家計を計画するうえで、相続や財産のことは避けて通れません。しかし、多くの人は「まだ先の話」と考えて、準備を後回しにしがちです。FPの視点では、早めに遺言や資産管理を考えることが、将来の家族の安心や財産トラブルの回避につながります。今回の記事では、遺言書や相続の基本を押さえながら、具体的に何を準備すべきなのかを、わかりやすく解説していきます。
そもそも遺言書とは?
遺言書とは、自身が亡くなった後の財産や権利をどのように分けるのか、死後の手続きをどのように行うのかを、自らの意思で法的に示す文書です。単なる書類ではなく、相続人に対する明確な意思表示であり、家族や関係者に迷惑をかけず、希望通りに財産を分配するための、重要な手段となります。
特に近年では、家族構成が複雑になったり、相続財産が多様化したりしているため、遺言書の存在は、単に財産分配を決めるだけではありません。家族関係の円滑化や、トラブル防止の観点からも非常に大切です。
【過去から今まで】遺言書が果たす役割
遺言制度の歴史は古く、古代ローマ法や日本の律令制度にも、類似の制度が存在しました。当時は土地や家屋、農作物といった財産を対象として、死亡後の分配を明確化する手段として利用されていました。現代の日本では、民法が遺言の作成・効力・執行方法を細かく規定しており、形式や手続きを正しく守ることが、効力を確保する条件です。
現代社会では、財産の種類が多様化して、金融資産、株式、不動産、さらにはデジタル資産まで含まれるようになりました。家族構成も、核家族化や再婚家庭などによって、複雑化しており、法定相続分だけでは希望通りの財産分配が、困難な場合があります。そのため、遺言書を作成することは、個人の意思を法的に尊重しつつ、家族間のトラブルを未然に防ぐための手段として、ますます重要になっています。
遺言書の法的な位置と相続での扱い
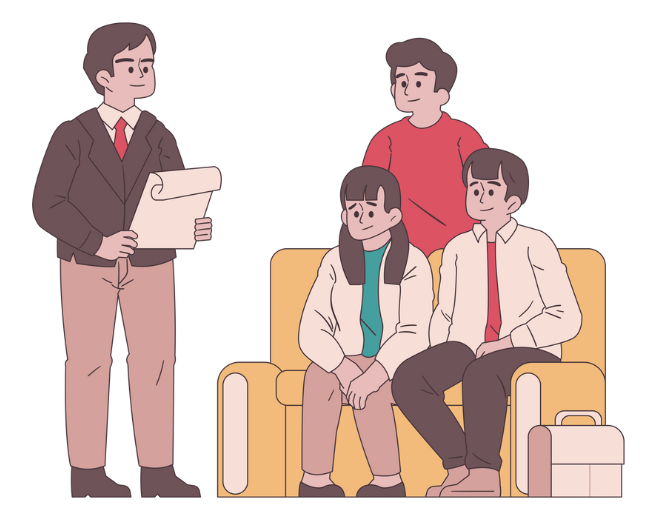
民法では、遺言により、本人の意思を尊重することができると規定されています。遺言書がある場合、その内容は原則として、法定相続分より優先されます。また、遺言書は死亡時に効力を発揮するため、生前は自由に変更や撤回が可能です。この特性により、財産状況や家族構成の変化に応じて、遺言内容を更新できる柔軟性も備えています。
遺言書の法的効力は、相続手続きや家庭裁判所での検認、遺言執行者による手続きが、中心的な役割を果たします。たとえば、遺言書があれば、相続人全員の合意による遺産分割協議を行わずとも、遺言書の内容に従って、相続手続きが進められます。これにより、家庭裁判所への申立てや、長期間の話し合いを避けることができるのです。
遺言書がもたらす安心とトラブル防止の効果
遺言書を作成することで、家族に対する心理的負担を軽減できます。特に、相続人が複数いる場合や、相続対象となる財産が高額な場合には、遺言書の有無によって、家族間の関係性に大きな影響を与えます。
遺言書を作成しておけば、「誰が何を受け取るのか」が明確になるため、相続人同士の感情的な争いを避けやすくなります。また、葬儀の形式や遺品整理の指示を記しておくことで、家族が迷わず手続きを進められるため、心理的・時間的負担を大幅に軽減できます。
さらに、遺言書を作成する過程で、自身の財産や相続人の状況を整理することにもつながるでしょう。財産目録の作成や、誰に何を残すのかを具体的に考えることで、自身の死後に備える意識が高まり、遺産管理や死後事務の計画が立てやすくなるのです。これにより、相続手続きの円滑化だけでなく、家族の安心感を増す効果も期待できます。
遺言書の種類
遺言書には、大きく分けて三つの形式があります。それぞれの形式には特徴や作成方法、メリット・デメリットがあり、財産の種類や家族構成、争いのリスクに応じて、最適な形式を選ぶことが重要です。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類について、わかりやすく紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を自身で手書きして、作成する形式の遺言書です。法律上、全文を自筆で書いて、日付と署名を記入することで効力が認められます。手軽に作成できる点が最大のメリットです。自宅で気軽に作成できることから、多くの人に利用されています。また、生前は自由に書き換えや訂正が可能で、自身の意思の変化に合わせて更新できます。
一方で、自筆証書遺言には注意すべき点があります。まず、形式が法律で定められているため、署名や日付の欠落、文章の曖昧さ、誤字脱字などがあると、遺言書が無効となる可能性があるのです。
さらに、内容が不明確な場合には、相続人間で効力を巡る争いが発生することもあります。たとえば、「家の財産は、子供たちで相談して決める」とだけ記載した場合、具体的な分配方法が不明確であるため、争いに発展するかもしれません。
近年では、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が整備されて、紛失や改ざんのリスクを減らせます。法務局で保管すれば、家庭裁判所での検認手続きも簡略化されて、安全性が大きく向上します。一方で、財産が多額で複雑な場合や、相続人間で争いが予想される場合には、公正証書遺言など、より確実性の高い形式を検討することがおすすめです。
| 項目 | 内容 |
| 自筆証書遺言の概要 | 全文を本人が自筆で作成して、日付と署名を記入することで効力が認められる形式。 |
| メリット | ・手軽に作成できる。 ・自宅で作成が可能。 ・生前に自由に書き換えや訂正が可能。 ・自身の意思に合わせて更新できる。 |
| 主な注意点 | 日付・署名の欠落、誤字脱字、曖昧な表現があると、無効になる可能性がある。 |
| トラブル例 | 「家の財産は子供たちで相談して決める」といった記載では具体性がなく、相続人間で争いが起きるおそれがある。 |
| 法務局での保管制度 | 法務局に保管を依頼することで、紛失・改ざんのリスクを減らせて、家庭裁判所での検認手続も簡略化される。 |
| 他形式との比較 | 財産が多い・複雑な場合、または争いの可能性がある場合は、公正証書遺言などの形式を検討する方が望ましい。 |
公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人と証人が関与して作成する遺言書です。法律上の形式不備による無効リスクがほとんどありません。公正証書遺言を作成することで、相続人間の争いを避けやすく、相続手続きもスムーズに進めやすくなります。そのため、多くの専門家が推奨する形式です。特に、財産が多額で家族構成が複雑な場合には、最も安全な方法になります。
作成の流れは、まず遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、公証人がその内容を文章にまとめます。その後、証人二人の立会いのもとで、署名・押印を行い、正式な公正証書として完成します。公正証書遺言のメリットは、形式不備による無効のリスクがほとんどないこと、内容が明確であるため、解釈の争いが起きにくいことです。
また、公証人が作成過程で内容をチェックするため、曖昧な表現や法律上問題のある記載を、未然に修正できる点もメリットです。一方で、作成費用がかかることや、作成手続きに時間が必要なことが、デメリットとして挙げられます。
| 項目 | 内容 |
| 公正証書遺言の概要 | 公証人と証人2名が関与して作成する遺言書。法律上の形式不備による無効リスクが、非常に低い。 |
| 主な特徴・効果 | 相続人間の争いを防ぎやすく、相続手続きがスムーズに進む。専門家が最も推奨する形式。 |
| 適したケース | 財産が多額、または家族構成が複雑な場合に最も安全 |
| 作成の手順 | ① 遺言者が公証人に内容を伝える ② 公証人が文書化する ③ 証人2人立会いのもと、署名・押印を行って完成する |
| メリット | ・形式不備による無効リスクがほぼない ・内容が明確で、解釈の争いが少ない ・公証人が内容を確認・修正するため、安全性が高い |
| デメリット | ・作成費用がかかる ・手続きに時間が必要となる |
秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書として効力を持たせられる形式です。本人が遺言書を作成した後に、封印して公証人に提出することで、内容を他人に知られることなく保管できます。この形式は、遺言の内容を家族や関係者に知られたくない場合や、財産分配を極秘にしたい場合に利用されます。
しかし、秘密証書遺言は、作成手続きや管理がやや複雑であり、一般的な利用は少ないです。作成手続きで封印された遺言書を公証人に提出する際に、署名・押印を確認してもらう必要があります。
公証人は中身を確認できないため、内容が不明瞭であったり、形式に不備があったりする場合は、効力が争われる可能性もあるのです。そのため、秘密証書遺言を作成する際には、司法書士や弁護士などの専門家に、アドバイスを受けながら作成することが大切です。
| 項目 | 内容 |
| 秘密証書遺言の概要 | 内容を秘密にしたまま、効力を持たせられる遺言形式。本人が作成後に封印して、公証人に提出して保管する。 |
| 利用目的 | 家族や関係者に内容を知られたくない場合、財産分配を極秘にしたい場合などに適している。 |
| 特徴 | 公証人は遺言の内容を確認せず、封印されたまま、署名・押印を確認する。 |
| 注意点 | 作成手続きや管理が複雑で、一般的な利用は少ない。 |
| リスク | 内容の不明瞭さや形式不備があると、効力が争われる可能性がある。 |
| 作成時の対策 | 司法書士・弁護士など、専門家の助言を受けながら作成することが望ましい。 |
遺言書の法的効力
遺言書の最大の特徴は、本人の意思を死亡後に法的に実現できる点にあります。しかし、その効力は無条件に発生するわけではなく、形式や内容、状況によって効力が認められない場合もあるのです。ここでは、遺言書の効力の意味、発生のタイミング、他の制度との関係、争われるケースなどを紹介します。
遺言書の効力が発生するタイミング
遺言書の効力は、作成時ではなく死亡時に発生します。生前は自由に変更・撤回が可能であり、意思の変化や状況の変化に応じて、何度でも更新できます。たとえば、財産状況が変わった場合や相続人に重大な変更があった場合には、遺言書を新たに作成しても、効力を持たせることができます。
効力の発生後、遺言書に基づく手続きは、相続人全員の合意がなくても進められます。しかし、遺留分を侵害する場合は、相続人から請求を受ける可能性があるため、作成時に法律上の制限を考慮しなければなりません。
生前贈与や遺留分との関係
遺言書による財産分配は、生前贈与や遺留分と密接に関係しています。生前に財産を贈与していた場合でも、遺言書で残りの財産の分配方法を指定することで、相続人間のトラブルを防ぐことが可能です。また、遺留分に関しても、遺言書で調整することにより、相続人の最低限の取り分を確保しつつ、希望通りの分配を実現できます。
たとえば、特定の相続人に多くの財産を譲りたい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成することで、後に争いになるリスクを最小限にできるでしょう。この点を考慮せずに作成された遺言書は、相続人間の紛争や、家庭裁判所への持ち込みにつながる可能性が高くなります。
遺言書が無効となる場合
遺言書が効力を発揮しない、あるいは無効とされるケースもあります。代表的なものは以下の通りです。
- 形式の不備
自筆証書遺言で署名や日付、押印が欠落している場合や、公正証書遺言で証人の立会いがない場合など、法律で定められた形式を守らないと無効になります。
- 心神喪失時の作成
作成時に意思能力がなかった場合、遺言書は無効とされます。
- 内容の不明瞭さ
「家の財産は子供たちで相談して決める」のように具体性が欠ける場合、解釈が争われて、効力を確定できないことがあります。
- 複数遺言書の存在
複数の遺言書が存在する場合、後に作成された遺言書が優先されますが、前後の内容が矛盾すると、家庭裁判所での調整が必要になります。
これらのケースを避けるためには、明確な文章での作成、形式の遵守、専門家の助言を受けることが重要です。
判例から見る遺言書の効力の範囲
裁判所の判例を参考にすると、遺言書の効力や解釈の基準が理解できます。たとえば、自筆証書遺言の一部に形式不備があった場合でも、主要部分が明確であれば、有効と認められることがあります。一方で、曖昧な表現や複数の解釈が可能な内容は、効力が争われる原因となるのです。
公正証書遺言においても、形式上の欠陥は少ないものの、文言の曖昧さや不明瞭な指示が争いを生むことがあります。判例から学ぶポイントは、効力を確実にするためには、文章の明確さと、形式遵守が不可欠であるという点です。
遺言書の作成の実務的なポイント
遺言書は、法的効力を持たせるためには形式だけでなく、内容や管理方法にも注意が必要です。正しく作成されていなければ、意思表示が争われたり無効になったりします。ここからは、遺言書を作成する際に押さえるべき基本的なルール、書き方のポイント、専門家の活用方法、保管の工夫について、順序立てて解説していきます。
遺言書作成の基本ルール
遺言書には、形式上、必ず守るべき基本ルールがあるのです。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれにおいても、日付、署名、押印は欠かすことができません。これらが欠落すると、遺言書の効力が認められない可能性があります。また、内容はできるだけ具体的で明確に書くことが大切です。
たとえば、「預金は長男に相続させる」とだけ書くよりも、「○○銀行の普通預金口座(口座番号○○)の全額を長男に相続させる」と、具体的に記載したほうが効力の争いを避けやすくなります。財産の種類や数量、受取人を特定できるように明示することで、解釈の余地を減らして、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
| 項目 | 内容 |
| 遺言書の基本ルール | 形式上、日付・署名・押印は必須。いずれかが欠けると、無効になる可能性がある。 |
| 対象となる遺言書の種類 | 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のすべてに共通して必要。 |
| 内容記載の原則 | できるだけ具体的で、明確に書くことが重要。 |
| 記載例(不十分) | 「預金は長男に相続させる」 |
| 記載例(理想) | 「○○銀行の普通預金口座(口座番号○○)の全額を長男に相続させる」 |
| 具体的な記載の効果 | 財産の種類・数量・受取人を明示することで、解釈の余地を減らして、相続トラブルを防止できる。 |
書き方のポイント
遺言書の内容を明確に伝えるためには、文章の書き方にも工夫が必要です。まず、抽象的な表現やあいまいな言葉は避けて、具体的な指示を書きましょう。たとえば「家の財産は公平に分ける」ではなく、「自宅不動産は長男に、現金預金は長女に分配する」と記載するほうが望ましいです。
次に、遺言書内で複数の財産を扱う場合は、財産ごとに章立てや箇条書きで整理すると、相続人や遺言執行者が手続きを進めやすくなります。また、遺言書には、複数の種類の指示を含めることができます。たとえば、財産分配だけでなく、葬儀の方法や遺品整理、特定の物品の処分方法なども明記できるのです。これにより、家族の負担を減らして、希望通りの手続きを実現できます。
遺言書の専門家を活用
遺言書を確実に効力あるものにするためには、専門家の活用が非常に有効です。司法書士や弁護士に内容を確認してもらうことで、形式不備や文章の曖昧さを防ぐことができます。特に、財産状況が複雑な場合や、相続人間に争いのリスクがある場合は、専門家の助言を受けることが必須です。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人が法律上の形式を確認するため、無効のリスクは低くなります。しかし、内容の明確性や曖昧な表現については、公証人のチェックだけでは十分でない場合もあるため、事前に弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。また、秘密証書遺言の作成時も、手続きが複雑であるため、専門家の指導を受けながら作成することが良いでしょう。
遺言書の保管と管理
遺言書を作成した後は、保管方法にも注意が必要です。自宅で保管する場合は、紛失や改ざんのリスクを避けるため、安全な場所に保管して、信頼できる家族や専門家に所在を知らせておくことが重要です。鍵付きの金庫や書類保管用ボックスを活用すると、安全性が高まります。
さらに、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。法務局に預けることで、死亡後に家庭裁判所での検認手続きが、簡略化されて遺言書の真正性が保証されます。公正証書遺言の場合は、公証役場で原本が保管されるため、紛失の心配はほとんどありません。
遺言書の更新と訂正
遺言書は、生前に何度でも更新や訂正が可能です。ただし、更新や訂正を行う場合は、形式を守り、古い遺言書との優先関係を明確にしておく必要があります。たとえば、自筆証書遺言を新たに作成する場合は、古い遺言書を破棄して無効であることを、明記しておくと安心です。
また、遺言書の更新や訂正が不十分だと、複数の遺言書が存在することで争いになる可能性があります。遺言書を作成・更新する際には、専門家に確認してもらい、正確に手続きを行うことが大切です。
遺言書作成の注意点
遺言書だけで全ての問題が解決するわけではありません。相続放棄や借金、税務上の問題など、遺言書だけでは対処できない事項もあります。また、自筆証書遺言は簡単に作れる反面、形式不備による無効のリスクがあるため、注意が必要です。
公正証書遺言でも、文章の曖昧さが争いの原因となることがあります。したがって、明確な表現、形式遵守、専門家の活用、保管方法の工夫を組み合わせることが、遺言書作成の実務上の基本方針になります。
【実際の流れ】遺言書と相続手続きについて
遺言書は、本人の意思を尊重しつつ、相続手続きを円滑に進めるための重要な手段です。遺言書の有無や内容、形式によって、手続きの流れや必要書類、相続人の関与度が大きく変わります。ここからは、遺言書がある場合とない場合の手続きの違い、遺言書の提示方法、遺言執行者の役割、相続手続きの具体的な流れを、分かりやすく紹介していきます。
遺言書がある場合の実際の手続き
遺言書がある場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に従って進められます。遺言書には、財産の分配や相続人への指示が明確に記載されているため、相続人全員の合意が不要です。家庭裁判所の関与も、最小限に抑えられます。
まず、死亡後に遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認は、遺言書の存在や内容を確認して、相続人間で改ざんや隠匿が行われないようにするための手続きです。自筆証書遺言の場合は必須ですが、公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるため、検認は不要です。
検認後、遺言執行者が指名されていれば、遺産分割や相続税申告、各種登記手続きを代行します。遺言執行者の関与により、相続人間の調整や手続きの迅速化が図られて、家族間のトラブルを防ぐことができます。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が協力して、手続きを進めなければなりません。
遺言書がない場合の手続き
一方で、遺言書が存在しない場合、相続手続きは全相続人の協議に基づいて行われます。相続人全員の合意が必要であり、意見が一致しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けることになります。
このプロセスは、相続人間のトラブルや手続きの遅延を招きやすいです。結果として、相続税申告や登記が遅れる原因になります。また、遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて、財産を分割することになりますが、家族関係が複雑な場合や遺産の種類が多い場合は、調整が難航することがあるでしょう。
遺言書の提示方法
遺言書を相続手続きで活用するには、適切な提示方法を理解しておくことが重要です。自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所で検認を受けるため、まず検認申立書を提出して、相続人全員に通知します。その後、遺言書の原本を家庭裁判所で確認してもらい、内容を各相続人に伝えることになります。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されているため、死亡証明書を添えて、公証役場に請求すれば、正本を受け取ることができます。正本をもとに遺産分割や登記手続きを進めることで、内容の真正性が保証されて、相続人間の争いを避けることが可能です。秘密証書遺言は、封印されたまま提出されるため、内容は相続人に知られず、家庭裁判所での検認手続きを経て、初めて効力が発揮されます。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言書の指示を実現するために重要な役割を果たします。具体的には、遺産の調査、財産の管理、各種手続きの代行、相続人との調整などを行います。遺言執行者がいることで、相続手続きはスムーズに進み、家族間でのトラブルを防ぐ効果が高まるでしょう。
また、遺言執行者は専門的知識を有していることが望ましいため、信頼できる家族や弁護士、司法書士が選ばれることが一般的です。遺言書には、執行者を指定することが可能で、指定がない場合は、相続人が協力して手続きを行う必要があります。
遺言書作成に関するよくある質問(FAQ)
遺言書は相続や死後事務に関わる重要な文書ですが、初めて作成する人にとっては、疑問が多いものです。ここでは、FPの視点から遺言書作成に関して、よくある質問を取り上げて具体的に解説します。ここでの回答を参考にすることで、遺言書作成に関する不安を減らして、より安全で確実な遺言書を作成できるでしょう。
- Q1:自筆証書遺言は簡単に無効になるのか?
自筆証書遺言は、全文を自身で手書きして、日付・署名・押印を正確に行う必要があります。形式を守らなかった場合、裁判所で無効と判断される可能性があります。しかし、形式に沿って作成すれば有効です。また、法務局の保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクも減らせます。ポイントは、内容を明確に書いて、形式を正確に守ることです。
- Q2:公正証書遺言なら完全に安心なのか?
公正証書遺言は、公証人と証人が関与して作成されるため、形式不備で無効になるリスクはほとんどありません。しかし、文章の内容が曖昧で、相続人間の利害調整を考慮していない場合は注意しましょう。効力そのものは有効でも、解釈を巡って争いが生じることがあります。専門家による文章チェックや、具体的な指示の記載が重要です。
- Q3:遺言書だけで全ての相続問題は解決できるのか?
遺言書は、財産分配や死後事務の指示に関して法的効力を持ちますが、借金や税務上の問題、遺留分の調整など、遺言書だけでは解決できない問題も存在します。たとえば、相続人の一部が遺留分を主張する場合、遺言書に反する分配でも調整が必要です。そのため、遺言書作成の際には、相続全体の状況を考慮して、専門家の助言を受けることが望ましいです。
- Q4:複数の遺言書がある場合、どれが有効になるのか?
複数の遺言書が存在する場合、原則として日付の新しい遺言書が優先されます。古い遺言書が残っている場合は、破棄するか、無効であることを明示しておくことが重要です。内容が一部重複する場合や、矛盾する場合には、相続人間で争いが生じやすくなるため、注意が必要です。
- Q5:遺言執行者は必ず必要なのか?
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを、代行する役割を持ちます。必須ではありませんが、複雑な財産や相続人間での調整が必要な場合は、指定しておくことがおすすめです。遺言執行者がいることで、手続きの迅速化や争い防止につながります。指定できるのは家族、弁護士、司法書士など、信頼できる人物です。指定がない場合は、相続人が協力して手続きを進める必要があります。
- Q6:遺言書に葬儀や遺品整理の指示も書けるのか?
遺言書には財産分配だけでなく、葬儀の方法や、遺品整理に関する指示も含めることが可能です。たとえば、「葬儀は自宅近くの寺院で家族だけで行う」「遺品は信頼できる業者に整理してもらう」といった具体的な指示を記載できます。これにより、家族の負担を軽減して、死後事務をスムーズに進めることができます。
- Q7:遺言書はどのタイミングで作成すべきなのか?
遺言書作成に「早すぎる」ということはありません。むしろ、健康なうちに作成しておくことで、死後に家族が迷うことなく、相続手続きを進められます。ライフステージの変化(結婚、出産、財産の増減など)があった場合は、見直しや更新を行うことも重要です。生前から遺言書を作成・保管して、必要に応じて、専門家に相談することで、効力を確実に維持できます。
デジタル遺品の管理も忘れずに!専門業者の活用で遺言書の見落としを防ぐ
遺言や相続の準備では、不動産や預貯金のような目に見える財産だけでなく、デジタル上の資産にも注意が必要です。ネット銀行、証券口座、暗号資産、電子マネー残高など、形のない資産は、相続人が存在を把握できずに放置されるケースが増えています。
こうした資産は、申告漏れやトラブルの原因になりかねません。FPとしては、まず「自身がどのようなデジタル情報を保有しているのか」を明確にして、一覧化しておくことを勧めます。さらに実務的には、専門のデジタル遺品業者に依頼しておくと安心です。デジタル遺品業者はパソコンやスマートフォン、クラウド上のデータを専門的に調査して、金融口座や契約情報の特定をサポートします。
この過程でFPや弁護士と連携すれば、法的な整合性を保ちながら、情報漏れやトラブルを防ぐことができるでしょう。遺言書を作成する際には、財産目録にデジタル資産を含めること、そして、必要に応じて専門業者の支援を受けることが、今後の相続対策において重要な視点です。
まとめ
遺言書は、単なる書類ではなく、死後の家族の安心と、円滑な相続手続きのための重要な手段です。今回解説した知識を活用することで、形式不備や文章の曖昧さによる無効リスクを最小化できます。
早めに遺言書を作成して、必要に応じて更新・保管することが、家族にとって最適な相続を実現する第一歩です。また、現代では、ネット銀行や証券口座、暗号資産などのデジタル資産も相続対象となるため、専門のデジタル遺品業者を活用して、資産の把握や整理を行うことも有効です。
遺言書の作成・保管・更新・遺言執行者の指定に加えて、デジタル遺品の管理も含めた準備を進めることで、より安心できる相続対策が可能になります。記事を読んだ方はこの機会に、自身や家族の将来に備えた遺言書作りと、デジタル遺品の整理を少しずつ始めてみましょう。
この記事の監修者
石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。