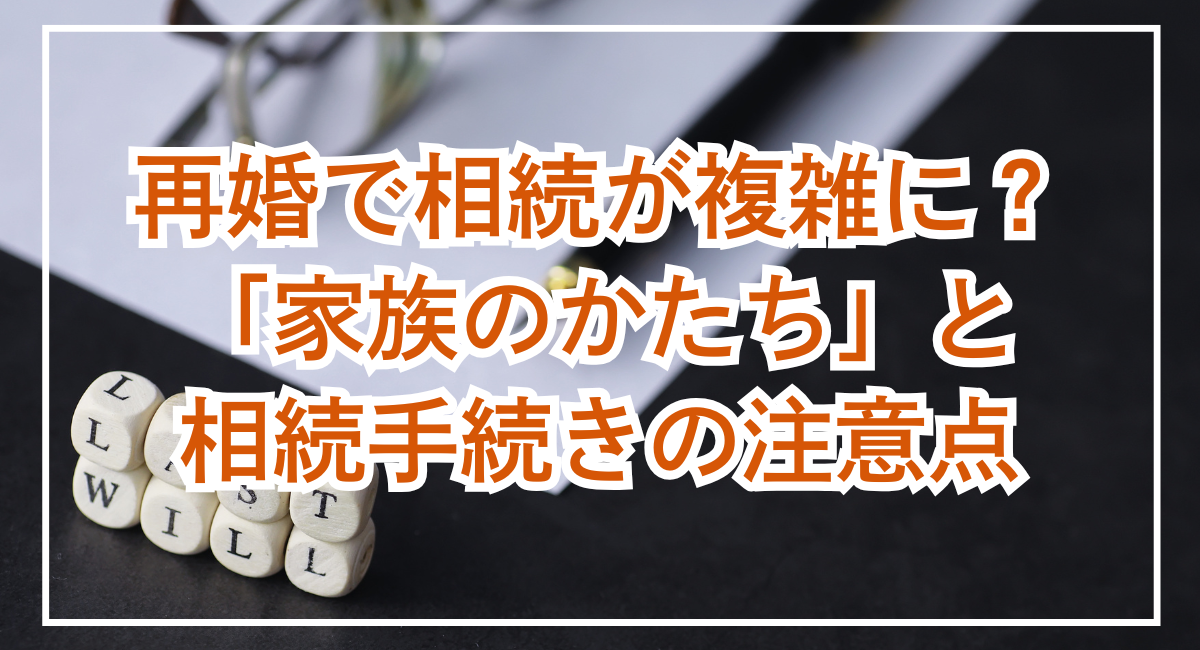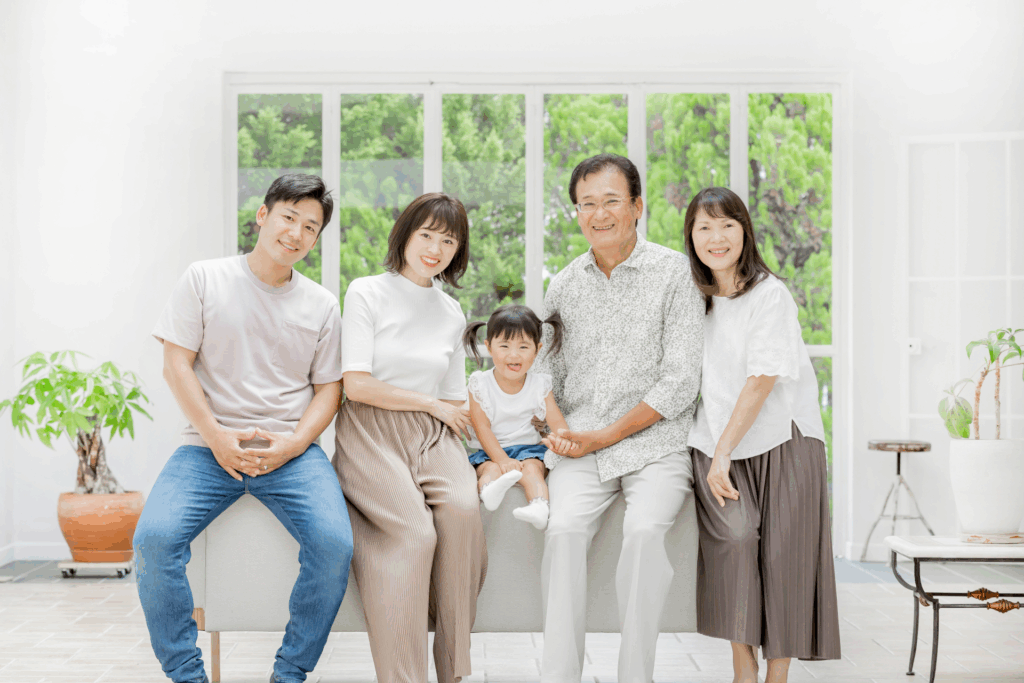
近年、家族の在り方は一層多様化しており、再婚やステップファミリーの形成は、もはや珍しいことではありません。一方で、家族構成の変化は、相続の場面において、予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。
「自分たちには関係ない」と考えていても、実際に相続が発生した際には、関係者間の利害が複雑に絡み合い、問題が表面化するかもしれません。
誰がどの程度の財産を取得するのか、連れ子や前婚時の子どもの取り扱いはどうなるのかなど、解決すべきテーマは数多く存在します。今回の記事では、再婚から生じうる相続上の課題と、その円滑な解決に向けた対応策について、解説していきます。
1.なぜ「再婚」は相続トラブルの火種になるのか

家族のかたちが多様化する現代において、再婚は決して珍しいことではありません。しかし、相続の場面で思わぬトラブルが発生します。例えば、再婚によって、新たな配偶者が法定相続人となります。それにより、元々の相続人の取り分が減少するのです。
再婚相手に連れ子がいる場合や、前妻・前夫の子どもと、再婚相手が相続人となる場合もあります。相続人の構成が複雑化しやすく、遺産分割協議が難航することも多いのです。再婚相手が、自宅などの不動産に住み続けるケースもあります。
遺言書の内容や財産の使い込みをめぐる疑念が、新たな争いのきっかけになるかもしれません。このように、親の再婚は家族関係の変化だけでなく、相続という現実的な問題にも大きな影響を及ぼします。
1-1.ステップファミリーが増える現代社会の背景
現代社会において、ステップファミリー(再婚により生まれた家族)が増加する背景には、様々な社会的変化が影響しています。
まず離婚率の上昇が挙げられます。日本では1960年代以降、離婚件数が年々増加しており、それに伴い、再婚も一般的になってきたのです。現在では、婚姻全体で再婚が占める割合は2割を超えています。再婚する夫婦の多くは連れ子を伴っているケースも少なくありません。このような背景から、子どもを含む新しい家族の形、ステップファミリーが増加しているのです。
参考文献:内閣府男女共同参画局|結婚と家族をめぐる基礎データ
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/10th/pdf/1.pdf
出典:特-1図 婚姻・離婚・再婚件数の年次推移
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-01.html
インターネットやSNSの普及により、ステップファミリーの当事者同士が情報を共有しています。支援団体や社会的なネットワークも広がりを見せています。これにより、これまで表に出ることのなかったステップファミリーの存在が、社会の中で「見える化」され始めました。
離婚や再婚の増加、ひとり親世帯の拡大など、家族の価値観が多様化しています。そして、情報社会の発展が重なり、ステップファミリーは年々増加しているのです。
1-2.法律が想定している“家族像”と現実のギャップ
日本の民法と戸籍制度は「夫婦とその未成年の子どもによる核家族」が標準的なモデルになっています。戦後の法改正により「家」制度から、個人の尊厳や男女平等を重視する近代的な家族観へと転換したのです。
しかし、現代社会においては、家族の形態が多様化しています。単身世帯や共働き家庭、事実婚など、従来の家族像とは、異なる事例が起きています。今後において、法制度の整備と家族形態を支援する社会的インフラの構築が必要になるかもしれません。
2.法律ではどのような体制なのか?ステップファミリーの相続制度

家族のかたちが多様化する中で、法律が現実の家族関係に対応しきれていないのが現状です。例えば、長年一緒に暮らしている連れ子がいた場合でも、相続人になれない可能性があります。
ステップファミリーは、実際の生活と法律上の扱いにズレが生じやすいです。相続をめぐるトラブルが起こることも少なくありません。大切な財産を円満に引き継ぐためには、現行の相続ルールを正しく理解する必要があります。
2-1.実子と養子の違い
実子と養子の相続における違いは、基本的には血縁関係の有無のみになります。実子は親と血縁関係がある子どもです。養子は血縁関係がないものの、養子縁組によって法律上の親子関係が成立した子どもです。
相続の際、実子も養子も法律上は同じ「第1順位の法定相続人」として扱われます。相続権や相続分についても、違いはありません。例えば、実子2人と養子1人がいる場合、親が亡くなった際の遺産は3人で均等に分けられます。遺留分(最低限保証される相続分)についても、実子と養子で差はありません。
一方で、養子縁組の種類によっては、相続権に違いが生じます。「普通養子縁組」では、養子は、実親と養親の両方の財産を相続できます。特別養子縁組の場合は、実親との法的な親子関係が終了するため、実親の財産は相続できず、養親の財産のみ相続できるのです。
実子と養子は、相続権や相続分において法的な違いはありません。どちらも平等に扱われます。ただし、養子縁組の種類や相続税法上の取り扱いに違いがあるため、具体的な相続手続きの際には、注意が必要です。
2-2.相続権があるのは誰?血縁と戸籍の関係
相続権を持つのは、法律で「法定相続人」と定められた人です。法定相続人は、配偶者と血族に分けられます。配偶者は、必ず相続人になるのです。血族については、まず亡くなった方の子どもが優先されます。子どもが既にいない場合は、孫がその権利を引き継ぎます。子どもや孫がいない場合は、親や祖父母などの直系尊属が相続人です。
これらに該当しない場合は、兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪に相続権が移る可能性があります。
相続の際には、血縁があるだけでは権利が認められません。戸籍によって、法律上の親子関係や親族関係が証明されていることが重要です。血のつながりがある場合でも、戸籍に親子関係が記載されていなければ、相続権は発生しないのです。逆に、養子縁組をして、戸籍上で親子関係が成立していれば、認められる可能性があります 。
| 順位 | 相続人になる人 | 状況 | 代わりに相続する人(代襲相続) |
| 配偶者 | 夫または妻 | どのような場合でも 必ず相続人 | なし |
| 第1順位 | 子ども | 子どもがいる場合 | 子どもが亡くなっていれば孫 |
| 第2順位 | 親・祖父母 | 子ども・孫が いない場合 | なし |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子ども・孫も親・ 祖父母もいない場合 | 兄弟姉妹が亡くなっていれば 甥・姪 |
2-3.再婚相手には相続権がある?配偶者の立場と権利
再婚した配偶者にも、法律上の結婚関係が成立していれば、相続権が認められます。婚姻届が受理されている限り、配偶者として法定相続人となります。つまり、遺産を受け取る権利があるのです。
配偶者がどの位遺産を受け取れるかは、他の相続人がいるかで異なります。例えば、被相続人に子どもがいる場合、配偶者は遺産の半分を、残り半分を子どもが分け合います。子どもがいない場合は、親や兄弟姉妹などと分け合いますが、配偶者の取り分はより多くなるのです。
再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。養子縁組をして初めて、実の子どもと同じ相続権を持ちます。
一方で、前の配偶者との間に生まれた子どもは、親権や同居の有無に関係ありません。被相続人の子として、相続権があります。このように、再婚家庭の相続は、家族構成で複雑になりやすいのです。トラブルを防ぐためにも、遺言書を準備したり、専門家に相談したりすることも大切でしょう。
3.相続トラブルを起こさない3つの対策

遺産の分け方や財産の把握不足、感情的な対立などが原因で、相続人同士の円満な関係がこじれるケースが多くあります。しかし、事前に対策を講じておくことで、相続のトラブルは未然に防げるのです。今回は、相続トラブルを防ぐための3つの対策を解説します。
3-1.公正証書遺言を活用する
再婚をした場合、先述の通り、家族構成が複雑になりやすいです。例えば、「再婚した配偶者に多くの財産を残したい」「前の配偶者との子どもにもきちんと財産を分けたい」など、様々な希望が生じます。
このような複雑な状況で、自身の意思を確実に反映するためには 、「公正証書遺言」の活用が有効です。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。法律的な不備がないように整えられるため、無効になるリスクがありません。相続が発生した際にも、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、スムーズに相続手続きが進められます。
また、公正証書遺言は遺言者の希望を正確に反映しやすいです。「連れ子に遺産を遺贈したい」などの意向も明確に記載できます。連れ子は、養子縁組をしない限り、法定相続人にはなりません。しかし、遺言によって財産を渡すことができます。遺言執行者を指定しておくことで、遺産分割や名義変更などの手続きも円滑に進むでしょう。
ただし、法定相続人には、最低限保証される「遺留分」があることに注意してください。全く相続させない場合でも、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるのです。この点にも注意しながら、遺言内容を検討してください。
| 項目 | 内容 |
| 公正証書遺言 | 法的に有効、検認不要で手続きが早い |
| 連れ子 | 養子縁組しないと、法定相続人にならないが、遺言で遺贈は可能 |
| 前妻の子 | 法定相続人、遺留分も請求できる |
| 遺留分 | 法定相続人に、最低限保証される取り分がある |
| 遺言執行者指定 | 手続きが円滑に進む |
3-2.家族で「相続を話せる環境」を作る
相続が発生した後に初めて話し合うと、感情的な対立や誤解が生じやすくなります。日頃から、家族の将来や老後の暮らしについて、自然に会話することを意識してください。それによって、相続に関する話題も切り出しやすくなります。突然、財産分与の話をするのではなく、健康や生活のこと、家族の思い出などから話を始めましょう。段取りを少しずつ踏むことで、相続について相談できる環境が作れるようになります。
3-3.信託や養子縁組を戦略的に使う
前妻や後妻との間に生まれた子どもや連れ子がいる場合、それぞれの相続権や財産の分配で、細かい配慮が必要です。このような状況では、従来の遺言だけでなく「信託」や「養子縁組」などの手段を活用しましょう。
例えば、再婚相手の連れ子にも財産を残したいケースです。養子縁組を行うことで、その子どもを法定相続人にできます。これにより、実子と同じ権利で相続を受けられるのです。一方で、養子縁組には人数制限や、将来的な家族関係の変化による影響もあるため、慎重な判断が求められます。
家族信託の場合も、事前に制度の仕組みを把握しておきましょう。「自分が亡くなった後は後妻に財産を管理・使用してもらい、後妻が亡くなった後は前妻との子財産を渡す」などの、財産承継の指定が可能です。これは、遺言だけでは実現できない柔軟な設計です。結果的に、家族間のトラブル防止にも役立ちます。
再婚家庭の相続対策では、養子縁組による法定相続人の調整など、複数の制度を上手に使い分けることも大切です。
| 手段 | 連れ子の相続権 | 主な特徴 |
| 養子縁組 | 法定相続人になる | 実子と同じ権利 |
| 遺言 | 遺贈で財産を渡せる | 相続税2割加算・遺留分に注意 |
| 家族信託 | 受益者として指定できる | 柔軟な財産承継が可能 |
4.多様な家族だからこそ、相続の備えは「見える化」を

再婚家庭や事実婚、子どものいない夫婦など、ひと昔前には想像していない家族のあり方が当たり前になりました。このような変化の中で、相続が発生した場合に「誰が何をどのように受け継ぐのか」が見えにくいのも現状です。
そのため、家族や財産の状況を「見える化」して、万が一に備えて、相続について事前に話し合うのが重要でしょう。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼