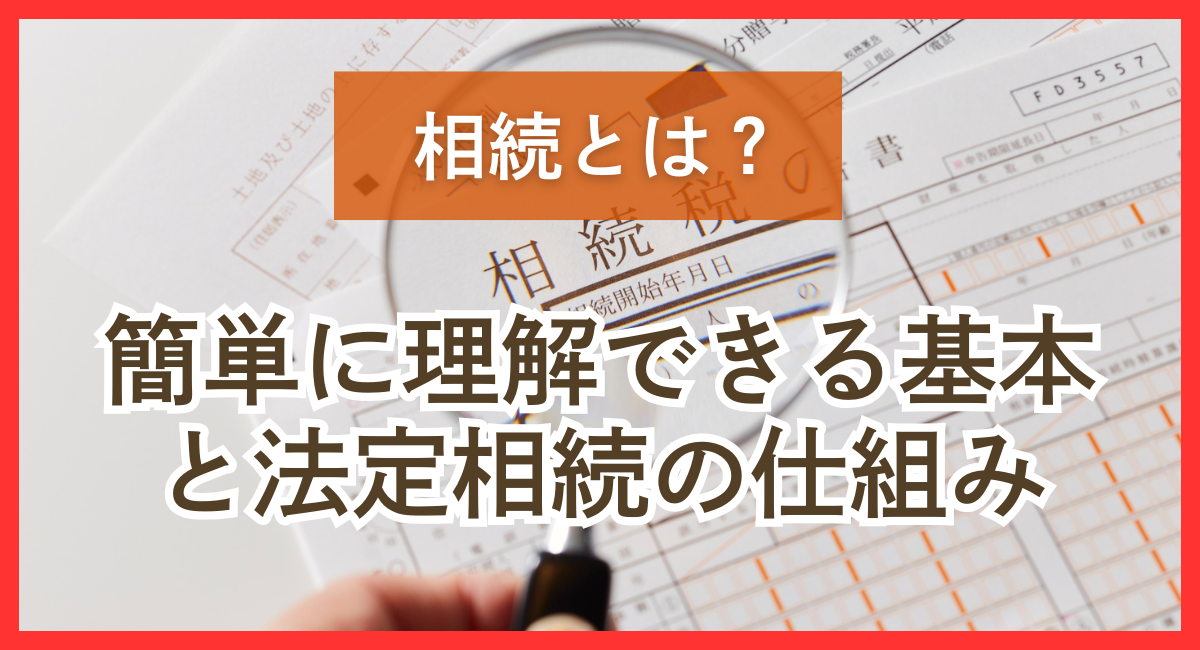「相続って難しそう…親が亡くなったらどうすればいいんだろう…」
こんな不安や疑問を抱えていませんか?相続は避けては通れない人生の重要なイベントですが、その仕組みや法律を理解するのは簡単ではありません。しかし、相続について知識がないまま放置してしまうと、将来的に家族間の争いを引き起こしたり、予期せぬ相続税の負担に直面したりする可能性があります。
本記事では、相続の基本的な概念から、対象となる財産、相続人の範囲、相続分の種類、そして相続の方法まで、わかりやすく解説します。相続に関する重要なポイントを押さえることで、将来の備えや家族との話し合いに役立つ知識を得ることができます。
この記事を読み終えた後には、相続に対する不安が和らぎ、自信を持って相続に関する計画を立てられるようになるはずです。家族の将来を守り、円滑な相続を実現するための第一歩を、ぜひこの記事から踏み出してみてください。
相続とは?
ある人が亡くなった時に、その人の財産や権利、義務を法律に従って引き継ぐ仕組みを相続と呼びます。この制度は故人の財産管理と次世代への円滑な継承を目指しています。
相続の目的
相続の本質は単なる資産移転ではありません。故人の意思を大切にしながら、遺族の生活を守り、社会の秩序を保つ重要な役割があります。例えば、事業主が亡くなった際に、その事業を滞りなく続けられるよう機能させるのも相続の一面です。
※参考リンク:
親族が経営する事業を相続したいという方は、事業承継税制特集(国税庁)をご参照ください。
概要:事業承継税制とは、承継円滑化法に基づく認可を得たうえで、会社または個人事業の後継者が一定の財産を取得する場合に、贈与税や相続税の納付を一定期間延長できる制度を指します。
相続の流れと重要な3つの形式
相続は人が亡くなった時に始まります。法律で定められた相続人に相続権が生じるのがこの時点です。ただし、実際の手続きは相続の受け入れや放棄の決定、遺産分与など、いくつかのステップを経て完了します。
相続には主に3つの形式があります。
- 法定相続: 遺言書がない場合や無効な場合に適用
- 遺言相続: 故人の遺言書に基づいて行われる
- 協議相続: 相続人同士で話し合って遺産分割を決める
相続の対象は幅広く、預貯金や不動産、有価証券などの資産に加え、借金などの債務も含まれます。プラスとマイナス両方の財産が相続の対象となるため、相続人は慎重に検討する必要があります。
※参考リンク:
具体的な相続税申告の手続きを知りたい方は、相続税の申告のしかた令和5年分用(国税庁)をご参照ください。
相続で起こりうる問題
相続は時に複雑で難しい問題を引き起こすことがあります。例えば:
- 相続する人達の間での遺産分割の争い
- 予期せぬ相続税の発生

これらの問題を避け、スムーズな相続を実現するには事前の知識と準備が欠かせません。以下のような対策を講じることで、将来の相続に備えられます。
- 遺言書の作成
- 生前贈与の活用
- 専門家への相談
相続について理解を深め、適切な準備をすることで、将来の不安を軽減することができます。
※参考リンク:
具体的に有効な遺言書の書き方を知りたいという方は、知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方(政府広報オンライン)をご参照ください。
相続の対象となる人とならない人
誰が相続人になれるのか、誰が相続から外れるのかを理解することは、将来の相続計画を立てる上で大切なポイントです。それでは見ていきましょう。
相続の対象となる人
相続人は、亡くなった方(被相続人)との関係や遺言書の有無によって決まります。
遺言書がある場合
遺言書に記載された人が相続人となります。法定相続人以外の人(友人や慈善団体など)を指定することも可能です。ただし、配偶者や子供などの法定相続人の遺留分(最低限保障される相続分)は侵害できません。
※参考リンク:
遺留分侵害の相談も含めた一般的な質問がある方は、お近くの市区町村役場で行われている無料相談会の活用をお勧めします。相続登記に関するご質問は、法務局(東京の場合は東京法務局が管轄)で相談可能です。相続税申告については、税務署(東京の場合は都内各地の管轄税務署)へお問い合わせいただけます。
法定相続の場合
遺言書がない場合や無効の場合、法定相続が適用されます。相続人の順位は以下の通りです:
- 第一順位:配偶者と子供

- 第二順位:配偶者と被相続人の親

- 第三順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹

配偶者がいない場合は、上記の順で単独相続となります。例えば第三順位において、配偶者不在の場合、被相続人の兄弟姉妹が単独で相続します。
代襲相続
本来の相続人が先に亡くなっているなどの場合、その人の子供や孫が代わりに相続人となる制度です。直系卑属(子や孫など)と兄弟姉妹の子に限り認められます。
相続の対象にならない人
以下の人々は原則として相続の対象となりません:
- 養子縁組が解消された養親や養子
- 離婚した元配偶者
- 相続欠格事由に該当する人(例:故意に被相続人を殺害した人)
- 相続人として廃除された人
- 遺言書によって相続人から外された人(ただし、遺留分権利者は請求可能)
ただし、特別縁故者(事実婚のパートナーや長年世話をしてきた人など)が例外的に相続財産の分与を受けられる可能性があります。この様に特別な事情がある場合は、例外もあるので注意が必要です。
相続分とは
相続分とは、相続人それぞれが受け取れる財産の割合や金額のことです。相続をめぐるトラブルの多くは、この相続分を理由に発生します。相続分には主に3つの種類があります。
相続分の種類と特徴
1. 指定相続分
遺言状によって定められた相続割合が、指定相続分に該当します。
特徴:
・ 故人の意思を反映できる
・ 法定相続人以外も相続人に指定可能
・ 特定の財産を特定の相続人に相続させられる(特定遺贈)
ただし、遺留分を侵害する指定は修正される可能性があります。
2. 法定相続分
法定相続分は、民法で定められた相続分です。遺言書がない場合や、相続分の指定がない場合に適用されます。
主な法定相続分:
| 相続人 | 配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 | ・ | ・ |
| 配偶者と父母 | 2/3 | ・ | 1/3 | ・ |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ・ | ・ | 1/4 |
子供のみの場合は均等に分割します。法定相続分は公平性を重視しており、子供や父母、兄弟姉妹が複数の場合には、均等分割が適用されます。実際の相続では個別の事情を考慮することも多いので、注意しましょう。
3. 遺留分
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の相続分です。
特徴:
- 権利者は配偶者、子供、直系尊属(親や祖父母)のみ
- 割合は法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)
- 生前贈与財産も計算に含まれることがある
- 請求権は相続開始を知ってから1年以内に行使する必要がある
遺留分制度は相続人の生活保障が目的ですが、故人の意思を制限する面もあります。
相続分の問題は相続トラブルの中心になりやすいため、事前の準備が大切です。遺言書の作成や専門家への相談をおすすめします。
相続の対象となる財産とは?

相続の対象となる財産(遺産)とは、亡くなった方(被相続人)が所有していたすべての財産権のことです。目に見える財産だけでなく、目に見えない財産も含まれます。
相続の対象となる財産
相続財産は大きく「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けられます。また、一般的な相続の対象とならない特殊な財産もあります。
プラスの財産(資産)
主なプラスの財産には以下のようなものがあります:
- 不動産: 土地、建物、マンションなど
- 金融資産: 預貯金、株式、投資信託、保険金など
- 動産: 自動車、貴金属、美術品、家財道具など
- 債権: 貸付金、未収金など
- 知的財産権: 著作権、特許権など
例:自宅、別荘、銀行預金、株式投資の評価額、生命保険の死亡保険金
マイナスの財産(負債)
主なマイナスの財産には以下のようなものがあります:
- 借入金: 住宅ローン、事業資金借入など
- 未払金: クレジットカードの利用残高、税金の未払い分など
- 保証債務: 他人の借金の保証人になっていた場合の債務など
例:返済途中の住宅ローン残債、経営していた会社の負債
注意: プラスとマイナスの財産を合わせた正味の財産が相続の対象となります。相続人は慎重に財産状況を確認する必要があります。
相続の対象とならない財産
以下の財産は一般的に相続の対象となりません:
- 死亡退職金: 会社から支給される死亡退職金(被相続人の療養看護に努めた人に支給)
- 生命保険金: 契約者が被相続人で、受取人が特定の相続人である場合
- 個人年金の死亡一時金: 受取人が指定されている場合
- 著作者人格権: 著作権のうち、一身専属権であるもの(著作財産権は対象)
- 祭祀財産: 仏壇、位牌、墓地など(祭祀主宰者が承継)
- 死因贈与財産: 贈与者の死亡によって効力を生じる贈与の目的物
※上記の財産は相続財産の計算からは除外されますが、相続税の計算では考慮される場合があります。
相続の方法は3つ
相続が始まると、相続人は財産を受け継ぐかどうかを選べます。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」といった以下の3つの方法があり、それぞれ特徴が異なります。
1. 単純承認
特徴:
- プラスもマイナスも全て引き継ぐ
- 相続人の財産でも債務を弁済する可能性あり
- 原則、3ヶ月以内に他の選択をしないと自動的に単純承認となる
注意点:
- 予期せぬ多額の負債を抱えるリスクがある
- 財産の処分や隠匿をすると、知らなくても単純承認とみなされることがある
2. 限定承認
特徴:
- 相続財産の範囲内でのみ債務を弁済
- 相続人の固有財産は保護される
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続人全員の同意が必要
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要
注意点:
- 相続財産の管理義務が発生
- 債権者への公告が必要
- 手続きが複雑で時間がかかる
3. 相続放棄
特徴:
- プラスもマイナスも一切相続しない
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要
- 一度放棄すると撤回不可
注意点:
- 放棄した人の子供が次の相続人になる(代襲相続)
- 放棄後に高額資産が見つかっても相続不可
各方法の選択は、相続財産の内容や相続人の状況によって異なります。特に限定承認と相続放棄は自動的な承認ではありません。承認に必要な期限があるため、早めの対応を検討しましょう。
まとめ
相続は複雑な法的プロセスですが、基本的な知識を持つことで不安を軽減できます。
法定相続、遺言相続、協議相続の3つの形があり、預貯金や不動産などの資産だけでなく、債務も対象となります。
法令により相続権者の枠組みや遺産の配分率が規定されていますが、遺言状を通じてこれらを独自に設定することもできます。
相続方法には単純承認、限定承認、相続放棄があり、それぞれ特徴が異なります。まずは基本と仕組みを理解することが重要です。
また、遺言書の活用や専門家への相談も円滑な相続には有効です。相続は避けられないものですが、事前の準備と知識により、家族間の紛争を防ぎ、被相続人の意思を尊重しつつ、相続人の権利を守ることができます。
相続に関する理解を深め、必要に応じて適切な対策を講じることで、将来の備えとすることができるでしょう。
相続財産不正調査2.0の紹介
「故人の財産が不自然に減っているように感じる」 「他の相続人からの説明が十分でない」 「故人が使っていたPCやスマホに、財産の手がかりがあるかもしれない」
このようなお悩みや懸念をお持ちでしたら、私たちの相続財産調査サービスをご検討ください。ご自身では確認が難しいデジタル記録に着目し、PCやスマートフォンの調査を通じて、資産に関する客観的な情報を探すお手伝いをします。
私たちの専門チームは、以下の方針で信頼できるサービスを提供しています。
✔️ デジタル記録の調査 専門的なツールを用い、PCやスマートフォンに残されたデータを解析します。削除された可能性のある情報やファイルについても調査し、発見された内容を客観的な資料として報告します。
✔️ デジタル資産の手がかり調査 ご遺族が把握していないネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)など、各種デジタル資産に関する手がかりの発見をサポートします。
✔️ データ復元・パスワード解析への対応 ロックされた機器やアクセスできないデータについて、復元やパスワード解析を試み、調査に必要な情報を探ります。
✔️ 分かりやすいプロセスと丁寧な報告 初回のヒアリングは無料です。ご契約後は調査内容を報告書にまとめ、発見された情報について丁寧にご説明します。
✔️ 秘密保持の徹底 関連法規を遵守し、お客様と故人のプライバシー情報を厳格に管理いたします。
まずはお気軽にご相談ください。専門の担当者が、お客様のお困りごとについて丁寧にお話を伺います。
▼ お問い合わせはこちらから ▼