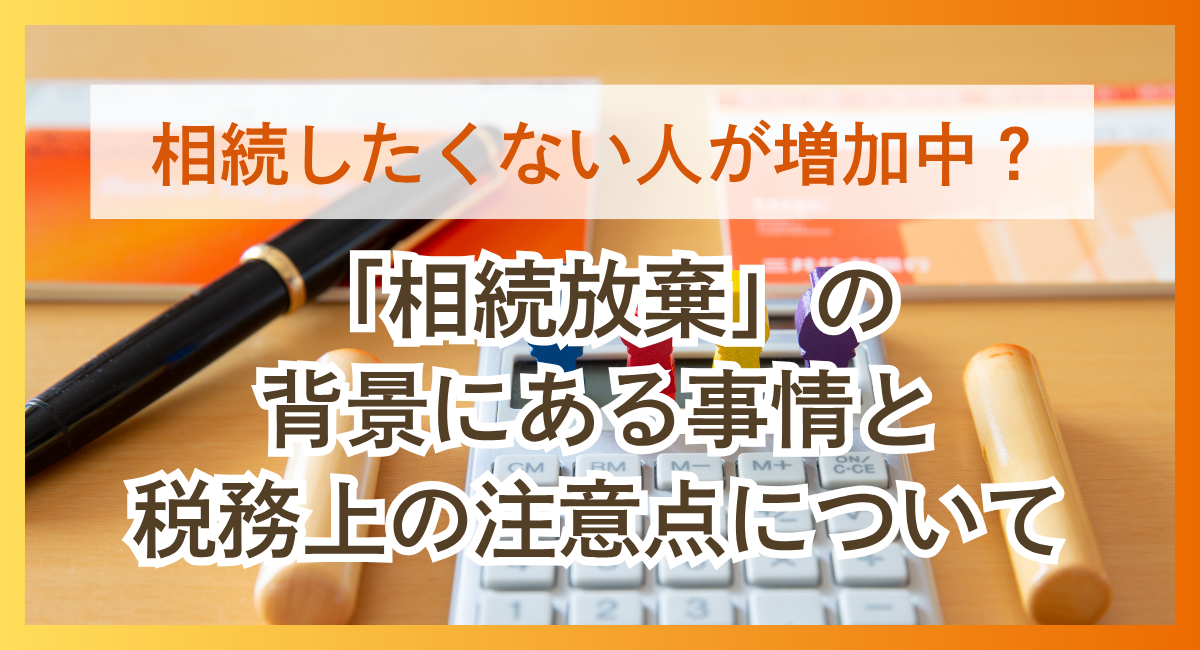近年、日本では「相続放棄」を選択する人が増えています。かつては、家や土地などの資産を受け継ぐことが、当たり前とされてきました。しかし、今の相続では「遺産を受け取らない」という決断も少なくありません。その背景には、社会や経済の変化、家族の多様化など、現代ならではの事情が影響します。今回は、多くの人が相続放棄を選ぶ理由と、その背景について解説していきます。
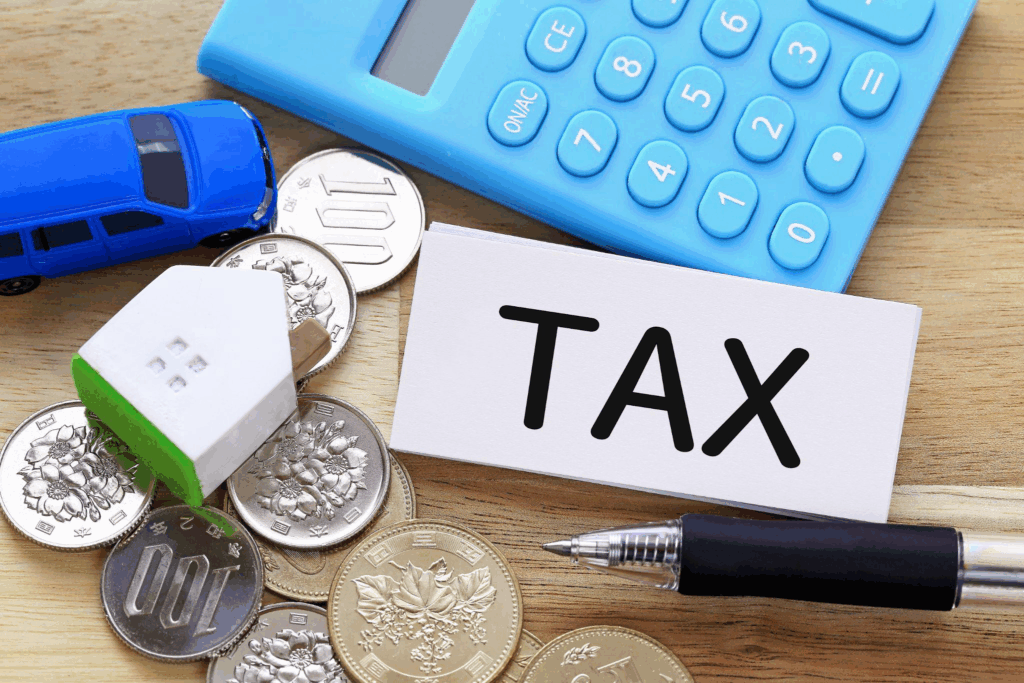
なぜ今、「相続放棄」を選ぶ人が増えているのか?

土地や家屋などの不動産は、「持っていれば安心」という資産ではなくなりつつあります。特に、地方の空き家などは、人口減少や需要の低迷で、売ることも貸すことも難しいです。その結果、所有するだけで固定資産税や管理費などの、様々な維持費が発生します。経済的な負担となるケースが増えているのです。
このような状況では、相続しても経済的なメリットは、ほとんどありません。維持や管理の負担が大きいため、相続放棄を選ぶ人が増加しています。相続放棄をすれば、税金や管理費の支払い義務から解放されます。つまり、不要なリスクを回避できるのです。
時代の流れとともに、不動産の価値観が変化しています。「所有すること自体が損失につながる」可能性があるのです。そのため、相続や処分方法を慎重に検討することが求められています。
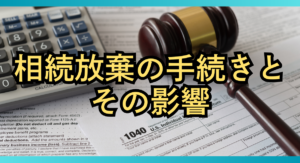
「相続しない」という意思決定とリスクマネジメント

「相続しない」という意思決定は、単なる責任の回避ではありません。相続を行う上での、1つの「戦略的なリスクマネジメント」です。相続放棄というと「家族を見捨てた」「義務から逃れたいだけ」などの印象を持たれるケースがあります。しかし、実情は大きく異なります。
相続財産が老朽化した空き家や、使い道がない土地の場合に、管理や税金の負担が大きくなるのです。被相続人(亡くなった方)に多くの借金があれば、その負債を引き継ぐリスクもあります。
このようなケースにおいて、「相続しない」という判断は重要です。ご自身の人生や家族の将来を考えた場合、最も合理的で現実的な選択肢になるでしょう。
| 方法 | 手続き | 債務の放棄 | 期限 | 主なリスク |
| 相続放棄 | 家庭裁判所 | できる | 3ヶ月以内 | 撤回不可、次順位に負債移行 |
| 遺産分割協議の放棄 | 遺産分割協議 | できない | なし | 債務を負う、内部的効力のみ |
| 相続分の譲渡 | 譲渡契約 | できない | なし | 債務を負う、譲渡契約内容に依存 |
税金はどうなる?放棄しても安心できないケースも
相続放棄は、不要な資産や債務を回避する有効な選択肢です。しかし、「相続放棄=完全に無関係」とは限りません。相続税や固定資産税の課税リスクなど、相続放棄後も、一定の注意が求められます。思いがけない負担を回避するためには、法的な手続きだけでなく、税務上の影響も考慮する必要があります。

相続放棄をした場合の税金の支払い義務
相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の財産や借金だけでなく、未払いの税金も引き継ぐ必要はありません。これは、相続放棄をした人は、法律上「はじめから相続人ではない」とみなされるためです。そのため、被相続人が残した所得税や住民税などの、支払い義務も生じません。
しかし、固定資産税に関しては注意点があります。固定資産税は、その年の1月1日時点で登記簿などに、名前が載っている人に課税されます。相続放棄の手続きが、1月1日を過ぎてから完了した場合、名義が変更されていないと一時的に納税通知が届くことがあるのです。
※納税通知が届いても、実際に納税義務があるとは限りません。市区町村に事情を説明することで納税義務を回避できる場合があります
| 相続放棄のタイミング | 固定資産税の支払い義務 |
| 1月1日より前に放棄完了 | なし |
| 1月1日時点で放棄未完了 | 一時的に支払い義務が発生する場合あり(納税通知が届く) |
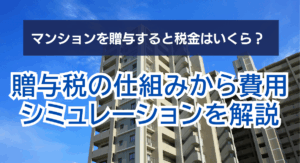
生命保険金・退職金等の非課税枠の消失
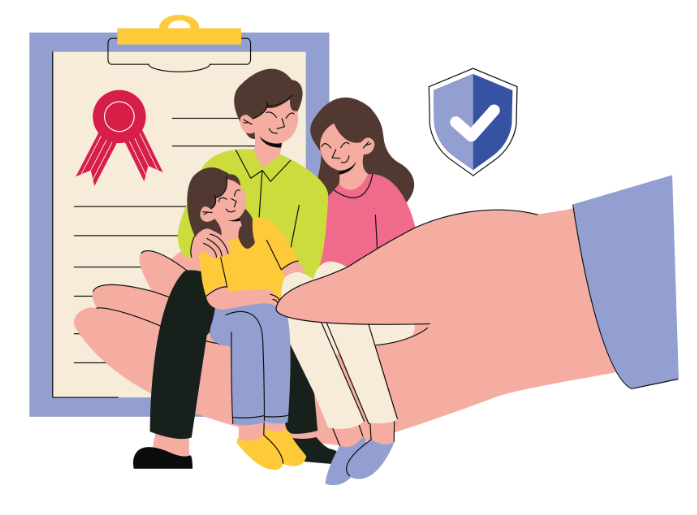
生命保険金や死亡退職金には、相続税の計算上「非課税枠」が設けられています。しかし、相続放棄をした場合、この非課税枠の扱いについて、注意する必要があります。
仮に生命保険金や、死亡退職金の受取人に指定されても、相続放棄をした人が受け取る分は、非課税枠が適用されません。結果として、相続放棄した人が受け取った生命保険金や死亡退職金は、全額が相続税の課税対象になるのです。
※生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続放棄者には原則適用されませんが、契約形態によっては非課税対象になる場合もあります
相続放棄をすることで、生命保険金などの非課税枠が使えなくなります。相続放棄を検討する際には、このような税制の取り扱いについて、事前に確認してください。必要に応じて、専門家に相談することも大切です。
| 受取人 | 非課税枠 | 課税対象 |
| 相続放棄していない | 使える | 枠超過分のみ課税 |
| 相続放棄した | 使えない | 全額課税 |
遺贈とみなし相続財産の取得について

相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続できません。しかし、相続放棄をしても、死亡退職金などの「みなし相続財産」や、遺言で贈与される「遺贈」に関しては、例外的に受け取れるのです。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として、受け取る財産です。民法上の相続財産とは異なります。一方で、相続税法上は「相続または遺贈により取得したもの」とみなされて、相続税の課税対象になります。
遺言による遺贈も、相続放棄をした人が受け取れます。一方で、みなし相続財産や遺贈を受け取った場合には、相続税の申告と納付が必要となるのです。特に、生命保険金などの非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続放棄をした人には適用されません。
これは、相続放棄をした人は、法定相続人とはみなされないためです。実際の手続きや税務処理については、専門家に相談することをおすすめします。
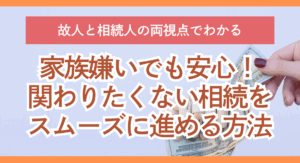
相続放棄で家族トラブルに?事前に考えておくべきこと

相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を、一切引き継がない法的な手続きです。借金などのマイナスの財産が多い場合に、選択されることが多いです。一方で、この選択によって、親族との間でトラブルが発生するケースも少なくありません。
例えば、相続放棄を行った結果、次の順位の相続人(兄弟姉妹やその子どもたち)が、突然相続人となる場合です。遺産分割や負債の問題が、新たに生じる可能性があります。

親族間で起きる前に、相続放棄の意思や手続きについて、事前に話し合わなければなりません。家族や親族から「なぜ相談してくれなかったのか」と不信感を持たれるためです。さらに、財産の全容を調べずに、相続放棄してしまうケースもあります、
このようなトラブルを避けるためには、まず、相続財産や負債の全体像をしっかり調査してください。相続人の範囲や順位を確認することが大切です。そのうえで、家族や親族と十分に話し合うことが重要です。相続放棄の理由や、今後の対応について共有することが大切です。次の順位の親族が相続人となる場合には、事前に説明しておくと、後々のトラブルを防げます。
様々な媒体を活用して相続人全員で話し合う

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。財産状況を正確に把握せず、相続放棄を決めると、後に問題になることも多いです。
トラブルを避けるためには、まず相続人全員で十分に話し合うことが大切です。相続財産の内容や、相続放棄がもたらす影響について情報を共有しましょう。家族の中で一部の人だけが、手続きを進めてはいけません。
話し合いは対面だけでなく、電話やメール、オンラインツールなどの活用もおすすめです。また、相続放棄や遺産分割には、法律や税務の知識が必要になります。司法書士などへの相談も視野に入れましょう。専門家の助言を受けることで、手続きの誤りや思わぬトラブルが防げます。
| 項目 | 内容・注意点 |
| 相続財産の種類 | プラス財産(預貯金・不動産等)、マイナス財産(借金・保証債務等) |
| 財産把握の重要性 | 正確に把握せず相続放棄を決めると、後でトラブルになる可能性がある |
| 話し合いの必要性 | 相続人全員で十分に話し合い、情報共有することが大切 |
| 話し合いの方法 | 対面、電話、メール、オンラインツール(Zoom等)を活用 |
| 専門家の活用 | 司法書士・弁護士などに相談して、手続きミスやトラブルを防ぐ |
相続放棄する前に財産の実態を把握する

相続財産の全体像を把握することは、遺産分割や相続放棄を判断するためには不可欠です。家族間のトラブルを避けるためにも、確認を怠ってはいけません。まず、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた、全ての資産と負債を1つずつ調べる必要があります。
具体的には、遺品や郵便物、通帳や証書類から、財産の手がかりを探します。預貯金については、金融機関の通帳や、インターネットバンキングの記録で確認しましょう。必要に応じて、銀行に残高証明書や取引履歴の開示を依頼します。
不動産の場合は、権利証や固定資産税の納付書、登記識別情報通知書、自治体で取得できる名寄帳などを活用してください。株式や投資信託などの金融商品は、証券会社からの郵便物や取引明細、銀行口座の配当記録などを調べます。「証券保管振替機構」に問い合わせて、証券口座の有無を調べることも可能です。

借入金やローンなどの負債に関しても、見落としてはいけません。借用書や請求書、督促状、不動産の抵当権設定状況などを確認しましょう。分からない場合は、信用情報機関に情報開示を請求する方法もあります。
このような調査には、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や、調査を行う相続人自身の身分証明書が必要です。事前に準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
相続財産の調査自体には期限はありません。しかし、相続放棄は「相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内」に決断する必要があるのです。後々の見落としやトラブルを防ぐために、専門家の力を借りることも検討しましょう。
| 分類 | 主な確認方法・資料例 |
| 預貯金 | 通帳、ネットバンキング、残高証明 |
| 不動産 | 権利証、固定資産税納付書、名寄帳 |
| 株・投信 | 証券会社の郵便物、取引明細 |
| 負債 | 借用書、請求書、信用情報機関 |
| 必要書類 | 戸籍謄本、身分証明書 |
相続放棄の手続きは3か月以内を厳守

相続放棄の手続きは「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に行わなければなりません。これは法律で定められていて、期限を必ず守る必要があるのです。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
被相続人が亡くなったこと、または自分が相続人であると知った時点から数え始めます。この期限内に、家庭裁判所へ申述書を提出しなければ、原則として相続放棄は認められません。期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て受け継ぐ「単純承認」とみなされます。借金などの負債も含めて、相続の対象となります。
財産の調査が3か月以内に終わらない場合には、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能です。相続放棄を検討している方は、この3か月の期限を意識して、早めに手続きを進めましょう。
相続放棄は家族の未来を守るための積極的な決断

相続放棄の増加は、家族関係の多様化や資産構成の変化など、現実的な事情を反映しています。単なる感情的な判断ではなく、法的・税務的な影響を踏まえて、冷静な対処が必要です。将来の負担とリスクを最小限に抑えるために、戦略的な相続対応を意識しましょう。
一方で、相続放棄の手続きには期限があり、一度手続きをすると、原則として撤回できません。判断に迷う場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。相続放棄は、家族や親族の関係性に大きく影響する可能性があります。関係者とよく話し合いながら、慎重に進めることが、トラブルを避けるためのポイントです。